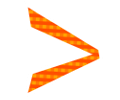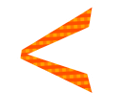<< 7:00~8:00





大日向研のすぐ向かいの学生室で、クレールたちはパライバ――いや、ライバ・カイネウスに対して、様々な指導を行っていた。人間としての振る舞い方に始まり、大学生として違和感のない状態にするための知識、――そしてかの世界の狭間における戦闘用の技能。
それら全てを、ライバはなんてことのないように飲み込む。容れ物に好きなものを注げ、と言われた時、それが得体のしれないものに変質しないか、それを真っ先に心配するだろう。けれど、パライバトルマリンにはそれがない。いつの間にか区切りが設置されていて、そしてなみなみと、それ以上に注いでいるはずなのに、底が知れない。
「……ほんと飲み込み早いな……ドン引きするほど早い」
「そう?ありがとう」
「別に。仕事だ」
ライバ・カイネウスを大学三年次相当に持ち上げるまで、一ヶ月も掛からなかった。
スポンジのように知識を吸い込み、それを決して溢れさせることがない。過剰にも思える知識を全て受け入れ、当然のように行使している。ごく短い間につくられた大学生だとは、誰も思いはしないだろう。
「ぼくは使われる生き物だから。使ってもらえるのなら、それに越したことはない」
「……それが、得体のしれない場所へ向かわされることでも?」
使われる生き物。ライバは常に自分のことをそう呼称していた。
それは、クレールたちの中でも共有されている理念だった。物以上として扱うな。それは高級な実験器具以外の何物でもない。必然的にその思考が根付いていない紀野が様々な担当から外され、同様に優しすぎるきらいのある二ノ平も外された。
最も“割り切れている”クレール、異能で“割り切ることのできる”西村、そもそもあまり他人に興味を持たない宮城野の三人で回しているが、学内での振る舞いを担当していた宮城野の出る幕はもうほぼなくなった。
戦い方を教えるクレールと、誤魔化し方を教える西村だけがいればいい。そして、一度教えたことを教え直す必要はなく、一度撃たせれば習熟度合いは判別できた。
これほどまでに無駄のない生き物がいる、という事実に、静かに目を背けたくなる。人間には無駄が多すぎると思い始めると、キリがないのは事実だ。
「抵抗はないな。だって、ぼくはそもそも、生み出されなければ生まれることもなかった。そういう点では、実験動物と変わりないと思うんだけど……」
「あー、モデル生物の変異体とかか。あれはまあ……知りたいが故のエゴ、みたいなところあるからな。動物愛護法もめんどくせえし」
傲慢で、貪欲な生き物だ。知りたいものに手を伸ばし、そのためなら他種の犠牲は厭わない。生存、快適さ、あるいは病気の駆逐のために、数多の哺乳類を犠牲にし、“そのためなら生命の枠組みすら組み替える”。繰り返すが、人間は傲慢な生き物だ。彼らが痛みを、苦痛を感じるのならそれを尊べ――それすらも、人のエゴ。少なくともクレールはそう思っているし、恐らく大日向も同じことを言うだろう。
「そうだね。ぼくは……もうちょっと尊ばれていた、というのも変だけど。それは材料が貴重だからだと思う」
「自己分析が出来ているやつを相手にするときほど楽なことはない」
大日向が持ち帰ってきたかの世界の記録は、ごく狭い範囲でとどまっている。
“彼ら”は、もっと先に進んでいるはずだ。その先にこの生き物を解き放つためには、もう少し鍛えてやる必要があると思っていた。
「お前は戦うのか?」
「えー……やだな。ぼくはそういうの向いてない」
「だろうな。あの店で店主から何か教わらなかったのか」
「軽い迷彩くらい……?」
「……チッ。これだから絶対中立主義は……」
異能登録データベースから、自分たち、あるいは創峰――紫筑大学の学生の中で、比較的汎用性が高く、逃げの一手・あるいはいざという時の防御として使えそうな異能を検索する。
データダウンロードに時間がかかることさえ除けば、それが最前の択だった。教えることはではなくても、パライバトルマリンはデータから使い方を構築し、その通りに使用する。
「もっとなにか教えてくれるのかい」
「当たり前だ。大日向の観測結果が確かなら、狭間は厳しい場所だ。戦闘を避ける手段は多いほうがいい」
キャスターつきの椅子に座って、転がって移動することを教えたのは大日向だ。
そういうどうでもいいことは切り捨てるべきでは、と上申したが、どうでもいいことが人間らしさを生む、の一言で全てが終わった。彼はこれからかの世界に送り込まれるだけではなく、一般大学生として生活をすることになる。
そういう無駄を教えるのは、紀野や宮城野の担当になるんだろう。大日向たちの理念さえ教え込めば、それはその理念のとおりに動き、余計なものを排除する。必要な時にだけものを取り出して利用する。そのようにできていることを、悲しむ人は今の段階に向いていない。
「優しいんだね」
「勘違いするな。俺たちにとってお前は、作戦遂行の駒に過ぎない。それも高い買い物をしているんだから、大切にして当然だ。……それ以上でも以下でもない、俺にとっては」
「うん。それはそれで正しいと思う」
何故だろう。割り切っているはずなのに、この生き物と話すとイライラした。
それがどこに起因するものかどうかは、きちんと調べてみないとわからないだろう。その機会も、資源も、技術も、場所も、この世界にはない。
だから今は、割り切るしかない。
「他がどう思っているかは知らん。俺がそう思っているだけだ」
「……そう。君、結構ツンデレだよね」
「奇遇だな。俺はどうしてお前の相手をしているとイライラするのか知りたかったところだ」
次はこれだ、と差し出したプリントが受け取られ、クレールは瞑目した。
そのうち、もう大丈夫、とプリントが突き返されてくるのだ。それはこういう生き物だと学習した。
なのに何故。
(こいつはこんなにムカつくんだ)
それを表に出すことはない。
ライバ・カイネウスには不要な情報だった。

付与されたナンバーはbc121。
それを受け取った順番――男の声を聞いた順番は、時に重要な意味を持つ。今回121番目に声を聞いた人はもう別にいるはずで、それを利用する。そして、未だに後からこの世界に訪れる人は存在する。
早い話が後付けのバグにしてチート行為だ。狭間への門戸は決して広いとは言えず、故にうまく、“誤魔化して声を聞く必要があった”。
『空き番号を探そうとも思ったが、どうにも面倒でな』
「いいよ。面倒でない方で」
『断じてお前のためではない。ボクたちのリスクを減らすためだ』
パライバトルマリンに課された任務は二つ。
ひとつ、怪異『鈴のなる夢』と接触すること。
ひとつ、怪異『鈴のなる夢』と交渉を行うこと。
“前の持ち主”のものが少しばかり残っていて、舌戦についてはあまり鍛える必要がなかった。それが残っているということは、パライバトルマリンは道に迷わないということも意味した。
そして、この過程を行う中で、接触するひとは最低限にすること。それもまた、可能ならと示された条件だった。
要するに、バグ技で立ち入っているのだから、極力姿を現すな、ひとりでやれ、ということだ。いくら素にされた生き物が世界の因果を無視するものだったとしても、全てがパライバトルマリンに残っているかは分からない。残っていたらそもそも捕まることもなかったはずだし、ないと思っておいたほうがいい。
『因果干渉は基本的に紫筑では禁忌だ。――創峰では知らんがな』
「なんだかあれだよな。口プロレスっていうか、重箱の隅をつつくっていうかだ」
『教授なんてそんなものよ。ましてや学生相手にはな』
声だけでも分かる。大日向というひとは、この世界を楽しみ尽くす気満々で、そのためなら手段を選ばない。
中立主義を謳う男よりずっと楽しいのは事実だったが、底が知れない人間の相手が疲れることに変わりはなかった。それでも待遇はずっといい。捕まえるだけ捕まえて、軟禁状態にしていたあの男よりは。
『データを送る。これが吉野暁海から計測した最後だ。結論から言うと、全くよくはない』
「……奇遇だね。受け取る前からそんな気がしてたよ」
与えられた異能は、記憶の送信と変化、そして高速起動。
そんなにもらっていいのか、と思うほど受け取った。逆に言えば、それだけ過酷な場所なのかもしれない。それ以上に、感情を感じ取る、元から備わっている器官が激しく動く。
怒り。悲しみ。無力感。怒り。罪悪感。怒り。怒り。拒絶。強い拒絶。凍てつくような拒絶。触れるもの皆凍らせるような拒絶。絶望。怒り。二人分の行き場のない感情の嵐。
(……そうだね、これを最悪と呼ばずして何と呼ぶんだろう)
理解不能。あるいは何らかの事案。本の世界での再会ですら奇跡だったのに、一体何があったのだろう。
『基本的にベースキャンプでしか様々なことは行えん。今何か感じているならフィードバックをしろ』
「オーケー。あなたの言う通り、全くよくないね」
あの人は、こんなに荒れ狂うような人だったろうか?
それとも、この狭間では異能が強化されるから、その影響だろうか?
――少なくとも後者は違う。違うことが分かってしまう。あの先生は、元の世界、生きていた時ですら、ほとんど力を持たなかった。死んでからだって、本の装丁でようやく力を得るような、そういう――ただの、人だった。
『受領した。……タイミングがよかったようだな、人に紛れてタクシーに乗れ。同じものには乗るなよ、さすがに感づかれん自信はない』
「ぼくもそれはさすがにないな……うん、分かってるとも。次戻ってくるまでに、その“感情”を解析してほしい。」
『ふむ。いいだろう……感情の解析か。興味深い』
「そこに、異能が絡んでいるかどうかが知りたいんだ。別に急ぎのことじゃないから、結果は戻ってきたときでいいよ」
この場所特有のことであることを祈りたかった。けれど、答えはずっと後にならないと出ない。はじめから分かっていて、それでもそれを頼む。人間のすることによく似ていた。
答えは恐らく、会ったそのときにもう分かる。今意図的にベースキャンプで身を隠していて、――タイミングが良くて。運も良くて。今からでも話しに行ける。それをしない理由は、ただひとつだった。
『なるほどな。お前は何らかの変化を受け取っているということか』
「……うん」
人間は変質する。それが死後にまで及ぶかどうかは分からない。基本的に人間にとって、死後の領域は専門ではない。形骸的な宗教、祈り、それらが死者と生者をゆるく繋ぐのみだ。
真にパライバトルマリンが神の御使いであったなら、それをよく知っていたはずだった。けれども、自分は死にかけた御使いを細切れにした上で、魔改造を施された、それ以下のものに過ぎない。
だから分からなかった。だから問いかけてみるしかなかった。
『ではそろそろ切る。ボクはそもそも狭間など知らないからな』
「了解。ミッションスタートします」
素知らぬ顔で、次元タクシーとやらに相乗りをする。良さげな集団が来るのを身を隠して待つ間、せわしなく動いていた触角が垂れた。
(……先生、何に怒っているの?)



ENo.426 アストロイェライ とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.3 不思議な装飾 を破棄しました。
ItemNo.4 水の護り を破棄しました。
ItemNo.5 異本の栞 を破棄しました。












六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



フェデルタ(165) から 80 PS 受け取りました。
サクヤさんSUN(401) に 200 PS 送付しました。
わこちゃん(1171) に 20 PS 送付しました。
菫(450) に 80 PS 送付しました。
ふゆげ(1019) に ItemNo.17 肉端のしぐれ煮 を送付しました。
ヤシロ(605) に ItemNo.15 栄養ドリンク を送付しました。
姫子(618) に ItemNo.14 柳 を送付しました。
サクヤさんSUN(401) から 良い石材 を受け取りました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV55⇒60、-5CP)
フェデルタ(165) により ItemNo.3 良い石材 から射程3の武器『グレイスフルブリンガー』を作製してもらいました!
⇒ グレイスフルブリンガー/武器:強さ140/[効果1]体力15 [効果2]- [効果3]-【射程3】
サクヤさんSUN(401) の持つ ItemNo.1 たけのこ から料理『たけのこごはん(ごんごうだき)』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.19 不思議な食材 から料理『中身不明のおにぎり』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.8 お野菜 から料理『サクサク野菜チップス』をつくりました!
わこちゃん(1171) により ItemNo.2 サレクススピン に ItemNo.16 毛 を付加してもらいました!
⇒ サレクススピン/装飾:強さ120/[効果1]風柳15 [効果2]回復10 [効果3]-
弥琴(37) とカードを交換しました!
プライドファイト (フィアスファング)

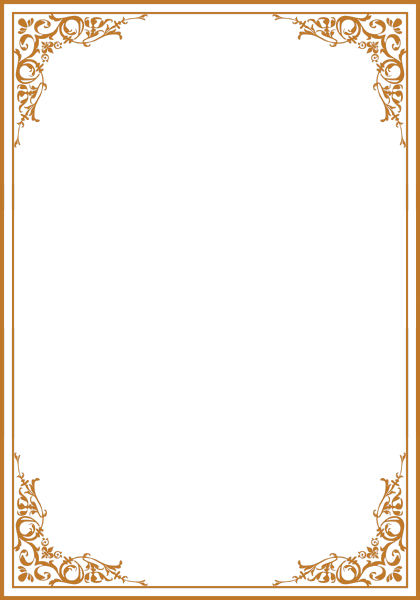
フレイムインパクト を研究しました!(深度0⇒1)
フレイムインパクト を研究しました!(深度1⇒2)
フレイムインパクト を研究しました!(深度2⇒3)
ティンダー を習得!
カームフレア を習得!
コントラスト を習得!
ファイアレイド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



迦楼羅(931) は 赤い薔薇 を入手!
フェデルタ(165) は 赤い薔薇 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 触手 を入手!
迦楼羅(931) は 触手 を入手!
迦楼羅(931) は 触手 を入手!
グノウ(909) は 触手 を入手!
グノウ(909) は 良いお肉 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ホスト がスキップしながら近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに チンピラ が興味津々な様子で近づいてきます。



次元タクシーに乗り ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 に転送されました!
ヒノデ区 M-10(道路)に移動!(体調30⇒29)
ヒノデ区 M-9(道路)に移動!(体調29⇒28)
ヒノデ区 M-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 M-7(道路)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 M-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- スズヒコ(244) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- スズヒコ(244) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)





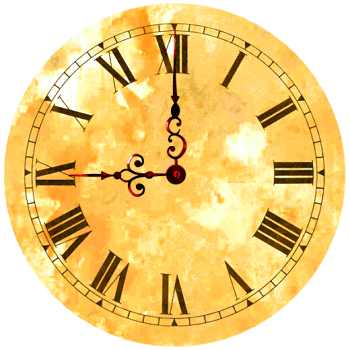
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
ザザッ――
ザザッ――
ザザッ――
チャットが閉じられる――













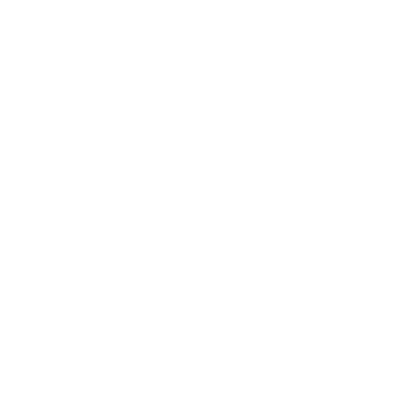
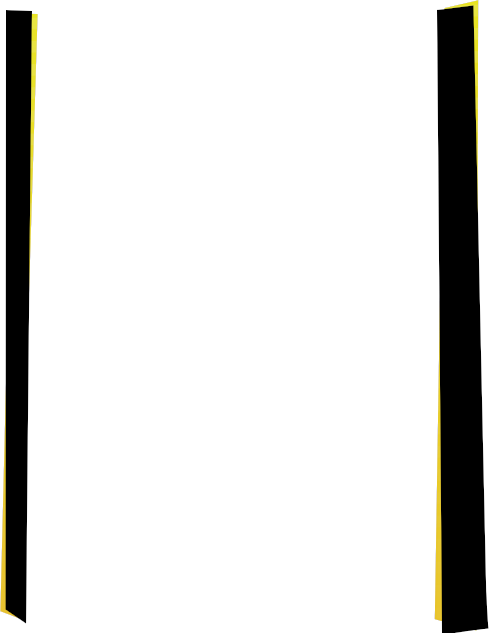
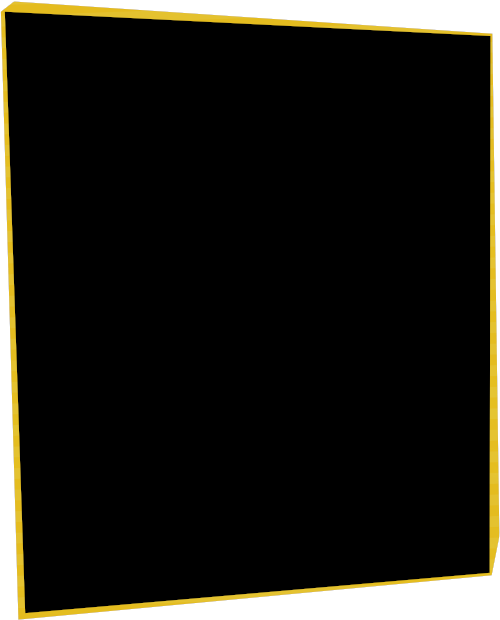





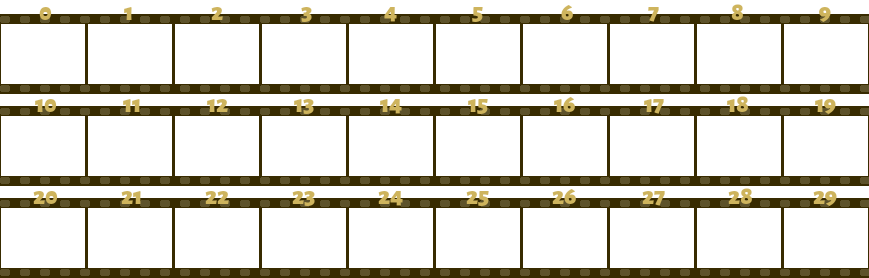









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




大日向研のすぐ向かいの学生室で、クレールたちはパライバ――いや、ライバ・カイネウスに対して、様々な指導を行っていた。人間としての振る舞い方に始まり、大学生として違和感のない状態にするための知識、――そしてかの世界の狭間における戦闘用の技能。
それら全てを、ライバはなんてことのないように飲み込む。容れ物に好きなものを注げ、と言われた時、それが得体のしれないものに変質しないか、それを真っ先に心配するだろう。けれど、パライバトルマリンにはそれがない。いつの間にか区切りが設置されていて、そしてなみなみと、それ以上に注いでいるはずなのに、底が知れない。
「……ほんと飲み込み早いな……ドン引きするほど早い」
「そう?ありがとう」
「別に。仕事だ」
ライバ・カイネウスを大学三年次相当に持ち上げるまで、一ヶ月も掛からなかった。
スポンジのように知識を吸い込み、それを決して溢れさせることがない。過剰にも思える知識を全て受け入れ、当然のように行使している。ごく短い間につくられた大学生だとは、誰も思いはしないだろう。
「ぼくは使われる生き物だから。使ってもらえるのなら、それに越したことはない」
「……それが、得体のしれない場所へ向かわされることでも?」
使われる生き物。ライバは常に自分のことをそう呼称していた。
それは、クレールたちの中でも共有されている理念だった。物以上として扱うな。それは高級な実験器具以外の何物でもない。必然的にその思考が根付いていない紀野が様々な担当から外され、同様に優しすぎるきらいのある二ノ平も外された。
最も“割り切れている”クレール、異能で“割り切ることのできる”西村、そもそもあまり他人に興味を持たない宮城野の三人で回しているが、学内での振る舞いを担当していた宮城野の出る幕はもうほぼなくなった。
戦い方を教えるクレールと、誤魔化し方を教える西村だけがいればいい。そして、一度教えたことを教え直す必要はなく、一度撃たせれば習熟度合いは判別できた。
これほどまでに無駄のない生き物がいる、という事実に、静かに目を背けたくなる。人間には無駄が多すぎると思い始めると、キリがないのは事実だ。
「抵抗はないな。だって、ぼくはそもそも、生み出されなければ生まれることもなかった。そういう点では、実験動物と変わりないと思うんだけど……」
「あー、モデル生物の変異体とかか。あれはまあ……知りたいが故のエゴ、みたいなところあるからな。動物愛護法もめんどくせえし」
傲慢で、貪欲な生き物だ。知りたいものに手を伸ばし、そのためなら他種の犠牲は厭わない。生存、快適さ、あるいは病気の駆逐のために、数多の哺乳類を犠牲にし、“そのためなら生命の枠組みすら組み替える”。繰り返すが、人間は傲慢な生き物だ。彼らが痛みを、苦痛を感じるのならそれを尊べ――それすらも、人のエゴ。少なくともクレールはそう思っているし、恐らく大日向も同じことを言うだろう。
「そうだね。ぼくは……もうちょっと尊ばれていた、というのも変だけど。それは材料が貴重だからだと思う」
「自己分析が出来ているやつを相手にするときほど楽なことはない」
大日向が持ち帰ってきたかの世界の記録は、ごく狭い範囲でとどまっている。
“彼ら”は、もっと先に進んでいるはずだ。その先にこの生き物を解き放つためには、もう少し鍛えてやる必要があると思っていた。
「お前は戦うのか?」
「えー……やだな。ぼくはそういうの向いてない」
「だろうな。あの店で店主から何か教わらなかったのか」
「軽い迷彩くらい……?」
「……チッ。これだから絶対中立主義は……」
異能登録データベースから、自分たち、あるいは創峰――紫筑大学の学生の中で、比較的汎用性が高く、逃げの一手・あるいはいざという時の防御として使えそうな異能を検索する。
データダウンロードに時間がかかることさえ除けば、それが最前の択だった。教えることはではなくても、パライバトルマリンはデータから使い方を構築し、その通りに使用する。
「もっとなにか教えてくれるのかい」
「当たり前だ。大日向の観測結果が確かなら、狭間は厳しい場所だ。戦闘を避ける手段は多いほうがいい」
キャスターつきの椅子に座って、転がって移動することを教えたのは大日向だ。
そういうどうでもいいことは切り捨てるべきでは、と上申したが、どうでもいいことが人間らしさを生む、の一言で全てが終わった。彼はこれからかの世界に送り込まれるだけではなく、一般大学生として生活をすることになる。
そういう無駄を教えるのは、紀野や宮城野の担当になるんだろう。大日向たちの理念さえ教え込めば、それはその理念のとおりに動き、余計なものを排除する。必要な時にだけものを取り出して利用する。そのようにできていることを、悲しむ人は今の段階に向いていない。
「優しいんだね」
「勘違いするな。俺たちにとってお前は、作戦遂行の駒に過ぎない。それも高い買い物をしているんだから、大切にして当然だ。……それ以上でも以下でもない、俺にとっては」
「うん。それはそれで正しいと思う」
何故だろう。割り切っているはずなのに、この生き物と話すとイライラした。
それがどこに起因するものかどうかは、きちんと調べてみないとわからないだろう。その機会も、資源も、技術も、場所も、この世界にはない。
だから今は、割り切るしかない。
「他がどう思っているかは知らん。俺がそう思っているだけだ」
「……そう。君、結構ツンデレだよね」
「奇遇だな。俺はどうしてお前の相手をしているとイライラするのか知りたかったところだ」
次はこれだ、と差し出したプリントが受け取られ、クレールは瞑目した。
そのうち、もう大丈夫、とプリントが突き返されてくるのだ。それはこういう生き物だと学習した。
なのに何故。
(こいつはこんなにムカつくんだ)
それを表に出すことはない。
ライバ・カイネウスには不要な情報だった。

付与されたナンバーはbc121。
それを受け取った順番――男の声を聞いた順番は、時に重要な意味を持つ。今回121番目に声を聞いた人はもう別にいるはずで、それを利用する。そして、未だに後からこの世界に訪れる人は存在する。
早い話が後付けのバグにしてチート行為だ。狭間への門戸は決して広いとは言えず、故にうまく、“誤魔化して声を聞く必要があった”。
『空き番号を探そうとも思ったが、どうにも面倒でな』
「いいよ。面倒でない方で」
『断じてお前のためではない。ボクたちのリスクを減らすためだ』
パライバトルマリンに課された任務は二つ。
ひとつ、怪異『鈴のなる夢』と接触すること。
ひとつ、怪異『鈴のなる夢』と交渉を行うこと。
“前の持ち主”のものが少しばかり残っていて、舌戦についてはあまり鍛える必要がなかった。それが残っているということは、パライバトルマリンは道に迷わないということも意味した。
そして、この過程を行う中で、接触するひとは最低限にすること。それもまた、可能ならと示された条件だった。
要するに、バグ技で立ち入っているのだから、極力姿を現すな、ひとりでやれ、ということだ。いくら素にされた生き物が世界の因果を無視するものだったとしても、全てがパライバトルマリンに残っているかは分からない。残っていたらそもそも捕まることもなかったはずだし、ないと思っておいたほうがいい。
『因果干渉は基本的に紫筑では禁忌だ。――創峰では知らんがな』
「なんだかあれだよな。口プロレスっていうか、重箱の隅をつつくっていうかだ」
『教授なんてそんなものよ。ましてや学生相手にはな』
声だけでも分かる。大日向というひとは、この世界を楽しみ尽くす気満々で、そのためなら手段を選ばない。
中立主義を謳う男よりずっと楽しいのは事実だったが、底が知れない人間の相手が疲れることに変わりはなかった。それでも待遇はずっといい。捕まえるだけ捕まえて、軟禁状態にしていたあの男よりは。
『データを送る。これが吉野暁海から計測した最後だ。結論から言うと、全くよくはない』
「……奇遇だね。受け取る前からそんな気がしてたよ」
与えられた異能は、記憶の送信と変化、そして高速起動。
そんなにもらっていいのか、と思うほど受け取った。逆に言えば、それだけ過酷な場所なのかもしれない。それ以上に、感情を感じ取る、元から備わっている器官が激しく動く。
怒り。悲しみ。無力感。怒り。罪悪感。怒り。怒り。拒絶。強い拒絶。凍てつくような拒絶。触れるもの皆凍らせるような拒絶。絶望。怒り。二人分の行き場のない感情の嵐。
(……そうだね、これを最悪と呼ばずして何と呼ぶんだろう)
理解不能。あるいは何らかの事案。本の世界での再会ですら奇跡だったのに、一体何があったのだろう。
『基本的にベースキャンプでしか様々なことは行えん。今何か感じているならフィードバックをしろ』
「オーケー。あなたの言う通り、全くよくないね」
あの人は、こんなに荒れ狂うような人だったろうか?
それとも、この狭間では異能が強化されるから、その影響だろうか?
――少なくとも後者は違う。違うことが分かってしまう。あの先生は、元の世界、生きていた時ですら、ほとんど力を持たなかった。死んでからだって、本の装丁でようやく力を得るような、そういう――ただの、人だった。
『受領した。……タイミングがよかったようだな、人に紛れてタクシーに乗れ。同じものには乗るなよ、さすがに感づかれん自信はない』
「ぼくもそれはさすがにないな……うん、分かってるとも。次戻ってくるまでに、その“感情”を解析してほしい。」
『ふむ。いいだろう……感情の解析か。興味深い』
「そこに、異能が絡んでいるかどうかが知りたいんだ。別に急ぎのことじゃないから、結果は戻ってきたときでいいよ」
この場所特有のことであることを祈りたかった。けれど、答えはずっと後にならないと出ない。はじめから分かっていて、それでもそれを頼む。人間のすることによく似ていた。
答えは恐らく、会ったそのときにもう分かる。今意図的にベースキャンプで身を隠していて、――タイミングが良くて。運も良くて。今からでも話しに行ける。それをしない理由は、ただひとつだった。
『なるほどな。お前は何らかの変化を受け取っているということか』
「……うん」
人間は変質する。それが死後にまで及ぶかどうかは分からない。基本的に人間にとって、死後の領域は専門ではない。形骸的な宗教、祈り、それらが死者と生者をゆるく繋ぐのみだ。
真にパライバトルマリンが神の御使いであったなら、それをよく知っていたはずだった。けれども、自分は死にかけた御使いを細切れにした上で、魔改造を施された、それ以下のものに過ぎない。
だから分からなかった。だから問いかけてみるしかなかった。
『ではそろそろ切る。ボクはそもそも狭間など知らないからな』
「了解。ミッションスタートします」
素知らぬ顔で、次元タクシーとやらに相乗りをする。良さげな集団が来るのを身を隠して待つ間、せわしなく動いていた触角が垂れた。
(……先生、何に怒っているの?)



ENo.426 アストロイェライ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.3 不思議な装飾 を破棄しました。
ItemNo.4 水の護り を破棄しました。
ItemNo.5 異本の栞 を破棄しました。





鵺 -nue-
|
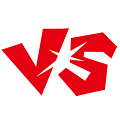 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|



ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
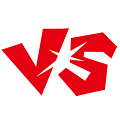 |
立ちはだかるもの
|



ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



フェデルタ(165) から 80 PS 受け取りました。
サクヤさんSUN(401) に 200 PS 送付しました。
わこちゃん(1171) に 20 PS 送付しました。
菫(450) に 80 PS 送付しました。
ふゆげ(1019) に ItemNo.17 肉端のしぐれ煮 を送付しました。
ヤシロ(605) に ItemNo.15 栄養ドリンク を送付しました。
姫子(618) に ItemNo.14 柳 を送付しました。
サクヤさんSUN(401) から 良い石材 を受け取りました。
 |
サクヤ 「ありがとうございますっ!これは頼まれていた物品ですっ!」 |
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV55⇒60、-5CP)
フェデルタ(165) により ItemNo.3 良い石材 から射程3の武器『グレイスフルブリンガー』を作製してもらいました!
⇒ グレイスフルブリンガー/武器:強さ140/[効果1]体力15 [効果2]- [効果3]-【射程3】
 |
いつの間にか、置かれている |
サクヤさんSUN(401) の持つ ItemNo.1 たけのこ から料理『たけのこごはん(ごんごうだき)』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.19 不思議な食材 から料理『中身不明のおにぎり』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.8 お野菜 から料理『サクサク野菜チップス』をつくりました!
わこちゃん(1171) により ItemNo.2 サレクススピン に ItemNo.16 毛 を付加してもらいました!
⇒ サレクススピン/装飾:強さ120/[効果1]風柳15 [効果2]回復10 [効果3]-
弥琴(37) とカードを交換しました!
プライドファイト (フィアスファング)

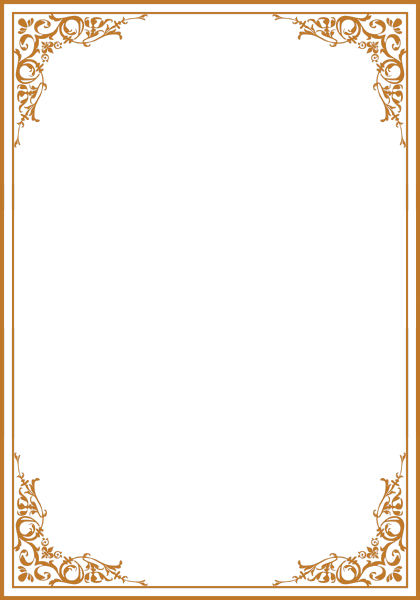
フレイムインパクト を研究しました!(深度0⇒1)
フレイムインパクト を研究しました!(深度1⇒2)
フレイムインパクト を研究しました!(深度2⇒3)
ティンダー を習得!
カームフレア を習得!
コントラスト を習得!
ファイアレイド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



迦楼羅(931) は 赤い薔薇 を入手!
フェデルタ(165) は 赤い薔薇 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 触手 を入手!
迦楼羅(931) は 触手 を入手!
迦楼羅(931) は 触手 を入手!
グノウ(909) は 触手 を入手!
グノウ(909) は 良いお肉 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ホスト がスキップしながら近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに チンピラ が興味津々な様子で近づいてきます。



次元タクシーに乗り ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ほら降りた降りた。次の客が待ってんだわ。」 |
ヒノデ区 M-10(道路)に移動!(体調30⇒29)
ヒノデ区 M-9(道路)に移動!(体調29⇒28)
ヒノデ区 M-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 M-7(道路)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 M-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- スズヒコ(244) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- スズヒコ(244) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)





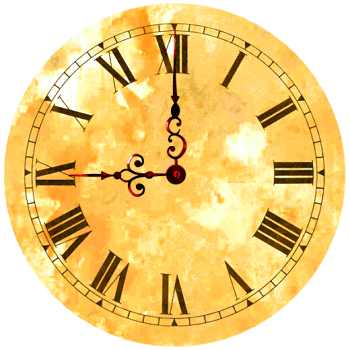
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・怖いだろうがよ。」 |
 |
エディアン 「・・・勘弁してくれませんか。」 |
 |
白南海 「ナレハテってあの!アレだろォッ!!?ドッロドロしてんじゃねーっすか!! なんすかあれキッモいのッ!!うげぇぇぇぇうげえええぇぇぇ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「私だって嫌ですよあんなの・・・・・ ・・・え、案内役って影響力どういう扱いに・・・??私達は関係ないですよね・・・????」 |
 |
白南海 「あんたアンジニティならそーゆーの平気じゃねーんすか? 何かアンジニティってそういう、変な、キモいの多いんじゃ?」 |
 |
エディアン 「こんな麗しき乙女を前に、ド偏見を撒き散らさないでくれます? 貴方こそ、アレな業界の人間なら似たようなの見慣れてるでしょうに。」 |
 |
白南海 「あいにくウチはキレイなお仕事しかしてないもんで。えぇ、本当にキレイなもんで。」 |
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
 |
白南海 「・・・っつーか、あれ本当にドライバーのオヤジっすか?何か雰囲気違くねぇ・・・??」 |
 |
エディアン 「まぁ別の何か、でしょうね。 雰囲気も言ってることも別人みたいでしたし。普通に、スワップ発動者さん?・・・うーん。」 |
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
 |
エディアン 「・・・・・?なんでしょう、何か変な雑音が。」 |
ザザッ――
 |
白南海 「ただの故障じゃねーっすか。」 |
ザザッ――
 |
声 「――・・・レーション、ヒノデコーポレーション。 襲撃に・・・・・・・・いる・・・ 大量・・・・・こ・・・・・・死体・・・・・・ゾ・・・・・・」 |
 |
声 「・・・・・ゾンビだッ!!!!助け――」 |
ザザッ――
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「ホラーはぁぁ――ッ!!!! やぁぁめろォォ―――ッ!!!!」 |
 |
エディアン 「勘弁してください勘弁してくださいマジ勘弁してください。 ホラーはプレイしないんですコメ付き実況でしか見れないんですやめてください。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
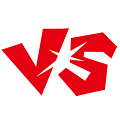 |
鋼響戦隊
|


ENo.244
鈴のなる夢
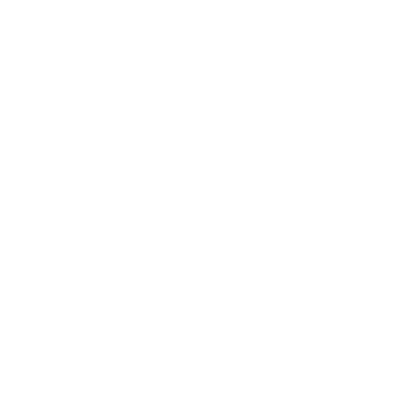
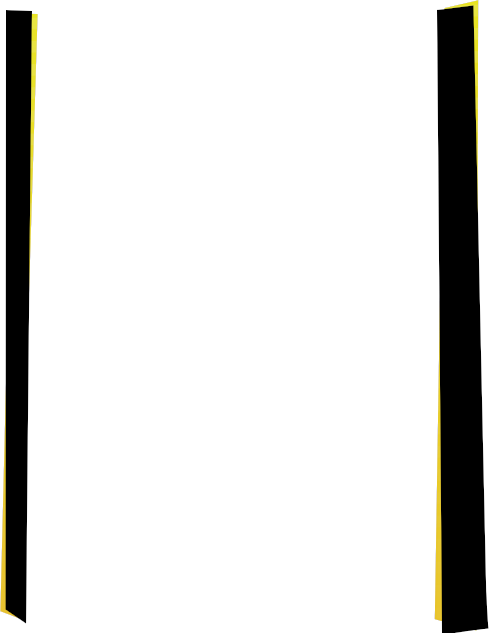
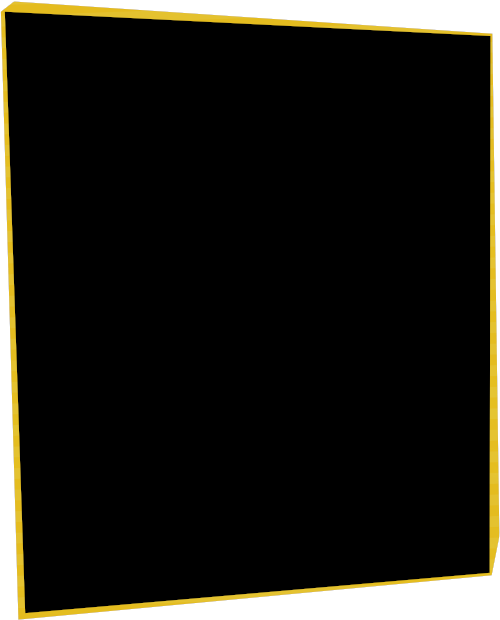
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
25 / 30
319 PS
ヒノデ区
M-6
M-6







痛撃友の会
8
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
1
アイコン60pxの会
4
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
6
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
4
カード報告会
10
とりあえず肉食う?
9



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | - | - | 【射程3】 |
| 4 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 5 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 山査子 | 素材 | 15 | [武器]防疫15(LV30)[防具]耐疫10(LV20)[装飾]快癒10(LV25) | |||
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | - | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 触手 | 素材 | 20 | [武器]器用20(LV30)[防具]迫撃20(LV40)[装飾]舞縛20(LV35) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 25 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 60 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| 練3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| 練2 | ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| 練1 | エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) |
| 練1 | リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 |
| 練3 | フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| 練2 | マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 練3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| 練1 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| 練1 | ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 9 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| 練3 | ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 |
| 練3 | サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
| 練1 | アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| グレイシア | 5 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| 練3 | サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 練1 | 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練1 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
|
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
| 練3 |
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]フィジカルブースター |
| [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]フレイムインパクト | [ 3 ]プロテクション |

PL / 紙箱みど