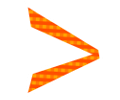<< 6:00~7:00





俺たちはきっといつか、やんごとなき理由でぶつかり合うだろう。そう思っている。
俺の些細なことを気に留める性格が、あなたのことを許さない。それを知っているからだ。こうして理性があるうちは、いくらでも解決しようがある。けれど、きっといつか――
俺たちは、対話以外の方法で、物事を解決しようとする。
これは予言とかそういったものではなく、ただの自己分析だ。
俺は何も言わないし、彼もまた何も言わない。俺たちはいつだって、危ない綱渡りを続けている。
どうして俺たちが何も言わないか、それは単純なことで、『言って割を食いすぎた』か、『言っても無駄だと思っている』からだ。組み合わせで言えば最悪だ。
俺はできることなら本当に何も言いたくないし、そのためなら何でもしようと思っている。そう、例えば、こうやって記すとか。
俺たちはお互いに人間が下手くそで、それは人間でなくなっても何も変わりはしなかった。本質として根付いているものが、何度死んでも己の肉体を苛むのはよく分かった。癖は治らない。ましてや死後矯正しようというのなら、だ。
俺はあなたが思っているよりずっと弱い人間で、それを隠そうとする人間で、それは――いつか考えうる最悪の事象を引き起こすはずだ。俺は追い詰められれば追い詰められるほど、周りを見ようとしなくなる。そうやって死んでいった。そうやって全てを灰燼に帰し、どのような因果か、ろくに顔を見せたことのない娘に呼び戻されてしまった。
下の娘は、ある意味で俺によく似ていた。お世辞などを被せるまでもなく、彼女は俺にそっくりだった。いつ死んでもいいように心を閉ざして、そして危険な場所に出向く。望んで狩人になったわけではないだろうけれど、そこに至るまでのことは俺によく似ていた。
彼女は運が良かった。そして俺はどちらかと言えば運が悪かった。僅かな偶然が本の世界へと彼女を導き、そして俺を呼んでしまった。俺は本の中で少しずつ“人間”としての姿を取り戻していった。物語にそう願われていたからだ。けれども、ある別離に耐えかねた彼女の弱みに付け込むような異教の本の呪いを、少しずつ人としての感覚を取り戻していた俺が、一手に引き受ける覚悟をした。そこで“人間”としての俺は完全に終了し、冷たい手だけが残った。
冷たい手のまま、かつての家族に背中を押され、俺は旅をする決意をした。探究心を認めてくれる家族は、とうの昔にバラバラになっていた。後ろめたさや名残惜しさがない、と言えば嘘になる。だが、彼女らは自分の背中を押してくれた。妻はとうに死んでいて、娘たちはとうに大人になっていた。俺の後ろめたさは全て家族を崩してしまったというところにあったが。彼女たちは口を揃えて『仕方ない』と言った。
だから俺は、異形と炎を抱えて、飛び回る旅人になった。根無し草もいいところだった。
ヒトはみな、防衛機制という精神を守る機序を持っている。それは、ヒトであった俺にも等しく適用され、俺はひたすら合理化と抑圧を振りかざして生き延びてきた。
要するに、俺は悪くない。要するに、全てを忘れようとする。
この二つを駆使するのが最も自分の中では楽で、誰もが愛他主義や受容行動を取れるわけではない。口は閉じていたほうが楽で、他人のせいにする方が楽なのだ。他にもその方がいいと思えば知性化も、解離もした。どうやっても成熟した防衛までには至れなかった。
所詮この程度の人間である、人間であった、と言ってしまえば、それで全てがおしまいだ。しかし、そういう人間である、という記述には、いつか意味が生じると考える。それが俺の最も恐れている、俺たちが対話以外でぶつかりあったとき、――その後に、役に立つはずなのだ。
なら初めから話し合っておけばいいのではないか、と思うだろう。
人間は忘れるようにできていて、俺にすべてが記載されていたとしても、記憶としては簡単に消え失せてしまう。ヒトの身では、あらゆる情報をその身に刻むことが難しい。ヒトの記憶領域は有限で、故に記録媒体が存在する。ヒトの身の中にすらだ。
DNAの使用されない領域に情報を入れ込もうという試みは、常に誤翻訳との戦いだ。故にまだ実用化には至らず、そしてこれからも恐らくはそうだろう。己は偶然にも外付けの力として記録する領域を得た、ただのヒトなのだ。
だから俺は忘れる。だから俺は覚えきれない。だけど俺には消えない記録媒体が外付けで存在し、それが人間と確かに袂を分かつ。
それを利用しない、という選択肢は、俺の中にはないのだ。
不出来だから手を伸ばすのではない。不出来だからこそ利用するのだ。それは、棚の上の物を取るために、踏み台を利用するくらい、自然なことだ。
それを思い出すのにだって、きっと時間がかかる。俺たちはそれくらい疲弊している。これを見て、何だそんなことだったのか、と呆気にとられるくらいには、きっと。

吉野暁海は、確かに火を見ていた。
その言葉も、その見たものも、全て己が知っていた。吉野暁海には参照する場所がない。恵まれた家庭で育ち、何の心配もすることなく進学し、守るべきものも背負わないま学んでいる。
それが確かに火の記憶を持って帰ってきて、咲良乃スズヒコは狼狽していた。
あの獣のような何かは、何をした?参照されないはずのものを映し出し、そして確かに干渉した。あの火の記憶は、吉野暁海のものではない。吉野暁海なんて人間はいないのだ。あれは間違いなく咲良乃スズヒコ、すなわち自分自身の記憶から参照され、そして引き出され、心的外傷として利用された。自分がそう思っている、自覚しているのだと言うことをたいへん忌々しく思った。いつまで経っても炎から逃れることが出来ない。
集団行動に支障のない範囲で、少し離れて歩くようになった。自分の能力があれば、多少離れたところであっても目も鼻も耳も利き、そこで何があったかくらいは察することが出来た。その方がほんの少しだけ気楽だった。獣は自分のところに寄ってくることもなく、時折思い出したように、視界を共有する。予定通りの歩みができていれば、それで全てが終わる。何を作って欲しいという話も、共有された聴覚で一瞬で伝わってくる。離れていても、というのが重要で、自分が時折木陰で蹲っても、引きずるほどの長い髪を結っている紐を解いて編み直しを始めても、それは彼らには伝わらない。あれは結局俺の一部だから、俺が伝えたくないものは伝えないのだ。
主従関係というには、歪で異質な関係だった。そもそも自分は、あのような獣を引き連れることはなく、あれは己の変身した姿だったはずだ。アンジニティに落ちて否定されてから、青かった手は少しずつ黒く染まった。さながら灰のようだった。もともとそれらしい爪なんて生えていなかったはずの前脚にそれが揃い、ラプトル系の前傾姿勢だった肉体は、前脚が発達するとともに四足歩行を主とするようになった。荒れ果てた地を踏み、そして荒れ果てた地に存在する生物を、罪人を、切り裂き、喰らい続けた。始めは確かに生き延びるためのことだったのをよく覚えていて、どんなに理屈をつけても、こんなことはしたくはない、こんなことをして生き延びるくらいなら、――そう思っていたはずだった。
人は慣れる。思っている以上に、ずっと早く。
“罪人”の首を刎ね、臓腑を喰らい、肉を裂いて骨を齧る。獣と何も変わらないようなことを始めるまで、そう時間は掛からなかった。そう記憶している。
『アンジニティの方々は暫くの間イバラシティの『仮の住人』となり、一時的に記憶・姿が『イバラシティに適応したもの』に置換されます。ひとまず与えられた記憶・姿に従ってイバラシティの住人として楽しんでください。』
何を勝手なことを言うのだろう、と初めは思っていた。
否定。侵略。全てが烏滸がましく、否定をしておいて利用しようというのか、と強く思った。何より一緒にされたくなかった。罪人たちが群れを成してどこかに向かっていく?
考えるだけで反吐が出る。ここには悪しかいないのだ。どうあれ結果に破滅しかない。それだけは嫌だった。それだけは絶対に嫌だった。自分を罪人どもと一緒にしないでほしかった。望みはただひとつで、そのためなら何でもしよう。何でもしなければならない。この爪もこの牙もこの体躯も、全てを賭けて、否定を否定しなければならない。
『イバラシティのために、ブチのめしちゃってください。』
気づいたら、そこは響奏の世界の陣営で、気づいたら、いつも通りにそこにフェデルタもいたのだ。否定を否定するためには、この機会を利用し尽くしてやるしかなかった。
全て。全てを。共に歩くひとも。手を組む人も。何もかもを。
こんなふざけた世界のためになんて、何一つしてやるものかと思う。
こんな世界に向かって奉仕をする必要があるなら、今すぐここで喉を掻き切って死ぬ。――死ぬことがなくても。
これは世界のためじゃない。自分のためだ。自分のため、前に進み続けなければならないのだ。わずか一時間、分にして六十分、秒にして三千六百秒で区切られ続け、そのたび押し潰すような幸せな記憶を押し付け、素知らぬ顔で幸せを享受する吉野暁海を殺すため、前に進まなければならないと、ここまでずっと思っていた。
火の記憶が参照されるまで、確かに。
自分は一体何のためにここまでの時間を過ごしてきたんだ?
従者と表面だけの付き合いを済ませ、その主人を料理で懐柔しようとし、――ずっと隣を歩いていたはずの、彼に。何もしていない。そこにいるのが当たり前だと思って。
全身が総毛立つような感覚があって、けれどすぐに消えていった。いつもそうだ。心配は必要ない。するだけ無駄だ。何故なら彼は“何も言わない”。
そして自分は“何も言いたくない”。失敗したくない。致命的な破滅への引き金を引きたくない。それはできれば他人のせいであってほしい。であれば、他人のせいにできるから。
――ああ、誰も味方だと思っていやしないのだ。全てがそこに収束し、血に濡れた手だけが語る。今の自分の味方であってほしくない。躊躇いなく喰い、殺し、引き裂く単なる獣の姿を、咲良乃スズヒコであると認めてほしくない。だから、だから、距離を置いて、突き放して、表面だけをなぞって。
そのままでいさせてほしかったのに。
「俺の言ってる事がお前にとって的外れならそれでいいよ。だけどよ、お前は何か考えたか?」
やめてほしい。その先の言葉を言うのはやめてほしかった。あなたはこれから俺の地雷を間違いなく踏むということすら言えない、ただ愚かに凍りついただけの怪物だ。
「――お得意の頭脳とやらはどうしたんだよ」
お前は知らない。頭脳の戦いを知らない。どれだけ俺がそれで苦しんだかも、知らない。
都合のいいところだけを拾う聴覚。解釈、そして防衛機制。それ以上続けるな、という衝動が、行動になってそのまま現れる。
知らない。知らない。知らないはずだ。知らないはずなのに、どうしてそんなことを言われなければならないのか。リジェクトされるたびの囁き声、査読にすら回してもらえない存在意義の欠如、――生前の怒りが燃え上がって貫通する。
「ねえ」
止められはしなかった。止めようともしなかった。



ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.15 焼き魚 を食べました!
体調が 1 回復!(16⇒17)
今回の全戦闘において 活力10 敏捷10 強靭10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








自然LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV15⇒25、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV50⇒55、-5CP)
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.14 パンの耳 から料理『サクサクパン耳ラスク(チョコ味)』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.7 お野菜 から料理『冷製ほうれん草ポタージュ』をつくりました!
ItemNo.17 ビーフ から料理『肉端のしぐれ煮』をつくりました!
⇒ 肉端のしぐれ煮/料理:強さ32/[効果1]活力5 [効果2]体力5 [効果3]防御5
E(1460) とカードを交換しました!
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー)
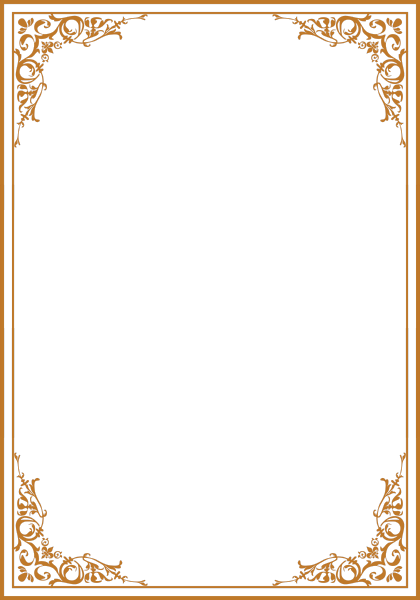
レーヴァテイン を研究しました!(深度0⇒1)
レーヴァテイン を研究しました!(深度1⇒2)
レーヴァテイン を研究しました!(深度2⇒3)
インヴァージョン を習得!
☆一望千里 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





ヒノデ区 J-11(道路)に移動!(体調17⇒16)
ヒノデ区 K-11(道路)に移動!(体調16⇒15)
ヒノデ区 L-11(道路)に移動!(体調15⇒14)
ヒノデ区 M-11(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
グノウ(909) からパーティに勧誘されました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 が発生!
- フェデルタ(165) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- スズヒコ(244) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- グノウ(909) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- 迦楼羅(931) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》





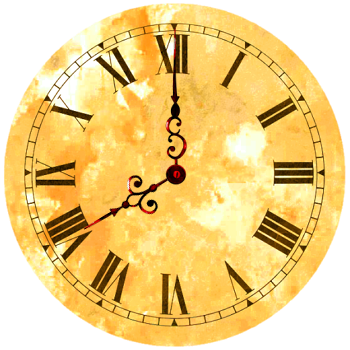
[787 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[347 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[301 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[75 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――
画面の情報が揺らぎ消えたかと思うと突然チャットが開かれ、
時計台の前にいるドライバーさんが映し出された。

チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)




















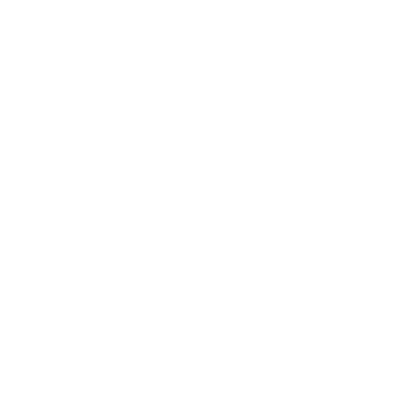
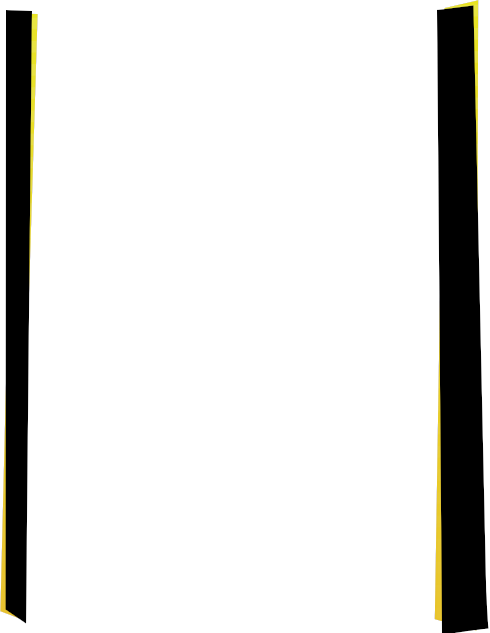
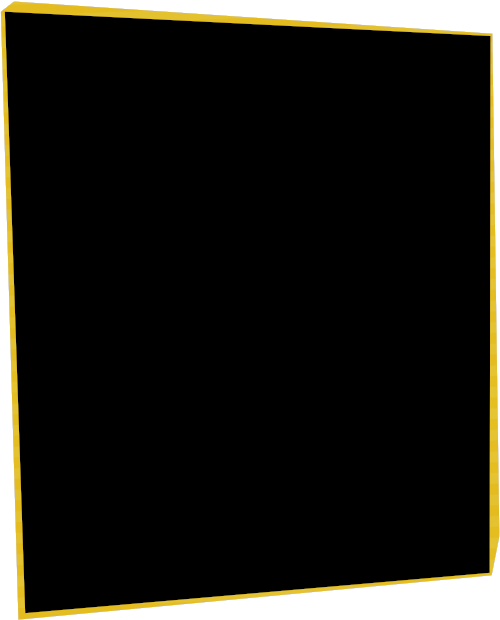





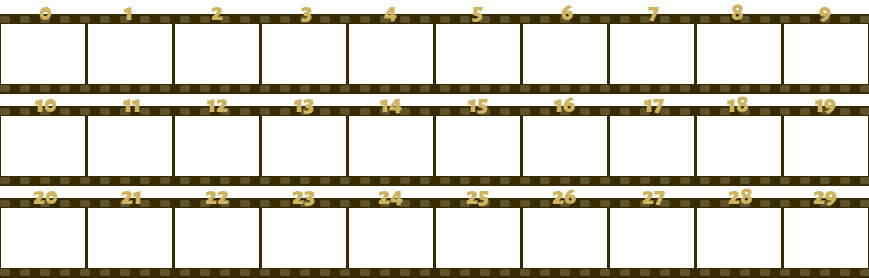









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




俺たちはきっといつか、やんごとなき理由でぶつかり合うだろう。そう思っている。
俺の些細なことを気に留める性格が、あなたのことを許さない。それを知っているからだ。こうして理性があるうちは、いくらでも解決しようがある。けれど、きっといつか――
俺たちは、対話以外の方法で、物事を解決しようとする。
これは予言とかそういったものではなく、ただの自己分析だ。
俺は何も言わないし、彼もまた何も言わない。俺たちはいつだって、危ない綱渡りを続けている。
どうして俺たちが何も言わないか、それは単純なことで、『言って割を食いすぎた』か、『言っても無駄だと思っている』からだ。組み合わせで言えば最悪だ。
俺はできることなら本当に何も言いたくないし、そのためなら何でもしようと思っている。そう、例えば、こうやって記すとか。
俺たちはお互いに人間が下手くそで、それは人間でなくなっても何も変わりはしなかった。本質として根付いているものが、何度死んでも己の肉体を苛むのはよく分かった。癖は治らない。ましてや死後矯正しようというのなら、だ。
俺はあなたが思っているよりずっと弱い人間で、それを隠そうとする人間で、それは――いつか考えうる最悪の事象を引き起こすはずだ。俺は追い詰められれば追い詰められるほど、周りを見ようとしなくなる。そうやって死んでいった。そうやって全てを灰燼に帰し、どのような因果か、ろくに顔を見せたことのない娘に呼び戻されてしまった。
下の娘は、ある意味で俺によく似ていた。お世辞などを被せるまでもなく、彼女は俺にそっくりだった。いつ死んでもいいように心を閉ざして、そして危険な場所に出向く。望んで狩人になったわけではないだろうけれど、そこに至るまでのことは俺によく似ていた。
彼女は運が良かった。そして俺はどちらかと言えば運が悪かった。僅かな偶然が本の世界へと彼女を導き、そして俺を呼んでしまった。俺は本の中で少しずつ“人間”としての姿を取り戻していった。物語にそう願われていたからだ。けれども、ある別離に耐えかねた彼女の弱みに付け込むような異教の本の呪いを、少しずつ人としての感覚を取り戻していた俺が、一手に引き受ける覚悟をした。そこで“人間”としての俺は完全に終了し、冷たい手だけが残った。
冷たい手のまま、かつての家族に背中を押され、俺は旅をする決意をした。探究心を認めてくれる家族は、とうの昔にバラバラになっていた。後ろめたさや名残惜しさがない、と言えば嘘になる。だが、彼女らは自分の背中を押してくれた。妻はとうに死んでいて、娘たちはとうに大人になっていた。俺の後ろめたさは全て家族を崩してしまったというところにあったが。彼女たちは口を揃えて『仕方ない』と言った。
だから俺は、異形と炎を抱えて、飛び回る旅人になった。根無し草もいいところだった。
ヒトはみな、防衛機制という精神を守る機序を持っている。それは、ヒトであった俺にも等しく適用され、俺はひたすら合理化と抑圧を振りかざして生き延びてきた。
要するに、俺は悪くない。要するに、全てを忘れようとする。
この二つを駆使するのが最も自分の中では楽で、誰もが愛他主義や受容行動を取れるわけではない。口は閉じていたほうが楽で、他人のせいにする方が楽なのだ。他にもその方がいいと思えば知性化も、解離もした。どうやっても成熟した防衛までには至れなかった。
所詮この程度の人間である、人間であった、と言ってしまえば、それで全てがおしまいだ。しかし、そういう人間である、という記述には、いつか意味が生じると考える。それが俺の最も恐れている、俺たちが対話以外でぶつかりあったとき、――その後に、役に立つはずなのだ。
なら初めから話し合っておけばいいのではないか、と思うだろう。
人間は忘れるようにできていて、俺にすべてが記載されていたとしても、記憶としては簡単に消え失せてしまう。ヒトの身では、あらゆる情報をその身に刻むことが難しい。ヒトの記憶領域は有限で、故に記録媒体が存在する。ヒトの身の中にすらだ。
DNAの使用されない領域に情報を入れ込もうという試みは、常に誤翻訳との戦いだ。故にまだ実用化には至らず、そしてこれからも恐らくはそうだろう。己は偶然にも外付けの力として記録する領域を得た、ただのヒトなのだ。
だから俺は忘れる。だから俺は覚えきれない。だけど俺には消えない記録媒体が外付けで存在し、それが人間と確かに袂を分かつ。
それを利用しない、という選択肢は、俺の中にはないのだ。
不出来だから手を伸ばすのではない。不出来だからこそ利用するのだ。それは、棚の上の物を取るために、踏み台を利用するくらい、自然なことだ。
それを思い出すのにだって、きっと時間がかかる。俺たちはそれくらい疲弊している。これを見て、何だそんなことだったのか、と呆気にとられるくらいには、きっと。

吉野暁海は、確かに火を見ていた。
その言葉も、その見たものも、全て己が知っていた。吉野暁海には参照する場所がない。恵まれた家庭で育ち、何の心配もすることなく進学し、守るべきものも背負わないま学んでいる。
それが確かに火の記憶を持って帰ってきて、咲良乃スズヒコは狼狽していた。
あの獣のような何かは、何をした?参照されないはずのものを映し出し、そして確かに干渉した。あの火の記憶は、吉野暁海のものではない。吉野暁海なんて人間はいないのだ。あれは間違いなく咲良乃スズヒコ、すなわち自分自身の記憶から参照され、そして引き出され、心的外傷として利用された。自分がそう思っている、自覚しているのだと言うことをたいへん忌々しく思った。いつまで経っても炎から逃れることが出来ない。
集団行動に支障のない範囲で、少し離れて歩くようになった。自分の能力があれば、多少離れたところであっても目も鼻も耳も利き、そこで何があったかくらいは察することが出来た。その方がほんの少しだけ気楽だった。獣は自分のところに寄ってくることもなく、時折思い出したように、視界を共有する。予定通りの歩みができていれば、それで全てが終わる。何を作って欲しいという話も、共有された聴覚で一瞬で伝わってくる。離れていても、というのが重要で、自分が時折木陰で蹲っても、引きずるほどの長い髪を結っている紐を解いて編み直しを始めても、それは彼らには伝わらない。あれは結局俺の一部だから、俺が伝えたくないものは伝えないのだ。
主従関係というには、歪で異質な関係だった。そもそも自分は、あのような獣を引き連れることはなく、あれは己の変身した姿だったはずだ。アンジニティに落ちて否定されてから、青かった手は少しずつ黒く染まった。さながら灰のようだった。もともとそれらしい爪なんて生えていなかったはずの前脚にそれが揃い、ラプトル系の前傾姿勢だった肉体は、前脚が発達するとともに四足歩行を主とするようになった。荒れ果てた地を踏み、そして荒れ果てた地に存在する生物を、罪人を、切り裂き、喰らい続けた。始めは確かに生き延びるためのことだったのをよく覚えていて、どんなに理屈をつけても、こんなことはしたくはない、こんなことをして生き延びるくらいなら、――そう思っていたはずだった。
人は慣れる。思っている以上に、ずっと早く。
“罪人”の首を刎ね、臓腑を喰らい、肉を裂いて骨を齧る。獣と何も変わらないようなことを始めるまで、そう時間は掛からなかった。そう記憶している。
『アンジニティの方々は暫くの間イバラシティの『仮の住人』となり、一時的に記憶・姿が『イバラシティに適応したもの』に置換されます。ひとまず与えられた記憶・姿に従ってイバラシティの住人として楽しんでください。』
何を勝手なことを言うのだろう、と初めは思っていた。
否定。侵略。全てが烏滸がましく、否定をしておいて利用しようというのか、と強く思った。何より一緒にされたくなかった。罪人たちが群れを成してどこかに向かっていく?
考えるだけで反吐が出る。ここには悪しかいないのだ。どうあれ結果に破滅しかない。それだけは嫌だった。それだけは絶対に嫌だった。自分を罪人どもと一緒にしないでほしかった。望みはただひとつで、そのためなら何でもしよう。何でもしなければならない。この爪もこの牙もこの体躯も、全てを賭けて、否定を否定しなければならない。
『イバラシティのために、ブチのめしちゃってください。』
気づいたら、そこは響奏の世界の陣営で、気づいたら、いつも通りにそこにフェデルタもいたのだ。否定を否定するためには、この機会を利用し尽くしてやるしかなかった。
全て。全てを。共に歩くひとも。手を組む人も。何もかもを。
こんなふざけた世界のためになんて、何一つしてやるものかと思う。
こんな世界に向かって奉仕をする必要があるなら、今すぐここで喉を掻き切って死ぬ。――死ぬことがなくても。
これは世界のためじゃない。自分のためだ。自分のため、前に進み続けなければならないのだ。わずか一時間、分にして六十分、秒にして三千六百秒で区切られ続け、そのたび押し潰すような幸せな記憶を押し付け、素知らぬ顔で幸せを享受する吉野暁海を殺すため、前に進まなければならないと、ここまでずっと思っていた。
火の記憶が参照されるまで、確かに。
自分は一体何のためにここまでの時間を過ごしてきたんだ?
従者と表面だけの付き合いを済ませ、その主人を料理で懐柔しようとし、――ずっと隣を歩いていたはずの、彼に。何もしていない。そこにいるのが当たり前だと思って。
全身が総毛立つような感覚があって、けれどすぐに消えていった。いつもそうだ。心配は必要ない。するだけ無駄だ。何故なら彼は“何も言わない”。
そして自分は“何も言いたくない”。失敗したくない。致命的な破滅への引き金を引きたくない。それはできれば他人のせいであってほしい。であれば、他人のせいにできるから。
――ああ、誰も味方だと思っていやしないのだ。全てがそこに収束し、血に濡れた手だけが語る。今の自分の味方であってほしくない。躊躇いなく喰い、殺し、引き裂く単なる獣の姿を、咲良乃スズヒコであると認めてほしくない。だから、だから、距離を置いて、突き放して、表面だけをなぞって。
そのままでいさせてほしかったのに。
「俺の言ってる事がお前にとって的外れならそれでいいよ。だけどよ、お前は何か考えたか?」
やめてほしい。その先の言葉を言うのはやめてほしかった。あなたはこれから俺の地雷を間違いなく踏むということすら言えない、ただ愚かに凍りついただけの怪物だ。
「――お得意の頭脳とやらはどうしたんだよ」
お前は知らない。頭脳の戦いを知らない。どれだけ俺がそれで苦しんだかも、知らない。
都合のいいところだけを拾う聴覚。解釈、そして防衛機制。それ以上続けるな、という衝動が、行動になってそのまま現れる。
知らない。知らない。知らないはずだ。知らないはずなのに、どうしてそんなことを言われなければならないのか。リジェクトされるたびの囁き声、査読にすら回してもらえない存在意義の欠如、――生前の怒りが燃え上がって貫通する。
「ねえ」
止められはしなかった。止めようともしなかった。



ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.15 焼き魚 を食べました!
体調が 1 回復!(16⇒17)
今回の全戦闘において 活力10 敏捷10 強靭10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







自然LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV15⇒25、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV50⇒55、-5CP)
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.14 パンの耳 から料理『サクサクパン耳ラスク(チョコ味)』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.7 お野菜 から料理『冷製ほうれん草ポタージュ』をつくりました!
ItemNo.17 ビーフ から料理『肉端のしぐれ煮』をつくりました!
⇒ 肉端のしぐれ煮/料理:強さ32/[効果1]活力5 [効果2]体力5 [効果3]防御5
E(1460) とカードを交換しました!
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー)
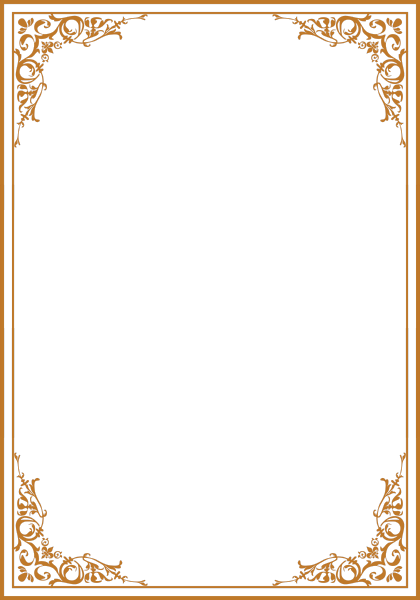
レーヴァテイン を研究しました!(深度0⇒1)
レーヴァテイン を研究しました!(深度1⇒2)
レーヴァテイン を研究しました!(深度2⇒3)
インヴァージョン を習得!
☆一望千里 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





ヒノデ区 J-11(道路)に移動!(体調17⇒16)
ヒノデ区 K-11(道路)に移動!(体調16⇒15)
ヒノデ区 L-11(道路)に移動!(体調15⇒14)
ヒノデ区 M-11(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
グノウ(909) からパーティに勧誘されました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 が発生!
- フェデルタ(165) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- スズヒコ(244) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- グノウ(909) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- 迦楼羅(931) が経由した ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》





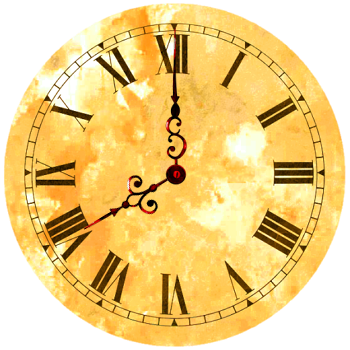
[787 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[347 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[301 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[75 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――
画面の情報が揺らぎ消えたかと思うと突然チャットが開かれ、
時計台の前にいるドライバーさんが映し出された。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「・・・こんにちは皆さん。ハザマでの暮らしは充実していますか?」 |
 |
ドライバーさん 「私も今回の試合には大変愉しませていただいております。 こうして様子を見に来るくらいに・・・ですね。ありがとうございます。」 |
 |
ドライバーさん 「さて、皆さんに今後についてお伝えすることがございまして。 あとで驚かれてもと思い、参りました。」 |
 |
ドライバーさん 「まず、影響力の低い方々に向けて。 影響力が低い状態が続きますと、皆さんの形状に徐々に変化が現れます。」 |
 |
ドライバーさん 「ナレハテ――最初に皆さんが戦った相手ですね。 多くは最終的にはあのように、または別の形に変化する者もいるでしょう。」 |
 |
ドライバーさん 「そして試合に関しまして。 ある条件を満たすことで、決闘を避ける手段が一斉に失われます。避けている皆さんは、ご注意を。」 |
 |
ドライバーさん 「手短に、用件だけで申し訳ありませんが。皆さんに幸あらんことを――」 |
チャットが閉じられる――







TeamNo.421
|
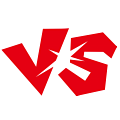 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|




ヒノデ区 M-11
チェックポイント《大通り》
チェックポイント。チェックポイント《大通り》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《OCTOPUS》
黒闇に包まれた巨大なタコのようなもの。
 |
守護者《OCTOPUS》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
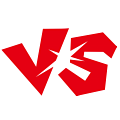 |
立ちはだかるもの
|

| 222 | 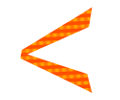 |
446 |
1st
迦楼羅


迦楼羅

2nd
フェデルタ


フェデルタ
3rd
グノウ


グノウ

4th
スズヒコ


スズヒコ
5th
守護者《OCTOPUS》


守護者《OCTOPUS》

6th
守護者《OCTOPUS》


守護者《OCTOPUS》

7th
守護者《OCTOPUS》


守護者《OCTOPUS》

8th
守護者《OCTOPUS》


守護者《OCTOPUS》


ENo.244
鈴のなる夢
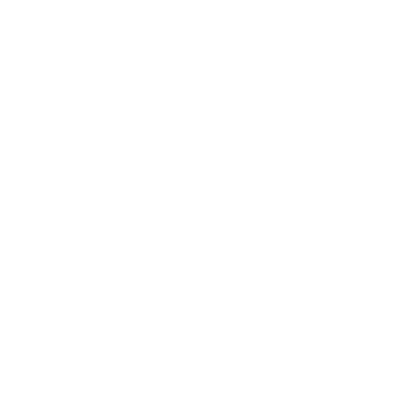
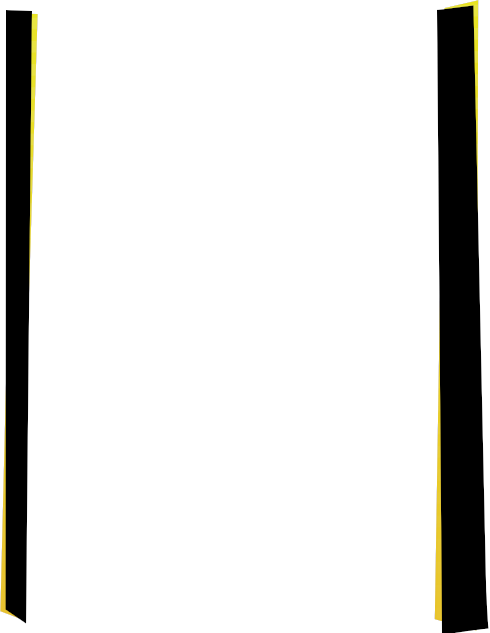
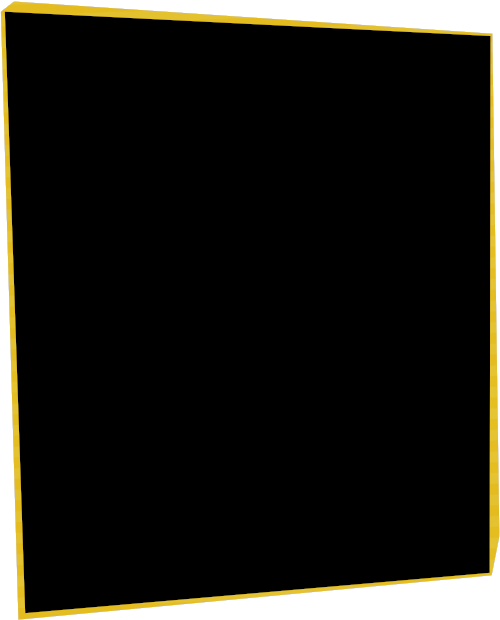
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
30 / 30
484 PS
チナミ区
D-2
D-2







痛撃友の会
4
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
3
アイコン60pxの会
3
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
6
長文大好きクラブ
1
自我とか意思とかある異能の交流会
3
カード報告会
10
とりあえず肉食う?
8



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 異本の栞 | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 山査子 | 素材 | 15 | [武器]防疫15(LV30)[防具]耐疫10(LV20)[装飾]快癒10(LV25) | |||
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | - | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 15 | 栄養ドリンク | 食材 | 20 | [効果1]活力10(LV10)[効果2]防御15(LV20)[効果3]鎮痛20(LV30) | |||
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | 肉端のしぐれ煮 | 料理 | 32 | 活力5 | 体力5 | 防御5 | |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 25 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 55 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| 練3 | ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 9 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| グレイシア | 5 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 練3 | 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練3 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
|
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]プチメテオカード | [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]マナポーション |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]レーヴァテイン |
| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]ブレイブハート |

PL / 紙箱みど