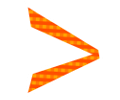<< 5:00~6:00





報せはいつだって突然で、そして予想外なものである。そうとは知っていても、大日向は足を進めざるを得なかった。
植物園の入場無料の報も確かに届いていたし、無料なら行ってみてもいいかな、と言っていた声はもまた、確かに聞いた。監督不行き届きと言えばそうだが、大学生に対してそこまでの責任を負う義務はない。早い話が自己責任だが、同時に好機も意味した。
未だ解明されていない、吉野暁海の異能に対して。未だわからないままでいるそれに傷をつけ、抉りこみ、引きずり出すための手段だ。
この“切り札”の存在は、大日向と、学生たちを取りまとめる長であるクレールしか知らない。
後手にドアを閉め、興奮を押さえきれない声で言った。
「パライバトルマリン!」
それは電気石。
それは切り札。
それは等価交換で手に入れた最終兵器。

「お呼ばれトルマリン!ようやくぼくの出番?だいぶ寝てるの飽きちゃったぜ」
道具店の店主が示してきた対価は“情報”で、それは大日向深知にとっては特に恐れるようなものではなかった。己の知見が対価になるというのなら、取りまとめて出してやってもいい。
それ――パライバトルマリンと呼ばれた生き物――は大日向たちの理解を超える存在で、そしてあまりにも強固に、“吉野暁海”とのコネクトがある。正確に言えば、吉野暁海の向こう側の存在にコネクトがある。
竜と呼ぶにはあまりに頼りなく、蛇と呼ぶには余計なものが付きすぎている。本来手がある場所からは毒々しい色の触手が生え、その足は未発達の胎児のような様態を留めている。その身体の一部ををユウレイボヤに似た被嚢が覆っており、――まあつまり、とにかく大日向たちの世界の範疇では到底ありえない生き物。それがこれだった。
「何、これでも想定よりは大分早い」
「マジ?じゃあぼくもちょっとはこの街満喫しようかな」
「一向に構わん。貴様に我々が求めていることはただひとつだ」
不格好な手足(と呼んでいいのかもわからない)が、寄り集まり、あるいは伸び、ゆっくりと人の形を取っていく。この世界に適応しつつあるのだ。
一メートルほどしかなかった生き物が、自分より背の高い青年になったのを見た大日向は、吐き捨てるように言った。
「なぜボクよりデカいんだ?頭が高いぞ」
「ハリカリさんにチクりますよ」
「この程度、チクられたところでなんとも思わん。何ならボクがこういうやつだと言うのは、アイツのほうがよく知っている」
薄い色の虹彩。
サングラスがいるな、と思いながら、キーボードを叩き指示を打つ。
「……で、ぼくは何をすれば?」
「来るときが来れば分かる……と言って放り出されるのも癪だろう。貴様には“先生”を探してもらう」
「……先生」
事前に手に入れていた情報から読み取れることがいくつかある。
この生き物は、かつて【鈴のなる夢】に飼われていたこと。この生き物そのものが越界能力を持ち、故に罠にはかかりやすいこと。戦闘能力はあの絶対中立主義者が素手で捕まえられる程度で、要はほぼないに等しいこと。触手には毒があるが、素手で捕まえられる時点で役に立っているかはまるで分からないこと。――そしてあの絶対中立主義者の店主を以てなお、『出自は謎』と言い切らせる生き物だということ。
「もう分かるな。お前の言う先生が誰か、というのは」
「……うん、分かる。分かるよ。けど、先生はもうあれで最後だと言った……と、思ってた」
鮮やかな髪の色を見、少しばかり染髪を勧めるか迷ったが、やめた。
この世界では、髪の色などほぼ無意味な記号である。もちろん個人特定にプラスに働く場合はあろうが、前情報の通りであれば、パライバトルマリンは変化し続ける。
「パライバトルマリン。ボクはお前を運用するに当たって、黎明の世界樹エーオシャフトの情報を可能な限り聞き出せ、と言われている。それはお前が解放されるのと同条件なはずだ」
普段自力で戦うことがほとんどない“あの”絶対中立主義者が素手で捕まえられるほど、この生き物はか弱い。しかしこうして生き延びているのだから、これは間違いなく“本物”だ。
とある世界で、世界全ての軸となる大いなる世界樹。一葉一葉が世界であり、その性質から、別の世界に“滑り落ちる”人間の多い世界。その滑り落ちたものに手を差し伸べたり差し伸べなかったりする神の御使い、あるいは天使。ありとあらゆる世界の因果に強力に働きかけ、どれだけ木っ端微塵になろうと、与えられた任務を遂行する御使い、その紛い物のような生き物が、今目の前にいる、何とも形容できない生き物だ。
「……なんだよ、ちゃっかりしてんなあの道具屋……」
「あいにくボクも“無知ではいられない”性質でな」
「先生みたいなタイプを期待したけど、そうじゃなさそうで残念だ」
伏せた虹彩の色が、見る間に青く変わっていく。
パライバは容れ物だ。ありとあらゆる力を注がれ、それを蓄積し、時には変化させて放出する。何を目的として彼が産み出されたのかまでは、過去に遡ることを嫌う絶対中立主義者の知るところではなかった。けれどおおよそ、軍事利用か破壊行為のためだろう。それくらいの想像はできた。あらゆることが、ヒトに対して都合が良すぎるのだ。
飼い主と認められた者の言葉には決して逆らえない。過剰な力を加えると爆発にも似た強烈な破壊現象を引き起こす。多くの種類の毒素を生産する部位があり、それは基本的に触手に蓄積される。手も脚も不自由だが、浮遊して移動ができる。
こんな都合のいい生き物は、よほどでなければ作られない。自然界の生物は生きるための本能があり、それに従って動くことができるが、パライバにはそれがない。故に、今は捕まえた男を主として行動する。それを自由に動かす権利を買い取ったのが、大日向だ。
「先生とやら、研究者に向いていなかったんじゃないか?ボクらは知識に貪欲だ。無知は機会だ。そしてあいつも、お前のことを知りたがっている。実にWin-Winな関係だろうよ」
「そこにぼくが全然入ってないじゃんかよ」
「なに、お前ももう分かっているだろう。人型で過ごすお前というだけで、そこに価値が生まれる」
指を細かに動かしている手に向かって、一枚のカードが差し出された。
いつの間に撮ったのか、正面からの写真と、知らぬ名前、そして2020から始まる番号の印字されたカード。創峰大学、という文字を読み取るより早く、手渡してきた本人が口を開く。
「これはお前の学生証だ。第二学群生物学科の三年次として、高専から編入してきたことになっている」
「……それで、ぼくに何を?」
「吉野暁海と接触しろ。それは、咲良乃スズヒコの写しだ」
ライバ・カイネウスと印字されているそれを眺めていた視線が明確に、こちらを向いた。
道具店の店主の言を信じるのなら、前飼い主。それをこちら側に何としてでも引き込むための布石として、決して安くはない買い物をした。とはいえ、実質的な学長の立場にいる以上、いくらでもやりようはあった。
「……先生と」
「然り。接触しろ。そして、かの狭間に記憶を刻め」
「……何言ってるかさっぱりわかんないけど、まあ分かった」
パライバトルマリンは、よくも悪くも邪魔をされない。
黎明の世界樹の神の御使いは強力な認識阻害能力を持っており、本来であれば対面どころか目視、気配の察知、その類のことを一切許さない。なりそこない、あるいは紛い物であるパライバには、世界の因果に邪魔されない、ということだけが残っている。
つまりこの生き物は、侵略の時間に事も無げに邪魔をして、そして干渉されることなく帰還する。理論上は。
帰還まで果たせれば御の字だ。目的は、パライバトルマリンの存在と、その後ろの存在を知らしめることにある。親しい存在を味方につけている人間に、“自殺を選んだ人間が靡かない可能性を考慮していない”。そもそも、考慮する必要がないのだ。必要なことは、コンタクトを取ることのみである。
「知識面はこれからサポートする。お前、注げば注ぐだけそれらしくなるんだろう。あいつが言っていた」
「らしいね。けどあんた、随分優しいな。ハリカリさんなんかさっぱりだよ」
「我々からすれば、お前は高い買い物でもあるが、同時に客人でもある。あのクソ道具店と一緒にされちゃあ困る」
ふと、何もない方向にパライバが振り返った。
きれいに一本線が引かれた空間を、押し開けるようにして男が一人、顔を出す。その向こう側は、どこかの店の中につながっていた。

「話聞いてたけど、クソ道具店呼ばわりはひどくない?大分頑張ってるんですよ、自分」
「お前の手は常に逃げだ。識ろうという意思はないのか?絶対中立主義者〈ユッカ・ハリカリ〉」
「うーん、もうだいたい識ってるし、あんまり」
「……マジでどこにでも出てくるんだな……この人」
それは興味があるようにも見えたし、ないようにも見えた。ユッカ・ハリカリと呼ばれた男は、そのまま空間の縁を肘置きのように使い始める。
空間の向こうから、ひっきりなしに紙を破る音が聞こえていた。パライバだけがその音を気にしていた。
「つい顔出しちゃったからサービスをしておこう。次の一時間より早く、吉野暁海に接触したほうがスムーズだ。これはもう、未来をチラ見したから確定だよ」
「過去は触れないのに未来は積極的に見るんだな、お前」
「未来予知、便利だからねー。例えば攻撃の回避とかさ。自分は戦いたくないから」
道具屋。あるいは絶対中立主義者。ありとあらゆる世界の交差点に居を構え、隠れ住みながら様々なものを売り捌き、手に入れる。しょうもない情報から人の命まで、望みのものはほとんどがある。あるいは、仕入れてくる。そこにどんな犠牲が伴おうとも。
彼の特性を理解している人間ほど、彼に対して慎重だ。それは大日向も例外ではない。自分の身に不相応でなく、そして達成できるものだけを買うのだ。それができないものは、こいつにもれなくいいようにされて殺される。
「過去の参照も時には糧となる。いいか、」
「うん、その話めちゃくちゃ聞いたから大丈夫。僕が過去を参照しに行かないのは干渉と編纂が怖いだけだよ」
「素直じゃないやつだな。本当にさっきのはサービスなんだろうな?」
故に厳密に問わねばならない。後で難癖をつけられたとき、困るのはこちら側だからだ。
さもなくば今から攻撃をする、という意思表示を見せながら、大日向は詰め寄る。
「ほんとにサービスだって。【哀歌の行進】は一度ちゃんと分からせておきたいからね、自分としても。悪意は等しくお返しすることにしてるんだ」
ウインクひとつ。
大日向がラボにあったティッシュの箱を掴んで投げようと振りかぶったところで、ハリカリは空間をさっと閉じてしまった。もう、そこに誰かがいたような形跡はない。はじめから何もなかったかのように。
「チッ。ボクの出血大サービスは受け取ってもらえんか」
「……そりゃ、物理が分かってたらしないんじゃないですか……?」
「ド正論だ」
早速だがお前を“大学生”にする、と言った瞬間、待ってましたと言わんばかりにドアが開く。そこに待っていたのは、大日向研の院生たちだった。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.426 アストロイェライ とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.14 海鮮丼 を食べました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 活力10 敏捷10 強靭10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












フェデルタ(165) から 柳 を受け取りました。
フェデルタ(165) から 毛 を受け取りました。
ニアク(784) に ItemNo.9 不思議な石 を送付しました。
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
メリーナ(646) により ItemNo.2 柳 から装飾『サレクススピン』を作製してもらいました!
⇒ サレクススピン/装飾:強さ120/[効果1]風柳15 [効果2]- [効果3]-
メリーナ(646) の持つ ItemNo.11 たけのこ から料理『たけのこサンド』をつくりました!
メリーナ(646) の持つ ItemNo.16 お魚 から料理『フィッシュサンド』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.14 たけのこ から料理『筍の炊き込みご飯』をつくりました!
歩行爆弾(1294) とカードを交換しました!
大爆発 (イグニス)
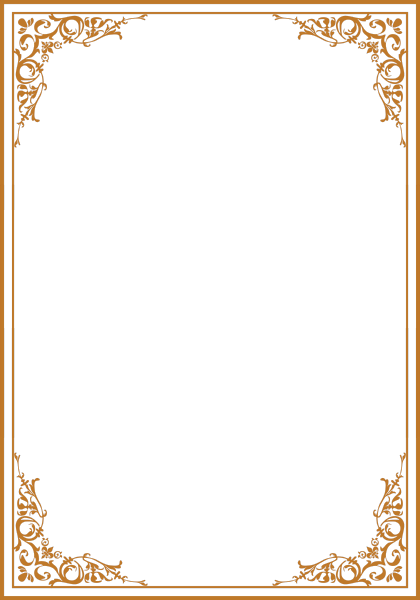
ブレイブハート を研究しました!(深度0⇒1)
ブレイブハート を研究しました!(深度1⇒2)
ブレイブハート を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
リフレッシュ を習得!
環境変調耐性 を習得!
ノーマライズ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ラベンダー を入手!
スズヒコ(244) は 山査子 を入手!
グノウ(909) は 大蒜 を入手!
迦楼羅(931) は 大蒜 を入手!
グノウ(909) は 爪 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は 何か柔らかい物体 を入手!
迦楼羅(931) は パンの耳 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに こぐま がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ローリングタイヤ がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに バニーガール がゆっくりと近づいてきます。



フェデルタ(165) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
ヒノデ区 E-11(草原)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 F-11(草原)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 G-11(草原)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 H-11(道路)に移動!(体調18⇒17)
ヒノデ区 I-11(道路)に移動!(体調17⇒16)





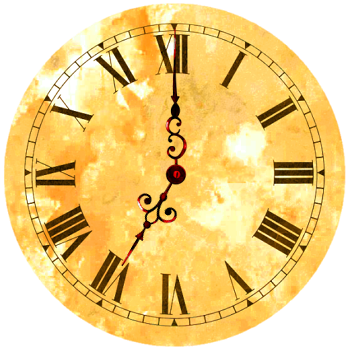
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映し出されるふたり。
チャットから消えるふたり。
チャットが閉じられる――







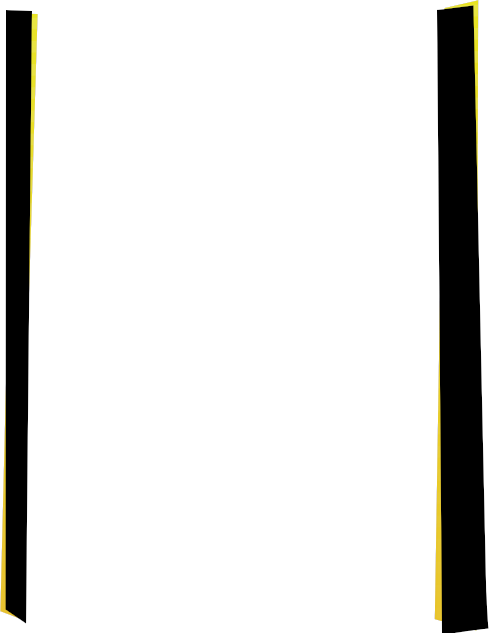
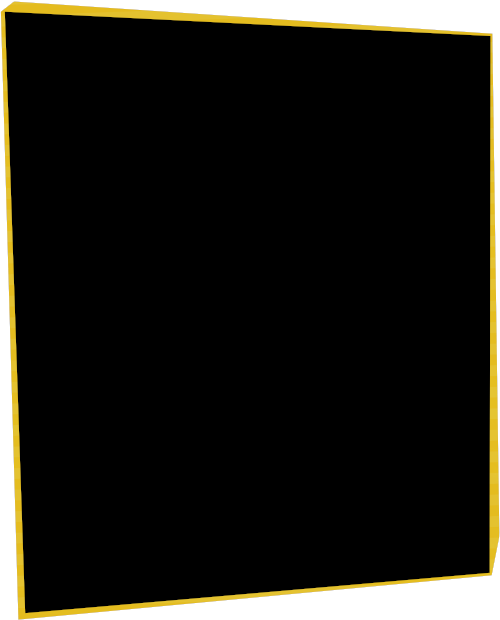





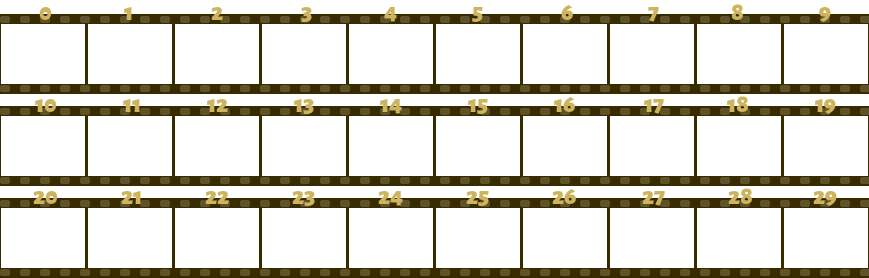









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




報せはいつだって突然で、そして予想外なものである。そうとは知っていても、大日向は足を進めざるを得なかった。
植物園の入場無料の報も確かに届いていたし、無料なら行ってみてもいいかな、と言っていた声はもまた、確かに聞いた。監督不行き届きと言えばそうだが、大学生に対してそこまでの責任を負う義務はない。早い話が自己責任だが、同時に好機も意味した。
未だ解明されていない、吉野暁海の異能に対して。未だわからないままでいるそれに傷をつけ、抉りこみ、引きずり出すための手段だ。
この“切り札”の存在は、大日向と、学生たちを取りまとめる長であるクレールしか知らない。
後手にドアを閉め、興奮を押さえきれない声で言った。
「パライバトルマリン!」
それは電気石。
それは切り札。
それは等価交換で手に入れた最終兵器。

「お呼ばれトルマリン!ようやくぼくの出番?だいぶ寝てるの飽きちゃったぜ」
道具店の店主が示してきた対価は“情報”で、それは大日向深知にとっては特に恐れるようなものではなかった。己の知見が対価になるというのなら、取りまとめて出してやってもいい。
それ――パライバトルマリンと呼ばれた生き物――は大日向たちの理解を超える存在で、そしてあまりにも強固に、“吉野暁海”とのコネクトがある。正確に言えば、吉野暁海の向こう側の存在にコネクトがある。
竜と呼ぶにはあまりに頼りなく、蛇と呼ぶには余計なものが付きすぎている。本来手がある場所からは毒々しい色の触手が生え、その足は未発達の胎児のような様態を留めている。その身体の一部ををユウレイボヤに似た被嚢が覆っており、――まあつまり、とにかく大日向たちの世界の範疇では到底ありえない生き物。それがこれだった。
「何、これでも想定よりは大分早い」
「マジ?じゃあぼくもちょっとはこの街満喫しようかな」
「一向に構わん。貴様に我々が求めていることはただひとつだ」
不格好な手足(と呼んでいいのかもわからない)が、寄り集まり、あるいは伸び、ゆっくりと人の形を取っていく。この世界に適応しつつあるのだ。
一メートルほどしかなかった生き物が、自分より背の高い青年になったのを見た大日向は、吐き捨てるように言った。
「なぜボクよりデカいんだ?頭が高いぞ」
「ハリカリさんにチクりますよ」
「この程度、チクられたところでなんとも思わん。何ならボクがこういうやつだと言うのは、アイツのほうがよく知っている」
薄い色の虹彩。
サングラスがいるな、と思いながら、キーボードを叩き指示を打つ。
「……で、ぼくは何をすれば?」
「来るときが来れば分かる……と言って放り出されるのも癪だろう。貴様には“先生”を探してもらう」
「……先生」
事前に手に入れていた情報から読み取れることがいくつかある。
この生き物は、かつて【鈴のなる夢】に飼われていたこと。この生き物そのものが越界能力を持ち、故に罠にはかかりやすいこと。戦闘能力はあの絶対中立主義者が素手で捕まえられる程度で、要はほぼないに等しいこと。触手には毒があるが、素手で捕まえられる時点で役に立っているかはまるで分からないこと。――そしてあの絶対中立主義者の店主を以てなお、『出自は謎』と言い切らせる生き物だということ。
「もう分かるな。お前の言う先生が誰か、というのは」
「……うん、分かる。分かるよ。けど、先生はもうあれで最後だと言った……と、思ってた」
鮮やかな髪の色を見、少しばかり染髪を勧めるか迷ったが、やめた。
この世界では、髪の色などほぼ無意味な記号である。もちろん個人特定にプラスに働く場合はあろうが、前情報の通りであれば、パライバトルマリンは変化し続ける。
「パライバトルマリン。ボクはお前を運用するに当たって、黎明の世界樹エーオシャフトの情報を可能な限り聞き出せ、と言われている。それはお前が解放されるのと同条件なはずだ」
普段自力で戦うことがほとんどない“あの”絶対中立主義者が素手で捕まえられるほど、この生き物はか弱い。しかしこうして生き延びているのだから、これは間違いなく“本物”だ。
とある世界で、世界全ての軸となる大いなる世界樹。一葉一葉が世界であり、その性質から、別の世界に“滑り落ちる”人間の多い世界。その滑り落ちたものに手を差し伸べたり差し伸べなかったりする神の御使い、あるいは天使。ありとあらゆる世界の因果に強力に働きかけ、どれだけ木っ端微塵になろうと、与えられた任務を遂行する御使い、その紛い物のような生き物が、今目の前にいる、何とも形容できない生き物だ。
「……なんだよ、ちゃっかりしてんなあの道具屋……」
「あいにくボクも“無知ではいられない”性質でな」
「先生みたいなタイプを期待したけど、そうじゃなさそうで残念だ」
伏せた虹彩の色が、見る間に青く変わっていく。
パライバは容れ物だ。ありとあらゆる力を注がれ、それを蓄積し、時には変化させて放出する。何を目的として彼が産み出されたのかまでは、過去に遡ることを嫌う絶対中立主義者の知るところではなかった。けれどおおよそ、軍事利用か破壊行為のためだろう。それくらいの想像はできた。あらゆることが、ヒトに対して都合が良すぎるのだ。
飼い主と認められた者の言葉には決して逆らえない。過剰な力を加えると爆発にも似た強烈な破壊現象を引き起こす。多くの種類の毒素を生産する部位があり、それは基本的に触手に蓄積される。手も脚も不自由だが、浮遊して移動ができる。
こんな都合のいい生き物は、よほどでなければ作られない。自然界の生物は生きるための本能があり、それに従って動くことができるが、パライバにはそれがない。故に、今は捕まえた男を主として行動する。それを自由に動かす権利を買い取ったのが、大日向だ。
「先生とやら、研究者に向いていなかったんじゃないか?ボクらは知識に貪欲だ。無知は機会だ。そしてあいつも、お前のことを知りたがっている。実にWin-Winな関係だろうよ」
「そこにぼくが全然入ってないじゃんかよ」
「なに、お前ももう分かっているだろう。人型で過ごすお前というだけで、そこに価値が生まれる」
指を細かに動かしている手に向かって、一枚のカードが差し出された。
いつの間に撮ったのか、正面からの写真と、知らぬ名前、そして2020から始まる番号の印字されたカード。創峰大学、という文字を読み取るより早く、手渡してきた本人が口を開く。
「これはお前の学生証だ。第二学群生物学科の三年次として、高専から編入してきたことになっている」
「……それで、ぼくに何を?」
「吉野暁海と接触しろ。それは、咲良乃スズヒコの写しだ」
ライバ・カイネウスと印字されているそれを眺めていた視線が明確に、こちらを向いた。
道具店の店主の言を信じるのなら、前飼い主。それをこちら側に何としてでも引き込むための布石として、決して安くはない買い物をした。とはいえ、実質的な学長の立場にいる以上、いくらでもやりようはあった。
「……先生と」
「然り。接触しろ。そして、かの狭間に記憶を刻め」
「……何言ってるかさっぱりわかんないけど、まあ分かった」
パライバトルマリンは、よくも悪くも邪魔をされない。
黎明の世界樹の神の御使いは強力な認識阻害能力を持っており、本来であれば対面どころか目視、気配の察知、その類のことを一切許さない。なりそこない、あるいは紛い物であるパライバには、世界の因果に邪魔されない、ということだけが残っている。
つまりこの生き物は、侵略の時間に事も無げに邪魔をして、そして干渉されることなく帰還する。理論上は。
帰還まで果たせれば御の字だ。目的は、パライバトルマリンの存在と、その後ろの存在を知らしめることにある。親しい存在を味方につけている人間に、“自殺を選んだ人間が靡かない可能性を考慮していない”。そもそも、考慮する必要がないのだ。必要なことは、コンタクトを取ることのみである。
「知識面はこれからサポートする。お前、注げば注ぐだけそれらしくなるんだろう。あいつが言っていた」
「らしいね。けどあんた、随分優しいな。ハリカリさんなんかさっぱりだよ」
「我々からすれば、お前は高い買い物でもあるが、同時に客人でもある。あのクソ道具店と一緒にされちゃあ困る」
ふと、何もない方向にパライバが振り返った。
きれいに一本線が引かれた空間を、押し開けるようにして男が一人、顔を出す。その向こう側は、どこかの店の中につながっていた。

「話聞いてたけど、クソ道具店呼ばわりはひどくない?大分頑張ってるんですよ、自分」
「お前の手は常に逃げだ。識ろうという意思はないのか?絶対中立主義者〈ユッカ・ハリカリ〉」
「うーん、もうだいたい識ってるし、あんまり」
「……マジでどこにでも出てくるんだな……この人」
それは興味があるようにも見えたし、ないようにも見えた。ユッカ・ハリカリと呼ばれた男は、そのまま空間の縁を肘置きのように使い始める。
空間の向こうから、ひっきりなしに紙を破る音が聞こえていた。パライバだけがその音を気にしていた。
「つい顔出しちゃったからサービスをしておこう。次の一時間より早く、吉野暁海に接触したほうがスムーズだ。これはもう、未来をチラ見したから確定だよ」
「過去は触れないのに未来は積極的に見るんだな、お前」
「未来予知、便利だからねー。例えば攻撃の回避とかさ。自分は戦いたくないから」
道具屋。あるいは絶対中立主義者。ありとあらゆる世界の交差点に居を構え、隠れ住みながら様々なものを売り捌き、手に入れる。しょうもない情報から人の命まで、望みのものはほとんどがある。あるいは、仕入れてくる。そこにどんな犠牲が伴おうとも。
彼の特性を理解している人間ほど、彼に対して慎重だ。それは大日向も例外ではない。自分の身に不相応でなく、そして達成できるものだけを買うのだ。それができないものは、こいつにもれなくいいようにされて殺される。
「過去の参照も時には糧となる。いいか、」
「うん、その話めちゃくちゃ聞いたから大丈夫。僕が過去を参照しに行かないのは干渉と編纂が怖いだけだよ」
「素直じゃないやつだな。本当にさっきのはサービスなんだろうな?」
故に厳密に問わねばならない。後で難癖をつけられたとき、困るのはこちら側だからだ。
さもなくば今から攻撃をする、という意思表示を見せながら、大日向は詰め寄る。
「ほんとにサービスだって。【哀歌の行進】は一度ちゃんと分からせておきたいからね、自分としても。悪意は等しくお返しすることにしてるんだ」
ウインクひとつ。
大日向がラボにあったティッシュの箱を掴んで投げようと振りかぶったところで、ハリカリは空間をさっと閉じてしまった。もう、そこに誰かがいたような形跡はない。はじめから何もなかったかのように。
「チッ。ボクの出血大サービスは受け取ってもらえんか」
「……そりゃ、物理が分かってたらしないんじゃないですか……?」
「ド正論だ」
早速だがお前を“大学生”にする、と言った瞬間、待ってましたと言わんばかりにドアが開く。そこに待っていたのは、大日向研の院生たちだった。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.426 アストロイェライ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| フェデルタ 「なあおい、なあ、バニーガールいるぞ。おい。すげえな。みろよあのデカいの。」 |
ItemNo.14 海鮮丼 を食べました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 活力10 敏捷10 強靭10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





正運極心
|
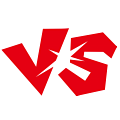 |
鈴のなる夢
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 4 増加!
影響力が 4 増加!



フェデルタ(165) から 柳 を受け取りました。
フェデルタ(165) から 毛 を受け取りました。
| フェデルタ 「……」 |
ニアク(784) に ItemNo.9 不思議な石 を送付しました。
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
メリーナ(646) により ItemNo.2 柳 から装飾『サレクススピン』を作製してもらいました!
⇒ サレクススピン/装飾:強さ120/[効果1]風柳15 [効果2]- [効果3]-
 |
メリーナ 「取引ありがとう。そちらの依頼の品も持ってきたよ。 こんな感じで大丈夫?」 |
メリーナ(646) の持つ ItemNo.11 たけのこ から料理『たけのこサンド』をつくりました!
メリーナ(646) の持つ ItemNo.16 お魚 から料理『フィッシュサンド』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.14 たけのこ から料理『筍の炊き込みご飯』をつくりました!
歩行爆弾(1294) とカードを交換しました!
大爆発 (イグニス)
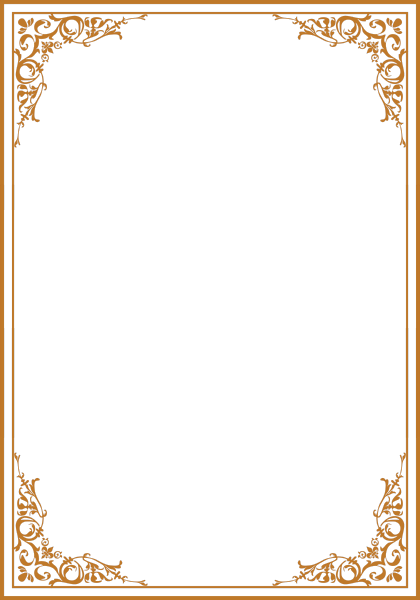
ブレイブハート を研究しました!(深度0⇒1)
ブレイブハート を研究しました!(深度1⇒2)
ブレイブハート を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
リフレッシュ を習得!
環境変調耐性 を習得!
ノーマライズ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ラベンダー を入手!
スズヒコ(244) は 山査子 を入手!
グノウ(909) は 大蒜 を入手!
迦楼羅(931) は 大蒜 を入手!
グノウ(909) は 爪 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は 何か柔らかい物体 を入手!
迦楼羅(931) は パンの耳 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに こぐま がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ローリングタイヤ がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに バニーガール がゆっくりと近づいてきます。



フェデルタ(165) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
ヒノデ区 E-11(草原)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 F-11(草原)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 G-11(草原)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 H-11(道路)に移動!(体調18⇒17)
ヒノデ区 I-11(道路)に移動!(体調17⇒16)





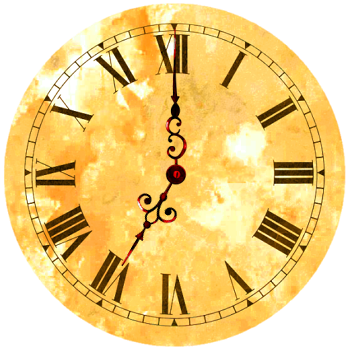
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「うんうん、順調じゃねーっすか。 あとやっぱうるせーのは居ねぇほうが断然いいっすね。」 |
 |
白南海 「いいから早くこれ終わって若に会いたいっすねぇまったく。 もう世界がどうなろうと一緒に歩んでいきやしょうワカァァ――」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カグハ 「・・・わ、変なひとだ。」 |
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
白南海 「――ん、んんッ・・・・・ ・・・なんすか。 お前らは・・・あぁ、梅楽園の団子むすめっこか。」 |
 |
カオリ 「チャットにいたからお邪魔してみようかなって!ごあいさつ!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
 |
白南海 「勝手に人の部屋に入るもんじゃねぇぞ、ガキンチョ。」 |
 |
カオリ 「勝手って、みんなに発信してるじゃんこのチャット。」 |
 |
カグハ 「・・・寂しがりや?」 |
 |
白南海 「・・・そ、操作ミスってたのか。クソ。・・・クソ。」 |
 |
白南海 「そういや、お前らは・・・・・ロストじゃねぇんよなぁ?」 |
 |
カグハ 「違うよー。」 |
 |
カオリ 「私はイバラシティ生まれのイバラシティ育ち!」 |
 |
白南海 「・・・・・は?なんだこっち側かよ。 だったらアンジニティ側に団子渡すなっての。イバラシティがどうなってもいいのか?」 |
 |
カオリ 「あ、・・・・・んー、・・・それがそれが。カグハちゃんは、アンジニティ側なの。」 |
 |
カグハ 「・・・・・」 |
 |
白南海 「なんだそりゃ。ガキのくせに、破滅願望でもあんのか?」 |
 |
カグハ 「・・・・・その・・・」 |
 |
カオリ 「うーあーやめやめ!帰ろうカグハちゃん!!」 |
 |
カオリ 「とにかく私たちは能力を使ってお団子を作ることにしたの! ロストのことは偶然そうなっただけだしっ!!」 |
 |
カグハ 「・・・カオリちゃん、やっぱり私――」 |
 |
カオリ 「そ、それじゃーね!バイビーン!!」 |
チャットから消えるふたり。
 |
白南海 「・・・・・ま、別にいいんすけどね。事情はそれぞれ、あるわな。」 |
 |
白南海 「でも何も、あんな子供を巻き込むことぁねぇだろ。なぁ主催者さんよ・・・」 |
チャットが閉じられる――





ENo.244
鈴のなる夢

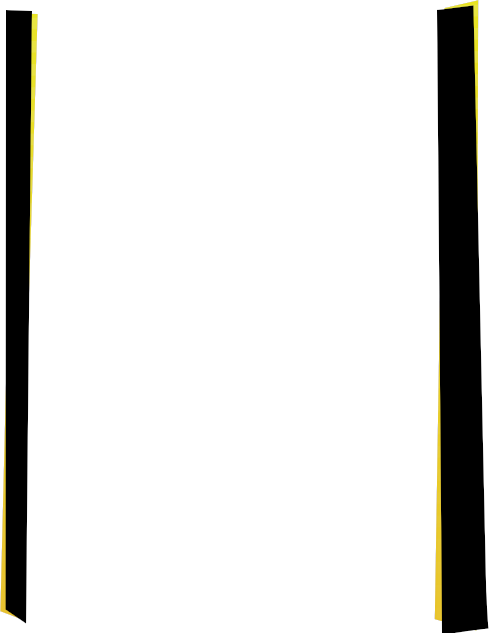
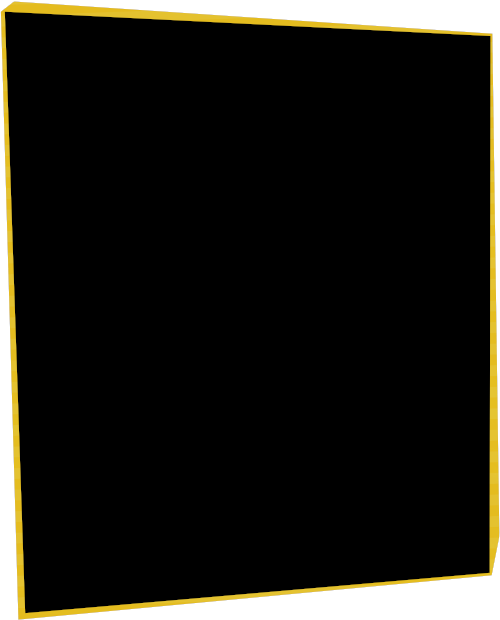
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
16 / 30
392 PS
ヒノデ区
I-11
I-11








痛撃友の会
2
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
3
アイコン60pxの会
3
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
7
長文大好きクラブ
1
自我とか意思とかある異能の交流会
3
カード報告会
7
とりあえず肉食う?
9



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 異本の栞 | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 山査子 | 素材 | 15 | [武器]防疫15(LV30)[防具]耐疫10(LV20)[装飾]快癒10(LV25) | |||
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | - | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 15 | 焼き魚 | 料理 | 55 | 活力10 | 敏捷10 | 強靭10 | |
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 50 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| 練3 | ブレイブハート | 8 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| 練3 | クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| グレイシア | 5 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 | |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]プロテクション |
| [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]ブレイブハート |

PL / 紙箱みど