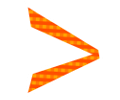<< 5:00~6:00




掌を見る。
イノカク部の選抜戦あたりから、明らかに異能を扱うという事がわかってきた気がする。自分の思いを強く持てば、異能もそれに応えてくれる。
その言葉を聞いてから、自分はまだこの力とちゃんと向き合ってない気がしたから、恥ずかしいと思っていたその名前を呼ぶようになった。
戦う時には、力を貸して欲しいと思うようになった。
そうしたら、力は、本当に応えてくれた気がした。
炎が生きているかのように、手に馴染む。
これならきっと、もう、誰かを傷つけることはない。
あの、植物園で見た景色は単なる夢なのだ。
『俺は、もっと、強くなる』
―――
――
―
一時間に一度を繰り返す事、六回目。どんな事でも回数をこなせば慣れてくるものだ、なんてどうでもいい感想を持ちながらフェデルタは細く息を吐いた。最初は、吉野俊彦と自分を頻繁に混同していた。その次は、自分が吉野俊彦ではない事にひどく申し訳なさを感じた。
(今は……)
大丈夫だ。本を開く程でもなく、自分は吉野俊彦ではない事と、そして彼で無い事に対する罪悪感は無い。そして、どうやら自分が彼の中で全く消えていないだろうことを感じた。"炎命の士"と名付けられた異能。そもそも、炎を操る力だと吉野俊彦は思わされているのだろう。その炎が自分自身などと、気付くはずも無い。異能という枠に収めて、名前を付けて閉じ込めているのだ。
けれども、彼がその異能に向き合い、力を求めれば自らの力なのだから応えるのは当然だ。
(……もしかしたら、辿り着くのかもな)
強さを、力をまっすぐに求める彼の周りには支え剥げます友や、暖かい家族がいる。それは、フェデルタには全く無かったものだ。だからこそ、彼がこの先をどう進むのかは予想出来ない。
フェデルタには、吉野俊彦の記憶が流れる度に、ぼんやりと感じていたことがある。それは、回数を重ねるごとにどんどんとはっきりした感情としての形を作り上げてきた。
そして、今完全にそれを理解した。
吉野俊彦という存在は、答え合わせなのだ。
今までの、生きていた頃か死んだ先まで、フェデルタ・アートルムが進んできた道への答え合わせ。
正解を積み重ねた吉野俊彦はどんどんと成長していく。
記憶が流れてくる度に前に進んでいく姿に、フェデルタはとっくの昔に置いていかれていた
「……くそ」
唐突に、軽く頭を横に振ってフェデルタは悪態吐く。ふと浮かび上がった植物園の記憶。フェデルタの中にこびりついている炎の記憶が、ご丁寧に吉野俊彦の家族に置き換わり再現されていた。怪しげな霧に見せられた、絶望の幻。
恐らく一緒にいた兄――スズヒコも、嫌なものを見せられたのだろう。冷たく睨み付けるあの瞳はまさに今、スズヒコが自分によく見せてくるものだった。
そして、それでもなお兄を求める吉野俊彦もまた、自分と大いに重なっている。情けなく独りよがりで利己的で相手の事など考えていない、自分ばかりの思考。
それは、普段の吉野俊彦からは考えられないものだった。
「……」
本を取り出し、何かを書こうとしたが頭の中がぐちゃぐちゃでまとめるための言葉も出てこなかった。
チェックポイントまで、特に遮る物もない平坦な道。相変わらず、同行者達との距離広い。敵と対応する時だけの関係だ。
それは、迦楼羅とグノウの主従とだけでなく、スズヒコとも。
(俺は、何をすれば、いいんだろう)
スズヒコに責め立てられてから、ずっとそんな考えばかりがぐるぐると頭を駆け巡り大した答えも無いまま消えていく。
(……あいつは)
吉野俊彦は、どうしてただろうか。
彼は、ずっと強いと思っていた友人の弱さを見付けた時、それを受け入れ、寄り添うことをした。
(俺は、)
スズヒコが強いと信じこんで、彼の弱さを知ろうともしなかった。弱い彼を違うと否定していた。勝手に自分の理想を押し付けていた。
「……」
本当は、あの人にだって弱さがあって、今彼をそうさせているのは強さ故ではなく、弱さ故なのではないのだろうか。
イバラシティでの仮初の人格がなければ、こんな答えにはたどり着けなかっただろう。
フェデルタは、掌をじっと見つめ。代わり映えのない自分の掌の先にいる、イバラシティの自分を見る。
吉野俊彦という存在は、答え合わせなのだ。
答えがあるなら、利用するまでだ。ずるい大人は、もう形振りなんて構っていられない。
(……いや)
彼の言葉を使うなら、その答えを借りる、という事になるのかもしれない。
ずるくて弱い大人は、到底、一人では立ち上がれないから。



ENo.244 スズヒコ とのやりとり

ENo.261 暮泥 唯 とのやりとり

ENo.360 瑞稀 とのやりとり

ENo.452 魄角 とのやりとり

ENo.912 愛夢 とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1039 オーディオル とのやりとり

以下の相手に送信しました




グノウ(909) に ItemNo.8 針 を手渡ししました。
ItemNo.10 お野菜 を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。












スズヒコ(244) に ItemNo.2 柳 を送付しました。
スズヒコ(244) に ItemNo.15 毛 を送付しました。
制約LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ItemNo.14 牙 から射程1の武器『ネックナイフ』を作製しました!
⇒ ネックナイフ/武器:強さ90/[効果1]追撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
モドラ(730) により ItemNo.12 皮 から防具『丈夫なコート』を作製してもらいました!
⇒ 丈夫なコート/防具:強さ90/[効果1]反護15 [効果2]- [効果3]-
グノウ(909) により ItemNo.14 ネックナイフ に ItemNo.1 駄物 を付加してもらいました!
⇒ ネックナイフ/武器:強さ90/[効果1]追撃10 [効果2]攻撃10 [効果3]-【射程1】
七夏(12) とカードを交換しました!
ディスカード・セブン (エファヴェセント)
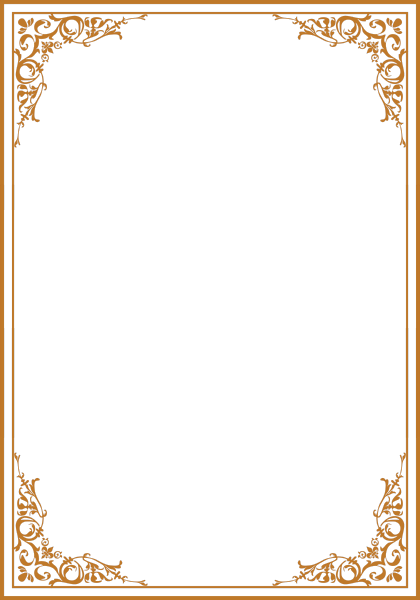
クリエイト:バトルフラッグ を研究しました!(深度2⇒3)
アラベスク を研究しました!(深度1⇒2)
アラベスク を研究しました!(深度2⇒3)
キャプチャートラップ を習得!
ブロック を習得!
フェイタルポイント を習得!
コンセントレイト を習得!
ジャックポット を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ラベンダー を入手!
スズヒコ(244) は 山査子 を入手!
グノウ(909) は 大蒜 を入手!
迦楼羅(931) は 大蒜 を入手!
グノウ(909) は 爪 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は 何か柔らかい物体 を入手!
迦楼羅(931) は パンの耳 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに こぐま がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ローリングタイヤ がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに バニーガール がゆっくりと近づいてきます。



現在のパーティから離脱しました!
ヒノデ区 E-11(草原)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 F-11(草原)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 G-11(草原)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 H-11(道路)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 I-11(道路)に移動!(体調18⇒17)





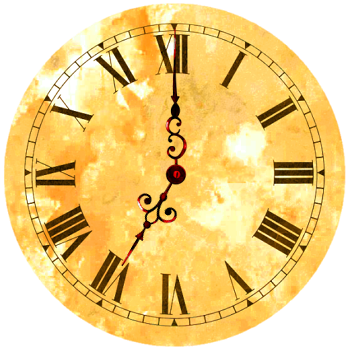
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映し出されるふたり。
チャットから消えるふたり。
チャットが閉じられる――







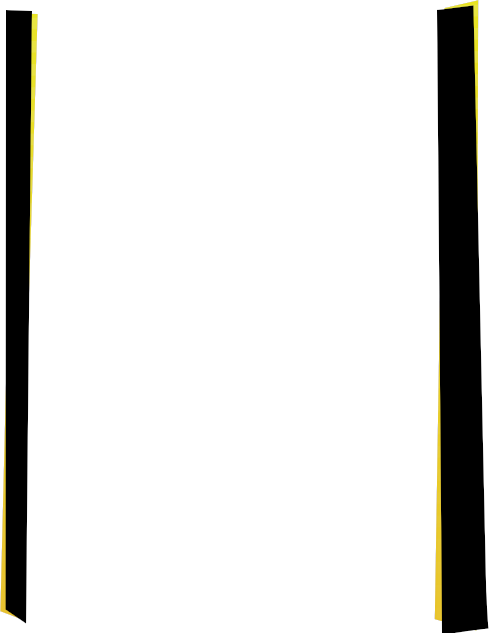
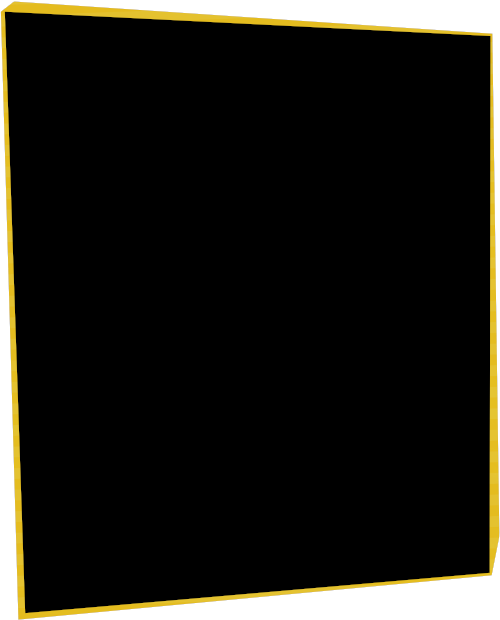





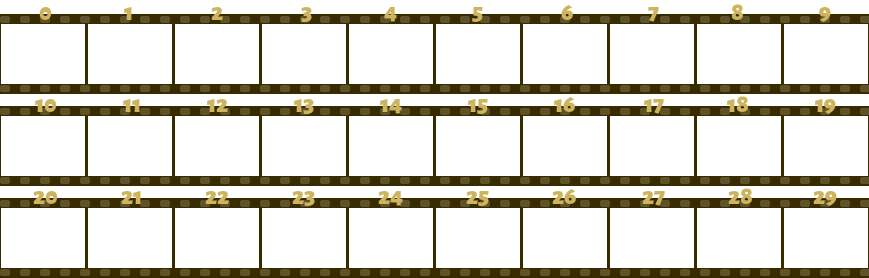







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



掌を見る。
イノカク部の選抜戦あたりから、明らかに異能を扱うという事がわかってきた気がする。自分の思いを強く持てば、異能もそれに応えてくれる。
その言葉を聞いてから、自分はまだこの力とちゃんと向き合ってない気がしたから、恥ずかしいと思っていたその名前を呼ぶようになった。
戦う時には、力を貸して欲しいと思うようになった。
そうしたら、力は、本当に応えてくれた気がした。
炎が生きているかのように、手に馴染む。
これならきっと、もう、誰かを傷つけることはない。
あの、植物園で見た景色は単なる夢なのだ。
『俺は、もっと、強くなる』
―――
――
―
一時間に一度を繰り返す事、六回目。どんな事でも回数をこなせば慣れてくるものだ、なんてどうでもいい感想を持ちながらフェデルタは細く息を吐いた。最初は、吉野俊彦と自分を頻繁に混同していた。その次は、自分が吉野俊彦ではない事にひどく申し訳なさを感じた。
(今は……)
大丈夫だ。本を開く程でもなく、自分は吉野俊彦ではない事と、そして彼で無い事に対する罪悪感は無い。そして、どうやら自分が彼の中で全く消えていないだろうことを感じた。"炎命の士"と名付けられた異能。そもそも、炎を操る力だと吉野俊彦は思わされているのだろう。その炎が自分自身などと、気付くはずも無い。異能という枠に収めて、名前を付けて閉じ込めているのだ。
けれども、彼がその異能に向き合い、力を求めれば自らの力なのだから応えるのは当然だ。
(……もしかしたら、辿り着くのかもな)
強さを、力をまっすぐに求める彼の周りには支え剥げます友や、暖かい家族がいる。それは、フェデルタには全く無かったものだ。だからこそ、彼がこの先をどう進むのかは予想出来ない。
フェデルタには、吉野俊彦の記憶が流れる度に、ぼんやりと感じていたことがある。それは、回数を重ねるごとにどんどんとはっきりした感情としての形を作り上げてきた。
そして、今完全にそれを理解した。
吉野俊彦という存在は、答え合わせなのだ。
今までの、生きていた頃か死んだ先まで、フェデルタ・アートルムが進んできた道への答え合わせ。
正解を積み重ねた吉野俊彦はどんどんと成長していく。
記憶が流れてくる度に前に進んでいく姿に、フェデルタはとっくの昔に置いていかれていた
「……くそ」
唐突に、軽く頭を横に振ってフェデルタは悪態吐く。ふと浮かび上がった植物園の記憶。フェデルタの中にこびりついている炎の記憶が、ご丁寧に吉野俊彦の家族に置き換わり再現されていた。怪しげな霧に見せられた、絶望の幻。
恐らく一緒にいた兄――スズヒコも、嫌なものを見せられたのだろう。冷たく睨み付けるあの瞳はまさに今、スズヒコが自分によく見せてくるものだった。
そして、それでもなお兄を求める吉野俊彦もまた、自分と大いに重なっている。情けなく独りよがりで利己的で相手の事など考えていない、自分ばかりの思考。
それは、普段の吉野俊彦からは考えられないものだった。
「……」
本を取り出し、何かを書こうとしたが頭の中がぐちゃぐちゃでまとめるための言葉も出てこなかった。
チェックポイントまで、特に遮る物もない平坦な道。相変わらず、同行者達との距離広い。敵と対応する時だけの関係だ。
それは、迦楼羅とグノウの主従とだけでなく、スズヒコとも。
(俺は、何をすれば、いいんだろう)
スズヒコに責め立てられてから、ずっとそんな考えばかりがぐるぐると頭を駆け巡り大した答えも無いまま消えていく。
(……あいつは)
吉野俊彦は、どうしてただろうか。
彼は、ずっと強いと思っていた友人の弱さを見付けた時、それを受け入れ、寄り添うことをした。
(俺は、)
スズヒコが強いと信じこんで、彼の弱さを知ろうともしなかった。弱い彼を違うと否定していた。勝手に自分の理想を押し付けていた。
「……」
本当は、あの人にだって弱さがあって、今彼をそうさせているのは強さ故ではなく、弱さ故なのではないのだろうか。
イバラシティでの仮初の人格がなければ、こんな答えにはたどり着けなかっただろう。
フェデルタは、掌をじっと見つめ。代わり映えのない自分の掌の先にいる、イバラシティの自分を見る。
吉野俊彦という存在は、答え合わせなのだ。
答えがあるなら、利用するまでだ。ずるい大人は、もう形振りなんて構っていられない。
(……いや)
彼の言葉を使うなら、その答えを借りる、という事になるのかもしれない。
ずるくて弱い大人は、到底、一人では立ち上がれないから。



ENo.244 スズヒコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.261 暮泥 唯 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
| |||||||
ENo.360 瑞稀 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.452 魄角 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.912 愛夢 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||||||||||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.1039 オーディオル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



| フェデルタ 「なあおい、なあ、バニーガールいるぞ。おい。すげえな。みろよあのデカいの。」 |
グノウ(909) に ItemNo.8 針 を手渡ししました。
ItemNo.10 お野菜 を食べました!
| フェデルタ 「ヤギみてえだな……(野菜バリムシャ」 |
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。





正運極心
|
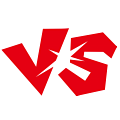 |
鈴のなる夢
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 4 増加!
影響力が 4 増加!



スズヒコ(244) に ItemNo.2 柳 を送付しました。
スズヒコ(244) に ItemNo.15 毛 を送付しました。
制約LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ItemNo.14 牙 から射程1の武器『ネックナイフ』を作製しました!
⇒ ネックナイフ/武器:強さ90/[効果1]追撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
| フェデルタ 「お守りみたいなモンか……」 |
モドラ(730) により ItemNo.12 皮 から防具『丈夫なコート』を作製してもらいました!
⇒ 丈夫なコート/防具:強さ90/[効果1]反護15 [効果2]- [効果3]-
 |
モドラ 「俺の針仕事どう? いいお嫁さんになれそう?」 |
グノウ(909) により ItemNo.14 ネックナイフ に ItemNo.1 駄物 を付加してもらいました!
⇒ ネックナイフ/武器:強さ90/[効果1]追撃10 [効果2]攻撃10 [効果3]-【射程1】
 |
( ペイッ ) |
七夏(12) とカードを交換しました!
ディスカード・セブン (エファヴェセント)
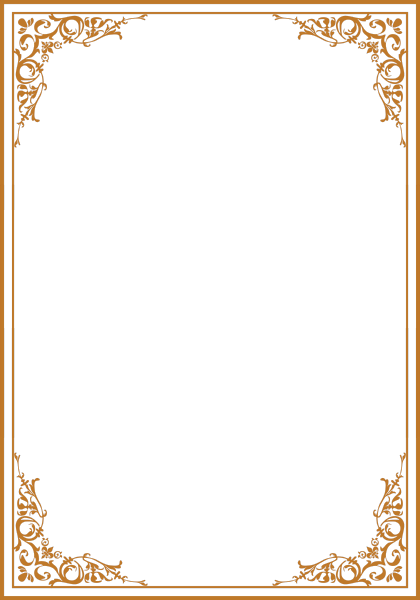
クリエイト:バトルフラッグ を研究しました!(深度2⇒3)
アラベスク を研究しました!(深度1⇒2)
アラベスク を研究しました!(深度2⇒3)
キャプチャートラップ を習得!
ブロック を習得!
フェイタルポイント を習得!
コンセントレイト を習得!
ジャックポット を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ラベンダー を入手!
スズヒコ(244) は 山査子 を入手!
グノウ(909) は 大蒜 を入手!
迦楼羅(931) は 大蒜 を入手!
グノウ(909) は 爪 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は 何か柔らかい物体 を入手!
迦楼羅(931) は パンの耳 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに こぐま がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ローリングタイヤ がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに バニーガール がゆっくりと近づいてきます。



現在のパーティから離脱しました!
ヒノデ区 E-11(草原)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 F-11(草原)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 G-11(草原)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 H-11(道路)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 I-11(道路)に移動!(体調18⇒17)





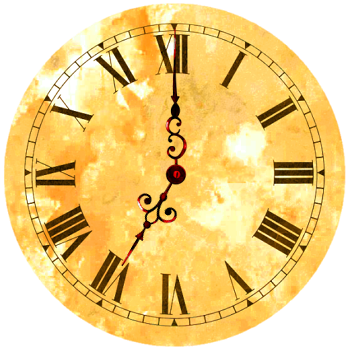
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「うんうん、順調じゃねーっすか。 あとやっぱうるせーのは居ねぇほうが断然いいっすね。」 |
 |
白南海 「いいから早くこれ終わって若に会いたいっすねぇまったく。 もう世界がどうなろうと一緒に歩んでいきやしょうワカァァ――」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カグハ 「・・・わ、変なひとだ。」 |
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
白南海 「――ん、んんッ・・・・・ ・・・なんすか。 お前らは・・・あぁ、梅楽園の団子むすめっこか。」 |
 |
カオリ 「チャットにいたからお邪魔してみようかなって!ごあいさつ!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
 |
白南海 「勝手に人の部屋に入るもんじゃねぇぞ、ガキンチョ。」 |
 |
カオリ 「勝手って、みんなに発信してるじゃんこのチャット。」 |
 |
カグハ 「・・・寂しがりや?」 |
 |
白南海 「・・・そ、操作ミスってたのか。クソ。・・・クソ。」 |
 |
白南海 「そういや、お前らは・・・・・ロストじゃねぇんよなぁ?」 |
 |
カグハ 「違うよー。」 |
 |
カオリ 「私はイバラシティ生まれのイバラシティ育ち!」 |
 |
白南海 「・・・・・は?なんだこっち側かよ。 だったらアンジニティ側に団子渡すなっての。イバラシティがどうなってもいいのか?」 |
 |
カオリ 「あ、・・・・・んー、・・・それがそれが。カグハちゃんは、アンジニティ側なの。」 |
 |
カグハ 「・・・・・」 |
 |
白南海 「なんだそりゃ。ガキのくせに、破滅願望でもあんのか?」 |
 |
カグハ 「・・・・・その・・・」 |
 |
カオリ 「うーあーやめやめ!帰ろうカグハちゃん!!」 |
 |
カオリ 「とにかく私たちは能力を使ってお団子を作ることにしたの! ロストのことは偶然そうなっただけだしっ!!」 |
 |
カグハ 「・・・カオリちゃん、やっぱり私――」 |
 |
カオリ 「そ、それじゃーね!バイビーン!!」 |
チャットから消えるふたり。
 |
白南海 「・・・・・ま、別にいいんすけどね。事情はそれぞれ、あるわな。」 |
 |
白南海 「でも何も、あんな子供を巻き込むことぁねぇだろ。なぁ主催者さんよ・・・」 |
チャットが閉じられる――





ENo.165
喰らい尽くす炎

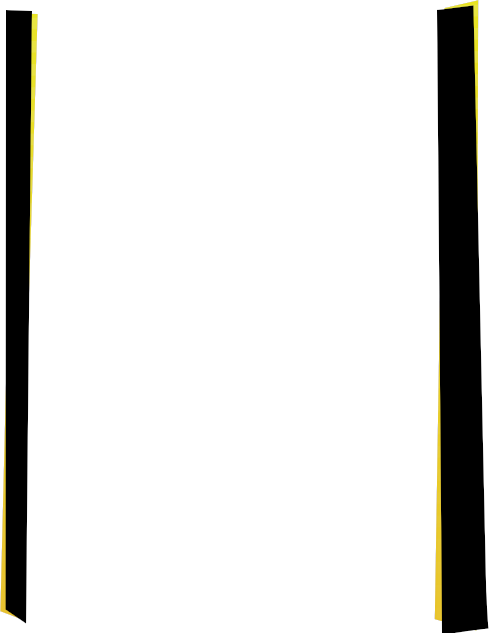
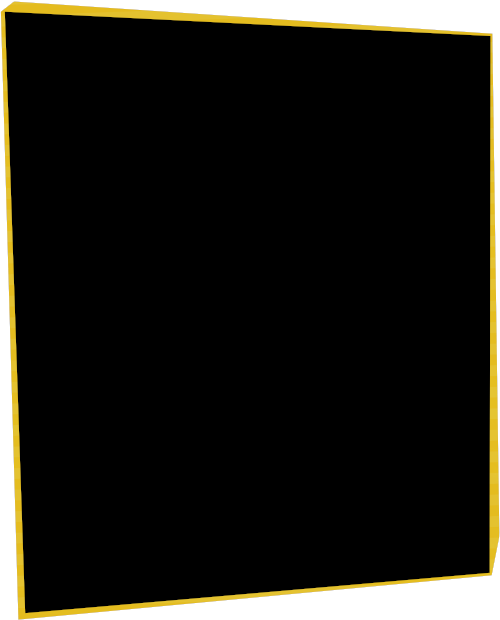
既知設定等大歓迎です。お友達ほしい。
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校2年3組
1年生の中期から異能総合格闘部に所属。
(PL都合で頻度がまばらですが、そこそこちゃんと出ている)
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは割と熱心に剣道をやっていたが、現在は住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校2年3組
1年生の中期から異能総合格闘部に所属。
(PL都合で頻度がまばらですが、そこそこちゃんと出ている)
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは割と熱心に剣道をやっていたが、現在は住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
17 / 30
403 PS
ヒノデ区
I-11
I-11









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | ラベンダー | 素材 | 15 | [武器]魅了15(LV25)[防具]気合10(LV25)[装飾]魔力15(LV30) | |||
| 2 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 粗削りのナイフ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 着なれたコート | 防具 | 35 | 防御10 | 火纏10 | - | |
| 6 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 7 | ぼろぼろマフラー | 装飾 | 45 | 幸運10 | - | - | |
| 8 | |||||||
| 9 | ぐい飲み野菜ジュース(ホット) | 料理 | 55 | 器用10 | 幸運10 | 命脈10 | |
| 10 | |||||||
| 11 | お野菜 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV15)[効果2]幸運10(LV25)[効果3]命脈10(LV35) | |||
| 12 | 丈夫なコート | 防具 | 90 | 反護15 | - | - | |
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 14 | ネックナイフ | 武器 | 90 | 追撃10 | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 15 | |||||||
| 16 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 制約 | 10 | 拘束/罠/リスク |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 50 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| 練3 | フィジカルブースター | 6 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 |
| カームフレア | 6 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| コントラスト | 6 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| デストロイ | 5 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| フェイタルポイント | 5 | 0 | 80 | 敵:精確痛撃 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| フレアトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵列:罠《猛火》LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 獄炎陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど獄炎LV増 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
常備薬 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
鉄球の一撃 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
念道波 (ショックウェイブ) |
0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
|
調息 (パリィ) |
5 | 0 | 自:AG増(2T)+SP増 | |
|
ティータイム (ハーバルメディスン) |
0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) | |
|
カレイドスコープ (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
|
ディスカード・セブン (エファヴェセント) |
0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]五月雨 | [ 3 ]クリエイト:バトルフラッグ | [ 3 ]アラベスク |
| [ 3 ]ヴィガラスチャージ | [ 3 ]プリディクション | [ 3 ]アジャイルフォーム |
| [ 3 ]ブレイブハート |

PL / カミヤキサラ