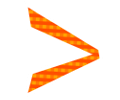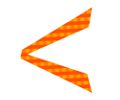<< 4:00~5:00





決定的な一言が浴びせられたときのことを覚えている。
その日は別に代わり映えもしない曇りの日で、俺に対するあらゆる反応はいつものものだった。無視。意図的な回避行動。軽蔑の視線。それら全てに慣れてしまっていた。俗に言う“いじめ”というカテゴリ、大人であるが故に性質の悪さが子供の比ではなく、意識の忌避から産まれるものではない、意図的な排除だ。
けれども、俺は退くわけには行かなかった。まだ独り立ちするには早い年齢の娘を一人抱えていて、故郷には妻と下の娘を残していた。俺が退くと言うことは、少なからず家庭の崩壊を意味する。だから退くわけにはいかず、初めから退路はなかった。
事の始まりは、“俺が界境の向こうの人間である”ということ唯一で、要するに子供と何の変わりもなかったのである。一人だけ存在していた異国(異世界、という方がより正しいのかもしれない)の人間を、自分たちと違うから、忌避した。直接手を下すわけでもなく、真綿で首を絞めるように、外堀を埋め、柵を立て区別し、差別し、そして俺は追いやられた。
初めが運が良かっただけと言えば、そうかもしれない。研究所勤めになったとき、初めて配属された研究室は『変人の集団』『正気のないやつらの掃き溜め』などと呼ばれていた。
要するに、人間の種類なんてどうでもいい、研究、研鑽、探究、探求――その力になるのなら何でもいい、誰でもいい。それは異端の思考であったが、確かにそこでは受け入れられていた。結果こそが全ての世界、人種ごときでどうこうするのがおかしいのだ、という話を聞かされたことがあるわけではないが、少なくとも室長はそういう考えでいたようで、俺の採用理由は“優秀だから”。俺のことを戦力として数えてくれていたのと、拾ってくれたことについては、本当に頭が上がらない――もうとっくに亡くなっているだろう。
時に、変わり者を追い出せないのには理由がある。例えば、それが年長者だった場合。例えば、それと仲良くしている上の者がいる場合。俺のいた研究室の室長は、両方に属する人間で、それ故に、俺はある程度の安寧を得ることが出来て、そしてその安寧は、楔を失った瞬間に崩れ落ちることが決まった。
俺は戦うしかなかった。
案外慣れるものだなあと思っていても、一人だけ書類を用意されなかったり、茶菓子が回ってこなかったり、廃液処理の当番や試験管洗いがやたらと回されてきたり、明確に追い込まれ、ひとつの方向へ向かうよう、誘導されているのを感じていた。
心を殺せ。人だと思われていないのなら、己も相手を人だと思うな。不運か、それとも幸運か、俺は心の殺し方を幼い頃から知っていた。冷たい人だと言われても、それが俺に対して取っている態度そのままで、俺はそれを反射しているに過ぎない。人として扱われないのなら、同じように人として扱われない覚悟はするべきで、それが足りない“人”に、直接詰め寄られたこともあった。俺は言う。
『それ、あなたのやってることですよね?』
時は巡る。研究室の異動がある。辞令が出た日、所長室へと呼ばれた。
当時の研究所長は喫煙者だった。一歩立ち入っただけで鼻の奥をつつく、ピリジンとアセトアルデヒドのにおい。白かった壁紙がうっすらと黄ばみかけていた。
『咲良乃さんさあ』
小さく返事をした。
『いつまでここにいるつもりなんです?』
分かっていた。それをよく分かっていたはずだった。
流水が少しずつ岩石を削り取るように、俺の心もまた、そうだった。加熱と冷却という負荷を繰り返し続けたガラス容器が唐突に壊れるように、高いところから落とされたものが位置エネルギーで破壊されるように。
組み立てたものを崩すのはあっという間で、それは信頼も同様で、元からないと思っていたものが、確かに崩れる音がした。俺は自分の職場に、“自分にこれ以上の悪いことはしないだろう”という信頼を、あれだけ同僚たちだったものから冷たくされてなお、持ってしまっていたのだ。どうして?こんな無法地帯で、律する何かを信じていたのか?
俺は選ばなければならなかった。責任を持たねばならなかった。家族に、娘に、そして己に。
逃げる。どうやって?どこへ?逃げた先でどうする?娘はついてきてくれるのか?それ以外の手段は?誰かに預ける?誰かって誰に?
思考が試行される渦。堂々巡りでどこへも辿り着けない中で、俺は確かに喧嘩を売ったのを覚えている。
『追い出されるまではいますけど』
それが地獄の始まりだった。地獄で一人、ペンを取り試験管を取りピペットを取り、孤立無援にも等しい戦いの始まりだった。
俺が疎まれていたのには、もう一つ理由がある。世界情勢だ。界境を隔てた二つの“世界”は、いよいよ以て混ざり合おうとしていた。それをよしとするもの、しないもの、その争いが始まった。あることないことを互いに吹き込み合い、疑心暗鬼が世界中に渦巻く。そして、繋がっているはずの世界は、断裂する。
境界渡りが制限され、俺の逃げ場(――地元に戻る気は欠片もなかったが)は本格的になくなっていく。異界の人というだけでこうも火の手に晒されるのだから、混ざり血の子供はどうなるのだろう。恐ろしかった。俺はいい。俺は別にいい。好き好んでやっている。子供は、子供には、選択肢がない。では、俺のできる最善はなんだろう。そう思った時、自然と全ては定まった。
俺は、俺の判断が正しかったと思っている。そう思わなければ、示しがつかないからだ。俺は決して気が狂ったわけではなく、そうすることが最適解だと導き出して、あのような行動を取ったのだ。
だから俺は、最後まで誇り高くありたくて、あの救いの手を跳ね除けた。それが本当に誇り高くと言えるものだったかはともかく、俺は最期まで、自分を貫き通したかったのだ。
俺という人間が、生まれ、育ち、学び、働き、萎れ、そして焼け落ちていくまで。
轟々と燃える炎の中でも、酸素量が減っていき二酸化炭素あるいは一酸化炭素が満ちていく中でも、俺はずっと未来を見ていた。俺の死んだ後。二人の娘が歩いていくだろう未来を。
あの瞬間、俺は確かに無敵の人だった。何も怖くはなかった。ひとつだけ恐ろしかったのは、救いの手を取ってしまいそうな弱さだった。
俺はできるなら、できる限り抗いたい。抗って、抗って、徹底的に抗戦し、鉄底まで沈んでも、極限環境でも、生物は生きることができる。適者生存という一言ですべてが終わる。
だから俺は戦い続けるし、俺の戦場は俺の中にしかない。俺の戦いを否定されたくないから、俺の戦場に、俺以外はいなくていい。戦わなくていいんだと言われたその瞬間に、全てが崩れてしまいそうで怖いのだ。
俺は、咲良乃スズヒコという名前で、当時39歳で、職場である研究所に最効率で火が回るよう可燃性ガスや薬品を配置した上で、突入が最も遅くなるだろう場所から火を放った。

火が。火が、燃えている。
ピリジン、アセトアルデヒド、ずんと重い有毒物の臭い、口の中に苦く広がる刺激物の感触味覚味蕾が激しく不快を伝えて、
「うっ、ぐ、おえぇっ……!!」
口の中に熱と不快な味が広がって、ベースキャンプのマーケットの影で吐き戻した。
4時間分。胃の中身はなくなるかなくならないかの瀬戸際だ。固形と液体の間くらいの、何を食べたのか判別できない消化物が道端に垂れた。
犯人はすぐに分かった。“俺”だ。それ以外と、感覚の共有なんてものは、行われていない。吸いたての煙草のどうしようもない味を水で濯いで、走り出した。

獣はそれを見下ろしていた。
共に旅をしている男。いつからそうだったのかはもはや朧げで。煙に巻かれたように思い出せない。
視線が合う。不思議そうな顔をしているのが、よく見える。
「……スズヒコはいねえのか」
いない。
己は咲良乃スズヒコではあるが、そうではない。この(恐らく二つの世界の)狭間でだけ、意思を持った何者でもない存在。ただの能力としての“鈴のなる夢”。
『鈴のなる夢』は所謂通り名でもあるが、今はただの能力だ。ただの能力、というには、意思を持ち、自立歩行をする己は、異質な存在だろう。
有り体に言えば“やることがない”己は、そっとその場に伏せた。巨体は役に立つときと、立たない時がある。
「……何だお前、慰めにでも来たのかよ」
そんなつもりはさらさらなかった。一言で言えば“暇”だったからだ。
けれども、己の中には確かな色眼鏡があった。この男がしゃんとしていないと、何となく落ち着かない。それは己が咲良乃スズヒコであることを、実に分かりやすく現していた。
「……こんなはずじゃなかった。もっとうまくやるつもりだった。少なくとも、このハザマとやらに来たら、少しは上手くいくと思ったんだ」
己はその言葉を聞いても、何とも思わない。己にとってこのハザマとやらは、最も存在しやすく、居心地のいいところだった。
けれども、どこかで、己ではない何かが言うのだ。その言葉に耳を傾けておくべきだと。
「……俺自身が揺らいでる。それはずっと、感じてた……これ以上死ねば、炎に喰われちまうって。……そんな所によお、俺よりもはっきりと意思と形を持った男の記憶が来るんだ」
己に、“イバラシティ”とやらの形は存在していない。
ただ、この男と己の主が、一つの家庭に入り、そして兄弟として存在していることは知っていた。俺の記憶は己の記憶であり、己はそれを他人事のように見ている。実際に、今はまだ、他人事だ。
「……いつか、あいつに喰われちまいそうで正直怖い。俺の身体の筈なのに」
怯えている。この男は、怯えている。
その炎が消えてなくなることに怯えている。
「我ながら情けねえよな。いっそ、俺も意地はるのやめちまおうか」
己は首を動かした。己は今、確かに聞き捨てならないと思ったのだ。
己が主と並び立つのであれば、そのようになってもらっては困るからだ。故に己は、それを睨めつけるしかなかった。
「……わかってる。わかってるよ」
分かれば良い。己は楔であり、鎹であり、重石であり、そして枷だ。永遠に長き時を引き止め続けてきた枷たる己は、だからこそこのように巨大に存在しているのだろう。
ずっと背負い続けてきたもの。怨嗟。愛情。怒り。悲しみ。微かな楽しさ。それが己を構成している。そして己の力として、この世界では発露する。
「……情けねえな、俺」
要するに、己は感情の機微には聡く、それ故己はこの男の思惑が、ある程度分かるのだ。
情けなく思っている。即ちそれはマイナスの感情で、今所持されていて良いものとは思えない。己はこの環境を良く思っていたが、俺はそうではなさそうだし、そうなるとこの男もそうだ。
己には複雑な言葉を発することのできる声帯はない。だから、これが最適解だと思ったのだ。
「うおっ」
人間は触れ合いである程度のストレス発散をする。己は俺であり、しかして俺ではない存在だが、それでもないよりはマシになるだろう。
己の頭に堂々と存在している、普段は敵に突き立てる角が邪魔で、鬱陶しい。故に己は、爪の代わりに舌を伸ばした。
巨大な獣の舌がフェデルタ・アートルムの頬を舐め上げ、それから右目と視線が合う。
何か文句でもあるか、と見つめてくる翠の目に、何も言えることはなかった。不意に大きな耳がピンと立ち、きょろきょろと辺りを見渡す。ここはベースキャンプだから、出向かなければ敵はいない。
「んだよ、お前……」
殺意が風となって向かってくるようだった。
(ENo165の日記に続きます)



ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

ENo.687 音和姉弟 とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました














赤毛の人狼(90) に 30 PS 送付しました。
アキジ(308) から 不思議な石 を受け取りました。
武術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
迦楼羅(931) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
赤毛の人狼(90) により ItemNo.14 お魚 から料理『海鮮丼』をつくってもらいました!
⇒ 海鮮丼/料理:強さ55/[効果1]活力10 [効果2]敏捷10 [効果3]強靭10
赤毛の人狼(90) により ItemNo.15 お魚 から料理『焼き魚』をつくってもらいました!
⇒ 焼き魚/料理:強さ55/[効果1]活力10 [効果2]敏捷10 [効果3]強靭10
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.9 お野菜 から料理『ぐい飲み野菜ジュース(ホット)』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.6 お野菜 から料理『挽き肉入りポテトコロッケ』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.12 ビーフ から料理『粗挽きビーフ10割ハンバーグ』をつくりました!
グノウ(909) により ItemNo.10 百科のエフェメラ に ItemNo.16 毛 を付加してもらいました!
⇒ 百科のエフェメラ/装飾:強さ50/[効果1]回復10 [効果2]回復10 [効果3]-
竹取の翁(1391) とカードを交換しました!
竹槍落とし穴 (ピットトラップ)


プチメテオカード を研究しました!(深度0⇒1)
プチメテオカード を研究しました!(深度1⇒2)
プチメテオカード を研究しました!(深度2⇒3)
スノードロップ を習得!
治癒領域 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は たけのこ を入手!
スズヒコ(244) は 柳 を入手!
グノウ(909) は 古雑誌 を入手!
迦楼羅(931) は 柳 を入手!
スズヒコ(244) は 牙 を入手!
フェデルタ(165) は 不思議な牙 を入手!
フェデルタ(165) は 皮 を入手!
グノウ(909) は 牙 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ウルフ が微笑を浮かべて近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 大蛇 がスキップしながら近づいてきます。



ヒノデ区 B-9(森林)に移動!(体調25⇒24)
ヒノデ区 B-10(山岳)に移動!(体調24⇒23)
ヒノデ区 B-11(山岳)に移動!(体調23⇒22)
ヒノデ区 C-11(草原)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 D-11(草原)に移動!(体調21⇒20)






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――





















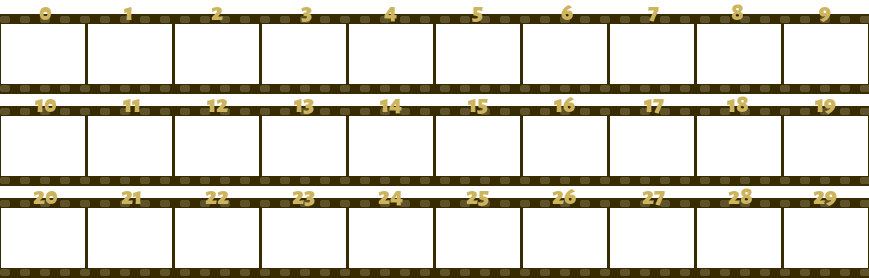









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




決定的な一言が浴びせられたときのことを覚えている。
その日は別に代わり映えもしない曇りの日で、俺に対するあらゆる反応はいつものものだった。無視。意図的な回避行動。軽蔑の視線。それら全てに慣れてしまっていた。俗に言う“いじめ”というカテゴリ、大人であるが故に性質の悪さが子供の比ではなく、意識の忌避から産まれるものではない、意図的な排除だ。
けれども、俺は退くわけには行かなかった。まだ独り立ちするには早い年齢の娘を一人抱えていて、故郷には妻と下の娘を残していた。俺が退くと言うことは、少なからず家庭の崩壊を意味する。だから退くわけにはいかず、初めから退路はなかった。
事の始まりは、“俺が界境の向こうの人間である”ということ唯一で、要するに子供と何の変わりもなかったのである。一人だけ存在していた異国(異世界、という方がより正しいのかもしれない)の人間を、自分たちと違うから、忌避した。直接手を下すわけでもなく、真綿で首を絞めるように、外堀を埋め、柵を立て区別し、差別し、そして俺は追いやられた。
初めが運が良かっただけと言えば、そうかもしれない。研究所勤めになったとき、初めて配属された研究室は『変人の集団』『正気のないやつらの掃き溜め』などと呼ばれていた。
要するに、人間の種類なんてどうでもいい、研究、研鑽、探究、探求――その力になるのなら何でもいい、誰でもいい。それは異端の思考であったが、確かにそこでは受け入れられていた。結果こそが全ての世界、人種ごときでどうこうするのがおかしいのだ、という話を聞かされたことがあるわけではないが、少なくとも室長はそういう考えでいたようで、俺の採用理由は“優秀だから”。俺のことを戦力として数えてくれていたのと、拾ってくれたことについては、本当に頭が上がらない――もうとっくに亡くなっているだろう。
時に、変わり者を追い出せないのには理由がある。例えば、それが年長者だった場合。例えば、それと仲良くしている上の者がいる場合。俺のいた研究室の室長は、両方に属する人間で、それ故に、俺はある程度の安寧を得ることが出来て、そしてその安寧は、楔を失った瞬間に崩れ落ちることが決まった。
俺は戦うしかなかった。
案外慣れるものだなあと思っていても、一人だけ書類を用意されなかったり、茶菓子が回ってこなかったり、廃液処理の当番や試験管洗いがやたらと回されてきたり、明確に追い込まれ、ひとつの方向へ向かうよう、誘導されているのを感じていた。
心を殺せ。人だと思われていないのなら、己も相手を人だと思うな。不運か、それとも幸運か、俺は心の殺し方を幼い頃から知っていた。冷たい人だと言われても、それが俺に対して取っている態度そのままで、俺はそれを反射しているに過ぎない。人として扱われないのなら、同じように人として扱われない覚悟はするべきで、それが足りない“人”に、直接詰め寄られたこともあった。俺は言う。
『それ、あなたのやってることですよね?』
時は巡る。研究室の異動がある。辞令が出た日、所長室へと呼ばれた。
当時の研究所長は喫煙者だった。一歩立ち入っただけで鼻の奥をつつく、ピリジンとアセトアルデヒドのにおい。白かった壁紙がうっすらと黄ばみかけていた。
『咲良乃さんさあ』
小さく返事をした。
『いつまでここにいるつもりなんです?』
分かっていた。それをよく分かっていたはずだった。
流水が少しずつ岩石を削り取るように、俺の心もまた、そうだった。加熱と冷却という負荷を繰り返し続けたガラス容器が唐突に壊れるように、高いところから落とされたものが位置エネルギーで破壊されるように。
組み立てたものを崩すのはあっという間で、それは信頼も同様で、元からないと思っていたものが、確かに崩れる音がした。俺は自分の職場に、“自分にこれ以上の悪いことはしないだろう”という信頼を、あれだけ同僚たちだったものから冷たくされてなお、持ってしまっていたのだ。どうして?こんな無法地帯で、律する何かを信じていたのか?
俺は選ばなければならなかった。責任を持たねばならなかった。家族に、娘に、そして己に。
逃げる。どうやって?どこへ?逃げた先でどうする?娘はついてきてくれるのか?それ以外の手段は?誰かに預ける?誰かって誰に?
思考が試行される渦。堂々巡りでどこへも辿り着けない中で、俺は確かに喧嘩を売ったのを覚えている。
『追い出されるまではいますけど』
それが地獄の始まりだった。地獄で一人、ペンを取り試験管を取りピペットを取り、孤立無援にも等しい戦いの始まりだった。
俺が疎まれていたのには、もう一つ理由がある。世界情勢だ。界境を隔てた二つの“世界”は、いよいよ以て混ざり合おうとしていた。それをよしとするもの、しないもの、その争いが始まった。あることないことを互いに吹き込み合い、疑心暗鬼が世界中に渦巻く。そして、繋がっているはずの世界は、断裂する。
境界渡りが制限され、俺の逃げ場(――地元に戻る気は欠片もなかったが)は本格的になくなっていく。異界の人というだけでこうも火の手に晒されるのだから、混ざり血の子供はどうなるのだろう。恐ろしかった。俺はいい。俺は別にいい。好き好んでやっている。子供は、子供には、選択肢がない。では、俺のできる最善はなんだろう。そう思った時、自然と全ては定まった。
俺は、俺の判断が正しかったと思っている。そう思わなければ、示しがつかないからだ。俺は決して気が狂ったわけではなく、そうすることが最適解だと導き出して、あのような行動を取ったのだ。
だから俺は、最後まで誇り高くありたくて、あの救いの手を跳ね除けた。それが本当に誇り高くと言えるものだったかはともかく、俺は最期まで、自分を貫き通したかったのだ。
俺という人間が、生まれ、育ち、学び、働き、萎れ、そして焼け落ちていくまで。
轟々と燃える炎の中でも、酸素量が減っていき二酸化炭素あるいは一酸化炭素が満ちていく中でも、俺はずっと未来を見ていた。俺の死んだ後。二人の娘が歩いていくだろう未来を。
あの瞬間、俺は確かに無敵の人だった。何も怖くはなかった。ひとつだけ恐ろしかったのは、救いの手を取ってしまいそうな弱さだった。
俺はできるなら、できる限り抗いたい。抗って、抗って、徹底的に抗戦し、鉄底まで沈んでも、極限環境でも、生物は生きることができる。適者生存という一言ですべてが終わる。
だから俺は戦い続けるし、俺の戦場は俺の中にしかない。俺の戦いを否定されたくないから、俺の戦場に、俺以外はいなくていい。戦わなくていいんだと言われたその瞬間に、全てが崩れてしまいそうで怖いのだ。
俺は、咲良乃スズヒコという名前で、当時39歳で、職場である研究所に最効率で火が回るよう可燃性ガスや薬品を配置した上で、突入が最も遅くなるだろう場所から火を放った。

火が。火が、燃えている。
ピリジン、アセトアルデヒド、ずんと重い有毒物の臭い、口の中に苦く広がる刺激物の感触味覚味蕾が激しく不快を伝えて、
「うっ、ぐ、おえぇっ……!!」
口の中に熱と不快な味が広がって、ベースキャンプのマーケットの影で吐き戻した。
4時間分。胃の中身はなくなるかなくならないかの瀬戸際だ。固形と液体の間くらいの、何を食べたのか判別できない消化物が道端に垂れた。
犯人はすぐに分かった。“俺”だ。それ以外と、感覚の共有なんてものは、行われていない。吸いたての煙草のどうしようもない味を水で濯いで、走り出した。

獣はそれを見下ろしていた。
共に旅をしている男。いつからそうだったのかはもはや朧げで。煙に巻かれたように思い出せない。
視線が合う。不思議そうな顔をしているのが、よく見える。
「……スズヒコはいねえのか」
いない。
己は咲良乃スズヒコではあるが、そうではない。この(恐らく二つの世界の)狭間でだけ、意思を持った何者でもない存在。ただの能力としての“鈴のなる夢”。
『鈴のなる夢』は所謂通り名でもあるが、今はただの能力だ。ただの能力、というには、意思を持ち、自立歩行をする己は、異質な存在だろう。
有り体に言えば“やることがない”己は、そっとその場に伏せた。巨体は役に立つときと、立たない時がある。
「……何だお前、慰めにでも来たのかよ」
そんなつもりはさらさらなかった。一言で言えば“暇”だったからだ。
けれども、己の中には確かな色眼鏡があった。この男がしゃんとしていないと、何となく落ち着かない。それは己が咲良乃スズヒコであることを、実に分かりやすく現していた。
「……こんなはずじゃなかった。もっとうまくやるつもりだった。少なくとも、このハザマとやらに来たら、少しは上手くいくと思ったんだ」
己はその言葉を聞いても、何とも思わない。己にとってこのハザマとやらは、最も存在しやすく、居心地のいいところだった。
けれども、どこかで、己ではない何かが言うのだ。その言葉に耳を傾けておくべきだと。
「……俺自身が揺らいでる。それはずっと、感じてた……これ以上死ねば、炎に喰われちまうって。……そんな所によお、俺よりもはっきりと意思と形を持った男の記憶が来るんだ」
己に、“イバラシティ”とやらの形は存在していない。
ただ、この男と己の主が、一つの家庭に入り、そして兄弟として存在していることは知っていた。俺の記憶は己の記憶であり、己はそれを他人事のように見ている。実際に、今はまだ、他人事だ。
「……いつか、あいつに喰われちまいそうで正直怖い。俺の身体の筈なのに」
怯えている。この男は、怯えている。
その炎が消えてなくなることに怯えている。
「我ながら情けねえよな。いっそ、俺も意地はるのやめちまおうか」
己は首を動かした。己は今、確かに聞き捨てならないと思ったのだ。
己が主と並び立つのであれば、そのようになってもらっては困るからだ。故に己は、それを睨めつけるしかなかった。
「……わかってる。わかってるよ」
分かれば良い。己は楔であり、鎹であり、重石であり、そして枷だ。永遠に長き時を引き止め続けてきた枷たる己は、だからこそこのように巨大に存在しているのだろう。
ずっと背負い続けてきたもの。怨嗟。愛情。怒り。悲しみ。微かな楽しさ。それが己を構成している。そして己の力として、この世界では発露する。
「……情けねえな、俺」
要するに、己は感情の機微には聡く、それ故己はこの男の思惑が、ある程度分かるのだ。
情けなく思っている。即ちそれはマイナスの感情で、今所持されていて良いものとは思えない。己はこの環境を良く思っていたが、俺はそうではなさそうだし、そうなるとこの男もそうだ。
己には複雑な言葉を発することのできる声帯はない。だから、これが最適解だと思ったのだ。
「うおっ」
人間は触れ合いである程度のストレス発散をする。己は俺であり、しかして俺ではない存在だが、それでもないよりはマシになるだろう。
己の頭に堂々と存在している、普段は敵に突き立てる角が邪魔で、鬱陶しい。故に己は、爪の代わりに舌を伸ばした。
巨大な獣の舌がフェデルタ・アートルムの頬を舐め上げ、それから右目と視線が合う。
何か文句でもあるか、と見つめてくる翠の目に、何も言えることはなかった。不意に大きな耳がピンと立ち、きょろきょろと辺りを見渡す。ここはベースキャンプだから、出向かなければ敵はいない。
「んだよ、お前……」
殺意が風となって向かってくるようだった。
(ENo165の日記に続きます)



ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.687 音和姉弟 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました







痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
番長連合
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 3 増加!
影響力が 3 増加!



赤毛の人狼(90) に 30 PS 送付しました。
アキジ(308) から 不思議な石 を受け取りました。
武術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
迦楼羅(931) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
赤毛の人狼(90) により ItemNo.14 お魚 から料理『海鮮丼』をつくってもらいました!
⇒ 海鮮丼/料理:強さ55/[効果1]活力10 [効果2]敏捷10 [効果3]強靭10
赤毛の人狼(90) により ItemNo.15 お魚 から料理『焼き魚』をつくってもらいました!
⇒ 焼き魚/料理:強さ55/[効果1]活力10 [効果2]敏捷10 [効果3]強靭10
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.9 お野菜 から料理『ぐい飲み野菜ジュース(ホット)』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.6 お野菜 から料理『挽き肉入りポテトコロッケ』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.12 ビーフ から料理『粗挽きビーフ10割ハンバーグ』をつくりました!
グノウ(909) により ItemNo.10 百科のエフェメラ に ItemNo.16 毛 を付加してもらいました!
⇒ 百科のエフェメラ/装飾:強さ50/[効果1]回復10 [効果2]回復10 [効果3]-
竹取の翁(1391) とカードを交換しました!
竹槍落とし穴 (ピットトラップ)


プチメテオカード を研究しました!(深度0⇒1)
プチメテオカード を研究しました!(深度1⇒2)
プチメテオカード を研究しました!(深度2⇒3)
スノードロップ を習得!
治癒領域 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は たけのこ を入手!
スズヒコ(244) は 柳 を入手!
グノウ(909) は 古雑誌 を入手!
迦楼羅(931) は 柳 を入手!
スズヒコ(244) は 牙 を入手!
フェデルタ(165) は 不思議な牙 を入手!
フェデルタ(165) は 皮 を入手!
グノウ(909) は 牙 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ウルフ が微笑を浮かべて近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 大蛇 がスキップしながら近づいてきます。



ヒノデ区 B-9(森林)に移動!(体調25⇒24)
ヒノデ区 B-10(山岳)に移動!(体調24⇒23)
ヒノデ区 B-11(山岳)に移動!(体調23⇒22)
ヒノデ区 C-11(草原)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 D-11(草原)に移動!(体調21⇒20)






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
メガネ販売部
|


ENo.244
鈴のなる夢



ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
20 / 30
257 PS
ヒノデ区
D-11
D-11







痛撃友の会
3
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
2
アイコン1000pxの会
7
#片道切符チャット
1
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
8
長文大好きクラブ
1
自我とか意思とかある異能の交流会
5
カード報告会
10
とりあえず肉食う?
12



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 異本の栞 | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | - | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | 海鮮丼 | 料理 | 55 | 活力10 | 敏捷10 | 強靭10 | |
| 15 | 焼き魚 | 料理 | 55 | 活力10 | 敏捷10 | 強靭10 | |
| 16 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 45 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 8 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| グレイシア | 5 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
竹槍落とし穴 (ピットトラップ) |
0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]マナポーション |

PL / 紙箱みど