<< 3:00~4:00





背の高い青年が、一人の少女を連れて――というには、随分と距離を取って、けれども彼らは確実に同じ行き先に歩いている。
金色の髪の中にはらはらと揺れる深紅を、少女の蒼い目がじっと見上げていた。
西村一騎――を騙る怪異、異端の者《哀歌の行進》は、創峰大学の周辺地域を適当にうろついていた。だが、それも終わりだと思った。元より“これ”が、自分より神に近しいものであることは、知っていたはずだ。己はもともと“西村一騎”だったもので、それがほんの僅かな可能性を勝ち取り、力を得、具現化し、数箇所を彷徨って、釣り餌に釣られて今に至る。釣られない、と言う選択はあったはずだった。それを選ぶことは自由意志だったはずだ。来てしまった以上、好奇心に抗えなかった、ということでしかない。
「クレープ。期間限定のやつ、2つだ」
この辺りは賑わいすぎている。学徒の集う街、そこに必然的に集まってくる学徒のためのもの、いつどこに行っても、疑いの視線など向けられる暇はなかった。高校生たちの通学を見送り、適当にクレープ屋で物を頼んでも、少女の特異さに誰も目を向けない。
ここは異能の街。少し人型から外れているくらいでは、何とも思われない、人種の坩堝。
「ミカ?食べるだろ?」
「食べるけれど、私に餌付けは通用しない。私は私の心に従って動くから」
諦めたようなため息。ミカ、と呼ばれた少女は、何の躊躇いもなくクレープの追加トッピングを要求した。
「……お前」
「払えないわけじゃないでしょう。私が今すぐあなたを焼いてもいいのなら、それでもいいけれど……」
ゆらりと傾けられた首に応じるように、長いポニーテールと、本来耳のある位置から生えている、鳥の羽の形状を取っているもの。肩を伸ばすようにそれが伸ばされ、ぴたりと畳まれると、改めて少女は男の方を見た。
「でも、それ、都合が悪いんでしょう?」
「クソ。これだから善寄りのやつは」
「寄りじゃないわ。私は優しいのよ、とても」
男は人間ではなく、そしてこの少女も人間ではない。人間をベースにしている男と違って、少女は根本から違う。一言で言うのなら、神だ。
何者でもなく、ただ混沌の上に存在する。それは燃える炎として顕現し、破壊と恵みを等しく与えていく。そのように祀り上げられていた、紛れもない神“だった”ものだ。
御火籠神社は、もはや神社の体を成していない神社だった。社は廃屋の如く、立ち入るものは誰一人としてない、寂れた場所だ。寂れた場所になってしまった。古のときに起こった災害で全てが押し流され、民草と土着の信仰を一気に失った哀れな八百万の神の一柱、それがこの【混沌たる御火籠の炎】だ。秩序の炎のみがひたすらに祀り上げられ、忘れられつつあった神は、その名のとおりに気まぐれな存在だった。
初めにしたことは、ひとつの可能性との接触だった。足を踏み外しかけていた可能性を気まぐれで救い、そのまま力を喪失した。次にしたことは、眷属を従えて、様々な地を巡ることだった。途中で見知らぬ庭園に立ち寄り、曰く『花を沢山食べてきた』。
【哀歌の行進】は知っている。何故なら、己ももとはその可能性のひとつで、【透翅流星飛行】に誑かされた存在だからだ。故に目をつけられ、そして追い回されている。靡いてしまったほう、靡かなかったほう、神に救われたほう、神に救われなかったほう。
それらが同時に存在している。
「六割くらい使ったんじゃなかったのか?」
「使った分、取り戻した。私の眷属はよく働いてくれるし、ちょうどいいところがあった。それだけの話で、それだけじゃない。それはあなたがよく分かっていたかと思ったけど、違った?」
「スケールのデカい話はわからん。俺は神様じゃないからね」
ターゲットにされていることが分かっていて、なお余裕の顔をしていられるのは、彼らも、そして自分も、同じように縛られていることが分かっていたからだった。要するに、彼らが全力を出すためにはまだそれなりの時間が必要で、それは自分も同様である。即ち、まだ向き合うまでには余裕があり、それまでは自由時間。彼らはしこたま準備をしてくるかもしれないが、自分にはその必要はなかった――はずだった。
イレギュラーとしてこの神が現れるまでは、だ。
それはまさしく籠であり、そして炎だった。想定ではもっと自由に“西村一騎”をこの手の中に収めていたはずだ。少なくとも、昨日まではそうだった。
魂だけでのこのこと現れたそれが、明らかすぎる罠だったと分かっていても、【哀歌の行進】は、それを捕まえる他なかった。捕まえて、手の中に置く。紫筑のクソどもに付き合って、踊らされているフリをする。それだけでよかったはずなのだ。か弱い少女という仮初の姿を与えたのも、この街を一緒に回ったのも――ただ、向こうの策に乗らないように。ただで返してやるわけにはいかないという挑戦状であり、そうすることを想定しているだろうという考えがあってのことだった、はずなのに、だ。
降りてきた神は一瞬でその仮初の姿を乗っ取り、魂を籠に閉じ込めてしまった。まるで横から攫っていくようにそれをやってのけ、そしてなお、こうして接触してくる。
神のすることは分からない。
「そう……けど、あなたは狩られる側」
「いつ決めた?」
「彼らの長がそう言っているのなら、私はその味方をしようかな」
「ここで殺すか?」
「私は炎。どこにでもあり、どこにもない。そうね、私の機嫌が損なわれたら、そのとき焼くというのはどう。私はあなたの居場所なんてものはすぐわかるから、いつだってそうできる」
炎は青く覚めていくほど高温になると聞いた。白に近い青の瞳に見上げられ、【哀歌の行進】は肩を竦める事しか出来なかった。
「神も怪異も変わらないもの。私にあってあなたにないのは、誰かに対する恵みくらい」
「……それは、そうやって囲い込むような?」
「ええ。私、分家とは言っても、私に連なる血は大切にする。例えとっくに忘れられていたとしても、私は忘れないから。それだけのことで、それだけじゃない」
長い髪を揺らして、クレープを食みながら歩き去り、雑踏に消えていく背中を追うことはではなかった。
あれは自分の上位存在だ。うかつに上位存在に手を出すと、ろくなことにならないのはよく知っている。それは紫筑の人間たちも同じだろうが、彼らの長は恐れを知らない。それが一番厄介で、要するにあれは“どうなってもいい”と思っている。手を出すことで掴める結果があるのなら、それを優先する。知識を何よりも優先する、怪異に限りなく近い人間。
(まあ、俺のやることになんら変わりはないんだけど……)
目標とすることはただひとつだった。
この世界に縛られている必要はない。ワールドスワップとかいう面白そうなものにも巻き込まれてはいない。
だから、彼らのターゲットから外れればいい。
「ヨシノアケミ、ヨシノアケミねえ……」
クレープを食んだ。
カスタードクリームとチョコレートソースが、ゆっくりと舌に染みていった。

初めにそれを聞いたとき、思ったことは「ですよね」ということただひとつだった。
実際に実行に移されたときも、思ったことは「ですよね」ということただひとつだった。
今、今だけは、そのどれもが当てはまらない。
発生したイレギュラーは、想定していたものとは遥かにかけ離れていた。『イレギュラーには自己判断で柔軟に対応しろ』ではない。創峰の本部にこの格好で行くか?どうする?行きたいわけあるか!!
『あの~あのさ、神様?俺はどうすれば?』
「さあ……」
説明しよう。俺は西村一騎、哀れにも怪異に対する釣り餌として魂を利用された人間だ。実際の俺は183cmあるイケメン(としたいところだがちょっと自信がなくなってきたので、それなりのイケメンに訂正する)である。魂だけを切り離された理由や技術面の話は割愛する。俺より詳しい人がたくさんいるからだ。具体的に言うと創峰大に。
俺の所属している創峰――紫筑大学、第四学群神秘研究科怪異対策類実務班は、要するに、ひとではないもの・人の道を踏み外したものを狩るための集団だ。人に害なすものをすべて怪異と断じ、被害が広まる前に狩る。不思議不可思議が跋扈する世の中で、明確に抑止力として働いている集団のうちのひとつに、能力を買われて所属しているのだ。学生の身だが給料も出る。
ちょっとした危険や遠征は常々付き物で、“今回もその一例でしかなかった”。別の世界で活動する時、最悪に備えて紫筑ではバックアップを取る。死、あるいは能力の喪失という救いようのない事態に直面したとき、その世界で死んだ記録を記載しない。荒業にもすぎる強力な能力者がいるからこそ(ちなみに学長のことである)、紫筑は積極的に“外”への派遣をしている。
つまり、この世界で何がどうなったとしても、最悪何も記載せず、何事もなかったかのように派遣前のバックアップの“西村一騎”を動かし始めれば良い。肉体の連続性は保たれるが魂の連続性は保たれなくなるとか、難しい話を聞いた覚えはあるが、死ななければ安く済む話だ。学長もそう言っていた。
ただ、今となってはいっそ殺してくれという気持ちに満ち溢れている。
『幼女の格好はまだいいよ、いいけど、神は何故ダイレクトに自分の格好を?俺は訝しんだ』
「私だって楽しみたいことくらいあるけれど……?」
人の魂を肉体から切り離したとき、それは即ち死と定義される。だが、それは元の世界での話であって、異なる世界線ではその定義は適用されない。それを利用して魂だけで行動したり、あるいは仮初の肉体を得たりして、真なる意味の死を回避する。そういう……そういう難しいことを、俺たちの同意の上でやっているのが、大日向深知で、紫筑大学で、その学長だ。
少なくとも今俺たちは、仮に肉体が破損したとしても、何の影響も受けない――とまでは行かないが、生命の保障はされている。そこまではいい。
仮初の肉体は基本的に魂の性別に依存するが、外から手を加えられた場合はこの限りではない。今の俺の場合は、双子であることを利用し、妹と入れ替わった上で魂を切り離した。故に、仮初の姿は女性となるはずなのだ。それはいい。
『そういうことじゃないんだっつの!俺は何故幼女にっていう話をしていて……』
そう。この姿は当然だが俺の妹の姿ではない。妹は成人女性である。
「……それは、省エネというもの。私もあまり、食べてきたものをここで吐くわけにはいかないから」
『省エネイコール幼女なの!?』
「大きい身体を作るのは面倒」
人ではないということを、繕うことすら放棄していることを省エネと呼ぶのだろうか。神の言うことは分からない。
ただ、そこにあるのは、確かな羽の感触と、長く艷やかな黒髪だ。それだけはどうやっても覆らない。
「あなたは安全な籠の中にいると思えばいい。私は優しいから、私の知るあなたでなくても、あなたには協力してあげるって決めている。私に眷属をくれたのは“あなた”。気が向いた私に、私は感謝をする必要がある」
『……けど、あれも俺らしいですけど?』
「在り方が合わないやつは嫌いなの」
クレープを食んだ。何の味も、感覚さえなかった。
この身体は、間違いなく神に主導権を握られているという証拠だった。
「私も楽しいことは好きよ。けど、楽しいことのために、何か悪いことをするのは嫌。その悪いことは私だけが決めていいから、あれとは絶対に合わない、それだけで、それだけではないの」
『……スケールの大きい話はちょっと分かんないっす』
「そっくりね。けど、あなたには秩序がある。従うべきものがある。それだけで、私が愛を与えるのに十分なの」
歩むつま先が炎に包まれ、そのうち全身をなめるように焼いたかと思うと、その姿はこつ然と消えている。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.426 アストロイェライ とのやりとり

ENo.889 ディルクルム とのやりとり

以下の相手に送信しました














六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



迦楼羅(931) に 41 PS 送付しました。
桔柳(1211) に 15 PS 送付しました。
ヒシュ(1202) から 30 PS 受け取りました。
お魚(50 PS)を購入しました。
お魚(50 PS)を購入しました。
具現LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
命術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
料理LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
筒井 粋(288) により ItemNo.12 藍鉄鉱 から防具『零度の背表紙』を作製してもらいました!
⇒ 零度の背表紙/防具:強さ100/[効果1]反凍10 [効果2]- [効果3]-
エインモーネ(421) により ItemNo.13 大軽石 から射程4の大砲『ドリームパイルバンカー』を作製してもらいました!
⇒ ドリームパイルバンカー/大砲:強さ75/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-【射程4】
ノジコ(456) により ItemNo.10 毛 から装飾『百科のエフェメラ』を作製してもらいました!
⇒ 百科のエフェメラ/装飾:強さ50/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
桔柳(1211) により ItemNo.6 大軽石 から射程1の武器『キャンベルストライカー』を作製してもらいました!
⇒ キャンベルストライカー/武器:強さ75/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
ヒシュ(1202) の持つ ItemNo.10 美味しい果実 から料理『尽くす炎のキャラメリゼタルト』をつくりました!
一海(853) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『春キャベツのペペロンチーノ』をつくりました!
グノウ(909) により ItemNo.6 キャンベルストライカー に ItemNo.11 牙 を付加してもらいました!
⇒ キャンベルストライカー/武器:強さ75/[効果1]幸運10 [効果2]追撃10 [効果3]-【射程1】
カナリア(501) とカードを交換しました!
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク)

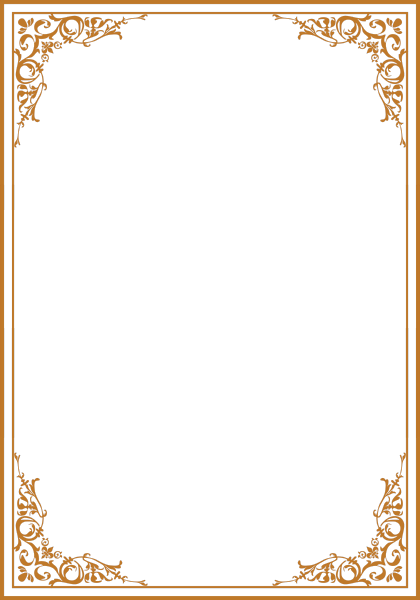
アブソーブ を研究しました!(深度0⇒1)
アブソーブ を研究しました!(深度1⇒2)
アブソーブ を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
フロウライフ を習得!
クリーンヒット を習得!
コンテイン を習得!
アンダークーリング を習得!
ヘイルカード を習得!
アクアヒール を習得!
フローズンフォーム を習得!
水の祝福 を習得!
☆グレイシア を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



スズヒコ(244) は ボロ布 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は ボロ布 を入手!
迦楼羅(931) は 剛毛 を入手!
迦楼羅(931) は ボロ布 を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は 毛 を入手!
迦楼羅(931) は 毛 を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 歩行軍手 がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 大黒猫 がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 に転送されました!
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 S-8(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 T-8(山岳)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 A-8(山岳)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 B-8(森林)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- フェデルタ(165) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- グノウ(909) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- フェデルタ(165) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- グノウ(909) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)





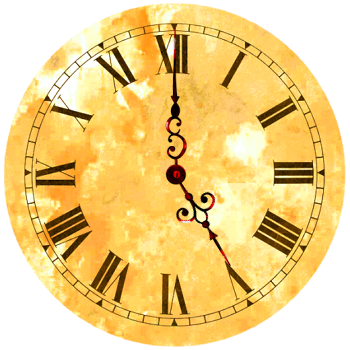
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。

ノウレットから遠く離れる白南海。
遠く離れた白南海を手招く。
チャットが閉じられる――














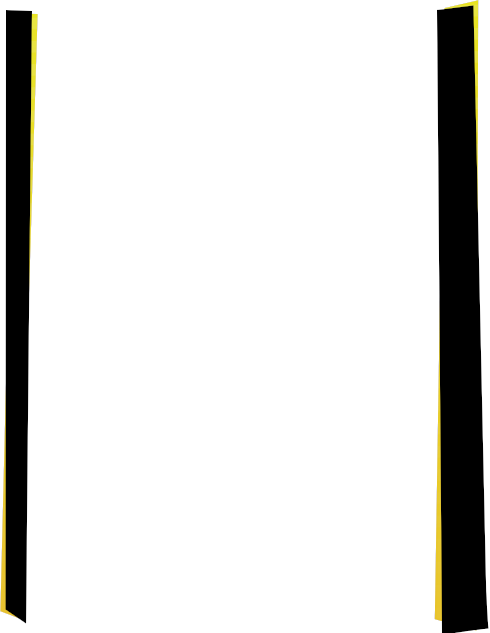
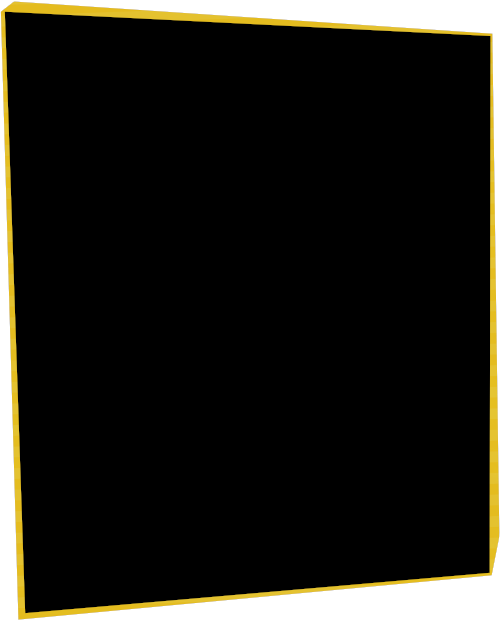





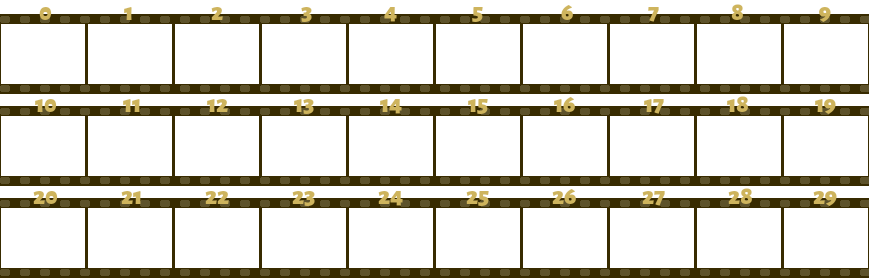









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




背の高い青年が、一人の少女を連れて――というには、随分と距離を取って、けれども彼らは確実に同じ行き先に歩いている。
金色の髪の中にはらはらと揺れる深紅を、少女の蒼い目がじっと見上げていた。
西村一騎――を騙る怪異、異端の者《哀歌の行進》は、創峰大学の周辺地域を適当にうろついていた。だが、それも終わりだと思った。元より“これ”が、自分より神に近しいものであることは、知っていたはずだ。己はもともと“西村一騎”だったもので、それがほんの僅かな可能性を勝ち取り、力を得、具現化し、数箇所を彷徨って、釣り餌に釣られて今に至る。釣られない、と言う選択はあったはずだった。それを選ぶことは自由意志だったはずだ。来てしまった以上、好奇心に抗えなかった、ということでしかない。
「クレープ。期間限定のやつ、2つだ」
この辺りは賑わいすぎている。学徒の集う街、そこに必然的に集まってくる学徒のためのもの、いつどこに行っても、疑いの視線など向けられる暇はなかった。高校生たちの通学を見送り、適当にクレープ屋で物を頼んでも、少女の特異さに誰も目を向けない。
ここは異能の街。少し人型から外れているくらいでは、何とも思われない、人種の坩堝。
「ミカ?食べるだろ?」
「食べるけれど、私に餌付けは通用しない。私は私の心に従って動くから」
諦めたようなため息。ミカ、と呼ばれた少女は、何の躊躇いもなくクレープの追加トッピングを要求した。
「……お前」
「払えないわけじゃないでしょう。私が今すぐあなたを焼いてもいいのなら、それでもいいけれど……」
ゆらりと傾けられた首に応じるように、長いポニーテールと、本来耳のある位置から生えている、鳥の羽の形状を取っているもの。肩を伸ばすようにそれが伸ばされ、ぴたりと畳まれると、改めて少女は男の方を見た。
「でも、それ、都合が悪いんでしょう?」
「クソ。これだから善寄りのやつは」
「寄りじゃないわ。私は優しいのよ、とても」
男は人間ではなく、そしてこの少女も人間ではない。人間をベースにしている男と違って、少女は根本から違う。一言で言うのなら、神だ。
何者でもなく、ただ混沌の上に存在する。それは燃える炎として顕現し、破壊と恵みを等しく与えていく。そのように祀り上げられていた、紛れもない神“だった”ものだ。
御火籠神社は、もはや神社の体を成していない神社だった。社は廃屋の如く、立ち入るものは誰一人としてない、寂れた場所だ。寂れた場所になってしまった。古のときに起こった災害で全てが押し流され、民草と土着の信仰を一気に失った哀れな八百万の神の一柱、それがこの【混沌たる御火籠の炎】だ。秩序の炎のみがひたすらに祀り上げられ、忘れられつつあった神は、その名のとおりに気まぐれな存在だった。
初めにしたことは、ひとつの可能性との接触だった。足を踏み外しかけていた可能性を気まぐれで救い、そのまま力を喪失した。次にしたことは、眷属を従えて、様々な地を巡ることだった。途中で見知らぬ庭園に立ち寄り、曰く『花を沢山食べてきた』。
【哀歌の行進】は知っている。何故なら、己ももとはその可能性のひとつで、【透翅流星飛行】に誑かされた存在だからだ。故に目をつけられ、そして追い回されている。靡いてしまったほう、靡かなかったほう、神に救われたほう、神に救われなかったほう。
それらが同時に存在している。
「六割くらい使ったんじゃなかったのか?」
「使った分、取り戻した。私の眷属はよく働いてくれるし、ちょうどいいところがあった。それだけの話で、それだけじゃない。それはあなたがよく分かっていたかと思ったけど、違った?」
「スケールのデカい話はわからん。俺は神様じゃないからね」
ターゲットにされていることが分かっていて、なお余裕の顔をしていられるのは、彼らも、そして自分も、同じように縛られていることが分かっていたからだった。要するに、彼らが全力を出すためにはまだそれなりの時間が必要で、それは自分も同様である。即ち、まだ向き合うまでには余裕があり、それまでは自由時間。彼らはしこたま準備をしてくるかもしれないが、自分にはその必要はなかった――はずだった。
イレギュラーとしてこの神が現れるまでは、だ。
それはまさしく籠であり、そして炎だった。想定ではもっと自由に“西村一騎”をこの手の中に収めていたはずだ。少なくとも、昨日まではそうだった。
魂だけでのこのこと現れたそれが、明らかすぎる罠だったと分かっていても、【哀歌の行進】は、それを捕まえる他なかった。捕まえて、手の中に置く。紫筑のクソどもに付き合って、踊らされているフリをする。それだけでよかったはずなのだ。か弱い少女という仮初の姿を与えたのも、この街を一緒に回ったのも――ただ、向こうの策に乗らないように。ただで返してやるわけにはいかないという挑戦状であり、そうすることを想定しているだろうという考えがあってのことだった、はずなのに、だ。
降りてきた神は一瞬でその仮初の姿を乗っ取り、魂を籠に閉じ込めてしまった。まるで横から攫っていくようにそれをやってのけ、そしてなお、こうして接触してくる。
神のすることは分からない。
「そう……けど、あなたは狩られる側」
「いつ決めた?」
「彼らの長がそう言っているのなら、私はその味方をしようかな」
「ここで殺すか?」
「私は炎。どこにでもあり、どこにもない。そうね、私の機嫌が損なわれたら、そのとき焼くというのはどう。私はあなたの居場所なんてものはすぐわかるから、いつだってそうできる」
炎は青く覚めていくほど高温になると聞いた。白に近い青の瞳に見上げられ、【哀歌の行進】は肩を竦める事しか出来なかった。
「神も怪異も変わらないもの。私にあってあなたにないのは、誰かに対する恵みくらい」
「……それは、そうやって囲い込むような?」
「ええ。私、分家とは言っても、私に連なる血は大切にする。例えとっくに忘れられていたとしても、私は忘れないから。それだけのことで、それだけじゃない」
長い髪を揺らして、クレープを食みながら歩き去り、雑踏に消えていく背中を追うことはではなかった。
あれは自分の上位存在だ。うかつに上位存在に手を出すと、ろくなことにならないのはよく知っている。それは紫筑の人間たちも同じだろうが、彼らの長は恐れを知らない。それが一番厄介で、要するにあれは“どうなってもいい”と思っている。手を出すことで掴める結果があるのなら、それを優先する。知識を何よりも優先する、怪異に限りなく近い人間。
(まあ、俺のやることになんら変わりはないんだけど……)
目標とすることはただひとつだった。
この世界に縛られている必要はない。ワールドスワップとかいう面白そうなものにも巻き込まれてはいない。
だから、彼らのターゲットから外れればいい。
「ヨシノアケミ、ヨシノアケミねえ……」
クレープを食んだ。
カスタードクリームとチョコレートソースが、ゆっくりと舌に染みていった。

初めにそれを聞いたとき、思ったことは「ですよね」ということただひとつだった。
実際に実行に移されたときも、思ったことは「ですよね」ということただひとつだった。
今、今だけは、そのどれもが当てはまらない。
発生したイレギュラーは、想定していたものとは遥かにかけ離れていた。『イレギュラーには自己判断で柔軟に対応しろ』ではない。創峰の本部にこの格好で行くか?どうする?行きたいわけあるか!!
『あの~あのさ、神様?俺はどうすれば?』
「さあ……」
説明しよう。俺は西村一騎、哀れにも怪異に対する釣り餌として魂を利用された人間だ。実際の俺は183cmあるイケメン(としたいところだがちょっと自信がなくなってきたので、それなりのイケメンに訂正する)である。魂だけを切り離された理由や技術面の話は割愛する。俺より詳しい人がたくさんいるからだ。具体的に言うと創峰大に。
俺の所属している創峰――紫筑大学、第四学群神秘研究科怪異対策類実務班は、要するに、ひとではないもの・人の道を踏み外したものを狩るための集団だ。人に害なすものをすべて怪異と断じ、被害が広まる前に狩る。不思議不可思議が跋扈する世の中で、明確に抑止力として働いている集団のうちのひとつに、能力を買われて所属しているのだ。学生の身だが給料も出る。
ちょっとした危険や遠征は常々付き物で、“今回もその一例でしかなかった”。別の世界で活動する時、最悪に備えて紫筑ではバックアップを取る。死、あるいは能力の喪失という救いようのない事態に直面したとき、その世界で死んだ記録を記載しない。荒業にもすぎる強力な能力者がいるからこそ(ちなみに学長のことである)、紫筑は積極的に“外”への派遣をしている。
つまり、この世界で何がどうなったとしても、最悪何も記載せず、何事もなかったかのように派遣前のバックアップの“西村一騎”を動かし始めれば良い。肉体の連続性は保たれるが魂の連続性は保たれなくなるとか、難しい話を聞いた覚えはあるが、死ななければ安く済む話だ。学長もそう言っていた。
ただ、今となってはいっそ殺してくれという気持ちに満ち溢れている。
『幼女の格好はまだいいよ、いいけど、神は何故ダイレクトに自分の格好を?俺は訝しんだ』
「私だって楽しみたいことくらいあるけれど……?」
人の魂を肉体から切り離したとき、それは即ち死と定義される。だが、それは元の世界での話であって、異なる世界線ではその定義は適用されない。それを利用して魂だけで行動したり、あるいは仮初の肉体を得たりして、真なる意味の死を回避する。そういう……そういう難しいことを、俺たちの同意の上でやっているのが、大日向深知で、紫筑大学で、その学長だ。
少なくとも今俺たちは、仮に肉体が破損したとしても、何の影響も受けない――とまでは行かないが、生命の保障はされている。そこまではいい。
仮初の肉体は基本的に魂の性別に依存するが、外から手を加えられた場合はこの限りではない。今の俺の場合は、双子であることを利用し、妹と入れ替わった上で魂を切り離した。故に、仮初の姿は女性となるはずなのだ。それはいい。
『そういうことじゃないんだっつの!俺は何故幼女にっていう話をしていて……』
そう。この姿は当然だが俺の妹の姿ではない。妹は成人女性である。
「……それは、省エネというもの。私もあまり、食べてきたものをここで吐くわけにはいかないから」
『省エネイコール幼女なの!?』
「大きい身体を作るのは面倒」
人ではないということを、繕うことすら放棄していることを省エネと呼ぶのだろうか。神の言うことは分からない。
ただ、そこにあるのは、確かな羽の感触と、長く艷やかな黒髪だ。それだけはどうやっても覆らない。
「あなたは安全な籠の中にいると思えばいい。私は優しいから、私の知るあなたでなくても、あなたには協力してあげるって決めている。私に眷属をくれたのは“あなた”。気が向いた私に、私は感謝をする必要がある」
『……けど、あれも俺らしいですけど?』
「在り方が合わないやつは嫌いなの」
クレープを食んだ。何の味も、感覚さえなかった。
この身体は、間違いなく神に主導権を握られているという証拠だった。
「私も楽しいことは好きよ。けど、楽しいことのために、何か悪いことをするのは嫌。その悪いことは私だけが決めていいから、あれとは絶対に合わない、それだけで、それだけではないの」
『……スケールの大きい話はちょっと分かんないっす』
「そっくりね。けど、あなたには秩序がある。従うべきものがある。それだけで、私が愛を与えるのに十分なの」
歩むつま先が炎に包まれ、そのうち全身をなめるように焼いたかと思うと、その姿はこつ然と消えている。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.426 アストロイェライ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.889 ディルクルム とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||
以下の相手に送信しました







痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
【PT2】LuckyStar
|



チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



迦楼羅(931) に 41 PS 送付しました。
桔柳(1211) に 15 PS 送付しました。
ヒシュ(1202) から 30 PS 受け取りました。
お魚(50 PS)を購入しました。
お魚(50 PS)を購入しました。
具現LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
命術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
料理LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
筒井 粋(288) により ItemNo.12 藍鉄鉱 から防具『零度の背表紙』を作製してもらいました!
⇒ 零度の背表紙/防具:強さ100/[効果1]反凍10 [効果2]- [効果3]-
| 筒井 粋 「金箔押しにしていいか?ダメか……そうか……」 |
エインモーネ(421) により ItemNo.13 大軽石 から射程4の大砲『ドリームパイルバンカー』を作製してもらいました!
⇒ ドリームパイルバンカー/大砲:強さ75/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-【射程4】
| エインモーネ 「指示通りにした。確認してくれ」 |
ノジコ(456) により ItemNo.10 毛 から装飾『百科のエフェメラ』を作製してもらいました!
⇒ 百科のエフェメラ/装飾:強さ50/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
 |
ノジコ 「こんな感じでいいかもっ! どうどう? どうかしらっ!」 |
桔柳(1211) により ItemNo.6 大軽石 から射程1の武器『キャンベルストライカー』を作製してもらいました!
⇒ キャンベルストライカー/武器:強さ75/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
 |
『幸運を齎す』と云われている本。その中身は深遠なる知識とも、こことは異なる世界の怪奇の一覧とも、あるいは異言語によるただの童話だとも噂される。その内容は非常に分厚いが……本当は何が書かれているか分からない。それを読んで確かめるのも、本の楽しみでもある。 |
ヒシュ(1202) の持つ ItemNo.10 美味しい果実 から料理『尽くす炎のキャラメリゼタルト』をつくりました!
一海(853) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『春キャベツのペペロンチーノ』をつくりました!
グノウ(909) により ItemNo.6 キャンベルストライカー に ItemNo.11 牙 を付加してもらいました!
⇒ キャンベルストライカー/武器:強さ75/[効果1]幸運10 [効果2]追撃10 [効果3]-【射程1】
 |
グノウ 「これがああなって、そうなって、こうなります。」 |
カナリア(501) とカードを交換しました!
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク)

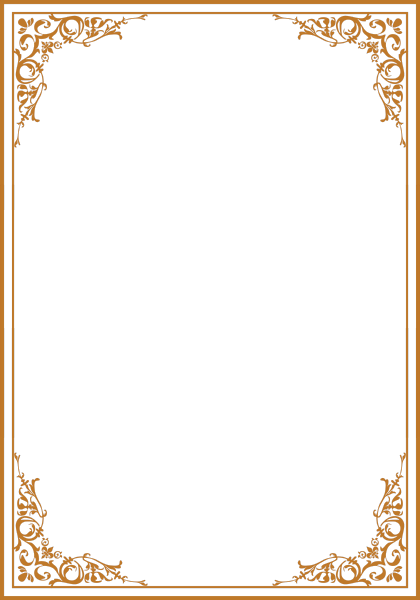
アブソーブ を研究しました!(深度0⇒1)
アブソーブ を研究しました!(深度1⇒2)
アブソーブ を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
フロウライフ を習得!
クリーンヒット を習得!
コンテイン を習得!
アンダークーリング を習得!
ヘイルカード を習得!
アクアヒール を習得!
フローズンフォーム を習得!
水の祝福 を習得!
☆グレイシア を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



スズヒコ(244) は ボロ布 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は ボロ布 を入手!
迦楼羅(931) は 剛毛 を入手!
迦楼羅(931) は ボロ布 を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
フェデルタ(165) は 毛 を入手!
迦楼羅(931) は 毛 を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 歩行軍手 がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 大黒猫 がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「はいお疲れさん。サービスの飴ちゃん持ってきな。」 |
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 S-8(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 T-8(山岳)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 A-8(山岳)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 B-8(森林)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- フェデルタ(165) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- グノウ(909) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- フェデルタ(165) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)
- グノウ(909) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》(ベースキャンプ外のため無効)





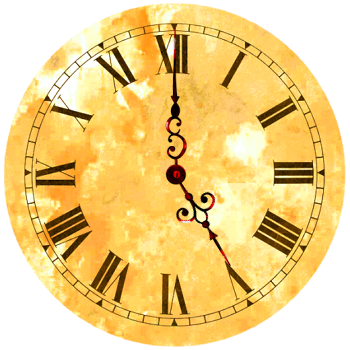
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「ん・・・・・」 |
 |
エディアン 「これは・・・・・」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「なんでしょうこれ!変な情報が映し出されてますねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・つーか何でまた一緒の部屋入ってるんですかね。」 |
 |
エディアン 「いいじゃないですかぁ!案外ヒマじゃないですか?案内役。」 |
 |
白南海 「私はひとりがいいんです、が、ね。」 |
 |
エディアン 「くッッらいですねぇ・・・・・クール気取りですか一匹狼気取りですか、まったく。」 |
 |
白南海 「うっせーオンナが嫌いなだけです。」 |
 |
エディアン 「・・・そういう発言、嫌われますよぉ?」 |
 |
白南海 「貴方も、ね。」 |
 |
エディアン 「――さて、まぁいいとしてこのログ?は何なんですかねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・・・仕方ねぇですね。・・・おーい、クソ妖精ー。」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!ノウレットはいつでも貴方の背後から―――ッ!!」 |
 |
エディアン 「あぁなるほどノウレットちゃん!」 |
 |
エディアン 「・・・っていうかクソ妖精って――」 |
 |
ノウレット 「あだ名をいただいちゃいました☆」 |
 |
白南海 「――ほれ、Cross+Roseに変な情報出てんぞ説明しろ。」 |
 |
ノウレット 「うおおぉぉぉ頼られてます!?もしかして頼られてますッ!!?」 |
ノウレットから遠く離れる白南海。
 |
ノウレット 「どうして離れていくんですッ!!!?」 |
 |
ノウレット 「これはですねぇ!チェックポイント開放者数の情報ですっ!!」 |
 |
エディアン 「えぇえぇ、それはまぁそうかなーとは。右側の1000って数字はなんでしょう? もしかして開放できる人数が限られてる・・・とか?」 |
 |
ノウレット 「いえいえー!開放は皆さんできますよーっ!! これはハザマにいる全員に新たな力を与えるという情報です!!」 |
 |
エディアン 「新たな力・・・?」 |
 |
ノウレット 「そうでぇっす!!各チェックポイントの開放者数が増えるほど、対応する力が強く与えられます! 1000というのは1000人より上は1000人として扱うってことです!!」 |
 |
エディアン 「なるほどなるほど。これ・・・・・敵も味方も、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!全部が全部、ハザマの全員でーす!!」 |
 |
エディアン 「具体的に、どんな力が与えられるんです?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・はーい、大丈夫ですよー。」 |
 |
エディアン 「これは言葉からイメージして実感してみるしかないですかね。 出てくる敵にも力が・・・・・気をつけないといけませんね。」 |
 |
エディアン 「・・・・・白南海さーん!聞きましたよー。」 |
遠く離れた白南海を手招く。
 |
白南海 「――まぁ聞こえていたわけですが。離れても音量変わらなかったわけですが。」 |
 |
エディアン 「・・・ノウレットちゃんの音量調整できますよ?コンフィグで。」 |
 |
白南海 「・・・・・ぁー、よくわかんねぇめんどくせぇ。」 |
 |
エディアン 「まったく、こういうのダメな人ですか。右上のここから・・・ほら、音量設定。あるでしょ。 それから・・・・・あぁ違いますって!それだとチャッ――」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
番長連合
|


ENo.244
鈴のなる夢

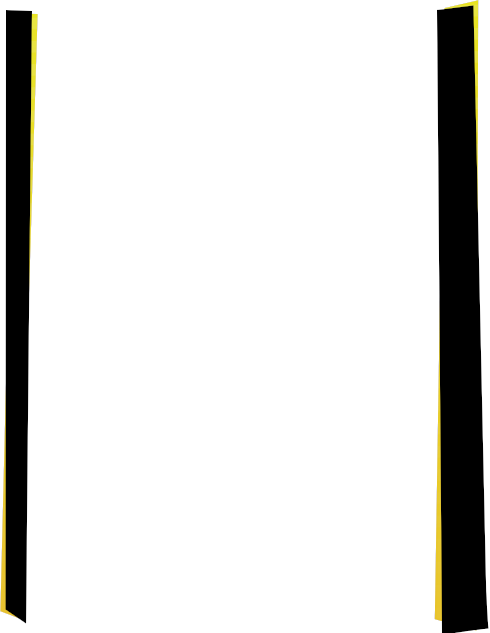
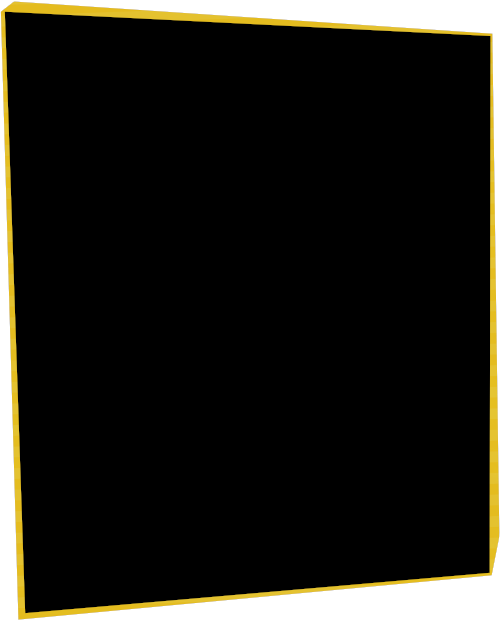
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
25 / 30
162 PS
ヒノデ区
B-8
B-8







痛撃友の会
2
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
5
アイコン60pxの会
8
#片道切符チャット
1
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
8
長文大好きクラブ
2
自我とか意思とかある異能の交流会
5
カード報告会
9



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 異本の栞 | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 孔雀石 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV25)[防具]耐狂15(LV25)[装飾]放毒10(LV20) | |||
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | - | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | - | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | お魚 | 食材 | 10 | [効果1]活力10(LV15)[効果2]敏捷10(LV25)[効果3]強靭10(LV35) | |||
| 15 | お魚 | 食材 | 10 | [効果1]活力10(LV15)[効果2]敏捷10(LV25)[効果3]強靭10(LV35) | |||
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 40 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| 練3 | ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 7 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| 練3 | クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| グレイシア | 5 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]プロテクション |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]フィジカルブースター |

PL / 紙箱みど




































