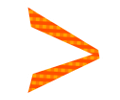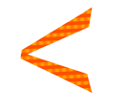<< 2:00~3:00





俺はいつも、笑い声とともに生きてきたと言っても過言ではなかっただろう。
純粋な笑顔。嘲笑の声。ひそひそと笑う声。繕った笑い。
もし俺が、もう少しだけ冷酷で、もう少しだけ心を強く持てていたのなら、そもそもこのような記述もまた、必要ないのである。
端的に述べるのなら、俺のいた環境は恵まれていなかった、という方に入るだろう。どれだけ酷かったか、という点については、各々の主観が大きく、己が体感したものを最も酷いものだと感じるものだろうから、割愛する。ただ、俺は常々思うのだ。死んでから動き続けてなお、思うのだ。己の可能性について。己の家を継げた可能性、研究者として大成できていた可能性、それらに思いを馳せなかった日はあっても、月や年という単位まで伸ばしてしまえば、いつもどこかで思考している。二度と叶わない願いだと言うのに、だ。
これは『記録』のつもりで書いている。俺は、俺の成せなかった数多のことを忘れてはならず、同時にそれらをいい加減に扱ってもならない。それは俺を成長させたものであることに間違いはないし、道を踏み外した結果に今の俺が存在している。
故に、再び道を踏み外すようなことがあってはならない。その時は、己の過ちを認め、然るべき処置を取るべきである。
息苦しい話が続くが、俺はきちんとこの話をしたことがなかったと思う。故に、記す。いつかの自分に丸投げするというのも変な話だが、向き合うことに未だにストレス性だろう身の強張りを感じたり、鼓動が速くなったり、そういうことがあるのだ。一度その拍動を完全に止めた身のはずなのに、奇妙なものである。
まず、俺は、一言で言うなら田舎の因習集落の生まれである。因習集落、という言い方は正しくない気もするが、俺が大学の友人たちに、自分の出自を話して最も言われた言葉が『因習村』である。故にそのように記載する。
俺の出身の世界である双極界『バイポーリス』(以下、当該世界と記す)は、何らかの要因で、全く文化・自然体系の異なる二つの世界が融合し、その文化・自然体系はそれぞれがほぼ独立したまま発展を遂げてきた世界である。自然の坩堝『ネイトリエ』、科学の極点『シエンティカ』。これら二つの対極にある世界が何故融合を果たしたのか、そしてその文化がほぼ混ざり合うことなく、互いに侵攻をすることもなく、それぞれで独立しているかというのは大変興味深い現象だが、あいにく専門ではない。何にせよ、当該世界のネイトリエ側、そしてその極地と呼ばれる『世界の果て』に限りなく近い、神を信仰し、魔術を呼吸のように行使する人間が多数暮らしていたカントカムイと呼ばれている地域が、俺の生まれた地である。
家を継げなかった人間であり、さらに言うと界境を渡ったため、ネイトリエの記述もシエンティカの記述も、不確かで古い情報になってしまう。しかし俺が俺のままであるなら、いつか『最後に一度くらいは故郷に帰りたい』と言い出さない保証もない。俺はどこまでも非情にはなりきれず、だからあのとき指輪を処分できなかった。娘が生きていれば、今持っているはずである。あの子はとにかく気が強いから、俺と違ってどこへ行ってもやっていけるだろう。
まず、俺の出身の集落の周辺では、信仰がほぼ全てであった。神に祈りを捧げ、神の声を聞く人間がいて、神のために捧げる舞があり、神のために捧げる刃があった。このどれかになれなければ、穀潰しだ。求められることは、早急に子を成し、次の代を育てることだった。
集落を出てから分かったことだが、魔力量は保有遺伝子によって大きく左右されるらしく、俺は本当にあの集落に向いていなかった、というのは、大変大きな収穫だった。鍛錬から引き離し、本を与えてくれた父の慧眼に眼を見張るばかりである。
要するに、俺は自分の生まれた場所では出来損ないだったが、他の場所ならまだやれる芽があった。そう、俺の父は判断してくれた。恐らくもう生きていないだろうが、閉鎖的な環境にありながら、そのような判断ができる人物は大変貴重である。
さて、生まれる場所に恵まれなかった俺は、生きていく場所を変えることにした。界境越えは俺の生きていた時代から活発化し、特にシエンティカからの科学者が、ネイトリエの自然を調査しに来ていた。極地、と呼ばれるカントカムイ周辺にすら、だ。小さな子供がぽつぽつと零す疑問に、満面の笑顔で答えてくれた、名も知らぬ科学者のことを、俺は忘れないだろう。
だから、俺は家を出ることにした。父は止めなかったし、何も言わなかった。母は狂ったように俺を責め立てた。生き恥を晒すことになるだの、私がこの集落で生きていけなくなるだの、いろいろと言われたけれど、俺には関係ないことだ。俺が努めて自分の子の私物化をしないようにできたのは、このことがあってこそだと思っている。
生まれる場所が選べないのなら、生きる場所は選んでもいい。否、選ぶ権利がある。だから俺は、家を出ることを選んだ。
選択には責任が伴う。俺は、以降人生の全ての責任を、自分で抱えなければいけなくなった。成人すればいずれそうなるとは言っても、一人で歩かせるのにはまだ危ない歳の頃から。
ここまで記載しても、俺の人生は言うほど波乱ではないのでは、と思うことがある。けれども、人生は各々に固有のものが割り当てられ、各々に固有の感じ方がある。俺のことをかわいそうだと思える人もいるだろうし、俺のことを恵まれていると思わざるを得ない人もいる。世界というものはかように残酷な構造をしていて、簡単に人が死ぬかもしれないような場合もあれば、生きていることそのものが苦痛である場合もある。
この先誰かに出会った時、ひとつ呼吸を置いて、冷静になる必要がある。
自分の常識は絶対ではないということ。自分を卑下しないこと。自分の怒りに囚われ、そのままに行動しないこと。
郷に入っては郷に従え、という言葉がある。俺が何らかの力を行使するためには、どのみちある程度その世界に馴染まなければならない。だから、少し冷静になれる時間があれば、俺はきちんと把握ができるだろうし、十分な時間があったのなら、状況を打破する思考もできるだろう。理論上、そうなっている。
これを記載している時点では、自分の正気が失われることについて、あまり確証が持てないでいる。ただ、人間は“忘れる生き物”で、それを模倣している以上、記載は必要な作業だし、俺が正気を失って、人を食い殺したという事実もまた、記載されるべき事象である。
改めて思う。俺は、すっかりバケモノになってしまったのだと。けれどもどうせなら、せめて誇り高くありたい。俺は確かにこの身を、自分で選び取ったのだということを、忘れないようにしていたい。それが俺の成せた唯一の、下の娘に成せた唯一の、父親らしいことなのだ。
故にゆめゆめ忘れるな、俺はバケモノである以前に人間で、最善の選択の結果としてそうなってしまっただけの、一人の人間なのだ。

――吉野暁海。吉野暁海、吉野暁海!!
俺はお前を絶対に許さない。許したくない。お前という存在が、お前という存在がある限り、俺は永劫に苦しめられる。俺の鏡写しを語るな。何も知らない顔で生きていようとするな。何も知らない顔で、平和な生活を享受するな。俺が、俺がそこに至るまで、どれだけ苦労したと思っているんだ。お前には分かるまい。分かられてたまるか。何も分からないまま、侵略されて死んでしまえ。
フェデルタは「引きずられた」と言っていた。俺は何も思わなかった、ただ、俺は平凡な大学生で、フェデルタの――吉野俊彦の、兄。そういう舞台装置として、世界に組み込まれている。そのことだけを理解した。
見下すだけなら人の姿でも十分な獣が、“アケミちゃんは冗談も聞かないのか”と言ったようなことを言っていたのを、獣の戯言として処理できた。
つい先程まで出来ていたことがもうできない。イバラシティ。吉野暁海。凡庸な学生ではなく、努力もしない天才で、苦労があったとすれば“何の能力も持たなかったこと”で、尽く恵まれた、恵まれてしかいない、同じ目の色をした大学生。何にも縛られず、知識を求めることを許された、平和で恵まれた家庭に生きている一人の青年。
もし神がそこにいたのなら、間違いなくその喉笛を掻っ切っている。どうして何の制約もない、ただただ恵まれた姿がねじ込まれているのか。俺という人間に対する当てつけだろうか。
否。罪に対する罰だとでも言うのか。
罪?犯した覚えなんてない。罰?生きている間にこれでもかと、浴びせるように与えてきたくせに。神なんて元から信じていなかったけれど、都合のいいときにだけ信じるような趣味も、思想も、持ち合わせてはいなかった。
それ以前に、ただただ怒っていた。
俺が何をしたと言うのか。異形と罪人と負の空気しかない、枯れた世界に落とされるようなことを、何をしたというのか。いつ。どのようにして。明確な証拠を求める。
そうだ。確かに俺たちには司法があったはずなのに、何もしてくれやしなかった。言葉をあげれば物理的にあの場所を焼き払うこともなかった。それが罪だとでも言うのか?
そこまで俺を追い詰めた人間たちへの罰は?
それらを棚に上げて俺を罰するのか?集団で叩いた側には何もなくて、人のいないタイミングを見計らって、可燃性の薬品を並べてから火を放った俺の方が悪いと言われる所以はどこにある?
――それが通るんだったら、世界なんて本当にクソだ。
クソ。クソ。クソッタレ。クソしかいない世界なんて滅んでしまえ。アンジニティなんていうクソッタレの世界から、まず、死ねばいい。元からどうせ、罪人の掃き溜めなんだから、なくたって困りやしないのだ。罪人は疾く死ねばいい。流刑にするような情けなんか与えずに殺せばいい。こんなところがあったから、こんなところがあるから、こんなことになって、俺たちは、俺は、
……何を邪魔されたんだっけ?
歩む獣は、それを人に合わせなければならなかった。
己のみなら大足ひとつで済むものを、頻繁に待ったり座ったり、時には首根っこ咥えて走ったり、そうすることは悪くないと思っていた。
何より、獣にはこの場所は快適であった。ひりついた空気。闘争、逃走、そして闘争。奇っ怪な空も何も気にならない。
「……」
“己”は、それを良しとしてはいないようだった。負の感情を常に胸の内に抱き、怒りの噴煙は常に立ち上り、どうしようもなく変質している。
気づき給え、“己”よ。その時が来ない限り、絶対に己はこの大地から逃れることはできまい。
残り三十時間を切ったうちに、気づかねばならない。その時初めて、この怒りたる己は、お前にようよう従おう。
己は“己”の思考も何も分からぬが、己はお前の怒りである。故に、こうしてお前に従うのだ。お前は正当に怒っているからだ。
けれどもゆめゆめ忘れるな、己は『怒っていい』が、『狂っていい』わけではない。
それを忘れている限り、お前は永遠に罪人だ。理知を忘れて狂うこと、それそのものが罪なのだ。お前という人間が築いてきた何もかもを破壊する、どうしようもない罪なのだ。
お前だけに向いているものではない。お前は孤独から脱した。お前はそのために火を放った。
それを思い出し給え。その時お前の転機が来る。




ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

ENo.687 音和姉弟 とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました
















ドレイク教授(370) に 5 PS 送付しました。
かぎ(170) から 毛 を受け取りました。
領域LV を 10 DOWN。(LV15⇒5、+10CP、-10FP)
具現LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
筒井 粋(288) の持つ ItemNo.8 パンの耳 から料理『あつあつパン耳グラタン』をつくりました!
ドレイク教授(370) により ItemNo.7 花の護り に ItemNo.9 毛 を付加してもらいました!
⇒ 花の護り/装飾:強さ40/[効果1]強靭10 [効果2]回復10 [効果3]-
都月桐胡(397) とカードを交換しました!
注射器 (ヒール)

プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
プロテクション を研究しました!(深度1⇒2)
プロテクション を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:タライ を習得!
ローバスト を習得!
クリエイト:ウィング を習得!
召喚強化 を習得!
クリエイト:バトルフラッグ を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
サモン:ビーフ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は 藍鉄鉱 を入手!
スズヒコ(244) は 孔雀石 を入手!
グノウ(909) は 平石 を入手!
迦楼羅(931) は 藍鉄鉱 を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
スズヒコ(244) は 牙 を入手!
迦楼羅(931) は 針 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 歩行小岩 がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに オオヤマアラシ が微笑を浮かべて近づいてきます。



チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 R-9(森林)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- フェデルタ(165) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- スズヒコ(244) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- グノウ(909) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- 迦楼羅(931) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














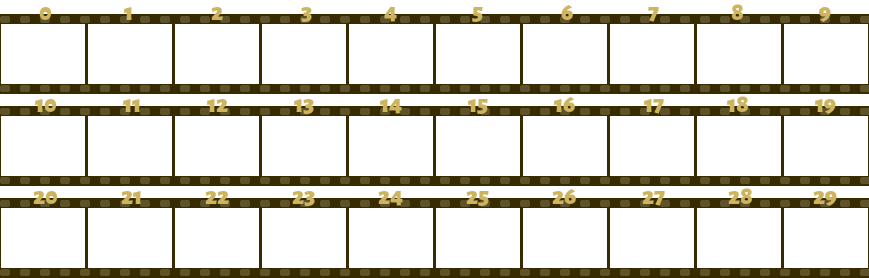







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




俺はいつも、笑い声とともに生きてきたと言っても過言ではなかっただろう。
純粋な笑顔。嘲笑の声。ひそひそと笑う声。繕った笑い。
もし俺が、もう少しだけ冷酷で、もう少しだけ心を強く持てていたのなら、そもそもこのような記述もまた、必要ないのである。
端的に述べるのなら、俺のいた環境は恵まれていなかった、という方に入るだろう。どれだけ酷かったか、という点については、各々の主観が大きく、己が体感したものを最も酷いものだと感じるものだろうから、割愛する。ただ、俺は常々思うのだ。死んでから動き続けてなお、思うのだ。己の可能性について。己の家を継げた可能性、研究者として大成できていた可能性、それらに思いを馳せなかった日はあっても、月や年という単位まで伸ばしてしまえば、いつもどこかで思考している。二度と叶わない願いだと言うのに、だ。
これは『記録』のつもりで書いている。俺は、俺の成せなかった数多のことを忘れてはならず、同時にそれらをいい加減に扱ってもならない。それは俺を成長させたものであることに間違いはないし、道を踏み外した結果に今の俺が存在している。
故に、再び道を踏み外すようなことがあってはならない。その時は、己の過ちを認め、然るべき処置を取るべきである。
息苦しい話が続くが、俺はきちんとこの話をしたことがなかったと思う。故に、記す。いつかの自分に丸投げするというのも変な話だが、向き合うことに未だにストレス性だろう身の強張りを感じたり、鼓動が速くなったり、そういうことがあるのだ。一度その拍動を完全に止めた身のはずなのに、奇妙なものである。
まず、俺は、一言で言うなら田舎の因習集落の生まれである。因習集落、という言い方は正しくない気もするが、俺が大学の友人たちに、自分の出自を話して最も言われた言葉が『因習村』である。故にそのように記載する。
俺の出身の世界である双極界『バイポーリス』(以下、当該世界と記す)は、何らかの要因で、全く文化・自然体系の異なる二つの世界が融合し、その文化・自然体系はそれぞれがほぼ独立したまま発展を遂げてきた世界である。自然の坩堝『ネイトリエ』、科学の極点『シエンティカ』。これら二つの対極にある世界が何故融合を果たしたのか、そしてその文化がほぼ混ざり合うことなく、互いに侵攻をすることもなく、それぞれで独立しているかというのは大変興味深い現象だが、あいにく専門ではない。何にせよ、当該世界のネイトリエ側、そしてその極地と呼ばれる『世界の果て』に限りなく近い、神を信仰し、魔術を呼吸のように行使する人間が多数暮らしていたカントカムイと呼ばれている地域が、俺の生まれた地である。
家を継げなかった人間であり、さらに言うと界境を渡ったため、ネイトリエの記述もシエンティカの記述も、不確かで古い情報になってしまう。しかし俺が俺のままであるなら、いつか『最後に一度くらいは故郷に帰りたい』と言い出さない保証もない。俺はどこまでも非情にはなりきれず、だからあのとき指輪を処分できなかった。娘が生きていれば、今持っているはずである。あの子はとにかく気が強いから、俺と違ってどこへ行ってもやっていけるだろう。
まず、俺の出身の集落の周辺では、信仰がほぼ全てであった。神に祈りを捧げ、神の声を聞く人間がいて、神のために捧げる舞があり、神のために捧げる刃があった。このどれかになれなければ、穀潰しだ。求められることは、早急に子を成し、次の代を育てることだった。
集落を出てから分かったことだが、魔力量は保有遺伝子によって大きく左右されるらしく、俺は本当にあの集落に向いていなかった、というのは、大変大きな収穫だった。鍛錬から引き離し、本を与えてくれた父の慧眼に眼を見張るばかりである。
要するに、俺は自分の生まれた場所では出来損ないだったが、他の場所ならまだやれる芽があった。そう、俺の父は判断してくれた。恐らくもう生きていないだろうが、閉鎖的な環境にありながら、そのような判断ができる人物は大変貴重である。
さて、生まれる場所に恵まれなかった俺は、生きていく場所を変えることにした。界境越えは俺の生きていた時代から活発化し、特にシエンティカからの科学者が、ネイトリエの自然を調査しに来ていた。極地、と呼ばれるカントカムイ周辺にすら、だ。小さな子供がぽつぽつと零す疑問に、満面の笑顔で答えてくれた、名も知らぬ科学者のことを、俺は忘れないだろう。
だから、俺は家を出ることにした。父は止めなかったし、何も言わなかった。母は狂ったように俺を責め立てた。生き恥を晒すことになるだの、私がこの集落で生きていけなくなるだの、いろいろと言われたけれど、俺には関係ないことだ。俺が努めて自分の子の私物化をしないようにできたのは、このことがあってこそだと思っている。
生まれる場所が選べないのなら、生きる場所は選んでもいい。否、選ぶ権利がある。だから俺は、家を出ることを選んだ。
選択には責任が伴う。俺は、以降人生の全ての責任を、自分で抱えなければいけなくなった。成人すればいずれそうなるとは言っても、一人で歩かせるのにはまだ危ない歳の頃から。
ここまで記載しても、俺の人生は言うほど波乱ではないのでは、と思うことがある。けれども、人生は各々に固有のものが割り当てられ、各々に固有の感じ方がある。俺のことをかわいそうだと思える人もいるだろうし、俺のことを恵まれていると思わざるを得ない人もいる。世界というものはかように残酷な構造をしていて、簡単に人が死ぬかもしれないような場合もあれば、生きていることそのものが苦痛である場合もある。
この先誰かに出会った時、ひとつ呼吸を置いて、冷静になる必要がある。
自分の常識は絶対ではないということ。自分を卑下しないこと。自分の怒りに囚われ、そのままに行動しないこと。
郷に入っては郷に従え、という言葉がある。俺が何らかの力を行使するためには、どのみちある程度その世界に馴染まなければならない。だから、少し冷静になれる時間があれば、俺はきちんと把握ができるだろうし、十分な時間があったのなら、状況を打破する思考もできるだろう。理論上、そうなっている。
これを記載している時点では、自分の正気が失われることについて、あまり確証が持てないでいる。ただ、人間は“忘れる生き物”で、それを模倣している以上、記載は必要な作業だし、俺が正気を失って、人を食い殺したという事実もまた、記載されるべき事象である。
改めて思う。俺は、すっかりバケモノになってしまったのだと。けれどもどうせなら、せめて誇り高くありたい。俺は確かにこの身を、自分で選び取ったのだということを、忘れないようにしていたい。それが俺の成せた唯一の、下の娘に成せた唯一の、父親らしいことなのだ。
故にゆめゆめ忘れるな、俺はバケモノである以前に人間で、最善の選択の結果としてそうなってしまっただけの、一人の人間なのだ。

――吉野暁海。吉野暁海、吉野暁海!!
俺はお前を絶対に許さない。許したくない。お前という存在が、お前という存在がある限り、俺は永劫に苦しめられる。俺の鏡写しを語るな。何も知らない顔で生きていようとするな。何も知らない顔で、平和な生活を享受するな。俺が、俺がそこに至るまで、どれだけ苦労したと思っているんだ。お前には分かるまい。分かられてたまるか。何も分からないまま、侵略されて死んでしまえ。
フェデルタは「引きずられた」と言っていた。俺は何も思わなかった、ただ、俺は平凡な大学生で、フェデルタの――吉野俊彦の、兄。そういう舞台装置として、世界に組み込まれている。そのことだけを理解した。
見下すだけなら人の姿でも十分な獣が、“アケミちゃんは冗談も聞かないのか”と言ったようなことを言っていたのを、獣の戯言として処理できた。
つい先程まで出来ていたことがもうできない。イバラシティ。吉野暁海。凡庸な学生ではなく、努力もしない天才で、苦労があったとすれば“何の能力も持たなかったこと”で、尽く恵まれた、恵まれてしかいない、同じ目の色をした大学生。何にも縛られず、知識を求めることを許された、平和で恵まれた家庭に生きている一人の青年。
もし神がそこにいたのなら、間違いなくその喉笛を掻っ切っている。どうして何の制約もない、ただただ恵まれた姿がねじ込まれているのか。俺という人間に対する当てつけだろうか。
否。罪に対する罰だとでも言うのか。
罪?犯した覚えなんてない。罰?生きている間にこれでもかと、浴びせるように与えてきたくせに。神なんて元から信じていなかったけれど、都合のいいときにだけ信じるような趣味も、思想も、持ち合わせてはいなかった。
それ以前に、ただただ怒っていた。
俺が何をしたと言うのか。異形と罪人と負の空気しかない、枯れた世界に落とされるようなことを、何をしたというのか。いつ。どのようにして。明確な証拠を求める。
そうだ。確かに俺たちには司法があったはずなのに、何もしてくれやしなかった。言葉をあげれば物理的にあの場所を焼き払うこともなかった。それが罪だとでも言うのか?
そこまで俺を追い詰めた人間たちへの罰は?
それらを棚に上げて俺を罰するのか?集団で叩いた側には何もなくて、人のいないタイミングを見計らって、可燃性の薬品を並べてから火を放った俺の方が悪いと言われる所以はどこにある?
――それが通るんだったら、世界なんて本当にクソだ。
クソ。クソ。クソッタレ。クソしかいない世界なんて滅んでしまえ。アンジニティなんていうクソッタレの世界から、まず、死ねばいい。元からどうせ、罪人の掃き溜めなんだから、なくたって困りやしないのだ。罪人は疾く死ねばいい。流刑にするような情けなんか与えずに殺せばいい。こんなところがあったから、こんなところがあるから、こんなことになって、俺たちは、俺は、
……何を邪魔されたんだっけ?
歩む獣は、それを人に合わせなければならなかった。
己のみなら大足ひとつで済むものを、頻繁に待ったり座ったり、時には首根っこ咥えて走ったり、そうすることは悪くないと思っていた。
何より、獣にはこの場所は快適であった。ひりついた空気。闘争、逃走、そして闘争。奇っ怪な空も何も気にならない。
「……」
“己”は、それを良しとしてはいないようだった。負の感情を常に胸の内に抱き、怒りの噴煙は常に立ち上り、どうしようもなく変質している。
気づき給え、“己”よ。その時が来ない限り、絶対に己はこの大地から逃れることはできまい。
残り三十時間を切ったうちに、気づかねばならない。その時初めて、この怒りたる己は、お前にようよう従おう。
己は“己”の思考も何も分からぬが、己はお前の怒りである。故に、こうしてお前に従うのだ。お前は正当に怒っているからだ。
けれどもゆめゆめ忘れるな、己は『怒っていい』が、『狂っていい』わけではない。
それを忘れている限り、お前は永遠に罪人だ。理知を忘れて狂うこと、それそのものが罪なのだ。お前という人間が築いてきた何もかもを破壊する、どうしようもない罪なのだ。
お前だけに向いているものではない。お前は孤独から脱した。お前はそのために火を放った。
それを思い出し給え。その時お前の転機が来る。




ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.687 音和姉弟 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
「ミグー、次は勝てるといいね」 |





痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
TeamNo.322
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 2 増加!
影響力が 2 増加!



ドレイク教授(370) に 5 PS 送付しました。
かぎ(170) から 毛 を受け取りました。
| かぎ 「おれの毛じゃないからね」 |
領域LV を 10 DOWN。(LV15⇒5、+10CP、-10FP)
具現LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
筒井 粋(288) の持つ ItemNo.8 パンの耳 から料理『あつあつパン耳グラタン』をつくりました!
ドレイク教授(370) により ItemNo.7 花の護り に ItemNo.9 毛 を付加してもらいました!
⇒ 花の護り/装飾:強さ40/[効果1]強靭10 [効果2]回復10 [効果3]-
都月桐胡(397) とカードを交換しました!
注射器 (ヒール)

プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
プロテクション を研究しました!(深度1⇒2)
プロテクション を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:タライ を習得!
ローバスト を習得!
クリエイト:ウィング を習得!
召喚強化 を習得!
クリエイト:バトルフラッグ を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
サモン:ビーフ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は 藍鉄鉱 を入手!
スズヒコ(244) は 孔雀石 を入手!
グノウ(909) は 平石 を入手!
迦楼羅(931) は 藍鉄鉱 を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
グノウ(909) は 大軽石 を入手!
スズヒコ(244) は 牙 を入手!
迦楼羅(931) は 針 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 歩行小岩 がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに オオヤマアラシ が微笑を浮かべて近づいてきます。



チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 R-9(森林)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- フェデルタ(165) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- スズヒコ(244) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- グノウ(909) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- 迦楼羅(931) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
【PT2】LuckyStar
|




チナミ区 R-7
チェックポイント《廃ビル》
チェックポイント。チェックポイント《廃ビル》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《OWL》
黒闇に包まれた巨大なフクロウのようなもの。
 |
守護者《OWL》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.244
鈴のなる夢



ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
30 / 30
159 PS
チナミ区
D-2
D-2









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 異本の栞 | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 孔雀石 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV25)[防具]耐狂15(LV25)[装飾]放毒10(LV20) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 11 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 具現 | 15 | 創造/召喚 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 35 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 練3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 7 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| 練3 | サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]フィジカルブースター |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ |

PL / 紙箱みど