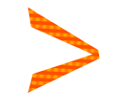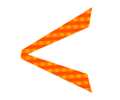<< 1:00~2:00





大日向女史曰く、『ワールドスワップ』はその幕を開けたそうだ。
一度声を掛けられたのなら造作もない、と言い切っていた彼女曰く、すでにワールドスワップの決戦場――世界のハザマ、その場所の情報も入手している、と。そして、その情報は更新され続けている、とも。
大日向深知は、積層構造世界の縦移動については、恐らく紫筑でも屈指の能力者で、知識人だ。故に意図的に“問題のない範囲で”事故を発生させ、双子に特有の入れ替わりも、擬似的に発生させることができる。そうして意図的な事故は発生し、『西村一騎の魂は持ち去られた』。釣り餌として放たれたそれを。目標は確かに確保している。理論的に説明できない部分で、西村一海はそう感じていた。
今回のターゲットである【哀歌の行進】は、分かりやすく説明すると『別の世界の西村一騎』だ。より説明の正確さを増すのなら、いち怪異が増長して、とある世界の西村一騎を殺害し、それに成り代わったものだ。
世界はいつだって可能性の塊でできている。無数に分岐しているうちのひとつの選択が、自分たちのいる紫筑に過ぎない。今回やってきた紫筑大学の六人チームが、揃わなかった世界。誰かが入学しなかった世界。誰かが途中で死んでしまった世界。誰かがそもそも生まれてこなかった世界。そういう無数の可能性と、常に隣り合わせ裏表、そんな状態で(少なくとも、紫筑大学のある世界は)成り立っている。
「……ふう」
大日向深知は、『可能性殺し』だ。
あらゆる積層世界の自分を殺し、可能性の芽を摘みまくっている。曰く『最強大天才はひとりで良い』、それだけの話だという。天才の考えることについていける気は全くしないが、その理論には、それなりに賛同せざるを得ない。
可能性を殺しておくことは、他の世界の衰退に繋がるかもしれない。だが、そもそもこちら側が侵略者だとしたら、『他の世界は衰退していたほうがいい』のだ。
大日向深知は侵略者だ。大日向深知は、自分が上に伸し上がるためなら、手段を選ばない。大日向深知は、“チビ女だとナメられるくらいなら、その相手を殺してしまう”。
「西村。“調子はどうだ”?」
「あまり芳しくないですね。」
時に、若いというだけで目をつけられることもある。時に、女だからというだけで目をつけられることもある。ようく、それを、識っている。
淡々と語られる言葉には、心配も何もない。ただ事実だけがあり、そこには何の感情も付随しない。そのように冷たくあることが能力で、だからこそ選ばれている。
【識り尽くす氷】西村一海は、意識的に感情を殺し、思考から感情を切り離し、何もかもを客観的に、己が即座に何も知らない第三者となり、そして全てを把握する。情報管理に特化した、あまり戦闘には向かない能力の持ち主だ。誰かをサポートするのなら、これ以上の適任はないとも言える。
「芳しくない、の内訳を聞こうか」
「はい。まず怪異【鈴のなる夢】が本格的に動き始めたようですね。近いうちに影響が吉野暁海に出ると思われます」
「想定の範囲内だ」
「次に、【哀歌の行進】ですが、恐らくこちらの手に気づいています」
「根拠は?」
たとえ血の繋がった、別の胎盤とはいえ腹の中から一緒だった、出てきた順番だけで上と下が決められた兄を、上司が躊躇いなく釣り餌に使おうとも、何も思わない。
それが最善だと、【識り尽くす氷】も言っている。
他の誰かが最善だったとしても、そうであることを選んだだろう。極限なまでに冷たくあることが責務で、それによって救われる何かがある。大日向深知はそう言った。温かくあるだけが、救いではないと。
「無意味な行動を取っています」
「どのように」
「釣り餌が何らかの形で当該世界に顕現することは想定されていました。恐らく御し易い子供の姿だろうというのも」
「そこまではその通りだ。では何が無意味だ?」
「連れ回して愛でています」
顎に手を当てて考え込み始めたところを見るに、真に想定外なのだろう。
“西村一騎”としての肉体が、明確に忌避感を示した。本来であれば、魂と肉体を何らかの方法で入れ替えた時、本来の肉体とのコネクションは消滅し、新しく充てがわれた肉体とコネクションを形成する。複数の肉体を同時に操れるのは、それこそが能力足りうる。例外として、血縁関係の間での入れ替えに限り、何の処置を施さなくても、僅かなコネクションが残る可能性がある。それは血縁関係が近ければ近いほど有意に多く発生し、通常のきょうだいと双子の中でも、さらに大きく有意差が出る。それを利用し、意図的に魂が入れ替わるレベルの世界間移動事故を発生させ、今に至っている。
魂を入れ替えているとき、本来の肉体の持ち主が仮初の肉体で何かを感じた場合、それを受け手側は、基本的に客観的な事実として受容する。肉体に見合わない多すぎる情報は、神経細胞に不可逆的な破壊を催すからだ。情報処理能力に特化していたとしても推奨されない。
しかし、血縁関係(近ければ近いほど良い)の間に限ってはそうではない。特に一卵性双生児の場合、主観的な情報として処理したほうが良いケースも認められている。西村兄妹はあいにく二卵性のため、ごく僅かな情報のみを主観として受け取っている。それでも心底嫌だというのが伝わってきたのだから、相当なのだろう。
「何を受け取った?」
「忌避感です」
「ふむ……」
話を戻す。
今作戦で追いかけている『怪異』とは、“人間の尺に当てはまらないもの”全てを指す言葉だ。紫筑大学をはじめとした能力者養成機関に所属していない人間の能力者すら、その使い方を間違えた瞬間に『怪異』と呼ばれる。都合のいい討伐対象を表す言葉だ。
幸いにして【哀歌の行進】には憐憫の情を持つような一般的な人間性はなく、好奇心と破滅願望で動く。それが兄の本質であると言われたなら、一海に何も返す言葉はない。
「まあ、あれなら気づいて嫌がらせをするのも考慮できる知的レベルだ。下手な人間より人間らしい」
「私もそう思います」
「忌避感とはな。余程をしているのだろう、面白い。ボクだって、可能性狩りのときですらそんなことは思わなかった」
いずれにせよ、戦いは始まっている。それ以上、あるいはそれ以下の意味は持たない。
最終的に【哀歌の行進】に打撃を与え、最低でも一定の行動不能期間を与えることができれば、こちら側の勝ちだ。逆に言えば、紫筑大学という塊に行動不能の期間ができてしまえば、こちらの負けということになる。それを回避するため、“世界同士の侵略行為”などという大げさな事象の発生している場所を選んだのだ。
【哀歌の行進】も自分たちも、他の世界の住人だ。土着の人間ではなく、故にこの響奏の世界には正確に認められず、何らかの不具合が起こりうる。そのデメリットをメリットと捉え、積極的な侵略行為を行うのが、大日向深知を始めとする紫筑大学第四学群神秘研究科怪異対策類実務班だ。自分たちにデバフ、あるいはデメリットが発生する意味。土着ではない怪異を相手にするとき、“等しく相手にも何かしらのデメリットが発生している”。
大日向深知は『創峰大学』を構成するパーツのひとつと化し、学内から出られなくなった。西村一騎は西村一海の魂を抱えたまま、【識り尽くす氷】として機能するしかなくなった。他、まだ確認を取っていないが、全員に何かしらの影響が及んでいる。そのために自由行動の時間を取らせ、好き勝手に遊び回るように指示している。それが戦略なのだ。
「……何故だと思いますか」
「何故、とは?」
「いえ。兄にわざわざ忌避感を与える理由が分からなかったもので」
今、わざわざ分かる形で、デメリットの究極系とも言える、魂だけで目の前に顕現し(おそらく仮初の肉体を得)、好き勝手に愛でられている状態として扱われているらしい、兄のことを思っても、本当に何も思わない。能力抜きで。自業自得という感じがしてならないのだ。
「ふむ。それは簡単だ。魂のみで現れたのなら、まずは正気を削ることが選択肢になるからだ」
「ですね。肉体が保持されている以上、強制的に呼び戻すことはいつでも可能です」
「何が行われているかを調べる手段は今はないが……春には準備できよう。焦ることはない。ボクたちは明確に勝利への道を歩いている」
どこかで何かがもうあって、その結果としてその選択をしている、ということも十分考えられる、と、深知は付け加えた。
別の世界の西村一騎が【哀歌の行進】と接触済みで、そこからそのような行動を取るに至り、そうすることが効率的に精神にダメージを与えることができる、と知っている場合。総合的に見て不利にはならないが、情報は精査する必要がある。
『可能性殺し』に明確に意味があるのは、これらの事由からだ。『怪異』と呼ばれるものの多くは、かなり自由に世界を移動し、行き来し、他の可能性と接触する。その結果として強度の高い『怪異』となりかねない。なら、そうなる前に全ての可能性を摘んでしまえ――そう、『可能性殺し』の思考は、限りなく『怪異』に近い。だから、常人にはとても出来ない。始めから狂っているか、確固たる意思を持った狂人か、偶然そうなってしまったか、そのどれかだ。
「……明確に、には賛同しかねます」
「ほう」
「理由なら、まさにずばり、それですよ」
大日向のパソコンの画面に表示されているのは、一人の創峰大学の学生の情報だった。
吉野暁海。
現創峰大学第二学群生物学科二年次、来年度三年次に進学予定。
取得単位数問題なし(超過気味だが生物学科に特有の範囲内である)。成績良好(上位十パーセント圏内)。
特筆事項、無能力者。
「何故そう思う?あえて問おう」
「あなた無駄なことが好きなんですか?それが【鈴のなる夢】。無能力者であることがでっち上げの、種々の怪異を紐付けた『怪異』だということが判明しています。――つまり、土着の人間ではない。私たちに協力させることを念頭に置いている現状の作戦では、何らかの不具合が生じるのではないかというのは、相当前から言ってきたつもりでしたが」
「冷たいなあ。だが君はそれでいい。そうあることが君に与えられた仕事だ」
大日向はディスプレイのモニターアームを曲げ、画面を西村の方に向けた。
表示されている学生の無帽の写真にカーソルが乗る。表示されたメニュープルダウンから最新のデータを表示されると、そこには、左側頭部から捻れた形状の角が生えている姿が映っていた。整った笑顔が、僅かな不安に陰っている。
「君たちが事前に取ってきたデータの通りなら、これはボクたちと同類の生き物だ。そういう生き物の御し方は、ボクらが一番知っている」
吉野暁海に異能が発現し、そしてそれが『侵略開始』の合図であることを、どうしてか大日向深知は知っていた。そして、その発現した異能――情報を手繰り寄せ、理解できる範囲で発現、攻撃や支援に転用する――【知識の坩堝・ご都合主義】とほぼ同様のものとして、“今は”認識されているものを、自らの手の届くものとするため、第四学群にやってくる。
「【深閉架書庫の錨】(ダイビングライブラリーアンカー)だ。それに気づいたとき、間違いなく【鈴のなる夢】はボクらにコンタクトを取ってくる。何故か?それは簡単だ。」
【知識の坩堝】系が、誰かの力で得られた知識、己の理解している知識をベースにするタイプの異能で、コツさえ掴めば誰にでも取り回せるものだとしたら、固有名詞のついたこの能力は、それとは全く異なる機序を取る。
「知的好奇心だ!好奇心は猫どころではなく、世界だって殺す!」
そう高らかに言い上げる大日向深知を、西村は相変わらずの冷めた目で見ていた。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.426 アストロイェライ とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.889 さまよう夜風 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 厚切り肉のフシギ焼き を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









響鳴LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
迦楼羅(931) により ItemNo.7 美味しくない草 に ItemNo.8 ねばねば を合成実験してもらい、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
迦楼羅(931) により ItemNo.8 ねばねば に ItemNo.9 毛 を合成実験してもらい、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
迦楼羅(931) により ItemNo.7 美味しくない草 に ItemNo.9 毛 を合成実験してもらい、駄物 に変化することが判明しました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)
フェデルタ(165) により ItemNo.8 ねばねば から射程1の武器『ハードカバークロウ』を作製してもらいました!
⇒ ハードカバークロウ/武器:強さ35/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
ノジコ(456) により ItemNo.7 美味しくない草 から装飾『花の護り』を作製してもらいました!
⇒ 花の護り/装飾:強さ40/[効果1]強靭10 [効果2]- [効果3]-
筒井 粋(288) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『DHA配合フィッシュサンド』をつくりました!
シンヤ(167) の持つ ItemNo.7 パンの耳 から料理『粒の立った塩おにぎり』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.3 不思議な食材 から料理『不思議ふわふわいちご蒸しパン』をつくりました!
ランメイ(892) とカードを交換しました!
《イレイザー》 (イレイザー)

フィジカルブースター を研究しました!(深度0⇒1)
フィジカルブースター を研究しました!(深度1⇒2)
フィジカルブースター を研究しました!(深度2⇒3)
アブソーブ を習得!
ツインブラスト を習得!
☆イクステンション を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-8(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- グノウ(909) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――





























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




大日向女史曰く、『ワールドスワップ』はその幕を開けたそうだ。
一度声を掛けられたのなら造作もない、と言い切っていた彼女曰く、すでにワールドスワップの決戦場――世界のハザマ、その場所の情報も入手している、と。そして、その情報は更新され続けている、とも。
大日向深知は、積層構造世界の縦移動については、恐らく紫筑でも屈指の能力者で、知識人だ。故に意図的に“問題のない範囲で”事故を発生させ、双子に特有の入れ替わりも、擬似的に発生させることができる。そうして意図的な事故は発生し、『西村一騎の魂は持ち去られた』。釣り餌として放たれたそれを。目標は確かに確保している。理論的に説明できない部分で、西村一海はそう感じていた。
今回のターゲットである【哀歌の行進】は、分かりやすく説明すると『別の世界の西村一騎』だ。より説明の正確さを増すのなら、いち怪異が増長して、とある世界の西村一騎を殺害し、それに成り代わったものだ。
世界はいつだって可能性の塊でできている。無数に分岐しているうちのひとつの選択が、自分たちのいる紫筑に過ぎない。今回やってきた紫筑大学の六人チームが、揃わなかった世界。誰かが入学しなかった世界。誰かが途中で死んでしまった世界。誰かがそもそも生まれてこなかった世界。そういう無数の可能性と、常に隣り合わせ裏表、そんな状態で(少なくとも、紫筑大学のある世界は)成り立っている。
「……ふう」
大日向深知は、『可能性殺し』だ。
あらゆる積層世界の自分を殺し、可能性の芽を摘みまくっている。曰く『最強大天才はひとりで良い』、それだけの話だという。天才の考えることについていける気は全くしないが、その理論には、それなりに賛同せざるを得ない。
可能性を殺しておくことは、他の世界の衰退に繋がるかもしれない。だが、そもそもこちら側が侵略者だとしたら、『他の世界は衰退していたほうがいい』のだ。
大日向深知は侵略者だ。大日向深知は、自分が上に伸し上がるためなら、手段を選ばない。大日向深知は、“チビ女だとナメられるくらいなら、その相手を殺してしまう”。
「西村。“調子はどうだ”?」
「あまり芳しくないですね。」
時に、若いというだけで目をつけられることもある。時に、女だからというだけで目をつけられることもある。ようく、それを、識っている。
淡々と語られる言葉には、心配も何もない。ただ事実だけがあり、そこには何の感情も付随しない。そのように冷たくあることが能力で、だからこそ選ばれている。
【識り尽くす氷】西村一海は、意識的に感情を殺し、思考から感情を切り離し、何もかもを客観的に、己が即座に何も知らない第三者となり、そして全てを把握する。情報管理に特化した、あまり戦闘には向かない能力の持ち主だ。誰かをサポートするのなら、これ以上の適任はないとも言える。
「芳しくない、の内訳を聞こうか」
「はい。まず怪異【鈴のなる夢】が本格的に動き始めたようですね。近いうちに影響が吉野暁海に出ると思われます」
「想定の範囲内だ」
「次に、【哀歌の行進】ですが、恐らくこちらの手に気づいています」
「根拠は?」
たとえ血の繋がった、別の胎盤とはいえ腹の中から一緒だった、出てきた順番だけで上と下が決められた兄を、上司が躊躇いなく釣り餌に使おうとも、何も思わない。
それが最善だと、【識り尽くす氷】も言っている。
他の誰かが最善だったとしても、そうであることを選んだだろう。極限なまでに冷たくあることが責務で、それによって救われる何かがある。大日向深知はそう言った。温かくあるだけが、救いではないと。
「無意味な行動を取っています」
「どのように」
「釣り餌が何らかの形で当該世界に顕現することは想定されていました。恐らく御し易い子供の姿だろうというのも」
「そこまではその通りだ。では何が無意味だ?」
「連れ回して愛でています」
顎に手を当てて考え込み始めたところを見るに、真に想定外なのだろう。
“西村一騎”としての肉体が、明確に忌避感を示した。本来であれば、魂と肉体を何らかの方法で入れ替えた時、本来の肉体とのコネクションは消滅し、新しく充てがわれた肉体とコネクションを形成する。複数の肉体を同時に操れるのは、それこそが能力足りうる。例外として、血縁関係の間での入れ替えに限り、何の処置を施さなくても、僅かなコネクションが残る可能性がある。それは血縁関係が近ければ近いほど有意に多く発生し、通常のきょうだいと双子の中でも、さらに大きく有意差が出る。それを利用し、意図的に魂が入れ替わるレベルの世界間移動事故を発生させ、今に至っている。
魂を入れ替えているとき、本来の肉体の持ち主が仮初の肉体で何かを感じた場合、それを受け手側は、基本的に客観的な事実として受容する。肉体に見合わない多すぎる情報は、神経細胞に不可逆的な破壊を催すからだ。情報処理能力に特化していたとしても推奨されない。
しかし、血縁関係(近ければ近いほど良い)の間に限ってはそうではない。特に一卵性双生児の場合、主観的な情報として処理したほうが良いケースも認められている。西村兄妹はあいにく二卵性のため、ごく僅かな情報のみを主観として受け取っている。それでも心底嫌だというのが伝わってきたのだから、相当なのだろう。
「何を受け取った?」
「忌避感です」
「ふむ……」
話を戻す。
今作戦で追いかけている『怪異』とは、“人間の尺に当てはまらないもの”全てを指す言葉だ。紫筑大学をはじめとした能力者養成機関に所属していない人間の能力者すら、その使い方を間違えた瞬間に『怪異』と呼ばれる。都合のいい討伐対象を表す言葉だ。
幸いにして【哀歌の行進】には憐憫の情を持つような一般的な人間性はなく、好奇心と破滅願望で動く。それが兄の本質であると言われたなら、一海に何も返す言葉はない。
「まあ、あれなら気づいて嫌がらせをするのも考慮できる知的レベルだ。下手な人間より人間らしい」
「私もそう思います」
「忌避感とはな。余程をしているのだろう、面白い。ボクだって、可能性狩りのときですらそんなことは思わなかった」
いずれにせよ、戦いは始まっている。それ以上、あるいはそれ以下の意味は持たない。
最終的に【哀歌の行進】に打撃を与え、最低でも一定の行動不能期間を与えることができれば、こちら側の勝ちだ。逆に言えば、紫筑大学という塊に行動不能の期間ができてしまえば、こちらの負けということになる。それを回避するため、“世界同士の侵略行為”などという大げさな事象の発生している場所を選んだのだ。
【哀歌の行進】も自分たちも、他の世界の住人だ。土着の人間ではなく、故にこの響奏の世界には正確に認められず、何らかの不具合が起こりうる。そのデメリットをメリットと捉え、積極的な侵略行為を行うのが、大日向深知を始めとする紫筑大学第四学群神秘研究科怪異対策類実務班だ。自分たちにデバフ、あるいはデメリットが発生する意味。土着ではない怪異を相手にするとき、“等しく相手にも何かしらのデメリットが発生している”。
大日向深知は『創峰大学』を構成するパーツのひとつと化し、学内から出られなくなった。西村一騎は西村一海の魂を抱えたまま、【識り尽くす氷】として機能するしかなくなった。他、まだ確認を取っていないが、全員に何かしらの影響が及んでいる。そのために自由行動の時間を取らせ、好き勝手に遊び回るように指示している。それが戦略なのだ。
「……何故だと思いますか」
「何故、とは?」
「いえ。兄にわざわざ忌避感を与える理由が分からなかったもので」
今、わざわざ分かる形で、デメリットの究極系とも言える、魂だけで目の前に顕現し(おそらく仮初の肉体を得)、好き勝手に愛でられている状態として扱われているらしい、兄のことを思っても、本当に何も思わない。能力抜きで。自業自得という感じがしてならないのだ。
「ふむ。それは簡単だ。魂のみで現れたのなら、まずは正気を削ることが選択肢になるからだ」
「ですね。肉体が保持されている以上、強制的に呼び戻すことはいつでも可能です」
「何が行われているかを調べる手段は今はないが……春には準備できよう。焦ることはない。ボクたちは明確に勝利への道を歩いている」
どこかで何かがもうあって、その結果としてその選択をしている、ということも十分考えられる、と、深知は付け加えた。
別の世界の西村一騎が【哀歌の行進】と接触済みで、そこからそのような行動を取るに至り、そうすることが効率的に精神にダメージを与えることができる、と知っている場合。総合的に見て不利にはならないが、情報は精査する必要がある。
『可能性殺し』に明確に意味があるのは、これらの事由からだ。『怪異』と呼ばれるものの多くは、かなり自由に世界を移動し、行き来し、他の可能性と接触する。その結果として強度の高い『怪異』となりかねない。なら、そうなる前に全ての可能性を摘んでしまえ――そう、『可能性殺し』の思考は、限りなく『怪異』に近い。だから、常人にはとても出来ない。始めから狂っているか、確固たる意思を持った狂人か、偶然そうなってしまったか、そのどれかだ。
「……明確に、には賛同しかねます」
「ほう」
「理由なら、まさにずばり、それですよ」
大日向のパソコンの画面に表示されているのは、一人の創峰大学の学生の情報だった。
吉野暁海。
現創峰大学第二学群生物学科二年次、来年度三年次に進学予定。
取得単位数問題なし(超過気味だが生物学科に特有の範囲内である)。成績良好(上位十パーセント圏内)。
特筆事項、無能力者。
「何故そう思う?あえて問おう」
「あなた無駄なことが好きなんですか?それが【鈴のなる夢】。無能力者であることがでっち上げの、種々の怪異を紐付けた『怪異』だということが判明しています。――つまり、土着の人間ではない。私たちに協力させることを念頭に置いている現状の作戦では、何らかの不具合が生じるのではないかというのは、相当前から言ってきたつもりでしたが」
「冷たいなあ。だが君はそれでいい。そうあることが君に与えられた仕事だ」
大日向はディスプレイのモニターアームを曲げ、画面を西村の方に向けた。
表示されている学生の無帽の写真にカーソルが乗る。表示されたメニュープルダウンから最新のデータを表示されると、そこには、左側頭部から捻れた形状の角が生えている姿が映っていた。整った笑顔が、僅かな不安に陰っている。
「君たちが事前に取ってきたデータの通りなら、これはボクたちと同類の生き物だ。そういう生き物の御し方は、ボクらが一番知っている」
吉野暁海に異能が発現し、そしてそれが『侵略開始』の合図であることを、どうしてか大日向深知は知っていた。そして、その発現した異能――情報を手繰り寄せ、理解できる範囲で発現、攻撃や支援に転用する――【知識の坩堝・ご都合主義】とほぼ同様のものとして、“今は”認識されているものを、自らの手の届くものとするため、第四学群にやってくる。
「【深閉架書庫の錨】(ダイビングライブラリーアンカー)だ。それに気づいたとき、間違いなく【鈴のなる夢】はボクらにコンタクトを取ってくる。何故か?それは簡単だ。」
【知識の坩堝】系が、誰かの力で得られた知識、己の理解している知識をベースにするタイプの異能で、コツさえ掴めば誰にでも取り回せるものだとしたら、固有名詞のついたこの能力は、それとは全く異なる機序を取る。
「知的好奇心だ!好奇心は猫どころではなく、世界だって殺す!」
そう高らかに言い上げる大日向深知を、西村は相変わらずの冷めた目で見ていた。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.426 アストロイェライ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.889 さまよう夜風 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
以下の相手に送信しました



 |
グノウ 「……これは、思っていたよりも厳しいかもしれません」 |
 |
グノウ 「ところで坊ちゃん、野菜とか残そうと考えていませんよ――」 |
 |
グノウ 「――ね?」 |
 |
(ぬいぐるみを抱きしめて大人達から少し距離を置いている。) |
ItemNo.6 厚切り肉のフシギ焼き を食べました!
| スズヒコ 「(ちょっとしょっぱいな……)」 |
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





ミナモニティ
|
 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|



響鳴LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
迦楼羅(931) により ItemNo.7 美味しくない草 に ItemNo.8 ねばねば を合成実験してもらい、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
迦楼羅(931) により ItemNo.8 ねばねば に ItemNo.9 毛 を合成実験してもらい、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
迦楼羅(931) により ItemNo.7 美味しくない草 に ItemNo.9 毛 を合成実験してもらい、駄物 に変化することが判明しました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)
フェデルタ(165) により ItemNo.8 ねばねば から射程1の武器『ハードカバークロウ』を作製してもらいました!
⇒ ハードカバークロウ/武器:強さ35/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
| フェデルタ 「……ん、これ」 |
ノジコ(456) により ItemNo.7 美味しくない草 から装飾『花の護り』を作製してもらいました!
⇒ 花の護り/装飾:強さ40/[効果1]強靭10 [効果2]- [効果3]-
 |
ノジコ 「キレーなお花は誰だって大好きなものよね!」 |
筒井 粋(288) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『DHA配合フィッシュサンド』をつくりました!
シンヤ(167) の持つ ItemNo.7 パンの耳 から料理『粒の立った塩おにぎり』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.3 不思議な食材 から料理『不思議ふわふわいちご蒸しパン』をつくりました!
ランメイ(892) とカードを交換しました!
《イレイザー》 (イレイザー)

フィジカルブースター を研究しました!(深度0⇒1)
フィジカルブースター を研究しました!(深度1⇒2)
フィジカルブースター を研究しました!(深度2⇒3)
アブソーブ を習得!
ツインブラスト を習得!
☆イクステンション を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-8(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- グノウ(909) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
TeamNo.322
|


ENo.244
鈴のなる夢



ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
17 / 30
28 PS
チナミ区
P-9
P-9









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 異本の栞 | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | - | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 30 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 6 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]マナポーション |

PL / 紙箱みど