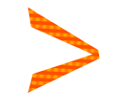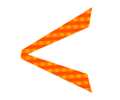<< 1:00~2:00




『これは……?』
俊彦が呟いた声は驚きと戸惑いに僅かに震えている。
あたり一面の炎。
真っ赤に染まる視界の中に揺らめく影で、どうやら家の中だということが辛うじてわかる。
炎が燃え広がる中にぽつん、と一人。何故こ
んな所に放り込まれたのかもわからぬままに
出口を探して歩くけれども、見つからない。そうしているうちに、焼け朽ちた柱が倒れてきて――

燃え盛る部屋に一人でいる夢なんて洒落にもならない。そんなことを思いながらゆっくりと体を起こした。
「なんであんな夢見たんだろう……」
呟きながら、考えを巡らせる。夢は、何かを伝えるなんて言葉があった気がして、だとしたら、これは何かの警告だったりするのだろうか。
「異能の使いすぎ……?」
俊彦にとって思い当たる部分と言えばその程度だ。じっと、両手を見つめる。
(……この力が使えたのはいつからだったかな)
俊彦が小学校四年生の時だ。なんの拍子で出たのかまでは忘れてしまったけど、突然指先に火が点った事で異能に気付いた。
両親はすぐに、異能の扱い教わりなさい、と異能専門のスクールに俊彦を通わせた。
人並みかそれよりは少し苦手だと評価されたが一年くらいで、もうスクールに通わなくて大丈夫と言われた。
(とはいえ、火を出す力なんてそうそう使う機会もないんだよな……それに、)
『じゃあ、このろうそく! 火つけれる?』
無邪気に笑う兄にかっこいいところが見せたかった。スクール卒業を喜ぶ兄からの課題をこなそうと、俊彦はろうそくに手を掲げた――
「……あれは、ひどかったよな」
結果を言ってしまえばそれに失敗して、兄は軽い火傷をおった。今は跡も無いくらいに完治しており、笑い話のひとつになってはいるのだが。
俊彦の中ではあまり笑える話ではない。この力は、容易に人を傷付ける力で、自分の大切な、守りたい人を確かに傷付けたという事実だけが胸の中に残り続けた。
この件もあって、俊彦は異能を使うことが殆んどなくなった。変に絡まれた時に脅しに使う程度はあったが、直接何かに向けて使うことは無かった。
「……」
ベッド脇にある目覚まし時計を見れば、まだ真夜中だった。けれども、すぐに寝直す気にもなれなくて静かにベッドをおりて、部屋を出るとキッチンへと向かう。
家族は眠っているので極力音を立てないように気を付けながら、コップに水を汲んで飲み干した。
静かな夜は少しだけ不安になる。もしかしたら、音もなく侵略者が近付いているのかもしれない。
夢なのか現実なのかもわからない“侵略者がやって来る”というあの言葉。冗談だと笑う者もいると理解したうえで、俊彦にはどうしてもそれを冗談で済ませる事は出来ない。
じっと、両手を見る。
自分には、守る力がある筈なのだ。この力は、誰かを傷付けるけれども、誰かを傷付けることで守れる事もある筈だと。
兄を傷付けた日から、向き合うことをやめていた異能と再び向き合った。今度はもっと、真剣に、本気で、この力で誰かを守るのだという強い気持ちで――
―――
――
―
「っ、……くそ、」
フェデルタは頭を軽くおさえながら、流れ込んできた吉野俊彦の記憶に悪態をついた。
煙草に手を伸ばしながら辺りを見る。この記憶の流入で足を止めてしまったので他のメンバーとは少し距離が空いていたが、追い付く範囲だ。咥えた煙草に火を付けながら、歩き始めた。
ゆっくりと肺に煙を吸い込んでから、細く長く吐きだせば、少しだけ気が紛れる。
吉野俊彦が見ていた夢には覚えがある。あれは、間違いなく自分の記憶だ。
あの少年と自分がやはり同じ存在であることを認めざるを得ない。そして、あのに焼かれた記憶がいつまで経っても消えることはない、魂にすら焼き付いているという事実も。
「しかし、参ったな……」
フェデルタは、煙と共に言葉を吐き出す。
最初に流れてきた大量の、吉野俊彦を形成するために生まれたあらゆる架空の記憶の奔流に比べれば、たかだか半月と少し程度の記憶は強く自我を保てば流されないが、これが一時間置きにくるというのは、ある種の拷問だ。
今は問題なくても疲弊すればまた、自分が何者か倒錯する可能性は捨てきれない。
何かしらの対策をしなければならないのだろうが、そうそうすぐ思い付く筈もなかった。
はあ、と重いため息を吐き出せば咥えていた煙草が一気に灰になって流れてしまった。
チッ、と大きく舌打ちをすれば新しいのを咥える。
力の調節が上手くいかない時が増えた。そもそも、魔法や異能力といったものへの適正が無く、この力が炎でなければとっくの昔に力に食われている、と言われたことがある。
唯一、そこそこ適正があったのが炎であったというだけで、ここまで自分を保てていたのだ。
この身体を切り刻んで溢れるのは血じゃなくて、煮えたぎる炎でかもしれない。
(あと、もう少しなんだ)
乾いた地面を踏み締める。まだ、人としての形を保っていることを確かめる。
吉野俊彦に流されるわけにも、身の内の炎に喰われる訳にもいけない。
その為に何か、そう、何か自分が自分である証拠でも残せたら……。
「……」
フェデルタはハッとした瞬間にすっかり火をつけ忘れていた煙草を地面に落としてしまった。それを拾うこともせず、思案する。
動いていた足がもう一度止まった。
単純な思い付きだと思うが、試してみる価値はあるかもしれない。
咲良乃スズヒコのように、自らを書き記す事を。
今、自分の中に彼の一部があることはわかっている。彼に喰われてから生き返る時に、一部を取り込んだものが、ずっとある。
そこを意識して、取り出すことが出来ればあるいは。
「……」
軽く意識をした程度でそこに辿り着ける気配は無い。小さく息を吐いて、止まっていた歩を進める。時間は多く無いがゼロではない。今は、合流を優先した方がいいだろう。小走りに先へと進む。
地面に取り残された煙草が、風でころころとどこかへと転がって行った。



ENo.244 スズヒコ とのやりとり

ENo.261 暮泥 唯 とのやりとり

ENo.360 瑞稀 とのやりとり

ENo.452 魄角 とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.912 愛夢 とのやりとり

ENo.1039 オーディオル とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 不思議な食材 を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。









制約LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
魔術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
モドラ(730) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『まじないセスタス』を作製しました!
スズヒコ(244) の持つ ItemNo.8 ねばねば から射程1の武器『ハードカバークロウ』を作製しました!
ノジコ(456) の持つ ItemNo.8 毛 から射程2の武器『みずいろトイカメラ』を作製しました!
グノウ(909) により ItemNo.5 着なれたコート に ItemNo.7 吸い殻 を付加してもらいました!
⇒ 着なれたコート/防具:強さ35/[効果1]防御10 [効果2]火纏10 [効果3]-/特殊アイテム
シュリ(1290) とカードを交換しました!
念道波 (ショックウェイブ)

五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度1⇒2)
五月雨 を研究しました!(深度2⇒3)
チャージ を習得!
デストロイ を習得!
イレイザー を習得!
火の祝福 を習得!
☆獄炎陣 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





スズヒコ(244) に移動を委ねました。
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-8(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- グノウ(909) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――





























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



『これは……?』
俊彦が呟いた声は驚きと戸惑いに僅かに震えている。
あたり一面の炎。
真っ赤に染まる視界の中に揺らめく影で、どうやら家の中だということが辛うじてわかる。
炎が燃え広がる中にぽつん、と一人。何故こ
んな所に放り込まれたのかもわからぬままに
出口を探して歩くけれども、見つからない。そうしているうちに、焼け朽ちた柱が倒れてきて――

燃え盛る部屋に一人でいる夢なんて洒落にもならない。そんなことを思いながらゆっくりと体を起こした。
「なんであんな夢見たんだろう……」
呟きながら、考えを巡らせる。夢は、何かを伝えるなんて言葉があった気がして、だとしたら、これは何かの警告だったりするのだろうか。
「異能の使いすぎ……?」
俊彦にとって思い当たる部分と言えばその程度だ。じっと、両手を見つめる。
(……この力が使えたのはいつからだったかな)
俊彦が小学校四年生の時だ。なんの拍子で出たのかまでは忘れてしまったけど、突然指先に火が点った事で異能に気付いた。
両親はすぐに、異能の扱い教わりなさい、と異能専門のスクールに俊彦を通わせた。
人並みかそれよりは少し苦手だと評価されたが一年くらいで、もうスクールに通わなくて大丈夫と言われた。
(とはいえ、火を出す力なんてそうそう使う機会もないんだよな……それに、)
『じゃあ、このろうそく! 火つけれる?』
無邪気に笑う兄にかっこいいところが見せたかった。スクール卒業を喜ぶ兄からの課題をこなそうと、俊彦はろうそくに手を掲げた――
「……あれは、ひどかったよな」
結果を言ってしまえばそれに失敗して、兄は軽い火傷をおった。今は跡も無いくらいに完治しており、笑い話のひとつになってはいるのだが。
俊彦の中ではあまり笑える話ではない。この力は、容易に人を傷付ける力で、自分の大切な、守りたい人を確かに傷付けたという事実だけが胸の中に残り続けた。
この件もあって、俊彦は異能を使うことが殆んどなくなった。変に絡まれた時に脅しに使う程度はあったが、直接何かに向けて使うことは無かった。
「……」
ベッド脇にある目覚まし時計を見れば、まだ真夜中だった。けれども、すぐに寝直す気にもなれなくて静かにベッドをおりて、部屋を出るとキッチンへと向かう。
家族は眠っているので極力音を立てないように気を付けながら、コップに水を汲んで飲み干した。
静かな夜は少しだけ不安になる。もしかしたら、音もなく侵略者が近付いているのかもしれない。
夢なのか現実なのかもわからない“侵略者がやって来る”というあの言葉。冗談だと笑う者もいると理解したうえで、俊彦にはどうしてもそれを冗談で済ませる事は出来ない。
じっと、両手を見る。
自分には、守る力がある筈なのだ。この力は、誰かを傷付けるけれども、誰かを傷付けることで守れる事もある筈だと。
兄を傷付けた日から、向き合うことをやめていた異能と再び向き合った。今度はもっと、真剣に、本気で、この力で誰かを守るのだという強い気持ちで――
―――
――
―
「っ、……くそ、」
フェデルタは頭を軽くおさえながら、流れ込んできた吉野俊彦の記憶に悪態をついた。
煙草に手を伸ばしながら辺りを見る。この記憶の流入で足を止めてしまったので他のメンバーとは少し距離が空いていたが、追い付く範囲だ。咥えた煙草に火を付けながら、歩き始めた。
ゆっくりと肺に煙を吸い込んでから、細く長く吐きだせば、少しだけ気が紛れる。
吉野俊彦が見ていた夢には覚えがある。あれは、間違いなく自分の記憶だ。
あの少年と自分がやはり同じ存在であることを認めざるを得ない。そして、あのに焼かれた記憶がいつまで経っても消えることはない、魂にすら焼き付いているという事実も。
「しかし、参ったな……」
フェデルタは、煙と共に言葉を吐き出す。
最初に流れてきた大量の、吉野俊彦を形成するために生まれたあらゆる架空の記憶の奔流に比べれば、たかだか半月と少し程度の記憶は強く自我を保てば流されないが、これが一時間置きにくるというのは、ある種の拷問だ。
今は問題なくても疲弊すればまた、自分が何者か倒錯する可能性は捨てきれない。
何かしらの対策をしなければならないのだろうが、そうそうすぐ思い付く筈もなかった。
はあ、と重いため息を吐き出せば咥えていた煙草が一気に灰になって流れてしまった。
チッ、と大きく舌打ちをすれば新しいのを咥える。
力の調節が上手くいかない時が増えた。そもそも、魔法や異能力といったものへの適正が無く、この力が炎でなければとっくの昔に力に食われている、と言われたことがある。
唯一、そこそこ適正があったのが炎であったというだけで、ここまで自分を保てていたのだ。
この身体を切り刻んで溢れるのは血じゃなくて、煮えたぎる炎でかもしれない。
(あと、もう少しなんだ)
乾いた地面を踏み締める。まだ、人としての形を保っていることを確かめる。
吉野俊彦に流されるわけにも、身の内の炎に喰われる訳にもいけない。
その為に何か、そう、何か自分が自分である証拠でも残せたら……。
「……」
フェデルタはハッとした瞬間にすっかり火をつけ忘れていた煙草を地面に落としてしまった。それを拾うこともせず、思案する。
動いていた足がもう一度止まった。
単純な思い付きだと思うが、試してみる価値はあるかもしれない。
咲良乃スズヒコのように、自らを書き記す事を。
今、自分の中に彼の一部があることはわかっている。彼に喰われてから生き返る時に、一部を取り込んだものが、ずっとある。
そこを意識して、取り出すことが出来ればあるいは。
「……」
軽く意識をした程度でそこに辿り着ける気配は無い。小さく息を吐いて、止まっていた歩を進める。時間は多く無いがゼロではない。今は、合流を優先した方がいいだろう。小走りに先へと進む。
地面に取り残された煙草が、風でころころとどこかへと転がって行った。



ENo.244 スズヒコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.261 暮泥 唯 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||
ENo.360 瑞稀 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.452 魄角 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.912 愛夢 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||
ENo.1039 オーディオル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
グノウ 「……これは、思っていたよりも厳しいかもしれません」 |
 |
グノウ 「ところで坊ちゃん、野菜とか残そうと考えていませんよ――」 |
 |
グノウ 「――ね?」 |
 |
(ぬいぐるみを抱きしめて大人達から少し距離を置いている。) |
ItemNo.6 不思議な食材 を食べました!
| フェデルタ 「(食後の一服)」 |
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。





ミナモニティ
|
 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|



制約LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
魔術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
モドラ(730) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『まじないセスタス』を作製しました!
スズヒコ(244) の持つ ItemNo.8 ねばねば から射程1の武器『ハードカバークロウ』を作製しました!
ノジコ(456) の持つ ItemNo.8 毛 から射程2の武器『みずいろトイカメラ』を作製しました!
グノウ(909) により ItemNo.5 着なれたコート に ItemNo.7 吸い殻 を付加してもらいました!
⇒ 着なれたコート/防具:強さ35/[効果1]防御10 [効果2]火纏10 [効果3]-/特殊アイテム
 |
(無言で作業をし、無言で終わらせたものを返す) |
シュリ(1290) とカードを交換しました!
念道波 (ショックウェイブ)

五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度1⇒2)
五月雨 を研究しました!(深度2⇒3)
チャージ を習得!
デストロイ を習得!
イレイザー を習得!
火の祝福 を習得!
☆獄炎陣 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





スズヒコ(244) に移動を委ねました。
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-8(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- グノウ(909) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
TeamNo.322
|


ENo.165
喰らい尽くす炎



既知設定等大歓迎です。お友達ほしい。
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校1年2組
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは剣道をやっていたが、今は部活動などはせずにたまに自分の住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校1年2組
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは剣道をやっていたが、今は部活動などはせずにたまに自分の住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
17 / 30
28 PS
チナミ区
P-9
P-9










| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 粗削りのナイフ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 着なれたコート | 防具 | 35 | 防御10 | 火纏10 | - | |
| 6 | 黄鉄鉱 | 素材 | 15 | [武器]麻痺10(LV20)[防具]反光10(LV25)[装飾]光纏10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| 練2 | フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| 練3 | デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 |
| 練1 | クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 |
| フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| デストロイ | 5 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
| 練1 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 獄炎陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど獄炎LV増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]プリディクション | [ 1 ]アジャイルフォーム | [ 1 ]アラベスク |
| [ 3 ]五月雨 | [ 1 ]クリエイト:バトルフラッグ |

PL / カミヤキサラ