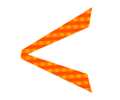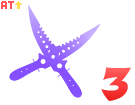<< 1:00~2:00




「あ、オーナー」
思わず口にしてしまってから、しまった、とボルドールは思った。
白髪に青いサングラスという派手ないで立ちのその男がボルドールの声に顔を上げた。彼はそれまで話をしていた自分の連れらしい青年と、ボルドールの同行者であるふみに一声かけてから、トコトコとボルドールの方にやってきた。
そうして、こちらの顔をまじまじと見て首を傾げてから。
「……もしかして、巌くん?」
そう言ってのけた。
本来の姿であるボルドールと、イバラシティ住民に偽装している七色巌。髪や肌の色、種族といった違いはあれど、実のところ顔立ちはほぼ同じだ。
イバラシティで日常的に接触している相手であれば、少し目を凝らせば特定できてしまう程度には。
ボルドールも、自分から声をかけてしまった段階でほぼ諦めていた。黙っているつもりだったのにそうしてしまったのは「七色巌」としての彼が勝手に喋ったからだ。ボルドールと巌は恐らく、種族や育ちといった部分を除いた、魂の性質とも言うべき部分が非常に似通っている。
だからこの時も、
「……うっス」
と、まるで七色巌本人のような返事を返してしまったのだった。
「いやあびっくりだね。巌くんがホントはボルドールくんっていうタコさんで、しかもアンジニティの人だったなんて。ワールドスワップ恐るべしって感じ……」
しみじみと語るのは、巌のバイト先の喫茶店「喫茶はねやすめ」のオーナー、関盛誠哉。
丸いフォルムに整えた真っ白な髪に青いサングラス、鳥の翼を思わせる青いストールを纏った派手な男だ。巌は彼を初めて見た際、どこかのファッション雑誌の関係者か何かと思ったぐらいである。それも偽りの記憶ではあるが。
しかし実際には素性のよく分からない、のんびりとした喫茶店オーナーであった。彼の異能『バッジー』によって生み出されたインコ的存在が、彼の周囲を飛び回りながら囀っている。
「……ボルドールでいい。あんたが思ってるよりは年寄りだ」
「そう? まあ、それを言ったらぼくもおじいちゃんなんだけどねえ」
くすくすと笑うその容貌は若いが、確かに彼の態度はどことなく年寄りめいている。おじいちゃん、という言葉にボルドールは眉根を寄せた。
「あんたもアンジニティか? あんまりあっちと変わってるようにゃ見えねえが」
「いや、ぼくはイバラシティの住人だよ。まあ、外の世界から来たタイプだけど。移住してコレに巻き込まれたって感じ」
「……じゃあ、見た目が老けない異能も持ってるとか?」
「ううん、正真正銘の二十代。……んー、まあ、向こうじゃ覚えてないだろうし、教えちゃおうかな」
そう言って誠哉は、愉快そうに目を細めた。
「ボルドール、人間の二十歳とセキセイインコの二十歳、どっちがお年寄りだと思う?」
「インコだろ、そりゃ」
「でしょ?」
「……実はインコですとか言うなよ?」
「それがねえ、そうなんだよねえ」
けらけらと笑う、その声がまさに鳥の囀りそのものだったので、ボルドールは思わず目を瞬いた。
「『バッジー』の本当の効果は『人間に化ける』こと。この子たちはその副産物だね。ぼくの生命エネルギーが漏れ出したのを成形してる」
「……何でまた、人間のふりを?」
「ぼくの出身世界ではね、寿命より長生きした生き物は何らかの異能に目覚めることが多かったんだ。みんなは神通力とか呼んでたけど……ぼくの場合は、それが人間になることだったって訳だね」
そう言ってから、誠哉は「ただねえ」とため息をついた。
「そうなると色々トラブルになっちゃうんだよ。異能に目覚めた子は知性も人間並みになるから……だから、ぼくが働いてる組織はそう言う元動物だった子たちや、異能で迫害されたりしてる人たちを保護して、不自由なく暮らしていけるように支援をしてるんだ。イバラシティへの移住もその一環だったってわけ」
「じゃあ、『はねやすめ』は」
「イバラシティでの拠点のひとつだね。実は結構、関係者の人も来てるんだよ。あ、コレは他の人には内緒ね!」
誠哉がそんなことを言いながら口元に人差し指を立ててみせるので、ボルドールは思わず笑ってしまった。
「あっちじゃここのことは覚えてねえよ、安心しろ」
「そ、そう言えばそうだったね……」
気まずそうに頭を掻いていた誠哉だったが、不意に真面目な顔になって、ボルドールの方を見た。思いの外、鋭い目をしていた。
「そんな訳で、イバラシティを侵略されちゃうと困るんだけど……ボルドール、君はイバラシティ側に味方してるって聞いたよ。それは本当?」
「……まあ、そうだな。乗るつもりはない。だからあんたらと敵対する気はねえよ」
「……それなら、いいんだけど」
息を吐いた誠哉だったが、その表情がふ、と曇る。
「……全部終わって、イバラシティ側が勝ったら……巌くんは、君は、いなくなっちゃうのかな」
「……ほんとは居ねえ奴が間借りしてるんだ。そうなるわな」
「ねえ、ボルドール。ぼくが聞くのも、おかしいかもしれないんだけど」
誠哉が、人間にしか見えないその顔が、ボルドールを見つめて言った。
「……君は、それでいいの?」
ボルドールは、ただ曖昧に笑うことしかできなかった。



ENo.244 スズヒコ とのやりとり

ENo.426 アストロイェライ とのやりとり

ENo.1387 ノーヴァル とのやりとり

ENo.1388 墨染ふみ とのやりとり










制約LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
墨染ふみ(1388) により ItemNo.8 美味しくない草 から装飾『黒真珠の欠片』を作製してもらいました!
⇒ 黒真珠の欠片/装飾:強さ40/[効果1]強靭10 [効果2]- [効果3]-
クロエ(584) とカードを交換しました!
ライトニング (ライトニング)

サモン:サーヴァント を研究しました!(深度0⇒1)
ガーディアン を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
ピットトラップ を習得!
☆阿修羅 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ボルドール(1386) は 花びら を入手!
ノーヴァル(1387) は 韮 を入手!
墨染ふみ(1388) は 韮 を入手!
ノーヴァル(1387) は 毛 を入手!
墨染ふみ(1388) は 不思議な雫 を入手!
ボルドール(1386) は 毛 を入手!



チナミ区 N-5(沼地)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 N-8(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



「あ、オーナー」
思わず口にしてしまってから、しまった、とボルドールは思った。
白髪に青いサングラスという派手ないで立ちのその男がボルドールの声に顔を上げた。彼はそれまで話をしていた自分の連れらしい青年と、ボルドールの同行者であるふみに一声かけてから、トコトコとボルドールの方にやってきた。
そうして、こちらの顔をまじまじと見て首を傾げてから。
「……もしかして、巌くん?」
そう言ってのけた。
本来の姿であるボルドールと、イバラシティ住民に偽装している七色巌。髪や肌の色、種族といった違いはあれど、実のところ顔立ちはほぼ同じだ。
イバラシティで日常的に接触している相手であれば、少し目を凝らせば特定できてしまう程度には。
ボルドールも、自分から声をかけてしまった段階でほぼ諦めていた。黙っているつもりだったのにそうしてしまったのは「七色巌」としての彼が勝手に喋ったからだ。ボルドールと巌は恐らく、種族や育ちといった部分を除いた、魂の性質とも言うべき部分が非常に似通っている。
だからこの時も、
「……うっス」
と、まるで七色巌本人のような返事を返してしまったのだった。
「いやあびっくりだね。巌くんがホントはボルドールくんっていうタコさんで、しかもアンジニティの人だったなんて。ワールドスワップ恐るべしって感じ……」
しみじみと語るのは、巌のバイト先の喫茶店「喫茶はねやすめ」のオーナー、関盛誠哉。
丸いフォルムに整えた真っ白な髪に青いサングラス、鳥の翼を思わせる青いストールを纏った派手な男だ。巌は彼を初めて見た際、どこかのファッション雑誌の関係者か何かと思ったぐらいである。それも偽りの記憶ではあるが。
しかし実際には素性のよく分からない、のんびりとした喫茶店オーナーであった。彼の異能『バッジー』によって生み出されたインコ的存在が、彼の周囲を飛び回りながら囀っている。
「……ボルドールでいい。あんたが思ってるよりは年寄りだ」
「そう? まあ、それを言ったらぼくもおじいちゃんなんだけどねえ」
くすくすと笑うその容貌は若いが、確かに彼の態度はどことなく年寄りめいている。おじいちゃん、という言葉にボルドールは眉根を寄せた。
「あんたもアンジニティか? あんまりあっちと変わってるようにゃ見えねえが」
「いや、ぼくはイバラシティの住人だよ。まあ、外の世界から来たタイプだけど。移住してコレに巻き込まれたって感じ」
「……じゃあ、見た目が老けない異能も持ってるとか?」
「ううん、正真正銘の二十代。……んー、まあ、向こうじゃ覚えてないだろうし、教えちゃおうかな」
そう言って誠哉は、愉快そうに目を細めた。
「ボルドール、人間の二十歳とセキセイインコの二十歳、どっちがお年寄りだと思う?」
「インコだろ、そりゃ」
「でしょ?」
「……実はインコですとか言うなよ?」
「それがねえ、そうなんだよねえ」
けらけらと笑う、その声がまさに鳥の囀りそのものだったので、ボルドールは思わず目を瞬いた。
「『バッジー』の本当の効果は『人間に化ける』こと。この子たちはその副産物だね。ぼくの生命エネルギーが漏れ出したのを成形してる」
「……何でまた、人間のふりを?」
「ぼくの出身世界ではね、寿命より長生きした生き物は何らかの異能に目覚めることが多かったんだ。みんなは神通力とか呼んでたけど……ぼくの場合は、それが人間になることだったって訳だね」
そう言ってから、誠哉は「ただねえ」とため息をついた。
「そうなると色々トラブルになっちゃうんだよ。異能に目覚めた子は知性も人間並みになるから……だから、ぼくが働いてる組織はそう言う元動物だった子たちや、異能で迫害されたりしてる人たちを保護して、不自由なく暮らしていけるように支援をしてるんだ。イバラシティへの移住もその一環だったってわけ」
「じゃあ、『はねやすめ』は」
「イバラシティでの拠点のひとつだね。実は結構、関係者の人も来てるんだよ。あ、コレは他の人には内緒ね!」
誠哉がそんなことを言いながら口元に人差し指を立ててみせるので、ボルドールは思わず笑ってしまった。
「あっちじゃここのことは覚えてねえよ、安心しろ」
「そ、そう言えばそうだったね……」
気まずそうに頭を掻いていた誠哉だったが、不意に真面目な顔になって、ボルドールの方を見た。思いの外、鋭い目をしていた。
「そんな訳で、イバラシティを侵略されちゃうと困るんだけど……ボルドール、君はイバラシティ側に味方してるって聞いたよ。それは本当?」
「……まあ、そうだな。乗るつもりはない。だからあんたらと敵対する気はねえよ」
「……それなら、いいんだけど」
息を吐いた誠哉だったが、その表情がふ、と曇る。
「……全部終わって、イバラシティ側が勝ったら……巌くんは、君は、いなくなっちゃうのかな」
「……ほんとは居ねえ奴が間借りしてるんだ。そうなるわな」
「ねえ、ボルドール。ぼくが聞くのも、おかしいかもしれないんだけど」
誠哉が、人間にしか見えないその顔が、ボルドールを見つめて言った。
「……君は、それでいいの?」
ボルドールは、ただ曖昧に笑うことしかできなかった。



ENo.244 スズヒコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.426 アストロイェライ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1387 ノーヴァル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1388 墨染ふみ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||



 |
装備の確認をしている |





制約LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
墨染ふみ(1388) により ItemNo.8 美味しくない草 から装飾『黒真珠の欠片』を作製してもらいました!
⇒ 黒真珠の欠片/装飾:強さ40/[効果1]強靭10 [効果2]- [効果3]-
 |
墨染ふみ 「これ、綺麗だが、……なん……黒い、真珠?」 |
クロエ(584) とカードを交換しました!
ライトニング (ライトニング)

サモン:サーヴァント を研究しました!(深度0⇒1)
ガーディアン を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
ピットトラップ を習得!
☆阿修羅 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ボルドール(1386) は 花びら を入手!
ノーヴァル(1387) は 韮 を入手!
墨染ふみ(1388) は 韮 を入手!
ノーヴァル(1387) は 毛 を入手!
墨染ふみ(1388) は 不思議な雫 を入手!
ボルドール(1386) は 毛 を入手!



チナミ区 N-5(沼地)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 N-8(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――





ENo.1386
『鉄の膚』のボルドール



◆七色 巌(ななしき いわお)
20歳 男性
創峰大学第二学群 比較文化学類所属 二年生
創峰大学に通う男子大学生。年相応に口は悪いものの性質は基本的に温厚。頼まれたことを断れない部分があり、文句は言いつつ他人の代返の手伝いなどをしている。実家はミナト区にあるが通学のために現在はマシカ区で一人暮らし中。自由時間が多いのが楽しくて仕方がないお年頃。しかし来年から始まる就職のことはあんまり考えたくない。
『十月の蛸』(エイトアームズ)
巌の異能。エネルギー体でできた触手を操る。
触手は最大で6本展開可能で、もともとの腕と合わせて8本の『腕』があるように見えるためにこの異能名がついた。
射程は巌の背中を中心として3m程度が基本で、めちゃくちゃ頑張れば5mギリギリまで届く。あまり重いものは持てない。
ちょっとした荷物運び程度に使うことが多いが、展開中の触手は淡い虹色に光るため、異能を使うとめちゃくちゃ目立ってしまうのが目下の悩み。
---
◆『鉄の膚』のボルドール
巌の本来の姿。
高い知性を持つ巨大頭足類「ニンギョマネダコ族」の男。箱海の世界『フレア・ウハラ』出身。荒っぽく物事を斜にとらえがちだが、真面目で臆病な面も垣間見える。
自分を人間の姿に変えるべく禁術に手を出し、代償に街一つを消し去った罪によりアンジニティに追放された。禁術により一度は人に化ける異能を得たものの、アンジニティに堕ちた際に異能は剥奪されている。しかし禁術の影響は様々な面で彼に残っており、乾燥に耐える鉄色の肌、空気から酸素を取り込むことを可能とする肺など、陸上で活動する能力を今も持つ。
本人は追放を納得しており、イバラシティへの侵略には反対の立場。そのため、アンジニティの住民でありながらイバラシティ側に味方する。
◆ニンギョマネダコ族
高い知能と文化を持つ巨大頭足類。人の上半身そっくりの胴体とタコの脚を持つが、真の頭部は腰に当たる部分である。腰飾りに見えるものは彼らの本体の目玉。
かつてフレア・ウハラを支配していた人魚族に恭順の意を示すため、始祖にあたる大蛸の王が魔法により自分たちの姿を人魚に似せて変えたのが始まりとされる。
---
◆関盛 誠哉(サブキャラ アイコン20〜29)
巌のバイト先の喫茶店のオーナー。
白い髪に青いサングラス、鳥の翼を思わせるストールをいつも羽織っている。見た目は若いが何となくじじくさい。
インコ的存在を操る異能『バッジー』を持つ。
彼の周りでは巨大な青いセキセイインコが度々目撃されている。
20歳 男性
創峰大学第二学群 比較文化学類所属 二年生
創峰大学に通う男子大学生。年相応に口は悪いものの性質は基本的に温厚。頼まれたことを断れない部分があり、文句は言いつつ他人の代返の手伝いなどをしている。実家はミナト区にあるが通学のために現在はマシカ区で一人暮らし中。自由時間が多いのが楽しくて仕方がないお年頃。しかし来年から始まる就職のことはあんまり考えたくない。
『十月の蛸』(エイトアームズ)
巌の異能。エネルギー体でできた触手を操る。
触手は最大で6本展開可能で、もともとの腕と合わせて8本の『腕』があるように見えるためにこの異能名がついた。
射程は巌の背中を中心として3m程度が基本で、めちゃくちゃ頑張れば5mギリギリまで届く。あまり重いものは持てない。
ちょっとした荷物運び程度に使うことが多いが、展開中の触手は淡い虹色に光るため、異能を使うとめちゃくちゃ目立ってしまうのが目下の悩み。
---
◆『鉄の膚』のボルドール
巌の本来の姿。
高い知性を持つ巨大頭足類「ニンギョマネダコ族」の男。箱海の世界『フレア・ウハラ』出身。荒っぽく物事を斜にとらえがちだが、真面目で臆病な面も垣間見える。
自分を人間の姿に変えるべく禁術に手を出し、代償に街一つを消し去った罪によりアンジニティに追放された。禁術により一度は人に化ける異能を得たものの、アンジニティに堕ちた際に異能は剥奪されている。しかし禁術の影響は様々な面で彼に残っており、乾燥に耐える鉄色の肌、空気から酸素を取り込むことを可能とする肺など、陸上で活動する能力を今も持つ。
本人は追放を納得しており、イバラシティへの侵略には反対の立場。そのため、アンジニティの住民でありながらイバラシティ側に味方する。
◆ニンギョマネダコ族
高い知能と文化を持つ巨大頭足類。人の上半身そっくりの胴体とタコの脚を持つが、真の頭部は腰に当たる部分である。腰飾りに見えるものは彼らの本体の目玉。
かつてフレア・ウハラを支配していた人魚族に恭順の意を示すため、始祖にあたる大蛸の王が魔法により自分たちの姿を人魚に似せて変えたのが始まりとされる。
---
◆関盛 誠哉(サブキャラ アイコン20〜29)
巌のバイト先の喫茶店のオーナー。
白い髪に青いサングラス、鳥の翼を思わせるストールをいつも羽織っている。見た目は若いが何となくじじくさい。
インコ的存在を操る異能『バッジー』を持つ。
彼の周りでは巨大な青いセキセイインコが度々目撃されている。
15 / 30
86 PS
チナミ区
N-9
N-9







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 鉄塊 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 戒めの腰飾り | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 黒真珠の欠片 | 装飾 | 40 | 強靭10 | - | - | |
| 9 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 10 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 15 | 拘束/罠/リスク |
| 武器 | 30 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 打ち払う腕 (ストライク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| 貫く腕 (アサルト) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| 乱舞・四式 (デアデビル) | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| 薙払・四式 (チャージ) | 6 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| 鉄の腕 (イレイザー) | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 『肺腑』 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 『鉄の膚』 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 『八腕』 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 『箱海の加護の残滓』 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
桜花の香り (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
アルコール依存症 (アクアリカバー) |
0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
|
ライトニング (ライトニング) |
0 | 50 | 敵:精確光撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]アクアヒール |
| [ 1 ]ファーマシー | [ 1 ]ガーディアン | [ 1 ]イレイザー |
| [ 1 ]サモン:サーヴァント | [ 2 ]ハードブレイク |

PL / しのだ