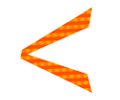<< 8:00~9:00




大きく吐き出した息は砂塵に混じって飛んでいく。フェデルタは、時折舞う砂ぼこりを眺めながら、ただ足を前に出し続ける。
最高の気分と最低の気分が交互にやってくるような、爽快感と不快感の境目が無いような、よくわからない感覚。
そこに、不安が付きまとってくるので基本的には気分は最悪の方が多い。
「……」
相変わらず胸の奥が痛い。フェデルタは歩きながらぎゅ、と胸を押さえた。
道路の割れ目を越える程度にはまだ、足取りはしっかりとしている。
チェックポイントから北、大きな通りから離れた道は険しい場所が多い。
「坊っちゃん、気をつけて下さい」
「うん、わかって――うわっ!」
進む道には大きな瓦礫の山。迂回する場所も見つからないそこを登っている途中で、迦楼羅は足を踏み外した。
「危ない!」
滑り落ちる寸前の迦楼羅を支えたのは従者の手ではなく、フェデルタのものだった。
「……大丈夫か?迦楼羅」
「う、うん……」
フェデルタは迦楼羅を後ろから支えながら登るのを補助しつつ、瓦礫の山を越える。
なんとかそこを越えきった所で、休憩する事となった。
「……」
折れ曲がった標識に背をあずけてぼんやりとしていたフェデルタに、迦楼羅が駆け寄ってくる。
「あの、さっきは……ありがとう」
遠慮がちに頭を下げる姿にフェデルタは、軽く笑みを浮かべてみせる。
「気にするなよ。それより怪我は?」
「……大丈夫」
フェデルタの問いに迦楼羅は首を軽く横に振ってみせる。それから、黙ってその顔をじっと見上げていた。
「……どうした?」
フェデルタが不思議そうに見上げる迦楼羅に視線を向けると、迦楼羅は何とも言えない表情で目を伏せた。
「……迦楼羅?」
「……貴方がおかしいと思っているんですよ。坊っちゃんは」
どうしたのだろう、と続けてる声をかけると主人のかわりに、と言わんばかりにグノウの姿が現れた。
迦楼羅の後ろに立てば、不安げな主人と視線を交わす。
「俺が、おかしい?」
「おや、自覚がお有りではない」
眉を寄せ、目を細める。フェデルタの表情が厳しくなる。しかし、グノウがそれを気にする様子はなく、むしろその表情こそが不快だと言わんばかりに鋭い双眸を更に細めた。
「坊っちゃんを助けてくれたお礼に教えてあげますよ。貴方が勝手に我々から離れ、戻ってきてから今まで、離れる前の面影はほぼありません」
「ッ、……」
グノウの言葉にフェデルタは自然と胸を押さえた。胸の奥がまた痛む。息が苦しい。言葉を返したいが口はただ空気を吸って吐くだけだ。
「まるで自分を捨ててイバラシティの姿にでもなろうかとしてるように見える。記憶に捕らわれていた時とは違うでしょうね。今は、自らの意思でそうしているのでしょう?」
「ちょ、ちょっと、グノウ」
「坊っちゃんも知っているでしょう?そんな事をして、救われる訳がないと」
従者の物言いに流石に不安になった迦楼羅が制しようとしたが、グノウの鋭い言葉と視線に思わずなにも言えなくなる。
フェデルタは相変わらず浅い呼吸を繰り返すばかりで、言葉を返すことができない。こいつは何を言っているんだ?という思いと、その通りだと肯定する思いが交互に浮かんで、混ざり合って、訳が分からなくなる。
「正直、そんな状態で一緒にいられては迷惑なんですよ」
「……そっちには関係無いだろ」
吐き捨てるように言われた言葉に、フェデルタは掠れた声で呟いた。その瞬間、フェデルタとグノウの間に流れる空気がぴり、と張りつめる。迦楼羅は自然と手にしていたぬいぐるみを強く抱きしめた。
「貴方たちが組むように言ってきて、勝手に分かれて、あげくこんな姿を見せられて、いつまた突然倒れるともわからないのに? これだけ人を振り回しておいておいて、無関係だと? あまりにも短慮では?」
苛立ちを隠さないグノウの言葉は、すべてがその通りだった。自分の行動は、その場その場の思い付きで、支離滅裂で、一貫した考えなどなくて、それを短慮であると言われればその通りなのだと。
『お得意の頭脳、お得意の頭脳ってさ、言うくせにさ、じゃあ“自分でなにか考えた?”』
スズヒコの言葉が頭をよぎる。あの時は、考えていると思っていたけど、本当に自分は"なにか考えていた"のか?
冷や汗が顔を伝う。心臓が握りつぶされるような錯覚。
「貴方がしていることは逃避です」
頭の上から、グノウの言葉が落ちてくる。また、逃げているのだ。今度こそ、逃げてはいけないと思っていたのに。
足が震える。立っているのがやっとといった出で立ちで、グノウを見るフェデルタの瞳はまるでおびえた子供のようなそれだった。
「せいぜいどうしたいのか、身の振り方を考えることですね……立ち止まるなら置いていきますので」
グノウはこれ以上話しても意味は無い、と言った感じで吐き捨てるように告げると、無駄の無い動きで踵を返す。
「あっ、ちょっと、グノウっ……」
迦楼羅も立ち去っていく従者に一歩遅れて、その場を歩き出す――が、数歩進んだところで立ち止まり、フェデルタの方を振り返った。
はた、と視線がぶつかれば迦楼羅はそっとうつむいた。
「……おじさんは、としひこお兄ちゃんじゃないんだよ」
ぽつり、とそうこぼすと迦楼羅はそのまま走り去っていった。
「……なんだよ、なんだっていうんだ。俺は、」
フェデルタは顔に手を当て、天を仰いだ。
グノウの言葉は冷たく鋭く怒りを含んでいる一方で、そのいっている言葉は的確だった。そして、迦楼羅もそれをとっくに見抜いていたのだ。とっくに見抜かれていたなんて、笑えるほどに滑稽だ。けれど、もうフェデルタとしている事に疲れてしまった。
何も出来ない、何も届けられない、つらいことから逃げてばかりの愚かで、どうしようもないクズなんかより、そう考えたって吉野俊彦の方がいいに決まっている。
そのくせ、胸の奥が痛むのは未だにそんな自分に未練を持っているからだ。正義感に厚い、真面目な少年の魂を歪な形で作り上げることがおかしいと思っているからだ。
空の赤さが濃くなっていく。まるで血が塗りたくられていくようなそれを、指の隙間からフェデルタは見ている。
『何も怖いことなんてない』
『俺に任せて』
『もう誰もお前を求めてない』
おおよそ記憶で見る吉野俊彦が言いそうにない言葉が、記憶にある吉野俊彦と同じ声で囁いてくる。
『あんなものを抱えているから未練があるんだろう?』
温い風が、まるで頬を包み込むように流れていく。泣いた子供をあやすような温かい両の掌のような柔らかさを感じる。
『咲良乃スズヒコの、力を』
「え……」
顔を押さえていた手がひとりでに動いていのを目の当たりにして、思わず掠れた声が漏れた。そのうち、手は胸に移動して、ずぶりと体の中に飲み込まれる。
とくに不快感どころか、感触もわからないまま、手が何かを掴む。本だ。身体の中に残る、咲良乃スズヒコの力を、形にしたそれがまるで体の中から心臓を引き抜かれるかのような生暖かさを伴いながら、引き抜かれた。
「……なにを」
『この力を燃やせば、お前(おれ)は未練を捨てられる』
本を燃やす。それは、本当の決別を意味する。フェデルタは、震える両手で本を握りしめる。そうだ、とささやく声がする。
これを燃やせばもう、全て捨てて終われるのだと。
正義感に厚い、真面目な少年のように振る舞うことになんの気持ちも抱かなくて済む。それこそが、求めていた身の振り方なのだ。
「……あ、」
ぱた、と握りしめた本に雫がひとつ落ちた。緩やかに染みをつくりながら消えていくそれは、間違いなく涙だった。
「……いやだ」
たとえ、自分を捨てることが出来ても俺があのひとを捨てられる筈がない。本当にあの人が俺の事を捨てたとしても、俺はあの人を捨てられる筈がない。
「いやだぁ……」
あのひとが求めてるのはこんな弱い自分じゃない。だけど、吉野俊彦でもない。だから俺は吉野俊彦にはなれない。あの人を捨てられない限り、俺はずっとフェデルタ・アートルムでいるしかない。
だだをこねる子供のように呟いて、折れ曲がった標識に寄りかかったままずるずると地面に座り込む。本を胸の中で抱き締めるように両手で抱えて、震える身体を縮こまらせた。
「あ……」
真っ赤な視界の中で、青い尾が揺れた。まるで霧を払うかのように大きく尾が揺れる度に、フェデルタの視界が元の色を取り戻していく。
「……」
大きな竜が、物言わぬ青い獣がフェデルタを見る。その視線は何かを見定めているかのように、感じられた。
「……スズヒコ」
この青い巨体は、もう一人のあのひとである。彼が、こうして側にいることには何らかの意味があるのだろうか。
大きな尾が、フェデルタの身体を叩く。
「……急かすなよ。わかってる」
フェデルタが抱き締めていた本を身体に押し付けると、吸い込まれるように消えていく。身体の中に柔らかな流れが染み込んでいくのを感じてから、フェデルタはゆっくりと立ち上がった。

「……」
「……」

フェデルタが戻ってくると、グノウが一度振り返って視線を交えてすぐに正面に向き直った。その一瞥で彼が何を考えているのかは全くわからなかったが、何かを言う必要もないだろう。ただ、スカした態度が気に食わなくてフェデルタは小さく舌打ちした。

グノウの隣にいる迦楼羅が少し不安げに振り替えるのをみれば、眉を寄せてながら顎をしゃくって前を見ろ、と示せば大人しく前に向き直る。
「……」

スズヒコは、先を歩いている。その背中を見ても、胸が苦しくならない。気分はといえば、最高でも最低でも無い。
その辺の石を蹴飛ばす程度に足取りもしっかりしている。
蹴飛ばした石は、アスファルトの割れ目に落ちて行った。



ENo.261 暮泥 唯 とのやりとり

ENo.360 瑞稀 とのやりとり

ENo.456 ノジコ とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.730 モドラ とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

以下の相手に送信しました




スズヒコ(244) に ItemNo.6 鉄板 を手渡ししました。
迦楼羅(931) から 触手 を手渡しされました。
ItemNo.17 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












メリーナ(646) から 15 PS 受け取りました。
迦楼羅(931) から 触手 を受け取りました。
具現LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV60⇒65、-5CP)
グノウ(909) の持つ ItemNo.27 孔雀石 から射程2の武器『夙迎のツバメ』を作製しました!
メリーナ(646) の持つ ItemNo.3 触手 から射程1の武器『鋭杖《スティンガー》』を作製しました!
ItemNo.6 触手 から射程1の武器『痛撃用のナイフ』を作製しました!
⇒ 痛撃用のナイフ/武器:強さ150/[効果1]器用20 [効果2]- [効果3]-【射程1】
メリーナ(646) により ItemNo.20 赤い薔薇 から装飾『ローズクォーツ』を作製してもらいました!
⇒ ローズクォーツ/装飾:強さ75/[効果1]火纏10 [効果2]- [効果3]-
グノウ(909) により ItemNo.1 献身のマフラー に ItemNo.16 不思議な牙 を付加してもらいました!
⇒ 献身のマフラー/装飾:強さ97/[効果1]魔力15 [効果2]体力10 [効果3]-
ノブナガ(1324) とカードを交換しました!
天使の目覚まし (ドラスティックレメディ)
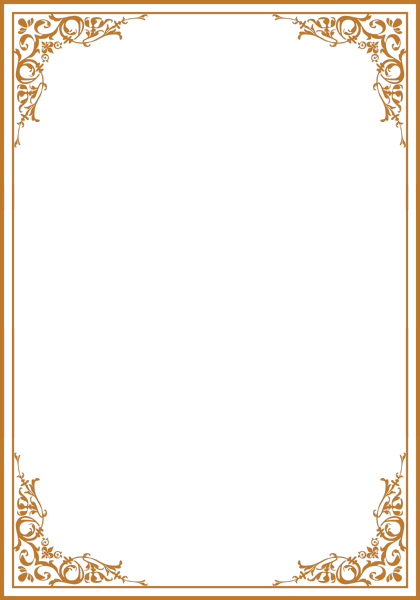
光輝燦然 を研究しました!(深度0⇒1)
光輝燦然 を研究しました!(深度1⇒2)
光輝燦然 を研究しました!(深度2⇒3)
リビルド を習得!
クリエイト:ウェポン を習得!
詠唱追加 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ボロ毛布 を入手!
スズヒコ(244) は タイヤ片 を入手!
グノウ(909) は タイヤ片 を入手!
迦楼羅(931) は タイヤ片 を入手!
フェデルタ(165) は 赤い薔薇 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 不思議な食材 を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ホスト が興味津々な様子で近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ネギさん がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



スズヒコ(244) に移動を委ねました。
ヒノデ区 N-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
ヒノデ区 O-6(草原)に移動!(体調25⇒24)
ヒノデ区 O-5(森林)に移動!(体調24⇒23)
ヒノデ区 O-4(森林)に移動!(体調23⇒22)
ヒノデ区 O-3(森林)に移動!(体調22⇒21)





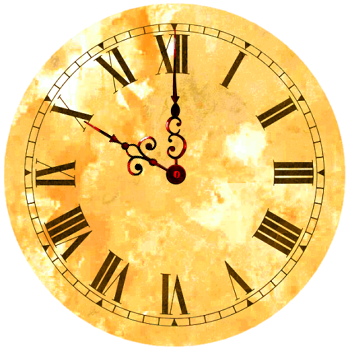
[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。




チャット画面に映る、4人の姿。
少しの間、無音となる。
くんくんと匂いを嗅ぐふたり。
3人の様子を遠目に眺める白南海。
チャットが閉じられる――














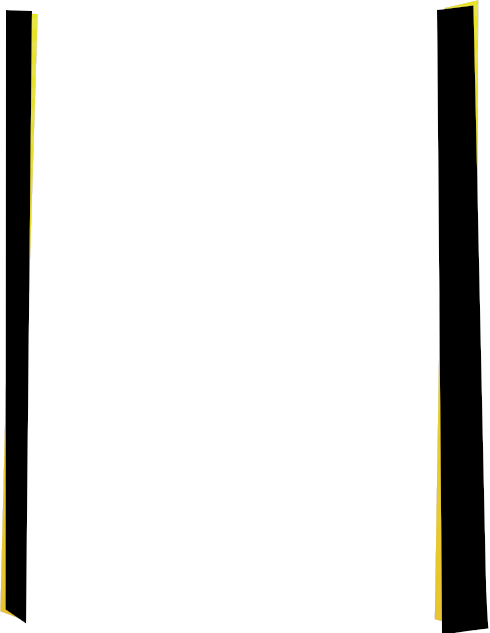
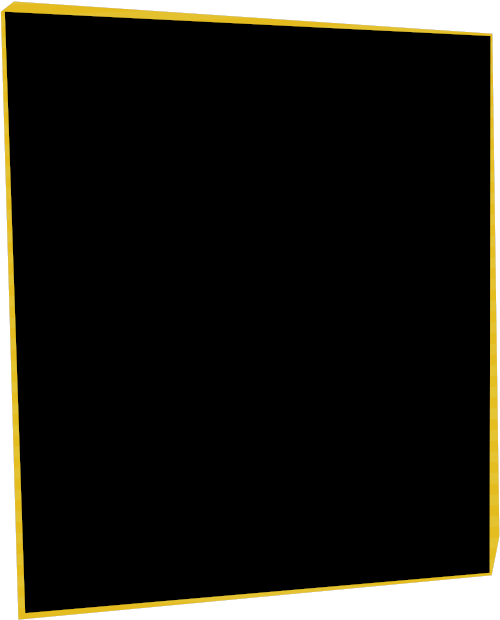





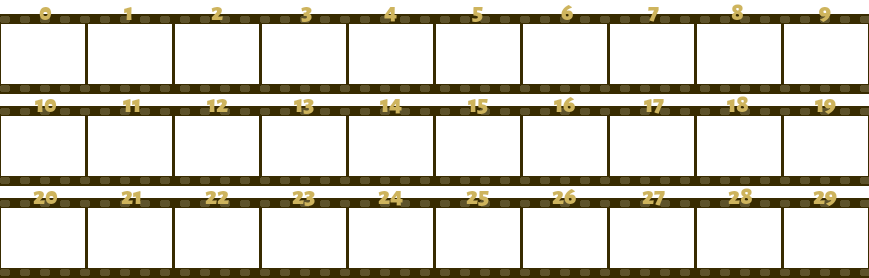







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



大きく吐き出した息は砂塵に混じって飛んでいく。フェデルタは、時折舞う砂ぼこりを眺めながら、ただ足を前に出し続ける。
最高の気分と最低の気分が交互にやってくるような、爽快感と不快感の境目が無いような、よくわからない感覚。
そこに、不安が付きまとってくるので基本的には気分は最悪の方が多い。
「……」
相変わらず胸の奥が痛い。フェデルタは歩きながらぎゅ、と胸を押さえた。
道路の割れ目を越える程度にはまだ、足取りはしっかりとしている。
チェックポイントから北、大きな通りから離れた道は険しい場所が多い。
「坊っちゃん、気をつけて下さい」
「うん、わかって――うわっ!」
進む道には大きな瓦礫の山。迂回する場所も見つからないそこを登っている途中で、迦楼羅は足を踏み外した。
「危ない!」
滑り落ちる寸前の迦楼羅を支えたのは従者の手ではなく、フェデルタのものだった。
「……大丈夫か?迦楼羅」
「う、うん……」
フェデルタは迦楼羅を後ろから支えながら登るのを補助しつつ、瓦礫の山を越える。
なんとかそこを越えきった所で、休憩する事となった。
「……」
折れ曲がった標識に背をあずけてぼんやりとしていたフェデルタに、迦楼羅が駆け寄ってくる。
「あの、さっきは……ありがとう」
遠慮がちに頭を下げる姿にフェデルタは、軽く笑みを浮かべてみせる。
「気にするなよ。それより怪我は?」
「……大丈夫」
フェデルタの問いに迦楼羅は首を軽く横に振ってみせる。それから、黙ってその顔をじっと見上げていた。
「……どうした?」
フェデルタが不思議そうに見上げる迦楼羅に視線を向けると、迦楼羅は何とも言えない表情で目を伏せた。
「……迦楼羅?」
「……貴方がおかしいと思っているんですよ。坊っちゃんは」
どうしたのだろう、と続けてる声をかけると主人のかわりに、と言わんばかりにグノウの姿が現れた。
迦楼羅の後ろに立てば、不安げな主人と視線を交わす。
「俺が、おかしい?」
「おや、自覚がお有りではない」
眉を寄せ、目を細める。フェデルタの表情が厳しくなる。しかし、グノウがそれを気にする様子はなく、むしろその表情こそが不快だと言わんばかりに鋭い双眸を更に細めた。
「坊っちゃんを助けてくれたお礼に教えてあげますよ。貴方が勝手に我々から離れ、戻ってきてから今まで、離れる前の面影はほぼありません」
「ッ、……」
グノウの言葉にフェデルタは自然と胸を押さえた。胸の奥がまた痛む。息が苦しい。言葉を返したいが口はただ空気を吸って吐くだけだ。
「まるで自分を捨ててイバラシティの姿にでもなろうかとしてるように見える。記憶に捕らわれていた時とは違うでしょうね。今は、自らの意思でそうしているのでしょう?」
「ちょ、ちょっと、グノウ」
「坊っちゃんも知っているでしょう?そんな事をして、救われる訳がないと」
従者の物言いに流石に不安になった迦楼羅が制しようとしたが、グノウの鋭い言葉と視線に思わずなにも言えなくなる。
フェデルタは相変わらず浅い呼吸を繰り返すばかりで、言葉を返すことができない。こいつは何を言っているんだ?という思いと、その通りだと肯定する思いが交互に浮かんで、混ざり合って、訳が分からなくなる。
「正直、そんな状態で一緒にいられては迷惑なんですよ」
「……そっちには関係無いだろ」
吐き捨てるように言われた言葉に、フェデルタは掠れた声で呟いた。その瞬間、フェデルタとグノウの間に流れる空気がぴり、と張りつめる。迦楼羅は自然と手にしていたぬいぐるみを強く抱きしめた。
「貴方たちが組むように言ってきて、勝手に分かれて、あげくこんな姿を見せられて、いつまた突然倒れるともわからないのに? これだけ人を振り回しておいておいて、無関係だと? あまりにも短慮では?」
苛立ちを隠さないグノウの言葉は、すべてがその通りだった。自分の行動は、その場その場の思い付きで、支離滅裂で、一貫した考えなどなくて、それを短慮であると言われればその通りなのだと。
『お得意の頭脳、お得意の頭脳ってさ、言うくせにさ、じゃあ“自分でなにか考えた?”』
スズヒコの言葉が頭をよぎる。あの時は、考えていると思っていたけど、本当に自分は"なにか考えていた"のか?
冷や汗が顔を伝う。心臓が握りつぶされるような錯覚。
「貴方がしていることは逃避です」
頭の上から、グノウの言葉が落ちてくる。また、逃げているのだ。今度こそ、逃げてはいけないと思っていたのに。
足が震える。立っているのがやっとといった出で立ちで、グノウを見るフェデルタの瞳はまるでおびえた子供のようなそれだった。
「せいぜいどうしたいのか、身の振り方を考えることですね……立ち止まるなら置いていきますので」
グノウはこれ以上話しても意味は無い、と言った感じで吐き捨てるように告げると、無駄の無い動きで踵を返す。
「あっ、ちょっと、グノウっ……」
迦楼羅も立ち去っていく従者に一歩遅れて、その場を歩き出す――が、数歩進んだところで立ち止まり、フェデルタの方を振り返った。
はた、と視線がぶつかれば迦楼羅はそっとうつむいた。
「……おじさんは、としひこお兄ちゃんじゃないんだよ」
ぽつり、とそうこぼすと迦楼羅はそのまま走り去っていった。
「……なんだよ、なんだっていうんだ。俺は、」
フェデルタは顔に手を当て、天を仰いだ。
グノウの言葉は冷たく鋭く怒りを含んでいる一方で、そのいっている言葉は的確だった。そして、迦楼羅もそれをとっくに見抜いていたのだ。とっくに見抜かれていたなんて、笑えるほどに滑稽だ。けれど、もうフェデルタとしている事に疲れてしまった。
何も出来ない、何も届けられない、つらいことから逃げてばかりの愚かで、どうしようもないクズなんかより、そう考えたって吉野俊彦の方がいいに決まっている。
そのくせ、胸の奥が痛むのは未だにそんな自分に未練を持っているからだ。正義感に厚い、真面目な少年の魂を歪な形で作り上げることがおかしいと思っているからだ。
空の赤さが濃くなっていく。まるで血が塗りたくられていくようなそれを、指の隙間からフェデルタは見ている。
『何も怖いことなんてない』
『俺に任せて』
『もう誰もお前を求めてない』
おおよそ記憶で見る吉野俊彦が言いそうにない言葉が、記憶にある吉野俊彦と同じ声で囁いてくる。
『あんなものを抱えているから未練があるんだろう?』
温い風が、まるで頬を包み込むように流れていく。泣いた子供をあやすような温かい両の掌のような柔らかさを感じる。
『咲良乃スズヒコの、力を』
「え……」
顔を押さえていた手がひとりでに動いていのを目の当たりにして、思わず掠れた声が漏れた。そのうち、手は胸に移動して、ずぶりと体の中に飲み込まれる。
とくに不快感どころか、感触もわからないまま、手が何かを掴む。本だ。身体の中に残る、咲良乃スズヒコの力を、形にしたそれがまるで体の中から心臓を引き抜かれるかのような生暖かさを伴いながら、引き抜かれた。
「……なにを」
『この力を燃やせば、お前(おれ)は未練を捨てられる』
本を燃やす。それは、本当の決別を意味する。フェデルタは、震える両手で本を握りしめる。そうだ、とささやく声がする。
これを燃やせばもう、全て捨てて終われるのだと。
正義感に厚い、真面目な少年のように振る舞うことになんの気持ちも抱かなくて済む。それこそが、求めていた身の振り方なのだ。
「……あ、」
ぱた、と握りしめた本に雫がひとつ落ちた。緩やかに染みをつくりながら消えていくそれは、間違いなく涙だった。
「……いやだ」
たとえ、自分を捨てることが出来ても俺があのひとを捨てられる筈がない。本当にあの人が俺の事を捨てたとしても、俺はあの人を捨てられる筈がない。
「いやだぁ……」
あのひとが求めてるのはこんな弱い自分じゃない。だけど、吉野俊彦でもない。だから俺は吉野俊彦にはなれない。あの人を捨てられない限り、俺はずっとフェデルタ・アートルムでいるしかない。
だだをこねる子供のように呟いて、折れ曲がった標識に寄りかかったままずるずると地面に座り込む。本を胸の中で抱き締めるように両手で抱えて、震える身体を縮こまらせた。
「あ……」
真っ赤な視界の中で、青い尾が揺れた。まるで霧を払うかのように大きく尾が揺れる度に、フェデルタの視界が元の色を取り戻していく。
「……」
大きな竜が、物言わぬ青い獣がフェデルタを見る。その視線は何かを見定めているかのように、感じられた。
「……スズヒコ」
この青い巨体は、もう一人のあのひとである。彼が、こうして側にいることには何らかの意味があるのだろうか。
大きな尾が、フェデルタの身体を叩く。
「……急かすなよ。わかってる」
フェデルタが抱き締めていた本を身体に押し付けると、吸い込まれるように消えていく。身体の中に柔らかな流れが染み込んでいくのを感じてから、フェデルタはゆっくりと立ち上がった。

「……」
「……」

フェデルタが戻ってくると、グノウが一度振り返って視線を交えてすぐに正面に向き直った。その一瞥で彼が何を考えているのかは全くわからなかったが、何かを言う必要もないだろう。ただ、スカした態度が気に食わなくてフェデルタは小さく舌打ちした。

グノウの隣にいる迦楼羅が少し不安げに振り替えるのをみれば、眉を寄せてながら顎をしゃくって前を見ろ、と示せば大人しく前に向き直る。
「……」

スズヒコは、先を歩いている。その背中を見ても、胸が苦しくならない。気分はといえば、最高でも最低でも無い。
その辺の石を蹴飛ばす程度に足取りもしっかりしている。
蹴飛ばした石は、アスファルトの割れ目に落ちて行った。



ENo.261 暮泥 唯 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
| |||||||
ENo.360 瑞稀 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.456 ノジコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.730 モドラ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
| |||||||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| フェデルタ 「……」 |
スズヒコ(244) に ItemNo.6 鉄板 を手渡ししました。
迦楼羅(931) から 触手 を手渡しされました。
ItemNo.17 エナジー棒 を食べました!
| (サクッ…… サクッ……) |
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
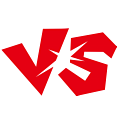 |
鋼響戦隊
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 8 増加!
影響力が 8 増加!



メリーナ(646) から 15 PS 受け取りました。
 |
メリーナ 「よくお世話になるね。はい、今回のお代だよ」 |
迦楼羅(931) から 触手 を受け取りました。
 |
迦楼羅 「にょろにょろ〜〜」 |
具現LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV60⇒65、-5CP)
グノウ(909) の持つ ItemNo.27 孔雀石 から射程2の武器『夙迎のツバメ』を作製しました!
メリーナ(646) の持つ ItemNo.3 触手 から射程1の武器『鋭杖《スティンガー》』を作製しました!
ItemNo.6 触手 から射程1の武器『痛撃用のナイフ』を作製しました!
⇒ 痛撃用のナイフ/武器:強さ150/[効果1]器用20 [効果2]- [効果3]-【射程1】
| フェデルタ 「……露骨な名前だな」 |
メリーナ(646) により ItemNo.20 赤い薔薇 から装飾『ローズクォーツ』を作製してもらいました!
⇒ ローズクォーツ/装飾:強さ75/[効果1]火纏10 [効果2]- [効果3]-
 |
メリーナ 「装飾の方もできてるよ。こんな感じでどうかな…?」 |
グノウ(909) により ItemNo.1 献身のマフラー に ItemNo.16 不思議な牙 を付加してもらいました!
⇒ 献身のマフラー/装飾:強さ97/[効果1]魔力15 [効果2]体力10 [効果3]-
ノブナガ(1324) とカードを交換しました!
天使の目覚まし (ドラスティックレメディ)
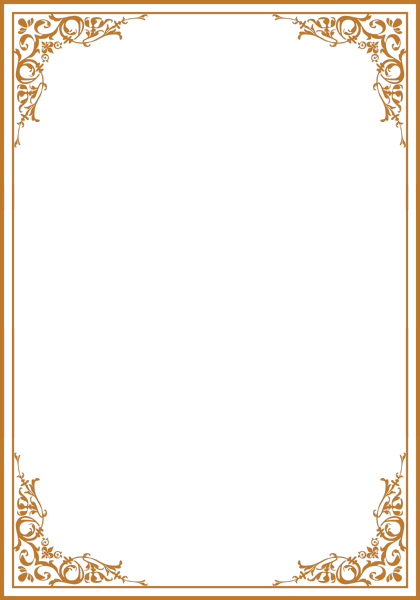
光輝燦然 を研究しました!(深度0⇒1)
光輝燦然 を研究しました!(深度1⇒2)
光輝燦然 を研究しました!(深度2⇒3)
リビルド を習得!
クリエイト:ウェポン を習得!
詠唱追加 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ボロ毛布 を入手!
スズヒコ(244) は タイヤ片 を入手!
グノウ(909) は タイヤ片 を入手!
迦楼羅(931) は タイヤ片 を入手!
フェデルタ(165) は 赤い薔薇 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 不思議な食材 を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ホスト が興味津々な様子で近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ネギさん がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



スズヒコ(244) に移動を委ねました。
ヒノデ区 N-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
ヒノデ区 O-6(草原)に移動!(体調25⇒24)
ヒノデ区 O-5(森林)に移動!(体調24⇒23)
ヒノデ区 O-4(森林)に移動!(体調23⇒22)
ヒノデ区 O-3(森林)に移動!(体調22⇒21)





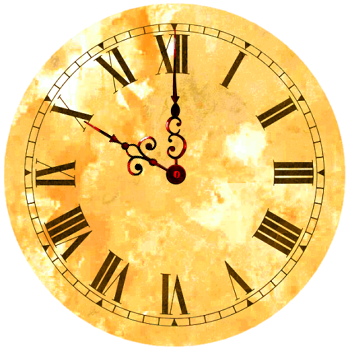
[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
 |
アンドリュウ 「ヘーイ!皆さんオゲンキですかー!!」 |
 |
ロジエッタ 「チャット・・・・・できた。・・・ん、あれ・・・?」 |
 |
エディアン 「あらあら賑やかですねぇ!!」 |
 |
白南海 「・・・ンだこりゃ。既に退室してぇんだが、おい。」 |
チャット画面に映る、4人の姿。
 |
ロジエッタ 「ぁ・・・ぅ・・・・・初めまして。」 |
 |
アンドリュウ 「はーじめまして!!アンドウリュウいいまーすっ!!」 |
 |
エディアン 「はーじめまして!エディアンカーグいいまーすっ!!」 |
 |
白南海 「ロストのおふたりですか。いきなり何用です?」 |
 |
アンドリュウ 「用・・・用・・・・・そうですねー・・・」 |
 |
アンドリュウ 「・・・特にないでーす!!」 |
 |
ロジエッタ 「私も別に・・・・・ ・・・ ・・・暇だったから。」 |
少しの間、無音となる。
 |
エディアン 「えぇえぇ!暇ですよねー!!いいんですよーそれでー。」 |
 |
ロジエッタ 「・・・・・なんか、いい匂いする。」 |
 |
エディアン 「ん・・・?そういえばほんのりと甘い香りがしますねぇ。」 |
くんくんと匂いを嗅ぐふたり。
 |
アンドリュウ 「それはわたくしでございますなぁ! さっきまで少しCookingしていたのです!」 |
 |
エディアン 「・・・!!もしかして甘いものですかーっ!!?」 |
 |
アンドリュウ 「Yes!ほおぼねとろけるスイーツ!!」 |
 |
ロジエッタ 「貴方が・・・?美味しく作れるのかしら。」 |
 |
アンドリュウ 「自信はございまーす!お店、出したいくらいですよー?」 |
 |
ロジエッタ 「プロじゃないのね・・・素人の作るものなんて自己満足レベルでしょう?」 |
 |
アンドリュウ 「ムムム・・・・・厳しいおじょーさん。」 |
 |
アンドリュウ 「でしたら勝負でーすっ!! わたくしのスイーツ、食べ残せるものなら食べ残してごらんなさーい!」 |
 |
エディアン 「・・・・・!!」 |
 |
エディアン 「た、確かに疑わしい!素人ですものね!!!! それは私も審査しますよぉー!!・・・審査しないとですよッ!!」 |
 |
アンドリュウ 「かかってこいでーす! ・・・ともあれ材料集まんないとでーすねー!!」 |
 |
ロジエッタ 「大した自信ですね。私の舌を満足させるのは難しいですわよ。 何せ私の家で出されるデザートといえば――」 |
 |
エディアン 「皆さん急務ですよこれは!急務ですッ!! ハザマはスイーツ提供がやたらと期待できちゃいますねぇ!!」 |
3人の様子を遠目に眺める白南海。
 |
白南海 「まぁ甘いもんの話ばっか、飽きないっすねぇ。 ・・・そもそも毎時強制のわりに、案内することなんてそんな無ぇっつぅ・・・な。」 |
 |
白南海 「・・・・・物騒な情報はノーセンキューですがね。ほんと。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



たのしいおともだち
|
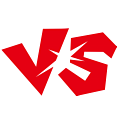 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|


ENo.165
喰らい尽くす炎

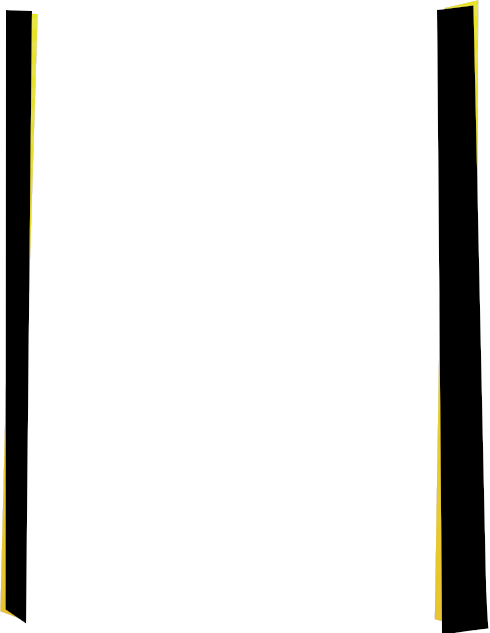
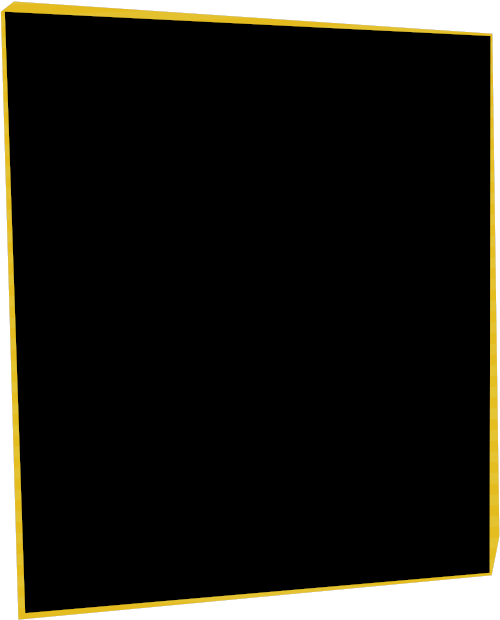
既知設定等大歓迎です。お友達ほしい。
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校2年3組
1年生の中期から異能総合格闘部に所属。
(PL都合で頻度がまばらですが、そこそこちゃんと出ている)
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは割と熱心に剣道をやっていたが、現在は住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校2年3組
1年生の中期から異能総合格闘部に所属。
(PL都合で頻度がまばらですが、そこそこちゃんと出ている)
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは割と熱心に剣道をやっていたが、現在は住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
21 / 30
568 PS
ヒノデ区
O-3
O-3








| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 献身のマフラー | 装飾 | 97 | 魔力15 | 体力10 | - | |
| 2 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 粗削りのナイフ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 着なれたコート | 防具 | 35 | 防御10 | 火纏10 | - | |
| 6 | 痛撃用のナイフ | 武器 | 150 | 器用20 | - | - | 【射程1】 |
| 7 | ぼろぼろマフラー | 装飾 | 45 | 幸運10 | - | - | |
| 8 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 11 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 12 | 丈夫なコート | 防具 | 90 | 反護15 | 火纏10 | - | |
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 14 | ネックナイフ | 武器 | 90 | 追撃10 | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | ボロ毛布 | 素材 | 20 | [武器]魔力15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]防災20(LV30) | |||
| 17 | 触手 | 素材 | 20 | [武器]器用20(LV30)[防具]迫撃20(LV40)[装飾]舞縛20(LV35) | |||
| 18 | お野菜 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV15)[効果2]幸運10(LV25)[効果3]命脈10(LV35) | |||
| 19 | お野菜 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV15)[効果2]幸運10(LV25)[効果3]命脈10(LV35) | |||
| 20 | ローズクォーツ | 装飾 | 75 | 火纏10 | - | - | |
| 21 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 22 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 20 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 25 | 破壊/詠唱/火 |
| 具現 | 20 | 創造/召喚 |
| 武器 | 65 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| 練2 | フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| 練3 | フィジカルブースター | 6 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 |
| カームフレア | 6 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| クリエイト:ダイナマイト | 5 | 0 | 120 | 自:道連LV増 | |
| コントラスト | 6 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| デストロイ | 6 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| フェイタルポイント | 5 | 0 | 80 | 敵:精確痛撃 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| クリエイト:ファイアウェポン | 5 | 0 | 200 | 味:炎上LV・反火LV増 | |
| ヒートイミッター | 6 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| フレアトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵列:罠《猛火》LV増 | |
| サモン:サラマンダー | 5 | 5 | 400 | 自:サラマンダー召喚 | |
| 練3 | ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
| 練2 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 | |
| スカーレットスキュア | 5 | 0 | 180 | 敵列:火痛撃 | |
| クリエイト:ウェポン | 5 | 0 | 280 | 味全:追撃LV増 | |
| フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| 練3 | グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 |
| フレイムインパクト | 6 | 0 | 230 | 敵:5連鎖火痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 火の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 獄炎陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど獄炎LV増 | |
| 練2 | 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 |
| 集気 | 5 | 4 | 0 | 【通常攻撃後】自:次与ダメ増 | |
| 詠唱追加 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:必殺スキル強化 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
常備薬 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
鉄球の一撃 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
念道波 (ショックウェイブ) |
0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
|
調息 (パリィ) |
5 | 0 | 自:AG増(2T)+SP増 | |
|
ティータイム (ハーバルメディスン) |
0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) | |
|
カレイドスコープ (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
|
ディスカード・セブン (エファヴェセント) |
0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) | |
|
石に花咲く (ハーバルメディスン) |
0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) | |
| 練2 |
若かりし頃 (ポーションラッシュ) |
0 | 240 | 味傷6:HP増 |
|
天使の目覚まし (ドラスティックレメディ) |
0 | 160 | 味傷:精確攻撃&HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]アジャイルフォーム | [ 3 ]ヴィガラスチャージ | [ 3 ]クリエイト:バトルフラッグ |
| [ 3 ]プリディクション | [ 3 ]アラベスク | [ 3 ]五月雨 |
| [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]光輝燦然 | [ 3 ]クリエイト:ピッチダーク |

PL / カミヤキサラ











.png)