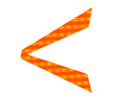<< 9:00~10:00




赤い空に紫煙が延びる。
自分を捨てようと間は全くそれを口にしなかった。どこまでも徹底して自分を捨てようとしていた事を思うと笑いすらおきない。
フェデルタは移動休みの短い時間、相変わらずその辺の瓦礫で寄りかかれそうな場所を見つけては煙草を咥えて火をつけた。
久しぶりの煙草は、口に咥えた途端に燃え尽きた。三本そうやって無駄にして、四本目で漸く吸えた煙草の味はいつもと変わらない。
ただ、煙草を掴む手は、震えていた。
思えばこれが切欠で、今だって吸う前に何度もまわりを確認した。煙草を手にすれば、激昂された事を思い出して手が震えている。
「……」
情けないと我ながら思いつつ、ふ、と煙を吐き出した。
この煙は、無害化された魔力だ。
自分の身体の中で常に産み出される炎の力。身体を突き破らんばかりに溜まるそれを、フィルターを通して無害化し、外に出す。
言わばマジックアイテム、というやつだ。
(見てんだろうなあ)
この煙草をくれたのは、本の世界で出会って長い長い付き合いになった魔女だ。もう、ずっと会ってはいないが。
きっと、自分の事を見ているのだろう。彼女は、享楽的に見えて意外と気にするタイプなのを知っている。
いつか役に立つと言われて渡された煙草は、無害化した魔力でまた新たな煙草を生み出す為、尽きることは無い。
四本目を吸い終え、それを握りしめるとさらさらと灰になり飛んでいく。
侵略闘争が始まってもうすぐ10時間。その間、大した進捗を生み出すところか同行者に迷惑をかけどおしで、正直動き方としては最悪だ。
迦楼羅やグノウは、本当に自分の都合で振り回した事は後悔しているが、過ぎたことを悔いても仕方がなく、今後あらゆる方法で報いるべきだ。
貸しや迷惑をかけたままなのは、好きではないし、返せるのは今 ここにいる間だけなのだ。
「……」
はあ、と溜め息にも似た吐息で煙を吐き出す。だとしてまずやるべきはひとつ。
「……どの面下げりゃいいんだろうな」
「ほんとだよ。まーそのツラしかないと思うんだけど……」
「!!」
天を仰いでこぼした独り言に、唐突に返事がきた。フェデルタは、咥えていた煙草を吐き捨てながら、がばっと寄りかかった瓦礫から離れ、辺りを見渡す。
そもそも、なんの気配もなかったし、自分の独り言にこんなフランクに言葉を返す相手はいない筈だ。
「……誰だ」
「やっほー。ぼくだよ。覚えてる?」
フェデルタが警戒した様子で声をかけると、瓦礫の裏側からするり、と蛇のような――というには体に色々なものがつきすぎているが――ものが這い出て来た。
「……覚えてる?」
まるで相手は自分を知っているような物言いだ。フェデルタは、警戒したままその姿を凝視する。確かになんとなく、その姿に覚えがある。
「あそこだよほら、本の世界!おじさんもいたでしょ?」
「……、あ、」
本の世界。その一言で合点がいった。死ぬ度に幾つもの記憶がボロボロと抜け落ちても、その世界の記憶だけは、消えていない。今でもすぐに思い出せる。
気の合う仲間が沢山いた、守りたいと思う人もいた、共に死の先を歩む人に会えた。
「……お前、たしか……なんだっけ、パラ、なんとか」
「ウワッ記憶ガバガバじゃん。パライバだよ!パライバトルマリン!」
「ああ、ああ、そうだ、パライバ」
フェデルタの様子に、パライバと呼ばれた生き物は手の変わりか頭の触覚を伸ばしてフェデルタをぺちぺちと叩く。
ただ、それもふざけたような様子で怒っている気配はとくに感じられない。
確かに、フェデルタの記憶のなかにあるこの生物は基本的に陽気だった。
だが、
「……なんでここに」
この生き物は確か、自分の世界に戻ったように記憶してる。もしくは、これが記憶違いなのか、それとも何かこの世界に彼を引き付けるに足るものが――
「――あ、」
この、パライバトルマリンという生き物にまつわるもうひとつの記憶が甦る。この生き物は、咲良乃スズヒコと関わりがあるのだ。
「……色々思い出せた?」
「ああ」
フェデルタの様子を察したパライバは、伸ばしていた触覚を引っ込めてフェデルタと向かい合う位置へと移動する。そもそもフェデルタは、人と違う生き物の表情を読むことは出来ないし、そもそもこの生き物に表情があるのかはわからない。
ただ、フェデルタにはその姿は楽しげに見えた。
「あーよかった! いや、だって、さっきまであんなよぼよぼふらふらで、ぴえんぴえんしてる感じだったからさあ。お話になるのかなって心配したよね、元気になってよかったよかった!」
「おま、え……いつから?」
「えー……ここにきてから2~3時間くらい?」
フェデルタは思わず片手で顔を覆った。よもや、自分の中でも最大レベルの情けない姿を見られていたとは夢にも思わず、しかもそれを目の前で朗々と語られるなんて!
「……あー、あ、そう……うん、元気……いや、元気ではねえ」
顔の熱がぐんとあがっていくのを感じながらフェデルタは弱々しくそう答えることしか出来なかった。
パライバは、まーまー等といいながらフェデルタの後ろにまわりこむと慰めるように再び頭の触覚を伸ばして、フェデルタの肩をポンポンとする。
「で、どうしてあんなにぐだってたわけ?」
「……スズヒコと、ちょっとな」
「……先生と?」
さっきまで明るかったパライバの声がワントーン落ちる。
フェデルタはその様子に、話していいのかと一瞬考えたが、誰かに話をしたい気持ちが勝って、自然と口を開いていた。
「……あの人は、ここに来て少し……いや、大分取り乱してる……それを自分で気付いてないのか、認めたくないのかわかんねえけど、全く直そうとしない。
俺は、あれがスズヒコだとは認めたくなかったし、だからこそ目を覚まして欲しくて、色々やろうとした。結果として、ろくな事は出来ずに、お互いがバカみたいに傷ついた」
「……ふうん」
「俺は、そんな自分に嫌気がさして、あとはご覧の通り――結局、俺はこうして生き続けて……自分でケジメをつける以外はねえって、ようやくわかったけどな」
フェデルタはひとしきりいい終えると、横目でパライバを見る。果たして話してよかったのか、と思わなくはないが、吐き出せた事で少しスッキリしたのも事実だ。
パライバの方が何を考えているかは、その態度や表情――そもそも表情が無いのだが――から読み取る事は出来そうもない。
「先生はね、何でも下準備する人。先のことを考えて、用意しなくていいものまで用意する人。それにはもちろん、自分の死に方も含まれてた」
「……」
「だから、ぼくは先生がなんもしてないわけがないって思うんだよね」
「……準備」
「うん。ポケットとかひっくり返してみたら?」
ふふふ、と笑いながらパライバはフェデルタの側からふわりとはなれていく。
「じゃ、ぼくそろそろ行くね」
「……ちょっと待て」
「……なに?」
「もし、もし万が一お前が――いや、お前をここに寄越した何かが、スズヒコに何かしようと思ってんなら――俺がどうするか、わかるよな?」
ぶわり、と風が吹き砂塵と共に火の粉が舞う。パライバを見据えるフェデルタの瞳は炎が燃える色をしていた。
「わかるとも。だから敢えて言うね、“そんな状況でボクたちに勝てると思わないことだ”」

パライバは臆する様子もなく、けれど否定もせずに最後の一言を告げるとす、とその姿を消した。

「……準備、か」
姿を消した後には赤い空だけが残っている。しばらくそこを見つめていたが、もう何も起こらないとわかればふい、と視線を外した。
パライバが最後に置いて行った一言は、本人の言葉ではないだろう。誰かが、何かをしようとしている。全く、ほっといてくれればもう少しですべての世界から消えていくというのに。
フェデルタは心の中で悪態を吐きつつ、小さくため息を吐いた。パライバ周りの事が気になりはするが、今はあの生き物がくれたヒントの方が重要な気がする。何をするにしたって、まずは、スズヒコが、スズヒコでいてもらわなければはじまらないのだ。
しかし、ゆっくり考える時間が残っているわけではない。フェデルタは、空から視線を外して正面に向き直ると瓦礫を乗り越えて集合場所に戻っていった。



ENo.360 瑞稀 とのやりとり

ENo.452 魄角 とのやりとり

ENo.912 愛夢 とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

以下の相手に送信しました




迦楼羅(931) に ItemNo.16 ボロ毛布 を手渡ししました。
ItemNo.22 ビーフ を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 活力5 が発揮されます。












グノウ(909) に ItemNo.13 ボロ布 を送付しました。
具現LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
アカイホノオ?(1305) の持つ ItemNo.1 ダンボール から射程1の武器『DXモエルAAAグローブ』を作製しました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.15 猫目石 から射程2の武器『猫目石の絵筆鎌』を作製しました!
スズヒコ(244) により ItemNo.20 ローズクォーツ に ItemNo.21 赤い薔薇 を付加してもらいました!
⇒ ローズクォーツ/装飾:強さ75/[効果1]火纏10 [効果2]火纏10 [効果3]-
グノウ(909) により ItemNo.6 痛撃用のナイフ に ItemNo.17 触手 を付加してもらいました!
⇒ 痛撃用のナイフ/武器:強さ150/[効果1]器用20 [効果2]器用20 [効果3]-【射程1】
うい(552) とカードを交換しました!
シールドエナジー (ガーディアン)
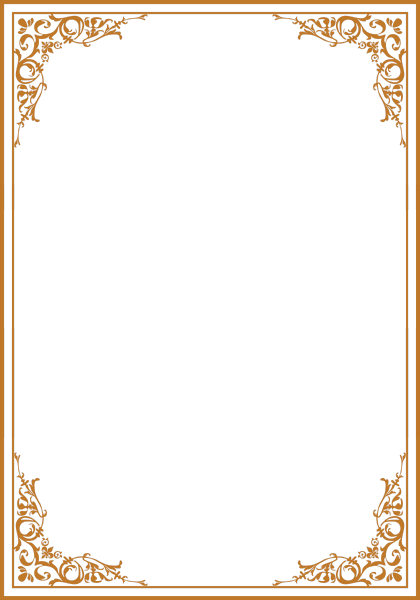
グリモワール を研究しました!(深度0⇒1)
グリモワール を研究しました!(深度1⇒2)
グリモワール を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:モンスター を習得!
レーヴァテイン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ポプラ を入手!
スズヒコ(244) は ポプラ を入手!
グノウ(909) は 竹 を入手!
迦楼羅(931) は 竹 を入手!
スズヒコ(244) は 羽 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
迦楼羅(931) は 皮 を入手!
グノウ(909) は 羽 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 皮 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに フェアリー がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに カメレオン が空を見上げなから近づいてきます。



グノウ(909) がパーティから離脱しました!
迦楼羅(931) がパーティから離脱しました!
スズヒコ(244) に移動を委ねました。
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 N-2(森林)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 P-2(森林)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 Q-2(草原)に移動!(体調18⇒17)
MISSION!!
ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション が発生!
- フェデルタ(165) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション
- スズヒコ(244) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション





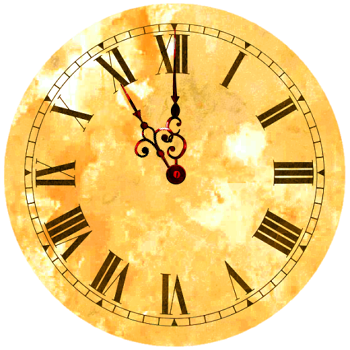
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
チャットが閉じられる――















その施設のほとんどは朽ち果てているようだ。
がさっ・・・・・
物陰から、何かが這い出てきた。


腐敗した者たちが、静かに迫ってくる・・・







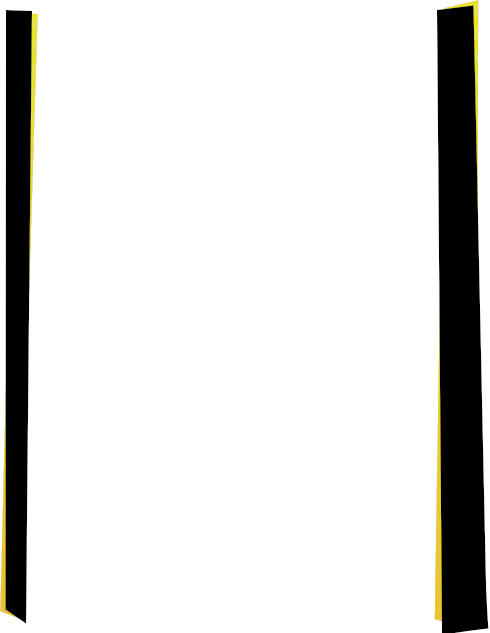
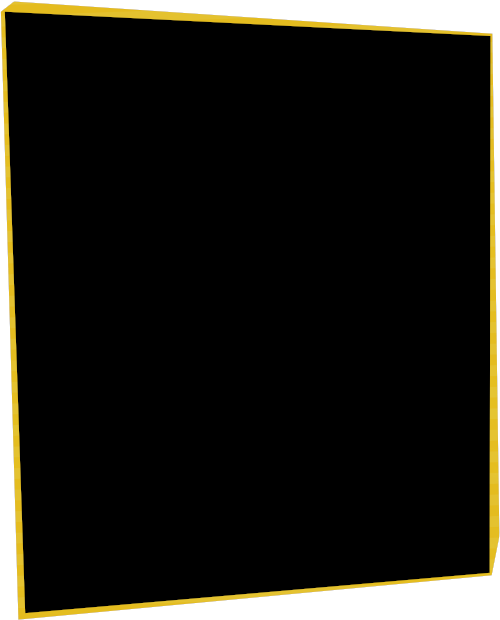





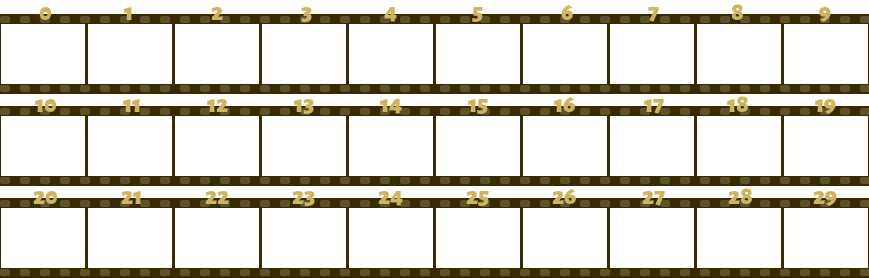







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



赤い空に紫煙が延びる。
自分を捨てようと間は全くそれを口にしなかった。どこまでも徹底して自分を捨てようとしていた事を思うと笑いすらおきない。
フェデルタは移動休みの短い時間、相変わらずその辺の瓦礫で寄りかかれそうな場所を見つけては煙草を咥えて火をつけた。
久しぶりの煙草は、口に咥えた途端に燃え尽きた。三本そうやって無駄にして、四本目で漸く吸えた煙草の味はいつもと変わらない。
ただ、煙草を掴む手は、震えていた。
思えばこれが切欠で、今だって吸う前に何度もまわりを確認した。煙草を手にすれば、激昂された事を思い出して手が震えている。
「……」
情けないと我ながら思いつつ、ふ、と煙を吐き出した。
この煙は、無害化された魔力だ。
自分の身体の中で常に産み出される炎の力。身体を突き破らんばかりに溜まるそれを、フィルターを通して無害化し、外に出す。
言わばマジックアイテム、というやつだ。
(見てんだろうなあ)
この煙草をくれたのは、本の世界で出会って長い長い付き合いになった魔女だ。もう、ずっと会ってはいないが。
きっと、自分の事を見ているのだろう。彼女は、享楽的に見えて意外と気にするタイプなのを知っている。
いつか役に立つと言われて渡された煙草は、無害化した魔力でまた新たな煙草を生み出す為、尽きることは無い。
四本目を吸い終え、それを握りしめるとさらさらと灰になり飛んでいく。
侵略闘争が始まってもうすぐ10時間。その間、大した進捗を生み出すところか同行者に迷惑をかけどおしで、正直動き方としては最悪だ。
迦楼羅やグノウは、本当に自分の都合で振り回した事は後悔しているが、過ぎたことを悔いても仕方がなく、今後あらゆる方法で報いるべきだ。
貸しや迷惑をかけたままなのは、好きではないし、返せるのは今 ここにいる間だけなのだ。
「……」
はあ、と溜め息にも似た吐息で煙を吐き出す。だとしてまずやるべきはひとつ。
「……どの面下げりゃいいんだろうな」
「ほんとだよ。まーそのツラしかないと思うんだけど……」
「!!」
天を仰いでこぼした独り言に、唐突に返事がきた。フェデルタは、咥えていた煙草を吐き捨てながら、がばっと寄りかかった瓦礫から離れ、辺りを見渡す。
そもそも、なんの気配もなかったし、自分の独り言にこんなフランクに言葉を返す相手はいない筈だ。
「……誰だ」
「やっほー。ぼくだよ。覚えてる?」
フェデルタが警戒した様子で声をかけると、瓦礫の裏側からするり、と蛇のような――というには体に色々なものがつきすぎているが――ものが這い出て来た。
「……覚えてる?」
まるで相手は自分を知っているような物言いだ。フェデルタは、警戒したままその姿を凝視する。確かになんとなく、その姿に覚えがある。
「あそこだよほら、本の世界!おじさんもいたでしょ?」
「……、あ、」
本の世界。その一言で合点がいった。死ぬ度に幾つもの記憶がボロボロと抜け落ちても、その世界の記憶だけは、消えていない。今でもすぐに思い出せる。
気の合う仲間が沢山いた、守りたいと思う人もいた、共に死の先を歩む人に会えた。
「……お前、たしか……なんだっけ、パラ、なんとか」
「ウワッ記憶ガバガバじゃん。パライバだよ!パライバトルマリン!」
「ああ、ああ、そうだ、パライバ」
フェデルタの様子に、パライバと呼ばれた生き物は手の変わりか頭の触覚を伸ばしてフェデルタをぺちぺちと叩く。
ただ、それもふざけたような様子で怒っている気配はとくに感じられない。
確かに、フェデルタの記憶のなかにあるこの生物は基本的に陽気だった。
だが、
「……なんでここに」
この生き物は確か、自分の世界に戻ったように記憶してる。もしくは、これが記憶違いなのか、それとも何かこの世界に彼を引き付けるに足るものが――
「――あ、」
この、パライバトルマリンという生き物にまつわるもうひとつの記憶が甦る。この生き物は、咲良乃スズヒコと関わりがあるのだ。
「……色々思い出せた?」
「ああ」
フェデルタの様子を察したパライバは、伸ばしていた触覚を引っ込めてフェデルタと向かい合う位置へと移動する。そもそもフェデルタは、人と違う生き物の表情を読むことは出来ないし、そもそもこの生き物に表情があるのかはわからない。
ただ、フェデルタにはその姿は楽しげに見えた。
「あーよかった! いや、だって、さっきまであんなよぼよぼふらふらで、ぴえんぴえんしてる感じだったからさあ。お話になるのかなって心配したよね、元気になってよかったよかった!」
「おま、え……いつから?」
「えー……ここにきてから2~3時間くらい?」
フェデルタは思わず片手で顔を覆った。よもや、自分の中でも最大レベルの情けない姿を見られていたとは夢にも思わず、しかもそれを目の前で朗々と語られるなんて!
「……あー、あ、そう……うん、元気……いや、元気ではねえ」
顔の熱がぐんとあがっていくのを感じながらフェデルタは弱々しくそう答えることしか出来なかった。
パライバは、まーまー等といいながらフェデルタの後ろにまわりこむと慰めるように再び頭の触覚を伸ばして、フェデルタの肩をポンポンとする。
「で、どうしてあんなにぐだってたわけ?」
「……スズヒコと、ちょっとな」
「……先生と?」
さっきまで明るかったパライバの声がワントーン落ちる。
フェデルタはその様子に、話していいのかと一瞬考えたが、誰かに話をしたい気持ちが勝って、自然と口を開いていた。
「……あの人は、ここに来て少し……いや、大分取り乱してる……それを自分で気付いてないのか、認めたくないのかわかんねえけど、全く直そうとしない。
俺は、あれがスズヒコだとは認めたくなかったし、だからこそ目を覚まして欲しくて、色々やろうとした。結果として、ろくな事は出来ずに、お互いがバカみたいに傷ついた」
「……ふうん」
「俺は、そんな自分に嫌気がさして、あとはご覧の通り――結局、俺はこうして生き続けて……自分でケジメをつける以外はねえって、ようやくわかったけどな」
フェデルタはひとしきりいい終えると、横目でパライバを見る。果たして話してよかったのか、と思わなくはないが、吐き出せた事で少しスッキリしたのも事実だ。
パライバの方が何を考えているかは、その態度や表情――そもそも表情が無いのだが――から読み取る事は出来そうもない。
「先生はね、何でも下準備する人。先のことを考えて、用意しなくていいものまで用意する人。それにはもちろん、自分の死に方も含まれてた」
「……」
「だから、ぼくは先生がなんもしてないわけがないって思うんだよね」
「……準備」
「うん。ポケットとかひっくり返してみたら?」
ふふふ、と笑いながらパライバはフェデルタの側からふわりとはなれていく。
「じゃ、ぼくそろそろ行くね」
「……ちょっと待て」
「……なに?」
「もし、もし万が一お前が――いや、お前をここに寄越した何かが、スズヒコに何かしようと思ってんなら――俺がどうするか、わかるよな?」
ぶわり、と風が吹き砂塵と共に火の粉が舞う。パライバを見据えるフェデルタの瞳は炎が燃える色をしていた。
「わかるとも。だから敢えて言うね、“そんな状況でボクたちに勝てると思わないことだ”」

パライバは臆する様子もなく、けれど否定もせずに最後の一言を告げるとす、とその姿を消した。

「……準備、か」
姿を消した後には赤い空だけが残っている。しばらくそこを見つめていたが、もう何も起こらないとわかればふい、と視線を外した。
パライバが最後に置いて行った一言は、本人の言葉ではないだろう。誰かが、何かをしようとしている。全く、ほっといてくれればもう少しですべての世界から消えていくというのに。
フェデルタは心の中で悪態を吐きつつ、小さくため息を吐いた。パライバ周りの事が気になりはするが、今はあの生き物がくれたヒントの方が重要な気がする。何をするにしたって、まずは、スズヒコが、スズヒコでいてもらわなければはじまらないのだ。
しかし、ゆっくり考える時間が残っているわけではない。フェデルタは、空から視線を外して正面に向き直ると瓦礫を乗り越えて集合場所に戻っていった。



ENo.360 瑞稀 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.452 魄角 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.912 愛夢 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
| |||||||||||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
以下の相手に送信しました



迦楼羅(931) に ItemNo.16 ボロ毛布 を手渡ししました。
ItemNo.22 ビーフ を食べました!
| (ビーフを勝手に自分で焼いて食べた) |
今回の全戦闘において 活力5 が発揮されます。





たのしいおともだち
|
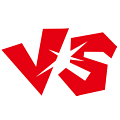 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 9 増加!
影響力が 9 増加!



グノウ(909) に ItemNo.13 ボロ布 を送付しました。
具現LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
アカイホノオ?(1305) の持つ ItemNo.1 ダンボール から射程1の武器『DXモエルAAAグローブ』を作製しました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.15 猫目石 から射程2の武器『猫目石の絵筆鎌』を作製しました!
スズヒコ(244) により ItemNo.20 ローズクォーツ に ItemNo.21 赤い薔薇 を付加してもらいました!
⇒ ローズクォーツ/装飾:強さ75/[効果1]火纏10 [効果2]火纏10 [効果3]-
グノウ(909) により ItemNo.6 痛撃用のナイフ に ItemNo.17 触手 を付加してもらいました!
⇒ 痛撃用のナイフ/武器:強さ150/[効果1]器用20 [効果2]器用20 [効果3]-【射程1】
 |
(ピチピチッ……ぐちゃ… グチュッ) |
 |
グノウ 「できました。」 |
うい(552) とカードを交換しました!
シールドエナジー (ガーディアン)
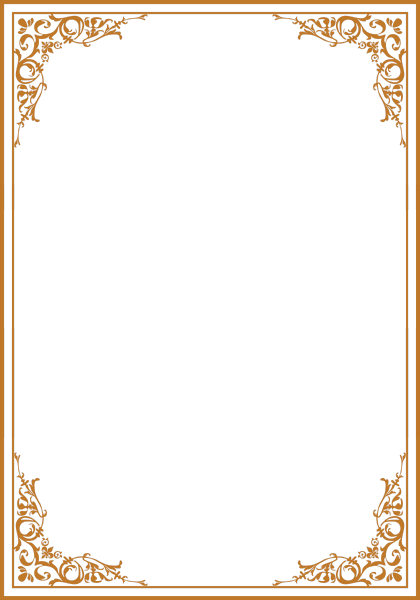
グリモワール を研究しました!(深度0⇒1)
グリモワール を研究しました!(深度1⇒2)
グリモワール を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:モンスター を習得!
レーヴァテイン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ポプラ を入手!
スズヒコ(244) は ポプラ を入手!
グノウ(909) は 竹 を入手!
迦楼羅(931) は 竹 を入手!
スズヒコ(244) は 羽 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
迦楼羅(931) は 皮 を入手!
グノウ(909) は 羽 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 皮 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに フェアリー がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに カメレオン が空を見上げなから近づいてきます。



グノウ(909) がパーティから離脱しました!
迦楼羅(931) がパーティから離脱しました!
スズヒコ(244) に移動を委ねました。
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 N-2(森林)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 P-2(森林)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 Q-2(草原)に移動!(体調18⇒17)
MISSION!!
ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション が発生!
- フェデルタ(165) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション
- スズヒコ(244) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション





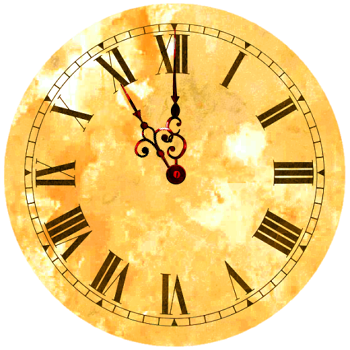
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
白南海 「・・・・・おや、どうしました?まだ恐怖心が拭えねぇんすか?」 |
 |
エディアン 「・・・何を澄ました顔で。窓に勧誘したの、貴方ですよね。」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!! 俺これ嫌っすよぉぉ!!最初は世界を救うカッケー役割とか思ってたっすけどッ!!」 |
 |
エディアン 「わかわかわかわか・・・・・何を今更なっさけない。 そんなにワカが恋しいんです?そんなに頼もしいんです?」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
 |
白南海 「それはもう!若はとんでもねぇ器の持ち主でねぇッ!!」 |
 |
エディアン 「突然元気になった・・・・・」 |
 |
白南海 「俺が頼んだラーメンに若は、若のチャーシューメンのチャーシューを1枚分けてくれたんすよッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・。・・・・他には?」 |
 |
白南海 「俺が501円のを1000円で買おうとしたとき、そっと1円足してくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・あとは?」 |
 |
白南海 「俺が車道側歩いてたら、そっと車道側と代わってくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・うーん。他の、あります?」 |
 |
白南海 「俺がアイスをシングルかダブルかで悩ん――」 |
 |
エディアン 「――あー、もういいです。いいでーす。」 |
 |
白南海 「・・・お分かりいただけましたか?若の素晴らしさ。」 |
 |
エディアン 「えぇぇーとってもーーー。」 |
 |
白南海 「いやー若の話をすると気分が良くなりますァ!」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「・・・あーうるさい。帰りますよ?帰りますからねー。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。







ヒノデ区 M-2 周辺
ヒノデコーポレーション
数々の巨大施設が立ち並ぶ、ヒノデコーポレーション構内。ヒノデコーポレーション
その施設のほとんどは朽ち果てているようだ。
がさっ・・・・・
物陰から、何かが這い出てきた。

ゾンビ
身を崩しながらも歩き回る、腐敗した何か。

ゾンビリーダー
リーダーの風格あふれる、腐敗した何か。
 |
ゾンビリーダー 「・・・・・・・・・」 |
腐敗した者たちが、静かに迫ってくる・・・





ENo.165
喰らい尽くす炎

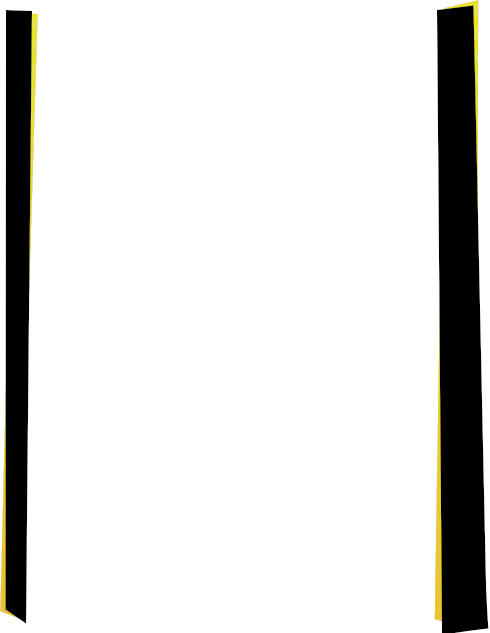
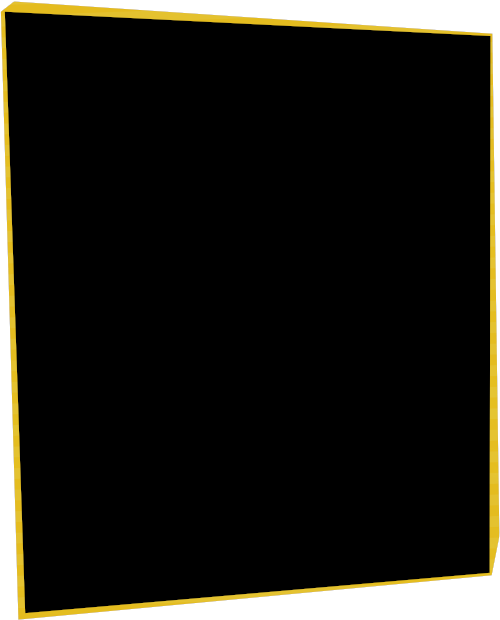
既知設定等大歓迎です。お友達ほしい。
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校2年3組
1年生の中期から異能総合格闘部に所属。
(PL都合で頻度がまばらですが、そこそこちゃんと出ている)
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは割と熱心に剣道をやっていたが、現在は住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
イバラシティでのRPについて。
・基本平日夕方~24時くらいはある程度レスポンスが可能です(ただし、21時~22時辺りで反応がなくなる場合もあります)
・基本が置きレスなので時系列あまり気にしないです
・長くなりがちなので切って頂いても大丈夫です
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
イバラの姿
吉野俊彦 よしの としひこ
16歳 175cm 相良伊橋高校2年3組
1年生の中期から異能総合格闘部に所属。
(PL都合で頻度がまばらですが、そこそこちゃんと出ている)
相良伊橋高校に通う男子高校生。
大学生の兄(Eno244)を持つ。
そこそこに真面目で、わりとおせっかい焼きでどちらかといえば熱血系。
中学までは割と熱心に剣道をやっていたが、現在は住んでる所の近くにある剣道サークルに顔を見せる程度。
勉強は中の下程度で体育は得意。
無愛想ではないが時々ぶっきらぼう。とはいえ、クラスの雰囲気に合わせて笑顔や表情の変化は増えてきた。わりと相手の事を主に考えて自分の事は後回しにしがち。
【炎命の士――リミテッド・ファイアーマン】
俊彦は火や炎、それにまつわるものを操る異能と認識している。自分が本気で燃やしたいと思わなければ草とかに燃え移っても燃え広がらない便利機能つき。
ただ、一般生活にそれほど役に立たないし使うには物騒なので本当に危険な相手等でなければめったに使わない。
また、異能名が本人としてはあまりにもこっぱずかしいので、詳しく聞かない限りは「火を操る能力」くらいに言いとどめている。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ハザマの姿
Fedelta Atrum フェデルタ・アートルム
年齢不詳(享年42歳) 175cm
一度死んだ後、多くの時を死に損なった男。
とある世界で人の身に炎の怪物を宿す存在となり、今ではその炎の怪物に自身が食われる事を危惧している。
彼の目的はアンジニティからの脱出であり、侵略自体には全くの興味を持たない。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
サブキャラクター(テストプレイから続投)
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
――であったが、とある者の手で、現在は【もしかしたらこのイバラシティに存在していたかもしれない舘和男】の場所を借りて
人間の頃の姿に近い形でイバラシティのカフェバー《白詰草》のマスターをしている。
この世界に存在している間はワールドスワップなどの事は覚えていない。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
また軽い休憩をとれば疲労も回復するしそもそも疲れにくい。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
以上は館和男のもつ異能であるが、古瀬圭一郎にも適用されている――が、そもそもこれは、動死体としての彼自身の特性とほぼ同じである。
その為、もし生命力を感知できる異能などを持つ人物が彼の事をよく見ればその事に気付く事は可能である。
カフェバー《白詰草》スポット
http://lisge.com/ib/talk.php?s=108
17 / 30
757 PS
ヒノデ区
Q-2
Q-2








| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 献身のマフラー | 装飾 | 97 | 魔力15 | 体力10 | - | |
| 2 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 粗削りのナイフ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 着なれたコート | 防具 | 35 | 防御10 | 火纏10 | - | |
| 6 | 痛撃用のナイフ | 武器 | 150 | 器用20 | 器用20 | - | 【射程1】 |
| 7 | ぼろぼろマフラー | 装飾 | 45 | 幸運10 | - | - | |
| 8 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 11 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 12 | 丈夫なコート | 防具 | 90 | 反護15 | 火纏10 | - | |
| 13 | ポプラ | 素材 | 25 | [武器]追風15(LV35)[防具]耐災25(LV35)[装飾]風纏25(LV40) | |||
| 14 | ネックナイフ | 武器 | 90 | 追撃10 | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 17 | |||||||
| 18 | お野菜 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV15)[効果2]幸運10(LV25)[効果3]命脈10(LV35) | |||
| 19 | お野菜 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV15)[効果2]幸運10(LV25)[効果3]命脈10(LV35) | |||
| 20 | ローズクォーツ | 装飾 | 75 | 火纏10 | 火纏10 | - | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 20 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 25 | 破壊/詠唱/火 |
| 具現 | 25 | 創造/召喚 |
| 武器 | 70 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 6 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| 練3 | デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| フィジカルブースター | 6 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| カームフレア | 6 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| 練3 | アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 |
| クリエイト:ダイナマイト | 5 | 0 | 120 | 自:道連LV増 | |
| コントラスト | 7 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| デストロイ | 6 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
| 練3 | スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| フェイタルポイント | 5 | 0 | 80 | 敵:精確痛撃 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| クリエイト:ファイアウェポン | 5 | 0 | 200 | 味:炎上LV・反火LV増 | |
| ヒートイミッター | 6 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| フレアトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵列:罠《猛火》LV増 | |
| サモン:サラマンダー | 5 | 5 | 400 | 自:サラマンダー召喚 | |
| 練3 | ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
| イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 | |
| スカーレットスキュア | 5 | 0 | 180 | 敵列:火痛撃 | |
| クリエイト:ウェポン | 5 | 0 | 280 | 味全:追撃LV増 | |
| 練3 | フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |
| 練3 | グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 |
| クリエイト:モンスター | 5 | 0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 | |
| フレイムインパクト | 6 | 0 | 230 | 敵:5連鎖火痛撃 | |
| レーヴァテイン | 5 | 0 | 330 | 自:破滅の炎LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 火の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 獄炎陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど獄炎LV増 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 集気 | 5 | 4 | 0 | 【通常攻撃後】自:次与ダメ増 | |
| 詠唱追加 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:必殺スキル強化 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
常備薬 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
鉄球の一撃 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
念道波 (ショックウェイブ) |
0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
|
調息 (パリィ) |
5 | 0 | 自:AG増(2T)+SP増 | |
|
ティータイム (ハーバルメディスン) |
0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) | |
|
カレイドスコープ (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
|
ディスカード・セブン (エファヴェセント) |
0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) | |
|
石に花咲く (ハーバルメディスン) |
0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) | |
|
若かりし頃 (ポーションラッシュ) |
0 | 240 | 味傷6:HP増 | |
|
天使の目覚まし (ドラスティックレメディ) |
0 | 160 | 味傷:精確攻撃&HP増 | |
|
シールドエナジー (ガーディアン) |
0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]光輝燦然 | [ 3 ]五月雨 | [ 3 ]グリモワール |
| [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]アラベスク | [ 3 ]アジャイルフォーム |
| [ 3 ]クリエイト:ピッチダーク | [ 3 ]クリエイト:バトルフラッグ | [ 3 ]ヴィガラスチャージ |
| [ 3 ]プリディクション |

PL / カミヤキサラ