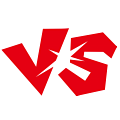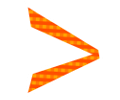<< 5:00~6:00





百物語 6話『雷尾』

『雷尾』イバラシティサイド
五月女というのは名家の筋で、なんでも華族の末裔だと、自分たちではそう言っていた。
五月女家には3人の娘がいた。上の二人は家名に恥じぬ才女であったが、
末の娘だけは、まるで不出来だった。何をやらせても一角の所まで行かず、その上に、大層わがままな娘だった。
それだから、呆れた両親も末娘だけははやくに
遠くの学校に預けてしまって、家に帰そうとはしなかったのだった。
城のような家に特上の家具、毎週の宴、五月女の家が裕福である事に疑問を持つ者はいなかった
だが、実情はというと少し妖しく霞んでいる。
父親の他にはこの家がなにをして財を手に入れているか、知る者はいなかったのだ。
末娘が16になる夜、女学院の宿舎の戸を叩くものがあった。
「お嬢様。
お嬢様。五月女の家が大変なことになってしまいました。」
末娘は、来訪者の顔に覚えがあった。姉たちの家庭教師だった人だ。
「あなたのお父さんは、雷尾との約束を破ったんだ。」
―― それはなに?父の取引先の方?
末娘の言葉を聞かずに、女は「あなたも五月女の娘だから、たたられる」
そう言い捨てて闇夜に走り去っていったのだった。
闇に風が強く吹き、木々をしならせる。
末娘は、夜冷えの中を校舎へ駆けた。
校舎裏の百葉箱。そこには『百葉箱のしぃらさん』という怪異がいて、時と次第では、子供を守ってくれると伝え聞いていた。
彼女は確かに存在していて、こっくりさんのような呪文に応じて
きまぐれに姿をあらわす。末娘はその怪談を知っていた。かくして、少女のおばけは姿を現しけらけらと笑いだした。
『雷尾というのは、ある化け物の親分ね。わたしとおなじ、怪異の類よ。貸し借りにうるさいの』
「化け物?そんな。
あの家は、五月女は私を邪魔にしたのよ。私の味方でなんかなかったのに。
それなのに、今になって巻き込まれるなんてごめんだわ!」
『もうすぐ嵐がやって来る。』
なるほど風が一層強まり、西の空では不気味な暗雲が、生物のように膨らんで迫っていた。
末娘はこきざみに震えて、しぃらさんに手を合わせる。
「何か助かる方法を教えて頂戴」
『そうね、それじゃ助けてあげましょ。
…
とっても簡単な事よ。
お部屋のクローゼットに隠れて、雷が鳴っている間は外へ出てはいけない。
嵐の夜が明けるまで隠れ続けること。
この約束だけ守ってちょうだい』
嵐だ。
末娘は風に飛ばされそうになりながら急いで部屋に戻る。
服が入ったままのクローゼットの中へ飛び込んで扉を閉めた。
道中振り出した大粒の雨に濡れて、じっとりと肌に張り付いたナイトドレスごしに、ぎゅっと体をちぢこめる。
外では間も無く雷が鳴り始めた。
ガシャン、バリ、バリ、今まで生きてきて耳にしたことの無い、大きな雷。
ゴロゴロ、バリバリ、空気を切り割いくようなおおきな大きな雷。
余りに近くにおちたためか、雷が落ちるたびにビリビリと家具が、地面が振動する。
クローゼットが震えるたび、末娘は怯えてただギュッと手をついて、
『おさまれおさまれ』と祈るばかりだった。
けれど、待てども待てども雷は鳴りやまず、
それが1時間も立てば、末娘は息の苦しさを覚えた。
―― もしかして、酸素が足りない?酸欠になりかけている?
このままこうしていたら、雷じゃあなくて、窒息して死んでしまうのでは。
不安に駆られて戸を少し開けようかと思った。
…だがその手を止めた。深呼吸して、また耐える。
五月女家への恨みと、神様への祈りを反復する。クローゼットからでさえしなければ。
息が苦しくなり、息が荒くなる。
それだけじゃない。気が付けば、汗が滝のように流れていた。
雨に濡れていたから、それかと思った。けれど生ぬるい水滴は塩の味をして、体からわき続ける。
暑い。とても暑いのだ。
―― もしかして、もしかして火事になったるんじゃ?雷はこの寮におちて、私は火に巻かれているんじゃ…
そう頭に思い描くと、末娘はたまらなく怖くなって、とうとうクローゼットの扉をこわごわ、そっと押した。
すると ――扉は、びくともしなかった。
開かない。扉があかない、もうそっとではなく、強く押した。
背側に手をついて、足でこじ開けるようにした。ダンダンと蹴りつける。
それでも扉は開かなかった。ゼイゼイと重く、息が荒くなっていく。
恐怖が満ちて、気が遠くなっていく。
『起きて。目を覚まして』
その次は、五月女の末娘は、眠りから目を覚ました。
「その声は、しぃらさん?
私、どうなったの…!火事が。雷が落ちて、外は火事なんでしょう?
息が出来なくて。それに、開かないの、私は…」
『扉があかないなんて、それはわたしが押さえてあげているだけよ。
出てはいけないって言ったでしょう。』
「それならそうといいなさいよ!
どれほど恐ろしかったか…」
『あら、知らなかった雷がうるさくて聞き取れなかったのじゃないかしら。』
末娘は怒り心頭に息を吐いて、ふと、扉の隙間から光が差し込んでいることに気付いた。
夜は明けたのだ。
「もういいから、扉を開けて」
『もういいなら、どうぞ』
バタン!勢いよく扉を開いて、末娘が部屋に転がり出る。
強い光に目が焼かれる。その眩しさの中で、
“しぃらさん”がニヤニヤ、面白いものを見るように笑っている顔が見えた。
末娘は息を詰まらせ、目を光にならそうとこじ開けた。
眩しさに適応する――必要もなく、光に包まれていた部屋が、静かに暗闇を取り戻す。
―― そんな。夜明けじゃなくて、雷光‥ねえ!私、どうなるの?
ほんのりと、“しぃらさん”が口を開くのが見えた。
けれど、バン、ゴロゴロ、続いて届く雷鳴にかき消されて、声はもう末娘に聞こえなかった。

『雷尾』アンジニティサイド
年の暮れに、西果ての魔導実験場に大きな雷が落ちて、何もかも灰になった。
それも春頃になると、悲劇の色は晴れてしまった。
哀悼褪せて、最初の盗掘者が現れたのだ。
ダルゲリオは決して悪人ではなったが、
身ごもったばかりの嫁に満足なくらしをさせようと思えば
悪にでも鬼にでもなってしまいたかった。
はじめにだれかが盗みに入ったと聞くと、
どうしても、早い者勝ちだという気持ちを起こしたのだ。
かくしてダルゲリオ、この男は粉々の瓦礫を踏みしめて、
なにか使えるものはないかと実験場跡地を散策し始めた。金目の物、金目の物。
ふと目に留まったのは、差し込む薄明かりを受けてきらめく
不思議な彫刻のされたアミュレットだった。きれいな石がはまっている。
男は何気なくそれを腕に巻いてみて、チャラチャラと一度揺らした。
高級な金属の響き。これはきっと平時なら近寄りもできない高価な魔道具に違いないと思って、そいつを懐に入れた。
男は一度アミュレットを家に持って帰り、愛妻の腕に巻いてやった。
妻は喜んで、そんな表情を見ると、男は自分の罪がむくわれるように感じた。
あたたかく、束の間のやすらぎの夕食だった。
男は自分を納得させようとの自問自答をして、夜遅くまで眠れなかった。
枕元で、ランプの光を受けてアミュレットはきらきらときらめいた。
翌日朝早く、男はアミュレットを鑑定のために質屋に持ち込んだ。
夕方に値段を聞きに来ると約束して、仕事へ出た。
だが、時刻を待たずして、その日その店が火事になった。
炎に巻かれて店主の生死も解らず、さわぎの中、男は、すすけたアミュレットを拾い上げる。
恐ろしい偶然もあるものだと思っていた。
不吉な気持ちも頭をもたげなくはないのだが、
演技が悪いには違いない。二束三文でも売り払ってしまいたいと思ったのだった。
そこで男はそのまま市場へ行って、行商人に言い値で買い取らせた。
その晩だ。また、火がおきた。
いや、今度は雷が人におちたのだ。
それどころか、質屋の出火元っていうのも、雷が落ちてきたのだという。
このような不幸が続けざまに起きれば、
男もさすがに思ったのだった。あのアミュレットが雷を呼んでいるんだと。
ところが男の罪とはこれからだった。
男は、誰にもそれを言い出さなかった。
なぜって?
盗んだ品だからだ。
それに、自分が盗んだ品のせいで二人も人が死んだなら、
このすべての罪をどうすればいいのだ。身重の妻もいるというのに、誰にも言わなければわからないことじゃないか。
男は雷が落ちたという場所へ急いでいって、
そして松明にきらきらときらめく、アミュレットを見つけた。
そして怖さのあまりに、アミュレットを用水路に投げ入れて証拠隠滅をした。
…
3日ほどたって、男を尋ねるものがあった。それは1人の魔女だった。
『アミュレットを持ち出したのは、ウワサによるとあなたね。返していただきたいの』
「そんなものはしらない。」
『知っているのよ。あのアミュレット自体に、持ち主が刻まれるのだから。
身に着けた人を順番に上書きしていくの。だけど持ち主が死ぬと、
繰り上がってそのひとつ前の持ち主の元へ所有権が帰るのよ』
男は、観念して大いに頭を下げた。
ロック鳥もかくやという大声で謝り倒し、もう用水路に捨ててしまったと白状した。
『それではいけない。探してきてちょうだい』
「もう見つかりはしないです。流れて行ってしまったはずです」
『少しでも申し訳ないと思っているなら、返してちょうだい。
あれは、捨てられたのでも忘れ去られたのでもない。あそこにおいておいたのよ。
雷を産む魔道具なの。でも失敗作。持ち主に雷をおとすものだから、封印していたようなものよ。』
男は言いなりになって、町へ降りて行って
人目もはばからず用水路、下水道あみでざぶざぶとサラって探して回った。
しかし、何も見つからない。
見つからない。陽が落ちて、地平がほの明るく燃えていた。
青ざめて肩を落とし、重たい足取りで家へと戻れば、
遠く、ぽつりと我が家は明るく燃えていた。
男は妻の名を叫び、家へと駆けた。
そうだ!あの晩妻が一度あのアミュレットを身に着けたのだ。
「そんな」「そんなことって」、顔をくしゃくしゃにして追いすがるように野原を駆ける、
男の上に雷が落ちた。
身に着けた人を順番に上書きしていくの。
だけど持ち主が死ぬと、繰り上がってそのひとつ前の持ち主の元へ所有権が帰るのよ。



ENo.205 ミツ とのやりとり

ENo.813 玲子 とのやりとり

ENo.1232 ダーシャ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.14 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










すると梅の香りとは別の、何か甘い香りが漂ってくる・・・
香りを追ってゆくと、梅の花に囲まれた売店がある。
そこに、店員?と思われるふたり。


こちらに気づく。
どうやら団子を作っているようだ。

空中に突然現れるミヨチン。
お団子を受け取り、早速ひとくち。
両手でピースサインをするふたり。
団子を食べて嬉しそうなミヨチン。
笑みを浮かべる。
ピョンっとジャンプすると、空中で姿を消した。
・・・・・身体の奥から、少し力が湧き出る感覚。
各CP・FPが2増加した!



魔法陣『槌』 と別れました。
ウルフ をエイドとして招き入れました!
サクマ(17) に 5 PS 送付しました。
使役LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
エリカ(649) により ItemNo.10 ボロ布 から防具『魔除けミサンガ』を作製してもらいました!
⇒ 魔除けミサンガ/防具:強さ60/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.9 肉の龍脈 に ItemNo.11 木瓜 を付加しました!
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.7 血曇り に ItemNo.10 駄木 を付加しました!
エリカ(649) の持つ ItemNo.16 赤い実の簪 に ItemNo.1 駄物 を付加しました!
雫玖(210) とカードを交換しました!
フィフスフレイム (バーニングチューン)
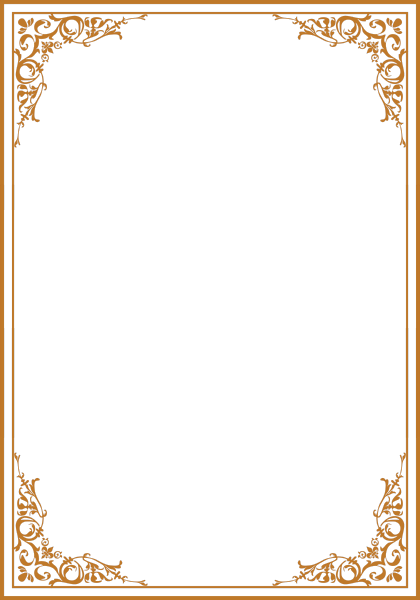
パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ファーマシー を研究しました!(深度0⇒1)
スタンピート を習得!
イービルサークル を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



悪意の魔女(103) は 古雑誌 を入手!
ダーシャ(1232) は 古雑誌 を入手!
悪意の魔女(103) は 牙 を入手!
悪意の魔女(103) は 不思議な牙 を入手!
ダーシャ(1232) は 禁断じゃない果実 を入手!
悪意の魔女(103) は 禁断じゃない果実 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
悪意の魔女(103) のもとに ウルフ が空を見上げなから近づいてきます。
悪意の魔女(103) のもとに キラークリーパー が恥ずかしそうに近づいてきます。



チナミ区 P-17(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-18(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 P-19(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 P-20(山岳)に移動!(体調19⇒18)
カミセイ区 P-1(草原)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 悪意の魔女(103) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》(ベースキャンプ外のため無効)





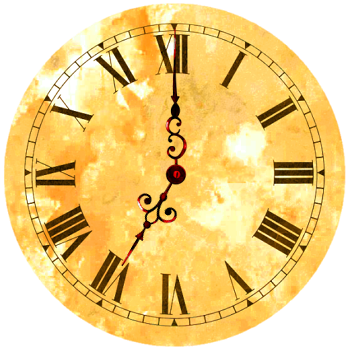
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
映し出される言葉を見て、腕を組む。


チャット画面に映し出されるふたり。
少し照れ臭そうにするエディアン。
チャットが閉じられる――














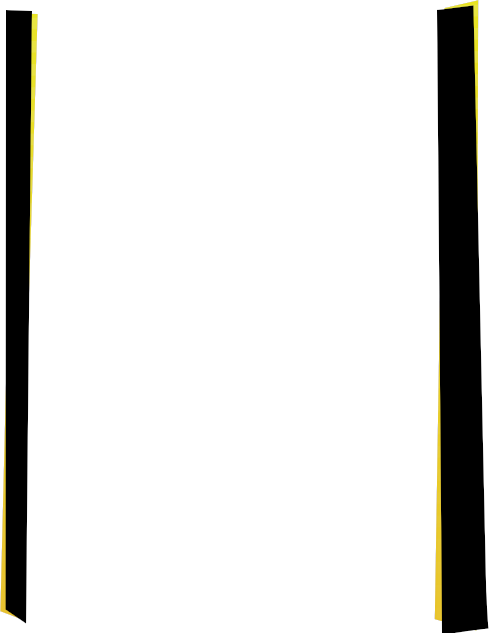
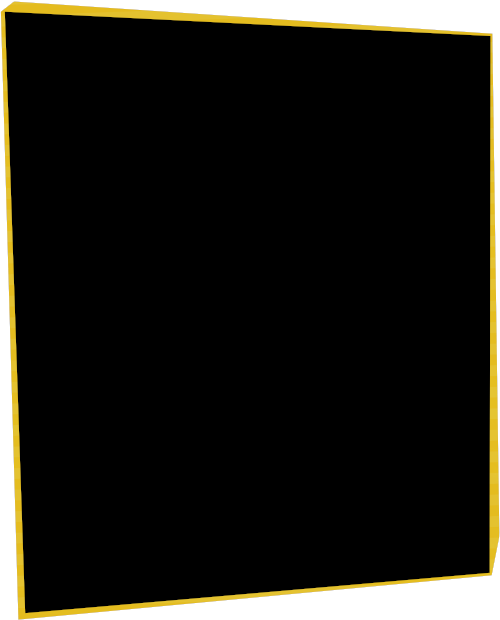





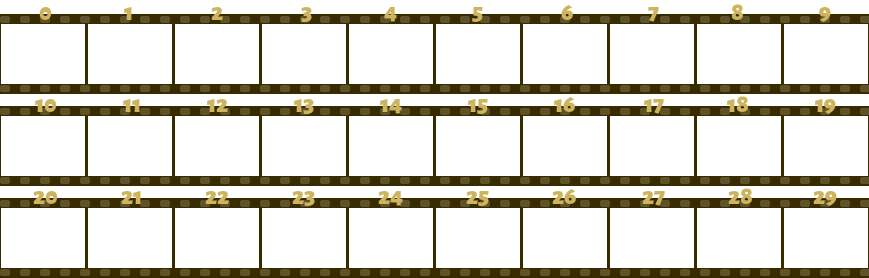




































No.1 魔法陣『錘』 (種族:ピクシー)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [戦闘:エイド2]OK. [戦闘:エイド3]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



※※ 注意 ※※
『コワイ話』です。胸の悪くなる描写があります。全体的にこのページの文章類は、あまり読まない方が良いです。

『DoRa・SiRa』
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html
『コワイ話』です。胸の悪くなる描写があります。全体的にこのページの文章類は、あまり読まない方が良いです。

『DoRa・SiRa』
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html

百物語 6話『雷尾』

『雷尾』イバラシティサイド
五月女というのは名家の筋で、なんでも華族の末裔だと、自分たちではそう言っていた。
五月女家には3人の娘がいた。上の二人は家名に恥じぬ才女であったが、
末の娘だけは、まるで不出来だった。何をやらせても一角の所まで行かず、その上に、大層わがままな娘だった。
それだから、呆れた両親も末娘だけははやくに
遠くの学校に預けてしまって、家に帰そうとはしなかったのだった。
城のような家に特上の家具、毎週の宴、五月女の家が裕福である事に疑問を持つ者はいなかった
だが、実情はというと少し妖しく霞んでいる。
父親の他にはこの家がなにをして財を手に入れているか、知る者はいなかったのだ。
末娘が16になる夜、女学院の宿舎の戸を叩くものがあった。
「お嬢様。
お嬢様。五月女の家が大変なことになってしまいました。」
末娘は、来訪者の顔に覚えがあった。姉たちの家庭教師だった人だ。
「あなたのお父さんは、雷尾との約束を破ったんだ。」
―― それはなに?父の取引先の方?
末娘の言葉を聞かずに、女は「あなたも五月女の娘だから、たたられる」
そう言い捨てて闇夜に走り去っていったのだった。
闇に風が強く吹き、木々をしならせる。
末娘は、夜冷えの中を校舎へ駆けた。
校舎裏の百葉箱。そこには『百葉箱のしぃらさん』という怪異がいて、時と次第では、子供を守ってくれると伝え聞いていた。
彼女は確かに存在していて、こっくりさんのような呪文に応じて
きまぐれに姿をあらわす。末娘はその怪談を知っていた。かくして、少女のおばけは姿を現しけらけらと笑いだした。
『雷尾というのは、ある化け物の親分ね。わたしとおなじ、怪異の類よ。貸し借りにうるさいの』
「化け物?そんな。
あの家は、五月女は私を邪魔にしたのよ。私の味方でなんかなかったのに。
それなのに、今になって巻き込まれるなんてごめんだわ!」
『もうすぐ嵐がやって来る。』
なるほど風が一層強まり、西の空では不気味な暗雲が、生物のように膨らんで迫っていた。
末娘はこきざみに震えて、しぃらさんに手を合わせる。
「何か助かる方法を教えて頂戴」
『そうね、それじゃ助けてあげましょ。
…
とっても簡単な事よ。
お部屋のクローゼットに隠れて、雷が鳴っている間は外へ出てはいけない。
嵐の夜が明けるまで隠れ続けること。
この約束だけ守ってちょうだい』
嵐だ。
末娘は風に飛ばされそうになりながら急いで部屋に戻る。
服が入ったままのクローゼットの中へ飛び込んで扉を閉めた。
道中振り出した大粒の雨に濡れて、じっとりと肌に張り付いたナイトドレスごしに、ぎゅっと体をちぢこめる。
外では間も無く雷が鳴り始めた。
ガシャン、バリ、バリ、今まで生きてきて耳にしたことの無い、大きな雷。
ゴロゴロ、バリバリ、空気を切り割いくようなおおきな大きな雷。
余りに近くにおちたためか、雷が落ちるたびにビリビリと家具が、地面が振動する。
クローゼットが震えるたび、末娘は怯えてただギュッと手をついて、
『おさまれおさまれ』と祈るばかりだった。
けれど、待てども待てども雷は鳴りやまず、
それが1時間も立てば、末娘は息の苦しさを覚えた。
―― もしかして、酸素が足りない?酸欠になりかけている?
このままこうしていたら、雷じゃあなくて、窒息して死んでしまうのでは。
不安に駆られて戸を少し開けようかと思った。
…だがその手を止めた。深呼吸して、また耐える。
五月女家への恨みと、神様への祈りを反復する。クローゼットからでさえしなければ。
息が苦しくなり、息が荒くなる。
それだけじゃない。気が付けば、汗が滝のように流れていた。
雨に濡れていたから、それかと思った。けれど生ぬるい水滴は塩の味をして、体からわき続ける。
暑い。とても暑いのだ。
―― もしかして、もしかして火事になったるんじゃ?雷はこの寮におちて、私は火に巻かれているんじゃ…
そう頭に思い描くと、末娘はたまらなく怖くなって、とうとうクローゼットの扉をこわごわ、そっと押した。
すると ――扉は、びくともしなかった。
開かない。扉があかない、もうそっとではなく、強く押した。
背側に手をついて、足でこじ開けるようにした。ダンダンと蹴りつける。
それでも扉は開かなかった。ゼイゼイと重く、息が荒くなっていく。
恐怖が満ちて、気が遠くなっていく。
『起きて。目を覚まして』
その次は、五月女の末娘は、眠りから目を覚ました。
「その声は、しぃらさん?
私、どうなったの…!火事が。雷が落ちて、外は火事なんでしょう?
息が出来なくて。それに、開かないの、私は…」
『扉があかないなんて、それはわたしが押さえてあげているだけよ。
出てはいけないって言ったでしょう。』
「それならそうといいなさいよ!
どれほど恐ろしかったか…」
『あら、知らなかった雷がうるさくて聞き取れなかったのじゃないかしら。』
末娘は怒り心頭に息を吐いて、ふと、扉の隙間から光が差し込んでいることに気付いた。
夜は明けたのだ。
「もういいから、扉を開けて」
『もういいなら、どうぞ』
バタン!勢いよく扉を開いて、末娘が部屋に転がり出る。
強い光に目が焼かれる。その眩しさの中で、
“しぃらさん”がニヤニヤ、面白いものを見るように笑っている顔が見えた。
末娘は息を詰まらせ、目を光にならそうとこじ開けた。
眩しさに適応する――必要もなく、光に包まれていた部屋が、静かに暗闇を取り戻す。
―― そんな。夜明けじゃなくて、雷光‥ねえ!私、どうなるの?
ほんのりと、“しぃらさん”が口を開くのが見えた。
けれど、バン、ゴロゴロ、続いて届く雷鳴にかき消されて、声はもう末娘に聞こえなかった。

『雷尾』アンジニティサイド
年の暮れに、西果ての魔導実験場に大きな雷が落ちて、何もかも灰になった。
それも春頃になると、悲劇の色は晴れてしまった。
哀悼褪せて、最初の盗掘者が現れたのだ。
ダルゲリオは決して悪人ではなったが、
身ごもったばかりの嫁に満足なくらしをさせようと思えば
悪にでも鬼にでもなってしまいたかった。
はじめにだれかが盗みに入ったと聞くと、
どうしても、早い者勝ちだという気持ちを起こしたのだ。
かくしてダルゲリオ、この男は粉々の瓦礫を踏みしめて、
なにか使えるものはないかと実験場跡地を散策し始めた。金目の物、金目の物。
ふと目に留まったのは、差し込む薄明かりを受けてきらめく
不思議な彫刻のされたアミュレットだった。きれいな石がはまっている。
男は何気なくそれを腕に巻いてみて、チャラチャラと一度揺らした。
高級な金属の響き。これはきっと平時なら近寄りもできない高価な魔道具に違いないと思って、そいつを懐に入れた。
男は一度アミュレットを家に持って帰り、愛妻の腕に巻いてやった。
妻は喜んで、そんな表情を見ると、男は自分の罪がむくわれるように感じた。
あたたかく、束の間のやすらぎの夕食だった。
男は自分を納得させようとの自問自答をして、夜遅くまで眠れなかった。
枕元で、ランプの光を受けてアミュレットはきらきらときらめいた。
翌日朝早く、男はアミュレットを鑑定のために質屋に持ち込んだ。
夕方に値段を聞きに来ると約束して、仕事へ出た。
だが、時刻を待たずして、その日その店が火事になった。
炎に巻かれて店主の生死も解らず、さわぎの中、男は、すすけたアミュレットを拾い上げる。
恐ろしい偶然もあるものだと思っていた。
不吉な気持ちも頭をもたげなくはないのだが、
演技が悪いには違いない。二束三文でも売り払ってしまいたいと思ったのだった。
そこで男はそのまま市場へ行って、行商人に言い値で買い取らせた。
その晩だ。また、火がおきた。
いや、今度は雷が人におちたのだ。
それどころか、質屋の出火元っていうのも、雷が落ちてきたのだという。
このような不幸が続けざまに起きれば、
男もさすがに思ったのだった。あのアミュレットが雷を呼んでいるんだと。
ところが男の罪とはこれからだった。
男は、誰にもそれを言い出さなかった。
なぜって?
盗んだ品だからだ。
それに、自分が盗んだ品のせいで二人も人が死んだなら、
このすべての罪をどうすればいいのだ。身重の妻もいるというのに、誰にも言わなければわからないことじゃないか。
男は雷が落ちたという場所へ急いでいって、
そして松明にきらきらときらめく、アミュレットを見つけた。
そして怖さのあまりに、アミュレットを用水路に投げ入れて証拠隠滅をした。
…
3日ほどたって、男を尋ねるものがあった。それは1人の魔女だった。
『アミュレットを持ち出したのは、ウワサによるとあなたね。返していただきたいの』
「そんなものはしらない。」
『知っているのよ。あのアミュレット自体に、持ち主が刻まれるのだから。
身に着けた人を順番に上書きしていくの。だけど持ち主が死ぬと、
繰り上がってそのひとつ前の持ち主の元へ所有権が帰るのよ』
男は、観念して大いに頭を下げた。
ロック鳥もかくやという大声で謝り倒し、もう用水路に捨ててしまったと白状した。
『それではいけない。探してきてちょうだい』
「もう見つかりはしないです。流れて行ってしまったはずです」
『少しでも申し訳ないと思っているなら、返してちょうだい。
あれは、捨てられたのでも忘れ去られたのでもない。あそこにおいておいたのよ。
雷を産む魔道具なの。でも失敗作。持ち主に雷をおとすものだから、封印していたようなものよ。』
男は言いなりになって、町へ降りて行って
人目もはばからず用水路、下水道あみでざぶざぶとサラって探して回った。
しかし、何も見つからない。
見つからない。陽が落ちて、地平がほの明るく燃えていた。
青ざめて肩を落とし、重たい足取りで家へと戻れば、
遠く、ぽつりと我が家は明るく燃えていた。
男は妻の名を叫び、家へと駆けた。
そうだ!あの晩妻が一度あのアミュレットを身に着けたのだ。
「そんな」「そんなことって」、顔をくしゃくしゃにして追いすがるように野原を駆ける、
男の上に雷が落ちた。
身に着けた人を順番に上書きしていくの。
だけど持ち主が死ぬと、繰り上がってそのひとつ前の持ち主の元へ所有権が帰るのよ。



ENo.205 ミツ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.813 玲子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.1232 ダーシャ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| シーラ 「(梅の木をみあげ、残念そうに笑う) 使役出来たら楽しいのに。この子たち、どうしてついてこないのかしら。」 |
 |
重く湿った咳。 |
ItemNo.14 エナジー棒 を食べました!
| ■ 「(エナジー棒を砕いてカラスたちにあげている)」 |
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









チナミ区 O-16 周辺:梅楽園
梅の木たちを退けながら進んでいく。すると梅の香りとは別の、何か甘い香りが漂ってくる・・・
香りを追ってゆくと、梅の花に囲まれた売店がある。
そこに、店員?と思われるふたり。

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
こちらに気づく。
 |
カオリ 「カグハちゃんカグハちゃん!お客さんだよぉー!!お客さんっ!!」 |
 |
カグハ 「はいお団子。カオリちゃん、具。」 |
 |
カオリ 「はいはーい!」 |
 |
カオリ 「・・・って、だからお客さんだってばーっ!!!!」 |
 |
カグハ 「うん、見えるよ。」 |
どうやら団子を作っているようだ。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
 |
ミヨチン 「おぉぉ!?これは匂いでわかる美味美味感♪」 |
空中に突然現れるミヨチン。
 |
カグハ 「わー・・・・・すごい。」 |
 |
カオリ 「うぎゃー!!なにやつぅぅーっ!!!!」 |
 |
ミヨチン 「怖いもの見たみたいなリアクション、やめてほしいっすねぇ。」 |
 |
ミヨチン 「ハイパーサイキックパワーJK☆ミヨチンっすよぉー!!」 |
 |
カオリ 「サイキック!すごい・・・!!!!」 |
 |
カグハ 「サイキック・・・・・なのかな、これ。」 |
 |
ミヨチン 「っとゆーわけで!お団子ひとつ、くださいなー!!」 |
 |
カオリ 「あ、はーい!どうぞっ!!」 |
お団子を受け取り、早速ひとくち。
 |
ミヨチン 「――これはこれはこれは!すごいっすねぇー!!超美味しいっすよぉぉ!!!!モッチモチ!!ちびっこふたりでこれ作れるならもう天下取れるっすねぇ!!」 |
 |
カオリ 「うちらの団子はサイキョーだから!」 |
 |
カグハ 「うん、サイキョー。」 |
両手でピースサインをするふたり。
団子を食べて嬉しそうなミヨチン。
 |
ミヨチン 「大!満!足ッ!!サイキョーっすねぇここ!!」 |
 |
ミヨチン 「これはいいトモダチができたっす! また今度、何かお願いしてもいいっすかー?にひひ・・・っ」 |
笑みを浮かべる。
 |
ミヨチン 「それじゃミヨチンはまた探検に!まったねーっ!!」 |
ピョンっとジャンプすると、空中で姿を消した。
・・・・・身体の奥から、少し力が湧き出る感覚。
各CP・FPが2増加した!



魔法陣『槌』 と別れました。
ウルフ をエイドとして招き入れました!
サクマ(17) に 5 PS 送付しました。
使役LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
エリカ(649) により ItemNo.10 ボロ布 から防具『魔除けミサンガ』を作製してもらいました!
⇒ 魔除けミサンガ/防具:強さ60/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
 |
エリカ 「切れると願いが叶うやつだっけ?」 |
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.9 肉の龍脈 に ItemNo.11 木瓜 を付加しました!
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.7 血曇り に ItemNo.10 駄木 を付加しました!
エリカ(649) の持つ ItemNo.16 赤い実の簪 に ItemNo.1 駄物 を付加しました!
雫玖(210) とカードを交換しました!
フィフスフレイム (バーニングチューン)
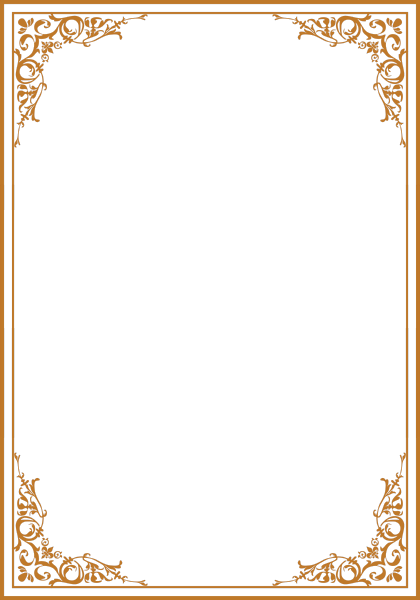
パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ファーマシー を研究しました!(深度0⇒1)
スタンピート を習得!
イービルサークル を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



悪意の魔女(103) は 古雑誌 を入手!
ダーシャ(1232) は 古雑誌 を入手!
悪意の魔女(103) は 牙 を入手!
悪意の魔女(103) は 不思議な牙 を入手!
ダーシャ(1232) は 禁断じゃない果実 を入手!
悪意の魔女(103) は 禁断じゃない果実 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
悪意の魔女(103) のもとに ウルフ が空を見上げなから近づいてきます。
悪意の魔女(103) のもとに キラークリーパー が恥ずかしそうに近づいてきます。



チナミ区 P-17(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-18(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 P-19(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 P-20(山岳)に移動!(体調19⇒18)
カミセイ区 P-1(草原)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 悪意の魔女(103) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》(ベースキャンプ外のため無効)





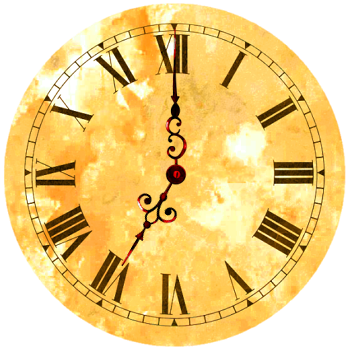
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
エディアン 「・・・おや。チェックポイントによる新たな影響があるようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「今度のは・・・・・割と分かりやすい?そういうことよね、多分。」 |
映し出される言葉を見て、腕を組む。

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
エディアン 「あら!梅楽園の、カオリちゃんとカグハちゃん?いらっしゃい!」 |
 |
カグハ 「おじゃまさまー。」 |
 |
カオリ 「へぇー、アンジニティの案内人さんやっぱり美人さん!」 |
 |
エディアン 「あ、ありがとー。褒めても何も出ませんよー?」 |
少し照れ臭そうにするエディアン。
 |
エディアン 「間接的だけど、お団子見ましたよ。美味しそうねぇあれ!」 |
 |
カオリ 「あー、チャットじゃなくて持ってくれば良かったー!」 |
 |
カグハ 「でも、危ないから・・・」 |
 |
エディアン 「えぇ、危ないからいいですよ。私が今度お邪魔しますから!」 |
 |
エディアン 「お団子、どうやって作ってるんです?」 |
 |
カオリ 「異能だよー!!私があれをこうすると具を作れてー。」 |
 |
カグハ 「お団子は私。」 |
 |
カオリ 「サイキョーコンビなのですっ!!」 |
 |
カグハ 「なのです。」 |
 |
エディアン 「すごーい・・・・・料理系の異能って便利そうねぇ。」 |
 |
カオリ 「お姉さんはどんな能力なの?」 |
 |
エディアン 「私は・・・アンジニティにいるだけあって、結構危ない能力・・・・・かなー。」 |
 |
カグハ 「危ない・・・・・」 |
 |
カオリ 「そっか、お姉さんアンジニティだもんね。なんか、そんな感じしないけど。」 |
 |
エディアン 「こう見えて凶悪なんですよぉー??ゲヘヘヘヘ・・・」 |
 |
カオリ 「それじゃ!梅楽園で待ってるねー!!」 |
 |
カグハ 「お姉さん用のスペシャルお団子、用意しとく。」 |
 |
エディアン 「わぁうれしい!!絶対行きますねーっ!!!!」 |
 |
エディアン 「ここじゃ甘いものなんて滅多に食べれなさそうだものねっ」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。





ENo.103
百葉箱のしぃらさん

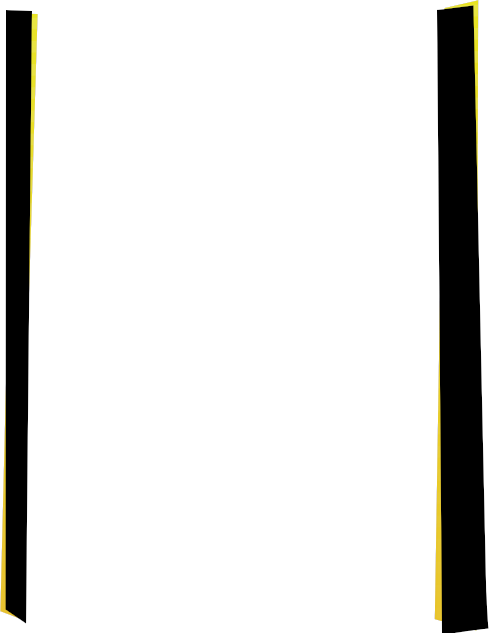
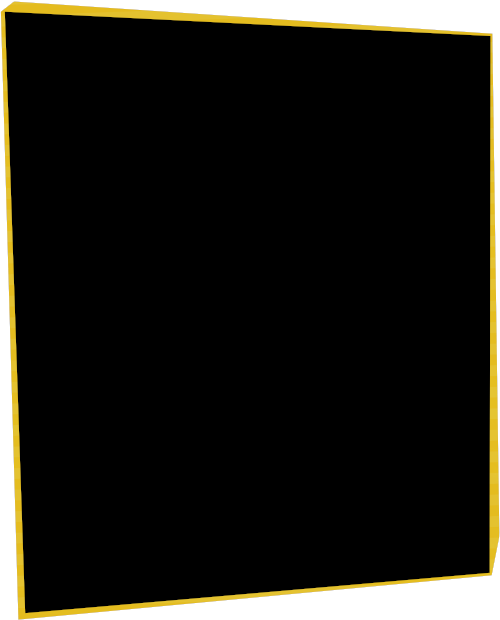
【 #荊街七不思議企画 】
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
【設定画など】https://karasuyokarasu.tumblr.com/
【アンジティ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/profdora.html
◆◇【悪意の魔女 ドーラ・シーラ】◇◆
魔法と魔物が存在する原始的なファンタジー世界、祝譚の世界≪ナタリス≫にて、魔物に知恵を与えていた科学者魔女。彼女の行いにより魔物は知力を増し人間にちかづき・人間はそれに対抗しようと武力を高め魔物にちかづき、人と魔物の戦は激化していった。
魔女の目的は人類の進化実験。彼女は研究のメインテーマに選ぶほどに、人類を愛している。
“まあ、言葉を尽くすのもそもそもナンセンスじゃないか。黒い物質を見つけたら『この世でもっとも黒い物質を新たに見つけ出せないだろうか』と ときめく、酸をみつけたら『この世でもっとも強い酸を新たに作り出せないだろうか』とときめく。科学者とはそんなもの。それが彼女のサイエンス、そしてマジック、その切実なときめきは、恋にも闘争心にもまさる、夢見心地な好奇心。とっても素敵な人類の進化をはじめましょう。”
(SICXLIVES-かつて否定の世界アンジニティが舞台だった別ゲームから継続参加)
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
【設定画など】https://karasuyokarasu.tumblr.com/
【アンジティ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/profdora.html
◆◇【悪意の魔女 ドーラ・シーラ】◇◆
魔法と魔物が存在する原始的なファンタジー世界、祝譚の世界≪ナタリス≫にて、魔物に知恵を与えていた科学者魔女。彼女の行いにより魔物は知力を増し人間にちかづき・人間はそれに対抗しようと武力を高め魔物にちかづき、人と魔物の戦は激化していった。
魔女の目的は人類の進化実験。彼女は研究のメインテーマに選ぶほどに、人類を愛している。
“まあ、言葉を尽くすのもそもそもナンセンスじゃないか。黒い物質を見つけたら『この世でもっとも黒い物質を新たに見つけ出せないだろうか』と ときめく、酸をみつけたら『この世でもっとも強い酸を新たに作り出せないだろうか』とときめく。科学者とはそんなもの。それが彼女のサイエンス、そしてマジック、その切実なときめきは、恋にも闘争心にもまさる、夢見心地な好奇心。とっても素敵な人類の進化をはじめましょう。”
(SICXLIVES-かつて否定の世界アンジニティが舞台だった別ゲームから継続参加)
17 / 30
379 PS
カミセイ区
P-1
P-1





































No.1 魔法陣『錘』 (種族:ピクシー)
 |
|
魔法陣『錘』- ・潰れ目妖精・薬草カカシ ・ハナナギトカゲ・イエロースライム のセット。 「まずはピクシーを一匹。 個体の選別は、できるだけ幸せなものが良いです、後に治癒魔法の質に関わります。材料は、魔嘱蛾6匹、オチカレハ10枚、マホローム、銀色ミミズの頭部、ジュニパーベリー、3倍希釈の魔法薬 精神強化薬少々。材料を集めたら、まずはピクシーの手足をペンチでねじりきり、はずします。事前に冷蔵庫に30分ほど入れてひやしておくと、痛みが少なくおすすめです。…」 ドーラ・シーラによって改造されたピクシー。明るい赤髪の色素は恐怖に抜け落ち、肌は石化の魔法で冷たくかたい。今はふわふわとした、蛾の羽根の集合体のようなボール状の生き物。 |
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 風特性回復 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:風属性スキルのHP増効果に風特性が影響 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]
No.2 魔法陣『旗』 (種族:歩行軍手) |
|
魔法陣『旗』- ・ウィッチプラント・ファットガス ・アイボール・プレーグネズミ のセット。 |
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| マナ | 5 | 0 | 10 | 自:消費SP減 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 背水 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど被攻撃ダメージ減 | |
| 強打 | 5 | 4 | 0 | 【自分行動前】自:次与ダメ増 |
最大EP[20]
No.3 ウルフ (種族:ウルフ) |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| 練1 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |
| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
| 見切 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 3 | カラスのフン | 大砲 | 40 | 束縛10 | - | - | 【射程4】 |
| 4 | 図録『大陸西哺乳類解剖図』 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 血錆びたサーベル | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程2】 |
| 6 | スピリチュアルピラミッド | 装飾 | 75 | 舞乱10 | - | - | |
| 7 | 魔法のフラスコ | 武器 | 75 | 攻撃10 | 体力10 | - | 【射程2】 |
| 8 | 血濡れたみつあみ | 防具 | 45 | 命脈10 | - | - | |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 魔除けミサンガ | 防具 | 60 | 敏捷10 | - | - | |
| 11 | ラベンダー | 素材 | 15 | [武器]魅了15(LV25)[防具]気合10(LV25)[装飾]魔力15(LV30) | |||
| 12 | 古雑誌 | 素材 | 20 | [武器]心酔15(LV30)[防具]鎮痛15(LV30)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
| 13 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
| 14 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 17 | てのりミミック | 武器 | 82 | 闇纏15 | 体力10 | - | 【射程1】 |
| 18 | 禁断じゃない果実 | 食材 | 5 | [効果1]攻撃5(LV5)[効果2]防御5(LV5)[効果3]器用5(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 呪術 | 20 | 呪詛/邪気/闇 |
| 使役 | 20 | エイド/援護 |
| 付加 | 50 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 初級魔法『エアロブレイク』 (ブレイク) | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 初級魔法『ウィンドスピア』 (ピンポイント) | 7 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 初級魔法『トルナド』 (クイック) | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 初級魔法『エアロブラスト』 (ブラスト) | 6 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 神経系再結合『感覚器鈍磨』 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 神経系再結合『多幸感』 (ドレイン) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 魔導具『フェロモン撒布器』 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 烏百羽・金切声 (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練2 | ストライク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| 練3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| アドレナリン | 5 | 0 | 50 | 自従傷:AT増(4T)+麻痺・衰弱をDX化 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| シュリーク | 5 | 0 | 50 | 敵貫:朦朧+自:混乱 | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 練1 | チャージ | 6 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| サモン:ウォリアー | 7 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| ワンオンキル | 5 | 0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 | |
| マリス | 5 | 0 | 120 | 自従全:AT・HATE増 | |
| 練3 | ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| マイアズマ | 5 | 0 | 150 | 敵列:猛毒+領域値[闇]3以上なら朦朧 | |
| モラール | 5 | 0 | 210 | 味全:DX増 | |
| ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
| スタンピート | 5 | 0 | 50 | 自従:AT・DX・AG増(3T) | |
| イービルサークル | 5 | 0 | 300 | 敵全:DF・闇耐性減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| シーラの眷属『下級木偶』 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| シーラの眷属『潰れ目精霊』 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| シーラの眷属『くずキマイラ』 (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| シーラの眷属『ハナナギトカゲ』 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| シーラの眷属『土くれゴーレム』 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| シーラの眷属『銀のドナテラ』 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| シーラの眷属『マジョ草』 (隠者) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魔女のくちびる (召喚強化) | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魔女のひとみ (魅惑) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 火炎避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:火耐性・炎上耐性増+他者から炎上を移される確率減 | |
| カリスマ (狂歌乱舞) | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:混乱+自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増(2T) | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
石の欠けた部分 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
グンニョリの煙 (ウィークネス) |
0 | 80 | 敵:衰弱 | |
|
幸房 (アブソーブ) |
0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
|
謎の光発生装置 (サモン:ウィスプ) |
5 | 300 | 自:ウィスプ召喚(複数可) | |
|
陰りし記憶の兵 (サモン:ウォリアー) |
5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
|
硝子の刺客 (サモン:ウォリアー) |
5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
|
フィフスフレイム (バーニングチューン) |
0 | 140 | 自:炎上+敵5:火撃&麻痺 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ファーマシー | [ 2 ]ストーンブラスト | [ 1 ]マインドボム |
| [ 1 ]フィジカルブースター | [ 1 ]ワンオンキル | [ 3 ]クリエイト:グレイル |
| [ 3 ]ダウンフォール | [ 3 ]イレイザー | [ 1 ]ティンダー |
| [ 1 ]アサルト | [ 2 ]ストライク | [ 2 ]パワフルヒール |

PL / 宮沢