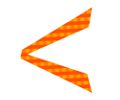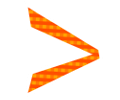<< 4:00~5:00




ぼくは両親の役に立てなかった。期待に応えられなかった。
いらない子だから捨てられて当然だ。
だから、お父さんもお母さんも悪くない。
悪いのはいつだって、ぼくひとりなんだ。
***
斑目水緒(まだらめ みずお)の異能が発現したのは4歳の時だった。
浜辺で遊んでいた水緒は、母親が一瞬目を離した隙に、波打ち際に落ちていた美しい青色の物体に目を奪われた。
子供らしい無垢で無知な好奇心故、彼は躊躇いなくそれに近付き、触れてしまった。
それが美しくも悪名高い有毒生物、カツオノエボシだということも知らずに。
カツオノエボシは例え打ち上げられた死骸であっても触れてはならない。
刺激に反応して刺胞が飛び出し、刺されることがあるからだ。
通常カツオノエボシに刺されると、傷口は赤く腫れ、電気ショックを受けたような鋭い痛みが長く続く。しかし、水緒の腕には何ヵ所かの刺し傷があるにも関わらず、腫れた様子が一切なかった。突然刺された驚きでわんわんと泣いていた水緒は、病院で処置が終わる頃にはけろりとしていた。
新薬の研究開発を仕事としていた父親は、事の顛末を聞いてこう考えた。
息子には、毒を無効化する異能が備わっている。
それは恐らく、体内に入った毒に対抗する物質を生成する異能であると。
斑目水緒の両親は共に、特定の種類の化学物質を生成する異能を持つ人間だった。故に、自分達の息子もまた"そう"であると、そう信じて疑わなかった。
それから、父親の研究所で検査を受けさせられた。
カツオノエボシの毒を投与して、血液の成分の変化を調べる検査だった。
異能によって作られた物質が何なのか。
もしもそれが未知の物質だったとしたら、それを新薬開発に転用できないか。彼の両親はそう考えたのだ。
しかし、何度か検査を行っても、水緒の体から新薬に使えそうな物質は出てこなかった。
検査方法が悪いのか。
カツオノエボシではなく、フグやイモガイなら。
それでも駄目なら、他の生物毒は。 あるいは、人工毒は。
水緒に対する検査はいつしか、実験になっていた。
毒を投与するにも血液を調べるにも注射が必要で、水緒は注射針が大嫌いになった。
土日はほとんど検査の予定で埋まり、友人はおろか両親と遊びに行くこともできなかった。
検査結果に影響が出ないように、食事も決められたものしか食べてはいけなかった。
痣のようになった注射の痕を気味悪がられて、夏でも長袖を着るようになった。
検査のことは口外してはいけないと言われていたので、あまり人と話さなくなった。
所謂生物毒でないものには異能が発動しないのか、シアン化合物を投与された時は普通に死にかけた。
小学校に上がる頃には、髪は真っ白になっていた。
それでも両親の期待に応えたくて、水緒はずっと我慢をした。
何度、どんな毒を試しても、両親の望む結果は出てこなかった。
父親が水緒を見る目は次第に冷たいものになった。
母親は検査の度に水緒を励ましたが、結果を見るといつも悲しそうな顔をした。
そうして、小学校を卒業する年。
ようやくひとつの、決定的な結果が出た。
水緒の血液から、微量の毒素が検出された。
本人に中毒症状が出たわけではない。ただ、その血はある時点から、僅かな毒性を帯びていた。
そこで初めて、血液以外の検査が行われた。
明らかになったのは、水緒の体は今まで投与された毒素を少しずつ蓄積しているということ。
汗や涙、唾液にもごく僅かな毒性が認められた。
今はまだ人に害を与えるほどの量ではないが、これ以上続ければいずれは触れるだけで周囲の人間を害するようになるかもしれない。そして、何よりも。
息子の異能は、新薬開発に役立つようなものではなかった。
両親の落胆は大きく、水緒に家での居場所はなくなった。
程なくして、水緒は遠縁の親戚に預けられた。
以来数十年、両親とは数えるほどしか顔を合わせる機会はなかった。
***
ごめんなさい。
やくにたてなくてごめんなさい。
きたいにこたえられなくてごめんなさい。
でも、がんばるから。
もっともっとがんばるから。
いたいのもさみしいのも、ぼくがまんできるから。
だから、おとうさんおかあさん。
ぼくを、




ENo.93 Eva とのやりとり

ENo.273 闇 とのやりとり

ENo.402 ジャックドゥ とのやりとり

ENo.520 チャコール とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。








フォンティ(729) に 15 PS 送付しました。
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
タウラシアス(173) の持つ ItemNo.11 ネジ から防具『メローペ』を作製しました!
フォンティ(729) により ItemNo.10 ド根性雑草 から装飾『薄紫の花びら』を作製してもらいました!
⇒ 薄紫の花びら/装飾:強さ82/[効果1]復活10 [効果2]- [効果3]-
炊飯器ちゃん!(910) とカードを交換しました!
なすー (ナース)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)
ヒーリングソング を研究しました!(深度1⇒2)
ヒーリングソング を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を習得!
肉体変調耐性 を習得!
アクアリカバー を習得!
ポイズン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





タウラシアス(173) に移動を委ねました。
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-16(森林)に移動!(体調21⇒20)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- タウラシアス(173) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- ナックラヴィー(502) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――












梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・














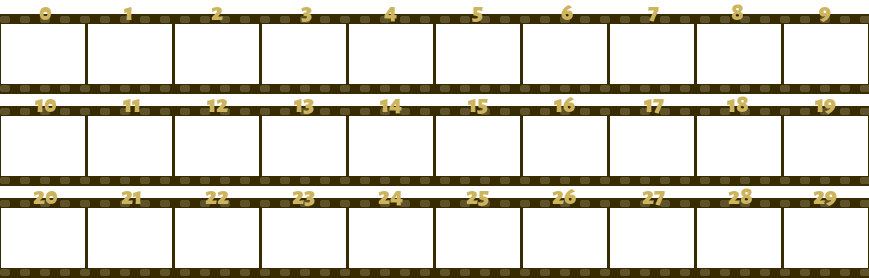







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



ぼくは両親の役に立てなかった。期待に応えられなかった。
いらない子だから捨てられて当然だ。
だから、お父さんもお母さんも悪くない。
悪いのはいつだって、ぼくひとりなんだ。
***
斑目水緒(まだらめ みずお)の異能が発現したのは4歳の時だった。
浜辺で遊んでいた水緒は、母親が一瞬目を離した隙に、波打ち際に落ちていた美しい青色の物体に目を奪われた。
子供らしい無垢で無知な好奇心故、彼は躊躇いなくそれに近付き、触れてしまった。
それが美しくも悪名高い有毒生物、カツオノエボシだということも知らずに。
カツオノエボシは例え打ち上げられた死骸であっても触れてはならない。
刺激に反応して刺胞が飛び出し、刺されることがあるからだ。
通常カツオノエボシに刺されると、傷口は赤く腫れ、電気ショックを受けたような鋭い痛みが長く続く。しかし、水緒の腕には何ヵ所かの刺し傷があるにも関わらず、腫れた様子が一切なかった。突然刺された驚きでわんわんと泣いていた水緒は、病院で処置が終わる頃にはけろりとしていた。
新薬の研究開発を仕事としていた父親は、事の顛末を聞いてこう考えた。
息子には、毒を無効化する異能が備わっている。
それは恐らく、体内に入った毒に対抗する物質を生成する異能であると。
斑目水緒の両親は共に、特定の種類の化学物質を生成する異能を持つ人間だった。故に、自分達の息子もまた"そう"であると、そう信じて疑わなかった。
それから、父親の研究所で検査を受けさせられた。
カツオノエボシの毒を投与して、血液の成分の変化を調べる検査だった。
異能によって作られた物質が何なのか。
もしもそれが未知の物質だったとしたら、それを新薬開発に転用できないか。彼の両親はそう考えたのだ。
しかし、何度か検査を行っても、水緒の体から新薬に使えそうな物質は出てこなかった。
検査方法が悪いのか。
カツオノエボシではなく、フグやイモガイなら。
それでも駄目なら、他の生物毒は。 あるいは、人工毒は。
水緒に対する検査はいつしか、実験になっていた。
毒を投与するにも血液を調べるにも注射が必要で、水緒は注射針が大嫌いになった。
土日はほとんど検査の予定で埋まり、友人はおろか両親と遊びに行くこともできなかった。
検査結果に影響が出ないように、食事も決められたものしか食べてはいけなかった。
痣のようになった注射の痕を気味悪がられて、夏でも長袖を着るようになった。
検査のことは口外してはいけないと言われていたので、あまり人と話さなくなった。
所謂生物毒でないものには異能が発動しないのか、シアン化合物を投与された時は普通に死にかけた。
小学校に上がる頃には、髪は真っ白になっていた。
それでも両親の期待に応えたくて、水緒はずっと我慢をした。
何度、どんな毒を試しても、両親の望む結果は出てこなかった。
父親が水緒を見る目は次第に冷たいものになった。
母親は検査の度に水緒を励ましたが、結果を見るといつも悲しそうな顔をした。
そうして、小学校を卒業する年。
ようやくひとつの、決定的な結果が出た。
水緒の血液から、微量の毒素が検出された。
本人に中毒症状が出たわけではない。ただ、その血はある時点から、僅かな毒性を帯びていた。
そこで初めて、血液以外の検査が行われた。
明らかになったのは、水緒の体は今まで投与された毒素を少しずつ蓄積しているということ。
汗や涙、唾液にもごく僅かな毒性が認められた。
今はまだ人に害を与えるほどの量ではないが、これ以上続ければいずれは触れるだけで周囲の人間を害するようになるかもしれない。そして、何よりも。
息子の異能は、新薬開発に役立つようなものではなかった。
両親の落胆は大きく、水緒に家での居場所はなくなった。
程なくして、水緒は遠縁の親戚に預けられた。
以来数十年、両親とは数えるほどしか顔を合わせる機会はなかった。
***
ごめんなさい。
やくにたてなくてごめんなさい。
きたいにこたえられなくてごめんなさい。
でも、がんばるから。
もっともっとがんばるから。
いたいのもさみしいのも、ぼくがまんできるから。
だから、おとうさんおかあさん。
ぼくを、

斑目 水緒
生物毒を無効化する異能を持つ少年。
両親は薬学系の研究者だった。
両親は薬学系の研究者だった。



ENo.93 Eva とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.273 闇 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
| |||||
ENo.402 ジャックドゥ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.520 チャコール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。







フォンティ(729) に 15 PS 送付しました。
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
タウラシアス(173) の持つ ItemNo.11 ネジ から防具『メローペ』を作製しました!
フォンティ(729) により ItemNo.10 ド根性雑草 から装飾『薄紫の花びら』を作製してもらいました!
⇒ 薄紫の花びら/装飾:強さ82/[効果1]復活10 [効果2]- [効果3]-
 |
フォンティ 「これで間違いないだろうか」 |
炊飯器ちゃん!(910) とカードを交換しました!
なすー (ナース)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)
ヒーリングソング を研究しました!(深度1⇒2)
ヒーリングソング を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を習得!
肉体変調耐性 を習得!
アクアリカバー を習得!
ポイズン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





タウラシアス(173) に移動を委ねました。
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-16(森林)に移動!(体調21⇒20)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- タウラシアス(173) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- ナックラヴィー(502) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――











チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・





ENo.502
藻噛 叢馬



藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
20 / 30
309 PS
チナミ区
P-16
P-16




















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 海棲馬の蹄 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 幻想藻の鬣 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | わたあめ | 料理 | 45 | 治癒13 | 充填13 | 増幅13 | |
| 7 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]幸運10(LV20) | |||
| 8 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]体力10(LV10)[装飾]増勢10(LV25) | |||
| 9 | 巻き込んだ石ころ | 魔晶 | 20 | 幸運10 | - | 充填6 | |
| 10 | 薄紫の花びら | 装飾 | 82 | 復活10 | - | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 13 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 14 | ラベンダー | 素材 | 15 | [武器]魅了15(LV25)[防具]気合10(LV25)[装飾]魔力15(LV30) | |||
| 15 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 防具 | 45 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| カース | 6 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| 決1 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| ボロウライフ | 6 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| 決3 | アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 |
| 決1 | アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 決3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 異形の膂力 (猛攻) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 怪物の体躯 (堅守) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 否定への憤怒 (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 幻想海・サルガッソー (五月雨) | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
夢喰花 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
≪s@4dw≫ (ダークネス) |
0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
|
塩弾 (ストーンブラスト) |
0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
|
大咆哮 (ブレイブハート) |
0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
|
なすー (ナース) |
0 | 180 | 味傷5:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]ノーマライズ | [ 3 ]リザレクション |
| [ 3 ]ヒーリングソング | [ 3 ]ナース | [ 3 ]ファーマシー |

PL / こか