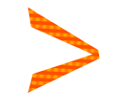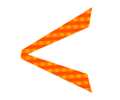<< 1:00~2:00




王歴325年。王城は混乱の只中にあった。
万を越す民衆によって叫ばれた自由革命。
どこから入手したのか手に手に武器を携えた暴徒達が、離反した一部の騎士団によって城中へと引き入れられた。
建国王の銅像は引き倒され、美しかった薔薇園は踏み荒らされ、上等の絨毯は既に血と死体が積み上げられている。
騎士達は多勢に無勢によって囲まれ、幾人かを相打ちにしては引き倒されて縊り殺された。
隠れ潜んでいた侍女たちは見つかり次第に引きずり出されて、その場で嬲られていた。
革命を叫ぶ民衆たちの狼藉が、城の全ての歴史と伝統を破壊していく最中。
まだ柱の金箔が剥がされていない廊下を急ぐ、2つの影があった。


廊下の先の一室には隠し通路があり、そこにたどり着けさえすれば、後は校外まで逃れられる。
しかし、隠し通路の入り口を開くには一定数の複雑な操作を要する。
それにかかる時間を思うと、既に怒声と剣戟の音はあまりにも近い。
────このままでは逃げ切れない。
それを悟った騎士は廊下の中腹で立ち止まり、少年へと告げた。
「この先はどうかお一人で」
少年は同じく足を止め、戸惑った。
無論、騎士の意図を理解はしている。
それでもすぐに気持ちを切り替えて進める程彼は冷酷ではなく、騎士に対して思い入れがあり、そして幼かった。
騎士もその事を理解してはいたが、それを慮る事のできる事態では無かった。
騎士は元々、どこの者とも知れぬ流れ者だった。
この国の者とは異形とも言える程異なる容貌を持ち、薄汚れた衣服を纏って、貧民街の路地で物乞いをしていた。
城下をお忍びで散策していた王子がそれを見つけ、物珍しさと好奇心から、まるで犬猫のように城へと連れて帰ったのだ。
城の者達は始めは王子の一時の気まぐれに過ぎないと見ていたが、王子がその男を己の護衛にすると言い出せば流石に苦言を呈した。
ましてや騎士叙勲を与えるとなれば苦言は猜疑となって降り注ぐ。
時にそれは実態を持って害を成したが、男はその全てを忠勤と、何より実力でもって跳ね除けた。
そして男は騎士となり、近衛として王子の側でその身を護っていた。
この革命の日までは。
尚も足を進めない少年に対し騎士は再度、視線によって強く促す。それでも動かなければ、兜の面頬を上げ────

何度命じられても頑なに「殿下」の呼称しか用いず、一度も呼んだ事のなかった少年の名。
それを口にした。
聞いた少年は瞠目し、目を伏せ、一度だけ強く唇を噛み締めた。
その後踵を返して、廊下の奥へと走り去っていった。
騎士は笑んで面頬を下げ直し、そして剣を抜いた。
音が近い。あの曲がり角からすぐにでも、狼藉者たちが顔を出すはずだ。
民衆が手にしていた武器や騎士団への内通の手はずからして、隣国の者の煽動があったのだろう。
だとすれば革命が成った後、この国は必ず割れる。
パイの切り分けを巡る争いで、この城で流れた何倍もの血を民自身が流す事になる。
皇族の血筋は割れた国を再び一つに纏める唯一の希望となろう。何があっても、絶やしてはならない。
故に、自分のするべき事は唯一つ。
出来る限り、時間を稼ぐこと。
そこに自分の命を守る事は含まれない。それを再度心に決めて、駆け出した。
廊下に屍が重なり合って、山を成している。
ある者は胸から滝の如く血を流し、ある者は首を折られ、ある者は袈裟懸けに斬りつけられた裂傷が、腰の近くまで及んでいた。
床に流れた血の量はもはや血の湖と呼ぶべき大きさで、元の絨毯の色などはもうどこにも見当たらない。
その中心に、騎士が立っていた。
鎧は全身が打撃痕で歪み、またあらゆるところにクロスボウのボルトが突き立っている。
腕の片方の手甲が外れ、そこから覗く腕は明後日の方向に捻じ折れ、それでも、無事なもう片方の手には剣を握り、立っていた。
血の湖の上にはもう騎士以外生者は居ない。まだ生きている者たちは皆屍の山の向こう側にいて、前列で槍を並べるか、後列でクロスボウを構えていた。
この陣形を取られてから、新たな死体は一つも増えていない。騎士もまだ倒れてはいなかったが、既に動きは酷く鈍い。
一矢、クロスボウが放たれ、足甲を貫いて膝の皿を砕いた。体勢が崩折れ、咄嗟に剣を杖代わりにしようとしたその手に、第二矢が突き立つ。
もはや体勢を保つ事は能わず、突っ伏して血の湖を舐め、それでも尚敵を睨視せんと背筋の力だけで面を上げる。
その眉間へと、第三矢が突き刺さった。
この城の最後の騎士がようやく動かなくなった。
それを見届け、群衆の中で一際声を大きく張り上げ、現在のこの陣形を指示していた男が胸を撫で下ろした。
男は一刻も早く、皇太子の確保をしなければならかったい。
それを取り逃がせば、この城の他のどの人物よりも男の”仕事”に差し障る。
だからこそいち早く駆け出し、倒れ伏した騎士の死体の上を跨ぎ、足早に廊下の奥へと向かわんとして。
その足首を、緑色の手が掴んだ。



ENo.466 ■■の■■ とのやりとり

ENo.1262 ヴェイナス とのやりとり

以下の相手に送信しました




白の書物:カスミ(257) から 不思議な石 を手渡しされました。









解析LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
リュジアプローシ(1224) により ItemNo.6 真っ白のまるいもの に ItemNo.7 真っ白のどろどろの液体 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
リュジアプローシ(1224) の持つ ItemNo.2 駄物 から装飾『虚像のケニンギ・チャーム』を作製しました!
藍浦英里織(1034) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『常磐の教鞭』を作製してもらいました!
⇒ 常磐の教鞭/武器:強さ40/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
白の書物:カスミ(257) により ItemNo.8 パンの耳 から料理『真っ白の焦げたもの』をつくってもらいました!
⇒ 真っ白の焦げたもの/料理:強さ40/[効果1]体力10 [効果2]幸運10 [効果3]活力10
ヴェイナス(1262) により ItemNo.5 緑石の丸盾 に ItemNo.9 不思議な石 を付加してもらいました!
⇒ 緑石の丸盾/防具:強さ35/[効果1]防御10 [効果2]防御10 [効果3]-/特殊アイテム
くるい(69) とカードを交換しました!
殻砕拳闘 (デストロイ)

五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:グレイル を研究しました!(深度0⇒1)
ヘイルカード を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を習得!
☆リザレクション を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



白の書物:カスミ(257) は 大軽石 を入手!
ミドリヤマ(949) は 大軽石 を入手!
藍浦英里織(1034) は 大軽石 を入手!
ヴェイナス(1262) は 藍鉄鉱 を入手!
藍浦英里織(1034) は 針 を入手!
ミドリヤマ(949) は 牙 を入手!
白の書物:カスミ(257) は 吸い殻 を入手!
白の書物:カスミ(257) は 何か固い物体 を入手!



白の書物:カスミ(257) に移動を委ねました。
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)
採集はできませんでした。
- 白の書物:カスミ(257) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

Cross+Roseの音量を調整する。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



王歴325年。王城は混乱の只中にあった。
万を越す民衆によって叫ばれた自由革命。
どこから入手したのか手に手に武器を携えた暴徒達が、離反した一部の騎士団によって城中へと引き入れられた。
建国王の銅像は引き倒され、美しかった薔薇園は踏み荒らされ、上等の絨毯は既に血と死体が積み上げられている。
騎士達は多勢に無勢によって囲まれ、幾人かを相打ちにしては引き倒されて縊り殺された。
隠れ潜んでいた侍女たちは見つかり次第に引きずり出されて、その場で嬲られていた。
革命を叫ぶ民衆たちの狼藉が、城の全ての歴史と伝統を破壊していく最中。
まだ柱の金箔が剥がされていない廊下を急ぐ、2つの影があった。

年若い少年
まだ年幼い少年。上質な真紅のマントを身に着け、急ぐ足取りの中にも気品が残る。

鎧を着た男
騎士。少年の護衛。略式とはいえ金属鎧を着込んだ上で極力足音を立てないその動きは熟達を感じさせる。
廊下の先の一室には隠し通路があり、そこにたどり着けさえすれば、後は校外まで逃れられる。
しかし、隠し通路の入り口を開くには一定数の複雑な操作を要する。
それにかかる時間を思うと、既に怒声と剣戟の音はあまりにも近い。
────このままでは逃げ切れない。
それを悟った騎士は廊下の中腹で立ち止まり、少年へと告げた。
「この先はどうかお一人で」
少年は同じく足を止め、戸惑った。
無論、騎士の意図を理解はしている。
それでもすぐに気持ちを切り替えて進める程彼は冷酷ではなく、騎士に対して思い入れがあり、そして幼かった。
騎士もその事を理解してはいたが、それを慮る事のできる事態では無かった。
騎士は元々、どこの者とも知れぬ流れ者だった。
この国の者とは異形とも言える程異なる容貌を持ち、薄汚れた衣服を纏って、貧民街の路地で物乞いをしていた。
城下をお忍びで散策していた王子がそれを見つけ、物珍しさと好奇心から、まるで犬猫のように城へと連れて帰ったのだ。
城の者達は始めは王子の一時の気まぐれに過ぎないと見ていたが、王子がその男を己の護衛にすると言い出せば流石に苦言を呈した。
ましてや騎士叙勲を与えるとなれば苦言は猜疑となって降り注ぐ。
時にそれは実態を持って害を成したが、男はその全てを忠勤と、何より実力でもって跳ね除けた。
そして男は騎士となり、近衛として王子の側でその身を護っていた。
この革命の日までは。
尚も足を進めない少年に対し騎士は再度、視線によって強く促す。それでも動かなければ、兜の面頬を上げ────

鎧を着た男
この国の皇太子に見出され、その近衛騎士として命尽きるまで忠義を捧げる男。全身が緑色。
何度命じられても頑なに「殿下」の呼称しか用いず、一度も呼んだ事のなかった少年の名。
それを口にした。
聞いた少年は瞠目し、目を伏せ、一度だけ強く唇を噛み締めた。
その後踵を返して、廊下の奥へと走り去っていった。
騎士は笑んで面頬を下げ直し、そして剣を抜いた。
音が近い。あの曲がり角からすぐにでも、狼藉者たちが顔を出すはずだ。
民衆が手にしていた武器や騎士団への内通の手はずからして、隣国の者の煽動があったのだろう。
だとすれば革命が成った後、この国は必ず割れる。
パイの切り分けを巡る争いで、この城で流れた何倍もの血を民自身が流す事になる。
皇族の血筋は割れた国を再び一つに纏める唯一の希望となろう。何があっても、絶やしてはならない。
故に、自分のするべき事は唯一つ。
出来る限り、時間を稼ぐこと。
そこに自分の命を守る事は含まれない。それを再度心に決めて、駆け出した。
廊下に屍が重なり合って、山を成している。
ある者は胸から滝の如く血を流し、ある者は首を折られ、ある者は袈裟懸けに斬りつけられた裂傷が、腰の近くまで及んでいた。
床に流れた血の量はもはや血の湖と呼ぶべき大きさで、元の絨毯の色などはもうどこにも見当たらない。
その中心に、騎士が立っていた。
鎧は全身が打撃痕で歪み、またあらゆるところにクロスボウのボルトが突き立っている。
腕の片方の手甲が外れ、そこから覗く腕は明後日の方向に捻じ折れ、それでも、無事なもう片方の手には剣を握り、立っていた。
血の湖の上にはもう騎士以外生者は居ない。まだ生きている者たちは皆屍の山の向こう側にいて、前列で槍を並べるか、後列でクロスボウを構えていた。
この陣形を取られてから、新たな死体は一つも増えていない。騎士もまだ倒れてはいなかったが、既に動きは酷く鈍い。
一矢、クロスボウが放たれ、足甲を貫いて膝の皿を砕いた。体勢が崩折れ、咄嗟に剣を杖代わりにしようとしたその手に、第二矢が突き立つ。
もはや体勢を保つ事は能わず、突っ伏して血の湖を舐め、それでも尚敵を睨視せんと背筋の力だけで面を上げる。
その眉間へと、第三矢が突き刺さった。
この城の最後の騎士がようやく動かなくなった。
それを見届け、群衆の中で一際声を大きく張り上げ、現在のこの陣形を指示していた男が胸を撫で下ろした。
男は一刻も早く、皇太子の確保をしなければならかったい。
それを取り逃がせば、この城の他のどの人物よりも男の”仕事”に差し障る。
だからこそいち早く駆け出し、倒れ伏した騎士の死体の上を跨ぎ、足早に廊下の奥へと向かわんとして。
その足首を、緑色の手が掴んだ。



ENo.466 ■■の■■ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1262 ヴェイナス とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
白の書物:カスミ 「記念すべき対イバラシティ第一戦!」「大々々々々勝利ー!」「がんがんががーん!」「ビクトリー!」「勝利のぶいっだ!」「やんややんやー」 |
 |
白の書物:カスミ 「ヴェイナスさんは策略家!」「他所のことまでようく知っている!」「すてきな博士さんなのかしら!」「魔法使いに脳みそを貰ったカカシさんなのかしら?」「改めて今後ともよろしくお願いしますわ!」 |
 |
白の書物:カスミ 「にしてもハザマの道って険しいのね!」「元気ポイントが目減りしていくのが見えるわ」「気球でもあればいいのに」「空飛ぶ絨毯でもあればいいのに!」「歩く草の大群を従えてえっさほいさ運んでほしいくらいだわ!」 *畳二畳ほどもある巨大な本は宙を浮きながら移動している。その頁から身を乗り出す人型は、無数の口でやかましく喋り続けている。 「人使いの荒いワールドスワップですこと!」「私達は殆ど人型の一行なのだから気を利かせてほしいわ」」 |
 |
ヴェイナス 「ああ、目的さえ……なら私としても気が楽です。期待以上の働きを約束しますよ。」 「白いお嬢さんも、これからよろしく」 |
白の書物:カスミ(257) から 不思議な石 を手渡しされました。





ミハクサマ親衛隊
|
 |
欠けた蜜蝋
|



解析LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
リュジアプローシ(1224) により ItemNo.6 真っ白のまるいもの に ItemNo.7 真っ白のどろどろの液体 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
| リュジアプローシ 「ᚾᛖᚹ ᛈᚩᚹᛖᚱ…」 |
リュジアプローシ(1224) の持つ ItemNo.2 駄物 から装飾『虚像のケニンギ・チャーム』を作製しました!
藍浦英里織(1034) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『常磐の教鞭』を作製してもらいました!
⇒ 常磐の教鞭/武器:強さ40/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
藍浦英里織 「紹介しよう。此れは只硬く、変わらず、曲がらないだけの金属製の棒だ。其れなりに長く、持ち手は存在するから、硬鞭としては使えるだろう。 ……教育的指導には、小細工なんて必要ありやがらないだろうが。死なないなら死ぬまで殴れるよな?」 |
 |
藍浦英里織 「……嗚呼、持ち手には、緑色に変わると、鉄の棘を掌に深く突き刺す機構がある。取り落とさなくて安心だな。 棘からはお前の体内にお好みの液体が注入出来る。強酸と猛毒は用意してやった。好きなのを選べよ。」 |
白の書物:カスミ(257) により ItemNo.8 パンの耳 から料理『真っ白の焦げたもの』をつくってもらいました!
⇒ 真っ白の焦げたもの/料理:強さ40/[効果1]体力10 [効果2]幸運10 [効果3]活力10
 |
白の書物:カスミ 「真っ白だけど真っ黒だわ!」「真っ黒だけど真っ白だわ!」「……おかしいわ?」「パンの耳を砂糖でまぶして揚げるだけのフレンチなものになるはずだったのに」「火加減?」「まごころ?」「ケミカルX?」「私達に足りないの、どーれだ!」 |
ヴェイナス(1262) により ItemNo.5 緑石の丸盾 に ItemNo.9 不思議な石 を付加してもらいました!
⇒ 緑石の丸盾/防具:強さ35/[効果1]防御10 [効果2]防御10 [効果3]-/特殊アイテム
 |
ヴェイナス 「これでその盾もより固くなるでしょう。」 |
くるい(69) とカードを交換しました!
殻砕拳闘 (デストロイ)

五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:グレイル を研究しました!(深度0⇒1)
ヘイルカード を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を習得!
☆リザレクション を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



白の書物:カスミ(257) は 大軽石 を入手!
ミドリヤマ(949) は 大軽石 を入手!
藍浦英里織(1034) は 大軽石 を入手!
ヴェイナス(1262) は 藍鉄鉱 を入手!
藍浦英里織(1034) は 針 を入手!
ミドリヤマ(949) は 牙 を入手!
白の書物:カスミ(257) は 吸い殻 を入手!
白の書物:カスミ(257) は 何か固い物体 を入手!



白の書物:カスミ(257) に移動を委ねました。
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)
採集はできませんでした。
- 白の書物:カスミ(257) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
エディアン 「わぁこんにちはノウレットさーん! えーと音量音量・・・コンフィグかな?」 |
Cross+Roseの音量を調整する。
 |
エディアン 「よし。・・・・・さて、どうしました?ノウレットちゃん。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたッ!」 |
 |
エディアン 「おや、てっきりあのざっくりした説明だけなのかと。」 |
 |
ノウレット 「お役に立てそうで嬉しいです!!」 |
 |
エディアン 「よろしくお願いしまーす。」 |
 |
ノウレット 「ではでは・・・・・ジャーンッ!こちらがロスト情報ですよー!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
エディアン 「なるほど、いろんなかたがいますねぇ。 彼らの願望を叶えることで影響力を得て、ハザマで強くもなれるんですか。」 |
 |
エディアン 「どこにいるかとか、願望の内容とか、そういうのは分かります?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「むむむ・・・・・頑張って見つけないといけませんねぇ。 こう、ロストには頭にマークが付いてるとか・・・そういうのは?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・システムメッセージなのかなこれ。 ・・・ノウレットちゃんの好きなものは?」 |
 |
ノウレット 「肉ですッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・嫌いなものは?」 |
 |
ノウレット 「白南海さん、です・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・さては何かしましたね、彼。」 |
 |
エディアン 「では、ロスト情報もそこそこ気にしながら進めていきましょう!」 |
 |
ノウレット 「ファイトでーすッ!!」 |
チャットが閉じられる――







塵も積もれば鱒となる
|
 |
『欠けた蜜蝋』
|


ENo.949
緑山 八百



「いやぁ、ちゃんと就職できて良かった~」
・緑山 八百 (みどりやま はっぴゃく)
公立爆波津中学校の異能指導教員にして3-B 担任。担当科目は理科だが、生物の高校教員免許も持っているらしい。28歳。
授業はしっかりするものの特に厳しくもなく、宿題も緩めだが、小テストの出題範囲がエグいと評判。
生徒としっかりとコミュニケーションが取れているに越した事はないが、生徒たちには生徒たちの世界があり、教師に理解できない部分があるのは当然の事だと考えている。
そのため、ハメを外している生徒を見てもそこまで注意はしない。
本人自身、宿直室に各種テレビゲーム機をこっそりと隠しているし、こっそり副業もしている。
・異能
『全身緑色』”オールグリーン”
あらゆるものを緑色にする異能。
この異能の影響でミドリヤマの全身は緑色になっている。
身につけているものなどの『自分の一部だと認識しているもの』も緑色になるので、諦めて最初から緑色の服を買うようにしている。ミドリヤマの意思でONOFF不可。
という風に公的には届け出ているが、ミドリヤマが全身緑色になっているのは、かつてイバラシティに存在した別の人物の異能によるもの。
『我が身に及ぶ危害無し』”オールグリーン”。それがミドリヤマの異能である。
解像度が高い方のプロフィール及び22~28番アイコンはコミッションにて@nkmn様より。ありがとうございました。
自らの選択による同一性の破壊こそが理不尽な永遠という病を終わらせる真の理(みずからのせんたくによるどういつせいのはかいこそがりふじんなえいえんというやまいをおわらせるまことのことわり)
略してミドリヤマ。
・緑山 八百 (みどりやま はっぴゃく)
公立爆波津中学校の異能指導教員にして3-B 担任。担当科目は理科だが、生物の高校教員免許も持っているらしい。28歳。
授業はしっかりするものの特に厳しくもなく、宿題も緩めだが、小テストの出題範囲がエグいと評判。
生徒としっかりとコミュニケーションが取れているに越した事はないが、生徒たちには生徒たちの世界があり、教師に理解できない部分があるのは当然の事だと考えている。
そのため、ハメを外している生徒を見てもそこまで注意はしない。
本人自身、宿直室に各種テレビゲーム機をこっそりと隠しているし、こっそり副業もしている。
・異能
『全身緑色』”オールグリーン”
あらゆるものを緑色にする異能。
この異能の影響でミドリヤマの全身は緑色になっている。
身につけているものなどの『自分の一部だと認識しているもの』も緑色になるので、諦めて最初から緑色の服を買うようにしている。ミドリヤマの意思でONOFF不可。
という風に公的には届け出ているが、ミドリヤマが全身緑色になっているのは、かつてイバラシティに存在した別の人物の異能によるもの。
『我が身に及ぶ危害無し』”オールグリーン”。それがミドリヤマの異能である。
解像度が高い方のプロフィール及び22~28番アイコンはコミッションにて@nkmn様より。ありがとうございました。
自らの選択による同一性の破壊こそが理不尽な永遠という病を終わらせる真の理(みずからのせんたくによるどういつせいのはかいこそがりふじんなえいえんというやまいをおわらせるまことのことわり)
略してミドリヤマ。
15 / 30
142 PS
チナミ区
P-9
P-9







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 緑色の鱗 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 緑石の丸盾 | 防具 | 35 | 防御10 | 防御10 | - | |
| 6 | 常磐の教鞭 | 武器 | 40 | 治癒10 | - | - | 【射程1】 |
| 7 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 8 | 真っ白の焦げたもの | 料理 | 40 | 体力10 | 幸運10 | 活力10 | |
| 9 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 装飾 | 30 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決1 | 蛍光色の液体 (ヒールポーション) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| 決1 | マナポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 |
| 決1 | 夜空の星 (ファーマシー) | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| 決1 | リザレクション | 5 | 0 | 150 | 味傷:HP増+瀕死ならHP増 |
| 決1 | 安寧の帳 (インフェクシャスキュア) | 6 | 0 | 140 | 味列:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 対症下薬 | 5 | 3 | 0 | 【HP回復後】対:変調軽減+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| 不変世界の住人 (薬師) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
プスっとする (ペネトレイト) |
0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 決1 |
生の活力を君に (インフェクシャスキュア) |
0 | 140 | 味列:HP増 |
|
殻砕拳闘 (デストロイ) |
0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヘイルカード | [ 1 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]アクアヒール |
| [ 1 ]五月雨 | [ 3 ]イレイザー | [ 2 ]イグニス |

PL / あどそん