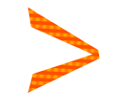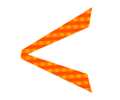<< 1:00~2:00




◇イバラシティ 某日 病院の一室
白い部屋の中、白いベッドに少女が横になっている。
白く細い肢体にいくつもの管が通っており、口には呼吸器が取り付けられていた。
部屋の中には彼女の両親と担当医が向かい合って座っており、規則的な電子音を響かせるベッドサイドモニタには、彼女の生存を示す数字が示されている。
少女の胸は静かに上下しているものの、ものかなり長い時間この状態のまま喋ることも、動くこともなく、触れても瞬きひとつさえ反応を示すことさえ無いまま生かされ続けてきていた。
胃には直接管を通され、定期的に巡回する看護師によって水分と栄養とが流し込まれて。
少女は既に植物状態だった。
「……残念ですが、これ以上は回復の見込みがありません。
延命は可能ですが、目を覚ます可能性は限りなく低いでしょう」
白衣を着た初老の男性は最初にそう前置きした上で、重苦しい雰囲気のまま続けて事務的に説明責任を果たしていく。その言葉の中には医療スタッフの力不足を謝罪する文面や、延命を続ける際の高額な費用についての説明など含まれており、
「嘘……嘘よ……だって、こんなにも血色がよくて……どう見ても生きてるでしょう……?」
少女の母親は言葉を受け入れらず、茫然自失といった風に言葉を漏らし。父親はその隣で肩を支えながら沈痛な表情で説明を聞いている。
どこにでもありふれた光景だ。
例えば街で車に撥ねられたとか。
学校でいじめの被害に遭ったとか。
家で自殺をしようとしただとか。
生まれながらに障害を持っていただとか。
そういった話はその辺に当たり前のように転がっているものだ。
その少女もまた、とある街の一角で。当たり前のように病院へ運ばれることとなった。
原因は後天性の希少疾患。徐々に身体や関節が樹の枝のように硬くなり、やがて脳の一部機能が停止して、完全な植物状態となる奇病。発症から一年で意識を失い、それから数えて今日で三か月。現代医学も特殊な能力持ちさえも匙を投げ、予め死ぬことが決まっていたように静かに今日という日を迎えた。
母親は病気発覚後から毎日病室へと足繫く通っていた。少女が読みたがる本を買ってきたり、好きな果物を持ってきて皮をむいてあげたり。
日数が経って段々と本を捲ることや果物を食べることが出来なくなってきてからは、本を代わりに読んで聞かせたり、フルーツの甘い匂いがするアロマを持ってきたり。
最初は感想を語り合ったりしたものだったが、それも段々と口数が少なくなっていく。
満足に口を動かす事さえ出来なくなると、次第に後ろ向きになりはじめた娘を励ましながら、何日も、何日も。
……そして眠る時間が長くなり、意識が戻らなくなってからは、泊まり込んで甲斐甲斐しく世話をして。
その日々はこれからも続いていく。
ほんの僅かでも可能性があるならば、と。
幸い両親は家柄も良く、父親の仕事も順調であったため、この先何十年も命が尽きるまで延命を続けていけるだけの資産は持っていた。
母親はその愛情の深さからいつまでもこの生活を続けるつもりであったし、宣告を受けて今はショックを受けているが、この日が来ることはずっと前から少しずつ覚悟をしてきていたのだ。決して受け止めきれないということはなく、もしも。もしも娘がいつか目覚めたら────
いつかくる、その日を夢見て。静かに娘を見守っていく。そのつもりだった。
父親の実家はその筋では有名な家系である。
代々受け継がれる特異な性質。それは小さな種のようであり、苗木のようでもあり。
また、大樹の様でもある一子相伝の秘術。父はそれを研究するために研究者として成果を上げてきており、ようやく先日その為の土台が整った。
何年もかけて計画してきた下準備は、しかし娘の発病を経て大きく頓挫する。
娘は動かぬ植物と成れ果て、隣で支えるはずの妻は娘を生涯世話していくと誓って。
そして…………
それから半年の後に、少女は退院することとなる。
娘は────夜道は、父親に付き添われて笑みを浮かべて。
すっかり細くなったものの、二本の足で歩いており、元気な姿で看護師たちに見送られて。その姿は半年前とは見違えるほどであり、病気の後遺症も実質ほとんど残っていない。
それは、どこにでもありふれていない奇跡のような出来事。
夜道は辛くて苦しい思い出がたくさんある病室から退院出来て、心底嬉しく思っていた。
となりでは大好きな父が微笑んでいて、握った手は温かくて大きくて。
なにより、また学校に行けるということが嬉しかったのだ。
以前住んでいた家は売り払ってしまったらしく、新しい地域でゼロから友達作りをしなくてはならないのが、少し残念ではあったけれど。
これからの生活を思い浮かべると、楽しくて楽しくて、仕方なかった。
夜道は白い大きな病室で、徐々に動かなくなっていく身体が恐ろしかった。
好きなことも、好きなものも。言葉さえも段々と離れていって……
大好きな人たちの顔はいつも苦しそうで。
それは、全部私が悪いのだと分かっていたから。
だから、精一杯笑顔で喜んだりはしゃいだり。
でも、それが満足に出来なくなってからは本当に辛くて、嫌で、苦しくて、悲しくて。
大好きな母の顔が悲嘆に暮れる姿を、泣きながら本を読む震える声をじっと聞いていた。
なにも反応を返せなくなってからも、ずっと。ずっと──……
こうして元気になったことで、悲しませてしまったことをひっくり返せるくらいに。
楽しい毎日にしていくのだと、帰途につきながら、そんなことを無邪気に思っていた。
───
降雪夜道の退院一か月前。
降雪桔梗が自宅の風呂場で倒れている姿が発見された。
手首は浴槽の水に浸かり、多量の出血はあったものの……命に別状はなかった。
それが、一回目の自殺未遂の記録。
───



ENo.138 スバル とのやりとり

ENo.515 フタバ とのやりとり

ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり

ENo.1341 エイゴウオー とのやりとり

以下の相手に送信しました




だれかのおうさま(366) に ItemNo.1 何かの殻 を手渡ししました。










具現LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
蹲る肉塊(251) により ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
持明院 寂怜(555) の持つ ItemNo.8 何かの殻 から装飾『光殻湛えし虚樹』を作製しました!
ItemNo.6 何か柔らかい物体 から装飾『腐り落ちた実の果て』を作製しました!
⇒ 腐り落ちた実の果て/装飾:強さ40/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ルリ(765) とカードを交換しました!
焼きナス (ホーリーポーション)

ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
ハードブレイク を研究しました!(深度2⇒3)
ハードブレイク を研究しましたが既に最大深度でした。
クリエイト:タライ を習得!
クリエイト:グレイル を習得!
クリエイト:パワードスピーカー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



蹲る肉塊(251) は 白樺 を入手!
だれかのおうさま(366) は 杉 を入手!
嬉野聖(399) は 松 を入手!
持明院 寂怜(555) は 杉 を入手!
持明院 寂怜(555) は 美味しい草 を入手!
持明院 寂怜(555) は ボロ布 を入手!
蹲る肉塊(251) は 美味しい草 を入手!
蹲る肉塊(251) は 美味しい草 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
だれかのおうさま(366) のもとに 疾走雑草 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。
だれかのおうさま(366) のもとに ミニゴースト が泣きながら近づいてきます。



チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- 持明院 寂怜(555) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

Cross+Roseの音量を調整する。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



◇イバラシティ 某日 病院の一室
白い部屋の中、白いベッドに少女が横になっている。
白く細い肢体にいくつもの管が通っており、口には呼吸器が取り付けられていた。
部屋の中には彼女の両親と担当医が向かい合って座っており、規則的な電子音を響かせるベッドサイドモニタには、彼女の生存を示す数字が示されている。
少女の胸は静かに上下しているものの、ものかなり長い時間この状態のまま喋ることも、動くこともなく、触れても瞬きひとつさえ反応を示すことさえ無いまま生かされ続けてきていた。
胃には直接管を通され、定期的に巡回する看護師によって水分と栄養とが流し込まれて。
少女は既に植物状態だった。
「……残念ですが、これ以上は回復の見込みがありません。
延命は可能ですが、目を覚ます可能性は限りなく低いでしょう」
白衣を着た初老の男性は最初にそう前置きした上で、重苦しい雰囲気のまま続けて事務的に説明責任を果たしていく。その言葉の中には医療スタッフの力不足を謝罪する文面や、延命を続ける際の高額な費用についての説明など含まれており、
「嘘……嘘よ……だって、こんなにも血色がよくて……どう見ても生きてるでしょう……?」
少女の母親は言葉を受け入れらず、茫然自失といった風に言葉を漏らし。父親はその隣で肩を支えながら沈痛な表情で説明を聞いている。
どこにでもありふれた光景だ。
例えば街で車に撥ねられたとか。
学校でいじめの被害に遭ったとか。
家で自殺をしようとしただとか。
生まれながらに障害を持っていただとか。
そういった話はその辺に当たり前のように転がっているものだ。
その少女もまた、とある街の一角で。当たり前のように病院へ運ばれることとなった。
原因は後天性の希少疾患。徐々に身体や関節が樹の枝のように硬くなり、やがて脳の一部機能が停止して、完全な植物状態となる奇病。発症から一年で意識を失い、それから数えて今日で三か月。現代医学も特殊な能力持ちさえも匙を投げ、予め死ぬことが決まっていたように静かに今日という日を迎えた。
母親は病気発覚後から毎日病室へと足繫く通っていた。少女が読みたがる本を買ってきたり、好きな果物を持ってきて皮をむいてあげたり。
日数が経って段々と本を捲ることや果物を食べることが出来なくなってきてからは、本を代わりに読んで聞かせたり、フルーツの甘い匂いがするアロマを持ってきたり。
最初は感想を語り合ったりしたものだったが、それも段々と口数が少なくなっていく。
満足に口を動かす事さえ出来なくなると、次第に後ろ向きになりはじめた娘を励ましながら、何日も、何日も。
……そして眠る時間が長くなり、意識が戻らなくなってからは、泊まり込んで甲斐甲斐しく世話をして。
その日々はこれからも続いていく。
ほんの僅かでも可能性があるならば、と。
幸い両親は家柄も良く、父親の仕事も順調であったため、この先何十年も命が尽きるまで延命を続けていけるだけの資産は持っていた。
母親はその愛情の深さからいつまでもこの生活を続けるつもりであったし、宣告を受けて今はショックを受けているが、この日が来ることはずっと前から少しずつ覚悟をしてきていたのだ。決して受け止めきれないということはなく、もしも。もしも娘がいつか目覚めたら────
いつかくる、その日を夢見て。静かに娘を見守っていく。そのつもりだった。
父親の実家はその筋では有名な家系である。
代々受け継がれる特異な性質。それは小さな種のようであり、苗木のようでもあり。
また、大樹の様でもある一子相伝の秘術。父はそれを研究するために研究者として成果を上げてきており、ようやく先日その為の土台が整った。
何年もかけて計画してきた下準備は、しかし娘の発病を経て大きく頓挫する。
娘は動かぬ植物と成れ果て、隣で支えるはずの妻は娘を生涯世話していくと誓って。
そして…………
それから半年の後に、少女は退院することとなる。
娘は────夜道は、父親に付き添われて笑みを浮かべて。
すっかり細くなったものの、二本の足で歩いており、元気な姿で看護師たちに見送られて。その姿は半年前とは見違えるほどであり、病気の後遺症も実質ほとんど残っていない。
それは、どこにでもありふれていない奇跡のような出来事。
夜道は辛くて苦しい思い出がたくさんある病室から退院出来て、心底嬉しく思っていた。
となりでは大好きな父が微笑んでいて、握った手は温かくて大きくて。
なにより、また学校に行けるということが嬉しかったのだ。
以前住んでいた家は売り払ってしまったらしく、新しい地域でゼロから友達作りをしなくてはならないのが、少し残念ではあったけれど。
これからの生活を思い浮かべると、楽しくて楽しくて、仕方なかった。
夜道は白い大きな病室で、徐々に動かなくなっていく身体が恐ろしかった。
好きなことも、好きなものも。言葉さえも段々と離れていって……
大好きな人たちの顔はいつも苦しそうで。
それは、全部私が悪いのだと分かっていたから。
だから、精一杯笑顔で喜んだりはしゃいだり。
でも、それが満足に出来なくなってからは本当に辛くて、嫌で、苦しくて、悲しくて。
大好きな母の顔が悲嘆に暮れる姿を、泣きながら本を読む震える声をじっと聞いていた。
なにも反応を返せなくなってからも、ずっと。ずっと──……
こうして元気になったことで、悲しませてしまったことをひっくり返せるくらいに。
楽しい毎日にしていくのだと、帰途につきながら、そんなことを無邪気に思っていた。
───
降雪夜道の退院一か月前。
降雪桔梗が自宅の風呂場で倒れている姿が発見された。
手首は浴槽の水に浸かり、多量の出血はあったものの……命に別状はなかった。
それが、一回目の自殺未遂の記録。
───



ENo.138 スバル とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.515 フタバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.1341 エイゴウオー とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
嬉野聖 「僕の世界なんざとっくに滅びてますのに。 アンジニティの枯れた世界でひっそり生きれたら、 後はもーーどーーでもいーーですわーー」 |
 |
持明院 寂怜 「さぁ鬨の声を上げよ!! 声の大きさ元気の強さで負けていては戦に勝てんぞぉ!!」 |
だれかのおうさま(366) に ItemNo.1 何かの殻 を手渡ししました。



(*‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(*‘∀‘)
|
 |
ハザマに生きるもの
|



巻き込まれ型冒険組
|
 |
(*‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(*‘∀‘)
|



具現LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
蹲る肉塊(251) により ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
持明院 寂怜(555) の持つ ItemNo.8 何かの殻 から装飾『光殻湛えし虚樹』を作製しました!
ItemNo.6 何か柔らかい物体 から装飾『腐り落ちた実の果て』を作製しました!
⇒ 腐り落ちた実の果て/装飾:強さ40/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
嬉野聖 「利用できるモノは全て利用する……」 |
ルリ(765) とカードを交換しました!
焼きナス (ホーリーポーション)

ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
ハードブレイク を研究しました!(深度2⇒3)
ハードブレイク を研究しましたが既に最大深度でした。
クリエイト:タライ を習得!
クリエイト:グレイル を習得!
クリエイト:パワードスピーカー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



蹲る肉塊(251) は 白樺 を入手!
だれかのおうさま(366) は 杉 を入手!
嬉野聖(399) は 松 を入手!
持明院 寂怜(555) は 杉 を入手!
持明院 寂怜(555) は 美味しい草 を入手!
持明院 寂怜(555) は ボロ布 を入手!
蹲る肉塊(251) は 美味しい草 を入手!
蹲る肉塊(251) は 美味しい草 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
だれかのおうさま(366) のもとに 疾走雑草 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。
だれかのおうさま(366) のもとに ミニゴースト が泣きながら近づいてきます。



チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- 持明院 寂怜(555) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
エディアン 「わぁこんにちはノウレットさーん! えーと音量音量・・・コンフィグかな?」 |
Cross+Roseの音量を調整する。
 |
エディアン 「よし。・・・・・さて、どうしました?ノウレットちゃん。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたッ!」 |
 |
エディアン 「おや、てっきりあのざっくりした説明だけなのかと。」 |
 |
ノウレット 「お役に立てそうで嬉しいです!!」 |
 |
エディアン 「よろしくお願いしまーす。」 |
 |
ノウレット 「ではでは・・・・・ジャーンッ!こちらがロスト情報ですよー!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
エディアン 「なるほど、いろんなかたがいますねぇ。 彼らの願望を叶えることで影響力を得て、ハザマで強くもなれるんですか。」 |
 |
エディアン 「どこにいるかとか、願望の内容とか、そういうのは分かります?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「むむむ・・・・・頑張って見つけないといけませんねぇ。 こう、ロストには頭にマークが付いてるとか・・・そういうのは?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・システムメッセージなのかなこれ。 ・・・ノウレットちゃんの好きなものは?」 |
 |
ノウレット 「肉ですッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・嫌いなものは?」 |
 |
ノウレット 「白南海さん、です・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・さては何かしましたね、彼。」 |
 |
エディアン 「では、ロスト情報もそこそこ気にしながら進めていきましょう!」 |
 |
ノウレット 「ファイトでーすッ!!」 |
チャットが閉じられる――



(‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(‘∀‘)
|
 |
ハザマに生きるもの
|




そろそろ決めませんか?
|
 |
(‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(‘∀‘)
|


ENo.399
嬉野 聖



PN:嬉野 聖(うれしの ひじり)
書評サイト『ユグドバイブル』の管理人
書評サイト『ユグドバイブル』
中高生の読書家にひっそりと知られる書評サイト。
細かくカテゴリ毎に分けられており、気に入った本の類似書籍を検索するのに便利な機能が多数盛り込まれている。
現役女子校生管理人としてネットでインタビューなども受けており、知名度は高くないがインターネットをよく見る読書好きであれば管理人『嬉野 聖』の名前を知っているかもしれない。
本名:降雪 夜道(コウセツ ヨミ)
ブランブル女学院高等部1-2、図書委員、文芸部所属
女性、15歳、167cm、47kg
外面はですます口調のお淑やかなお嬢様だが、内面はとても明るくツッコミ気質
SNS等ではハイテンションな関西弁で捲し立てるため、なかなか同一人物と信じてもらえない
笑いの沸点が低く、何気ないことでツボに刺さり、本で口元を隠しながら笑いをこらえたりする
静かに本を読んでいれば知的で深窓の令嬢然とした装いのため、
彼女を知る友人達からは残念文学少女と言われている。
関西弁のクラスメイトがいないため標準語を使っているが、慣れているのは関西弁。うっかり地が出ることも
中学までは別の街に居たため、イバラシティに古い知り合いは居ないようだ
【第一回更新後の情報】
本人が言う異能[本の虫]は、読書することで身体機能を強化するもの
知り合いには気軽にその事を伝えるだろう
ちょこっと力が強くなる程度で、リンゴを握りつぶすことはできない。らしい
≪一部の学校関係者等に伝わっている情報≫
降雪夜道は身体機能が常人の半分以下
それを補うために異能が必要で、歩きながらの読書も黙認されている
【第二回更新後の情報】
夜道は両親と離れて暮らしている。
母桔梗は夜道を死んだ娘の親友だと思い込んでいるようだ。
整合性を保つ為に大量の薬を服用している。
■ハザマ体
降雪夜道を形作っている樹木。全体的に薄い緑だが、髪や一部皮膚などが焦げ茶色に枯れている。
肌はヒトのようだが色が緑っぽく、よく見れば苔むした樹皮だとわかるだろう。
顔は笑みを形作っているが……中身は腐っており、異臭がする。
服はブランブル女学院の物をどこかから調達して着込んでいる。
裸足で、眼鏡は樹で作っておりレンズがなく歪。
【第三回更新後の情報】
降雪夜道は幼い頃に病気で入院し、その後一度脳死の診断を受けている。しかしその後、無事に退院することができた。その頃から引っ越しが多くなり、身体機能を維持するために読書が必要となった。
□司書さん
身長168、体重51、年齢21、女性
まだ年若いけれど知識豊富な21歳
本業の傍ら司書としても勤めている
** プロフ及びアイコンは有償依頼で描いてもらったもの、もしくはpicrewを利用したものになります。 **
** 演出等で十con様(http://rainpark.sub.jp/palir/tawaiconfree.html)をお借りしております **
書評サイト『ユグドバイブル』の管理人
書評サイト『ユグドバイブル』
中高生の読書家にひっそりと知られる書評サイト。
細かくカテゴリ毎に分けられており、気に入った本の類似書籍を検索するのに便利な機能が多数盛り込まれている。
現役女子校生管理人としてネットでインタビューなども受けており、知名度は高くないがインターネットをよく見る読書好きであれば管理人『嬉野 聖』の名前を知っているかもしれない。
本名:降雪 夜道(コウセツ ヨミ)
ブランブル女学院高等部1-2、図書委員、文芸部所属
女性、15歳、167cm、47kg
外面はですます口調のお淑やかなお嬢様だが、内面はとても明るくツッコミ気質
SNS等ではハイテンションな関西弁で捲し立てるため、なかなか同一人物と信じてもらえない
笑いの沸点が低く、何気ないことでツボに刺さり、本で口元を隠しながら笑いをこらえたりする
静かに本を読んでいれば知的で深窓の令嬢然とした装いのため、
彼女を知る友人達からは残念文学少女と言われている。
関西弁のクラスメイトがいないため標準語を使っているが、慣れているのは関西弁。うっかり地が出ることも
中学までは別の街に居たため、イバラシティに古い知り合いは居ないようだ
【第一回更新後の情報】
本人が言う異能[本の虫]は、読書することで身体機能を強化するもの
知り合いには気軽にその事を伝えるだろう
ちょこっと力が強くなる程度で、リンゴを握りつぶすことはできない。らしい
≪一部の学校関係者等に伝わっている情報≫
降雪夜道は身体機能が常人の半分以下
それを補うために異能が必要で、歩きながらの読書も黙認されている
【第二回更新後の情報】
夜道は両親と離れて暮らしている。
母桔梗は夜道を死んだ娘の親友だと思い込んでいるようだ。
整合性を保つ為に大量の薬を服用している。
■ハザマ体
降雪夜道を形作っている樹木。全体的に薄い緑だが、髪や一部皮膚などが焦げ茶色に枯れている。
肌はヒトのようだが色が緑っぽく、よく見れば苔むした樹皮だとわかるだろう。
顔は笑みを形作っているが……中身は腐っており、異臭がする。
服はブランブル女学院の物をどこかから調達して着込んでいる。
裸足で、眼鏡は樹で作っておりレンズがなく歪。
【第三回更新後の情報】
降雪夜道は幼い頃に病気で入院し、その後一度脳死の診断を受けている。しかしその後、無事に退院することができた。その頃から引っ越しが多くなり、身体機能を維持するために読書が必要となった。
□司書さん
身長168、体重51、年齢21、女性
まだ年若いけれど知識豊富な21歳
本業の傍ら司書としても勤めている
** プロフ及びアイコンは有償依頼で描いてもらったもの、もしくはpicrewを利用したものになります。 **
** 演出等で十con様(http://rainpark.sub.jp/palir/tawaiconfree.html)をお借りしております **
16 / 30
132 PS
チナミ区
I-15
I-15









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 松 | 素材 | 15 | [武器]器用10(LV15)[防具]応報10(LV25)[装飾]耐地10(LV20) | |||
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 強迫観念 | 武器 | 35 | - | - | - | 【射程3】 |
| 4 | 錆びついた牙飾り | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 苔むした樹皮 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 腐り落ちた実の果て | 装飾 | 40 | 防御10 | - | - | |
| 7 | |||||||
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]地纏10(LV20)[防具]防御10(LV15)[装飾]反射10(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 5 | 夢幻/精神/光 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 響鳴 | 20 | 歌唱/音楽/振動 |
| 装飾 | 30 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ささやかな抵抗 (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| むなしい叫び (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| わずかな反抗 (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 生き延びたいという願い (ドレイン) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 聖なる光 (ライトニング) | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| 決3 | エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) |
| 決3 | クリエイト:グレイル | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
| アトラクト | 5 | 0 | 50 | 自:HATE・連続増 | |
| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |
| 生き汚い憐れな叫び (ビブラート) | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| 枯れる大地。芽生える息吹。 (ヒーリングソング) | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| 鳴動する世界樹 (エファヴェセント) | 6 | 0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]アクアヒール |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]サモン:サーヴァント | [ 3 ]ハードブレイク |

PL / yukkki