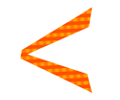<< 0:00~1:00





『DoRa・SiRa』
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html
百物語 1話『半顔』

『半顔』イバラシティサイド
ぽた ぽた、黒すぐりのジュースが2滴紙の上に落ちた。
その紙とは、辞書のページだった。
同級生から『半顔』のウワサを聞いたのは10月の事だ。
三か月経った今日、巡り合わせてその話を思い出した。
『半顔』は、カスミ区の開かずの踏切に現れるという怪異で、
すっぱりとケーキを切り分けるように、顔が半分しかないのだという。
恐ろしい怪異で、見たら最後、なのだそうだ。
同級生の、先輩の、いとこが『半顔』を見て、
―― 、…
果物の匂いに顔を顰める。
こぼしたジュースが黒ずんだ血のように、『半』という文字を滲ませていた。
スタンドライト以外の明りを消した孤独に暗い部屋を出る。
受験勉強ったって、最近は根を詰めすぎている気もする。
閉じるに閉じられない辞書をそのままにして、カバンを手に引き寄せる。
気分転換に、外へ行こうと思った。
カスミ区の開かずの踏切に、だ。
久しぶりの外は、なんだか現実感がない。
車窓を眺めているとなんだか目の前がチカチカする。
駅から続くさびれた商店街は人もいず、冷たい鼻先の痛みだけ気にしていた。
規則的な歩行の振動さえ、他人事のように感じられる。
商店街を抜けて、一番坂を上り、塀沿いに曲がる。
住宅街を貫くように、うわさの開かずの踏切はそこにあった。
あった、はずだ。
というのも、来ては見たものの開かずの踏切は『開いて』いたのだった。
老朽化し、塗装が剥げて 本来黄色と黒色のしまに塗られているはずが
赤黒く錆びた身がむき出しになっている。
『4号踏切』のこそげた文字は『4』の文字のみが残っていた。
それから、電車の接近を知らせる、踏切の電燈が左右非対称に片方だけ残っていた。
『半顔』というのは、ここから来た名前かもしれない。
この風体は怪談の題材にされるのも納得する雰囲気があった。
けれど開かずの踏切は、ただの踏切だった。
パチリと幻想が剥げて、途端に、現実感が湧いてきた。
私は何を期待していたのか、そんなもの、なくてよかった。
私は一旦振り返り、とどまってもう一回振り返った。
踏切の方を向き直した。
せっかくだから渡って帰ろうと思ったのだった。
踏み出す、コンクリートの道。レールのくぼみ。開かれた、
――危ない!
えっ?
そんな、まさか。心臓が収縮する。風を感じて私が右手を振り向くと、
目と鼻の先に電車が迫っていた。ごうごうとうなりを上げ、
つんざくような警笛を鳴らし、ライトが、視界いっぱいくらませる。
踏切は開いていたのに。どうして!
私は、私は、反射的に地面にべったりとへばりついた。
前に、そんな動画を見た事がある。無鉄砲なチキンレーサーがそうして
列車の下に寝転んで、勇気を示すような肝の冷える動画。
そうすればレールと車体の隙間にいて助かる、
なんであんなものを見たのか解らなかったが、今のためであってほしい、
―地獄だった、こんな恐怖は。
1秒や2秒が10分や20分に感じる。ここだけ宇宙が捻じ曲げられたみたいに、時間がガム状に伸びる。
その間中ずっと、自分の手足が吹き飛ぶ想像ばかりが
走馬燈もかき消すように浮かんで消える、想像の痛みがズキズキ明滅する。
何度も殺されているようだった。
自分のすぐ上で、重い金属ごうごうと猛スピードで走り抜けていく。
この音は、耳にこびりついて一生離れないだろう。
…魂が汗と涙になって流れ出てしまったみたいだ。
電車が通り過ぎる頃には、へんに軽くなった身体と対照的に、服が濡れて重く感じた。
私は、がくがくと震えながら、ゆっくり立ち上がる。
先程「危ない」と声をかけてくれた人にお礼を言わなくては。
その人は、車の窓から身を乗り出して私に声を投げかけていた。
振り返ると、悲鳴が上がった。
整えようとしても整わない息、
汗が止まらない。汗をぬぐう。
汗が…いや、手についていたのは血だった。
わたしは焦って自分の体をベタベタと触って確かめた。
どこをケガしたのか、触って確かめる、
頭に差し掛かった時、手が空を切る。
車に駆け寄り、フロントガラスに映る自分を見た。
顔が、顔が半分、ない
『半顔』を見たら最後。
ぐらりと世界が傾ぐ。電車の接近を知らせる、赤いはずの踏切の電燈が
妙な色をしていた。最後の力を振り絞って目を凝らすと、それは目玉だった。
踏切の電燈にはまった目玉が、私を見下ろしていた。
黄昏時、私の死を見世物のように。カラスが一羽、カアと笑った。

『半顔』アンジニティサイド
よし、棺を抱えた男が、荒野をずりずりと歩いていた。
ぼろをまとった浮浪者風の男は、蛾のように焚き木に寄って来て、腰を下ろす。
――あなた、ちょっと、いいかい、私の懺悔を聞いてはくれはしないか。
わかってるさ。私のように、いやしいものが他人の時間を借りるなんて滅相もない話だ。わきまえている。
それでも、もし情けをかけてくれるなら、このつまらない話を聞いてくれ。
聞いてくれるだけで、私には救われるんだから。
男はしくしくと泣きながら、涙交じりにそれでも語りを始めたのだった。
私には娘がいた。
とても出来の良い娘で、私のつまらない人生の、唯一の誉れだった。
私は職人たちの家に出向いて、失敗の商品をただ同然の安値で引き取って
町のほうでは職人の名を掲げて高値で売ることで暮らしていた。
泥棒のような私だが、娘はなんとも学のある子供に育ったんだよ。
娘は、とても難しい魔法を勉強して魔術師になったんだ。
そんな輝いている娘が…とても大事で、とても誇らしく、
正直に申し上げると…私にはコンプレックスでもあった。
時折、娘を凌辱する夢を見た。この私よりも優れた娘を、暴力によって蹂躙し、
服従させられれば、私はこの世の王にもなったような気がするだろうと夢想していた。
ああ、いやだ。まだ聞いてくれ。待ってくれ。
懺悔というのは、私がそのような下劣な夢想を現実化したという話ではない。
そのようなことは…。
娘の運命は、もっと、時世のどうしようもない話なんだ。
ある時、我らの大陸で、ある『風土病』が発見されたのだ。
それというのは、体に大きなこぶができるというものだ。
こぶを切開してみると、膿のように見えたが、どうもその中に詰まっているものが
脳神経の神経細胞なのだという。こぶができると小さな脳が出来る、と世間では言われていた。
それで、その病気を研究していたらしい、ある魔術師がこんな発表をした。
こぶは、肉体を動かす神経経路は持たないが、記憶することに使える。
難解な魔法の術式や詠唱を記憶して、魔術師の仕事を楽にする、と。
わかるかね。
これはね、大変支持された研究発表だったんだよ。
先進的な魔術師たちはこぞって病気をうつしてもらいたがった。
都会では眠れぬほどに、よなよなこぶの移植手術が行われたものだ。
この流行のなかで、噂に聞いたのはだね、
魔術師たちは、魔法を使えない者たちを見下して
こぶをすりあわせて官能を得ていたというそうだよ。
ともかく爆発的な流行だったんだ。
世間はすっかり、こぶが多ければ多いほど、こぶが大きければ大きいほど、
賢く有能な魔術師だという風潮だった。このこぶは、魅力の証だったんだ。
それで私の娘も、顔面に大きなこぶをつけたんだ。
林檎ほどもある大きなこぶだった。
私はこんな風に野暮ったいものだから、
それが流行っていると言われれば理解があるふりをして過ごすしかなかった。
乳房の揺れを蕩けてみるように、皆が娘のこぶをうっとりと眺めていた。
夜眠る前、これは私がもっともよく見た娘の姿だが、
娘は顔面のの脳を宝物のようにめで、クリームや粉を念入りに塗っていたよ。
大きくなりなさい、と
それからあの子は『こぶは今夢を見ているんだろうか』とつぶやいた。
ある時、娘は魔術院の褒賞式典に呼ばれることになった。
人生最大のほまれ。娘こそが主役になる日だ。
林檎ほどのこぶは、栄光のごとくに大きくなり、
いまは赤ん坊のほどまでもお気くなっていた。
沢山の視線と光、称賛を浴びる娘を、
私も段下から見つめていた。
娘がスピーチを行おうと舞台の真ん中へ歩み出す。
その知的な外見には、だれもが息をのんだ。
光がまっすぐに彼女に集まったまさにその瞬間だった、
あっと声をあげる間も無く、娘の顔が半分もげたんだ。
…
ちょっと、まっておくんなさいな。
ここまで聞いて、あなたは思ったのじゃないか。私の懺悔といったのに、私は何もしてはいないだろう。
そうなのだ。私は何も悪事を働いてなどいない。
病が流行したのは時代のせいだ。私の懺悔というのはここからさ。
娘の顔の半分がもげた。
本来の脳がこぼれて、その場で姉は絶命した。
混沌と悲鳴のうねるその会場で、ある魔術師が、
娘の史上最大のこぶを抱えて、大急ぎで走り去った。
皆、娘の肉体をばかり見ていたので、私の他にはそれに気づくものがいなかった。
その魔術師は、娘のこぶを実験室にもっていき、
そして私には何やらわからないが、
肉体――つまり娘、本体、とおなじ機能をするだけの装置を急ぎ、取りつけたと言った。
血液を送ったり、酸素を送るようなものをね。
それで?それで、こぶは生きた。
神経細胞は活性し、生命活動と呼ばれるものを、おこなっている。
魔術師はこちらを振り返ると、おもむろに私の手を取って、私をこぶに触れさせた。
やわらかな弾力。ほんのりと汗をかきながら、しめったこぶは
私に生命のぬくもりを伝えていました。
『どうでしょう。
娘さんは、まだ脈打っています。
大きさも、温かさも、ちょうど、赤ん坊のようなものだとは思いませんか』
『選んでくださいな。
わたしがあなたを助けましょう。
この顛末は、わたしの研究のせいでもありましょう。
あなたは踵を返し、死せる半顔の娘さんを弔いに行くもよい。
もしもこぶをこそ娘さんだと思うのであれば、わたしが彼女を生かしましょう。』
――――
――――
――それが、この棺に入ってる。
解りますまい、解りますまい。
私は娘の顔の半分と愛し合っております。解りますまい、
脳はきっと夢を見ております。
私のような人生の。唯一の財産というものが、どのようなものか、解りますまい。
おいおいと男は泣きながら、棺に顔をうずめる。
わたくしのお話を聞いてくださって、有難うございます。
あなたの時間を無駄にしてしまって、誠に申し訳ない。
ですが…
そうだ…
はじめにあの風土病を発見した魔術師、
そしてそれが魔術の詠唱に使えるという研究発表を行った魔術師、
私に娘の死体と娘のこぶとを選ばせた魔術師、これらはどれも同じひとりの人間でね。
どうもその女も、ここにいるんだ。
その魔術師は、名をドーラ・シーラという。
くれぐれもお気を付けて…。



ENo.205 ミツ とのやりとり

ENo.1232 犬 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 フラスコ入り ホット山羊ミルク を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








武術LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
具現LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
使役LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
あなた(425) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
あざらし姫(642) により ItemNo.1 駄物 から法衣『老魔女の遺言書』を作製してもらいました!
⇒ 老魔女の遺言書/法衣:強さ17/[効果1]- [効果2]- [効果3]幸運5/特殊アイテム
あざらし姫(642) の持つ ItemNo.3 不思議な食材 から料理『イモリ丸焼きスープ』をつくりました!
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『イモリ丸焼きスープ』をつくりました!
⇒ イモリ丸焼きスープ/料理:強さ25/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
犬(1232) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『竜の血』をつくりました!
マキナ(567) とカードを交換しました!
護身 (カウンター)

ストライク を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度0⇒1)
ストーンブラスト を研究しました!(深度1⇒2)
カース を習得!
サステイン を習得!
ヒールポーション を習得!
クリエイト:スパイク を習得!
ペレル を習得!
ポイズン を習得!
アシスト を習得!
クリエイト:ヴェノム を習得!
スコーピオン を習得!
魅惑 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- ドーラ・シーラ(103) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 犬(1232) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




『DoRa・SiRa』
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html
百物語 1話『半顔』

『半顔』イバラシティサイド
ぽた ぽた、黒すぐりのジュースが2滴紙の上に落ちた。
その紙とは、辞書のページだった。
同級生から『半顔』のウワサを聞いたのは10月の事だ。
三か月経った今日、巡り合わせてその話を思い出した。
『半顔』は、カスミ区の開かずの踏切に現れるという怪異で、
すっぱりとケーキを切り分けるように、顔が半分しかないのだという。
恐ろしい怪異で、見たら最後、なのだそうだ。
同級生の、先輩の、いとこが『半顔』を見て、
―― 、…
果物の匂いに顔を顰める。
こぼしたジュースが黒ずんだ血のように、『半』という文字を滲ませていた。
スタンドライト以外の明りを消した孤独に暗い部屋を出る。
受験勉強ったって、最近は根を詰めすぎている気もする。
閉じるに閉じられない辞書をそのままにして、カバンを手に引き寄せる。
気分転換に、外へ行こうと思った。
カスミ区の開かずの踏切に、だ。
久しぶりの外は、なんだか現実感がない。
車窓を眺めているとなんだか目の前がチカチカする。
駅から続くさびれた商店街は人もいず、冷たい鼻先の痛みだけ気にしていた。
規則的な歩行の振動さえ、他人事のように感じられる。
商店街を抜けて、一番坂を上り、塀沿いに曲がる。
住宅街を貫くように、うわさの開かずの踏切はそこにあった。
あった、はずだ。
というのも、来ては見たものの開かずの踏切は『開いて』いたのだった。
老朽化し、塗装が剥げて 本来黄色と黒色のしまに塗られているはずが
赤黒く錆びた身がむき出しになっている。
『4号踏切』のこそげた文字は『4』の文字のみが残っていた。
それから、電車の接近を知らせる、踏切の電燈が左右非対称に片方だけ残っていた。
『半顔』というのは、ここから来た名前かもしれない。
この風体は怪談の題材にされるのも納得する雰囲気があった。
けれど開かずの踏切は、ただの踏切だった。
パチリと幻想が剥げて、途端に、現実感が湧いてきた。
私は何を期待していたのか、そんなもの、なくてよかった。
私は一旦振り返り、とどまってもう一回振り返った。
踏切の方を向き直した。
せっかくだから渡って帰ろうと思ったのだった。
踏み出す、コンクリートの道。レールのくぼみ。開かれた、
――危ない!
えっ?
そんな、まさか。心臓が収縮する。風を感じて私が右手を振り向くと、
目と鼻の先に電車が迫っていた。ごうごうとうなりを上げ、
つんざくような警笛を鳴らし、ライトが、視界いっぱいくらませる。
踏切は開いていたのに。どうして!
私は、私は、反射的に地面にべったりとへばりついた。
前に、そんな動画を見た事がある。無鉄砲なチキンレーサーがそうして
列車の下に寝転んで、勇気を示すような肝の冷える動画。
そうすればレールと車体の隙間にいて助かる、
なんであんなものを見たのか解らなかったが、今のためであってほしい、
―地獄だった、こんな恐怖は。
1秒や2秒が10分や20分に感じる。ここだけ宇宙が捻じ曲げられたみたいに、時間がガム状に伸びる。
その間中ずっと、自分の手足が吹き飛ぶ想像ばかりが
走馬燈もかき消すように浮かんで消える、想像の痛みがズキズキ明滅する。
何度も殺されているようだった。
自分のすぐ上で、重い金属ごうごうと猛スピードで走り抜けていく。
この音は、耳にこびりついて一生離れないだろう。
…魂が汗と涙になって流れ出てしまったみたいだ。
電車が通り過ぎる頃には、へんに軽くなった身体と対照的に、服が濡れて重く感じた。
私は、がくがくと震えながら、ゆっくり立ち上がる。
先程「危ない」と声をかけてくれた人にお礼を言わなくては。
その人は、車の窓から身を乗り出して私に声を投げかけていた。
振り返ると、悲鳴が上がった。
整えようとしても整わない息、
汗が止まらない。汗をぬぐう。
汗が…いや、手についていたのは血だった。
わたしは焦って自分の体をベタベタと触って確かめた。
どこをケガしたのか、触って確かめる、
頭に差し掛かった時、手が空を切る。
車に駆け寄り、フロントガラスに映る自分を見た。
顔が、顔が半分、ない
『半顔』を見たら最後。
ぐらりと世界が傾ぐ。電車の接近を知らせる、赤いはずの踏切の電燈が
妙な色をしていた。最後の力を振り絞って目を凝らすと、それは目玉だった。
踏切の電燈にはまった目玉が、私を見下ろしていた。
黄昏時、私の死を見世物のように。カラスが一羽、カアと笑った。

『半顔』アンジニティサイド
よし、棺を抱えた男が、荒野をずりずりと歩いていた。
ぼろをまとった浮浪者風の男は、蛾のように焚き木に寄って来て、腰を下ろす。
――あなた、ちょっと、いいかい、私の懺悔を聞いてはくれはしないか。
わかってるさ。私のように、いやしいものが他人の時間を借りるなんて滅相もない話だ。わきまえている。
それでも、もし情けをかけてくれるなら、このつまらない話を聞いてくれ。
聞いてくれるだけで、私には救われるんだから。
男はしくしくと泣きながら、涙交じりにそれでも語りを始めたのだった。
私には娘がいた。
とても出来の良い娘で、私のつまらない人生の、唯一の誉れだった。
私は職人たちの家に出向いて、失敗の商品をただ同然の安値で引き取って
町のほうでは職人の名を掲げて高値で売ることで暮らしていた。
泥棒のような私だが、娘はなんとも学のある子供に育ったんだよ。
娘は、とても難しい魔法を勉強して魔術師になったんだ。
そんな輝いている娘が…とても大事で、とても誇らしく、
正直に申し上げると…私にはコンプレックスでもあった。
時折、娘を凌辱する夢を見た。この私よりも優れた娘を、暴力によって蹂躙し、
服従させられれば、私はこの世の王にもなったような気がするだろうと夢想していた。
ああ、いやだ。まだ聞いてくれ。待ってくれ。
懺悔というのは、私がそのような下劣な夢想を現実化したという話ではない。
そのようなことは…。
娘の運命は、もっと、時世のどうしようもない話なんだ。
ある時、我らの大陸で、ある『風土病』が発見されたのだ。
それというのは、体に大きなこぶができるというものだ。
こぶを切開してみると、膿のように見えたが、どうもその中に詰まっているものが
脳神経の神経細胞なのだという。こぶができると小さな脳が出来る、と世間では言われていた。
それで、その病気を研究していたらしい、ある魔術師がこんな発表をした。
こぶは、肉体を動かす神経経路は持たないが、記憶することに使える。
難解な魔法の術式や詠唱を記憶して、魔術師の仕事を楽にする、と。
わかるかね。
これはね、大変支持された研究発表だったんだよ。
先進的な魔術師たちはこぞって病気をうつしてもらいたがった。
都会では眠れぬほどに、よなよなこぶの移植手術が行われたものだ。
この流行のなかで、噂に聞いたのはだね、
魔術師たちは、魔法を使えない者たちを見下して
こぶをすりあわせて官能を得ていたというそうだよ。
ともかく爆発的な流行だったんだ。
世間はすっかり、こぶが多ければ多いほど、こぶが大きければ大きいほど、
賢く有能な魔術師だという風潮だった。このこぶは、魅力の証だったんだ。
それで私の娘も、顔面に大きなこぶをつけたんだ。
林檎ほどもある大きなこぶだった。
私はこんな風に野暮ったいものだから、
それが流行っていると言われれば理解があるふりをして過ごすしかなかった。
乳房の揺れを蕩けてみるように、皆が娘のこぶをうっとりと眺めていた。
夜眠る前、これは私がもっともよく見た娘の姿だが、
娘は顔面のの脳を宝物のようにめで、クリームや粉を念入りに塗っていたよ。
大きくなりなさい、と
それからあの子は『こぶは今夢を見ているんだろうか』とつぶやいた。
ある時、娘は魔術院の褒賞式典に呼ばれることになった。
人生最大のほまれ。娘こそが主役になる日だ。
林檎ほどのこぶは、栄光のごとくに大きくなり、
いまは赤ん坊のほどまでもお気くなっていた。
沢山の視線と光、称賛を浴びる娘を、
私も段下から見つめていた。
娘がスピーチを行おうと舞台の真ん中へ歩み出す。
その知的な外見には、だれもが息をのんだ。
光がまっすぐに彼女に集まったまさにその瞬間だった、
あっと声をあげる間も無く、娘の顔が半分もげたんだ。
…
ちょっと、まっておくんなさいな。
ここまで聞いて、あなたは思ったのじゃないか。私の懺悔といったのに、私は何もしてはいないだろう。
そうなのだ。私は何も悪事を働いてなどいない。
病が流行したのは時代のせいだ。私の懺悔というのはここからさ。
娘の顔の半分がもげた。
本来の脳がこぼれて、その場で姉は絶命した。
混沌と悲鳴のうねるその会場で、ある魔術師が、
娘の史上最大のこぶを抱えて、大急ぎで走り去った。
皆、娘の肉体をばかり見ていたので、私の他にはそれに気づくものがいなかった。
その魔術師は、娘のこぶを実験室にもっていき、
そして私には何やらわからないが、
肉体――つまり娘、本体、とおなじ機能をするだけの装置を急ぎ、取りつけたと言った。
血液を送ったり、酸素を送るようなものをね。
それで?それで、こぶは生きた。
神経細胞は活性し、生命活動と呼ばれるものを、おこなっている。
魔術師はこちらを振り返ると、おもむろに私の手を取って、私をこぶに触れさせた。
やわらかな弾力。ほんのりと汗をかきながら、しめったこぶは
私に生命のぬくもりを伝えていました。
『どうでしょう。
娘さんは、まだ脈打っています。
大きさも、温かさも、ちょうど、赤ん坊のようなものだとは思いませんか』
『選んでくださいな。
わたしがあなたを助けましょう。
この顛末は、わたしの研究のせいでもありましょう。
あなたは踵を返し、死せる半顔の娘さんを弔いに行くもよい。
もしもこぶをこそ娘さんだと思うのであれば、わたしが彼女を生かしましょう。』
――――
――――
――それが、この棺に入ってる。
解りますまい、解りますまい。
私は娘の顔の半分と愛し合っております。解りますまい、
脳はきっと夢を見ております。
私のような人生の。唯一の財産というものが、どのようなものか、解りますまい。
おいおいと男は泣きながら、棺に顔をうずめる。
わたくしのお話を聞いてくださって、有難うございます。
あなたの時間を無駄にしてしまって、誠に申し訳ない。
ですが…
そうだ…
はじめにあの風土病を発見した魔術師、
そしてそれが魔術の詠唱に使えるという研究発表を行った魔術師、
私に娘の死体と娘のこぶとを選ばせた魔術師、これらはどれも同じひとりの人間でね。
どうもその女も、ここにいるんだ。
その魔術師は、名をドーラ・シーラという。
くれぐれもお気を付けて…。



ENo.205 ミツ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.1232 犬 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
(カラスがあちらこちらつついている…) |
 |
手渡された瓶をゆるやかに口元に運ぶ。 |
ItemNo.6 フラスコ入り ホット山羊ミルク を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







武術LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
具現LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
使役LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
あなた(425) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
 |
ウサギ? 「ややっ!!これはこれは! イイものハッケーン!! これとこれで……ふむふむふ~~む!」 |
 |
「何がでるかな~ 何がでるかな~! ちちんぷいぷい かわいくなぁれ~~☆」 |
あざらし姫(642) により ItemNo.1 駄物 から法衣『老魔女の遺言書』を作製してもらいました!
⇒ 老魔女の遺言書/法衣:強さ17/[効果1]- [効果2]- [効果3]幸運5/特殊アイテム
 |
あざらし姫 「はいどーぞ。 ポイントカードにアザラシ印ひとつつけとくわね。 5の倍数ごとにオリジナルグッズプレゼント! なくさんようにね?」 |
あざらし姫(642) の持つ ItemNo.3 不思議な食材 から料理『イモリ丸焼きスープ』をつくりました!
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『イモリ丸焼きスープ』をつくりました!
⇒ イモリ丸焼きスープ/料理:強さ25/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
| シーラ 「(鼻歌を歌いながら なべをかきまぜる すすけた魔女の鍋に色々の具材がほうりこまれていく)」 |
 |
(禍々しい色の液体に それ雑草じゃないのか?ってかんじのハーブ、 黒焦げイモリが丸ごとはいっている 鍋からサフランにも似たワキガ的な芳香がたちのぼる なんだか ぜんたいてきにちょっと不衛生そうだ。) |
犬(1232) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『竜の血』をつくりました!
マキナ(567) とカードを交換しました!
護身 (カウンター)

ストライク を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度0⇒1)
ストーンブラスト を研究しました!(深度1⇒2)
カース を習得!
サステイン を習得!
ヒールポーション を習得!
クリエイト:スパイク を習得!
ペレル を習得!
ポイズン を習得!
アシスト を習得!
クリエイト:ヴェノム を習得!
スコーピオン を習得!
魅惑 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- ドーラ・シーラ(103) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 犬(1232) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――







ENo.103
百葉箱のしぃらさん



【 #荊街七不思議企画 】
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
設定画など
https://karasuyokarasu.tumblr.com/
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
設定画など
https://karasuyokarasu.tumblr.com/
21 / 30
72 PS
チナミ区
E-13
E-13





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 老魔女の遺言書 | 法衣 | 17 | - | - | 幸運5 | |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 4 | 図録『大陸西哺乳類解剖図』 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 血錆びたサーベル | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程2】 |
| 6 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV10)[効果2]充填10(LV20)[効果3]増幅10(LV30) | |||
| 7 | イモリ丸焼きスープ | 料理 | 25 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 15 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 初級魔法『エアロブレイク』 (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 初級魔法『ウィンドスピア』 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 初級魔法『トルナド』 (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 初級魔法『エアロブラスト』 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 神経系再結合『感覚器鈍磨』 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 神経系再結合『多幸感』 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 魔導具『フェロモン撒布器』 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 烏百羽・金切声 (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| シーラの眷属『下級木偶』 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| シーラの眷属『潰れ目精霊』 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| シーラの眷属『くずキマイラ』 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| シーラの眷属『ハナナギトカゲ』 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| シーラの眷属『土くれゴーレム』 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| シーラの眷属『銀のドナテラ』 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| シーラの眷属『マジョ草』 (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ストライク | [ 1 ]ティンダー | [ 2 ]ストーンブラスト |
| [ 1 ]アサルト |

PL / 宮沢