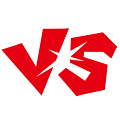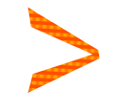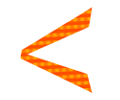<< 0:00~0:00





【SICX LIVES】
否定の世界アンジニティ 『ドーラ・シーラ』ログ
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html
【1更新目】http://grandaria.ddo.jp/sicx/sicxlist/sicxlist.cgi?eno=670&imgon=1&season=1&day=1&mode=e2p&mount=O&type=k

【騒乱イバラシティ 百葉箱のしぃらさんの呪文 より】
カラスよカラス、なぜにとぶ
我が身をカワズとおもうてか?

【SICX LIVES ドーラ・シーラの日記 10ページめより】
あ、そうだ。
かえるだ。
かえる。
誰だって、一生に一度のことは、忘れがたく、強い。
感動的で、ぞっとして、熱くなる。
潤い、魂から震えが来て、圧倒される。
初恋。初潮。初産。死。それに、初めて人を殺めた、思い出。
+ + +
少女のドーラ・シーラの友達は、カエルだった。
カエルはそこらにいた。そして、手に入れ、同じ年代の少年がするように、振舞っても、いい訳だから。
だから、カエルはシーラの友達だった。
ドーラ・シーラはカエルを捕らえ、瓶の中に閉じ込めた。
鳴き声を聞いた。
泳ぐ姿を見た。
跳ねる姿を見た。
質感を味わった。
手に吸い付いた。
舌をつまんだ。
捕食の姿を見た。
つがわせてみた。
乾くのを見た。
足を切った。
這う様を眺めた。
…何故だか解らない軽蔑があった。
きっとそれは(彼女には――)虫や、蛙には、工夫が無いように思えたからだ。
バランスがとれないのは仕方が無い。けれど『無いもの』に同じ様に力を込める姿がイヤだった。
ドーラ・シーラは友人を通して、自分が何を愛するのかを見つけ始めていた。
空気を入れた。
目を潰した。
ショックを与えた。
腹を割いた。
…回を重ねるごとに、シーラはカエルに詳しくなっていった。
シーラはガラスや金属の破片、鳥の骨、糸などを上手に使い、カエルをばらばらにした。
皮をはぎ、心臓、肝臓、胃、腸、肺、脂肪体を傷つけずに取り出して、
パズルのように、またもと通りに戻す事ができた。
シーラにはカエルの体を見透かしたような喜びがあったが、満足感までには至らなかった。
だって、シーラにはカエルの心が解らなかったから。
カエルはシーラに何かを望みはしなかった。
自由を求めも。許しを請いも。感謝を叫びも。
彼等は自分の子供すら、守ろうなんてしないのだ。
シーラは頭を捻って、村中を歩きながらぐるぐると考えて、
それでようやく、カエルの欲望を思い当たった。
シーラはわざとカエルを空腹にさせた。
「おなかがすいた」もしくは、「なにかたべたい」。
これだ。カエルの心はきっと今、そうだ。そして、エサを入れてやれば、食べる。
この一瞬。この一瞬だけだが、シーラはカエルを見透かしたという満足感があった。
シーラはそのような事を考えながら、指先で友人を玩び、それでも解らない。
見透かす事の出来る、親しい彼等を、どうして心の底でイヤがってしまうのか。
か弱いから、自分は彼らを見下すのだろうか。
ドーラ・シーラは分別があった、自分のすることを残酷な事だとある程度認識していた。
そう、『カエル』は『私』にひどい事をされている。
だけどこれらの手ひどい仕打ちに対して、歯向かう術を持たないから―だから彼等を蔑むのだろうか?
現状を把握できず、どこかへ逃げ惑う姿が滑稽だから?弱いから、ばかだから…
だけど、
ちがう。
知性、それから力の差。そのような生物としての方向性は、彼女は百も承知で、好きなはずだった。
少女のドーラ・シーラは思う。
(やはり私も人間ということなのかしら。)
人間という種に生まれつき、無条件に同じ種を殺す事に嫌悪を抱き、傍に寄る事を許す、
人間という種をカエルという種よりも愛する。
だけど、
ちがう。
負傷した足を労われ。きっとそれだ。
その無遠慮な動作が、痛々しいのだ。
『痛み』だ。
痛みが無い生き物はいけない。
痛みは存在の重みに直結する。少なくとも、彼女の感性に置いては。
痛みは、人間という生き物を象る大切な要素だった。
だからシーラは、友人を捨てた。
体の隅々まで、心の予測まで、理解したとして、
これはなんて軽い存在なのだろう。
今こそは、彼らが釣り針を通され、餌にされてしまう理由が解る気がした。
…
命には重さがある。
命自体が同じ重さであろうと、複雑さに応じ付加されるものは、無視できない。
そして秤を作るのは人間なのだ。彼女は彼女のピンセットで、命の重さを秤にかけた。
どの要素をその生き物に加えれば、どれだけ重要になるものか。
どの要素をその生き物から取り去れば、どれだけ些末になるものか。
そうしているうちに、生物を分ける、生物の枠組み、
哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類…という認識が一度、曖昧になっていく気がした。
紐を解けば、解く程に、人間はヒトになっていった。
言葉を授け、歴史を語り、社会を築く、けものは、シーラの一等のお気に入りの生物へと。
ふっ、と、思ったのだ。
カエルの心を見透かしたあの時。
状況を作ってやることで、カエルと自分の考えが一体になった、あの瞬間。
それをヒトで出来るなら、より面白い、のではないかと。
その先に今の彼女がある。
そうだ、かえるだ。でも、かえるよりずっと素敵な感じがする。
幸福な、甘い罪悪感だけが残っていた。
少し恥ずかしい、若さに満ちた麗しい通過儀礼のように思われた。
初めて人を殺すとき、心が湿って気持ちがいいの。

・・・【ドーラ・シーラ】・・・
ある世界で、その魔女はこう呼ばれていた、『悪意の魔女』と。
彼女はこころない冷血である。
大陸の伝記によれば、
ドーラ・シーラの出自はある原始的な田舎村の、ありふれた娘だった。
科学と哲学を愛する、いつも上の空な「ちょっと変な子」。
子供の頃の彼女には、なんらおかしな兆候はなかった。
人懐こい笑みを浮かべる彼女に、“こころがない”なんて事は誰も思いもしなかった。
暮しぶりにも他と比べて何が足りないという事はなく、満足の行くものだったはずだった。
発達途上の少女の心を不安にさせる危険と言えば、この大陸には魔物がいて、
人は魔物退治を日常としなければいけなかったという事はあったものの。
ドーラ・シーラは大人になる頃、魔物の討伐ギルドに入るために都会に出てきた。
仕事ぶりは可もなく不可もなく、目立つ方ではなかった。
研究者気質で、自ら進んで討伐に出かけるというよりは 内地で魔法や薬品の開発の役割を担っていた。
いつすれ違っても、研究あがりで寝間着でそのまま外に出てきたような、「ちょっと変な人」。
彼女が内部から、ギルドの依頼文の内容を勝手に書き換えたり
出征前の討伐者の道具に悪いまじないをかけたり
秘密裏に倫理にもとる研究をしてきたこと、全ては後から解ったことである。
依頼に失敗して誰かが死ぬ横を、誰にも気づかれないまま彼女は鼻歌交じりに笑って通り過ぎていた。
例えばそれは「これからまだ強大になる魔物の幼体の討伐が行われる」と言ったとき、
魔物の成長を守るために行われた対処だった。
ドーラ・シーラという魔女は、魔物を繁殖し、育て、力や知恵を分け与え、
人類と魔物の戦争を激化、長期化させていたのだ。
そんなことをするドーラ・シーラとは、一体何者なのか。
それは、まさしく、何者でもなかった。
彼女にはそうしなければいけない理由や立場は何もなかった。
出自から変わらぬ無名の娘だ。
ただ、彼女の中では、自分の行動は常に連綿と繋がっていた。
子供の頃、彼女はカエルをよく観察していた。
観察・実験対象が、彼女の何よりの親友だった。
一番一緒にいて楽しいし、一番心が通じたように感じる存在。
彼女は元より親友とは実験対象で、実験対象以外には親愛もない。
生命のつながりは、実験者と被検体というかたちでしか感じられなかった。
人に責められると、とても戸惑う。家族や、恋人や友人に人体実験をしてはいけない理由があるはずがないのに。
まるでおばけでも見るかのような、不可思議なことだった。
人はなぜか恋人や友人や家族に人体実験をしてはいけないというおばけを見ている。
おばけとは、あるいは脳波の誤作動、あると思うからあると感じるものじゃないか。
ドーラ・シーラを占める最も大きなものは知的好奇心である。
彼女は研究が好きだった。ある種の善意でもあったし、被検体に対する愛着でもあった。
彼女は『人間は壁があって初めて乗り越えようとする力を発揮する』と考える性質だった。
彼女は、愛すべき人類の進化と繁栄の為に日夜血なまぐさい研究に励んでいたのだ。
そして彼女にとって“痛み”は高尚さのキーだった。
心身のきず、痛みが、人間の価値を証明する最も大きな要素だった。
逆もしかり…痛みの感じられない生物なら、興味を注ぐ研究対象の地位を失う。
ドーラ・シーラの作り上げた『現象』は、まさしくその世界の脅威であった。
魔物の知力は人間にちかづき怪物となり、魔物の武力を超えようと人間は怪物になって行く。
だが同時に、なんとも陳腐な顛末は、彼女自身にはなんら特別な力は無かったことだ。
彼女はさして魔力も強くも無く、科学者的な立場から地道に人間の敵となるようなものを作っていた。
魔物らもシーラの言うことを聞くのではなく、シーラがただ彼等の習性を理解しているだけだった。
正体に辿り着けばただの一人の人間である彼女は、簡単に倒れる。
例えば恋人、例えば家族。真心からの愛を受け、心動くことはあった。
ちょうど水族館のペンギンが飼育員に求愛行動を受け
「なんてかわいらしいの!」と感激するかんじだった。
ペンギンがかわいければかわいいほどに返せる愛情は飼育してやるだけの事、
彼女には、なんの同情もいらない。
彼女は人間だ、けれどもなんの同情もいらない。
彼女とて、想像できうるすべての犠牲をはらい、
一人の人間が出来る限り最大の努力をとして、他人に同情することが出来ないのだから。
まあ、言葉を尽くすのもそもそもナンセンスじゃないか。
黒い物質を見つけたら「この世でもっとも黒い物質を新たに見つけ出せないだろうか」とときめく、酸をみつけたら「この世でもっとも強い酸を新たに作り出せないだろうか」とときめく。科学者とはそんなもの。
放っておいても彼女は人間に痛みを蒔く。それが彼女のサイエンス、そしてマジック、その切実なときめきは、恋にも闘争心にもまさる、夢見心地な好奇心。
とっても素敵な人類の進化をはじめましょう。
=この侵略戦によって、悪意は否定の世界『アンジニティ』から解き放れようとしている=



ENo.17 サクマ とのやりとり

ENo.100 百物語アカリ とのやりとり

ENo.205 ミツ とのやりとり

ENo.403 アミナ とのやりとり










駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
具現LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
森(1047) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『図録『大陸西哺乳類解剖図』』を作製してもらいました!
⇒ 図録『大陸西哺乳類解剖図』/装飾:強さ30/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
犬(1232) により ItemNo.5 不思議な石 から射程2の武器『血錆びたサーベル』を作製してもらいました!
⇒ 血錆びたサーベル/武器:強さ30/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程2】/特殊アイテム
御曹院(699) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『涙が出る料理』をつくりました!
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『フラスコ入り ホット山羊ミルク』をつくりました!
⇒ フラスコ入り ホット山羊ミルク/料理:強さ20/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]-/特殊アイテム
犬(1232) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『身体強化薬A(治験中)』をつくりました!
小石(1270) とカードを交換しました!
石の欠けた部分 (ブレイク)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
アサルト を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
クリエイト:タライ を習得!
クリエイト:シールド を習得!
チャージ を習得!
召喚強化 を習得!
サモン:ウォリアー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 E-10(森林)に移動!(体調26⇒25)
犬(1232) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- ドーラ・シーラ(103) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 犬(1232) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
エディアンからのチャットが閉じられる――














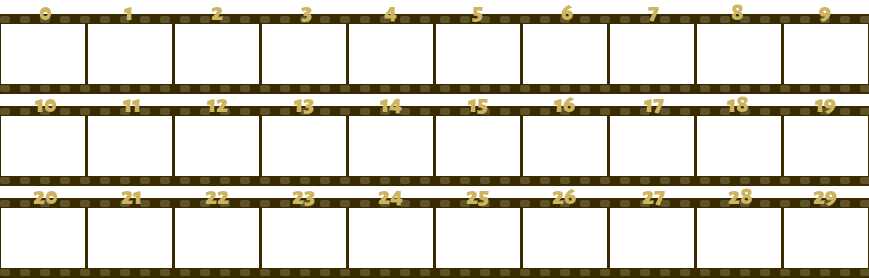







































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




【SICX LIVES】
否定の世界アンジニティ 『ドーラ・シーラ』ログ
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html
【1更新目】http://grandaria.ddo.jp/sicx/sicxlist/sicxlist.cgi?eno=670&imgon=1&season=1&day=1&mode=e2p&mount=O&type=k

【騒乱イバラシティ 百葉箱のしぃらさんの呪文 より】
カラスよカラス、なぜにとぶ
我が身をカワズとおもうてか?

【SICX LIVES ドーラ・シーラの日記 10ページめより】
あ、そうだ。
かえるだ。
かえる。
誰だって、一生に一度のことは、忘れがたく、強い。
感動的で、ぞっとして、熱くなる。
潤い、魂から震えが来て、圧倒される。
初恋。初潮。初産。死。それに、初めて人を殺めた、思い出。
+ + +
少女のドーラ・シーラの友達は、カエルだった。
カエルはそこらにいた。そして、手に入れ、同じ年代の少年がするように、振舞っても、いい訳だから。
だから、カエルはシーラの友達だった。
ドーラ・シーラはカエルを捕らえ、瓶の中に閉じ込めた。
鳴き声を聞いた。
泳ぐ姿を見た。
跳ねる姿を見た。
質感を味わった。
手に吸い付いた。
舌をつまんだ。
捕食の姿を見た。
つがわせてみた。
乾くのを見た。
足を切った。
這う様を眺めた。
…何故だか解らない軽蔑があった。
きっとそれは(彼女には――)虫や、蛙には、工夫が無いように思えたからだ。
バランスがとれないのは仕方が無い。けれど『無いもの』に同じ様に力を込める姿がイヤだった。
ドーラ・シーラは友人を通して、自分が何を愛するのかを見つけ始めていた。
空気を入れた。
目を潰した。
ショックを与えた。
腹を割いた。
…回を重ねるごとに、シーラはカエルに詳しくなっていった。
シーラはガラスや金属の破片、鳥の骨、糸などを上手に使い、カエルをばらばらにした。
皮をはぎ、心臓、肝臓、胃、腸、肺、脂肪体を傷つけずに取り出して、
パズルのように、またもと通りに戻す事ができた。
シーラにはカエルの体を見透かしたような喜びがあったが、満足感までには至らなかった。
だって、シーラにはカエルの心が解らなかったから。
カエルはシーラに何かを望みはしなかった。
自由を求めも。許しを請いも。感謝を叫びも。
彼等は自分の子供すら、守ろうなんてしないのだ。
シーラは頭を捻って、村中を歩きながらぐるぐると考えて、
それでようやく、カエルの欲望を思い当たった。
シーラはわざとカエルを空腹にさせた。
「おなかがすいた」もしくは、「なにかたべたい」。
これだ。カエルの心はきっと今、そうだ。そして、エサを入れてやれば、食べる。
この一瞬。この一瞬だけだが、シーラはカエルを見透かしたという満足感があった。
シーラはそのような事を考えながら、指先で友人を玩び、それでも解らない。
見透かす事の出来る、親しい彼等を、どうして心の底でイヤがってしまうのか。
か弱いから、自分は彼らを見下すのだろうか。
ドーラ・シーラは分別があった、自分のすることを残酷な事だとある程度認識していた。
そう、『カエル』は『私』にひどい事をされている。
だけどこれらの手ひどい仕打ちに対して、歯向かう術を持たないから―だから彼等を蔑むのだろうか?
現状を把握できず、どこかへ逃げ惑う姿が滑稽だから?弱いから、ばかだから…
だけど、
ちがう。
知性、それから力の差。そのような生物としての方向性は、彼女は百も承知で、好きなはずだった。
少女のドーラ・シーラは思う。
(やはり私も人間ということなのかしら。)
人間という種に生まれつき、無条件に同じ種を殺す事に嫌悪を抱き、傍に寄る事を許す、
人間という種をカエルという種よりも愛する。
だけど、
ちがう。
負傷した足を労われ。きっとそれだ。
その無遠慮な動作が、痛々しいのだ。
『痛み』だ。
痛みが無い生き物はいけない。
痛みは存在の重みに直結する。少なくとも、彼女の感性に置いては。
痛みは、人間という生き物を象る大切な要素だった。
だからシーラは、友人を捨てた。
体の隅々まで、心の予測まで、理解したとして、
これはなんて軽い存在なのだろう。
今こそは、彼らが釣り針を通され、餌にされてしまう理由が解る気がした。
…
命には重さがある。
命自体が同じ重さであろうと、複雑さに応じ付加されるものは、無視できない。
そして秤を作るのは人間なのだ。彼女は彼女のピンセットで、命の重さを秤にかけた。
どの要素をその生き物に加えれば、どれだけ重要になるものか。
どの要素をその生き物から取り去れば、どれだけ些末になるものか。
そうしているうちに、生物を分ける、生物の枠組み、
哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類…という認識が一度、曖昧になっていく気がした。
紐を解けば、解く程に、人間はヒトになっていった。
言葉を授け、歴史を語り、社会を築く、けものは、シーラの一等のお気に入りの生物へと。
ふっ、と、思ったのだ。
カエルの心を見透かしたあの時。
状況を作ってやることで、カエルと自分の考えが一体になった、あの瞬間。
それをヒトで出来るなら、より面白い、のではないかと。
その先に今の彼女がある。
そうだ、かえるだ。でも、かえるよりずっと素敵な感じがする。
幸福な、甘い罪悪感だけが残っていた。
少し恥ずかしい、若さに満ちた麗しい通過儀礼のように思われた。
初めて人を殺すとき、心が湿って気持ちがいいの。

・・・【ドーラ・シーラ】・・・
ある世界で、その魔女はこう呼ばれていた、『悪意の魔女』と。
彼女はこころない冷血である。
大陸の伝記によれば、
ドーラ・シーラの出自はある原始的な田舎村の、ありふれた娘だった。
科学と哲学を愛する、いつも上の空な「ちょっと変な子」。
子供の頃の彼女には、なんらおかしな兆候はなかった。
人懐こい笑みを浮かべる彼女に、“こころがない”なんて事は誰も思いもしなかった。
暮しぶりにも他と比べて何が足りないという事はなく、満足の行くものだったはずだった。
発達途上の少女の心を不安にさせる危険と言えば、この大陸には魔物がいて、
人は魔物退治を日常としなければいけなかったという事はあったものの。
ドーラ・シーラは大人になる頃、魔物の討伐ギルドに入るために都会に出てきた。
仕事ぶりは可もなく不可もなく、目立つ方ではなかった。
研究者気質で、自ら進んで討伐に出かけるというよりは 内地で魔法や薬品の開発の役割を担っていた。
いつすれ違っても、研究あがりで寝間着でそのまま外に出てきたような、「ちょっと変な人」。
彼女が内部から、ギルドの依頼文の内容を勝手に書き換えたり
出征前の討伐者の道具に悪いまじないをかけたり
秘密裏に倫理にもとる研究をしてきたこと、全ては後から解ったことである。
依頼に失敗して誰かが死ぬ横を、誰にも気づかれないまま彼女は鼻歌交じりに笑って通り過ぎていた。
例えばそれは「これからまだ強大になる魔物の幼体の討伐が行われる」と言ったとき、
魔物の成長を守るために行われた対処だった。
ドーラ・シーラという魔女は、魔物を繁殖し、育て、力や知恵を分け与え、
人類と魔物の戦争を激化、長期化させていたのだ。
そんなことをするドーラ・シーラとは、一体何者なのか。
それは、まさしく、何者でもなかった。
彼女にはそうしなければいけない理由や立場は何もなかった。
出自から変わらぬ無名の娘だ。
ただ、彼女の中では、自分の行動は常に連綿と繋がっていた。
子供の頃、彼女はカエルをよく観察していた。
観察・実験対象が、彼女の何よりの親友だった。
一番一緒にいて楽しいし、一番心が通じたように感じる存在。
彼女は元より親友とは実験対象で、実験対象以外には親愛もない。
生命のつながりは、実験者と被検体というかたちでしか感じられなかった。
人に責められると、とても戸惑う。家族や、恋人や友人に人体実験をしてはいけない理由があるはずがないのに。
まるでおばけでも見るかのような、不可思議なことだった。
人はなぜか恋人や友人や家族に人体実験をしてはいけないというおばけを見ている。
おばけとは、あるいは脳波の誤作動、あると思うからあると感じるものじゃないか。
ドーラ・シーラを占める最も大きなものは知的好奇心である。
彼女は研究が好きだった。ある種の善意でもあったし、被検体に対する愛着でもあった。
彼女は『人間は壁があって初めて乗り越えようとする力を発揮する』と考える性質だった。
彼女は、愛すべき人類の進化と繁栄の為に日夜血なまぐさい研究に励んでいたのだ。
そして彼女にとって“痛み”は高尚さのキーだった。
心身のきず、痛みが、人間の価値を証明する最も大きな要素だった。
逆もしかり…痛みの感じられない生物なら、興味を注ぐ研究対象の地位を失う。
ドーラ・シーラの作り上げた『現象』は、まさしくその世界の脅威であった。
魔物の知力は人間にちかづき怪物となり、魔物の武力を超えようと人間は怪物になって行く。
だが同時に、なんとも陳腐な顛末は、彼女自身にはなんら特別な力は無かったことだ。
彼女はさして魔力も強くも無く、科学者的な立場から地道に人間の敵となるようなものを作っていた。
魔物らもシーラの言うことを聞くのではなく、シーラがただ彼等の習性を理解しているだけだった。
正体に辿り着けばただの一人の人間である彼女は、簡単に倒れる。
例えば恋人、例えば家族。真心からの愛を受け、心動くことはあった。
ちょうど水族館のペンギンが飼育員に求愛行動を受け
「なんてかわいらしいの!」と感激するかんじだった。
ペンギンがかわいければかわいいほどに返せる愛情は飼育してやるだけの事、
彼女には、なんの同情もいらない。
彼女は人間だ、けれどもなんの同情もいらない。
彼女とて、想像できうるすべての犠牲をはらい、
一人の人間が出来る限り最大の努力をとして、他人に同情することが出来ないのだから。
まあ、言葉を尽くすのもそもそもナンセンスじゃないか。
黒い物質を見つけたら「この世でもっとも黒い物質を新たに見つけ出せないだろうか」とときめく、酸をみつけたら「この世でもっとも強い酸を新たに作り出せないだろうか」とときめく。科学者とはそんなもの。
放っておいても彼女は人間に痛みを蒔く。それが彼女のサイエンス、そしてマジック、その切実なときめきは、恋にも闘争心にもまさる、夢見心地な好奇心。
とっても素敵な人類の進化をはじめましょう。
=この侵略戦によって、悪意は否定の世界『アンジニティ』から解き放れようとしている=
| 「さあ!この監獄のような世界はもううんざり。 わたしをここから出してくださいな、実験を続けましょう…! イバラシティよりもっとたくさんの、人類種の繁栄と発展のために、進化の為の礎となるって それってなんだか…とってもとっても、すてきじゃない?」 |



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.100 百物語アカリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.205 ミツ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.403 アミナ とのやりとり



 |
(カラスがあちらこちらつついている…) |





駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
具現LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
森(1047) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『図録『大陸西哺乳類解剖図』』を作製してもらいました!
⇒ 図録『大陸西哺乳類解剖図』/装飾:強さ30/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
《おまえから見てすぐ右の木は朽ちかけだ、紙とすることを特別に許そう》 |
犬(1232) により ItemNo.5 不思議な石 から射程2の武器『血錆びたサーベル』を作製してもらいました!
⇒ 血錆びたサーベル/武器:強さ30/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程2】/特殊アイテム
 |
誰のものとも知れない乾いた血が張り付いている。 |
御曹院(699) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『涙が出る料理』をつくりました!
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『フラスコ入り ホット山羊ミルク』をつくりました!
⇒ フラスコ入り ホット山羊ミルク/料理:強さ20/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]-/特殊アイテム
| シーラ 「(鼻歌を歌いながら ミルクを温めている)」 |
犬(1232) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『身体強化薬A(治験中)』をつくりました!
小石(1270) とカードを交換しました!
石の欠けた部分 (ブレイク)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
アサルト を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
クリエイト:タライ を習得!
クリエイト:シールド を習得!
チャージ を習得!
召喚強化 を習得!
サモン:ウォリアー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ほれ、着いたぜ。お代は土産話でよろしく。」 |
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 E-10(森林)に移動!(体調26⇒25)
犬(1232) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- ドーラ・シーラ(103) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 犬(1232) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「1時間が経過しましたね。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャットで時間が伝えられる。
 |
エディアン 「ナレハテとの戦闘、お疲れ様でした! 相手を戦闘不能にすればいいようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「さてさて。皆さんにご紹介したい方がいるんです。 ――はい、こちらです!こちらでーっす!!」 |
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
エディアン 「陣営に関わらず連れて行ってくれるようですのでどんどん利用しましょー!! ドライバーさんは中立ってことですよね?」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
エディアン 「たくさん・・・同じ顔がいっぱいいるんですかねぇ・・・。 ここはまだ、分からないことだらけです。」 |
 |
エディアン 「それでは再びの1時間、頑張りましょう! 新情報を得たらご連絡しますね。ファイトー!!オーッ!!」 |
エディアンからのチャットが閉じられる――





ENo.103
百葉箱のしぃらさん



【 #荊街七不思議企画 】
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
設定画など
https://karasuyokarasu.tumblr.com/
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
設定画など
https://karasuyokarasu.tumblr.com/
25 / 30
5 PS
チナミ区
E-10
E-10





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 図録『大陸西哺乳類解剖図』 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 血錆びたサーベル | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程2】 |
| 6 | フラスコ入り ホット山羊ミルク | 料理 | 20 | 器用10 | 敏捷10 | - | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 10 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 初級魔法『エアロブレイク』 (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 初級魔法『ウィンドスピア』 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 初級魔法『トルナド』 (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 初級魔法『エアロブラスト』 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 神経系再結合『感覚器鈍磨』 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 神経系再結合『多幸感』 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 魔導具『フェロモン撒布器』 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 烏百羽・金切声 (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| シーラの眷属『下級木偶』 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| シーラの眷属『潰れ目精霊』 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| シーラの眷属『くずキマイラ』 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| シーラの眷属『ハナナギトカゲ』 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| シーラの眷属『土くれゴーレム』 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| シーラの眷属『銀のドナテラ』 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| シーラの眷属『マジョ草』 (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]アサルト |

PL / 宮沢