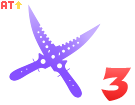<< 5:00




***
脳裏に残った、最初で最後のこの森の記憶は、
開いて間もない目から見えた、おぼろげな光景。
深い緑を、淡い白と青の光が覆う、幻想の世界。
習わしどおりであれば、この場所に育ち、
いつしか求めに応じて外に出ていく。
神の使いとして人々に祝福を与え。
あるいは人々を守るために神力を用い。
その狐には終ぞ、元来望まれたことをする機会は巡ってこなかった。
生まれた森から、奪われて、いなくなってしまった。
爾来、在るべき姿を知らぬまま、
敵対するものに災厄を与え、生を断つために妖力を用い。
***
倒れた少女の身体を抱いて、
狐は自分が生まれた世界へと戻る。
場所としては何も変わらない、少女のいる里の森の奥。
ただ、普通の人には見えない世界、
見えないだけで、常にそこにある、 怪異の住む世界。
自分がなにか行うにはこちらのほうがやりやすく、都合がいいし、
さっきのような追手がまだいる可能性もある。
そこら中にいる怪異が興味本位で手を出してくる可能性もあるが、
こちらから何もしなければ基本的になにも仕返してはこないし、
追手に比べればよほどましだ。
少女を木の根元に置いて、ヒトの姿から狐の姿へと戻る。
少女の顔色は、世界の色を差し引いても、血の気を失って青白くなっていく。
結局――数多の犠牲を強いて、
生まれた森に帰ってきたと思えば、
静かに過ごせるなどという都合のいい話はなく、
今も、他人の血に塗れている。
どこまでいっても、血で血を洗うような世界から逃れられないのであれば、
せめて最後に、目の前の少女を助けて終わりにしよう。
本来なら、きっとこのような目に合うことのなかった子を。
――ただひとつ、誤算だったのは。
この少女は、
こんな世界で生きていくことに
・・・・・・・・・
向いていなさすぎた。
何にでも手を伸ばして、
なんでも手で掴もうとして。
怖れもなく、抵抗もなく。
ただ真っ直ぐに。
自分が持ち合わせることはなかった性質ばかりで、
見ているだけでもどかしく思うぐらいに。
自分が持っていた力は尾が3本分。
追手を直ちに退かせるのに1本使った。
少女を助けるために、1本分を少女の内へ。
そして、この少女に霊的な素養は皆無と目されるので、
この致命傷が癒えるまで、最期の一本は、少女に憑く。
少女の傷が癒えたなら、あとは消えるまで、時間が過ぎるのを待つだけだ。
本来であればいくつも手順を踏む必要があるものの、
そのような猶予も、実現できる可能性もないので、
事前の準備も、合意も何もなく、強制的に執り行う。
人と狐の間で何かをする場合、狐笛の『音』が多くの場合要件に挙がるが、
『音』でなければならない必要は、あまりない。
要は、笛を介して、自分の情報が相手に渡りさえすれば良い。
自分の魂を、相手に移すように。
狐は、自分が持っていた狐笛をくわえる。
通例、術者が死ぬなどして、狐が笛を持ち帰るというような場合でもなければ、
狐が笛を持つことはないが、この笛は、この森に帰ってくる前に、
最後に自分を使役していた術者に渡されたものだ。
いわく、帰ってから、どうするかは決めればいいと。
ありがたく、そのようにさせてもらう。
狐は、動かない少女の身体に触れる。
目を覚まして、気づいたときには、
驚くといった程度では済まないだろうが、
そこは目を瞑ってもらうことにする。
少女に狐が憑いて、一命を取り留めて、そして目を覚ました時。
そこは、彼女にとってまったく見覚えのない森の中。
まだ頭の中がぼやけているせいか思い出せないが、
何かしないといけないことがある気がする。
すこし後になって、
彼女は、そこが学校の敷地の中だったと知った。
***
***
イバラシティの5月の終わり。
音のない静かな夜更。
住んでいるマンションの屋上。
わたしはなにもなかった屋上に、仰向けになって転がった。
「だーめーだー。うまくいーかーなーいー」
チョークで見よう見まねの陣を描いてみたり。
なにかそれっぽいものを燻してみたり。
指を切って血を落とそうとしてみたり(これは止められた。)
狐笛を吹こうとしてみたり。
自前の霊力がそろそろ枯渇して消えていきそうな霊狐を
なんとか繋ぎ止めようと四苦八苦しているところ、
最初から薄々感じていたし、色々試して改めて突きつけられるが、
どうやら根本的に、わたしにはそういった霊力やら何やらを操るといった才能が足りないらしい。
昔聞いたような記憶によれば、自分の祖父母以前は割とその方面に長けていたそうだが、
隔世遺伝とかそういったうまい話はないようだ。
その世代あたりで才能が尽きたのかも知れない。
自分の親についても、そういった話はあまり聞いた覚えがない。
(聞かされていないだけかも知れないけど。)
3月や4月の半ばあたりまでは呼ばなくてもたまには出てきた狐は、
5月になってからは、用があって初めて出てくるぐらいになった。
それだけ消耗しているのか、温存しているのか。
自分がうまいこと、それこそ何かを召喚するみたいな力でもあれば、
自分の中に埋もれてるはずの狐の尾の霊力をぱっと明け渡すなどなんとでもできたろうに。
しかしないものをいくらねだっても仕方がないので、最後の作戦を試すことにする。
「こーかーげー。出てー」
ずるりと自分の中から狐が這い出す。
最初は驚きもしたが、とうの昔に慣れてしまった。
月の光が狐の身体をすり抜けるように通っていく。
それぐらい薄く、存在は弱々しい。
さっきまではそんな霊体に対して
なんとか契約などしようと試していたが、
そういう霊的な素養はないので。
もっと物理的に。原始的に。
「10秒だけでいいから、言ったら実体化して」
それが相手が消える時間を早めるというのは十分承知している。
もとより、おもっている手段が全部付きたらどうしようもないから、気にしてはいられない。
わたしの言葉に、狐は一瞬嫌そうな表情をした。ような気がした。
「逃げないでよ。
これは、きっと『お前がわたしにやった』ことのはずだから」
わたしはそれをやり返すだけ」
起き上がると、自分の首から提げた笛を手に持って、
体長だけみれば自分とそんなに変わらない狐に近づいていく。
「移してもらったんだから、それをちょっとでも、返すだけ」
狐笛を口に咥える。
そこでちょうど。
星がまたたく。
何が起きたのかは、分からない。
ただ、強く強く輝く光が、夜空を覆っていく。
流れ星というには強すぎる光。
でも、わたしにとっては、少しでも希望になる光。
「神使様に大切なお守りももらって、流れ星まで降ってきて、失敗するわけないよね!」
合図をする。
眼の前の狐の身体がほんの僅かな間、質量を持つ。
淡い月の光のような毛。
わたしは膝をついて、目線を合わせて、さらに近づいていく。
狐笛を介して、眼の前の狐とつながるように。
触れる。



ENo.167 うさ子 とのやりとり

ENo.664 闇のおえかき とのやりとり

ENo.959 安倍葛子 とのやりとり

ENo.1132 玲瓏 とのやりとり

以下の相手に送信しました













ニアク(79) は たけのこ を入手!
ヘイゼル(1355) は 柳 を入手!
モドラ(1457) は 柳 を入手!
みつき(1495) は たけのこ を入手!
ニアク(79) は 美味しい草 を入手!
ヘイゼル(1355) は 爪 を入手!
ニアク(79) は 剛毛 を入手!
みつき(1495) は 牙 を入手!





チナミ区 J-19(沼地)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 J-20(沼地)に移動!(体調6⇒5)
カミセイ区 J-1(沼地)に移動!(体調5⇒4)
カミセイ区 J-2(沼地)に移動!(体調4⇒3)
カミセイ区 J-3(道路)に移動!(体調3⇒2)





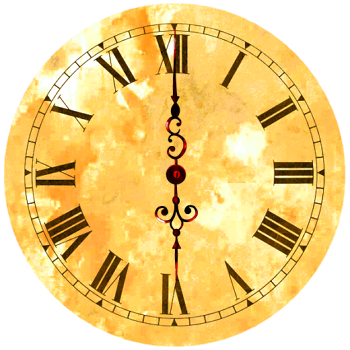
―― ハザマ時間が紡がれる。


ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
声は淡々と、話を続ける。
声はそこで終わる。
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



***
脳裏に残った、最初で最後のこの森の記憶は、
開いて間もない目から見えた、おぼろげな光景。
深い緑を、淡い白と青の光が覆う、幻想の世界。
習わしどおりであれば、この場所に育ち、
いつしか求めに応じて外に出ていく。
神の使いとして人々に祝福を与え。
あるいは人々を守るために神力を用い。
その狐には終ぞ、元来望まれたことをする機会は巡ってこなかった。
生まれた森から、奪われて、いなくなってしまった。
爾来、在るべき姿を知らぬまま、
敵対するものに災厄を与え、生を断つために妖力を用い。
***
倒れた少女の身体を抱いて、
狐は自分が生まれた世界へと戻る。
場所としては何も変わらない、少女のいる里の森の奥。
ただ、普通の人には見えない世界、
見えないだけで、常にそこにある、 怪異の住む世界。
自分がなにか行うにはこちらのほうがやりやすく、都合がいいし、
さっきのような追手がまだいる可能性もある。
そこら中にいる怪異が興味本位で手を出してくる可能性もあるが、
こちらから何もしなければ基本的になにも仕返してはこないし、
追手に比べればよほどましだ。
少女を木の根元に置いて、ヒトの姿から狐の姿へと戻る。
少女の顔色は、世界の色を差し引いても、血の気を失って青白くなっていく。
結局――数多の犠牲を強いて、
生まれた森に帰ってきたと思えば、
静かに過ごせるなどという都合のいい話はなく、
今も、他人の血に塗れている。
どこまでいっても、血で血を洗うような世界から逃れられないのであれば、
せめて最後に、目の前の少女を助けて終わりにしよう。
本来なら、きっとこのような目に合うことのなかった子を。
――ただひとつ、誤算だったのは。
この少女は、
こんな世界で生きていくことに
・・・・・・・・・
向いていなさすぎた。
何にでも手を伸ばして、
なんでも手で掴もうとして。
怖れもなく、抵抗もなく。
ただ真っ直ぐに。
自分が持ち合わせることはなかった性質ばかりで、
見ているだけでもどかしく思うぐらいに。
自分が持っていた力は尾が3本分。
追手を直ちに退かせるのに1本使った。
少女を助けるために、1本分を少女の内へ。
そして、この少女に霊的な素養は皆無と目されるので、
この致命傷が癒えるまで、最期の一本は、少女に憑く。
少女の傷が癒えたなら、あとは消えるまで、時間が過ぎるのを待つだけだ。
本来であればいくつも手順を踏む必要があるものの、
そのような猶予も、実現できる可能性もないので、
事前の準備も、合意も何もなく、強制的に執り行う。
人と狐の間で何かをする場合、狐笛の『音』が多くの場合要件に挙がるが、
『音』でなければならない必要は、あまりない。
要は、笛を介して、自分の情報が相手に渡りさえすれば良い。
自分の魂を、相手に移すように。
狐は、自分が持っていた狐笛をくわえる。
通例、術者が死ぬなどして、狐が笛を持ち帰るというような場合でもなければ、
狐が笛を持つことはないが、この笛は、この森に帰ってくる前に、
最後に自分を使役していた術者に渡されたものだ。
いわく、帰ってから、どうするかは決めればいいと。
ありがたく、そのようにさせてもらう。
狐は、動かない少女の身体に触れる。
目を覚まして、気づいたときには、
驚くといった程度では済まないだろうが、
そこは目を瞑ってもらうことにする。
少女に狐が憑いて、一命を取り留めて、そして目を覚ました時。
そこは、彼女にとってまったく見覚えのない森の中。
まだ頭の中がぼやけているせいか思い出せないが、
何かしないといけないことがある気がする。
すこし後になって、
彼女は、そこが学校の敷地の中だったと知った。
***
***
イバラシティの5月の終わり。
音のない静かな夜更。
住んでいるマンションの屋上。
わたしはなにもなかった屋上に、仰向けになって転がった。
「だーめーだー。うまくいーかーなーいー」
チョークで見よう見まねの陣を描いてみたり。
なにかそれっぽいものを燻してみたり。
指を切って血を落とそうとしてみたり(これは止められた。)
狐笛を吹こうとしてみたり。
自前の霊力がそろそろ枯渇して消えていきそうな霊狐を
なんとか繋ぎ止めようと四苦八苦しているところ、
最初から薄々感じていたし、色々試して改めて突きつけられるが、
どうやら根本的に、わたしにはそういった霊力やら何やらを操るといった才能が足りないらしい。
昔聞いたような記憶によれば、自分の祖父母以前は割とその方面に長けていたそうだが、
隔世遺伝とかそういったうまい話はないようだ。
その世代あたりで才能が尽きたのかも知れない。
自分の親についても、そういった話はあまり聞いた覚えがない。
(聞かされていないだけかも知れないけど。)
3月や4月の半ばあたりまでは呼ばなくてもたまには出てきた狐は、
5月になってからは、用があって初めて出てくるぐらいになった。
それだけ消耗しているのか、温存しているのか。
自分がうまいこと、それこそ何かを召喚するみたいな力でもあれば、
自分の中に埋もれてるはずの狐の尾の霊力をぱっと明け渡すなどなんとでもできたろうに。
しかしないものをいくらねだっても仕方がないので、最後の作戦を試すことにする。
「こーかーげー。出てー」
ずるりと自分の中から狐が這い出す。
最初は驚きもしたが、とうの昔に慣れてしまった。
月の光が狐の身体をすり抜けるように通っていく。
それぐらい薄く、存在は弱々しい。
さっきまではそんな霊体に対して
なんとか契約などしようと試していたが、
そういう霊的な素養はないので。
もっと物理的に。原始的に。
「10秒だけでいいから、言ったら実体化して」
それが相手が消える時間を早めるというのは十分承知している。
もとより、おもっている手段が全部付きたらどうしようもないから、気にしてはいられない。
わたしの言葉に、狐は一瞬嫌そうな表情をした。ような気がした。
「逃げないでよ。
これは、きっと『お前がわたしにやった』ことのはずだから」
わたしはそれをやり返すだけ」
起き上がると、自分の首から提げた笛を手に持って、
体長だけみれば自分とそんなに変わらない狐に近づいていく。
「移してもらったんだから、それをちょっとでも、返すだけ」
狐笛を口に咥える。
そこでちょうど。
星がまたたく。
何が起きたのかは、分からない。
ただ、強く強く輝く光が、夜空を覆っていく。
流れ星というには強すぎる光。
でも、わたしにとっては、少しでも希望になる光。
「神使様に大切なお守りももらって、流れ星まで降ってきて、失敗するわけないよね!」
合図をする。
眼の前の狐の身体がほんの僅かな間、質量を持つ。
淡い月の光のような毛。
わたしは膝をついて、目線を合わせて、さらに近づいていく。
狐笛を介して、眼の前の狐とつながるように。
触れる。



ENo.167 うさ子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.664 闇のおえかき とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.959 安倍葛子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1132 玲瓏 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ニアク 「……あれは何だっけ? ぞう?」 |
 |
ヘイゼル 「ふっかけられる戦いも増えてきたな。厄介な……」 |
 |
ヘイゼル 「私たちの立ち位置からして、致し方ない面もあるがな」 |
 |
モドラ 「あんなよくしゃべるナレハテはじめてみたなあ~(棒)」 |
 |
モドラ 「ニアクも俺も、イバラシティじゃもうちょい大人しく…穏やかに?してるよ。 イバラシティのみつきさん、どんなんなん…?」 |
 |
モドラ 「この辺はあんま詳しくないけど、ウシ区とリュウジン区はわりと分かるよ。 あっちがカミセイで、あっちがウシ区でしょお」 |





軍手より速いやつら
|
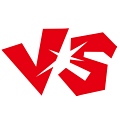 |
血盟の行進
|



ニアク(79) は たけのこ を入手!
ヘイゼル(1355) は 柳 を入手!
モドラ(1457) は 柳 を入手!
みつき(1495) は たけのこ を入手!
ニアク(79) は 美味しい草 を入手!
ヘイゼル(1355) は 爪 を入手!
ニアク(79) は 剛毛 を入手!
みつき(1495) は 牙 を入手!





チナミ区 J-19(沼地)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 J-20(沼地)に移動!(体調6⇒5)
カミセイ区 J-1(沼地)に移動!(体調5⇒4)
カミセイ区 J-2(沼地)に移動!(体調4⇒3)
カミセイ区 J-3(道路)に移動!(体調3⇒2)





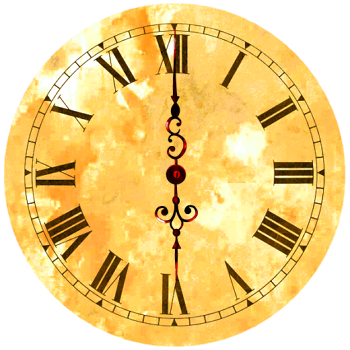
―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「……時計台に呼ばれてしまいましたが、はてさて。」 |
 |
エディアン 「なーんか、嫌な予感がします。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
 |
エディアン 「ほら……ほらぁ……。」 |
 |
榊 「どういうことでしょうねぇ。」 |
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝してます。」 |
 |
エディアン 「……ワールドスワップの能力者さんですよね。 機会を与えてくれて、感謝していますよ?」 |
 |
榊 「お姿は拝めないんですかねぇ。私は興味津々桃色片想いなのですが。」 |
声は淡々と、話を続ける。
 |
声 「どうやらこのワールドスワップ、時計の進みが狂っているようです。 特殊な因子を含めてしまった為と能力が訴えます。その因子が――」 |
 |
声 「――榊さん、貴方のようですね。何か、心当たりは?」 |
 |
榊 「大いにございます!特殊な世界の住人ゆえ、私は今や特異な存在なのでしょう。 妻に『貴方は変人』とよく言われていましたが、そういうことでしたか!納得ですッ」 |
 |
榊 「では、役目を果たすのは難しいということでよろしいですか?」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
榊 「……? ……どうしました?」 |
 |
声 「……仕切り直し、世界線を変更する、と能力が言ってきます。 貴方が案内役にならない世界線。イバラシティも、アンジニティも、新たなものになる……と。」 |
 |
エディアン 「……そ、そんなことまでできてしまう能力? ワールドスワップという名の範疇を超えてません?」 |
 |
榊 「世界線を別のものと交換する……と考えるなら、ギリギリ……ですかね。 というか、スワップから外れた現象は既に起こっていますが。」 |
 |
声 「これは能力ではなく、……呪い。呪いという言葉が合う。 今まで勝手に発動した数度、自分への利はない。制御下にない、把握できない、呪い。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「ハザマへの次の転送時間に、ハザマに転送される代わりに、世界線が変更される。 そして、案内役も、転送対象も、変わる。」 |
 |
声 「変わるものは、多いだろう。しかし変わらぬものも、あるだろう。」 |
 |
エディアン 「別の世界線、ですものね。 ……どうせなら私がアンジニティにいない世界線がいいんですけど。」 |
 |
榊 「……なるほど、奇妙な枝の正体は世界線操作者でしたかッ! 少なくとも私が案内役となれない世界線になるのですね、残念です。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「連絡は終わり。さようなら。」 |
声はそこで終わる。
 |
榊 「さて…… とても短い間ではありましたが、 エディアンさん、皆様、お付き合いありがとうございました!」 |
 |
エディアン 「お別れですか。悪人顔っぽくて敵視しやすい相手だったんですけどねー。」 |
 |
榊 「こんな素敵な笑顔を悪人顔呼ばわりとは、失礼な娘さんです。 なるほどアンジニティにいらっしゃるわけですねぇ。」 |
 |
エディアン 「……うるっさいですね。事情は人それぞれあるんですよ、色々!」 |
 |
榊 「……それでは、」 |
 |
エディアン 「……それでは、」 |
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
 |
榊 「お疲れ様でした。」 |
 |
エディアン 「お疲れ様でしたー!」 |

ENo.1495
鹿瀬 満月



【Tips】
ログ保管プレイス
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2565
5/10
メインキャラクターの情報に加筆しました。
サブキャラクターを追加しました。
------------------------------------------
【メインキャラクター】
○基本情報
・名前:鹿瀬 満月(かなせ みつき)
・種族:人間
・性別:女性
・身長:145cmぐらい
・年齢:15歳(?)
○プロフィール
いつも、首から小笛を提げている少女。
勝気で前のめり向こう見ずで、口よりも先に手が出る性格。
稲荷信仰が厚い里に生まれ育ち、野山を遊び場に育つ。
早駆けをはじめ身体を動かすことは好きだが、
頭で勝負を仕掛けられるとだいたい手玉に取られる。
野生の勘か第六感か稲荷様のお告げかは不明だが、
直感にとても優れている。
身体能力は高く、一般人なら大人でも軽くいなせる程度には力もある。
本人は動物が好きだが、どうやら動物が、
自分に近寄りがたい雰囲気を感じることがあるらしいと
最近気づきはじめて、少し傷心している。
イバラシティには最近引っ越してきた。
周りには秘密だが、イバラシティになにかの予兆あり、ということらしく、
イバラシティを守るために送られてきたせいぎのしのび!なのだ!
……という記憶を持ってイバラシティにいる。
彼女の使命は【イバラシティを守ること】だ。たぶん。
そして、満月の保護者のようなかたちで、
霊狐「こかげ」が憑いているようだが、満月は当初、全く知らなかった。
知らずにいろいろと恥ずかしいことをやらかしていた。
※補足
某TRPGが初出のキャラ。
イバラシティでは異能が目につくため目立たないが、忍のお里で育ったれっきとした忍。武闘派脳筋流派。
○異能
【しんそく】(神速)
本人のそのときの集中の深さに応じ、常人の目では追えないレベルで、早く動くことができる。
もっとも、武芸などを習熟していたり、高度な動体視力を
持つものからすると、反応が不可能な速度ではない。
満月本人の認識が追いつかなければ結局行動できないため、
戦闘時など複雑な状況下で、常に発動したまま動くことはできない。
身体への反動など、本人が自覚できるようなペナルティは
生じてはおらず、比較的使い勝手のよい能力。
とはいえ、あまり人前で使うことはない。
奥義情報はおいそれと渡せない。
【みずかがみ】(水鏡)
満月にこの異能の自覚はない。
しかし、異能を感じることができるものから見ると、
常に彼女を護っているかのような異能が作動していることを認識可能である。
満月が最近気づくことがあるとすれば、
ぜんぜん風邪などをひかないことと、
うっかり火に触ってしまったのに大した火傷もしなかったこと、
そして、ちょっと大きい怪我をしても、わりとはやく治ってしまうことぐらいだ。
(とはいえ、回復術のように骨折が一瞬で治るような治癒力ではなく、
自然治癒力が高い、といったほうが適切)
【サブキャラクター】
○基本情報
・名前:こかげ
・種族:霊狐
・性別:♂(男性)
・身長:狐のときは体高1m程度。大きい目
人間に化けるときは175cm程度
・年齢:見た目は狐でいえば10歳。人間で言えば50歳前後。
(実際に生きた年月で言えば、もっと長い。)
○プロフィール
アンジニティの民となったばかり。
動物が妖となった妖狐というよりは、精霊に近い霊狐。
本来は、人には見えない、世界の狭間のようなところに住む種族。
種族として妖術のような異能の適正を持つため、
術者や陰陽師といった類に使役されて暗躍することが多い。
より強い霊狐を探して捕らえ、使役する輩もまま居る。
実際彼も、何人もの人間に仕え、そのような役目を
数えればきりがないくらいこなしてきた。
最後に仕えた人間と死別したあと、満月の故郷の山奥に移り
住んだところ、満月が(ご法度とされている)山に入り込んで
彼を見つけてしまったのが始まりとなる。
ちなみに、こかげという名前は満月がつけて呼んでいるだけで、
特に名前が決まっているわけではない。
これまでも色々な呼ばれ方をしてきている。
アンジニティに追放されるに値する罪状はいくらでも有しているが、
最後に人を殺し、その後に元いた狭間に戻り、しばらく経ったところで、
こかげはアンジニティへの追放を受けた。
それから大した間もなく、ワールドスワップが始まり、イバラシティへ。
満月という既知の少女に憑く霊狐として。
満月とこかげの関係性を簡単に言えば、
満月がこかげに『憑かれている』状態。
満月がこかげを使役する、もしくはこかげが満月を支配している
というような一方的な関係性ではなく、
どちらかが死ねばどちらも死ぬという相互依存。
いま肉体のないこかげのほうが、立場的には弱い。
適切に措置すれば、満月を生かしたまま憑依状態を解消することは可能だが、
イバラシティでの視点ではアンジニティの侵略が想定されている以上、余分な危険を増やせず、
ハザマで解消してもイバラシティの満月には影響がないのであまり意味はない。
イバラシティでは、満月について動くものの
基本的に隠形しているため、普通の人には見えない。
なお満月も、こかげがついてきていることに全く気づいていなかった。1週間くらい。
ちなみに、満月が最近動物と仲良くなれないのはこかげが原因である。
(隠形していてもある程度の力は保持しているので、特に小さい動物にはかなりの威圧になっているらしい。)
見たかったり話したりしたい場合は、
それっぽいRPをして見えることにしてもいいし、
ダイスで判定してみてもいい。
○異能
【???】
異能を有しているが、イバラシティにいる彼は使用することができない。
ハザマでは何かしら強化されるため、使用できるようだ。
------------------------------------------
【おれい】
プロフ、アイコンは以下のメーカーさんで作らせてもらいました。
プロフ→https://picrew.me/image_maker/327
(とびはねメーカー)
アイコン→https://picrew.me/image_maker/21492
(じょじメーカー)
https://picrew.me/image_maker/11811
(お兄さんも作れるおじさんメーカー)
https://picrew.me/image_maker/36849
(ガン見してぅるメーカー)
-------------------------------------------
【その他】
・深夜1時ぐらいまではお付き合いできます。(途中で落ちるときは書きます。)
・情報の既知、未知は基本ゆるいです。個々の情報だったりプレイスで話した内容など、適宜どうぞ。
・背後(@weisstier)は雑食なので、利用規約内であればだいたいのロール、絡みOKです。なにかあればご連絡ください。(外部でなにかするのも差し支えないです。)
ログ保管プレイス
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2565
5/10
メインキャラクターの情報に加筆しました。
サブキャラクターを追加しました。
------------------------------------------
【メインキャラクター】
○基本情報
・名前:鹿瀬 満月(かなせ みつき)
・種族:人間
・性別:女性
・身長:145cmぐらい
・年齢:15歳(?)
○プロフィール
いつも、首から小笛を提げている少女。
勝気で前のめり向こう見ずで、口よりも先に手が出る性格。
稲荷信仰が厚い里に生まれ育ち、野山を遊び場に育つ。
早駆けをはじめ身体を動かすことは好きだが、
頭で勝負を仕掛けられるとだいたい手玉に取られる。
野生の勘か第六感か稲荷様のお告げかは不明だが、
直感にとても優れている。
身体能力は高く、一般人なら大人でも軽くいなせる程度には力もある。
本人は動物が好きだが、どうやら動物が、
自分に近寄りがたい雰囲気を感じることがあるらしいと
最近気づきはじめて、少し傷心している。
イバラシティには最近引っ越してきた。
周りには秘密だが、イバラシティになにかの予兆あり、ということらしく、
イバラシティを守るために送られてきたせいぎのしのび!なのだ!
……という記憶を持ってイバラシティにいる。
彼女の使命は【イバラシティを守ること】だ。たぶん。
そして、満月の保護者のようなかたちで、
霊狐「こかげ」が憑いているようだが、満月は当初、全く知らなかった。
知らずにいろいろと恥ずかしいことをやらかしていた。
※補足
某TRPGが初出のキャラ。
イバラシティでは異能が目につくため目立たないが、忍のお里で育ったれっきとした忍。武闘派脳筋流派。
○異能
【しんそく】(神速)
本人のそのときの集中の深さに応じ、常人の目では追えないレベルで、早く動くことができる。
もっとも、武芸などを習熟していたり、高度な動体視力を
持つものからすると、反応が不可能な速度ではない。
満月本人の認識が追いつかなければ結局行動できないため、
戦闘時など複雑な状況下で、常に発動したまま動くことはできない。
身体への反動など、本人が自覚できるようなペナルティは
生じてはおらず、比較的使い勝手のよい能力。
とはいえ、あまり人前で使うことはない。
奥義情報はおいそれと渡せない。
【みずかがみ】(水鏡)
満月にこの異能の自覚はない。
しかし、異能を感じることができるものから見ると、
常に彼女を護っているかのような異能が作動していることを認識可能である。
満月が最近気づくことがあるとすれば、
ぜんぜん風邪などをひかないことと、
うっかり火に触ってしまったのに大した火傷もしなかったこと、
そして、ちょっと大きい怪我をしても、わりとはやく治ってしまうことぐらいだ。
(とはいえ、回復術のように骨折が一瞬で治るような治癒力ではなく、
自然治癒力が高い、といったほうが適切)
【サブキャラクター】
○基本情報
・名前:こかげ
・種族:霊狐
・性別:♂(男性)
・身長:狐のときは体高1m程度。大きい目
人間に化けるときは175cm程度
・年齢:見た目は狐でいえば10歳。人間で言えば50歳前後。
(実際に生きた年月で言えば、もっと長い。)
○プロフィール
アンジニティの民となったばかり。
動物が妖となった妖狐というよりは、精霊に近い霊狐。
本来は、人には見えない、世界の狭間のようなところに住む種族。
種族として妖術のような異能の適正を持つため、
術者や陰陽師といった類に使役されて暗躍することが多い。
より強い霊狐を探して捕らえ、使役する輩もまま居る。
実際彼も、何人もの人間に仕え、そのような役目を
数えればきりがないくらいこなしてきた。
最後に仕えた人間と死別したあと、満月の故郷の山奥に移り
住んだところ、満月が(ご法度とされている)山に入り込んで
彼を見つけてしまったのが始まりとなる。
ちなみに、こかげという名前は満月がつけて呼んでいるだけで、
特に名前が決まっているわけではない。
これまでも色々な呼ばれ方をしてきている。
アンジニティに追放されるに値する罪状はいくらでも有しているが、
最後に人を殺し、その後に元いた狭間に戻り、しばらく経ったところで、
こかげはアンジニティへの追放を受けた。
それから大した間もなく、ワールドスワップが始まり、イバラシティへ。
満月という既知の少女に憑く霊狐として。
満月とこかげの関係性を簡単に言えば、
満月がこかげに『憑かれている』状態。
満月がこかげを使役する、もしくはこかげが満月を支配している
というような一方的な関係性ではなく、
どちらかが死ねばどちらも死ぬという相互依存。
いま肉体のないこかげのほうが、立場的には弱い。
適切に措置すれば、満月を生かしたまま憑依状態を解消することは可能だが、
イバラシティでの視点ではアンジニティの侵略が想定されている以上、余分な危険を増やせず、
ハザマで解消してもイバラシティの満月には影響がないのであまり意味はない。
イバラシティでは、満月について動くものの
基本的に隠形しているため、普通の人には見えない。
なお満月も、こかげがついてきていることに全く気づいていなかった。1週間くらい。
ちなみに、満月が最近動物と仲良くなれないのはこかげが原因である。
(隠形していてもある程度の力は保持しているので、特に小さい動物にはかなりの威圧になっているらしい。)
見たかったり話したりしたい場合は、
それっぽいRPをして見えることにしてもいいし、
ダイスで判定してみてもいい。
○異能
【???】
異能を有しているが、イバラシティにいる彼は使用することができない。
ハザマでは何かしら強化されるため、使用できるようだ。
------------------------------------------
【おれい】
プロフ、アイコンは以下のメーカーさんで作らせてもらいました。
プロフ→https://picrew.me/image_maker/327
(とびはねメーカー)
アイコン→https://picrew.me/image_maker/21492
(じょじメーカー)
https://picrew.me/image_maker/11811
(お兄さんも作れるおじさんメーカー)
https://picrew.me/image_maker/36849
(ガン見してぅるメーカー)
-------------------------------------------
【その他】
・深夜1時ぐらいまではお付き合いできます。(途中で落ちるときは書きます。)
・情報の既知、未知は基本ゆるいです。個々の情報だったりプレイスで話した内容など、適宜どうぞ。
・背後(@weisstier)は雑食なので、利用規約内であればだいたいのロール、絡みOKです。なにかあればご連絡ください。(外部でなにかするのも差し支えないです。)
2 / 30
366 PS
カミセイ区
J-3
J-3




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ヘアゴム | 装飾 | 33 | 防御10 | - | - | |
| 5 | グリーブ | 防具 | 30 | 敏捷10 | - | - | |
| 6 | スティレット | 武器 | 34 | 衰弱10 | 加速10 | - | 【射程1】 |
| 7 | どうでもよさげな物体 | 素材 | 10 | [武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2) | |||
| 8 | みかわしのふく | 防具 | 39 | 舞撃10 | 追撃10 | - | |
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 11 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 13 | たけのこ | 食材 | 20 | [効果1]反撃10(LV15)[効果2]風柳10(LV25)[効果3]復活20(LV35) | |||
| 14 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]器用10(LV15)[装飾]反撃10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 12 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 3 | 生命/復元/水 |
| 時空 | 10 | 空間/時間/風 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 合成 | 35 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 7 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| エアシュート | 5 | 0 | 80 | 敵:風撃&連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 80 | 自:DF増(2T) | |
| ウィンドスピア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:風痛撃 | |
| イレイザー | 7 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
| エアスラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:4連風撃 | |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 | |
| スカイディバイド | 5 | 0 | 200 | 敵貫:風撃&風耐性減 | |
| チャージ | 5 | 0 | 60 | 敵:4連鎖撃 | |
| アクセルフォーム | 5 | 0 | 140 | 自:AG・加速LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 6 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
正義の青い鳥『サイン』 (ピンポイント) |
0 | 20 | 敵:痛撃 | |
|
実体創造>頭上注意金盥 (クリエイト:タライ) |
0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
|
輝きの太陽けだま (シャイン) |
0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
|
甘露のカトルカール (ヒールポーション) |
0 | 60 | 味傷:HP増 | |
|
ろるけきちゃん (サンクタム) |
0 | 60 | 味全:守護+祝福状態なら更に守護 | |
|
石像召喚Lv1 (サモン:ゴーレム) |
0 | 400 | 自:ゴーレム召喚 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 2 ]ティンダー | [ 3 ]リストリクト |
| [ 3 ]ストライキング | [ 3 ]クイックアナライズ | [ 3 ]リミテッドアナライズ |

PL / せつな