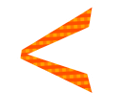<< 4:00>> 6:00




『響奏の世界』イバラシティ 。
特殊な能力を持った人々が住まう街。
私たち
『アンジニティの住民』は驚くほどすんなりと
この世界に馴染むことができた。
与えられた姿に、与えられた名前、記憶。
それらは平穏なこの世界に準拠したもので、
『否定の世界』から逃げ出したい私からすれば
この『侵略』の時間がいつまでも続けばいい、と。
それ以外の感想は特になかった。
欲を言うならば、何とかして『侵略』のルールから
逃れてこの街に残り、他の侵略者はアンジニティに
送り返されてほしいと思うことはあったけれど。
それはこの街が平和だと思っていたからだ。
それはこの街の住民が優しいと信じていたからだ。
今は──そうは思わない。
イバラシティ アンジニティ
『響奏の世界』の住民も。『否定の世界』の住民も。
等しく地獄に堕ちてしまえばいい。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「いい加減にさあ、警察に駆け込みなさいよ」
傷の手当てをしながら▇▇▇は膨れっ面でそう言う。
僕が止めていなければ、彼女は僕がされていることを
洗いざらい警察に話しているのだろう。
それをしないのは、僕がそう願ったから。
『お星様』へのお願いではなく、▇▇▇へのお願い。
だって『先生』は僕のたった1人の家族だから。
彼女は僕の意思を尊重してくれるけれど、それでも
こうして度々お節介を焼いてくれる。
「とばりがやだっていうから黙っててあげるけど、
それってほとんど私も共犯みたいなものだからね?」
私の鼻先を指で弾き、▇▇▇は不満げに呟いた。
「本当に危なくなったらちゃんと言うこと。
死んじゃったりしたら、どうにもならないんだから」
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
皆が私を疎んだ。皆が私を憎んだ。
私が抱えていた『ただ当たり前の願い』は
私以外の皆にとっては邪魔でしかなかった。
旧い幸福は棄てられて、新しい幸福を歓迎する。
それが『世界』の在り方なのだと。
だから私は置いていかれてしまった。
それを理解できるほど、私は世界をよく知らなかった。
何となく分かるのは、進む世界に逆らった私は
本来淘汰されるべき存在であったということ。
しかし実際にはそうならず、ただ『否定の世界』に
追放されるだけで終わってしまった。
確証はないけれど、▇▇が手を回してくれたのだろう、と。
私は今もそう信じている。
ただ、それが私を憐れんだ結果なのか、それとも
他の皆と同じように私を憎んだ結果なのか──
それだけが、分からない。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
音を奏でた。歌を唄った。
毎日毎日、少しずつ前に進んではいたと思う。
それでも僕の演奏は、僕の歌は『先生』が求める
ものには遠く及ばなかった。
焦っていた。僕も、『先生』も。
練習の時間は日に日に長くなっていった。
上達はしても、怒られる頻度は増えていった。
見限られるのが怖かった。見捨てられるのが怖かった。
その日、練習時間が終わっても僕はピアノに向かっていた。
真っ暗な部屋の中で習ったばかりの曲を伴奏に
口慣れない歌を口ずさんだ。
そうして──気付いた。気付いてしまった。
僕の歌は『暗闇の中』でしか輝かない。
それが僕の──『異能』だった。














ナズミ(68) は 雑木 を入手!
せら(83) は ド根性雑草 を入手!
すてら(130) は ネジ を入手!
ラ―トゲルダ(842) は ネジ を入手!
せら(83) は 美味しい果実 を入手!
ナズミ(68) は 不思議な牙 を入手!
ナズミ(68) は ボロ布 を入手!
せら(83) は 毛 を入手!



幻術LV を 2 UP!(LV10⇒12、-2CP)
響鳴LV を 1 UP!(LV19⇒20、-1CP)
付加LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
ナヴァル(1173) とカードを交換しました!
no.5「徒花」 (ドレイン)


イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)
クレイジーチューン を研究しました!(深度2⇒3)
ブラックアサルト を研究しました!(深度0⇒1)



せら(83) に移動を委ねました。
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調8⇒7)
採集はできませんでした。
- せら(83) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- すてら(130) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- ラ―トゲルダ(842) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。


















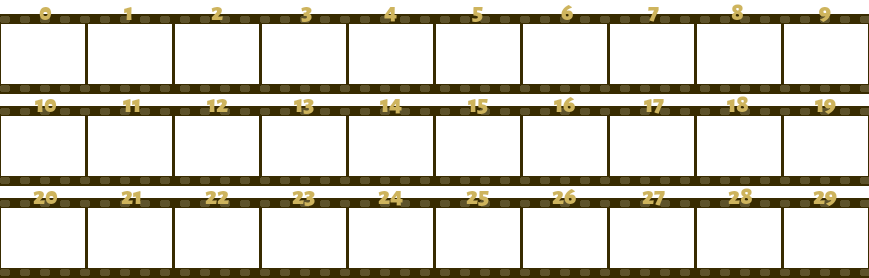





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



『響奏の世界』イバラシティ 。
特殊な能力を持った人々が住まう街。
私たち
『アンジニティの住民』は驚くほどすんなりと
この世界に馴染むことができた。
与えられた姿に、与えられた名前、記憶。
それらは平穏なこの世界に準拠したもので、
『否定の世界』から逃げ出したい私からすれば
この『侵略』の時間がいつまでも続けばいい、と。
それ以外の感想は特になかった。
欲を言うならば、何とかして『侵略』のルールから
逃れてこの街に残り、他の侵略者はアンジニティに
送り返されてほしいと思うことはあったけれど。
それはこの街が平和だと思っていたからだ。
それはこの街の住民が優しいと信じていたからだ。
今は──そうは思わない。
イバラシティ アンジニティ
『響奏の世界』の住民も。『否定の世界』の住民も。
等しく地獄に堕ちてしまえばいい。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「いい加減にさあ、警察に駆け込みなさいよ」
傷の手当てをしながら▇▇▇は膨れっ面でそう言う。
僕が止めていなければ、彼女は僕がされていることを
洗いざらい警察に話しているのだろう。
それをしないのは、僕がそう願ったから。
『お星様』へのお願いではなく、▇▇▇へのお願い。
だって『先生』は僕のたった1人の家族だから。
彼女は僕の意思を尊重してくれるけれど、それでも
こうして度々お節介を焼いてくれる。
「とばりがやだっていうから黙っててあげるけど、
それってほとんど私も共犯みたいなものだからね?」
私の鼻先を指で弾き、▇▇▇は不満げに呟いた。
「本当に危なくなったらちゃんと言うこと。
死んじゃったりしたら、どうにもならないんだから」
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
皆が私を疎んだ。皆が私を憎んだ。
私が抱えていた『ただ当たり前の願い』は
私以外の皆にとっては邪魔でしかなかった。
旧い幸福は棄てられて、新しい幸福を歓迎する。
それが『世界』の在り方なのだと。
だから私は置いていかれてしまった。
それを理解できるほど、私は世界をよく知らなかった。
何となく分かるのは、進む世界に逆らった私は
本来淘汰されるべき存在であったということ。
しかし実際にはそうならず、ただ『否定の世界』に
追放されるだけで終わってしまった。
確証はないけれど、▇▇が手を回してくれたのだろう、と。
私は今もそう信じている。
ただ、それが私を憐れんだ結果なのか、それとも
他の皆と同じように私を憎んだ結果なのか──
それだけが、分からない。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
音を奏でた。歌を唄った。
毎日毎日、少しずつ前に進んではいたと思う。
それでも僕の演奏は、僕の歌は『先生』が求める
ものには遠く及ばなかった。
焦っていた。僕も、『先生』も。
練習の時間は日に日に長くなっていった。
上達はしても、怒られる頻度は増えていった。
見限られるのが怖かった。見捨てられるのが怖かった。
その日、練習時間が終わっても僕はピアノに向かっていた。
真っ暗な部屋の中で習ったばかりの曲を伴奏に
口慣れない歌を口ずさんだ。
そうして──気付いた。気付いてしまった。
僕の歌は『暗闇の中』でしか輝かない。
それが僕の──『異能』だった。





| せら 「何時間か経ったけど、まだ誰も殺せてないなんて~!」 |
| せら 「今回こそ頑張ろうねー!」 |





ハザマわくわくピクニック(NEXT)
|
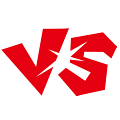 |
騎士会のひとたち
|



ナズミ(68) は 雑木 を入手!
せら(83) は ド根性雑草 を入手!
すてら(130) は ネジ を入手!
ラ―トゲルダ(842) は ネジ を入手!
せら(83) は 美味しい果実 を入手!
ナズミ(68) は 不思議な牙 を入手!
ナズミ(68) は ボロ布 を入手!
せら(83) は 毛 を入手!



幻術LV を 2 UP!(LV10⇒12、-2CP)
響鳴LV を 1 UP!(LV19⇒20、-1CP)
付加LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
ナヴァル(1173) とカードを交換しました!
no.5「徒花」 (ドレイン)


イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)
クレイジーチューン を研究しました!(深度2⇒3)
ブラックアサルト を研究しました!(深度0⇒1)



せら(83) に移動を委ねました。
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調8⇒7)
採集はできませんでした。
- せら(83) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- すてら(130) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- ラ―トゲルダ(842) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |



ハザマわくわくピクニック(NEXT)
|
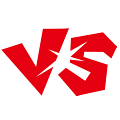 |
ハザマに生きるもの
|




ハザマわくわくピクニック(NEXT)
|
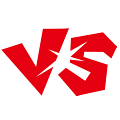 |
大騒乱オヒッコシブラザーズ
|


ENo.130
星空 帳



「──次のニュ …ース…す。本…未明、
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
・青色ステージ
5作目。淡々としたリズムのバラード。
思い悩む気持ちを抱えたまま歩む女の子の歌。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
・青色ステージ
5作目。淡々としたリズムのバラード。
思い悩む気持ちを抱えたまま歩む女の子の歌。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
7 / 30
209 PS
チナミ区
K-12
K-12






| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]活力10(LV10)[防具]体力10(LV10)[装飾]舞撃10(LV20) | |||
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 9 | とばりさんねばねば | 武器 | 34 | 攻撃10 | 束縛10 | - | 【射程3】 |
| 10 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 11 | 幸せになる石 | 装飾 | 39 | 幸運10 | - | - | |
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 12 | 夢幻/精神/光 |
| 響鳴 | 20 | 歌唱/音楽/振動 |
| 付加 | 32 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| シャイン | 7 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| ブリランテ | 5 | 0 | 140 | 自:光特性・魅了LV増 | |
| バトルソング | 7 | 0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |
| クレイジーチューン | 8 | 0 | 140 | 味全:強制混乱+次与ダメ増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 7 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 7 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 光特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:光属性スキルのHP増効果に光特性が影響 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
エーレンベルク (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
イバラキッス! (エアスラスト) |
0 | 60 | 敵:4連風撃 | |
|
薬草 (ヒールハーブ) |
0 | 80 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| 決3 |
下弦ノ月 (ウィルスゾーン) |
0 | 140 | 敵全:衰弱 |
|
no.5「徒花」 (ドレイン) |
0 | 60 | 敵:闇撃&自:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 3 ]ヒールポーション | [ 1 ]ブラックアサルト |
| [ 1 ]ウィルスゾーン | [ 3 ]イレイザー | [ 3 ]クレイジーチューン |

PL / すずらん