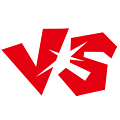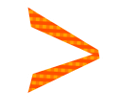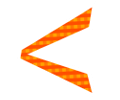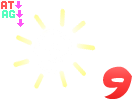<< 3:00>> 5:00




【LOG//http://dolch.bitter.jp/sub/agata/log/agata.html】

春子がいじめられはじめた理由は、はっきりとは覚えていない。
あの家がひどくまずしかったことは、理由のひとつであったように思う。
思春期の女子の中では、身なりがあか抜けないということは、
それだけで申し訳なさそうなふるまいを求められることだ。
リップが買えなかったり。ワックスが買えなかったり。制汗スプレーが買えなかったり。
少しのことだけれど、違和感を持たれる。
そんなことどうだっていい、と言える人間が、あの頃の私たちの中にどれだけいたか。
私は、 私のリップを貸してあげながら
私たちは、おんなじやすっぽい合成メロンのにおいを唇から放ちながら
かわりばんこで未来を憂いた。
14歳の春。私たちは二人で家出した。
所持金いっぱい叩いた電車の片道切符は、子供ながらに決心の証だった。
14歳。自分が、自分の異能に目覚めた年だ。
: : :
「えっ…もういいんですか?」
救急車を呼んだ後、所々のやり取りがあって、
私達――私とチナミ警察署の警察官2人は、
今はがらんとした渡世歩のマンションで状況確認をしていた。
若い女性の急死。
私はその場にいた上に、実際に後ろめたいことがある。
歩さんが亡くなってから、6時間ほどその事実を隠していたのだ。
だから、事情徴収を受けている間中、もっと疑われるとか、
事実が事実として明るみになって、何かしらの罪に問われるかと想像していた。
だとしても仕方ない。そうなったとしても狼狽えない理由が自分にはあると、そこまで覚悟していた。
「ご遺族と連絡とりまして、検死が済みましたから。事件性なしという判断です。」
おかしいじゃないですか。
のどまで出かかった言葉を飲み込む。
「病死ですよ。」
「アユミさん、どこかわるかったんですか?……」
「 」
眩暈。
「子宮にがんがありまして、」
: : :
-回想・葬式-
8畳の和室で執り行われたみすぼらしいお葬式で、
すすり泣く声に取り囲まれながら、私は唇を噛んで涙をこらえた。
私だけは絶対に泣くもんかと思っていた。
親族らしき人達が『この場合一体誰がお葬式の費用をだすのか』、
ということで暗い顔をしていたことを覚えている。
この世というのはなんとも汚らわしくて、どうしてこんな境遇に取り囲まれたまま、
春子がその人生を閉じなければいけなかったのかと思う。
せめてこの境遇から彼女を連れ出したかった。
世界はおそらく広いはずなのに、家出は、たったの1日で足がついて、私達は囲いに戻された。
私は気丈にふるまって、出棺の後にも火葬場についていった。
「リコちゃん」
「リコちゃん」
「リコちゃ~ん!
コレみて~。おそうしきのひとねえ、いうとったよお。
お花の色、燃え残るんがあるんじゃって!ねころんどるまわりねえ、お花いっぱいしとったじゃろ?
おねえちゃん、こんなんなったわあ!」

い
気色わるい
こどもだから?
こどもだから、なにかわからないから、
春子の、
春子の、
遺骨を、くすねたって、それで?それで、こどもだから?
こんな――
彼は7歳だった。ずっと、目に映ってはいた。
葬儀の席で、泣くまいと耐える私の他にも もう一人泣いてない人間がいた。
春子の弟。彼は笑っていた。
私にぶたれたその子供は、にわかに声をあげて泣きだした。
親戚や葬儀場の従業員たちは、彼が家族の死を悲しんで泣いているのだろうと心痛めた。
だけど違う。彼はただ、叩かれたから泣きだしたんだ。
阿片せつせつ。
一家が中毒死した事故でたった一人生き残った彼に対して、私はある時までは同情して、面倒を見ていた。
: : :
-渡世 歩の葬式-
「刑事さあん、なんで死んだ人に花供えるんじゃろねえ」
「…はあ」
「花、供えられたら供養になるんかねえ。」

「あ、アガタ先生、それ俺いっこ聞いたことあります。土葬の習慣がある場所では、
遺体に動物を寄せ付けない為に薬効や毒のある花を植えたとか」
「おお~。供養じゃなくて死体守りの花いうのもあるんじゃねえ」
「アガタ。
雨が降りそうだから中に入って。」
「鬼頭さんしっとる?なんで死んだ人には花なんか」
「調べとく。」
大きな渡世歩の写真を取り囲み、段々に飾られた菊花をアガタが撫でるようにしていた。
ふんふんと鼻歌を歌っていた。それが癪に障る。
なぜ歌う?
恋人が死んだのに。
: : :
私はアガタを気にかけていた。何かと面倒見てやっていて、
アガタが高校生になるころ、私達は付き合った。
それがヘンだと言われればそうだ。本当に。
たのしかったこと、よかったこともあるにはある。束の間、しあわせだったようにもおもう。
だけど私が別れた理由を話したい。
アガタはなんでもない日によく花束をくれた。
うれしかった。自分のこれまでの恋人に、花を贈ってくれる男がいなかったから、虚をつかれた。
花という何の役にも立たない、けれど価値のあるものを用意するという行為そのものが、
妙にオシャレに感じたのを覚えている。高校生のクセに、花を贈るというのがやはりなんだか、ずるい。
うれしい反面気がかりでもあった。
小遣いもさほどないだろうに、自分の娯楽費を削っても花を買うなんて無茶だと思った。
私はある時彼を着けた。
これ、いくらくらいなんだろうって、気になってしまったのだ。
どこで買っているのか見れば、贈り物の値段の相場が解る。非情にマナーが悪いけど。
そしてはっきり見た。彼はひしゃげたガードレールに供えられた献花のひとつを
『拾った』。
私は叫んで、急いで部屋に生けていた花束を捨てた。
手が震えていた。思い出した。気色わるい。
あの時立った鳥肌。
それまで、親友の弟としてかわいがっていたものを『気色わるい』と思った。
あの時立った鳥肌とおなじものが。気色わるい。気色わるい!
ほどなく私達は別れた。
: : :
私は悟った。
この男には人の心がないのだ。
: : :
私は裏切られ続けた。
アイフェイヨ~ンで春子を生き返らせてほしかった。
私を愛していると信じたかった。
5年も付き合った歩さんが亡くなった時、涙のひとつでも流してほしかった。
子供の頃だったから笑っていられたんだと、信じたかった。
これまで、歩さんの子宮にがんがあると知ってなお抱いていたのではないと信じたい。
期待するたび裏切りに終わる。この男には、人の心がない。
…そして始めに戻る。
私が私の異能に目覚めたのは14歳。
春子のことで塞ぎこんでいた私は逃避先をさがして、
ネットで一晩中痛みを吐露するだけのチャットなんかに勤しんでいた。
そうする中、パソコンのモニターに勝手に文字が打たれたのだ。
自動筆記で、『イワン』はみずから能力者である私に語りかけた。
そしてそれは私のやりきれなさを救うはずのものだった。

『イワン』は私に、私の異能の使い方を教えた。
インフルエンサー。
私は春子が死んだことを私ばかりが引きずっていることに耐えられなかった。
だからその死を広めたかった。
阿片一家の死がニュースになると、事故の原因になった旧式ガス給湯器の取換が全国で行われた。
そのガス給湯器の会社が 賠償か何かをしたと思う。
その事が、未来に起きるかもしれなかった事故を防いだのかもしれない。わからない。
そうか、それで起きるかもしれない事故が防げたのか。
春子の死は無駄じゃなかったんだ。
なんて、思えるわけがない。
やりきれなくて、次に春子が学校でいじめられていたと世間に広めた。
それは確かに噂になった。だけれど、それがなにかになったのか、今もわからない。
半年も経てば元通り、話題に上がらなくなった。
春子を置いて世界は回る。
『弟は特別なんだ』と春子は言っていた。
弟は、まるで、神々に愛されているかのようだと。
私はそうは思わない。
思いたくない。
[Backspace]
[Backspace]
パソコンに文字を打ち込む。そして消す。くりかえし打ち込む。
きっとイワンだけが聞いている。
『事件性がない』。それは14歳の時にも繰り返し言われた言葉だった。
一番体力のないはずの、いちばん年少の弟だけが生き延びて、
他の全員が死んだのに。はい、なんの不審もありませんでしたなんて。
私は。
私の手に回ってきたこの男に、自分の異能を行使したことを、
神のご意向だとか、運命だとか、そんなことに組み込まれるのはぜったいにいやだ。
そんなつもりはない。決して。
神々に愛されているから生き延びたなんて、絶対に納得がいかない。
他の家族が、春子が死んだことは、神に愛されていなかったからなんて、バカな言い草はさせない。
私が遠巻きにながめるこの現象は、
渡世歩の手を離れた。そして、速水徹也の手に渡った。



ENo.664 ハヤミ とのやりとり

ENo.931 伊舎那 とのやりとり




ItemNo.7 ささやき を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










自然LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
使役LV を 9 UP!(LV0⇒9、-9CP)
付加LV を 4 UP!(LV25⇒29、-4CP)
ItemNo.5 インスピレーション に ItemNo.9 駄木 を付加しようとしましたが、既に効果2が付加されていました。
天弖(825) とカードを交換しました!
光輝一閃 (ライトセイバー)

パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールハーブ を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールハーブ を研究しました!(深度1⇒2)
ラッシュ を習得!
ライフリンク を習得!
ワイルドナーヴ を習得!
チャーム を習得!



チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 R-3(沼地)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-4(沼地)に移動!(体調14⇒13)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――







瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



【LOG//http://dolch.bitter.jp/sub/agata/log/agata.html】

春子がいじめられはじめた理由は、はっきりとは覚えていない。
あの家がひどくまずしかったことは、理由のひとつであったように思う。
思春期の女子の中では、身なりがあか抜けないということは、
それだけで申し訳なさそうなふるまいを求められることだ。
リップが買えなかったり。ワックスが買えなかったり。制汗スプレーが買えなかったり。
少しのことだけれど、違和感を持たれる。
そんなことどうだっていい、と言える人間が、あの頃の私たちの中にどれだけいたか。
私は、 私のリップを貸してあげながら
私たちは、おんなじやすっぽい合成メロンのにおいを唇から放ちながら
かわりばんこで未来を憂いた。
14歳の春。私たちは二人で家出した。
所持金いっぱい叩いた電車の片道切符は、子供ながらに決心の証だった。
14歳。自分が、自分の異能に目覚めた年だ。
: : :
「えっ…もういいんですか?」
救急車を呼んだ後、所々のやり取りがあって、
私達――私とチナミ警察署の警察官2人は、
今はがらんとした渡世歩のマンションで状況確認をしていた。
若い女性の急死。
私はその場にいた上に、実際に後ろめたいことがある。
歩さんが亡くなってから、6時間ほどその事実を隠していたのだ。
だから、事情徴収を受けている間中、もっと疑われるとか、
事実が事実として明るみになって、何かしらの罪に問われるかと想像していた。
だとしても仕方ない。そうなったとしても狼狽えない理由が自分にはあると、そこまで覚悟していた。
「ご遺族と連絡とりまして、検死が済みましたから。事件性なしという判断です。」
おかしいじゃないですか。
のどまで出かかった言葉を飲み込む。
「病死ですよ。」
「アユミさん、どこかわるかったんですか?……」
「 」
眩暈。
「子宮にがんがありまして、」
: : :
 |
8畳の和室で執り行われたみすぼらしいお葬式で、
すすり泣く声に取り囲まれながら、私は唇を噛んで涙をこらえた。
私だけは絶対に泣くもんかと思っていた。
親族らしき人達が『この場合一体誰がお葬式の費用をだすのか』、
ということで暗い顔をしていたことを覚えている。
この世というのはなんとも汚らわしくて、どうしてこんな境遇に取り囲まれたまま、
春子がその人生を閉じなければいけなかったのかと思う。
せめてこの境遇から彼女を連れ出したかった。
世界はおそらく広いはずなのに、家出は、たったの1日で足がついて、私達は囲いに戻された。
私は気丈にふるまって、出棺の後にも火葬場についていった。
「リコちゃん」
「リコちゃん」
「リコちゃ~ん!
コレみて~。おそうしきのひとねえ、いうとったよお。
お花の色、燃え残るんがあるんじゃって!ねころんどるまわりねえ、お花いっぱいしとったじゃろ?
おねえちゃん、こんなんなったわあ!」

い
気色わるい
こどもだから?
こどもだから、なにかわからないから、
春子の、
春子の、
遺骨を、くすねたって、それで?それで、こどもだから?
こんな――
彼は7歳だった。ずっと、目に映ってはいた。
葬儀の席で、泣くまいと耐える私の他にも もう一人泣いてない人間がいた。
春子の弟。彼は笑っていた。
私にぶたれたその子供は、にわかに声をあげて泣きだした。
親戚や葬儀場の従業員たちは、彼が家族の死を悲しんで泣いているのだろうと心痛めた。
だけど違う。彼はただ、叩かれたから泣きだしたんだ。
阿片せつせつ。
一家が中毒死した事故でたった一人生き残った彼に対して、私はある時までは同情して、面倒を見ていた。
: : :
 |
「刑事さあん、なんで死んだ人に花供えるんじゃろねえ」
「…はあ」
「花、供えられたら供養になるんかねえ。」

弔花
死人に備える花、その風習。仏教は仏への精進の誓いとして、キリスト教は神に返す故人を飾る為等と考えられる。しかし、諸宗教が興る以前、原始人の時代から遺骸と共に花粉が見つかっている。
「あ、アガタ先生、それ俺いっこ聞いたことあります。土葬の習慣がある場所では、
遺体に動物を寄せ付けない為に薬効や毒のある花を植えたとか」
「おお~。供養じゃなくて死体守りの花いうのもあるんじゃねえ」
「アガタ。
雨が降りそうだから中に入って。」
「鬼頭さんしっとる?なんで死んだ人には花なんか」
「調べとく。」
大きな渡世歩の写真を取り囲み、段々に飾られた菊花をアガタが撫でるようにしていた。
ふんふんと鼻歌を歌っていた。それが癪に障る。
なぜ歌う?
恋人が死んだのに。
: : :
私はアガタを気にかけていた。何かと面倒見てやっていて、
アガタが高校生になるころ、私達は付き合った。
それがヘンだと言われればそうだ。本当に。
たのしかったこと、よかったこともあるにはある。束の間、しあわせだったようにもおもう。
だけど私が別れた理由を話したい。
アガタはなんでもない日によく花束をくれた。
うれしかった。自分のこれまでの恋人に、花を贈ってくれる男がいなかったから、虚をつかれた。
花という何の役にも立たない、けれど価値のあるものを用意するという行為そのものが、
妙にオシャレに感じたのを覚えている。高校生のクセに、花を贈るというのがやはりなんだか、ずるい。
うれしい反面気がかりでもあった。
小遣いもさほどないだろうに、自分の娯楽費を削っても花を買うなんて無茶だと思った。
私はある時彼を着けた。
これ、いくらくらいなんだろうって、気になってしまったのだ。
どこで買っているのか見れば、贈り物の値段の相場が解る。非情にマナーが悪いけど。
そしてはっきり見た。彼はひしゃげたガードレールに供えられた献花のひとつを
『拾った』。
私は叫んで、急いで部屋に生けていた花束を捨てた。
手が震えていた。思い出した。気色わるい。
あの時立った鳥肌。
それまで、親友の弟としてかわいがっていたものを『気色わるい』と思った。
あの時立った鳥肌とおなじものが。気色わるい。気色わるい!
ほどなく私達は別れた。
: : :
私は悟った。
この男には人の心がないのだ。
: : :
私は裏切られ続けた。
アイフェイヨ~ンで春子を生き返らせてほしかった。
私を愛していると信じたかった。
5年も付き合った歩さんが亡くなった時、涙のひとつでも流してほしかった。
子供の頃だったから笑っていられたんだと、信じたかった。
これまで、歩さんの子宮にがんがあると知ってなお抱いていたのではないと信じたい。
期待するたび裏切りに終わる。この男には、人の心がない。
…そして始めに戻る。
私が私の異能に目覚めたのは14歳。
春子のことで塞ぎこんでいた私は逃避先をさがして、
ネットで一晩中痛みを吐露するだけのチャットなんかに勤しんでいた。
そうする中、パソコンのモニターに勝手に文字が打たれたのだ。
自動筆記で、『イワン』はみずから能力者である私に語りかけた。
そしてそれは私のやりきれなさを救うはずのものだった。

鬼頭 莉子/キガシラリコ
異能名は『インフルエンサー・ワクチン』略してイワン。通信回線に顕現する、さまざまな情報の伝播力を操作する異能。制約付きで伝播力を高めるインフルエンサーと、同じく伝播力を弱めるワクチン。
『イワン』は私に、私の異能の使い方を教えた。
インフルエンサー。
私は春子が死んだことを私ばかりが引きずっていることに耐えられなかった。
だからその死を広めたかった。
阿片一家の死がニュースになると、事故の原因になった旧式ガス給湯器の取換が全国で行われた。
そのガス給湯器の会社が 賠償か何かをしたと思う。
その事が、未来に起きるかもしれなかった事故を防いだのかもしれない。わからない。
そうか、それで起きるかもしれない事故が防げたのか。
春子の死は無駄じゃなかったんだ。
なんて、思えるわけがない。
やりきれなくて、次に春子が学校でいじめられていたと世間に広めた。
それは確かに噂になった。だけれど、それがなにかになったのか、今もわからない。
半年も経てば元通り、話題に上がらなくなった。
 |
(そう。 私はこの異能を、アガタという画家の名声を広めることに使った。) |
 |
彼のよいニュースを広めた。 はじめはこんな風になるとは思わなかった。 阿片家のニュースも、春子のうわさも、話題として半年と持たなかった。 だから、何の気なしに少し――食べていけなさそうな、アーティストなんて仕事に力を貸したつもりだった。この人間が自活しないということは、誰かしらに迷惑をかけることだとも思ったからだ。 それがこんな、大成するなんて。 |
春子を置いて世界は回る。
『弟は特別なんだ』と春子は言っていた。
弟は、まるで、神々に愛されているかのようだと。
私はそうは思わない。
思いたくない。
 |
おかしいじゃないですか。_ |
 |
おかしいじゃないか。_ |
 |
おかしいじゃないか!_ |
パソコンに文字を打ち込む。そして消す。くりかえし打ち込む。
きっとイワンだけが聞いている。
『事件性がない』。それは14歳の時にも繰り返し言われた言葉だった。
一番体力のないはずの、いちばん年少の弟だけが生き延びて、
他の全員が死んだのに。はい、なんの不審もありませんでしたなんて。
私は。
私の手に回ってきたこの男に、自分の異能を行使したことを、
神のご意向だとか、運命だとか、そんなことに組み込まれるのはぜったいにいやだ。
そんなつもりはない。決して。
神々に愛されているから生き延びたなんて、絶対に納得がいかない。
他の家族が、春子が死んだことは、神に愛されていなかったからなんて、バカな言い草はさせない。
私が遠巻きにながめるこの現象は、
渡世歩の手を離れた。そして、速水徹也の手に渡った。



ENo.664 ハヤミ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 伊舎那 とのやりとり



 |
(ありもしないザリガニ釣りの思い出から間もなく、オオザリガニがハヤミの行く手を挟んでいる。) |
『ねえ、ハヤミさんはこれから何処へ行くの?』 『彷徨うの?』 『足掻くの?』 『藻掻くの?』 |
『ひとりで?』 |
…………幻影が囁く。返事をするものはいない。 ただ、そこにある人影は黙々と星を追うように歩く。 |
――――ひとりで。 |
ItemNo.7 ささやき を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









自然LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
使役LV を 9 UP!(LV0⇒9、-9CP)
付加LV を 4 UP!(LV25⇒29、-4CP)
ItemNo.5 インスピレーション に ItemNo.9 駄木 を付加しようとしましたが、既に効果2が付加されていました。
天弖(825) とカードを交換しました!
光輝一閃 (ライトセイバー)

パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールハーブ を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールハーブ を研究しました!(深度1⇒2)
ラッシュ を習得!
ライフリンク を習得!
ワイルドナーヴ を習得!
チャーム を習得!



チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 R-3(沼地)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-4(沼地)に移動!(体調14⇒13)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――






 |
マイケル 「あ、来ましたかー。チェックポイントはこちらですよー。」 |
瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「遠方までご苦労さまです、私はマイケルです。 お疲れでしょう。とりあえずお茶でも。」 |
チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
 |
マイケル 「……少しは休めましたか?」 |
 |
マイケル 「それではさっさとおっ始めましょう。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんからねぇー!!」 |
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.537
光のおえかき



■アガタ関連ロールまとめ
ログ:http://dolch.bitter.jp/sub/agata/log/agata.html
スポット:http://lisge.com/ib/talk.php?p=1266
■管理プレイス
阿片せつせつ展〘エフェメラル〙http://lisge.com/ib/talk.php?p=914
星〘アイフェイヨ~ン〙http://lisge.com/ib/talk.php?s=471
【阿片 せつせつ(アガタ セツセツ)】
かなりぱっとした絵描きの男。芸術一本でやっていける名声があり、駅前とかで展覧会ひらかれます!とか大々的に宣伝してある。ハヤミ(速水徹夜)の中学時代の美術部の後輩で、個展の為に移動していてハヤミと再会し、昔のノリそのままでしたっている。
【異能】『アイフェイヨ~ン』
一生に一度しか使えないらしい能力。巨大な星の姿で、日夜イバラシティ上空に浮かんでいるイバラシティならどこでも天気によって見れる。使うと落ち、燃え尽きながらアガタが指定した「ねがいごと」を一つだけ叶える…と思われるが、使ったことがないし一回しか使えないから証明しようがなく、本当に叶うのか なぞ。
…と、いうような人生を侵略によってあたえられた『否定の世界:アンジニティ』の存在である。
ログ:http://dolch.bitter.jp/sub/agata/log/agata.html
スポット:http://lisge.com/ib/talk.php?p=1266
■管理プレイス
阿片せつせつ展〘エフェメラル〙http://lisge.com/ib/talk.php?p=914
星〘アイフェイヨ~ン〙http://lisge.com/ib/talk.php?s=471
【阿片 せつせつ(アガタ セツセツ)】
かなりぱっとした絵描きの男。芸術一本でやっていける名声があり、駅前とかで展覧会ひらかれます!とか大々的に宣伝してある。ハヤミ(速水徹夜)の中学時代の美術部の後輩で、個展の為に移動していてハヤミと再会し、昔のノリそのままでしたっている。
【異能】『アイフェイヨ~ン』
一生に一度しか使えないらしい能力。巨大な星の姿で、日夜イバラシティ上空に浮かんでいるイバラシティならどこでも天気によって見れる。使うと落ち、燃え尽きながらアガタが指定した「ねがいごと」を一つだけ叶える…と思われるが、使ったことがないし一回しか使えないから証明しようがなく、本当に叶うのか なぞ。
…と、いうような人生を侵略によってあたえられた『否定の世界:アンジニティ』の存在である。
13 / 30
159 PS
チナミ区
R-4
R-4



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | 防御10 | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||
| 5 | インスピレーション | 武器 | 15 | 回復10 | 祝福10 | - | 【射程1】 |
| 6 | 平石 | 素材 | 15 | [武器]攻撃15(LV25)[防具]治癒10(LV10)[装飾]防御15(LV25) | |||
| 7 | 腐木 | 素材 | 15 | [武器]腐食15(LV25)[防具]反腐15(LV30)[装飾]舞腐15(LV30) | |||
| 8 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]活力10(LV15) | |||
| 9 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 幻術 | 5 | 夢幻/精神/光 |
| 使役 | 9 | エイド/援護 |
| 付加 | 29 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練1 | アクアヒール | 6 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
| 練1 | ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 |
| オートヒール | 5 | 0 | 80 | 味傷:治癒LV増 | |
| ブレス | 7 | 0 | 60 | 味傷:HP増+祝福 | |
| ライフリンク | 5 | 0 | 30 | エ傷:HP増&自:HP減 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 60 | 自:LK増 | |
| ワイルドナーヴ | 5 | 0 | 150 | エ全:AT・DX・AG増 | |
| チャーム | 5 | 0 | 40 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
| クラック | 5 | 0 | 160 | 敵全:地撃&次与ダメ減 | |
| フローラルキュア | 5 | 0 | 150 | 味全:HP増+強制魅了 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
スポーツドリンク (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練1 |
飲水 (アクアヒール) |
0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
|
きのこの山 (ロックスティング) |
0 | 50 | 敵:地痛撃 | |
|
光輝一閃 (ライトセイバー) |
0 | 110 | 敵貫:光痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]アクアヒール | [ 2 ]ヒールポーション | [ 3 ]ブレス |
| [ 1 ]ヒーリングソング | [ 2 ]ヒールハーブ | [ 2 ]パワフルヒール |

PL / 宮沢