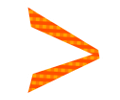<< 2:00>> 4:00




パーティーメンバーと離れて、雫は一人瓦礫に腰かけていた。
一人でいる時間を確保することは大事だ。特に、考え事をするときは一人でいたい。それが自分自身でもよく分からない、自分の心に関することであればなおさらだ。
唇にそっと手を当てる。みずみずしく、なめらかで柔らかく、指で押せばプルンとした弾力で押し返してくる唇だ。栄養も清潔も、最低限を上回ればそれで構わないと思っている自分にしては、きれいな唇だと思う。
しかし、この前、この唇に触れた千雪さんの唇はもっと美しく、心地よかった。抱き着かれてから、千雪さんの白くきれいな顔がすっと自分の近くに寄ってきて、あれ、と思うころには唇どうしが触れ合っていた。少しだけ触れて、すぐに離れたが、その感触の余韻は少しの間残っていた。
初めてのキスだった。
キスというものは知識として知っていたし、実際に他の人がしているのを見たこともあった。同じ部隊の仲間には、挨拶代わりにやたらとキスをする子もいた。夜、興奮が収まらない仲間たちがお互いを慰め合うために、水音を響かせ舌を絡ませ合うキスをしているところを見てしまったこともあった。
指先で唇にチョンと触れる。自分の初めてのキスを再現するように。同性でのキスは全く嫌ではなかった。
昔見てしまった濃厚なキスとは、比べ物にならないほどあっさりとしたキスだった。挨拶代わりのキスに似ていた。しかし、自分の感じたドキドキは強かった。顔は熱く、心臓は早鐘を打っていて、胸の奥が熱くて、興奮なのか緊張なのかよくわからない感情だった。
もし、もう一度千雪さんとキスをすることになったのなら、自分からキスをするのは怖いと思うが……千雪さんからしてくれるのなら、それは嬉しいし、してほしいと思う。
千雪さんも、キスをした後は赤くなっていた。千雪さんが自分にキスをしてきたのは、どういう意味なのだろうか。あの子と同じように、さようならの挨拶だったのだろうか。それとも、それ以上の意味があったのだろうか。
それに……自分がキスをしてほしいと思うのは、どういう意味なのだろうか。千雪さんとのつながりを感じていたい、そう思ってはいる。ただ、それはどういう意味なのだろうか……
雫には、自分の心がよく分からなかった。



ENo.7 ランノ とのやりとり

ENo.87 天遣 柚依 とのやりとり

ENo.245 初早森 兎乃 とのやりとり

ENo.510 ジャックドゥ とのやりとり

ENo.791 ミロワール とのやりとり

以下の相手に送信しました




れーこ(764) に ItemNo.10 不思議な雫 を手渡ししました。










ハティ(741) は パンの耳 を入手!
れーこ(764) は 吸い殻 を入手!
ソラ(936) は パンの耳 を入手!
雫(939) は 吸い殻 を入手!
ハティ(741) は 毛 を入手!
ソラ(936) は 毛 を入手!
ソラ(936) は 不思議な石 を入手!
れーこ(764) は ボロ布 を入手!



武術LV を 2 DOWN。(LV18⇒16、+2CP、-2FP)
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ハティ(741) により ItemNo.5 不思議な石 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
ソラ(936) の持つ ItemNo.8 韮 から射程1の武器『スタンガン』を作製しました!
ハイヤ(1248) の持つ ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から射程1の武器『どうでもよさげなグローブ』を作製しました!
フーコ(1232) により ItemNo.5 何か柔らかい物体 から装飾『真綿のお守り』を作製してもらいました!
⇒ 真綿のお守り/装飾:強さ36/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ミツフネ(940) とカードを交換しました!
流速制御・偽 (アクアスピット)

レッドインペイル を研究しました!(深度0⇒1)
レッドインペイル を研究しました!(深度1⇒2)
レッドインペイル を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
クラッシュ を習得!
アニマート を習得!



チナミ区 J-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――


















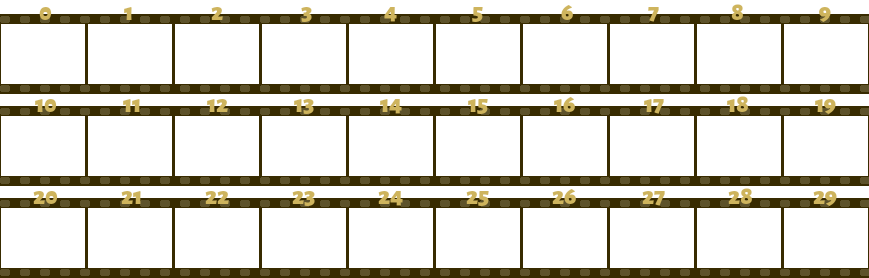





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



パーティーメンバーと離れて、雫は一人瓦礫に腰かけていた。
一人でいる時間を確保することは大事だ。特に、考え事をするときは一人でいたい。それが自分自身でもよく分からない、自分の心に関することであればなおさらだ。
唇にそっと手を当てる。みずみずしく、なめらかで柔らかく、指で押せばプルンとした弾力で押し返してくる唇だ。栄養も清潔も、最低限を上回ればそれで構わないと思っている自分にしては、きれいな唇だと思う。
しかし、この前、この唇に触れた千雪さんの唇はもっと美しく、心地よかった。抱き着かれてから、千雪さんの白くきれいな顔がすっと自分の近くに寄ってきて、あれ、と思うころには唇どうしが触れ合っていた。少しだけ触れて、すぐに離れたが、その感触の余韻は少しの間残っていた。
初めてのキスだった。
キスというものは知識として知っていたし、実際に他の人がしているのを見たこともあった。同じ部隊の仲間には、挨拶代わりにやたらとキスをする子もいた。夜、興奮が収まらない仲間たちがお互いを慰め合うために、水音を響かせ舌を絡ませ合うキスをしているところを見てしまったこともあった。
指先で唇にチョンと触れる。自分の初めてのキスを再現するように。同性でのキスは全く嫌ではなかった。
昔見てしまった濃厚なキスとは、比べ物にならないほどあっさりとしたキスだった。挨拶代わりのキスに似ていた。しかし、自分の感じたドキドキは強かった。顔は熱く、心臓は早鐘を打っていて、胸の奥が熱くて、興奮なのか緊張なのかよくわからない感情だった。
もし、もう一度千雪さんとキスをすることになったのなら、自分からキスをするのは怖いと思うが……千雪さんからしてくれるのなら、それは嬉しいし、してほしいと思う。
千雪さんも、キスをした後は赤くなっていた。千雪さんが自分にキスをしてきたのは、どういう意味なのだろうか。あの子と同じように、さようならの挨拶だったのだろうか。それとも、それ以上の意味があったのだろうか。
それに……自分がキスをしてほしいと思うのは、どういう意味なのだろうか。千雪さんとのつながりを感じていたい、そう思ってはいる。ただ、それはどういう意味なのだろうか……
雫には、自分の心がよく分からなかった。



ENo.7 ランノ とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.87 天遣 柚依 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.245 初早森 兎乃 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.510 ジャックドゥ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.791 ミロワール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| れーこ 「無事に帰れるかな…」 |
 |
ソラ 「見たことの無い生物だらけね。しかも好戦的。気を付けていきましょう。」 |
| 雫 「……さて、今回も気負わず征きましょう。」 |
れーこ(764) に ItemNo.10 不思議な雫 を手渡ししました。



行き当たりばったり4人組
|
 |
ハザマに生きるもの
|



株式会社オークランド
|
 |
行き当たりばったり4人組
|



ハティ(741) は パンの耳 を入手!
れーこ(764) は 吸い殻 を入手!
ソラ(936) は パンの耳 を入手!
雫(939) は 吸い殻 を入手!
ハティ(741) は 毛 を入手!
ソラ(936) は 毛 を入手!
ソラ(936) は 不思議な石 を入手!
れーこ(764) は ボロ布 を入手!



武術LV を 2 DOWN。(LV18⇒16、+2CP、-2FP)
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ハティ(741) により ItemNo.5 不思議な石 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
ソラ(936) の持つ ItemNo.8 韮 から射程1の武器『スタンガン』を作製しました!
ハイヤ(1248) の持つ ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から射程1の武器『どうでもよさげなグローブ』を作製しました!
フーコ(1232) により ItemNo.5 何か柔らかい物体 から装飾『真綿のお守り』を作製してもらいました!
⇒ 真綿のお守り/装飾:強さ36/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ミツフネ(940) とカードを交換しました!
流速制御・偽 (アクアスピット)

レッドインペイル を研究しました!(深度0⇒1)
レッドインペイル を研究しました!(深度1⇒2)
レッドインペイル を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
クラッシュ を習得!
アニマート を習得!



チナミ区 J-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――



行き当たりばったり4人組
|
 |
ハザマに生きるもの
|




行き当たりばったり4人組
|
 |
トートとトード
|


ENo.939
狭霧雫/兎斬雫



名前:狭霧 雫(さぎり しずく)
年齢:14歳(イバラ創藍高校中等部二年生)
身長:156cm 体重:52kg
好き:お肉、甘いもの、炭酸水、歌うこと、散歩
嫌い:孤独、雪
タニモリ区の北部にある狭霧精肉店の一人娘。
家の手伝いをすることが多いため、帰宅部。
家の近くにあるヤガミ神社をよく訪れている。
異能は人並み外れた怪力と身体能力。
その副作用として犬耳と犬の尻尾が生えている。
不断着は和服かジャージのことが多い。
基本的には穏やかで心優しい性格。
以下の精神的な疾患を抱えている。
・他者を傷つけることに忌避感を抱かない。
・音楽(旋律)を覚えることが極端に苦手。
_____________________
本名:兎斬 雫(うさぎり しずく)
イバラシティの住人でもアンジニティの住人でもない。
アンジニティの住人と同じく、イバラシティでは元の記憶を失っている。
ハザマでは本来の記憶を取り戻す。見た目は変わらない。
半妖と呼ばれる遺伝子変異した人間で、元軍人。
14歳のときに死出の旅路に出たはずであったが、
今回の侵略行動に巻き込まれる形で参戦している。
世界間の抗争には関心を示さず、ただ戦場を駆け抜ける。
_____________________
交流歓迎。置きレス多めかもしれません。
既知設定やロールプレイの相談など、お気軽にどうぞ。
現在、プロフ絵は3種類。
▼ホームスポット▼
[狭霧精肉店]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=332
▼よく行くスポット▼
[ヤガミ神社]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=62
[イバラ創藍高校]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=161
[桜並木のさんぽみち]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=443
▼今までのロールプレイ記録▼
[雫の日記帳]
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1532
_____________________
【サブキャラ】
名前:六徳堂 慈(りっとくどう いつき)
年齢:12歳(イバラ創藍高校初等部六年生)
身長:140cm 体重:35kg
好き:味噌汁
嫌い:悲しいこと
最近イバラシティに引っ越してきた男の子。祖父と一緒に住んでいる。
狸の耳と狸の尻尾が生えている。素直で、頭のねじが緩い。
異能は封印されており、使うことができない。
年齢:14歳(イバラ創藍高校中等部二年生)
身長:156cm 体重:52kg
好き:お肉、甘いもの、炭酸水、歌うこと、散歩
嫌い:孤独、雪
タニモリ区の北部にある狭霧精肉店の一人娘。
家の手伝いをすることが多いため、帰宅部。
家の近くにあるヤガミ神社をよく訪れている。
異能は人並み外れた怪力と身体能力。
その副作用として犬耳と犬の尻尾が生えている。
不断着は和服かジャージのことが多い。
基本的には穏やかで心優しい性格。
以下の精神的な疾患を抱えている。
・他者を傷つけることに忌避感を抱かない。
・音楽(旋律)を覚えることが極端に苦手。
_____________________
本名:兎斬 雫(うさぎり しずく)
イバラシティの住人でもアンジニティの住人でもない。
アンジニティの住人と同じく、イバラシティでは元の記憶を失っている。
ハザマでは本来の記憶を取り戻す。見た目は変わらない。
半妖と呼ばれる遺伝子変異した人間で、元軍人。
14歳のときに死出の旅路に出たはずであったが、
今回の侵略行動に巻き込まれる形で参戦している。
世界間の抗争には関心を示さず、ただ戦場を駆け抜ける。
_____________________
交流歓迎。置きレス多めかもしれません。
既知設定やロールプレイの相談など、お気軽にどうぞ。
現在、プロフ絵は3種類。
▼ホームスポット▼
[狭霧精肉店]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=332
▼よく行くスポット▼
[ヤガミ神社]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=62
[イバラ創藍高校]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=161
[桜並木のさんぽみち]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=443
▼今までのロールプレイ記録▼
[雫の日記帳]
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1532
_____________________
【サブキャラ】
名前:六徳堂 慈(りっとくどう いつき)
年齢:12歳(イバラ創藍高校初等部六年生)
身長:140cm 体重:35kg
好き:味噌汁
嫌い:悲しいこと
最近イバラシティに引っ越してきた男の子。祖父と一緒に住んでいる。
狸の耳と狸の尻尾が生えている。素直で、頭のねじが緩い。
異能は封印されており、使うことができない。
15 / 30
114 PS
チナミ区
K-14
K-14






| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | コルト・ガバメント | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 真綿のお守り | 装飾 | 36 | 防御10 | - | - | |
| 6 | おいものスープ | 料理 | 30 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | |||||||
| 8 | 防弾チョッキ | 防具 | 33 | 鎮痛10 | - | - | |
| 9 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]防御10(LV20)[効果3]治癒10(LV30) | |||
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 16 | 身体/武器/物理 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 26 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 月の型・月虹 (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 雪の型・早雪 (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 花の型・早梅 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 雪の型・雪風 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 決3 | 雪の型・深雪 (エキサイト) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| 花の型・残英 (ビブラート) | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| クラッシュ | 5 | 0 | 80 | 敵列:地撃 | |
| 隠し・春雷 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 100 | 敵貫:攻撃 | |
| アニマート | 5 | 0 | 120 | 味全:AT増(2T) | |
| 決3 | 月の型・落月 (イレイザー) | 6 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 雪泥鴻爪 (攻撃) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 行雲流水 (器用) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 槿花一朝 (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 海底撈月 (体力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 氷姿雪魄 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]レッドインペイル | [ 3 ]ブレッシングレイン | [ 3 ]見切り |

PL / そめいろ