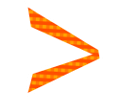<< 1:00>> 3:00




久しぶりの戦いは、思ったよりもあっけなく終わった。武器を使うまでもなく、拳と蹴り、それだけで血の色をしたスライムのような何かは崩れ去ってしまった。
身体の調子はずいぶんと良くなっていた。薬の使い過ぎで壊れた体は、すっかり元に戻っていた。つぶれてほとんど見えなくなってしまっていた目は、相手のようすをつぶさに観察できるほどになっていた。動かなくなっていた左足も、自分の体を支え、地面を蹴って力を生み出すことができるほどになっていた。左足で相手を蹴り飛ばしたとき、丈夫な靴に包まれた自分の足先が相手の体にめり込んでいく感触を確かに感じ取ることができた。両の足で大地を踏みしめ、腰をひねって拳をナレハテに向けて振りぬくとき、地面から生み出された力が、自分の体の中を伝ってねじれと共に相手に漏れることなく移り渡っていくようすが感覚できた。
右手を肩の高さまで上げる。そのまま、すうっと地面と水平にゆっくりと動かしていく。自分の手が空間を切り裂いて綺麗な直線を描いた。右足をゆっくりと上げていく。左足一本で体を支え、バランスを取りながら、足を大きく開いて頭の上の方まで上げた。足の軌道は綺麗な曲線だった。
足元に落ちているコンクリートのかけらを拾い上げる。ポンポンと手の上で弾ませて重さを感じ取ってから、垂直に高く投げ上げた。コンクリート片がやがて頂点に達し、真下に落ちてくる。
雫が垂直に飛び上がる。空中で体を横向きに倒し、体を回転させて反動をつけ、右足を上に伸ばした。地面からおよそ四メートルの位置で雫の右足がコンクリート片をとらえた。蹴り飛ばさないように力と動きを調節しつつ、欠片を甲に乗せるようにして回収する。回転の勢いのまま、足から手へと欠片を投げ飛ばす。地面に着地するときには、雫の左手には投げ上げたコンクリート片がしっかりと握られていた。
欠片を蹴り飛ばすと、近くの廃ビルの割れた窓の中へと吸いこまれて行った。体の制御には問題がなかった。
しかし、体について一点気になることがあった。ナレハテとの戦闘中に負ったはずの傷……それは戦闘終了後にあっという間に治ってしまっていた。雫には傷をたちまちに治してしまう能力など存在しない。そうすると、自分の体は一体どうなっていまっているのだろうか。一つ思い当たるところがあるとすれば、雫は既に死んでしまってるということだ。死してなお、自分が体を保っていることが原因なのではないか、生前の自分の体とは違うのではないか……そう考えてしまうのだ。
『ここでも、向こうでも、雫ちゃんは生きてる。その身体も魂も本物だって、わたしが断言してあげる。』
千雪さんはそう言って励ましてくれた。だが、今の自分の治癒能力は、普通の人間のそれとはかけ離れているし、雫自身の記憶のそれともかけ離れている。もう死んでいるから、死者の体だから、傷はたちまちに治ってしまうのではないか。体の鼓動も体温もかりそめのもので、自分は冷たく朽ちていく死者だから、体の傷をものともしないのではないか……そう考えてしまう。
きっとこの世界に来たのは、罰なのだ。仲間は戦場で苦しんで死んでいったのに、自分は生き延びて、治療まで受けて、安らかな最期を迎えることができたことへの罰なのだ。皆と同じ極光の彼方へ行くためには、最期に得られた温かさをすすがなければならないのだ。この戦場を最後まで駆け抜けて初めて皆と同じところへ行けるのだ。だから、死んだはずの自分の魂に、怪我が治るかりそめの体が与えられたのではないか。たとえ道半ばで斃れることがあったとしても、それは仲間の苦しみに到底及ばないだろうから、何度斃れても前に進むことができる体を与えられたのではないか。
……そう考えると辻褄が合うような気がした。自分が斃れたとき、どうなるのかは分からない。ただ、それでも自分は戦場で目を覚ますだろう……そういう予感がした。
もう、自分は道に乗っている。あとは歩いていけばいいだけなのだ。用意された道を、ひたすらに。ひたすらに。



ENo.14 縷々 エネ とのやりとり

ENo.73 向陽 葵 とのやりとり

ENo.87 天遣 柚依 とのやりとり

ENo.143 ラプリナ とのやりとり

ENo.493 狐草 藤花&千雪 とのやりとり

ENo.936 久手 奏楽 とのやりとり

以下の相手に送信しました














ハティ(741) は 美味しい草 を入手!
れーこ(764) は 美味しい草 を入手!
ソラ(936) は 美味しい草 を入手!
雫(939) は 花びら を入手!
れーこ(764) は 不思議な雫 を入手!
れーこ(764) は 毛 を入手!
れーこ(764) は 美味しい草 を入手!
れーこ(764) は 美味しい草 を入手!



武術LV を 2 DOWN。(LV20⇒18、+2CP、-2FP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ItemNo.8 何か柔らかい物体 に ItemNo.4 コルト・ガバメント を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
ItemNo.8 何か柔らかい物体 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
外郎(802) により ItemNo.8 何か柔らかい物体 から防具『防弾チョッキ』を作製してもらいました!
⇒ 防弾チョッキ/防具:強さ33/[効果1]鎮痛10 [効果2]- [効果3]-
れーこ(764) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『スリングショット』を作製しました!
ウォン(314) とカードを交換しました!
聖なる浄火 (アクアヒール)

ブレッシングレイン を研究しました!(深度0⇒1)
ブレッシングレイン を研究しました!(深度1⇒2)
ブレッシングレイン を研究しました!(深度2⇒3)
ビブラート を習得!
ペネトレイト を習得!



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















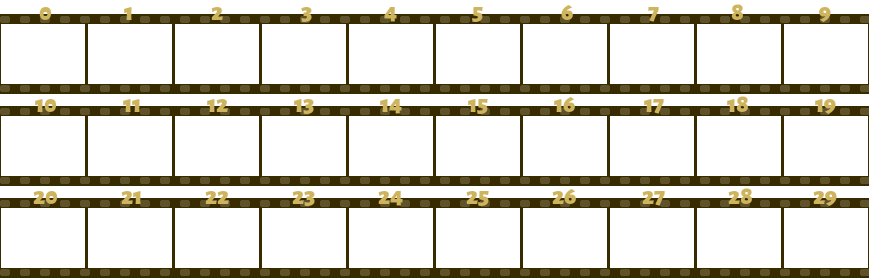





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



久しぶりの戦いは、思ったよりもあっけなく終わった。武器を使うまでもなく、拳と蹴り、それだけで血の色をしたスライムのような何かは崩れ去ってしまった。
身体の調子はずいぶんと良くなっていた。薬の使い過ぎで壊れた体は、すっかり元に戻っていた。つぶれてほとんど見えなくなってしまっていた目は、相手のようすをつぶさに観察できるほどになっていた。動かなくなっていた左足も、自分の体を支え、地面を蹴って力を生み出すことができるほどになっていた。左足で相手を蹴り飛ばしたとき、丈夫な靴に包まれた自分の足先が相手の体にめり込んでいく感触を確かに感じ取ることができた。両の足で大地を踏みしめ、腰をひねって拳をナレハテに向けて振りぬくとき、地面から生み出された力が、自分の体の中を伝ってねじれと共に相手に漏れることなく移り渡っていくようすが感覚できた。
右手を肩の高さまで上げる。そのまま、すうっと地面と水平にゆっくりと動かしていく。自分の手が空間を切り裂いて綺麗な直線を描いた。右足をゆっくりと上げていく。左足一本で体を支え、バランスを取りながら、足を大きく開いて頭の上の方まで上げた。足の軌道は綺麗な曲線だった。
足元に落ちているコンクリートのかけらを拾い上げる。ポンポンと手の上で弾ませて重さを感じ取ってから、垂直に高く投げ上げた。コンクリート片がやがて頂点に達し、真下に落ちてくる。
| 「……よっと。」 |
雫が垂直に飛び上がる。空中で体を横向きに倒し、体を回転させて反動をつけ、右足を上に伸ばした。地面からおよそ四メートルの位置で雫の右足がコンクリート片をとらえた。蹴り飛ばさないように力と動きを調節しつつ、欠片を甲に乗せるようにして回収する。回転の勢いのまま、足から手へと欠片を投げ飛ばす。地面に着地するときには、雫の左手には投げ上げたコンクリート片がしっかりと握られていた。
| 「うん、上出来。」 |
欠片を蹴り飛ばすと、近くの廃ビルの割れた窓の中へと吸いこまれて行った。体の制御には問題がなかった。
しかし、体について一点気になることがあった。ナレハテとの戦闘中に負ったはずの傷……それは戦闘終了後にあっという間に治ってしまっていた。雫には傷をたちまちに治してしまう能力など存在しない。そうすると、自分の体は一体どうなっていまっているのだろうか。一つ思い当たるところがあるとすれば、雫は既に死んでしまってるということだ。死してなお、自分が体を保っていることが原因なのではないか、生前の自分の体とは違うのではないか……そう考えてしまうのだ。
『ここでも、向こうでも、雫ちゃんは生きてる。その身体も魂も本物だって、わたしが断言してあげる。』
| (……そう、言ってはくれたのだけれど。) |
千雪さんはそう言って励ましてくれた。だが、今の自分の治癒能力は、普通の人間のそれとはかけ離れているし、雫自身の記憶のそれともかけ離れている。もう死んでいるから、死者の体だから、傷はたちまちに治ってしまうのではないか。体の鼓動も体温もかりそめのもので、自分は冷たく朽ちていく死者だから、体の傷をものともしないのではないか……そう考えてしまう。
きっとこの世界に来たのは、罰なのだ。仲間は戦場で苦しんで死んでいったのに、自分は生き延びて、治療まで受けて、安らかな最期を迎えることができたことへの罰なのだ。皆と同じ極光の彼方へ行くためには、最期に得られた温かさをすすがなければならないのだ。この戦場を最後まで駆け抜けて初めて皆と同じところへ行けるのだ。だから、死んだはずの自分の魂に、怪我が治るかりそめの体が与えられたのではないか。たとえ道半ばで斃れることがあったとしても、それは仲間の苦しみに到底及ばないだろうから、何度斃れても前に進むことができる体を与えられたのではないか。
……そう考えると辻褄が合うような気がした。自分が斃れたとき、どうなるのかは分からない。ただ、それでも自分は戦場で目を覚ますだろう……そういう予感がした。
| (……だって、わたしが行く場所はそこしかないから。) |
もう、自分は道に乗っている。あとは歩いていけばいいだけなのだ。用意された道を、ひたすらに。ひたすらに。



ENo.14 縷々 エネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.73 向陽 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.87 天遣 柚依 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.143 ラプリナ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||||
ENo.493 狐草 藤花&千雪 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.936 久手 奏楽 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ハティ 「右も左も分からない状態だが……よろしく頼む」 |
| れーこ 「よろしくおねがいします…(大丈夫かな…?)」 |
 |
ソラ 「みんな、まずは自分を守ることを大事にね。」 |
| 雫 「……よろしくお願いします。さあ、征きましょう。」 |



行き当たりばったり4人組
|
 |
ハザマに生きるもの
|



サラリーマン外郎と愉快な仲間達
|
 |
行き当たりばったり4人組
|



ハティ(741) は 美味しい草 を入手!
れーこ(764) は 美味しい草 を入手!
ソラ(936) は 美味しい草 を入手!
雫(939) は 花びら を入手!
れーこ(764) は 不思議な雫 を入手!
れーこ(764) は 毛 を入手!
れーこ(764) は 美味しい草 を入手!
れーこ(764) は 美味しい草 を入手!



武術LV を 2 DOWN。(LV20⇒18、+2CP、-2FP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ItemNo.8 何か柔らかい物体 に ItemNo.4 コルト・ガバメント を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
ItemNo.8 何か柔らかい物体 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
外郎(802) により ItemNo.8 何か柔らかい物体 から防具『防弾チョッキ』を作製してもらいました!
⇒ 防弾チョッキ/防具:強さ33/[効果1]鎮痛10 [効果2]- [効果3]-
 |
外郎 「いい感じで作れたと思うよ。」 |
れーこ(764) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『スリングショット』を作製しました!
ウォン(314) とカードを交換しました!
聖なる浄火 (アクアヒール)

ブレッシングレイン を研究しました!(深度0⇒1)
ブレッシングレイン を研究しました!(深度1⇒2)
ブレッシングレイン を研究しました!(深度2⇒3)
ビブラート を習得!
ペネトレイト を習得!



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――







ここにパーティ名を入力
|
 |
行き当たりばったり4人組
|


ENo.939
狭霧雫/兎斬雫



名前:狭霧 雫(さぎり しずく)
年齢:14歳(イバラ創藍高校中等部二年生)
身長:156cm 体重:52kg
好き:お肉、甘いもの、炭酸水、歌うこと、散歩
嫌い:孤独、雪
タニモリ区の北部にある狭霧精肉店の一人娘。
家の手伝いをすることが多いため、帰宅部。
家の近くにあるヤガミ神社をよく訪れている。
異能は人並み外れた怪力と身体能力。
その副作用として犬耳と犬の尻尾が生えている。
不断着は和服かジャージのことが多い。
基本的には穏やかで心優しい性格。
以下の精神的な疾患を抱えている。
・他者を傷つけることに忌避感を抱かない。
・音楽(旋律)を覚えることが極端に苦手。
_____________________
本名:兎斬 雫(うさぎり しずく)
イバラシティの住人でもアンジニティの住人でもない。
アンジニティの住人と同じく、イバラシティでは元の記憶を失っている。
ハザマでは本来の記憶を取り戻す。見た目は変わらない。
半妖と呼ばれる遺伝子変異した人間で、元軍人。
14歳のときに死亡したはずだが……
_____________________
交流歓迎。置きレス多めかもしれません。
既知設定やロールプレイの相談など、お気軽にどうぞ。
現在、プロフ絵は3種類。
▼ホームスポット▼
[狭霧精肉店]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=332
▼よく行くスポット▼
[ヤガミ神社]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=62
[イバラ創藍高校]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=161
[桜並木のさんぽみち]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=443
▼今までのロールプレイ記録▼
[雫の日記帳]
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1532
年齢:14歳(イバラ創藍高校中等部二年生)
身長:156cm 体重:52kg
好き:お肉、甘いもの、炭酸水、歌うこと、散歩
嫌い:孤独、雪
タニモリ区の北部にある狭霧精肉店の一人娘。
家の手伝いをすることが多いため、帰宅部。
家の近くにあるヤガミ神社をよく訪れている。
異能は人並み外れた怪力と身体能力。
その副作用として犬耳と犬の尻尾が生えている。
不断着は和服かジャージのことが多い。
基本的には穏やかで心優しい性格。
以下の精神的な疾患を抱えている。
・他者を傷つけることに忌避感を抱かない。
・音楽(旋律)を覚えることが極端に苦手。
_____________________
本名:兎斬 雫(うさぎり しずく)
イバラシティの住人でもアンジニティの住人でもない。
アンジニティの住人と同じく、イバラシティでは元の記憶を失っている。
ハザマでは本来の記憶を取り戻す。見た目は変わらない。
半妖と呼ばれる遺伝子変異した人間で、元軍人。
14歳のときに死亡したはずだが……
_____________________
交流歓迎。置きレス多めかもしれません。
既知設定やロールプレイの相談など、お気軽にどうぞ。
現在、プロフ絵は3種類。
▼ホームスポット▼
[狭霧精肉店]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=332
▼よく行くスポット▼
[ヤガミ神社]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=62
[イバラ創藍高校]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=161
[桜並木のさんぽみち]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=443
▼今までのロールプレイ記録▼
[雫の日記帳]
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1532
20 / 30
83 PS
チナミ区
I-11
I-11






| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | コルト・ガバメント | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | おいものスープ | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | 防弾チョッキ | 防具 | 33 | [効果1]鎮痛10 [効果2]- [効果3]- |
| 9 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 18 | 身体/武器/物理 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 23 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 月の型・月虹 (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 雪の型・早雪 (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 花の型・早梅 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 雪の型・雪風 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練1 | 雪の型・深雪 (エキサイト) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:攻撃 | |
| 練2 | 月の型・落月 (イレイザー) | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 雪泥鴻爪 (攻撃) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 行雲流水 (器用) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 槿花一朝 (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 海底撈月 (体力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ブレッシングレイン | [ 3 ]見切り |

PL / そめいろ