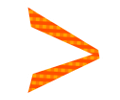<< 2:00>> 4:00




荒廃したハザマの大地を、一人の男が歩いている。
ゆるく結った白髪に、装飾のない黒い簪を二本差しした痩せた男。その後ろを、巨大な蛸がついてくる。触手を使って立ち上がれば人の背丈を超えそうな大きさのそれは、黄色に青の斑点を散らした鮮やかな表皮をうねらせながら、地面を滑るようにゆっくり這って進んでいる。
「くららちゃん〜、ぼく疲れちゃったよお……一休みしようよぉ……」
男が立ち止まり、情けない声を上げて蛸を振り返る。くらら、と呼ばれた蛸は男の言葉を無視して横を通り過ぎ、そのまま進んでいく。
「ふええ、もぉ歩けないよお……」
ぐすぐすと愚痴をこねながらも、男も蛸の後を追って歩き始めた。が、覚束ない足取りが地面の凹凸に引っ掛かり、つんのめって前に倒れる――と、蛸が素早く伸ばした触手が男の体を抱き止めた。
岩や細かい亀裂のある地面で転べば、僅かなりとも傷を負うことは免れないだろう。血を流すことを極度に恐れる男への気遣いか、単に同行者が負傷すると面倒だと思っただけなのかは定かではない。蛸だから。
「うう……くららちゃんやさしい……」
男は都合よく好意的に受け取ったようで、自分の体を支える触手をだらしない表情でぎゅ、と抱き締めた。
ベチィッッ
「いだァッ!!?」
すかさず飛んできた第二の触手が男の頬を張った。小気味いい音が周囲に響く。
男は頬を押さえて涙目で蛸を見つめる。
「ひどい……DVだよぉ……」
ビタァンッッ
「ぉぶッッ」
すかさず反対側の頬にも触手ビンタが飛んだ。
お前は家族じゃないから家庭内暴力(domestic violence)には当てはまらない、と言いたいのかどうかは定かではない。蛸だから。
そうやって往復ビンタを食らわせている間にも、男の体を支える触手は動かない。
ただ重そうな頭を少し傾けて、巨大な頭足類は横長の瞳孔でちらりと男を見た。
「……わかったよお、歩くよお……
藻噛くんと宇佐くん、探さないとだもんね」
頷いて、男は触手を支えに立ち上がり、再び歩き始める。
創峰大学第二学部海洋生物学専攻、斑目研究室。
その主である斑目水緒は、間違いなくイバラシティの住人である。
そして彼は。
この荒廃した世界に来てから姿の見えない生徒、藻噛叢馬と宇佐秋雨の行方を探している。
藻噛叢馬の異能は把握している。彼ならば多少は異能を使って身を守れるだろうし、体力も胆力もある。そう簡単にはやられないだろう。
宇佐秋雨については、異能の有無すら聞いていない。しかし、クロスローズによると、どうやらここに来てはいるらしい。ならば異能は持っているのだろうが、その異能が身を守るのに役立つものなのかは、わからない。
どちらと先に合流するべきだろう、と考える。が、この状況では連絡がついた方から合流した方が良さそうだ。
とりあえず、どちらにもメッセージを送っておくことにした。『Cross+Rose』に慣れるのに手間取ってしまったが、二人ともまだ無事でいてくれるだろうか。
「秋雨くんはさ。困ってても、自分から助けを求められないタイプだと思うんだよね。
まあ、ぼくは戦えないから、くららちゃんに守ってもらうことになるんだけど」
ちらりと蛸を見る。蛸は男の視線を気にする様子もなく、するすると後をついてくる。
くらら。
斑目水緒の研究室で飼われているメスのヒョウモンダコ。
研究室で一番大きな水槽を与えられた小さな美しい蛸は、今はその水槽でも入りきらない大きさに膨れ上がっている。
戦闘能力の一切ない斑目にとって、くららと合流できたことは天の助けと呼ぶべきだろう。巨大化していても、斑紋のパターンが同じだったので一目でくららだとわかった。
「いやあ、持つべきものは頼りになるくららちゃんだねえ。……アッやめてぶたないで」
撫でようとくららの頭部に手を伸ばして、視界の端にスッと持ち上がった触手が見えて慌てて離れた。
「……藻噛くんも、秋雨くんも。他の皆も」
ぽつりと呟く。
「向こうとは違う姿、なのかな」
くららは答えない。蛸は答える舌を持たない。
「もし。ぼくの大切な誰かが、この世界を侵略しようとしているものだったとしたら」
一人の大人として。
たくさんの教え子を持つ、大学の教授として。
――イバラシティの住人として。
「ぼくは、どうするべきなんだろうね」
答えてくれるものはいない。
答えのないまま、決めれらないまま。
一人と一匹はゆっくりとハザマの地を進んでいく。



ENo.371 鈍谷鳴江 とのやりとり

ENo.512 Hǝɯɐʇᴉʇǝ・Nɐupᴉuɐ とのやりとり

ENo.570 タウラシアス とのやりとり

ENo.576 銅見矢凜々子 とのやりとり

ENo.909 スカリム・ヴェノケルコス とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 卵入りポテトサラダのサンドイッチ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










命術LV を 2 UP!(LV8⇒10、-2CP)
呪術LV を 1 UP!(LV0⇒1、-1CP)
防具LV を 6 UP!(LV20⇒26、-6CP)
アザラシの女王(1164) の持つ ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から防具『高級な鞍』を作製しました!
タウラシアス(570) の持つ ItemNo.8 吸い殻 から防具『マイア』を作製しました!
ItemNo.10 毛 から防具『幻想藻の鬣』を作製しました!
⇒ 幻想藻の鬣/防具:強さ36/[効果1]加速10 [効果2]- [効果3]-
アザラシの女王(1164) により ItemNo.4 不思議な投擲斧 に ItemNo.8 駄石 を付加してもらいました!
⇒ 不思議な投擲斧/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]活力10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
齊一(975) とカードを交換しました!
傷薬 (ヒール)

リワインド を研究しました!(深度1⇒2)
ノーマライズ を研究しました!(深度1⇒2)
ブロック を研究しました!(深度1⇒2)
水特性回復 を習得!
パワフルヒール を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。

エディアンが香りの元へと振り向くと――

満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
鬼の口へと放り込まれる。
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
屋台の前ではしゃぐエディアン。
チャットが閉じられる――
















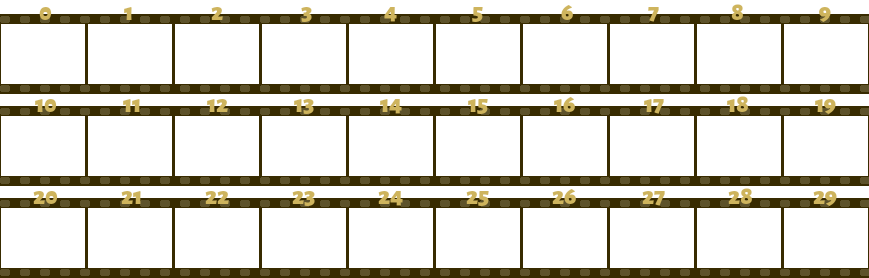





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



荒廃したハザマの大地を、一人の男が歩いている。
ゆるく結った白髪に、装飾のない黒い簪を二本差しした痩せた男。その後ろを、巨大な蛸がついてくる。触手を使って立ち上がれば人の背丈を超えそうな大きさのそれは、黄色に青の斑点を散らした鮮やかな表皮をうねらせながら、地面を滑るようにゆっくり這って進んでいる。
「くららちゃん〜、ぼく疲れちゃったよお……一休みしようよぉ……」
男が立ち止まり、情けない声を上げて蛸を振り返る。くらら、と呼ばれた蛸は男の言葉を無視して横を通り過ぎ、そのまま進んでいく。
「ふええ、もぉ歩けないよお……」
ぐすぐすと愚痴をこねながらも、男も蛸の後を追って歩き始めた。が、覚束ない足取りが地面の凹凸に引っ掛かり、つんのめって前に倒れる――と、蛸が素早く伸ばした触手が男の体を抱き止めた。
岩や細かい亀裂のある地面で転べば、僅かなりとも傷を負うことは免れないだろう。血を流すことを極度に恐れる男への気遣いか、単に同行者が負傷すると面倒だと思っただけなのかは定かではない。蛸だから。
「うう……くららちゃんやさしい……」
男は都合よく好意的に受け取ったようで、自分の体を支える触手をだらしない表情でぎゅ、と抱き締めた。
ベチィッッ
「いだァッ!!?」
すかさず飛んできた第二の触手が男の頬を張った。小気味いい音が周囲に響く。
男は頬を押さえて涙目で蛸を見つめる。
「ひどい……DVだよぉ……」
ビタァンッッ
「ぉぶッッ」
すかさず反対側の頬にも触手ビンタが飛んだ。
お前は家族じゃないから家庭内暴力(domestic violence)には当てはまらない、と言いたいのかどうかは定かではない。蛸だから。
そうやって往復ビンタを食らわせている間にも、男の体を支える触手は動かない。
ただ重そうな頭を少し傾けて、巨大な頭足類は横長の瞳孔でちらりと男を見た。
「……わかったよお、歩くよお……
藻噛くんと宇佐くん、探さないとだもんね」
頷いて、男は触手を支えに立ち上がり、再び歩き始める。
創峰大学第二学部海洋生物学専攻、斑目研究室。
その主である斑目水緒は、間違いなくイバラシティの住人である。
そして彼は。
この荒廃した世界に来てから姿の見えない生徒、藻噛叢馬と宇佐秋雨の行方を探している。
藻噛叢馬の異能は把握している。彼ならば多少は異能を使って身を守れるだろうし、体力も胆力もある。そう簡単にはやられないだろう。
宇佐秋雨については、異能の有無すら聞いていない。しかし、クロスローズによると、どうやらここに来てはいるらしい。ならば異能は持っているのだろうが、その異能が身を守るのに役立つものなのかは、わからない。
どちらと先に合流するべきだろう、と考える。が、この状況では連絡がついた方から合流した方が良さそうだ。
とりあえず、どちらにもメッセージを送っておくことにした。『Cross+Rose』に慣れるのに手間取ってしまったが、二人ともまだ無事でいてくれるだろうか。
「秋雨くんはさ。困ってても、自分から助けを求められないタイプだと思うんだよね。
まあ、ぼくは戦えないから、くららちゃんに守ってもらうことになるんだけど」
ちらりと蛸を見る。蛸は男の視線を気にする様子もなく、するすると後をついてくる。
くらら。
斑目水緒の研究室で飼われているメスのヒョウモンダコ。
研究室で一番大きな水槽を与えられた小さな美しい蛸は、今はその水槽でも入りきらない大きさに膨れ上がっている。
戦闘能力の一切ない斑目にとって、くららと合流できたことは天の助けと呼ぶべきだろう。巨大化していても、斑紋のパターンが同じだったので一目でくららだとわかった。
「いやあ、持つべきものは頼りになるくららちゃんだねえ。……アッやめてぶたないで」
撫でようとくららの頭部に手を伸ばして、視界の端にスッと持ち上がった触手が見えて慌てて離れた。
「……藻噛くんも、秋雨くんも。他の皆も」
ぽつりと呟く。
「向こうとは違う姿、なのかな」
くららは答えない。蛸は答える舌を持たない。
「もし。ぼくの大切な誰かが、この世界を侵略しようとしているものだったとしたら」
一人の大人として。
たくさんの教え子を持つ、大学の教授として。
――イバラシティの住人として。
「ぼくは、どうするべきなんだろうね」
答えてくれるものはいない。
答えのないまま、決めれらないまま。
一人と一匹はゆっくりとハザマの地を進んでいく。



| 斑目教授 「――藻噛くん。ぼくだ、斑目だよ」 |
| 斑目教授 「連絡が遅くなってごめんね。 『Cross+Rose』とやら、なかなかうまく使えなくって」 |
| 斑目教授 「無事なら、どうか返事をしてくれ。 もしも困っていたら、助けに行くから連絡してくれ。 ……待ってるから」 |
ENo.371 鈍谷鳴江 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.512 Hǝɯɐʇᴉʇǝ・Nɐupᴉuɐ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.570 タウラシアス とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.576 銅見矢凜々子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.909 スカリム・ヴェノケルコス とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||||||
| |||
| |||||||
以下の相手に送信しました



 |
タウラシアス 「不用意に俺に近付くなよ? 俺はお前を巻き込まないように配慮とかしねぇからな」 |
ItemNo.7 卵入りポテトサラダのサンドイッチ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









命術LV を 2 UP!(LV8⇒10、-2CP)
呪術LV を 1 UP!(LV0⇒1、-1CP)
防具LV を 6 UP!(LV20⇒26、-6CP)
アザラシの女王(1164) の持つ ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から防具『高級な鞍』を作製しました!
タウラシアス(570) の持つ ItemNo.8 吸い殻 から防具『マイア』を作製しました!
ItemNo.10 毛 から防具『幻想藻の鬣』を作製しました!
⇒ 幻想藻の鬣/防具:強さ36/[効果1]加速10 [効果2]- [効果3]-
| 鬣に絡まった小石や枝をちまちまと取り除いている。 |
アザラシの女王(1164) により ItemNo.4 不思議な投擲斧 に ItemNo.8 駄石 を付加してもらいました!
⇒ 不思議な投擲斧/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]活力10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
すやぴ 「くるるるぅ きゅー」 |
齊一(975) とカードを交換しました!
傷薬 (ヒール)

リワインド を研究しました!(深度1⇒2)
ノーマライズ を研究しました!(深度1⇒2)
ブロック を研究しました!(深度1⇒2)
水特性回復 を習得!
パワフルヒール を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。
 |
エディアン 「皆さんこんにちはー!! 私はいま、梅楽園に来ていまーす!」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
エディアン 「・・・・・何か匂いますね。(くんくん・・・) ・・・これは!・・・パンケーキの香りッ」 |
エディアンが香りの元へと振り向くと――

ベニ
二本の角を持つ体格の良い赤い大鬼。怖い顔。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
 |
ベニ 「残念、こいつはベビーカステラだ。」 |
満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
 |
エディアン 「ベビーカステラ!?私も食べてみ――」 |
 |
ベニ 「残念、品切れだよ。」 |
鬼の口へと放り込まれる。
 |
エディアン 「・・・・・。・・・何なんですか? ただ美味しいものを見せつけたい人ですか?」 |
 |
ベニ 「ああそうさ、羨ましいだろ。」 |
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
 |
エディアン 「・・・どうしてこんなところでこんなことを?」 |
 |
ベニ 「あー、あんたエディ・・・アン?だったな。俺はベニだ。イバラじゃアカツカという名だった。 あちらの生活がクセになっちまったようで、同じように梅楽園でこれを焼いちまってる。」 |
 |
エディアン 「そうですか・・・ それにしても、よく道具や素材がありましたねぇ。」 |
 |
ベニ 「残骸を根気強く漁ってみろ。イバラシティの物が深く埋もれていたりする。 何故か新鮮な食い物だったりな。アンジニティに比べりゃここハザマすら天国だ。」 |
 |
ベニ 「俺の住処ら辺にも食材が在ったようで、いま仲間に運ばせている。 届いたらどんどん焼いてやる。飢えてっだろ、アンジニティ連中は。」 |
 |
エディアン 「本当ですか!?それは楽しみですっ!! 準備ができたらまたこうして連絡してくださいね!絶対行きますッ!!」 |
屋台の前ではしゃぐエディアン。
 |
ベニ 「・・・あいよ、よろしくよろしく。あー、有料だから金は用意しとけよ。」 |
 |
エディアン 「はい!皆さんもぜひぜひ訪れてみてくださいねぇ!! それでは、また来週・・・じゃなくって―― また1時間後っ!!」 |
チャットが閉じられる――







ENo.1017
藻噛 叢馬



藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君、あんた
24歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人は特に気にしていない。
嫌いな食べ物は馬肉とホルモン。それ以外の肉は寧ろ好き。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳がない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
住まいは『コーポロザ111号室』。故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む青い馬。または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■主な出没場所
コーポロザ(http://lisge.com/ib/talk.php?s=145)
海洋生物学専攻斑目研究室(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1296)
アライ海岸(http://lisge.com/ib/talk.php?s=516)
アンディの骨董屋(http://lisge.com/ib/talk.php?p=230)
■個人・交流ログまとめ
微睡む藻屑の幻想海(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1336)
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
46歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能︰"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
***
現在プロフ絵2種。
置きレス多めですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
十card使用中!!(http://rainpark.sub.jp/palir/jucard.html)
自重しないついった:@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君、あんた
24歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人は特に気にしていない。
嫌いな食べ物は馬肉とホルモン。それ以外の肉は寧ろ好き。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳がない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
住まいは『コーポロザ111号室』。故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む青い馬。または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■主な出没場所
コーポロザ(http://lisge.com/ib/talk.php?s=145)
海洋生物学専攻斑目研究室(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1296)
アライ海岸(http://lisge.com/ib/talk.php?s=516)
アンディの骨董屋(http://lisge.com/ib/talk.php?p=230)
■個人・交流ログまとめ
微睡む藻屑の幻想海(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1336)
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
46歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能︰"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
***
現在プロフ絵2種。
置きレス多めですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
十card使用中!!(http://rainpark.sub.jp/palir/jucard.html)
自重しないついった:@yaneura_coqua
16 / 30
64 PS
チナミ区
K-14
K-14















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な投擲斧 | 武器 | 30 | 攻撃10 | 活力10 | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な謎肉スペアリブのロースト | 料理 | 30 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | |||||||
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 10 | 幻想藻の鬣 | 防具 | 36 | 加速10 | - | - | |
| 11 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 1 | 呪詛/邪気/闇 |
| 防具 | 26 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| 望郷の執念 (アクアヒール) | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 | |
| 幻想の藻海 (アイスバインド) | 6 | 0 | 80 | 敵:水撃&凍結 | |
| 決3 | イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確攻撃&HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 赤剥けた剛腕 (攻撃) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 異形の体躯 (活力) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]リワインド | [ 2 ]ノーマライズ | [ 2 ]ブロック |

PL / こか