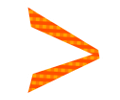<< 2:00>> 4:00





四男のマグヘマタイトとは歳が近かったが、
三男のマグネタイトと四男の間は10歳程の差があった。
次男のウスタイトは家を継ぎ、齢が二桁になったばかりで私は叔父になった。
長男のリモナイトのことはよく知らない。四男が誕生する前に悲しい事があったそうだ。
私は黒の騎士に憧れてからずっと、四男と共に親衛隊に入る三男に稽古をつけてもらった。
「私たち赤色個体は、赤い剣が一番軽く扱える」
「明るい黄色であればその次に軽く、重い青であれば重く感じる」
「だが、補色の緑色には及ばない。有彩色では、あれが一番重く感じるのだ」
三男の説明に私は疑問を投げ掛けた。
「では、黒い剣はどうなのですか? 」
返答は三男ではなく、四男がしてきた。
「重いに決まってるだろう。男の使用人がうちの“あの剣”を数人がかりで運んでたんだぞ」
ですが、と私は反論した。
「私たちは黒の騎士の末裔です。そうであれば、黒の剣を持てるのは当然でしょう」
そうですよね、と私は三男を見た。
三男は何も言わず、いつも私たちを見守る温かい目をしたままだった。
黒の騎士は偉大な英雄であり、私はその末裔である。
そうであれば、この剣を扱う権利があるはずである。
幼い私は信じていた。根拠なく確信していた。私は生まれながらの英雄なのだと。
吸い込まれそうな程の漆黒の”黒の剣”の柄を掴む。持ち上げようとする。
だが、微動だにしない。それどころか、これまで持ったことのない重さを感じる。
次第に私は焦り、力任せに振り上げようとする。
剣はそれでも動かず、代わりに手が滑った私は後ろに転び、ショーケースのガラスを割った。















フレイル(112) は 杉 を入手!
シャルル(246) は 白樺 を入手!
南天 燭(512) は 杉 を入手!
花折美織(1089) は 松 を入手!
フレイル(112) は 美味しい果実 を入手!
花折美織(1089) は 羽 を入手!
シャルル(246) は 美味しい草 を入手!
シャルル(246) は 毛 を入手!



具現LV を 2 DOWN。(LV3⇒1、+2CP、-2FP)
料理LV を 8 DOWN。(LV10⇒2、+8CP、-8FP)
時空LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 11 UP!(LV8⇒19、-11CP)
ユーゴ(192) とカードを交換しました!
If (プロテクション)


リストリクト を研究しました!(深度1⇒2)
ラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
エアスラスト を習得!



チナミ区 F-10(森林)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 F-11(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。

エディアンが香りの元へと振り向くと――

満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
鬼の口へと放り込まれる。
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
屋台の前ではしゃぐエディアン。
チャットが閉じられる――


















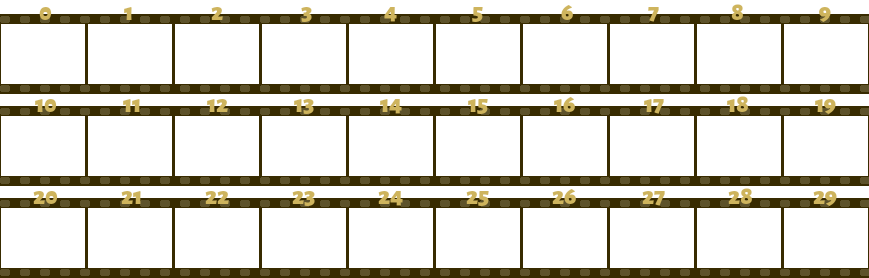





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.




難を転じる事を掲げたナンディナ家。
現在でも王族との近縁に属し、貴族の中でも地位は高い。
その祖は古く、黒の騎士の末裔とも言われている程だ。
私はその五男兄弟の末弟として生を受けた。
現在でも王族との近縁に属し、貴族の中でも地位は高い。
その祖は古く、黒の騎士の末裔とも言われている程だ。
私はその五男兄弟の末弟として生を受けた。
四男のマグヘマタイトとは歳が近かったが、
三男のマグネタイトと四男の間は10歳程の差があった。
次男のウスタイトは家を継ぎ、齢が二桁になったばかりで私は叔父になった。
長男のリモナイトのことはよく知らない。四男が誕生する前に悲しい事があったそうだ。
私は黒の騎士に憧れてからずっと、四男と共に親衛隊に入る三男に稽古をつけてもらった。
「私たち赤色個体は、赤い剣が一番軽く扱える」
「明るい黄色であればその次に軽く、重い青であれば重く感じる」
「だが、補色の緑色には及ばない。有彩色では、あれが一番重く感じるのだ」
三男の説明に私は疑問を投げ掛けた。
「では、黒い剣はどうなのですか? 」
返答は三男ではなく、四男がしてきた。
「重いに決まってるだろう。男の使用人がうちの“あの剣”を数人がかりで運んでたんだぞ」
ですが、と私は反論した。
「私たちは黒の騎士の末裔です。そうであれば、黒の剣を持てるのは当然でしょう」
そうですよね、と私は三男を見た。
三男は何も言わず、いつも私たちを見守る温かい目をしたままだった。
それは、長男が黒地に還って16年目の追悼日だった。
最も大事にされる“16”という数字であったからか、その年は親戚だけでなく外の人も集まった。
その会場に、我が一族の象徴としいて“あの剣”は飾られることになった。
齢二桁に成長したばかりの私は、この時を待っていたと言わんばかりに使用人の間に立ち入った。
使用人は私の要望を断れず、そのショーケースの鍵を開けた。
いつも眺めていただけの“あの剣”が手の届く所にいる。
私はこの剣を手に取り、会場に運ぶつもりでいた。
使用人の手間を楽にさせたい。そんな建前を持って。
最も大事にされる“16”という数字であったからか、その年は親戚だけでなく外の人も集まった。
その会場に、我が一族の象徴としいて“あの剣”は飾られることになった。
齢二桁に成長したばかりの私は、この時を待っていたと言わんばかりに使用人の間に立ち入った。
使用人は私の要望を断れず、そのショーケースの鍵を開けた。
いつも眺めていただけの“あの剣”が手の届く所にいる。
私はこの剣を手に取り、会場に運ぶつもりでいた。
使用人の手間を楽にさせたい。そんな建前を持って。
黒の騎士は偉大な英雄であり、私はその末裔である。
そうであれば、この剣を扱う権利があるはずである。
幼い私は信じていた。根拠なく確信していた。私は生まれながらの英雄なのだと。
吸い込まれそうな程の漆黒の”黒の剣”の柄を掴む。持ち上げようとする。
だが、微動だにしない。それどころか、これまで持ったことのない重さを感じる。
次第に私は焦り、力任せに振り上げようとする。
剣はそれでも動かず、代わりに手が滑った私は後ろに転び、ショーケースのガラスを割った。
血塗れになった私を、両親は涙を流しながら何度も叱りつけた。
上の兄弟にも理由を聞かれ、私はただ泣いていた。
痛かったし、反省は勿論のこと。そして、黒の剣を持ち上げられなかったショックもあった。
私は、英雄ではなかった。黒の騎士にはなれないのだ。
憧れとの解離を見せ付けられたようで、私は手当てを受けても泣き止むことが出来なかった。
そんな中、三男が私の腕の包帯に触れながら話す。
「お前の色変術硬化膜は綺麗な深紅だったな?」
私は頷く。
皮膚の下にあるという色素の塊である臓器は、ガラスが皮膚を裂いた際に見えた。
「そうだ。それで間違いない」
「だが、ここに“黒”が混ざれば濁った色になる」
「うちの家系に黒色個体は居ないんだ」
上の兄弟にも理由を聞かれ、私はただ泣いていた。
痛かったし、反省は勿論のこと。そして、黒の剣を持ち上げられなかったショックもあった。
私は、英雄ではなかった。黒の騎士にはなれないのだ。
憧れとの解離を見せ付けられたようで、私は手当てを受けても泣き止むことが出来なかった。
そんな中、三男が私の腕の包帯に触れながら話す。
「お前の色変術硬化膜は綺麗な深紅だったな?」
私は頷く。
皮膚の下にあるという色素の塊である臓器は、ガラスが皮膚を裂いた際に見えた。
「そうだ。それで間違いない」
「だが、ここに“黒”が混ざれば濁った色になる」
「うちの家系に黒色個体は居ないんだ」
「だが、これも忘れるな」
「英雄は、誰かを救ってこそなれるものだ」
「英雄は、誰かを救ってこそなれるものだ」





 |
フレイル 「行軍開始、できる事を確実に」 |
 |
シャルル 「では、参りましょうか」 |
 |
男はこのPT名に覚えがある。 何故か食べさせられた燃えるチップスター。名前があるならこれだろう。 |
| 黒鬼 「■■■■■■■■■■■■■■■■■■!!」 |



ちりちり☆ちっぷすたー
|
 |
ハザマに生きるもの
|



ちりちり☆ちっぷすたー
|
 |
イバラ部特別捜査隊さっちゃんず
|



フレイル(112) は 杉 を入手!
シャルル(246) は 白樺 を入手!
南天 燭(512) は 杉 を入手!
花折美織(1089) は 松 を入手!
フレイル(112) は 美味しい果実 を入手!
花折美織(1089) は 羽 を入手!
シャルル(246) は 美味しい草 を入手!
シャルル(246) は 毛 を入手!



具現LV を 2 DOWN。(LV3⇒1、+2CP、-2FP)
料理LV を 8 DOWN。(LV10⇒2、+8CP、-8FP)
時空LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 11 UP!(LV8⇒19、-11CP)
ユーゴ(192) とカードを交換しました!
If (プロテクション)


リストリクト を研究しました!(深度1⇒2)
ラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
エアスラスト を習得!



チナミ区 F-10(森林)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 F-11(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。
 |
エディアン 「皆さんこんにちはー!! 私はいま、梅楽園に来ていまーす!」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
エディアン 「・・・・・何か匂いますね。(くんくん・・・) ・・・これは!・・・パンケーキの香りッ」 |
エディアンが香りの元へと振り向くと――

ベニ
二本の角を持つ体格の良い赤い大鬼。怖い顔。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
 |
ベニ 「残念、こいつはベビーカステラだ。」 |
満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
 |
エディアン 「ベビーカステラ!?私も食べてみ――」 |
 |
ベニ 「残念、品切れだよ。」 |
鬼の口へと放り込まれる。
 |
エディアン 「・・・・・。・・・何なんですか? ただ美味しいものを見せつけたい人ですか?」 |
 |
ベニ 「ああそうさ、羨ましいだろ。」 |
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
 |
エディアン 「・・・どうしてこんなところでこんなことを?」 |
 |
ベニ 「あー、あんたエディ・・・アン?だったな。俺はベニだ。イバラじゃアカツカという名だった。 あちらの生活がクセになっちまったようで、同じように梅楽園でこれを焼いちまってる。」 |
 |
エディアン 「そうですか・・・ それにしても、よく道具や素材がありましたねぇ。」 |
 |
ベニ 「残骸を根気強く漁ってみろ。イバラシティの物が深く埋もれていたりする。 何故か新鮮な食い物だったりな。アンジニティに比べりゃここハザマすら天国だ。」 |
 |
ベニ 「俺の住処ら辺にも食材が在ったようで、いま仲間に運ばせている。 届いたらどんどん焼いてやる。飢えてっだろ、アンジニティ連中は。」 |
 |
エディアン 「本当ですか!?それは楽しみですっ!! 準備ができたらまたこうして連絡してくださいね!絶対行きますッ!!」 |
屋台の前ではしゃぐエディアン。
 |
ベニ 「・・・あいよ、よろしくよろしく。あー、有料だから金は用意しとけよ。」 |
 |
エディアン 「はい!皆さんもぜひぜひ訪れてみてくださいねぇ!! それでは、また来週・・・じゃなくって―― また1時間後っ!!」 |
チャットが閉じられる――



タスクフォーサー
|
 |
ハザマに生きるもの
|




TeamNo.13
|
 |
タスクフォーサー
|


ENo.512
Hǝɯɐʇᴉʇǝ・Nɐupᴉuɐ



南天 燭 【ナンテン ショク】 身長:170cm 体重:重い
観光兼人探しに来た30代の男。ペイントにも似た赤い模様が顔を横断し、それが全身にある。
五男兄弟の末弟。とある企業の上層部で子供二人もいる妻帯者。そんな彼が休暇をとってまで捜したい友人は、現在行方不明。
「この島の人間は特殊能力を持ち、ある時間に異世界への扉が開くらしい」
そんな噂を聞き、少しでも手掛かりを得られれば。そんな期待をもって彼はイバラシティを訪れる。
時々イバラシティから離れて家族の元に帰っていたりする。
好きなものはミュージック。あと、とにかく赤い料理。辛くても肉々しくてもどちらでも好き。反面、緑黄色野菜は好きじゃない。
あまり表情を変えることはないが、貰いタバコをするくらいには無自覚甘えん坊。
―――――――――――――――――――――――――
【難を転ずる】
常時発動。如何なる禍難、苦難、困難であろうと彼は諦めることはない。絶対に変えて見せるという意思。諦めない心。それらを覆すその時まで挑み続ける不屈の精神。
それはある種の特殊能力とも言えるだろう。
【黒の騎士】
あらゆるものを分解し、消滅させる“無”の系譜による力。本来であれば灰色を示す力であるが、上手く力が調整出来ないのか黒の力として発現される。
全てに囚われない無の力は時空間を操ることも可能で、武器を無数に取り出したり宙を走ることも出来る。
だが、イバラシティでの彼はこの能力に気づいていない。
――――――――――――――――――
Hǝɯɐʇᴉʇǝ・Nɐupᴉuɐ 【ヘマタイト・ナンディナ】
ある男が道を踏み誤った。もしも、運命に逆らってでも己を貫き、己の願いを叶えた男の辿る末路。黒の騎士。世界の裏切り者。
護りたかった国に帰る事も出来ず、世界の裏切り者としての役目も果たせず。掃き溜めを老いぬ身体で、黒の大剣を携え徘徊する。
“世界に抗え”
“黒の騎士として恥じぬ戦いを”
彼は何を選択するか。それはまだ得られていない。
― 情報
+ “厄災”を滅ぼすため黒の騎士になった
+ お伽噺に出る黒の騎士とは、黒地すらも救った英雄である
+ 彼の身体は己の意思で支えられている
+ 本来は黒の剣を振るう事も叶わない赤色個体
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Twitter @gensolove_0104
観光兼人探しに来た30代の男。ペイントにも似た赤い模様が顔を横断し、それが全身にある。
五男兄弟の末弟。とある企業の上層部で子供二人もいる妻帯者。そんな彼が休暇をとってまで捜したい友人は、現在行方不明。
「この島の人間は特殊能力を持ち、ある時間に異世界への扉が開くらしい」
そんな噂を聞き、少しでも手掛かりを得られれば。そんな期待をもって彼はイバラシティを訪れる。
時々イバラシティから離れて家族の元に帰っていたりする。
好きなものはミュージック。あと、とにかく赤い料理。辛くても肉々しくてもどちらでも好き。反面、緑黄色野菜は好きじゃない。
あまり表情を変えることはないが、貰いタバコをするくらいには無自覚甘えん坊。
―――――――――――――――――――――――――
【難を転ずる】
常時発動。如何なる禍難、苦難、困難であろうと彼は諦めることはない。絶対に変えて見せるという意思。諦めない心。それらを覆すその時まで挑み続ける不屈の精神。
それはある種の特殊能力とも言えるだろう。
【黒の騎士】
あらゆるものを分解し、消滅させる“無”の系譜による力。本来であれば灰色を示す力であるが、上手く力が調整出来ないのか黒の力として発現される。
全てに囚われない無の力は時空間を操ることも可能で、武器を無数に取り出したり宙を走ることも出来る。
だが、イバラシティでの彼はこの能力に気づいていない。
――――――――――――――――――
Hǝɯɐʇᴉʇǝ・Nɐupᴉuɐ 【ヘマタイト・ナンディナ】
ある男が道を踏み誤った。もしも、運命に逆らってでも己を貫き、己の願いを叶えた男の辿る末路。黒の騎士。世界の裏切り者。
護りたかった国に帰る事も出来ず、世界の裏切り者としての役目も果たせず。掃き溜めを老いぬ身体で、黒の大剣を携え徘徊する。
“世界に抗え”
“黒の騎士として恥じぬ戦いを”
彼は何を選択するか。それはまだ得られていない。
― 情報
+ “厄災”を滅ぼすため黒の騎士になった
+ お伽噺に出る黒の騎士とは、黒地すらも救った英雄である
+ 彼の身体は己の意思で支えられている
+ 本来は黒の剣を振るう事も叶わない赤色個体
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Twitter @gensolove_0104
20 / 30
117 PS
チナミ区
I-11
I-11




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 紅の八塩 | 装飾 | 15 | 器用10 | 幸運10 | - | |
| 5 | 杉 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV30)[防具]舞痺10(LV20)[装飾]加速10(LV10) | |||
| 6 | 肉丼 | 料理 | 20 | 治癒10 | 活力10 | - | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 10 | 空間/時間/風 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 具現 | 1 | 創造/召喚 |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 装飾 | 19 | 装飾作製に影響 |
| 付加 | 5 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 2 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| 決3 | ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| レックレスチャージ | 5 | 0 | 80 | 自:HP減+敵全:風痛撃 | |
| クリエイト:ピコハン | 5 | 0 | 60 | 敵列:朦朧 | |
| ウィンドスピア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:風痛撃 | |
| スナイプ | 5 | 0 | 60 | 自:DX増(3T) | |
| ウィザー | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| ヒンダー | 5 | 0 | 40 | 自:炎上・凍結・束縛防御増+次受ダメ減 | |
| キーンフォーム | 5 | 0 | 80 | 自:DX・貫通LV増 | |
| クリエイト:ガトリング | 5 | 0 | 110 | 味:貫撃LV増 | |
| アドバンテージ | 5 | 0 | 80 | 敵:攻撃&AT奪取 | |
| エアスラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:4連風撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]エキサイト | [ 2 ]リストリクト | [ 1 ]ラッシュ |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]プロテクション | [ 1 ]アリア |
| [ 1 ]イレイザー |

PL / 薄(ススキ)