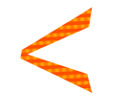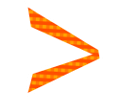<< 1:00>> 3:00




第二話 予知の姫とサーディラン・グッドスピード
「本当に、いいんだな?」
俺の声が密かに目の前の綺麗な着物を着た女性に届く。
……懐かしいな、あの時の夢か。
「ええ、構いません。サーディラン・グッドスピード、忍びの里の一人の忍者……私は、貴方に殺される運命にありました」
目の前にいる女は「予知の姫」と呼ばれる女性だ。
実際彼女のいる国は、彼女を女王として国を興し、そして、あらゆる国に攻め入っていた。
俺の住む里がある国も襲撃対象であり、里にはこの依頼がいくつも何重にも舞い込んできたが、これまでで述べ29人の当時の同胞、里の仲間が帰らぬ人となった。
中には俺に忍びとしての戦い方を教えてくれた先輩や上司もいた。
俺はどちらかと言うと、あまりにも有力な里の人間が帰らぬ人となりすぎたため、「仕方なく選ばれた」と言ってもいいであろう忍びだ。
要は、「もう当たればいい」と自棄になった鉄砲玉の一つに過ぎないわけだ。
「分かんねえな……俺よりも腕のいいやつ、賢いやつ、強いやつ……さんざんあんたの所に送られてきたはずだ。そしてそれをあんたの『予知能力』で全て死んでいった。
だが、俺の時は見張り兵すらいなかった、罠なんか当然ない。
こんなの、ナイフの使い方を覚えた齢二桁になったばかりの人間でも、殺すのは容易いだろう。
なぜ、俺の時だけ『こう』なんだ?」
予知の姫から帰ってきた答えは、まあ、大したものではなかった。
「ここで、貴方に殺されると予知にあったからですよ」
そうとしか言わねえよな……と思いつつ、手元の刃物を首にあてようとした時。
「その前に、私は貴方に三つ、伝えなければならないことがあります」
俺は手を止める。
「命乞い、じゃねえよな流石に。そもそも命乞いをするのであれば最初から予知を潰すために『サーディラン・グッドスピード』を見つけ出し殺すようにするべきだ。
でも、あんたはそれをしなかった。死にたいのは確かなんだろう」
「ええ、私は貴方に三つ、伝えたいことがあって、ここまでしてきました。
他の国を滅ぼし、貴方の国に致命的な制裁を与え、全ては、貴方にこれらを伝えるために」
俺如きのために?ただ里で生きてただ忍びとして生きて、そして忍びの任務で死ぬか、寿命で死ぬしかないであろう平凡な忍びとして生きるであろう俺に?
そんな心の声を見透かすように、彼女は続けた。
「貴方は自分の人生において、恐ろしいほどの奔流にのまれることになります。
まず一つ。貴方は今回の任務成功によってかなりの腕前だと見込まれますが、それでもとある男の暗殺に失敗します。さらに言えば、失敗後の退却の後、とある男の部下にあたる少年にまで負けてしまいます」
俺の眉間にしわがよったのを見たのだろうか、少し慌てて続ける。
「いえ、貴方がヘマをしたとかそういうのではありません。貴方の世界ではいずれ……いえ、実際には既に私がそうなのですが、P-BLOODと言う血液感染症による異能が発現していきます。
これについては、そういうものがあるとだけ思ってくれていればいいです」
「なるほどね……あんたもそうだと」
「そして二つ目。一つ目で話した任務で失敗した貴方は、その任務で殺す対象だった彼らによって救われます。
貴方はそこで新たな仲間と、かけがえのない友人を手に入れます」
里の掟を覆すほどの者と出会うというわけか。
しかし、その程度の予知だけで国を滅ぼすものなのか?
「ここまでは、貴方に私の予知を信じてほしいからこそ伝えた内容です。
最も重要な予知は最後の三つ目です」
本題はここなのだろうな。そう思いつつ、聞くことにする。
「貴方が二つ目の予知で入ることになった組織。そこで貴方の仲間が世界花を咲かせます。
その世界花が私そのものであり、そして……
『私が咲き続ける限り この世界は他の世界に侵食され……この世界が、この世界でなくなります』」
なるほど、あくまでも俺と言う存在のためだけに国を滅ぼし続けるには大きすぎる予言だ。
もちろん、それが当たればの話だが。
……当たればの話だが。
「一応、覚えてはおく。
とりあえず、どれか一つでも間違っちまえば、一番最後のは起こらねえ、そうだろう?」
彼女は首を横に振る。
「いいえ、むしろ変えられるのは一番最後の予知だけです。
そこだけ、枝分かれした未来になっていて、その鍵を握るのは貴方を含めて5人の仲間です。
……伝えたいことは伝えました。それでは、貴方は貴方のなすべきことを」
俺は、そのまま刃物を彼女の首に当て。
引いた。
この夢からの後日談になるが、俺はこの件がきっかけとなり、P-BLOODの発現が起こった。
さて、夢の通りであると、俺たちのいた世界をなんとかするために戦う理由があるのは、「ラルクベルテ・ハンドレッド」「ミリー・ブロッサム」「グランバスタ・ダブルシザース」「レシチア・マリンシンガー」、そしてこの俺「サーディラン・グッドスピード」となるわけだ。
なんだかんだいって、主にミリーの働きにより同行者が増えたものの。
……俺たちは、アンジニティの勢いを削ぐことが出来るのか?



ENo.321 マリア・フォレストライト とのやりとり

ENo.683 東堂玄樹 とのやりとり




ItemNo.6 マジカルグラタン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









マリア(321) は 美味しくない草 を入手!
ラクベル(322) は パンの耳 を入手!
フェナ(984) は 吸い殻 を入手!
ラクベル(322) は 不思議な石 を入手!
フェナ(984) は ねばねば を入手!
フェナ(984) は 不思議な石 を入手!



魔術LV を 3 UP!(LV5⇒8、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『治癒刀・鈴蘭』を作製しました!
⇒ 治癒刀・鈴蘭/武器:強さ33/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
マリア(321) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『荊棘の蔓』を作製しました!
アカリ(798) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程5の武器『投げても戻る不思議な石』を作製しました!
マリア(321) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『「マリアお手製薔薇緑茶」』をつくってもらいました!
⇒ 「マリアお手製薔薇緑茶」/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
れいか(292) とカードを交換しました!
これいる? (リストリクト)

サモン:ナレハテ を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:セイレーン を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:ガーゴイル を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 E-9(森林)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 F-9(森林)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調23⇒22)
リラ(1264) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















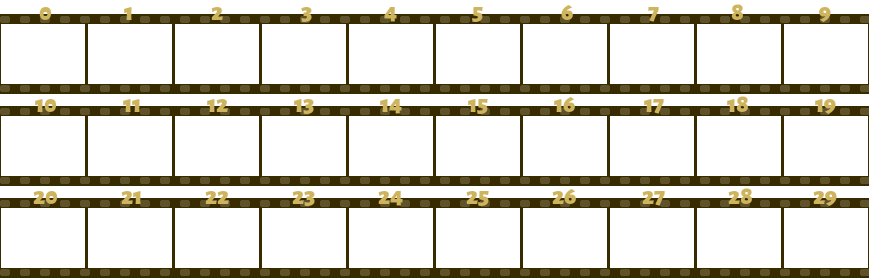





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



第二話 予知の姫とサーディラン・グッドスピード
「本当に、いいんだな?」
俺の声が密かに目の前の綺麗な着物を着た女性に届く。
……懐かしいな、あの時の夢か。
「ええ、構いません。サーディラン・グッドスピード、忍びの里の一人の忍者……私は、貴方に殺される運命にありました」
目の前にいる女は「予知の姫」と呼ばれる女性だ。
実際彼女のいる国は、彼女を女王として国を興し、そして、あらゆる国に攻め入っていた。
俺の住む里がある国も襲撃対象であり、里にはこの依頼がいくつも何重にも舞い込んできたが、これまでで述べ29人の当時の同胞、里の仲間が帰らぬ人となった。
中には俺に忍びとしての戦い方を教えてくれた先輩や上司もいた。
俺はどちらかと言うと、あまりにも有力な里の人間が帰らぬ人となりすぎたため、「仕方なく選ばれた」と言ってもいいであろう忍びだ。
要は、「もう当たればいい」と自棄になった鉄砲玉の一つに過ぎないわけだ。
「分かんねえな……俺よりも腕のいいやつ、賢いやつ、強いやつ……さんざんあんたの所に送られてきたはずだ。そしてそれをあんたの『予知能力』で全て死んでいった。
だが、俺の時は見張り兵すらいなかった、罠なんか当然ない。
こんなの、ナイフの使い方を覚えた齢二桁になったばかりの人間でも、殺すのは容易いだろう。
なぜ、俺の時だけ『こう』なんだ?」
予知の姫から帰ってきた答えは、まあ、大したものではなかった。
「ここで、貴方に殺されると予知にあったからですよ」
そうとしか言わねえよな……と思いつつ、手元の刃物を首にあてようとした時。
「その前に、私は貴方に三つ、伝えなければならないことがあります」
俺は手を止める。
「命乞い、じゃねえよな流石に。そもそも命乞いをするのであれば最初から予知を潰すために『サーディラン・グッドスピード』を見つけ出し殺すようにするべきだ。
でも、あんたはそれをしなかった。死にたいのは確かなんだろう」
「ええ、私は貴方に三つ、伝えたいことがあって、ここまでしてきました。
他の国を滅ぼし、貴方の国に致命的な制裁を与え、全ては、貴方にこれらを伝えるために」
俺如きのために?ただ里で生きてただ忍びとして生きて、そして忍びの任務で死ぬか、寿命で死ぬしかないであろう平凡な忍びとして生きるであろう俺に?
そんな心の声を見透かすように、彼女は続けた。
「貴方は自分の人生において、恐ろしいほどの奔流にのまれることになります。
まず一つ。貴方は今回の任務成功によってかなりの腕前だと見込まれますが、それでもとある男の暗殺に失敗します。さらに言えば、失敗後の退却の後、とある男の部下にあたる少年にまで負けてしまいます」
俺の眉間にしわがよったのを見たのだろうか、少し慌てて続ける。
「いえ、貴方がヘマをしたとかそういうのではありません。貴方の世界ではいずれ……いえ、実際には既に私がそうなのですが、P-BLOODと言う血液感染症による異能が発現していきます。
これについては、そういうものがあるとだけ思ってくれていればいいです」
「なるほどね……あんたもそうだと」
「そして二つ目。一つ目で話した任務で失敗した貴方は、その任務で殺す対象だった彼らによって救われます。
貴方はそこで新たな仲間と、かけがえのない友人を手に入れます」
里の掟を覆すほどの者と出会うというわけか。
しかし、その程度の予知だけで国を滅ぼすものなのか?
「ここまでは、貴方に私の予知を信じてほしいからこそ伝えた内容です。
最も重要な予知は最後の三つ目です」
本題はここなのだろうな。そう思いつつ、聞くことにする。
「貴方が二つ目の予知で入ることになった組織。そこで貴方の仲間が世界花を咲かせます。
その世界花が私そのものであり、そして……
『私が咲き続ける限り この世界は他の世界に侵食され……この世界が、この世界でなくなります』」
なるほど、あくまでも俺と言う存在のためだけに国を滅ぼし続けるには大きすぎる予言だ。
もちろん、それが当たればの話だが。
……当たればの話だが。
「一応、覚えてはおく。
とりあえず、どれか一つでも間違っちまえば、一番最後のは起こらねえ、そうだろう?」
彼女は首を横に振る。
「いいえ、むしろ変えられるのは一番最後の予知だけです。
そこだけ、枝分かれした未来になっていて、その鍵を握るのは貴方を含めて5人の仲間です。
……伝えたいことは伝えました。それでは、貴方は貴方のなすべきことを」
俺は、そのまま刃物を彼女の首に当て。
引いた。
この夢からの後日談になるが、俺はこの件がきっかけとなり、P-BLOODの発現が起こった。
さて、夢の通りであると、俺たちのいた世界をなんとかするために戦う理由があるのは、「ラルクベルテ・ハンドレッド」「ミリー・ブロッサム」「グランバスタ・ダブルシザース」「レシチア・マリンシンガー」、そしてこの俺「サーディラン・グッドスピード」となるわけだ。
なんだかんだいって、主にミリーの働きにより同行者が増えたものの。
……俺たちは、アンジニティの勢いを削ぐことが出来るのか?



ENo.321 マリア・フォレストライト とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.683 東堂玄樹 とのやりとり



 |
ラクベル 「よし、全員揃いましたね、改めてよろしくお願いしま……いない!!一人いない!?」 |
ItemNo.6 マジカルグラタン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





TeamNo.1571
|
 |
フリージア
|



マリア(321) は 美味しくない草 を入手!
ラクベル(322) は パンの耳 を入手!
フェナ(984) は 吸い殻 を入手!
ラクベル(322) は 不思議な石 を入手!
フェナ(984) は ねばねば を入手!
フェナ(984) は 不思議な石 を入手!



魔術LV を 3 UP!(LV5⇒8、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『治癒刀・鈴蘭』を作製しました!
⇒ 治癒刀・鈴蘭/武器:強さ33/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
ラクベル 「んー、間に合わせですが作っておきますか。」 |
マリア(321) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『荊棘の蔓』を作製しました!
アカリ(798) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程5の武器『投げても戻る不思議な石』を作製しました!
マリア(321) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『「マリアお手製薔薇緑茶」』をつくってもらいました!
⇒ 「マリアお手製薔薇緑茶」/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
マリア 「ちょっとだけ趣向を凝らしてみたのですが、いかがでしょうか。念のため胃薬を用意することをおすすめします。」 |
れいか(292) とカードを交換しました!
これいる? (リストリクト)

サモン:ナレハテ を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:セイレーン を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:ガーゴイル を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 E-9(森林)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 F-9(森林)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調23⇒22)
リラ(1264) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――



フリージア
|
 |
ハザマに生きるもの
|




ピップパップギー
|
 |
フリージア
|


ENo.322
ラルクベルテ・ハンドレッド



エルタ・ブレイアからアンジニティを経てアンジニティの進行を防ぐためにイバラシティ側についた異能者達。
今回の依頼ではいつものように異世界の物資を回収する目的ではなく、エルタ・ブレイアへの進行の足掛かりになる前にイバラシティにてアンジニティ勢力を削ぐ事を目的とする。
メンバーはネイキッドブレイブに所属する第二部隊の面々であり、主に戦闘に参加するのは隊長である「ラルクベルテ・ハンドレッド」である。
以下、メンバーの紹介
アンジニティの姿「ラルクベルテ・ハンドレッド」
イバラシティの姿「百瀬 楽太郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第二部隊隊長を務める。いわゆる特攻隊長であり、前線に立って戦うことを得意とする。焔とサムライ流の剣術を得意とする。好きな女性のタイプはおねーさん。好きな食べ物飲み物は緑茶(特に玉露)。
☆イバラシティの姿では児童養護施設「フリージア」に住んでいる少年であり、母子家庭であったものの財政難の理由から母親が養えなくなり、この施設に所属した経緯を持つ。基本的に控えめな性格であるが、「美愛」以外のお姉さんに対してはデレデレである。
アンジニティの姿「サーディラン・グッドスピード」
イバラシティの姿「速水 三十郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ副隊長を務める。毒や高速起動によるサポートを得意とする、ニンジャスタイルの戦闘を好む。好きな食べ物はショートケーキ。
☆イバラシティの姿ではフリージア所属3年目の職員。もともと利用児童だったのであるが、これといった就職先が見つからなかったのでそのままここの職員になった。昼間は常に眠そうにしているが、陽気な性格で児童ウケはいいらしい。
アンジニティの姿「ミリー・ブロッサム」
イバラシティの姿「咲 美里」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第三席を務める。主に植物による回復、支援、妨害を行うドルイドスタイルで戦う。好きな食べ物はよもぎ餅。
☆イバラシティの姿では花をこよなく愛する児童で、笑顔を絶やさない穏やかな性格。いわゆるロッカー児童だったのであるが、幸い泣き声に気づいた大人の人によって保護され、この施設で育った。父や母を知らないためか、職員のメンバーを親のように思っており、たまにうっかり「お母さん」と呼んだりする。
アンジニティの姿「グランバスタ・ダブルシザース」
イバラシティの姿「鋼鐡 蔵助」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第四席を務める。自己強化と回復、そして拳による格闘術に長けており、いわゆるモンクスタイルで戦う。好きな食べ物は激辛カレー。
☆イバラシティの姿では両親がヤのつく自営業の方々であり、まともな教育が出来ないと判断されてこの施設に預けられることになる。勤勉家であり、かつ努力家でもあるのだが、そこにはいじっぱりな性格が関係しているらしい。
アンジニティの姿「レシチア・マリンシンガー」
イバラシティの姿「響 美愛」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第五席を務める。音楽と氷の超能力を持ちいて戦う。スタイルとしてはバードのような戦い方と言えるであろう。好きな食べ物は鯖の南蛮漬け。
☆イバラシティの姿ではピアニストとしてある程度名をはせていたものの、「子供ともっと触れ合って音楽の楽しさを教えたい」という理由から施設の職員となる。彼女の引くピアノは歌を覚えた子供は歌いたくなり、さらに小さい子には子守歌のようにすやすやと寝るほどの技術力を持つ。図太い性格なので細かいことは気にしない。
児童養護施設「フリージア」について
創設者である施設長の方針で、家族のような暖かい場所を作ろうと思って作られた施設である。
施設長自身は「イバラシティの一般人」なのであるが、なんとなくこの世界の異変にはうっすらと気づいている様子。
この施設でどのような物語になるのか、ラクベル達の行動で変わっていくだろう。
今回の依頼ではいつものように異世界の物資を回収する目的ではなく、エルタ・ブレイアへの進行の足掛かりになる前にイバラシティにてアンジニティ勢力を削ぐ事を目的とする。
メンバーはネイキッドブレイブに所属する第二部隊の面々であり、主に戦闘に参加するのは隊長である「ラルクベルテ・ハンドレッド」である。
以下、メンバーの紹介
アンジニティの姿「ラルクベルテ・ハンドレッド」
イバラシティの姿「百瀬 楽太郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第二部隊隊長を務める。いわゆる特攻隊長であり、前線に立って戦うことを得意とする。焔とサムライ流の剣術を得意とする。好きな女性のタイプはおねーさん。好きな食べ物飲み物は緑茶(特に玉露)。
☆イバラシティの姿では児童養護施設「フリージア」に住んでいる少年であり、母子家庭であったものの財政難の理由から母親が養えなくなり、この施設に所属した経緯を持つ。基本的に控えめな性格であるが、「美愛」以外のお姉さんに対してはデレデレである。
アンジニティの姿「サーディラン・グッドスピード」
イバラシティの姿「速水 三十郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ副隊長を務める。毒や高速起動によるサポートを得意とする、ニンジャスタイルの戦闘を好む。好きな食べ物はショートケーキ。
☆イバラシティの姿ではフリージア所属3年目の職員。もともと利用児童だったのであるが、これといった就職先が見つからなかったのでそのままここの職員になった。昼間は常に眠そうにしているが、陽気な性格で児童ウケはいいらしい。
アンジニティの姿「ミリー・ブロッサム」
イバラシティの姿「咲 美里」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第三席を務める。主に植物による回復、支援、妨害を行うドルイドスタイルで戦う。好きな食べ物はよもぎ餅。
☆イバラシティの姿では花をこよなく愛する児童で、笑顔を絶やさない穏やかな性格。いわゆるロッカー児童だったのであるが、幸い泣き声に気づいた大人の人によって保護され、この施設で育った。父や母を知らないためか、職員のメンバーを親のように思っており、たまにうっかり「お母さん」と呼んだりする。
アンジニティの姿「グランバスタ・ダブルシザース」
イバラシティの姿「鋼鐡 蔵助」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第四席を務める。自己強化と回復、そして拳による格闘術に長けており、いわゆるモンクスタイルで戦う。好きな食べ物は激辛カレー。
☆イバラシティの姿では両親がヤのつく自営業の方々であり、まともな教育が出来ないと判断されてこの施設に預けられることになる。勤勉家であり、かつ努力家でもあるのだが、そこにはいじっぱりな性格が関係しているらしい。
アンジニティの姿「レシチア・マリンシンガー」
イバラシティの姿「響 美愛」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第五席を務める。音楽と氷の超能力を持ちいて戦う。スタイルとしてはバードのような戦い方と言えるであろう。好きな食べ物は鯖の南蛮漬け。
☆イバラシティの姿ではピアニストとしてある程度名をはせていたものの、「子供ともっと触れ合って音楽の楽しさを教えたい」という理由から施設の職員となる。彼女の引くピアノは歌を覚えた子供は歌いたくなり、さらに小さい子には子守歌のようにすやすやと寝るほどの技術力を持つ。図太い性格なので細かいことは気にしない。
児童養護施設「フリージア」について
創設者である施設長の方針で、家族のような暖かい場所を作ろうと思って作られた施設である。
施設長自身は「イバラシティの一般人」なのであるが、なんとなくこの世界の異変にはうっすらと気づいている様子。
この施設でどのような物語になるのか、ラクベル達の行動で変わっていくだろう。
22 / 30
73 PS
チナミ区
G-8
G-8





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 光球 | 装飾 | 30 | [効果1]器用10 [効果2]- [効果3]- |
| 5 | 治癒刀・鈴蘭 | 武器 | 33 | [効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 6 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) |
| 7 | 「マリアお手製薔薇緑茶」 | 料理 | 33 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 8 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 8 | 破壊/詠唱/火 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 武器 | 23 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練2 | エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| 練2 | ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ヒートバインド | 5 | 0 | 80 | 敵:火撃&麻痺 | |
| エアシュート | 5 | 0 | 80 | 敵:風撃&連続減 | |
| インスレイト | 5 | 0 | 60 | 味傷:次被ダメ減 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]ヒートバインド | [ 1 ]イレイザー |
| [ 1 ]サモン:ナレハテ | [ 1 ]サモン:セイレーン | [ 1 ]サモン:ガーゴイル |

PL / にゃりょん