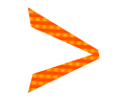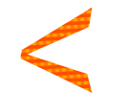<< 0:00>> 2:00




第一話 世界花とミリー・ブロッサム
「久しぶりですね、遊馬さん」
今回の話はこの僕、柚子島雄太が語り部となります。
遊馬さんとは僕の先輩で、この物語を紡ぐ人。
物語自体が彼の魔法で、ラルクベルテ・ハンドレッド、サーディラン・グッドスピード、ミリー・ブロッサム、グランバスタ・ダブルシザース、レシチア・マリンシンガー、以上五名は、彼の物語の登場人物であり、そしてそれ自体がほぼ現実の世界のように喜び、怒り、哀しみ、楽しみ、恐怖し、まるでそれぞれが個々の人であるように動く魔法。
遊馬さんは要するに、「小説を媒体に創造神になった魔法使い」と言っていいでしょう。
「ああ、久しぶりだな、柚子島…なんだかんだあって、今は営業の仕事をしているんだったか?」
そう、僕は彼が物語を紡ぎ始めてから数年。僕自身の魔法は「ゲームを作り上げること」だったのですが、その壁はあまりにも高く…
結果、自分の才能を別に活かせる、ゲームを宣伝する営業マンとして生きているのです。
「ええ、その通りです。貴方とは違って僕は途中で折れたので」
目の前にいる遊馬さんは小説家として活動をしています。売れ行きはそれほど良くない、むしろカツカツの生活のようですが、それでも楽しそうに生きているのです。
「なあに、僕の場合は君と違って、創造の魔法を使えるんだ。極端な話、住む場所と筆と原稿用紙さえあれば毎日の食事には困らない、隠遁者としてのんびりと生活が出来るわけだ」
……まったくもって、でたらめな話である。
「さて、それはそれとして、君の営業力を見込んで頼みがある」
なるほど。厄介ごとらしい。
「君に、再びネイキッドブレイブのギルドに赴き、ラルクベルテ・ハンドレッド、以下その部隊の5名に伝えてほしいことがある。
『ミリー・ブロッサムが育てているその世界花の影響で、君たちの世界が数年後に否定の世界に侵食される』と」
そして、ここ、ネイキッドブレイブの本拠地。
このギルドはギルド長であるガイアレッグ=スペランツァを頭領として、顧問医師をしている弟のガランガル=スペランツァ、副頭領で第三部隊隊長であるシシカバブ・ダイバード、そしてその下に基本的に5人小隊で構成された部隊が現在七部隊ある中小規模のギルドだ。
彼らのほとんどがP-BLOODと呼ばれる血液感染症による異能の持ち主で、特に現在の遊馬さんのお気に入りは「ラルクベルテ・ハンドレッド」という名の齢14にして二番隊隊長である少年だ。
最近の物語の主人公は、この「ラルクベルテ」なのだ。
「ん…ああ、あんたは確か柚子島だったっけか。久しぶりだな…久しぶりって言っても、お前の世界の方ではどうやら俺たちの数年ほど多く時間が経ったみたいだが」
今僕と話しているのは、ネイキッドブレイブの頭領である「ガイアレッグ=スペランツァ」。
僕の世界では数年の時が経ったものの、彼らの世界では第二部隊の面々がセルフォリーフに旅立ってからおそらく半月程度しか経っていない。
その代わり、彼ら…特にラルクベルテが率いる第二部隊は様々な異世界に旅立ち、武力と超能力を磨いているのもあり、半月程度ではとても手に入らないほどの力を伸ばしている。
「しかし、あんたが提供してくれた技術のおかげで、もう第二部隊の一人一人が既に俺を超えるレベルの戦闘力を身に着けているのだから大したものだ。
そういえば、サーディに殺されかけたことがあったが、今なら余裕で死ねそうだな、ハハハ」
そういえば、そのような過去もあった。
「さて、あんたがわざわざ来たってことは、何かあるんだろう?」
そう、ガイアレッグに促され、僕はただ、こう告げる。
「ラクベル、サーディ、ミリー、グラスタ、レシチア、以上5名に、『君たちの世界の英雄になってもらいたい』」
ガイアレッグは目を丸くしている。そりゃそうだ、言っている僕ですら「何を言っているんだ」と思ってしまう。
しかしこれが、遊馬さんに頼まれた内容だったのだ。
「正直よくわからねえ…確かにあいつらは強くなった。だが、それぞれの世界の法則を把握しなければ行った先の世界においてはただのひよっこだ。ちなみに、世界の英雄になれって言うのは、この世界でやれることなのか?」
僕は首を横に振る。
「だろうな…そもそもこの世界で危機が起こってるのであれば、俺や第一部隊の奴らが察知してるはずだ。
で、英雄になるために、あいつらに何をさせる気だ?」
さて、ここからが僕の実力の見せ所、というのだろうか。
「まず、貴方たち、というか、ミリーさんが育てている花がありましたね」
「ああ、ミリーが種を拾ってきて、育てたいって言ったから許可しているが」
「あの種が、そしてあの種が咲かせる花が問題なんです。あの花は『他の世界を侵略する世界を呼び寄せる』という異質な力があります」
ガタッ、と、ガイアレッグが椅子から立ち上がり、「なんてこった」という顔をする。
「あいつは、ミリーは。少なくともうちのギルドの中では一番花を愛する子だ。例えあの花が世界の危機を持ち込むからと言って、『枯らせ』なんて俺には言えねえ」
「分かっています。そこについては僕自身も織り込み済みです。そもそも、おそらく第二部隊の中で『枯らすべき』と判断する人はいないと思われます。ですので、第二部隊の全員を呼んでください」
ガイアレッグは通信機を使い、第二部隊のメンバーのいる部屋に緊急連絡として集合することを伝える。
程なくして、全員が集合した。
ミリーが育てている花を枯らすという選択肢は、やはり皆「反対」の意を示した。
ミリーの意見としてはこうだ。
「大切に育てた花は私にとって子供のようなものです。それを手にかけることなんてできません」
グラスタの意見はこうだった。
「その花を枯らすともっと取り返しのつかないことになる、そんな夢を見た。正直夢はそこまで信用しないのだが、俺の直感が、『この夢は正夢になる』と感じたのでな…」
レシチアとラクベルに至って言えば、上の二人ほどではないが「枯らす以外に選択肢はないのか?」という質問をしてきた。
そして、おそらくであれば一番冷徹な判断を下し、自ら汚れ仕事を引き受けるタイプであるサーディすら、思うところがあった。
「昔、俺がシノビの里にいた頃に、予知をする女がいたんだ。俺はそいつを暗殺する仕事を引き受けた。予知能力のある女だから、当然俺の行動などお見通しで、ほぼ俺が暗殺失敗、そしてそこが俺の死に時だった…はずだった。
結果がどうなったかって?無事、殺せた。そりゃそうだ、あいつ自身が『俺に殺されることを望んでいた』のだから。そしてあいつは殺される前にいくつかの言葉を残した。
『あなたはとある男を暗殺しようとして失敗する。さらに年端も行かない少年と偶然出会い、血が上ったあなたは彼とも戦闘を行い、惨敗する。
この予言は、見事に当たっていた。だよな、ガイのおっさん。ラク太郎」
ガイアレッグとラルクベルテは首を縦に振る。
「さらにだ。その後この二人の縁によって、俺はシノビの里で処刑されることなく、おっさんの計らいとラク太郎が共に戦う友として一緒にいたいと。そう言ったから、俺は生きている。
あいつの予知能力では、『そして掛け替えのない仲間を手に入れる』。そこまでも合っていたんだ」
思った以上に、サーディランはこの予知に縛られているようだ。しかし、だからこそ最後の予知が恐ろしいものであった。
「そしてミリーが育てている花。あれは世界花と言うんだが、あれは、その俺が殺した予知能力の女そのものなんだ。本人は『枯らさないとこの世界が侵食される』と告げてきた。それが最後の予言だ。
……でもな。
あの頃の俺なら躊躇なく殺せただろう。枯らせただろう。でも俺は知ってしまった。
大事な仲間ってやつを。そしてもう一度あいつに手をかけたくないという感情をだ!」
普段はちゃらけた様子の彼から放たれる言葉は、それ故に重かった。
「だから、枯らさないで済む方法があるんだろう?あんたはそのために来たんだろう!?
教えろよ!頼むから教えろよ!!俺は!!!その方法に賭けたい!!」
感情の行き場のない彼が僕の胸ぐらを掴むことに、僕は抵抗が出来なかった。
そして、すっと彼を落ち着けたのは、隊長であるラルクベルテであった。
「と、言うわけで、僕らは『枯らす』という選択肢を選ぶことはありません。ですから、サーディさんはその手を放してください」
サーディランから解放されると、僕はこう告げる。
「君たちには、アンジニティに潜り込み、そして、アンジニティ陣営の侵攻能力を削ぐために、イバラシティ側の味方になり、そこから迎撃してほしい。アンジニティ、イバラシティの説明についてはそれぞれ選んだ先で聞くことになるだろう。後、君たちは『アンジニティの侵攻者』として認識されることになる。その際、君たちは一時的に君たちではなくなる。具体的に言えば、ラクベル。君はイバラシティにおいて『百瀬楽太郎』という少年に成り代わる」
ラルクベルテはこう確認する。
「それはつまり、イバラシティの『百瀬楽太郎』を犠牲にするということですか?」
僕はこう返す。
「君たちが負ければ、そうなる。ただし、勝てば百瀬楽太郎は本来の百瀬楽太郎として生きられる」
そしてラルクベルテの反応は意外なものだった。
「なるほど、別の人としてあえて生きてみる、正直面白そうですね。勝てば実質被害もなく、そしてついでに異世界における『普通の中学生を満喫できる』……やりましょう!いえ!やらせてください!!」
僕は言葉を返そうと思ったが、もうやる気になっているのにこれ以上は無粋だろう。
そう判断して、彼らがアンジニティに潜り込む手はずを整えた。
……彼らの運命が、もうすぐ始まろうとしている。





特に何もしませんでした。








武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
メリーナ(221) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『光球』を作製してもらいました!
⇒ 光球/装飾:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
フェナ(984) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程3の武器『:Durak』を作製しました!
リラ(1264) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『光刃』を作製しました!
メリーナ(221) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『魔機《シルバーバレッド》』を作製しました!
リラ(1264) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『マジカルグラタン』をつくってもらいました!
⇒ マジカルグラタン/料理:強さ25/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
おかっきー(1452) とカードを交換しました!
顔から火を噴く (ブレイク)


イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ヒートバインド を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を習得!
ティンダー を習得!
ヘイスト を習得!
ヒートバインド を習得!
エアシュート を習得!
インスレイト を習得!
イレイザー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調26⇒25)
マリア(321) をパーティに勧誘しました!
フェナ(984) をパーティに勧誘しました!
リラ(1264) をパーティに勧誘しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



第一話 世界花とミリー・ブロッサム
「久しぶりですね、遊馬さん」
今回の話はこの僕、柚子島雄太が語り部となります。
遊馬さんとは僕の先輩で、この物語を紡ぐ人。
物語自体が彼の魔法で、ラルクベルテ・ハンドレッド、サーディラン・グッドスピード、ミリー・ブロッサム、グランバスタ・ダブルシザース、レシチア・マリンシンガー、以上五名は、彼の物語の登場人物であり、そしてそれ自体がほぼ現実の世界のように喜び、怒り、哀しみ、楽しみ、恐怖し、まるでそれぞれが個々の人であるように動く魔法。
遊馬さんは要するに、「小説を媒体に創造神になった魔法使い」と言っていいでしょう。
「ああ、久しぶりだな、柚子島…なんだかんだあって、今は営業の仕事をしているんだったか?」
そう、僕は彼が物語を紡ぎ始めてから数年。僕自身の魔法は「ゲームを作り上げること」だったのですが、その壁はあまりにも高く…
結果、自分の才能を別に活かせる、ゲームを宣伝する営業マンとして生きているのです。
「ええ、その通りです。貴方とは違って僕は途中で折れたので」
目の前にいる遊馬さんは小説家として活動をしています。売れ行きはそれほど良くない、むしろカツカツの生活のようですが、それでも楽しそうに生きているのです。
「なあに、僕の場合は君と違って、創造の魔法を使えるんだ。極端な話、住む場所と筆と原稿用紙さえあれば毎日の食事には困らない、隠遁者としてのんびりと生活が出来るわけだ」
……まったくもって、でたらめな話である。
「さて、それはそれとして、君の営業力を見込んで頼みがある」
なるほど。厄介ごとらしい。
「君に、再びネイキッドブレイブのギルドに赴き、ラルクベルテ・ハンドレッド、以下その部隊の5名に伝えてほしいことがある。
『ミリー・ブロッサムが育てているその世界花の影響で、君たちの世界が数年後に否定の世界に侵食される』と」
そして、ここ、ネイキッドブレイブの本拠地。
このギルドはギルド長であるガイアレッグ=スペランツァを頭領として、顧問医師をしている弟のガランガル=スペランツァ、副頭領で第三部隊隊長であるシシカバブ・ダイバード、そしてその下に基本的に5人小隊で構成された部隊が現在七部隊ある中小規模のギルドだ。
彼らのほとんどがP-BLOODと呼ばれる血液感染症による異能の持ち主で、特に現在の遊馬さんのお気に入りは「ラルクベルテ・ハンドレッド」という名の齢14にして二番隊隊長である少年だ。
最近の物語の主人公は、この「ラルクベルテ」なのだ。
「ん…ああ、あんたは確か柚子島だったっけか。久しぶりだな…久しぶりって言っても、お前の世界の方ではどうやら俺たちの数年ほど多く時間が経ったみたいだが」
今僕と話しているのは、ネイキッドブレイブの頭領である「ガイアレッグ=スペランツァ」。
僕の世界では数年の時が経ったものの、彼らの世界では第二部隊の面々がセルフォリーフに旅立ってからおそらく半月程度しか経っていない。
その代わり、彼ら…特にラルクベルテが率いる第二部隊は様々な異世界に旅立ち、武力と超能力を磨いているのもあり、半月程度ではとても手に入らないほどの力を伸ばしている。
「しかし、あんたが提供してくれた技術のおかげで、もう第二部隊の一人一人が既に俺を超えるレベルの戦闘力を身に着けているのだから大したものだ。
そういえば、サーディに殺されかけたことがあったが、今なら余裕で死ねそうだな、ハハハ」
そういえば、そのような過去もあった。
「さて、あんたがわざわざ来たってことは、何かあるんだろう?」
そう、ガイアレッグに促され、僕はただ、こう告げる。
「ラクベル、サーディ、ミリー、グラスタ、レシチア、以上5名に、『君たちの世界の英雄になってもらいたい』」
ガイアレッグは目を丸くしている。そりゃそうだ、言っている僕ですら「何を言っているんだ」と思ってしまう。
しかしこれが、遊馬さんに頼まれた内容だったのだ。
「正直よくわからねえ…確かにあいつらは強くなった。だが、それぞれの世界の法則を把握しなければ行った先の世界においてはただのひよっこだ。ちなみに、世界の英雄になれって言うのは、この世界でやれることなのか?」
僕は首を横に振る。
「だろうな…そもそもこの世界で危機が起こってるのであれば、俺や第一部隊の奴らが察知してるはずだ。
で、英雄になるために、あいつらに何をさせる気だ?」
さて、ここからが僕の実力の見せ所、というのだろうか。
「まず、貴方たち、というか、ミリーさんが育てている花がありましたね」
「ああ、ミリーが種を拾ってきて、育てたいって言ったから許可しているが」
「あの種が、そしてあの種が咲かせる花が問題なんです。あの花は『他の世界を侵略する世界を呼び寄せる』という異質な力があります」
ガタッ、と、ガイアレッグが椅子から立ち上がり、「なんてこった」という顔をする。
「あいつは、ミリーは。少なくともうちのギルドの中では一番花を愛する子だ。例えあの花が世界の危機を持ち込むからと言って、『枯らせ』なんて俺には言えねえ」
「分かっています。そこについては僕自身も織り込み済みです。そもそも、おそらく第二部隊の中で『枯らすべき』と判断する人はいないと思われます。ですので、第二部隊の全員を呼んでください」
ガイアレッグは通信機を使い、第二部隊のメンバーのいる部屋に緊急連絡として集合することを伝える。
程なくして、全員が集合した。
ミリーが育てている花を枯らすという選択肢は、やはり皆「反対」の意を示した。
ミリーの意見としてはこうだ。
「大切に育てた花は私にとって子供のようなものです。それを手にかけることなんてできません」
グラスタの意見はこうだった。
「その花を枯らすともっと取り返しのつかないことになる、そんな夢を見た。正直夢はそこまで信用しないのだが、俺の直感が、『この夢は正夢になる』と感じたのでな…」
レシチアとラクベルに至って言えば、上の二人ほどではないが「枯らす以外に選択肢はないのか?」という質問をしてきた。
そして、おそらくであれば一番冷徹な判断を下し、自ら汚れ仕事を引き受けるタイプであるサーディすら、思うところがあった。
「昔、俺がシノビの里にいた頃に、予知をする女がいたんだ。俺はそいつを暗殺する仕事を引き受けた。予知能力のある女だから、当然俺の行動などお見通しで、ほぼ俺が暗殺失敗、そしてそこが俺の死に時だった…はずだった。
結果がどうなったかって?無事、殺せた。そりゃそうだ、あいつ自身が『俺に殺されることを望んでいた』のだから。そしてあいつは殺される前にいくつかの言葉を残した。
『あなたはとある男を暗殺しようとして失敗する。さらに年端も行かない少年と偶然出会い、血が上ったあなたは彼とも戦闘を行い、惨敗する。
この予言は、見事に当たっていた。だよな、ガイのおっさん。ラク太郎」
ガイアレッグとラルクベルテは首を縦に振る。
「さらにだ。その後この二人の縁によって、俺はシノビの里で処刑されることなく、おっさんの計らいとラク太郎が共に戦う友として一緒にいたいと。そう言ったから、俺は生きている。
あいつの予知能力では、『そして掛け替えのない仲間を手に入れる』。そこまでも合っていたんだ」
思った以上に、サーディランはこの予知に縛られているようだ。しかし、だからこそ最後の予知が恐ろしいものであった。
「そしてミリーが育てている花。あれは世界花と言うんだが、あれは、その俺が殺した予知能力の女そのものなんだ。本人は『枯らさないとこの世界が侵食される』と告げてきた。それが最後の予言だ。
……でもな。
あの頃の俺なら躊躇なく殺せただろう。枯らせただろう。でも俺は知ってしまった。
大事な仲間ってやつを。そしてもう一度あいつに手をかけたくないという感情をだ!」
普段はちゃらけた様子の彼から放たれる言葉は、それ故に重かった。
「だから、枯らさないで済む方法があるんだろう?あんたはそのために来たんだろう!?
教えろよ!頼むから教えろよ!!俺は!!!その方法に賭けたい!!」
感情の行き場のない彼が僕の胸ぐらを掴むことに、僕は抵抗が出来なかった。
そして、すっと彼を落ち着けたのは、隊長であるラルクベルテであった。
「と、言うわけで、僕らは『枯らす』という選択肢を選ぶことはありません。ですから、サーディさんはその手を放してください」
サーディランから解放されると、僕はこう告げる。
「君たちには、アンジニティに潜り込み、そして、アンジニティ陣営の侵攻能力を削ぐために、イバラシティ側の味方になり、そこから迎撃してほしい。アンジニティ、イバラシティの説明についてはそれぞれ選んだ先で聞くことになるだろう。後、君たちは『アンジニティの侵攻者』として認識されることになる。その際、君たちは一時的に君たちではなくなる。具体的に言えば、ラクベル。君はイバラシティにおいて『百瀬楽太郎』という少年に成り代わる」
ラルクベルテはこう確認する。
「それはつまり、イバラシティの『百瀬楽太郎』を犠牲にするということですか?」
僕はこう返す。
「君たちが負ければ、そうなる。ただし、勝てば百瀬楽太郎は本来の百瀬楽太郎として生きられる」
そしてラルクベルテの反応は意外なものだった。
「なるほど、別の人としてあえて生きてみる、正直面白そうですね。勝てば実質被害もなく、そしてついでに異世界における『普通の中学生を満喫できる』……やりましょう!いえ!やらせてください!!」
僕は言葉を返そうと思ったが、もうやる気になっているのにこれ以上は無粋だろう。
そう判断して、彼らがアンジニティに潜り込む手はずを整えた。
……彼らの運命が、もうすぐ始まろうとしている。





特に何もしませんでした。







武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
メリーナ(221) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『光球』を作製してもらいました!
⇒ 光球/装飾:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
メリーナ 「取引感謝する。そちらからの依頼の品はこの通り、上々の出来さ」 |
フェナ(984) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程3の武器『:Durak』を作製しました!
リラ(1264) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『光刃』を作製しました!
メリーナ(221) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『魔機《シルバーバレッド》』を作製しました!
リラ(1264) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『マジカルグラタン』をつくってもらいました!
⇒ マジカルグラタン/料理:強さ25/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
おかっきー(1452) とカードを交換しました!
顔から火を噴く (ブレイク)


イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ヒートバインド を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を習得!
ティンダー を習得!
ヘイスト を習得!
ヒートバインド を習得!
エアシュート を習得!
インスレイト を習得!
イレイザー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調26⇒25)
マリア(321) をパーティに勧誘しました!
フェナ(984) をパーティに勧誘しました!
リラ(1264) をパーティに勧誘しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――







フリージア
|
 |
もずくパーティ
|


ENo.322
ラルクベルテ・ハンドレッド



エルタ・ブレイアからアンジニティを経てアンジニティの進行を防ぐためにイバラシティ側についた異能者達。
今回の依頼ではいつものように異世界の物資を回収する目的ではなく、エルタ・ブレイアへの進行の足掛かりになる前にイバラシティにてアンジニティ勢力を削ぐ事を目的とする。
メンバーはネイキッドブレイブに所属する第二部隊の面々であり、主に戦闘に参加するのは隊長である「ラルクベルテ・ハンドレッド」である。
以下、メンバーの紹介
アンジニティの姿「ラルクベルテ・ハンドレッド」
イバラシティの姿「百瀬 楽太郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第二部隊隊長を務める。いわゆる特攻隊長であり、前線に立って戦うことを得意とする。焔とサムライ流の剣術を得意とする。好きな女性のタイプはおねーさん。好きな食べ物飲み物は緑茶(特に玉露)。
☆イバラシティの姿では児童養護施設「フリージア」に住んでいる少年であり、母子家庭であったものの財政難の理由から母親が養えなくなり、この施設に所属した経緯を持つ。基本的に控えめな性格であるが、「美愛」以外のお姉さんに対してはデレデレである。
アンジニティの姿「サーディラン・グッドスピード」
イバラシティの姿「速水 三十郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ副隊長を務める。毒や高速起動によるサポートを得意とする、ニンジャスタイルの戦闘を好む。好きな食べ物はショートケーキ。
☆イバラシティの姿ではフリージア所属3年目の職員。もともと利用児童だったのであるが、これといった就職先が見つからなかったのでそのままここの職員になった。昼間は常に眠そうにしているが、陽気な性格で児童ウケはいいらしい。
アンジニティの姿「ミリー・ブロッサム」
イバラシティの姿「咲 美里」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第三席を務める。主に植物による回復、支援、妨害を行うドルイドスタイルで戦う。好きな食べ物はよもぎ餅。
☆イバラシティの姿では花をこよなく愛する児童で、笑顔を絶やさない穏やかな性格。いわゆるロッカー児童だったのであるが、幸い泣き声に気づいた大人の人によって保護され、この施設で育った。父や母を知らないためか、職員のメンバーを親のように思っており、たまにうっかり「お母さん」と呼んだりする。
アンジニティの姿「グランバスタ・ダブルシザース」
イバラシティの姿「鋼鐡 蔵助」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第四席を務める。自己強化と回復、そして拳による格闘術に長けており、いわゆるモンクスタイルで戦う。好きな食べ物は激辛カレー。
☆イバラシティの姿では両親がヤのつく自営業の方々であり、まともな教育が出来ないと判断されてこの施設に預けられることになる。勤勉家であり、かつ努力家でもあるのだが、そこにはいじっぱりな性格が関係しているらしい。
アンジニティの姿「レシチア・マリンシンガー」
イバラシティの姿「響 美愛」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第五席を務める。音楽と氷の超能力を持ちいて戦う。スタイルとしてはバードのような戦い方と言えるであろう。好きな食べ物は鯖の南蛮漬け。
☆イバラシティの姿ではピアニストとしてある程度名をはせていたものの、「子供ともっと触れ合って音楽の楽しさを教えたい」という理由から施設の職員となる。彼女の引くピアノは歌を覚えた子供は歌いたくなり、さらに小さい子には子守歌のようにすやすやと寝るほどの技術力を持つ。図太い性格なので細かいことは気にしない。
児童養護施設「フリージア」について
創設者である施設長の方針で、家族のような暖かい場所を作ろうと思って作られた施設である。
施設長自身は「イバラシティの一般人」なのであるが、なんとなくこの世界の異変にはうっすらと気づいている様子。
この施設でどのような物語になるのか、ラクベル達の行動で変わっていくだろう。
今回の依頼ではいつものように異世界の物資を回収する目的ではなく、エルタ・ブレイアへの進行の足掛かりになる前にイバラシティにてアンジニティ勢力を削ぐ事を目的とする。
メンバーはネイキッドブレイブに所属する第二部隊の面々であり、主に戦闘に参加するのは隊長である「ラルクベルテ・ハンドレッド」である。
以下、メンバーの紹介
アンジニティの姿「ラルクベルテ・ハンドレッド」
イバラシティの姿「百瀬 楽太郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第二部隊隊長を務める。いわゆる特攻隊長であり、前線に立って戦うことを得意とする。焔とサムライ流の剣術を得意とする。好きな女性のタイプはおねーさん。好きな食べ物飲み物は緑茶(特に玉露)。
☆イバラシティの姿では児童養護施設「フリージア」に住んでいる少年であり、母子家庭であったものの財政難の理由から母親が養えなくなり、この施設に所属した経緯を持つ。基本的に控えめな性格であるが、「美愛」以外のお姉さんに対してはデレデレである。
アンジニティの姿「サーディラン・グッドスピード」
イバラシティの姿「速水 三十郎」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ副隊長を務める。毒や高速起動によるサポートを得意とする、ニンジャスタイルの戦闘を好む。好きな食べ物はショートケーキ。
☆イバラシティの姿ではフリージア所属3年目の職員。もともと利用児童だったのであるが、これといった就職先が見つからなかったのでそのままここの職員になった。昼間は常に眠そうにしているが、陽気な性格で児童ウケはいいらしい。
アンジニティの姿「ミリー・ブロッサム」
イバラシティの姿「咲 美里」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第三席を務める。主に植物による回復、支援、妨害を行うドルイドスタイルで戦う。好きな食べ物はよもぎ餅。
☆イバラシティの姿では花をこよなく愛する児童で、笑顔を絶やさない穏やかな性格。いわゆるロッカー児童だったのであるが、幸い泣き声に気づいた大人の人によって保護され、この施設で育った。父や母を知らないためか、職員のメンバーを親のように思っており、たまにうっかり「お母さん」と呼んだりする。
アンジニティの姿「グランバスタ・ダブルシザース」
イバラシティの姿「鋼鐡 蔵助」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第四席を務める。自己強化と回復、そして拳による格闘術に長けており、いわゆるモンクスタイルで戦う。好きな食べ物は激辛カレー。
☆イバラシティの姿では両親がヤのつく自営業の方々であり、まともな教育が出来ないと判断されてこの施設に預けられることになる。勤勉家であり、かつ努力家でもあるのだが、そこにはいじっぱりな性格が関係しているらしい。
アンジニティの姿「レシチア・マリンシンガー」
イバラシティの姿「響 美愛」
★アンジニティの姿ではネイキッドブレイブ第五席を務める。音楽と氷の超能力を持ちいて戦う。スタイルとしてはバードのような戦い方と言えるであろう。好きな食べ物は鯖の南蛮漬け。
☆イバラシティの姿ではピアニストとしてある程度名をはせていたものの、「子供ともっと触れ合って音楽の楽しさを教えたい」という理由から施設の職員となる。彼女の引くピアノは歌を覚えた子供は歌いたくなり、さらに小さい子には子守歌のようにすやすやと寝るほどの技術力を持つ。図太い性格なので細かいことは気にしない。
児童養護施設「フリージア」について
創設者である施設長の方針で、家族のような暖かい場所を作ろうと思って作られた施設である。
施設長自身は「イバラシティの一般人」なのであるが、なんとなくこの世界の異変にはうっすらと気づいている様子。
この施設でどのような物語になるのか、ラクベル達の行動で変わっていくだろう。
25 / 30
50 PS
チナミ区
D-9
D-9





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 光球 | 装飾 | 30 | [効果1]器用10 [効果2]- [効果3]- |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | マジカルグラタン | 料理 | 25 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 武器 | 20 | 武器作製と、武器への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 |
| ヒートバインド | 5 | 0 | 80 | 敵:火撃&麻痺 |
| エアシュート | 5 | 0 | 80 | 敵:風撃&連続減 |
| インスレイト | 5 | 0 | 60 | 味傷:次被ダメ減 |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]ヒートバインド | [ 1 ]イレイザー |

PL / にゃりょん