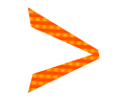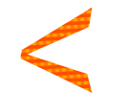<< 0:00>> 2:00




某日、ベースキャンプ
薄暗い「ベースキャンプ」の隅で、私は膝を抱えて丸くなっていた。
不気味な空の夕暮れ色、冷たい空気、土の香り、手に持ったペットボトルの水がひんやりと冷たい。
現実感の無いそれらを、五感が現実だと教えてくる。
人の声が遠くでする。私の知っている生徒たちもいる。ざわついている。
他の人から見えない場所を選んですわりこんだのは、生徒たちから距離を取りたかったから。
――大丈夫、もう少したてば笑顔になれる。
こんな経験は初めてだった。痛いわけでも苦しいわけでもなかったけれど、息が、詰まった。
しばらくしてまず思い出したのは呼吸の仕方だった。
息をすって、はく。
冷たい空気が肺へと入り、つんとした空気が、気管を通って胸へと伝わる。
さっきまで理科室にいたはずだった。
気づいたら私はここにいた。
夢とは違うのがわかった。いつもの日常に別の映画のフィルムが無理やりつなげられたかのようだ。
今日来てた服とも違う、今日の化粧の香りとも違う。
ここに来た瞬間、私の「設定」が流れ込んできた。
私は侵略者である「アンジニティ」らしい。
蚕の異形、人々に忘れ去られ、ゆがんだ現人神である「銀の巫女」
『この街はシルクの町と呼ばれることになるかもしれないぞ?』
『そうだ、神社を作ってこ巫女様をたたえよう』
『蚕の文字をとって、神社の名前に付けましょう』
そんな、人々の会話を”覚えている”。
――ちがう。
私はさっきまで理科室にいた。ハレ高の先生だ。
ちょっと前は流星を皆と見たし、こないだはバレンタインデーだった。
作ったクッキーのレシピだって覚えている。紅茶の香りがうまく出たんだった。
「こかげちゃん先生ー?どこー?」
だれかの生徒の声がして私はどきっとする。いや、そうだ、私は先生だった。
なにかが起こっているのは確かだ。
私は、異能をもっているし、どちらかといえば戦える。まずは疑問はしまっておこう。
生徒を傷つけちゃいけない。先生が生徒を守らなくっちゃいけない。
異能格闘技の話を聞いた時、私は本当は生徒に「戦う」ことを意識してほしくなかった。
ハレ高は温厚な子たちがそろっていると私は思う。
やんちゃなことはするけれど。武力を好んでする子は少ないように思う。
水を一口飲む。これだってさっき生徒にもらったものだ。
うん、ちゃんとおいしい。いつもの通りだ。
「皆、私よりしっかりしてる」
アンジニティの”設定”が本当かもしれないし、この”先生”がもしかしたら架空なのかもしれない。
世界5分間仮説を思い出した。人類は5分前に生まれたといわれてもそれは反証できないのだそうだ。どうってことはない、それだけ世界は不安定なものの上に成り立ってる。それでも、私は私だ。
「はーい。わたしはここだよ、ごめんごめん。みんな結構落ち着いてるみたいだね?びっくりだー。えらいぞー。」
うん、大丈夫。私はちゃんと笑顔だ。




ENo.87 天遣 柚依 とのやりとり

ENo.643 蚕霊いとは とのやりとり




特に何もしませんでした。








幻術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
真紅(852) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『こかげの紅茶クッキー』をつくりました!
ナイ(701) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『こかげの紅茶クッキー』をつくりました!
このみ(451) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『こかげの紅茶クッキー』をつくりました!
魔女ナヴィーニャ(326) とカードを交換しました!
占星術:使い捨てカード (ブラスト)

アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度2⇒3)
シャイン を習得!
ヒールポーション を習得!
プロテクション を習得!
プリディクション を習得!
ハルシネイト を習得!
プロビデンス を習得!
レイ を習得!
ウィルスゾーン を習得!
キュアディジーズ を習得!
エリアグラスプ を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
ナイ(701) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



某日、ベースキャンプ
薄暗い「ベースキャンプ」の隅で、私は膝を抱えて丸くなっていた。
不気味な空の夕暮れ色、冷たい空気、土の香り、手に持ったペットボトルの水がひんやりと冷たい。
現実感の無いそれらを、五感が現実だと教えてくる。
人の声が遠くでする。私の知っている生徒たちもいる。ざわついている。
他の人から見えない場所を選んですわりこんだのは、生徒たちから距離を取りたかったから。
――大丈夫、もう少したてば笑顔になれる。
こんな経験は初めてだった。痛いわけでも苦しいわけでもなかったけれど、息が、詰まった。
しばらくしてまず思い出したのは呼吸の仕方だった。
息をすって、はく。
冷たい空気が肺へと入り、つんとした空気が、気管を通って胸へと伝わる。
さっきまで理科室にいたはずだった。
気づいたら私はここにいた。
夢とは違うのがわかった。いつもの日常に別の映画のフィルムが無理やりつなげられたかのようだ。
今日来てた服とも違う、今日の化粧の香りとも違う。
ここに来た瞬間、私の「設定」が流れ込んできた。
私は侵略者である「アンジニティ」らしい。
蚕の異形、人々に忘れ去られ、ゆがんだ現人神である「銀の巫女」
『この街はシルクの町と呼ばれることになるかもしれないぞ?』
『そうだ、神社を作ってこ巫女様をたたえよう』
『蚕の文字をとって、神社の名前に付けましょう』
そんな、人々の会話を”覚えている”。
――ちがう。
私はさっきまで理科室にいた。ハレ高の先生だ。
ちょっと前は流星を皆と見たし、こないだはバレンタインデーだった。
作ったクッキーのレシピだって覚えている。紅茶の香りがうまく出たんだった。
「こかげちゃん先生ー?どこー?」
だれかの生徒の声がして私はどきっとする。いや、そうだ、私は先生だった。
なにかが起こっているのは確かだ。
私は、異能をもっているし、どちらかといえば戦える。まずは疑問はしまっておこう。
生徒を傷つけちゃいけない。先生が生徒を守らなくっちゃいけない。
異能格闘技の話を聞いた時、私は本当は生徒に「戦う」ことを意識してほしくなかった。
ハレ高は温厚な子たちがそろっていると私は思う。
やんちゃなことはするけれど。武力を好んでする子は少ないように思う。
水を一口飲む。これだってさっき生徒にもらったものだ。
うん、ちゃんとおいしい。いつもの通りだ。
「皆、私よりしっかりしてる」
アンジニティの”設定”が本当かもしれないし、この”先生”がもしかしたら架空なのかもしれない。
世界5分間仮説を思い出した。人類は5分前に生まれたといわれてもそれは反証できないのだそうだ。どうってことはない、それだけ世界は不安定なものの上に成り立ってる。それでも、私は私だ。
「はーい。わたしはここだよ、ごめんごめん。みんな結構落ち着いてるみたいだね?びっくりだー。えらいぞー。」
うん、大丈夫。私はちゃんと笑顔だ。




ENo.87 天遣 柚依 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.643 蚕霊いとは とのやりとり
| ▲ |
| ||



特に何もしませんでした。







幻術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
真紅(852) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『こかげの紅茶クッキー』をつくりました!
ナイ(701) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『こかげの紅茶クッキー』をつくりました!
このみ(451) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『こかげの紅茶クッキー』をつくりました!
魔女ナヴィーニャ(326) とカードを交換しました!
占星術:使い捨てカード (ブラスト)

アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度2⇒3)
シャイン を習得!
ヒールポーション を習得!
プロテクション を習得!
プリディクション を習得!
ハルシネイト を習得!
プロビデンス を習得!
レイ を習得!
ウィルスゾーン を習得!
キュアディジーズ を習得!
エリアグラスプ を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
ナイ(701) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――







梟の住処
|
 |
イバラシティ防衛隊(仮)
|


ENo.789
絹笠こかげ



「綺麗でしょ?植物の色をもらって、糸を染めるの」
熾盛天晴学園、5年目の理科の先生。愛称はこかげちゃん先生。
わかりやすい授業で生徒からの評判はおおむね悪くはない。150cmない身長や子供っぽさをからかわれもするが、それはそれで生徒に甘え楽している節もある。
織物師の親に影響され、草木で染めた絹糸で服や雑貨を作るのが趣味。毎日、染料の草木を探して散歩している。
実はかつてイバラシティに伝わった絹織物の神「銀の乙女」。
時とともに忘れ去られ変質し、アンジニティとして存在していた。
忘れ去られた悲しみと先生としての記憶に戸惑いながら、守るべき世界は今のイバラシティなのだと決意する。
異能は糸を操る「願絲(ねがいいと)」。ハザマでも姿は大きく変わらないが、下半身が巨大な蚕のような半虫形態になることもでき、糸の力をより高めることができる。
* よくいる場所
こかげの連絡先(ご自由に連絡ください)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2095
天景三神社跡(織物雑貨屋あり)
http://lisge.com/ib/talk.php?s=275
熾盛天晴学園
http://lisge.com/ib/talk.php?s=122
PL:タクト twitter @alenazlard
熾盛天晴学園、5年目の理科の先生。愛称はこかげちゃん先生。
わかりやすい授業で生徒からの評判はおおむね悪くはない。150cmない身長や子供っぽさをからかわれもするが、それはそれで生徒に甘え楽している節もある。
織物師の親に影響され、草木で染めた絹糸で服や雑貨を作るのが趣味。毎日、染料の草木を探して散歩している。
実はかつてイバラシティに伝わった絹織物の神「銀の乙女」。
時とともに忘れ去られ変質し、アンジニティとして存在していた。
忘れ去られた悲しみと先生としての記憶に戸惑いながら、守るべき世界は今のイバラシティなのだと決意する。
異能は糸を操る「願絲(ねがいいと)」。ハザマでも姿は大きく変わらないが、下半身が巨大な蚕のような半虫形態になることもでき、糸の力をより高めることができる。
* よくいる場所
こかげの連絡先(ご自由に連絡ください)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2095
天景三神社跡(織物雑貨屋あり)
http://lisge.com/ib/talk.php?s=275
熾盛天晴学園
http://lisge.com/ib/talk.php?s=122
PL:タクト twitter @alenazlard
25 / 30
50 PS
チナミ区
J-5
J-5





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 5 | 夢幻/精神/光 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 20 | 料理に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 |
| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) |
| ハルシネイト | 5 | 0 | 90 | 敵列:光撃&混乱 |
| プロビデンス | 5 | 0 | 120 | 味全:祝福 |
| レイ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:盲目 |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 |
| キュアディジーズ | 5 | 0 | 70 | 味肉2:HP増&肉体変調減 |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 90 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]アクアヒール |

PL / タクト