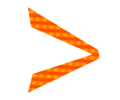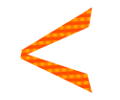<< 12:00~13:00




どうして髪を切らなくなったのか、それについて考えていた。どうして髪を切らなくなり。長すぎる髪を厭わなくなったのか、考えていた。
今更何故、と思うこともあろう。早い話が気の迷いだった。強く表に押し出された“変化する”という性質の前では、擬似的に髪を切ることは容易だった。どこで得た知識だったか、あの服装のほうが相応しいと確かに思ったのだ。
(頭が軽かった)
編んでなお引き摺る髪の毛は、そこに縫い止めるような重さが確かにあった。尻尾に引っ掛けて土汚れをつけないようにしているが、それも大して意味はなかった。髪は時に解かれ、変化して武器や防具になる。戦っている間に見目を気にするようなことがあれば、負けてしまう。一度土をつけられている以上、嫌だった。形振り構ってはいられない。形振り構ってていたら負けてしまう。それで、必死でいた。
そんな状態で、ずっと引き摺り続けていたのは何故か?というのを自問自答し続けている。あるいはそうするだけの余裕が生まれた、というのが最も正しいのかも知れない。伸ばしていた理由。それを思いつかない限り、前にも後ろにも進めない。そんな直感が働いていた。
(俺は、どこから間違い続けていた?)
長い髪を解いて編み直す時間ができると、そのたびに土埃を払い、微かな水の残渣で汚れを洗い落としている。手の代わりに“俺”を使って、刃物にも等しい爪で髪を編ませている。俺は“俺”なので、髪を引きちぎることはなかった。俺は自分の髪が、自分にとってどれくらい大切かを知っていた。
生まれ故郷での話だ。生まれ故郷というより、生まれた地方――大陸の半分全体での話だ。魔力は髪に宿り、故に必要があれば男であっても髪を伸ばす。死んだ細胞である髪を力の貯蔵庫とし、神秘の力を行使する。それがあの世界での常識だった。
誰もが大なり小なりの力を持って生まれてくる世界で、偶然弾かれてしまった。それは本当にどうしようもない遺伝要因で、閉鎖的なままならいずれ自分の故郷は滅ぶだろうとも理解した。近親間の交配による“血の濃縮”といえば聞こえがいいが、それの行き着く先は多様性の消失だ。多様性を失った集団は、簡単に滅びていく。
ある意味でその中の多様性のひとつだったと言えるのかも知れないが、あの世界では致命傷だった。例えるのなら、大気中にごく僅かに含まれている有害物質に対処できないのだ。大気汚染のように何らかの力(と呼ばれていた)が大気中に満ちていて、抵抗する力がなければ気管や肺が簡単に毒される。必然的に病弱な子として育ち、あの集落ではどこへも受け入れられない。だから外に出ていくしかなかったのだ。隣の国はその影響がほとんどないから、早々に故郷を捨てる選択をした。
実情は自分の故郷周辺が特に大気中の魔力が濃かっただけで、少し故郷から離れるだけでどうということはなくなってしまった。けれど、俺はもう戻れないと思っていた。それは思い込みだったのかもしれないが、元より戻るつもりはなかった。弱者として爪弾きにされるくらいなら、それに抗ったほうがよほど気持ちが良かった。認めないのなら抗って認めさせるしかない。抗い、戦い、徹底的に分からせる。思えば、“それしか知らなかった”のだ。
研究者というのも競争社会で、業績を残せなければ死んでいく。だから必死に食らいついていったし、いくつもの論文に名を連ねた。道は半ばで焼き払ってしまったが、若輩者にしては十分戦ったと思っていた。ところがどうだ、死んでもなお戦いは終わらないのだ。まず始めの戦いは、娘を取り戻す戦いだった。あれは、死者だからこそできた戦いだったと思う。死人に先はない。なら、全てを引き受けてしまえばいい。後のことは何も考えていなかった。
次の戦いは人探しだった。その炎を消さないため、無限に歩き続けた。その頃はまだ、見目に気を遣っていて、行く先々で怪しまれないように髪を染めたりもしていた。隠れ潜みながら歩く日々だった。その火が消えていない、ただそれだけを頼りにして、いくつもの世界を渡り歩いた。
その次の戦いは、理性との戦いだった。死という概念に対する躊躇を捨ててしまったツケが来たのだな、と思っていた。蘇ると分かっていたから、手足も頭も簡単に捨てた。全身を引き裂くはずの痛みは少しずつ精神を蝕んでいるのが手にとるように分かって、それでもやめられなかった。そうすることでしか生きていられなかった。
――その辺りで記憶が途切れている。

(整えることを、何もかも忘れている)
あとは、怒り狂って暴れ続けた記憶。罪人の掃き溜めに相応しい記録。今こそアクセスしなければならない。本を捲らなければならない。幸い、次は全てにおいて安息が約束されている。ごく僅かな安息ではある。見据えなければならないものがあると言っても、少し本を捲る時間くらいはもらってもいいだろう。
(ヒト、とは何か?)
大型の直立二足歩行を行う動物。それがヒトだ。
中枢神経系が大変発達しており、自ら考え、話すことができる。それがヒトだ。
道具を扱い、狩りなどを行い、調理して食べる。それがヒトだ。
全身が体毛に覆われていない。それがヒトだ。
独自の文化を持ち、群れる。それがヒトだ。
――では逆算して、そうなるためにはどうすればいい?
(……整えなくちゃ)
分かりやすい答えだ。自分がヒトという枠組みから外れているのなら、そこに押し込め直せばいい。暴れたところでどうにもならない。暴れたところで、自分の怪物性が前面に押し出されるだけで、何も生み出してくれやしないのだ。
考える余裕があるのなら、そうすることは簡単だ。まずこの髪の毛を切り落とそう。切り落としたあとのことは、切り落としたあとの自分が考えてくれる。この場所において、髪の毛を伸ばし続けている意味はほぼないに等しかった。時間が経つにつれて等しく皆が力をつけ、一時間経つごとに動きは軽やかになる。今重いものを捨ててしまっても、困ることは何もなかった。今までどうして、そんな簡単なことにすら気づかなかったのだろう?
手を握って開く。目を閉じて開く。どこにも違和感はなく、むしろ何かが成せそうな高揚感すら覚えた。
一歩前に進むなら、今だ。
赤いコート。その背中をじっと見つめていた。彼はいつからこの格好を良しとしていたのだろう?思えば何も知らないのだ。過去を掘り下げることは、互いに良しとしなかった。自分が最も嫌っていたから、何も。何もしなかった。語らなかった。蓋をしていた。絶対に明かしたくないと思っていたことはいくつかあり、そのうちの一つが自分の故郷のことだったが、それも自分の妄言のせいで詳らかになった。もちろん今だって言う気はない。知らない人間に妄言を晒してやるつもりはさらさらない。
やり取りに残っているログを見つめていた。手紙。書いた記憶はないが、それが必然の処理だったのだろう。気が狂っていたら絶対に破り捨てていたはずだ。こうなることを見越して残していた言伝てなど、頼ろうとは思わない。数時間前の自分だというに、おかしくて笑いが出そうだった。
自分たちは獣のように殴り合わないと答えが出せなくて、けれどそれが足掻きだというのなら、いくらだってやってやろう。いくらでも暴れて、いくらでも壊してやる。結局、自分の根っこには戦いが横たわっている。ペンは剣よりも強しとは言うが、まさにその通りだった。自分はそれ以外の戦う方法を知らず、全ては死んでから身につけたものだった。故郷に伝わる武術も、ろくに受け継ぐことができないままここまで来ているのだから、よくやれているものだと思う。
そもそも己は本として定義されているのだから、ペンの方が強く効力を示すのは普通に考えて当たり前なのだ。書き込んで定義してしまえば如何様にもなれる。それがこの世界で与えられている“変化”に落とし込まれているのだろう。
『それが答えなんだと、俺は思ってる』
答え。解答。自分もそれを導き出さなければならない。その時はもう間近に迫っている。折返しが見えてきた道筋で、いつまでも同じところに留まってはいられない。自分たちは先に進まなければならない。問いかけにどこでもないと答え続けて、行き着く先は外。そう定義している。されている。そこが最終目的地ではない。
ここも通過点でしかない。通過点で、もう少し先に向かって歩かなければならない。それこそ妄言を成立させるために、そのために歩かなければならない。
吉野暁海はそれを見るかもしれないが、自分の目で見なければ意味はない。偽りの記憶はいらない。自分が見たという記録が欲しい。――ではそのために何をしなければならないのか、戦え。戦え。抗ってみせろ。そして勝ち取ってみせるしかない。結局最期まで戦い通しになったとしても、もはやそれが自分の在り方なのだ。
「――」
何か言おうとして、結局やめた。
何か言おうとして、何の意味も成さないと思った。
行動で示したほうが早い。重苦しくまとわりついてくる思考を断ち切り、少しでも肩を軽くしてから言ったほうがずっと早い。ずるずると伸ばし続けた髪が、自分を縛る鎖になると誰が思っただろう?いつから髪を切らずにいたのだろう?べったりとこの地に縛り付けるように伸びた髪が枷になっているのなら、邪魔だ。切り落としてしまえ。必要なことなら、躊躇いはない。見目を気にすることはあっても、整えてこなかったのだから、あってもなくても大して変わりはない。ずっと昔の話、聞いた話を本から拾い出す。『ここでは髪が大事になるんだから、短くなろうと長くなろうと、適切に整えなさい』――父親の言葉。ずっと重石を乗せられたようにのしかかってくる重圧――ここから出なければならないという呵責がそれで薄まるのであれば。賭けてみる価値は十二分にあった。
戦え。足掻け。抗え。結局はそこに帰結する。
残り何時間になったか、記録しておかなければならない。パライバトルマリンがただでこちらに向かってやってくるわけがない。明瞭な思考と視界を取り戻さなければならない。
あとのことは?いいえ。何も考えていない。あとの俺が全てをまとめ、そして立ち向かってくれるだろうから。無責任に書置きだけを残すような奴なのだ、自分がそうしたって構わないバズた。
僅かな時間の間に分厚い本を開き、そして閉じた。それだけで十分だった。戦略上の思索にリソースを割かねばならないタイミングが来る。それに全力を注がなければならないが、ただ一言掛ける言葉は決まった。
本当に長々と書き残していることだな、と。自分でも思う。長々と書き連ねて、私情を極力排除して、本としての体裁を守っている。異物として排除しないようにそうしたのだろう。今なら分かる。今だからこそ分かる。理解のバトンを置かれてしまった以上、それを拾わなければならない。そうでなければ、ヒトとして続こうと抗い続けてきた己を真正面から否定することになるのだ。自分の手のひらにいるのも心底気に食わなかったが、それこそ形振り構ってはいられなかった。使えるものは何もかも利用して、戦わなければならない。
だから声をかける。
「フェデルタ」
すれ違いざまだったかもしれない。一度それぞれに分かれて。チェックポイントまで足を進めようとしていたときに言った。
「ナイフを貸して」




ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 花の護り を破棄しました。
ItemNo.8 ハードカバークロウ を破棄しました。
ItemNo.15 エナジー棒 を食べました!
体調が 2 回復!(9⇒11)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












フェデルタ(165) から ペットボトル を受け取りました。
グノウ(909) から ペットボトル を受け取りました。
変化LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
領域LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
自然LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ItemNo.3 グレイスフルブリンガー に ItemNo.21 白い塊 を付加しました!
⇒ グレイスフルブリンガー/武器:強さ140/[効果1]体力15 [効果2]閃光10 [効果3]-【射程3】
ItemNo.9 ルリユールリング に ItemNo.25 腐肉 を付加しました!
⇒ ルリユールリング/装飾:強さ170/[効果1]気合15 [効果2]耐疫15 [効果3]-
グノウ(909) の持つ ItemNo.20 曙追のツバメ に ItemNo.24 皮 を付加しました!
ここね(582) とカードを交換しました!
余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター)

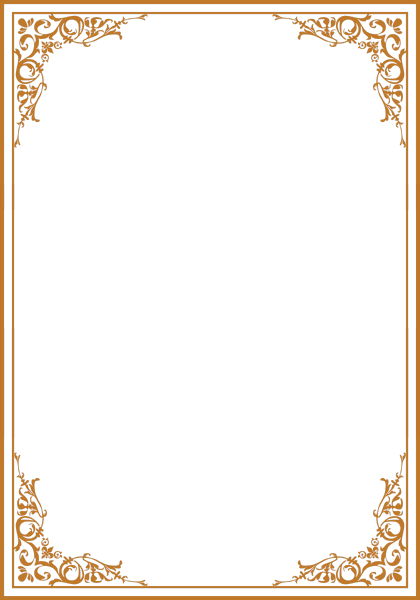
ゴッズディサイド を研究しました!(深度0⇒1)
ゴッズディサイド を研究しました!(深度1⇒2)
ゴッズディサイド を研究しました!(深度2⇒3)
レッドアゲート を習得!
ブルーム を習得!
環境変調特性 を習得!
オートヒール を習得!
グロウスルーツ を習得!
ディスターバンス を習得!
地の祝福 を習得!
イラプション を習得!
パワフルヒール を習得!
沙羅双樹 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は 葵 を入手!
スズヒコ(244) は 公孫樹 を入手!
グノウ(909) は 公孫樹 を入手!
迦楼羅(931) は 公孫樹 を入手!
フェデルタ(165) は 翠小石 を入手!
グノウ(909) は ぬめぬめ を入手!
グノウ(909) は 鱗 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 風使い が恥ずかしそうに近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ラフレシア がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
迦楼羅(931) のもとに 陸鮎 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。
迦楼羅(931) のもとに 甘酒婆 がスキップしながら近づいてきます。



フェデルタ(165) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
マガサ区 F-4(山岳)に移動!(体調11⇒10)
マガサ区 F-5(山岳)に移動!(体調10⇒9)
マガサ区 F-6(チェックポイント)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
順(39) からパーティに勧誘されました!
『カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》』へ採集に向かうことにしました!
- 順(39) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- フェデルタ(165) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- ノジコ(456) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
MISSION!!
マガサ区 F-6:チェックポイント《美術館》 が発生!
- フェデルタ(165) が経由した マガサ区 F-6:チェックポイント《美術館》
- スズヒコ(244) が経由した マガサ区 F-6:チェックポイント《美術館》





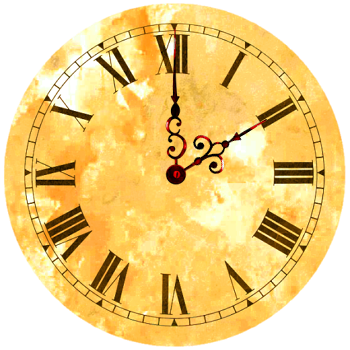
[844 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[412 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[464 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[156 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[340 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[237 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[160 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[97 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[41 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[17 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
ぽつ・・・
ぽつ・・・

サァ・・・――
雨が降る。
よく見ると雨は赤黒く、やや重い。
急いで雨宿り先を探す白南海。
しかし服は色付かず、雨は物に当たると同時に赤い煙となり消える。
地面にも雨は溜まらず、赤い薄煙がゆらゆらと舞っている。
チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)







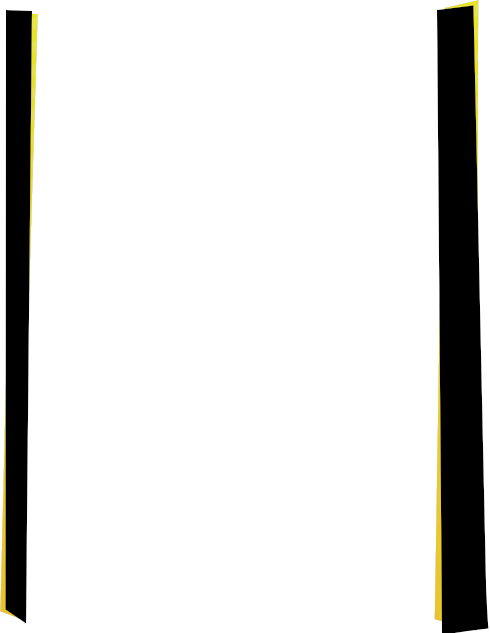
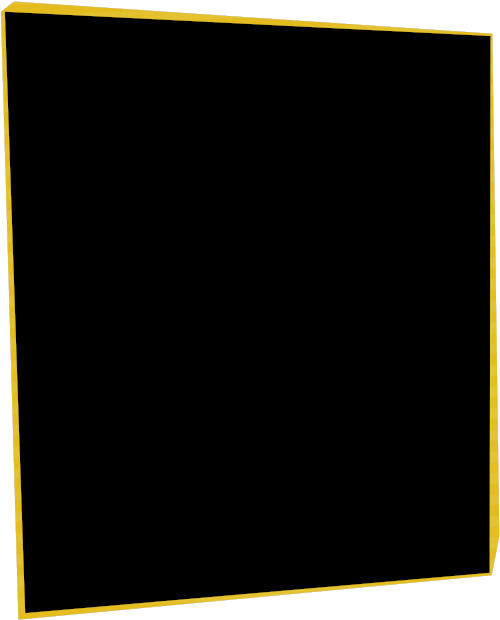





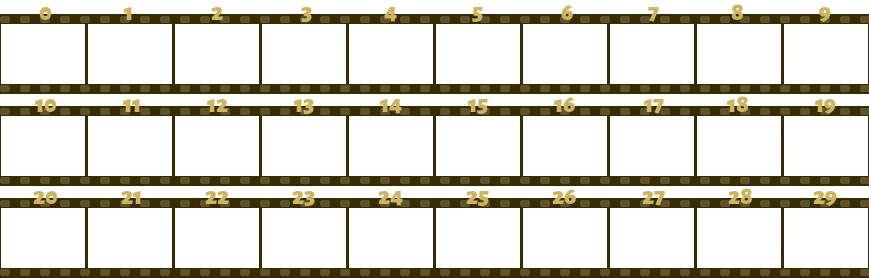









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



どうして髪を切らなくなったのか、それについて考えていた。どうして髪を切らなくなり。長すぎる髪を厭わなくなったのか、考えていた。
今更何故、と思うこともあろう。早い話が気の迷いだった。強く表に押し出された“変化する”という性質の前では、擬似的に髪を切ることは容易だった。どこで得た知識だったか、あの服装のほうが相応しいと確かに思ったのだ。
(頭が軽かった)
編んでなお引き摺る髪の毛は、そこに縫い止めるような重さが確かにあった。尻尾に引っ掛けて土汚れをつけないようにしているが、それも大して意味はなかった。髪は時に解かれ、変化して武器や防具になる。戦っている間に見目を気にするようなことがあれば、負けてしまう。一度土をつけられている以上、嫌だった。形振り構ってはいられない。形振り構ってていたら負けてしまう。それで、必死でいた。
そんな状態で、ずっと引き摺り続けていたのは何故か?というのを自問自答し続けている。あるいはそうするだけの余裕が生まれた、というのが最も正しいのかも知れない。伸ばしていた理由。それを思いつかない限り、前にも後ろにも進めない。そんな直感が働いていた。
(俺は、どこから間違い続けていた?)
長い髪を解いて編み直す時間ができると、そのたびに土埃を払い、微かな水の残渣で汚れを洗い落としている。手の代わりに“俺”を使って、刃物にも等しい爪で髪を編ませている。俺は“俺”なので、髪を引きちぎることはなかった。俺は自分の髪が、自分にとってどれくらい大切かを知っていた。
生まれ故郷での話だ。生まれ故郷というより、生まれた地方――大陸の半分全体での話だ。魔力は髪に宿り、故に必要があれば男であっても髪を伸ばす。死んだ細胞である髪を力の貯蔵庫とし、神秘の力を行使する。それがあの世界での常識だった。
誰もが大なり小なりの力を持って生まれてくる世界で、偶然弾かれてしまった。それは本当にどうしようもない遺伝要因で、閉鎖的なままならいずれ自分の故郷は滅ぶだろうとも理解した。近親間の交配による“血の濃縮”といえば聞こえがいいが、それの行き着く先は多様性の消失だ。多様性を失った集団は、簡単に滅びていく。
ある意味でその中の多様性のひとつだったと言えるのかも知れないが、あの世界では致命傷だった。例えるのなら、大気中にごく僅かに含まれている有害物質に対処できないのだ。大気汚染のように何らかの力(と呼ばれていた)が大気中に満ちていて、抵抗する力がなければ気管や肺が簡単に毒される。必然的に病弱な子として育ち、あの集落ではどこへも受け入れられない。だから外に出ていくしかなかったのだ。隣の国はその影響がほとんどないから、早々に故郷を捨てる選択をした。
実情は自分の故郷周辺が特に大気中の魔力が濃かっただけで、少し故郷から離れるだけでどうということはなくなってしまった。けれど、俺はもう戻れないと思っていた。それは思い込みだったのかもしれないが、元より戻るつもりはなかった。弱者として爪弾きにされるくらいなら、それに抗ったほうがよほど気持ちが良かった。認めないのなら抗って認めさせるしかない。抗い、戦い、徹底的に分からせる。思えば、“それしか知らなかった”のだ。
研究者というのも競争社会で、業績を残せなければ死んでいく。だから必死に食らいついていったし、いくつもの論文に名を連ねた。道は半ばで焼き払ってしまったが、若輩者にしては十分戦ったと思っていた。ところがどうだ、死んでもなお戦いは終わらないのだ。まず始めの戦いは、娘を取り戻す戦いだった。あれは、死者だからこそできた戦いだったと思う。死人に先はない。なら、全てを引き受けてしまえばいい。後のことは何も考えていなかった。
次の戦いは人探しだった。その炎を消さないため、無限に歩き続けた。その頃はまだ、見目に気を遣っていて、行く先々で怪しまれないように髪を染めたりもしていた。隠れ潜みながら歩く日々だった。その火が消えていない、ただそれだけを頼りにして、いくつもの世界を渡り歩いた。
その次の戦いは、理性との戦いだった。死という概念に対する躊躇を捨ててしまったツケが来たのだな、と思っていた。蘇ると分かっていたから、手足も頭も簡単に捨てた。全身を引き裂くはずの痛みは少しずつ精神を蝕んでいるのが手にとるように分かって、それでもやめられなかった。そうすることでしか生きていられなかった。
――その辺りで記憶が途切れている。

(整えることを、何もかも忘れている)
あとは、怒り狂って暴れ続けた記憶。罪人の掃き溜めに相応しい記録。今こそアクセスしなければならない。本を捲らなければならない。幸い、次は全てにおいて安息が約束されている。ごく僅かな安息ではある。見据えなければならないものがあると言っても、少し本を捲る時間くらいはもらってもいいだろう。
(ヒト、とは何か?)
大型の直立二足歩行を行う動物。それがヒトだ。
中枢神経系が大変発達しており、自ら考え、話すことができる。それがヒトだ。
道具を扱い、狩りなどを行い、調理して食べる。それがヒトだ。
全身が体毛に覆われていない。それがヒトだ。
独自の文化を持ち、群れる。それがヒトだ。
――では逆算して、そうなるためにはどうすればいい?
(……整えなくちゃ)
分かりやすい答えだ。自分がヒトという枠組みから外れているのなら、そこに押し込め直せばいい。暴れたところでどうにもならない。暴れたところで、自分の怪物性が前面に押し出されるだけで、何も生み出してくれやしないのだ。
考える余裕があるのなら、そうすることは簡単だ。まずこの髪の毛を切り落とそう。切り落としたあとのことは、切り落としたあとの自分が考えてくれる。この場所において、髪の毛を伸ばし続けている意味はほぼないに等しかった。時間が経つにつれて等しく皆が力をつけ、一時間経つごとに動きは軽やかになる。今重いものを捨ててしまっても、困ることは何もなかった。今までどうして、そんな簡単なことにすら気づかなかったのだろう?
手を握って開く。目を閉じて開く。どこにも違和感はなく、むしろ何かが成せそうな高揚感すら覚えた。
一歩前に進むなら、今だ。
赤いコート。その背中をじっと見つめていた。彼はいつからこの格好を良しとしていたのだろう?思えば何も知らないのだ。過去を掘り下げることは、互いに良しとしなかった。自分が最も嫌っていたから、何も。何もしなかった。語らなかった。蓋をしていた。絶対に明かしたくないと思っていたことはいくつかあり、そのうちの一つが自分の故郷のことだったが、それも自分の妄言のせいで詳らかになった。もちろん今だって言う気はない。知らない人間に妄言を晒してやるつもりはさらさらない。
やり取りに残っているログを見つめていた。手紙。書いた記憶はないが、それが必然の処理だったのだろう。気が狂っていたら絶対に破り捨てていたはずだ。こうなることを見越して残していた言伝てなど、頼ろうとは思わない。数時間前の自分だというに、おかしくて笑いが出そうだった。
自分たちは獣のように殴り合わないと答えが出せなくて、けれどそれが足掻きだというのなら、いくらだってやってやろう。いくらでも暴れて、いくらでも壊してやる。結局、自分の根っこには戦いが横たわっている。ペンは剣よりも強しとは言うが、まさにその通りだった。自分はそれ以外の戦う方法を知らず、全ては死んでから身につけたものだった。故郷に伝わる武術も、ろくに受け継ぐことができないままここまで来ているのだから、よくやれているものだと思う。
そもそも己は本として定義されているのだから、ペンの方が強く効力を示すのは普通に考えて当たり前なのだ。書き込んで定義してしまえば如何様にもなれる。それがこの世界で与えられている“変化”に落とし込まれているのだろう。
『それが答えなんだと、俺は思ってる』
答え。解答。自分もそれを導き出さなければならない。その時はもう間近に迫っている。折返しが見えてきた道筋で、いつまでも同じところに留まってはいられない。自分たちは先に進まなければならない。問いかけにどこでもないと答え続けて、行き着く先は外。そう定義している。されている。そこが最終目的地ではない。
ここも通過点でしかない。通過点で、もう少し先に向かって歩かなければならない。それこそ妄言を成立させるために、そのために歩かなければならない。
吉野暁海はそれを見るかもしれないが、自分の目で見なければ意味はない。偽りの記憶はいらない。自分が見たという記録が欲しい。――ではそのために何をしなければならないのか、戦え。戦え。抗ってみせろ。そして勝ち取ってみせるしかない。結局最期まで戦い通しになったとしても、もはやそれが自分の在り方なのだ。
「――」
何か言おうとして、結局やめた。
何か言おうとして、何の意味も成さないと思った。
行動で示したほうが早い。重苦しくまとわりついてくる思考を断ち切り、少しでも肩を軽くしてから言ったほうがずっと早い。ずるずると伸ばし続けた髪が、自分を縛る鎖になると誰が思っただろう?いつから髪を切らずにいたのだろう?べったりとこの地に縛り付けるように伸びた髪が枷になっているのなら、邪魔だ。切り落としてしまえ。必要なことなら、躊躇いはない。見目を気にすることはあっても、整えてこなかったのだから、あってもなくても大して変わりはない。ずっと昔の話、聞いた話を本から拾い出す。『ここでは髪が大事になるんだから、短くなろうと長くなろうと、適切に整えなさい』――父親の言葉。ずっと重石を乗せられたようにのしかかってくる重圧――ここから出なければならないという呵責がそれで薄まるのであれば。賭けてみる価値は十二分にあった。
戦え。足掻け。抗え。結局はそこに帰結する。
残り何時間になったか、記録しておかなければならない。パライバトルマリンがただでこちらに向かってやってくるわけがない。明瞭な思考と視界を取り戻さなければならない。
あとのことは?いいえ。何も考えていない。あとの俺が全てをまとめ、そして立ち向かってくれるだろうから。無責任に書置きだけを残すような奴なのだ、自分がそうしたって構わないバズた。
僅かな時間の間に分厚い本を開き、そして閉じた。それだけで十分だった。戦略上の思索にリソースを割かねばならないタイミングが来る。それに全力を注がなければならないが、ただ一言掛ける言葉は決まった。
本当に長々と書き残していることだな、と。自分でも思う。長々と書き連ねて、私情を極力排除して、本としての体裁を守っている。異物として排除しないようにそうしたのだろう。今なら分かる。今だからこそ分かる。理解のバトンを置かれてしまった以上、それを拾わなければならない。そうでなければ、ヒトとして続こうと抗い続けてきた己を真正面から否定することになるのだ。自分の手のひらにいるのも心底気に食わなかったが、それこそ形振り構ってはいられなかった。使えるものは何もかも利用して、戦わなければならない。
だから声をかける。
「フェデルタ」
すれ違いざまだったかもしれない。一度それぞれに分かれて。チェックポイントまで足を進めようとしていたときに言った。
「ナイフを貸して」




ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.7 花の護り を破棄しました。
ItemNo.8 ハードカバークロウ を破棄しました。
ItemNo.15 エナジー棒 を食べました!
体調が 2 回復!(9⇒11)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
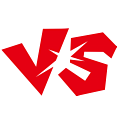 |
トレイターズ
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 19 増加!
影響力が 19 増加!



フェデルタ(165) から ペットボトル を受け取りました。
グノウ(909) から ペットボトル を受け取りました。
 |
グノウ 「ペットボトルに対してなかなかいい素材だ、と思う日がくるとは思いませんでした」 |
変化LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
領域LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
自然LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ItemNo.3 グレイスフルブリンガー に ItemNo.21 白い塊 を付加しました!
⇒ グレイスフルブリンガー/武器:強さ140/[効果1]体力15 [効果2]閃光10 [効果3]-【射程3】
ItemNo.9 ルリユールリング に ItemNo.25 腐肉 を付加しました!
⇒ ルリユールリング/装飾:強さ170/[効果1]気合15 [効果2]耐疫15 [効果3]-
グノウ(909) の持つ ItemNo.20 曙追のツバメ に ItemNo.24 皮 を付加しました!
ここね(582) とカードを交換しました!
余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター)

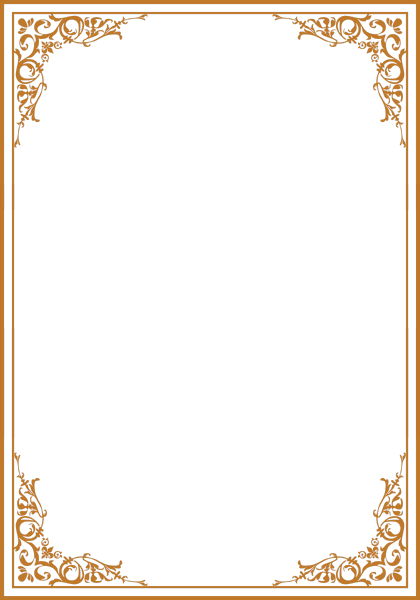
ゴッズディサイド を研究しました!(深度0⇒1)
ゴッズディサイド を研究しました!(深度1⇒2)
ゴッズディサイド を研究しました!(深度2⇒3)
レッドアゲート を習得!
ブルーム を習得!
環境変調特性 を習得!
オートヒール を習得!
グロウスルーツ を習得!
ディスターバンス を習得!
地の祝福 を習得!
イラプション を習得!
パワフルヒール を習得!
沙羅双樹 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は 葵 を入手!
スズヒコ(244) は 公孫樹 を入手!
グノウ(909) は 公孫樹 を入手!
迦楼羅(931) は 公孫樹 を入手!
フェデルタ(165) は 翠小石 を入手!
グノウ(909) は ぬめぬめ を入手!
グノウ(909) は 鱗 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 風使い が恥ずかしそうに近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ラフレシア がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
迦楼羅(931) のもとに 陸鮎 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。
迦楼羅(931) のもとに 甘酒婆 がスキップしながら近づいてきます。



フェデルタ(165) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
マガサ区 F-4(山岳)に移動!(体調11⇒10)
マガサ区 F-5(山岳)に移動!(体調10⇒9)
マガサ区 F-6(チェックポイント)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
順(39) からパーティに勧誘されました!
『カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》』へ採集に向かうことにしました!
- 順(39) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- フェデルタ(165) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
- スズヒコ(244) の選択は チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- ノジコ(456) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
MISSION!!
マガサ区 F-6:チェックポイント《美術館》 が発生!
- フェデルタ(165) が経由した マガサ区 F-6:チェックポイント《美術館》
- スズヒコ(244) が経由した マガサ区 F-6:チェックポイント《美術館》





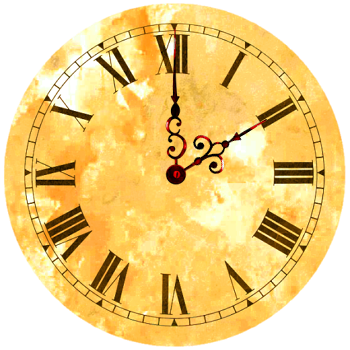
[844 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[412 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[464 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[156 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[340 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[237 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[160 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[97 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[41 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[17 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
ぽつ・・・
ぽつ・・・

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
 |
白南海 「・・・・・ん?」 |
サァ・・・――
雨が降る。
 |
白南海 「結構降ってきやがったなぁ。・・・・・って、・・・なんだこいつぁ。」 |
よく見ると雨は赤黒く、やや重い。
 |
白南海 「・・・ッだあぁ!何だこりゃ!!服が汚れちまうだろうがッ!!」 |
急いで雨宿り先を探す白南海。
しかし服は色付かず、雨は物に当たると同時に赤い煙となり消える。
地面にも雨は溜まらず、赤い薄煙がゆらゆらと舞っている。
 |
白南海 「・・・・・。・・・・・きもちわるッ」 |
チャットが閉じられる――







TeamNo.288
|
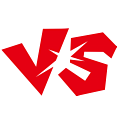 |
立ちはだかられるもの
|




マガサ区 F-6
チェックポイント《美術館》
チェックポイント。チェックポイント《美術館》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《TURTLE》
黒闇に包まれた巨大なカメのようなもの。
 |
守護者《TURTLE》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



立ちはだかられるもの
|
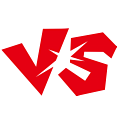 |
立ちはだかるもの
|


ENo.244
鈴のなる夢

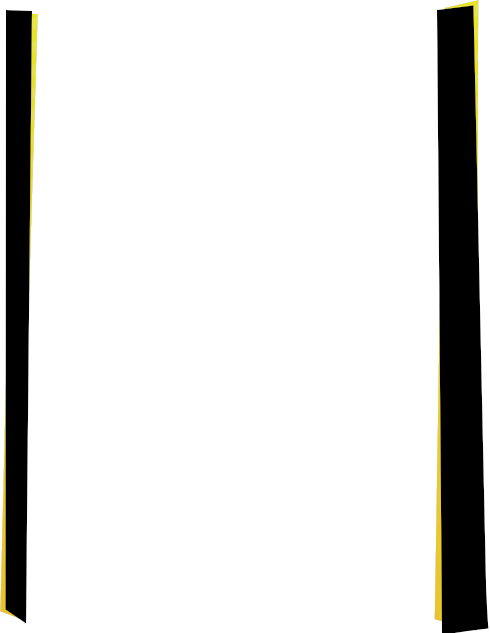
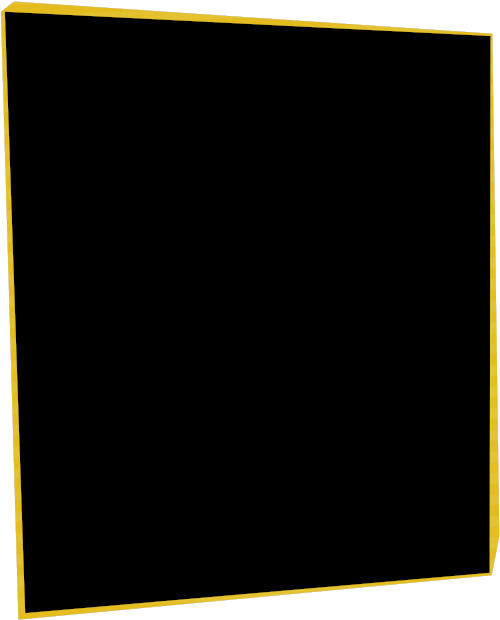
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
30 / 30
1272 PS
チナミ
D-2
D-2







痛撃友の会
4
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
3
アイコン60pxの会
2
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
3
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
3
カード報告会
5
とりあえず肉食う?
8



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | 閃光10 | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | ポプラ | 素材 | 25 | [武器]追風15(LV35)[防具]耐災25(LV35)[装飾]風纏25(LV40) | |||
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | ペットボトル | 素材 | 25 | [武器]水撃15(LV40)[防具]反水15(LV35)[装飾]活力20(LV40) | |||
| 8 | ペットボトル | 素材 | 25 | [武器]水撃15(LV40)[防具]反水15(LV35)[装飾]活力20(LV40) | |||
| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | 耐疫15 | - | |
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | 風柳10 | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | 竹 | 素材 | 30 | [武器]致命20(LV40)[防具]加速20(LV35)[装飾]応報20(LV40) | |||
| 15 | 公孫樹 | 素材 | 30 | [武器]地撃25(LV50)[防具]活力30(LV45)[装飾]快癒25(LV45) | |||
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 塩茹で枝豆 | 料理 | 100 | 復活15 | 快癒15 | 増幅15 | |
| 21 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 22 | 車前草 | 素材 | 25 | [武器]共鳴15(LV40)[防具]復活20(LV40)[装飾]治癒20(LV40) | |||
| 23 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
| 24 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 20 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 25 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 15 | 植物/鉱物/地 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 45 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 40 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 9 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 8 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練1 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| 練2 | ヘイルカード | 6 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 6 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 練3 | ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 12 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 6 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| 練2 | サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
| アブソーブ | 6 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 | |
| イラプション | 5 | 0 | 180 | 敵列:地撃+敵味全:火撃&炎上 | |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| 練3 | パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| グレイシア | 7 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 6 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 | |
| イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 | |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 | |
| 練3 | コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 練3 | 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 | |
| 治癒領域 | 7 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 | |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| 練3 |
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
|
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
| 練2 |
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 |
|
ギフトカード (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |
5 | 500 | 自:エンペラー召喚 | |
| 練3 |
余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター) |
0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]フィアスファング |
| [ 3 ]イディオータ | [ 3 ]ゴッズディサイド | [ 3 ]クリエイト:メガネ |
| [ 3 ]クリエイト:モンスター | [ 3 ]ミゼラブルメモリー | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]マナポーション |
| [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]フレイムインパクト |

PL / 紙箱みど