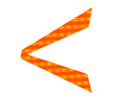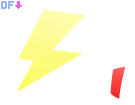<< 9:00~10:00




※各PL様に許可を頂き、テストプレイ時に存在していた施設の設定やキャラクター、ログを取り扱っております。
俺たちの街には、子どもの王国がある。
それは廃れたゲームセンターであり、ちょっとワケありの子どもたちのたまり場だ。
来る者拒まず去るもの追わず──その王国はゲームセンターの看板に紐つけて<ZOO>と呼ばれていた。
大人、学校、社会──それらの輪から逸れた子ども達の向かう先。と言っても自然発生的な集まりで、子どもの大半は素行が悪いわけでもなし、ガチの不良ってわけじゃない。要は子どもの子どもによる子どものための王国ということだ。
なんなら昔メンバーが警察と組んで事件を解決した実績があるとかで、たまに協力的関係を結んだり、未成年が夜遅くにふらふらしててもある程度目を瞑ってくれるくらいには贔屓されていた。
まあ、その事件とやらに関わった当事者はきっと活発に動く連中の話だろう。端で屯すだけだった俺達はあまり詳しくない話だ。
そう、俺や莉稲もその<ZOO>の国民だった。
王国の子どもたちはヘッドホンを着けたゾウの国章をプリントした缶バッジを【国章】として持ち歩き仲間としてつるみ合うが、特別何かを目的とした集まりではない。俺たちはその集団のゆるい居心地の良さに通いつめていた。
そこではメンバーの異能のおかげでゲーム筐体も動かすこともできたし、時々集まってゲーム大会を開くこともあった。ただエレベーター等は動いていなかったので、俺は莉稲を背負って階段昇降する度に足腰を鍛えられた──手すりに掴まり立ちして時間を掛ければ彼女一人でも不可能ではない──がその話は一旦置いておく。
集まる連中は大抵何かを抱えた奴らばかりだったが、それらを取り立てて詮索し合う必要もなかった。そこでは異能を持たない俺の疎外感も意識することはなく、干渉し過ぎない繋がりが心地良かった。
とは言えそれは、曲がりなりにもまだ“子ども”と呼べた頃の話。俺はもういい歳だし、なにより道を踏み外してしまっている。
こんな大人こそ、<ZOO>の子どもたちが忌み嫌うような悪辣な人間だ。
であれば当然、導き出される結論は一つ。大人になった俺はもう子どもの王国に入国する資格は無い。のだが。
「わーくん、上の階お願いしてもいい……?」
莉稲は二十歳に至るまでずっと、オトナコドモの面をして廃ゲームセンターに通い続けていた。子どもの王国に大学生以上のメンバーはさすがに少ない。居ない訳ではないが、国民の大多数が中高生の王国内ではすこし目立つ方だ。
けれど彼女は根気強く通い、俺は断りきれずそこに付き添い続けた。それはよく知らないガキにまで「わーくん」と呼ばれるほどに、ずるずるずるずると悪い惰性を長引かせていたのである。
そうして会うガキ共とすっぱり関係を絶たなかったのが悪かったんだろう。
俺は思いがけないところで不幸にも、王国で出会った一人の少女の秘密を俺は知ってしまった。知らないままでいれば、彼女に不自由を与えることもなかったものを。

事のきっかけは、なんとも面妖で摩訶不思議な話だ。
たまたま日の落ちた神社でタヌキとキツネ憑きの喧嘩に巻き込まれた、なんて言って一体誰が信じるだろう?
タヌキとキツネ、それぞれに縁ある生き方を背負う少年少女へ俺は争う火種を与えてしまったらしい。

あの晩の俺は頼まれた迷い猫を探すため因幡うさ子に変身し、神社を訪れていた。猫を追いかけていただけの筈なのに、俺は目を潰されかけるわ彼らの勝負に巻き込まれるわでまあ酷い目に遭うことになる。よく五体満足で帰ってこられたなと思う。
この時、口を滑らせた俺は少女に正体を見抜かれてしまっていた。それと同時だ。俺が彼女の秘密に触れたのは。

早い話、子どもの王国で出会った少女は“普通の女の子”ではなかった。ごく普通の女子高生と思った少女の正体は、彼女曰く“狐憑き”なるものであるらしい。それと関係するのか、あの夜に会った彼女の所作には普段と打って変わる鋭さが見受けられた。
片や少年の方も普通の人間ではなさそうで、俊敏な身のこなしや物騒な思考を平然とに披露する上に彼はキツネを目の敵にしていた。
俺の干渉によって(意図せず)彼らの素性が露見し、戦いの火蓋は切って落とされたのである。
ここまで語った話は自分でもまるで夢物語だと思う。それはもう互いに一歩も退かないような本気の戦い──俺にはそう取れた──で、どうも俺の常識ではついていけない話が繰り広げられていたのだ。
まだガキの内から、なんだってそんな生き方をするようになってしまったのか。そんなことを考えている内に、その場から逃げたい一心だった筈の俺は気づけば間に割って入っていた。

とはいえ、うさ子の力があっても素人は素人だ。場の流れに格好悪く翻弄されっぱなしで、俺ができた事といえばちょっと場を引っかき回しただけ。
幸いその場は何とか丸く収めることができたのだが、彼らには拗れた因縁が残ってしまった。そして俺が齎したその因縁は、恐らく因幡うさ子の正体なんかよりずっと深刻な話だったのだろう。

後日。少女は俺を<ZOO>に呼び出して、俺に顔を見せるのは最後にすると別れを告げた。
目をつけられた以上一緒にいる訳にはいかない。それが彼女の主張だった。
呑気に一件落着と安堵していた俺の愚かしさと言ったらない。彼女に取ってはそこまでする程の事だったのだ。
俺に会わないようにするということは、俺の現れる場所も避けるということで、それはつまり<ZOO>にももう来ないようにするということだ。俺との関わりを断つこと自体は全く構わないが、俺が首を突っ込んだばかりに一人の子どもの自由が削がれ、居場所が奪われてしまう。これを看過できなかった。
俺はガキ一人を普通のガキにしてやることもできないくせに、自分の後暗い秘密は隠したままで。少女に責任を取らせようとする自分に耐えられなかった。
だってそれって、なんだか凄くずるい大人じゃないか?
彼女は嘗て俺に、自分のしたいことは自分で決めろと言ったことがあった。だから、その言葉を借りて俺は自分のしたいようにしようとしたのだと思う。
やることは一つだった。
俺は自分の【国章】をその少女に譲ることにした。帰る場所が無いんじゃ、あんまりだろうって。ここで去らなくちゃいけないのは俺の方だろうって。お前が居たらいけないなんて、間違っているって。
全部全部、言うことができない代わりに投げ渡した。俺の長々とした惰性に終止符を打つつもりで。ところが。

彼女から返されたのは再会を仄めかす挨拶だった。どういうわけか、いつになるかもわからない「次」を示唆された。
明るい調子でまたねと言うものだから、もう会わないつもりでいた俺も調子を崩されて、つい笑ってしまった。
あんな挨拶されたら調子も狂う。俺は大人の顔をして、もう少しだけ動くことにした。
彼女の生き方を今更どうにかするなんて俺にはできないことだ。そんなことわかりきっている。
だとしても。仮に、もう会うことがないとしても。彼女が衝突し得る弊害を少しでも解消できるかもしれないなら、彼女に焼けるお節介がまだあるなら、それを為すのが「大人」の仕事だ。
以来、俺は手がかりも無く見つかりっこないのに、世を忍ぶタヌキ少年の姿を探してあの夜の同じ神社に通いつめるようになった。やがては、いつかの夜に出会った少年と少女がよろしくやれるような甘っちょろい展開を夢見て。
それから最後にどうか、俺のことを忘れてくれるように。
こんな話は誰も知らないし、莉稲だって何も知らない。
「わーくん、<ZOO>行こう〜。今日はお菓子持っていくんだ〜」
国章を少女に渡してからは、莉稲の<ZOO>へ誘う莉稲のことも断ることに決めた。本来、もっとずっと早く俺が出て行くべき場所だった。
「……悪い、莉稲。俺、行かねェよ。【国章】失くしちまったしさ。もうガキじゃねェんだ」
俺はもう「子ども」ではなくなったのだと、噛むように言い聞かせて俺は莉稲の誘いを拒んだ。
もう莉稲を背負って<ZOO>の階段を昇り降りできなくなるが、莉稲なら遊びに行った時にきっと誰かが力を貸してくれる筈だ。俺じゃなくても良い。
莉稲はなにかを言いかけて、けれど深くは追及しなかった。

*Special Thanks*
PC:Eno.541 Eno.789
団体設定:子どもの王国<ZOO>



ENo.153 十九号 とのやりとり

ENo.388 ユイノ とのやりとり

ENo.490 雛 とのやりとり

ENo.631 クロウラ とのやりとり

ENo.768 サキ とのやりとり

以下の相手に送信しました
















六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



サキ(768) に 200 PS 送付しました。
すごい木材(400 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
魔術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
ItemNo.23 すごい木材 から法衣『潮騒波飛沫法衣』を作製しました!
⇒ 潮騒波飛沫法衣/法衣:強さ120/[効果1]敏捷20 [効果2]- [効果3]幸運14
ケムルス(719) の持つ ItemNo.29 すごい木材 から防具『煙纏うコート』を作製しました!
サキ(768) の持つ ItemNo.19 すごい石材 から防具『神秘のパーカー』を作製しました!
ケムルス(719) により ItemNo.23 潮騒波飛沫法衣 に ItemNo.15 燐灰石 を付加してもらいました!
⇒ 潮騒波飛沫法衣/法衣:強さ120/[効果1]敏捷20 [効果2]奪命20 [効果3]幸運14
Loretta(179) とカードを交換しました!
淡雪の祝福 (クライオセラピー)
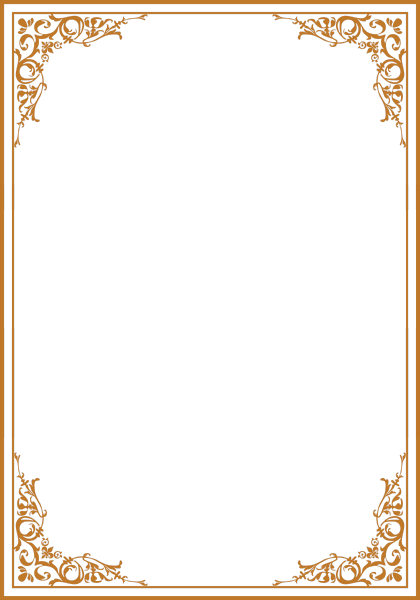
ビッグウェイブ を研究しました!(深度0⇒1)
ビッグウェイブ を研究しました!(深度1⇒2)
ビッグウェイブ を研究しました!(深度2⇒3)
ガーディアン を習得!
クリムゾンスカイ を習得!
スノードロップ を習得!
パージ を習得!
火の祝福 を習得!
セイクリットファイア を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ケムルス(719) は 不思議な食材 を入手!
ケムルス(719) は ビーフ を入手!
ケムルス(719) は 紅小石 を入手!
うさ子(266) は 紅小石 を入手!
ケムルス(719) は ねばねば を入手!
サキ(768) は ビーフ を入手!
サキ(768) は 毛 を入手!
うさ子(266) は 毛 を入手!
ケムルス(719) は 毛 を入手!
ナキドリ(516) は 毛 を入手!



次元タクシーに乗り カミセイ区 F-11:チェックポイント《商店街》 に転送されました!
カミセイ区 G-11(道路)に移動!(体調30⇒29)
カミセイ区 G-12(森林)に移動!(体調29⇒28)
カミセイ区 H-12(森林)に移動!(体調28⇒27)
カミセイ区 I-12(山岳)に移動!(体調27⇒26)
カミセイ区 J-12(山岳)に移動!(体調26⇒25)





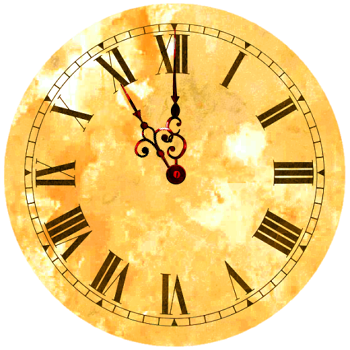
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
チャットが閉じられる――











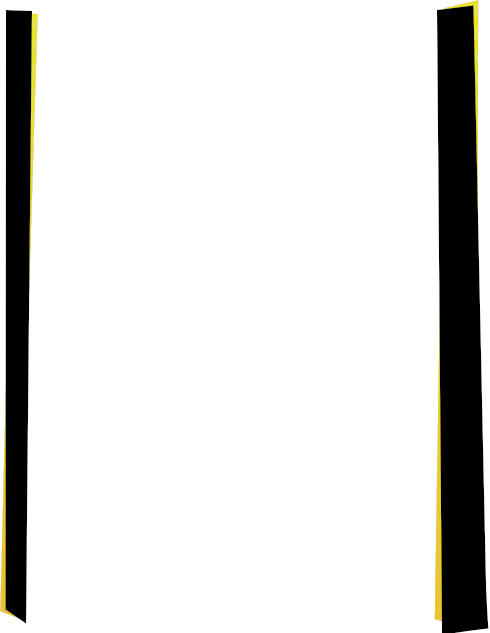
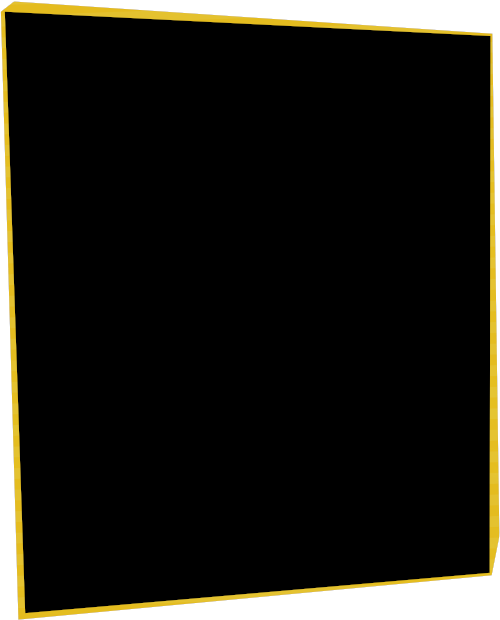





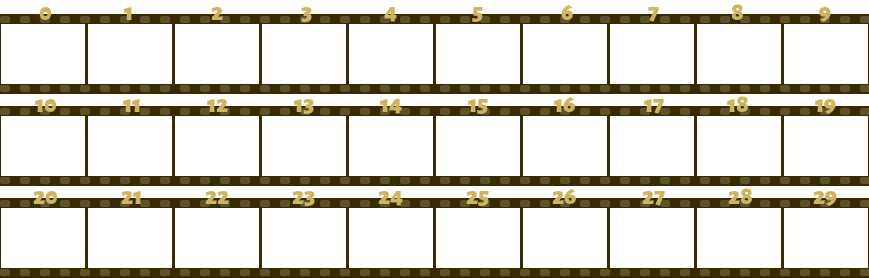







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



※各PL様に許可を頂き、テストプレイ時に存在していた施設の設定やキャラクター、ログを取り扱っております。
俺たちの街には、子どもの王国がある。
それは廃れたゲームセンターであり、ちょっとワケありの子どもたちのたまり場だ。
来る者拒まず去るもの追わず──その王国はゲームセンターの看板に紐つけて<ZOO>と呼ばれていた。
大人、学校、社会──それらの輪から逸れた子ども達の向かう先。と言っても自然発生的な集まりで、子どもの大半は素行が悪いわけでもなし、ガチの不良ってわけじゃない。要は子どもの子どもによる子どものための王国ということだ。
なんなら昔メンバーが警察と組んで事件を解決した実績があるとかで、たまに協力的関係を結んだり、未成年が夜遅くにふらふらしててもある程度目を瞑ってくれるくらいには贔屓されていた。
まあ、その事件とやらに関わった当事者はきっと活発に動く連中の話だろう。端で屯すだけだった俺達はあまり詳しくない話だ。
そう、俺や莉稲もその<ZOO>の国民だった。
王国の子どもたちはヘッドホンを着けたゾウの国章をプリントした缶バッジを【国章】として持ち歩き仲間としてつるみ合うが、特別何かを目的とした集まりではない。俺たちはその集団のゆるい居心地の良さに通いつめていた。
そこではメンバーの異能のおかげでゲーム筐体も動かすこともできたし、時々集まってゲーム大会を開くこともあった。ただエレベーター等は動いていなかったので、俺は莉稲を背負って階段昇降する度に足腰を鍛えられた──手すりに掴まり立ちして時間を掛ければ彼女一人でも不可能ではない──がその話は一旦置いておく。
集まる連中は大抵何かを抱えた奴らばかりだったが、それらを取り立てて詮索し合う必要もなかった。そこでは異能を持たない俺の疎外感も意識することはなく、干渉し過ぎない繋がりが心地良かった。
とは言えそれは、曲がりなりにもまだ“子ども”と呼べた頃の話。俺はもういい歳だし、なにより道を踏み外してしまっている。
こんな大人こそ、<ZOO>の子どもたちが忌み嫌うような悪辣な人間だ。
であれば当然、導き出される結論は一つ。大人になった俺はもう子どもの王国に入国する資格は無い。のだが。
「わーくん、上の階お願いしてもいい……?」
莉稲は二十歳に至るまでずっと、オトナコドモの面をして廃ゲームセンターに通い続けていた。子どもの王国に大学生以上のメンバーはさすがに少ない。居ない訳ではないが、国民の大多数が中高生の王国内ではすこし目立つ方だ。
けれど彼女は根気強く通い、俺は断りきれずそこに付き添い続けた。それはよく知らないガキにまで「わーくん」と呼ばれるほどに、ずるずるずるずると悪い惰性を長引かせていたのである。
そうして会うガキ共とすっぱり関係を絶たなかったのが悪かったんだろう。
俺は思いがけないところで不幸にも、王国で出会った一人の少女の秘密を俺は知ってしまった。知らないままでいれば、彼女に不自由を与えることもなかったものを。

事のきっかけは、なんとも面妖で摩訶不思議な話だ。
たまたま日の落ちた神社でタヌキとキツネ憑きの喧嘩に巻き込まれた、なんて言って一体誰が信じるだろう?
タヌキとキツネ、それぞれに縁ある生き方を背負う少年少女へ俺は争う火種を与えてしまったらしい。

あの晩の俺は頼まれた迷い猫を探すため因幡うさ子に変身し、神社を訪れていた。猫を追いかけていただけの筈なのに、俺は目を潰されかけるわ彼らの勝負に巻き込まれるわでまあ酷い目に遭うことになる。よく五体満足で帰ってこられたなと思う。
この時、口を滑らせた俺は少女に正体を見抜かれてしまっていた。それと同時だ。俺が彼女の秘密に触れたのは。

早い話、子どもの王国で出会った少女は“普通の女の子”ではなかった。ごく普通の女子高生と思った少女の正体は、彼女曰く“狐憑き”なるものであるらしい。それと関係するのか、あの夜に会った彼女の所作には普段と打って変わる鋭さが見受けられた。
片や少年の方も普通の人間ではなさそうで、俊敏な身のこなしや物騒な思考を平然とに披露する上に彼はキツネを目の敵にしていた。
俺の干渉によって(意図せず)彼らの素性が露見し、戦いの火蓋は切って落とされたのである。
ここまで語った話は自分でもまるで夢物語だと思う。それはもう互いに一歩も退かないような本気の戦い──俺にはそう取れた──で、どうも俺の常識ではついていけない話が繰り広げられていたのだ。
まだガキの内から、なんだってそんな生き方をするようになってしまったのか。そんなことを考えている内に、その場から逃げたい一心だった筈の俺は気づけば間に割って入っていた。

とはいえ、うさ子の力があっても素人は素人だ。場の流れに格好悪く翻弄されっぱなしで、俺ができた事といえばちょっと場を引っかき回しただけ。
幸いその場は何とか丸く収めることができたのだが、彼らには拗れた因縁が残ってしまった。そして俺が齎したその因縁は、恐らく因幡うさ子の正体なんかよりずっと深刻な話だったのだろう。

後日。少女は俺を<ZOO>に呼び出して、俺に顔を見せるのは最後にすると別れを告げた。
目をつけられた以上一緒にいる訳にはいかない。それが彼女の主張だった。
呑気に一件落着と安堵していた俺の愚かしさと言ったらない。彼女に取ってはそこまでする程の事だったのだ。
俺に会わないようにするということは、俺の現れる場所も避けるということで、それはつまり<ZOO>にももう来ないようにするということだ。俺との関わりを断つこと自体は全く構わないが、俺が首を突っ込んだばかりに一人の子どもの自由が削がれ、居場所が奪われてしまう。これを看過できなかった。
俺はガキ一人を普通のガキにしてやることもできないくせに、自分の後暗い秘密は隠したままで。少女に責任を取らせようとする自分に耐えられなかった。
だってそれって、なんだか凄くずるい大人じゃないか?
彼女は嘗て俺に、自分のしたいことは自分で決めろと言ったことがあった。だから、その言葉を借りて俺は自分のしたいようにしようとしたのだと思う。
やることは一つだった。
俺は自分の【国章】をその少女に譲ることにした。帰る場所が無いんじゃ、あんまりだろうって。ここで去らなくちゃいけないのは俺の方だろうって。お前が居たらいけないなんて、間違っているって。
全部全部、言うことができない代わりに投げ渡した。俺の長々とした惰性に終止符を打つつもりで。ところが。

彼女から返されたのは再会を仄めかす挨拶だった。どういうわけか、いつになるかもわからない「次」を示唆された。
明るい調子でまたねと言うものだから、もう会わないつもりでいた俺も調子を崩されて、つい笑ってしまった。
 |
卯島 「もう会わないんじゃなかったのかよ」 |
あんな挨拶されたら調子も狂う。俺は大人の顔をして、もう少しだけ動くことにした。
彼女の生き方を今更どうにかするなんて俺にはできないことだ。そんなことわかりきっている。
だとしても。仮に、もう会うことがないとしても。彼女が衝突し得る弊害を少しでも解消できるかもしれないなら、彼女に焼けるお節介がまだあるなら、それを為すのが「大人」の仕事だ。
以来、俺は手がかりも無く見つかりっこないのに、世を忍ぶタヌキ少年の姿を探してあの夜の同じ神社に通いつめるようになった。やがては、いつかの夜に出会った少年と少女がよろしくやれるような甘っちょろい展開を夢見て。
それから最後にどうか、俺のことを忘れてくれるように。
こんな話は誰も知らないし、莉稲だって何も知らない。
「わーくん、<ZOO>行こう〜。今日はお菓子持っていくんだ〜」
国章を少女に渡してからは、莉稲の<ZOO>へ誘う莉稲のことも断ることに決めた。本来、もっとずっと早く俺が出て行くべき場所だった。
「……悪い、莉稲。俺、行かねェよ。【国章】失くしちまったしさ。もうガキじゃねェんだ」
俺はもう「子ども」ではなくなったのだと、噛むように言い聞かせて俺は莉稲の誘いを拒んだ。
もう莉稲を背負って<ZOO>の階段を昇り降りできなくなるが、莉稲なら遊びに行った時にきっと誰かが力を貸してくれる筈だ。俺じゃなくても良い。
莉稲はなにかを言いかけて、けれど深くは追及しなかった。

<ZOO>の国章
ゾウを模した国章がプリントされた缶バッジ。
子どもの王国<ZOO>の一員である証。
着ける義務はないが、<ZOO>に来る多くの子どもは身に着けている。
子どもの王国<ZOO>の一員である証。
着ける義務はないが、<ZOO>に来る多くの子どもは身に着けている。
*Special Thanks*
PC:Eno.541 Eno.789
団体設定:子どもの王国<ZOO>



ENo.153 十九号 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.388 ユイノ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.490 雛 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.631 クロウラ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.768 サキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



(よいしょ、とケムルス公を下ろす) |
| うさ子 「さァて、今回この場を守っているのは……ダチョウ! 私達の勝利のためです、そこを退いて貰いましょうッ!」 |
| ナキドリ 『はい、……頑張っていきましょう! しっかりしなきゃです!』 |
 |
ケムルス 「どうなろうとオマエラに働いてもらうのは変わりないっス」 |
 |
ケムルス 「……ところで、奇妙な鳥が出てきたっスよ 燻製の失敗作っスか?」 |
 |
サキ 「ようやく一息つけるな。……ひとつ終わればまたひとつ。何が出てくることやら」 |





I'm bloody
|
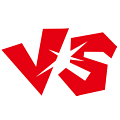 |
メガネ販売部
|



カミセイ区 F-11:チェックポイント《商店街》
メガネ販売部
|
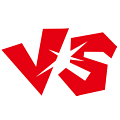 |
立ちはだかるもの
|



カミセイ区 F-11:チェックポイント《商店街》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



サキ(768) に 200 PS 送付しました。
すごい木材(400 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
魔術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
ItemNo.23 すごい木材 から法衣『潮騒波飛沫法衣』を作製しました!
⇒ 潮騒波飛沫法衣/法衣:強さ120/[効果1]敏捷20 [効果2]- [効果3]幸運14
ケムルス(719) の持つ ItemNo.29 すごい木材 から防具『煙纏うコート』を作製しました!
サキ(768) の持つ ItemNo.19 すごい石材 から防具『神秘のパーカー』を作製しました!
ケムルス(719) により ItemNo.23 潮騒波飛沫法衣 に ItemNo.15 燐灰石 を付加してもらいました!
⇒ 潮騒波飛沫法衣/法衣:強さ120/[効果1]敏捷20 [効果2]奪命20 [効果3]幸運14
Loretta(179) とカードを交換しました!
淡雪の祝福 (クライオセラピー)
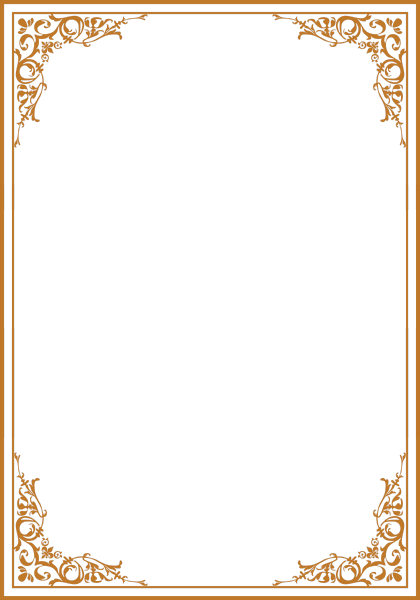
ビッグウェイブ を研究しました!(深度0⇒1)
ビッグウェイブ を研究しました!(深度1⇒2)
ビッグウェイブ を研究しました!(深度2⇒3)
ガーディアン を習得!
クリムゾンスカイ を習得!
スノードロップ を習得!
パージ を習得!
火の祝福 を習得!
セイクリットファイア を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ケムルス(719) は 不思議な食材 を入手!
ケムルス(719) は ビーフ を入手!
ケムルス(719) は 紅小石 を入手!
うさ子(266) は 紅小石 を入手!
ケムルス(719) は ねばねば を入手!
サキ(768) は ビーフ を入手!
サキ(768) は 毛 を入手!
うさ子(266) は 毛 を入手!
ケムルス(719) は 毛 を入手!
ナキドリ(516) は 毛 を入手!



次元タクシーに乗り カミセイ区 F-11:チェックポイント《商店街》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「はいお疲れさん。サービスの飴ちゃん持ってきな。」 |
カミセイ区 G-11(道路)に移動!(体調30⇒29)
カミセイ区 G-12(森林)に移動!(体調29⇒28)
カミセイ区 H-12(森林)に移動!(体調28⇒27)
カミセイ区 I-12(山岳)に移動!(体調27⇒26)
カミセイ区 J-12(山岳)に移動!(体調26⇒25)





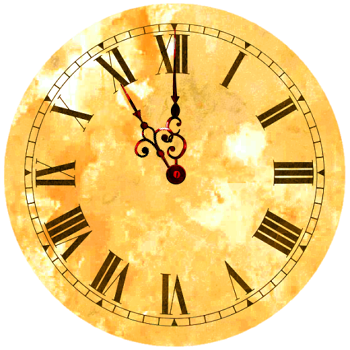
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
白南海 「・・・・・おや、どうしました?まだ恐怖心が拭えねぇんすか?」 |
 |
エディアン 「・・・何を澄ました顔で。窓に勧誘したの、貴方ですよね。」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!! 俺これ嫌っすよぉぉ!!最初は世界を救うカッケー役割とか思ってたっすけどッ!!」 |
 |
エディアン 「わかわかわかわか・・・・・何を今更なっさけない。 そんなにワカが恋しいんです?そんなに頼もしいんです?」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
 |
白南海 「それはもう!若はとんでもねぇ器の持ち主でねぇッ!!」 |
 |
エディアン 「突然元気になった・・・・・」 |
 |
白南海 「俺が頼んだラーメンに若は、若のチャーシューメンのチャーシューを1枚分けてくれたんすよッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・。・・・・他には?」 |
 |
白南海 「俺が501円のを1000円で買おうとしたとき、そっと1円足してくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・あとは?」 |
 |
白南海 「俺が車道側歩いてたら、そっと車道側と代わってくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・うーん。他の、あります?」 |
 |
白南海 「俺がアイスをシングルかダブルかで悩ん――」 |
 |
エディアン 「――あー、もういいです。いいでーす。」 |
 |
白南海 「・・・お分かりいただけましたか?若の素晴らしさ。」 |
 |
エディアン 「えぇぇーとってもーーー。」 |
 |
白南海 「いやー若の話をすると気分が良くなりますァ!」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「・・・あーうるさい。帰りますよ?帰りますからねー。」 |
チャットが閉じられる――







メガネ販売部
|
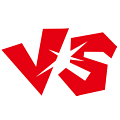 |
三位四体
|


ENo.266
卯島渉/因幡うさ子

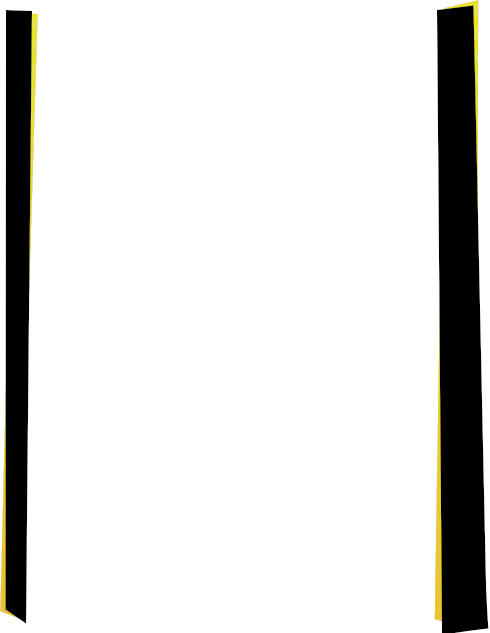
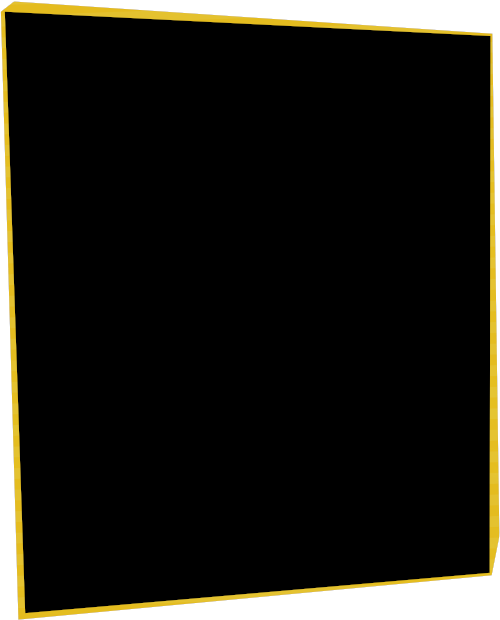
俺の名前は卯島渉。
ごく普通の詐欺師だ。厳密にはグルーブの末端。
人の善意につけ込み利益を巻き上げる──
そういう、屑みたいな普通の悪人。
だが、こんな俺にも普通じゃない点がひとつある。
それはこの街に生まれていながら異能に心当たりがないこと。
何かしら持っているとして、自覚できないほど地味な力なんだろう。
幼馴染の莉稲ですら『卵焼きを美味しく作る補正を得る』能力があるのに、俺には何もなかった。
どこぞから侵略されてるなんて報が来るまでは。
怪しいサメから守りたいものを問われ、頷いた俺は新たな力を手に入れる。
――それは、正義の兎耳少女になる力。
……なんでだ!!!!
──────────────
◆卯島渉(うしま わたる)
24歳/♂/173cm(変身時138cm)
異能がない、もしくは自覚できないような地味な能力しかないと信じて生きてきた青年。
ある日怪しいサメぬいぐるみから侵略対策の誘いを受け、うっかりうさ耳少女に変身する力を与えられてしまう。
フリーター兼詐欺師。彼には金が必要だった。
お洒落ぶった顎髭、指輪や耳飾り等、軽薄そうに自身を飾る。
幼馴染からは『わーくん』と呼ばれている。
・借り物の異能
パワフルな癒しのうさ耳少女『因幡うさ子』に変身する。
謎のサメ型ぬいぐるみ『鰐淵さん』に貸し与えられた力。
所謂魔法少女的な存在である。
◆因幡うさ子
小~中学生程度/138cm
卯島が変身した姿。兎の耳を生やした白髪の少女。
浮世離れした華美な和装を纏っている。
ついでに子供の頃の幼馴染にすこし似ている。
運動能力や聴覚が強化され、『奇跡杖・蒲ノ穂』による治癒術を扱う。が、卯島はどれも使いこなせていない。
変身中は少女キャラを全力で演じるが、異能無しとして生きてきた手前、周囲に打ち明けづらく、身バレしたくないので異能のことは専ら黙っている。
(詰めは甘いので普通に目撃したり異能による見破りは可能)
ハザマでは変身持続時間が延びたうさ子の力を駆使して戦い、気付かれない限りはやはり少女キャラを演じる。
ハザマのバレは街の自分に影響しないがメンタルの問題。
・所属『にこにこパートナーズ』(※Eno.333様発案の組織)
勧誘を受けて因幡うさ子として入った派遣会社。
兎にも角にも目立つ容姿の彼女だが、にこパ見習いとなりただの不審な少女から「(特殊な)集団の一員」として振る舞えるようになった。
なお結局は目立つ。ついでに獣扱いなので人権も消えた。
各所のご主人様の下で元気に人権を放棄し奉仕活動もとい派遣業務に赴いている。
※雇用ロールのご相談も承ります。
獣に人権は無いのでご主人様方の法では認められないような条件下での派遣も可能です。
* そのほか *
※以下、テストプレイ時の一部組織や施設等の設定を各PL様のご厚意に与り引き継いでおります。
・“子どもの王国<ZOO>”のメンバーだった。
ちょっぴり訳ありの子ども達の集まり。
拠点である廃ゲームセンターに以前は幼馴染の莉稲とよく入り浸っていた。基本的に大人は歓迎されない傾向にあり、自身の身分を省みれば子ども達と接点を持つべきではない。
大人になった彼はもう行かないつもりでいたが……?
「わーくんが居ないと上の階行けないんだもん〜」
・住居はウシ区のアパート。
確かに存在しているが管理人の異能で見つけにくい。
・特殊詐欺集団とは別に、指定暴力団の三下。
非合法の賭場で負け倒したり上司へ腰低く頭を下げている。
戦々恐々とお世話になっているが、昔ながらの義理人情仁義の世界であり、普段は半グレ集団で良いように使われる彼も案外安全でいられる場所となっている。
──────────────
◆鰐淵さん
喋って動く正体不明の鮫のぬいぐるみ。
なぜか卯島の意志を問い変身能力を与えた。
今の姿は力を貸し与えた代償と語る。
卯島の変身の管理権を握っており、ふてぶてしく彼にマウントを取ってくる。曰く「渉は下僕」。
取って付けたように「だジョー」と語尾を付ける。
アウトドア派。
──────────────
◆汐見莉稲(しおみ りいね)
20歳♀/154cm
イメージ:http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=EaquariumX&file=inbplof_kari02.jpg
卯島の住居へよく訪ねてくる幼馴染。平和を生きるひと。
生まれつき体が弱く、筋力も弱いため移動に補装具の杖や車椅子を用いる。
「卵焼きを美味しく作る」異能の持ち主。
卵焼きを作る時だけは身体能力や運勢が著しく向上し、卵焼きが美味しく出来上がるよう補正が掛かる。
物腰柔らかくのんびり屋。マイブームは喫茶店巡り。
『因幡うさ子』にすこし似ているがうさ子の正体は知らない。
カラーリングや年齢に差はあるが姉妹かな〜と言われたらまあ納得できるぐらいのレベル。
未だに<ZOO>へ通うオトナコドモ。
ハザマにおける彼女は不自由なはずの自身の脚で立ち、難なく歩行する。
・バイト先
ウシ区守護像前のたこ焼き屋(Eno.880様のお店)
卵焼き担当。
居ない時でもEno266宛にレスを頂けるとPLが気付きます。
──────────────
* 上記と無関係ジニティ *
◆宝来 千代子(たからぎ ちよこ)
17歳♀/158cm
イメージ:http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=EaquariumX&file=ibr_cycplof.png
ブランブル女学院3年2組・放送委員会・美術部。
知る人ぞ知るネットアイドルめいた活動をしている女子高生。
いつもニコニコ!『チョコちゃん』の愛称で親しまれる。
お嬢様学校に通ってはいるが普遍的な家庭育ち。
Web番組「チョコっとリポート」や「蕪もどきと遊ぼう!」の配信が主活動。なぜそんなことを……というコンテンツに取り組む胡乱な番組である。
(番組配信プレイスは下に記載)
・異能:《トリックアート・トリックスター》
少しのあいだ対象の外見情報を描き変える。変化対象や行使者である千代子が【他者】と認識するものに触れられると元に戻る。
ハザマで取り戻すその正体は暴虐の悪魔。
笑顔を剥がせぬ少女の末路。
いつもニコニコ笑顔がトレードマーク!
悪魔と呼ばれたので悪魔として生きることにした。
──────────────
* プレイス *
・自宅
http://lisge.com/ib/talk.php?p=683
・思い出(たまに鍵。パスはEno)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=295
・RP上の連絡先
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1342
・莉稲のバイト先
たこやきの店 「オバチャン」@イバラ守護像
※Eno266宛にレスを頂ければ卵焼きお作りします。
・千代子自宅
203号室@メゾンド・シャングリラ
・配信チャンネル
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3902
──────────────
*頂きものアイコン*
ありがとうございます!
ウッシッシポーズ:おジル様
やっだー☆:うみ様
デフォルメ卯島6種:ぎぃ。様
──────────────
* PL的なこと *
・置きレス進行中心です。
日によりあまり張り付けなかったりするので長引くことがあります。
また、23時過ぎると翌日以降に返す可能性が高くなります。
・大体サ●エさん時空的に生きています。
テストプレイ時の引き継ぎ具合は相手側の都合に合わせます。
PLはガバガバなので時々間違えるかもしれません。
・おおむねフリーです。
割となんでもやります。
防ぐぞ!!という時はなんやかんや防ぎます。
PCの今後に支障が出ない程度の確定ロールや既知設定はお好きに。
気になることやロールのご提案等ありましたらログイン画面の「連絡」や外部連絡ツール等からお声かけください。
逆にこちらのアクションを不快に感じられた際は、ブロックしたりやり取り自体を夢オチや無かったことにして中断するなどの対処をして頂けますと幸いです。
ごく普通の詐欺師だ。厳密にはグルーブの末端。
人の善意につけ込み利益を巻き上げる──
そういう、屑みたいな普通の悪人。
だが、こんな俺にも普通じゃない点がひとつある。
それはこの街に生まれていながら異能に心当たりがないこと。
何かしら持っているとして、自覚できないほど地味な力なんだろう。
幼馴染の莉稲ですら『卵焼きを美味しく作る補正を得る』能力があるのに、俺には何もなかった。
どこぞから侵略されてるなんて報が来るまでは。
怪しいサメから守りたいものを問われ、頷いた俺は新たな力を手に入れる。
――それは、正義の兎耳少女になる力。
……なんでだ!!!!
──────────────
◆卯島渉(うしま わたる)
24歳/♂/173cm(変身時138cm)
異能がない、もしくは自覚できないような地味な能力しかないと信じて生きてきた青年。
ある日怪しいサメぬいぐるみから侵略対策の誘いを受け、うっかりうさ耳少女に変身する力を与えられてしまう。
フリーター兼詐欺師。彼には金が必要だった。
お洒落ぶった顎髭、指輪や耳飾り等、軽薄そうに自身を飾る。
幼馴染からは『わーくん』と呼ばれている。
・借り物の異能
パワフルな癒しのうさ耳少女『因幡うさ子』に変身する。
謎のサメ型ぬいぐるみ『鰐淵さん』に貸し与えられた力。
所謂魔法少女的な存在である。
◆因幡うさ子
小~中学生程度/138cm
卯島が変身した姿。兎の耳を生やした白髪の少女。
浮世離れした華美な和装を纏っている。
ついでに子供の頃の幼馴染にすこし似ている。
運動能力や聴覚が強化され、『奇跡杖・蒲ノ穂』による治癒術を扱う。が、卯島はどれも使いこなせていない。
変身中は少女キャラを全力で演じるが、異能無しとして生きてきた手前、周囲に打ち明けづらく、身バレしたくないので異能のことは専ら黙っている。
(詰めは甘いので普通に目撃したり異能による見破りは可能)
ハザマでは変身持続時間が延びたうさ子の力を駆使して戦い、気付かれない限りはやはり少女キャラを演じる。
ハザマのバレは街の自分に影響しないがメンタルの問題。
・所属『にこにこパートナーズ』(※Eno.333様発案の組織)
勧誘を受けて因幡うさ子として入った派遣会社。
兎にも角にも目立つ容姿の彼女だが、にこパ見習いとなりただの不審な少女から「(特殊な)集団の一員」として振る舞えるようになった。
なお結局は目立つ。ついでに獣扱いなので人権も消えた。
各所のご主人様の下で元気に人権を放棄し奉仕活動もとい派遣業務に赴いている。
※雇用ロールのご相談も承ります。
獣に人権は無いのでご主人様方の法では認められないような条件下での派遣も可能です。
* そのほか *
※以下、テストプレイ時の一部組織や施設等の設定を各PL様のご厚意に与り引き継いでおります。
・“子どもの王国<ZOO>”のメンバーだった。
ちょっぴり訳ありの子ども達の集まり。
拠点である廃ゲームセンターに以前は幼馴染の莉稲とよく入り浸っていた。基本的に大人は歓迎されない傾向にあり、自身の身分を省みれば子ども達と接点を持つべきではない。
大人になった彼はもう行かないつもりでいたが……?
「わーくんが居ないと上の階行けないんだもん〜」
・住居はウシ区のアパート。
確かに存在しているが管理人の異能で見つけにくい。
・特殊詐欺集団とは別に、指定暴力団の三下。
非合法の賭場で負け倒したり上司へ腰低く頭を下げている。
戦々恐々とお世話になっているが、昔ながらの義理人情仁義の世界であり、普段は半グレ集団で良いように使われる彼も案外安全でいられる場所となっている。
──────────────
◆鰐淵さん
喋って動く正体不明の鮫のぬいぐるみ。
なぜか卯島の意志を問い変身能力を与えた。
今の姿は力を貸し与えた代償と語る。
卯島の変身の管理権を握っており、ふてぶてしく彼にマウントを取ってくる。曰く「渉は下僕」。
取って付けたように「だジョー」と語尾を付ける。
アウトドア派。
──────────────
◆汐見莉稲(しおみ りいね)
20歳♀/154cm
イメージ:http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=EaquariumX&file=inbplof_kari02.jpg
卯島の住居へよく訪ねてくる幼馴染。平和を生きるひと。
生まれつき体が弱く、筋力も弱いため移動に補装具の杖や車椅子を用いる。
「卵焼きを美味しく作る」異能の持ち主。
卵焼きを作る時だけは身体能力や運勢が著しく向上し、卵焼きが美味しく出来上がるよう補正が掛かる。
物腰柔らかくのんびり屋。マイブームは喫茶店巡り。
『因幡うさ子』にすこし似ているがうさ子の正体は知らない。
カラーリングや年齢に差はあるが姉妹かな〜と言われたらまあ納得できるぐらいのレベル。
未だに<ZOO>へ通うオトナコドモ。
ハザマにおける彼女は不自由なはずの自身の脚で立ち、難なく歩行する。
・バイト先
ウシ区守護像前のたこ焼き屋(Eno.880様のお店)
卵焼き担当。
居ない時でもEno266宛にレスを頂けるとPLが気付きます。
──────────────
* 上記と無関係ジニティ *
◆宝来 千代子(たからぎ ちよこ)
17歳♀/158cm
イメージ:http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=EaquariumX&file=ibr_cycplof.png
ブランブル女学院3年2組・放送委員会・美術部。
知る人ぞ知るネットアイドルめいた活動をしている女子高生。
いつもニコニコ!『チョコちゃん』の愛称で親しまれる。
お嬢様学校に通ってはいるが普遍的な家庭育ち。
Web番組「チョコっとリポート」や「蕪もどきと遊ぼう!」の配信が主活動。なぜそんなことを……というコンテンツに取り組む胡乱な番組である。
(番組配信プレイスは下に記載)
・異能:《トリックアート・トリックスター》
少しのあいだ対象の外見情報を描き変える。変化対象や行使者である千代子が【他者】と認識するものに触れられると元に戻る。
ハザマで取り戻すその正体は暴虐の悪魔。
笑顔を剥がせぬ少女の末路。
いつもニコニコ笑顔がトレードマーク!
悪魔と呼ばれたので悪魔として生きることにした。
──────────────
* プレイス *
・自宅
http://lisge.com/ib/talk.php?p=683
・思い出(たまに鍵。パスはEno)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=295
・RP上の連絡先
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1342
・莉稲のバイト先
たこやきの店 「オバチャン」@イバラ守護像
※Eno266宛にレスを頂ければ卵焼きお作りします。
・千代子自宅
203号室@メゾンド・シャングリラ
・配信チャンネル
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3902
──────────────
*頂きものアイコン*
ありがとうございます!
ウッシッシポーズ:おジル様
やっだー☆:うみ様
デフォルメ卯島6種:ぎぃ。様
──────────────
* PL的なこと *
・置きレス進行中心です。
日によりあまり張り付けなかったりするので長引くことがあります。
また、23時過ぎると翌日以降に返す可能性が高くなります。
・大体サ●エさん時空的に生きています。
テストプレイ時の引き継ぎ具合は相手側の都合に合わせます。
PLはガバガバなので時々間違えるかもしれません。
・おおむねフリーです。
割となんでもやります。
防ぐぞ!!という時はなんやかんや防ぎます。
PCの今後に支障が出ない程度の確定ロールや既知設定はお好きに。
気になることやロールのご提案等ありましたらログイン画面の「連絡」や外部連絡ツール等からお声かけください。
逆にこちらのアクションを不快に感じられた際は、ブロックしたりやり取り自体を夢オチや無かったことにして中断するなどの対処をして頂けますと幸いです。
25 / 30
534 PS
カミセイ区
J-12
J-12






















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 潮騒狡兎装束 | 防具 | 35 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 可愛いメガネ | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | ツナサンド | 料理 | 60 | 活力13 | 敏捷13 | 強靭13 | |
| 7 | 護りのメガネ | 装飾 | 187 | 舞護15 | 復活15 | - | |
| 8 | 島渡りわらじ | 武器 | 60 | 器用10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 花弁飾りの銀メガネ | 装飾 | 50 | 祝福10 | - | - | |
| 10 | ネジ付き蒲ノ穂 | 武器 | 97 | 貫撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 12 | ボロ毛布 | 素材 | 20 | [武器]魔力15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]防災20(LV30) | |||
| 13 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 14 | 潮風羽衣 | 防具 | 82 | 反護15 | - | - | |
| 15 | 紅小石 | 素材 | 15 | [武器]火撃15(LV30)[防具]耐火20(LV30)[装飾]舞痺20(LV35) | |||
| 16 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 17 | 里のチョコレート菓子 | 料理 | 90 | 貫撃13 | 器用13 | 深手27 | |
| 18 | 針 | 素材 | 15 | [武器]致命15(LV20)[防具]舞撃15(LV30)[装飾]器用15(LV20) | |||
| 19 | 翌檜ノ蒲ノ穂 | 武器 | 175 | 器用25 | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 20 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
| 21 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 22 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 23 | 潮騒波飛沫法衣 | 法衣 | 120 | 敏捷20 | 奪命20 | 幸運14 | |
| 24 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 25 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 26 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 27 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 28 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 25 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 70 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 6 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| 練3 | フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| サンダーショット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:光撃&麻痺 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| 練3 | フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| 練3 | レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 |
| サンダーボルト | 5 | 0 | 80 | 敵痺:光痛撃&麻痺 | |
| クリエイト:ダイナマイト | 6 | 0 | 120 | 自:道連LV増 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| ヘイルカード | 7 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| 練3 | プチメテオカード | 5 | 0 | 40 | 敵:粗雑地撃 |
| 練3 | クリエイト:グレイル | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
| ビューティーフォーム | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
| ピュリフィケーション | 5 | 0 | 50 | 敵味腐:SP増+腐食状態なら、精確光撃&腐食を猛毒化 | |
| レイ | 5 | 0 | 30 | 敵貫:盲目 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| カタラクト | 7 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| 練3 | マインドボム | 5 | 1 | 100 | 敵:SP火撃 |
| クリエイト:ファイアウェポン | 5 | 0 | 200 | 味:炎上LV・反火LV増 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| ラディウス | 5 | 0 | 150 | 敵全:光撃+自:HP増&祝福消費で次与ダメ増 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |
| サンダーフォーム | 5 | 0 | 140 | 自:光特性・麻痺LV増 | |
| パージ | 5 | 0 | 120 | 敵列:粗雑SP光撃 | |
| ライトジャベリン | 5 | 0 | 150 | 敵貫3:光痛撃 | |
| セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 | |
| アイシクルランス | 6 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| カレイドスコープ | 5 | 0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
| アイスエイジ | 5 | 0 | 300 | 敵:X連水領撃 ※X=対象の弱化ターン効果の数+1 | |
| コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| アルシナシオン | 5 | 2 | 300 | 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 | |
| オラシオン | 5 | 0 | 160 | 味傷:HP増&祝福消費でHP増&祝福消費でHP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 練3 | 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 光の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
| 泡沫 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP減+AG・LK・領域値[水]増 | |
| 法衣作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で防具「法衣」を選択できる。法衣は効果3に幸運LVが付加される。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ヒール (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
天球儀 (リフレクション) |
0 | 50 | 自:反射 | |
|
『行進曲:錨を上げて』 (ヴィガラスチャージ) |
0 | 100 | 味全:次与ダメ増 | |
| 練3 |
大地の怒り (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
| 練3 |
式符【椿】 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
|
メルティ・ウェブ (アイシング) |
0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 | |
| 練3 |
Skyfall (チェインリアクト) |
1 | 150 | 敵:5連鎖撃 |
| 練3 |
フォックスコーヒー(2倍濃縮) (リザレクション) |
0 | 150 | 味傷:HP増+瀕死ならHP増 |
|
夜霧地下科学研究所 (ウィルスゾーン) |
0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
|
凄いやばい竹 (インファイト) |
0 | 50 | 敵:攻撃&隊列1なら更に4連撃 | |
|
淡雪の祝福 (クライオセラピー) |
0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒドラジン | [ 3 ]グランドクラッシャー | [ 3 ]ハードブレイク |
| [ 3 ]デッドライン | [ 2 ]ダウンフォール | [ 3 ]イグニス |
| [ 3 ]ボンバルディエ | [ 3 ]ジャックポット | [ 2 ]クリエイト:グレイル |
| [ 2 ]イレイザー | [ 2 ]プチメテオカード | [ 3 ]ストーンブラスト |
| [ 3 ]ビッグウェイブ |

PL / 希月スズ