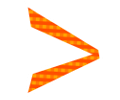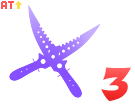<< 5:00~6:00




―――第3話「耳尻尾のルーツ」
練習試合の戦闘の合間、移動の隙間時間を見繕って鈴は得物の手入れをしていた。
己自身ともいえる大妖刀「大神成」、それと同時に振るう銘の無い他の五刀。
厳密にいえば手入れが必要なのは無銘の五刀。汚れを拭い、打粉で拭い研ぎ、錆止めの油を塗る。
今となっては極稀だが、欠けが大きければ砥石で研磨する。
僅かな鞘走りの差が勝敗を分けることもあるし、代わりの得物が手に入るかもわからない今は長持ちするよう丁寧に扱うべきだ。
しばしの後、5本の手入れを終えて愛刀の手入れに取り掛かる。
手入れといっても多少拭うだけだ。
神刀と化したこの刀は己の本体であり、生半可なことでは傷も入らない。
そう、刀身を拭うこれは、人でいうシャワーを浴びるようなものだ。
なんとなくすっきりした気分になって眼前に刃を立てる。
透き通るような清冽な輝きを宿すその刀身は、朝焼けの光を受けてきらりと瞬いた。
目を閉じ、己のうちに思いを馳せる。
イバラシティに生きる鈴とアンジニティを放浪した鈴、そしてこの神刀とうちに封じられたモノ。
全てが混じったこの身体に私が意識を残しているのは奇跡なのかもしれない。
一度目の異変は、徒党を組んだならず者共を追い払った時だった。
あの時は、まだ私は甘かったし、人を斬ることに慣れていなかった。
全身を打たれ斬られながらも戦い続け、最後に立っていたのは私だけだった。
全身が傷だらけだし、左腕はちぎれかけ。失血して頭が働かなくて、動けなくなったときは「あ、ここで死ぬのか。」そう思った。
よしんば助かったとしてももう戦えないのだろうな。みんな、もう守れなくてごめんね。遠く暗くなっていく視界の中、謝りながらふっつりと意識は途切れた
けれど―――死ななかった。起きた時はもうほとんどの傷が治っていて。
その時はどうして治ってるのかわからなくて、通りすがりの誰かが治してくれたのだろうか、なんてありもしないことを考えていた。
―――それが、私の愛刀「大神成」のおかげだということが分かったのは4度目の異変からしばらく経った後だった。
そう、あれから3度私は死んだ。正しくは、死に掛けて気づけば治っていた。
それもこれもこの刀のおかげで助かっていて、この刀が無ければ私は死んでいたはずだ。
私の扱える力が強くなっている。身体能力も、刀が持っているらしい雷を操る力も、素直に扱える。
刀もいつも以上に手に馴染む。武器の扱いに習熟した達人が到達するような身体と一体となって手の延長となったような感覚。それが以前とは比べ物にならないほど強くなっていた。
それはそうだ。当たり前のこと。私と刀は文字通り混然一体となり始めていたのだから。
夢を見た。
それは獣の夢。
山に住むその獣は、生まれた時から雷を起こす権能を持っていた。
念ずれば身から稲妻が迸り、高らかに遠吠えをすればたちまち空に暗雲が立ち込め雷が降り落ちた。
意のままに降り注ぐ落雷は害獣や侵略者を打ち倒し、畑には豊穣をもたらした。
そんな、獣はいつしか近隣の人里で“神狼”として祀られるようになった。
神狼は供えられた食べ物で腹を満たし、信仰で力を得た。そのお礼に、雷を程よく呼び、害獣や化生の類が現れればそれを退治することに一層励んだ。
それでも、神狼にどうにもできないことはあった。病だ。
周辺の村落で病が流行った。流行りに流行ったその病にかかった人間は、床に臥せってたちまち死んでしまう。
数か月のうちにほとんどの人間が死んでしまった。運良く生き延びた人間はこんな有り様では生活出来ぬとどこか遠くへ行ってしまった。
神狼は置いて行かれた。病が理解できない神狼は捨てられた。と理解した。
それでも、死んだ人間は己を捨てなかった人間である。その程度は理解できた。
撃ち捨てられた人里に転がる己を崇めていた人間だったものを一口食べては順番に埋葬し、いつしかその身には死臭が染みついた。
裏切られたと思った神狼は、恨みを募らせ遠く高らかに吠え上げた。
それは完全に八つ当たりであったが、報復とばかりに付近を通りかかる人間を噛み殺し、人の味を覚えた。
いつしかその山の周辺は魔狼の棲む山として方々に恐れられた。
そして当然、人を喰らう魔物として名の知れた獣は、退治される。
獣を調伏するためだけに打たれた神刀によって斬られたのだ。
ただ、一時は神狼とされた格の高い獣である。斬られるだけでは死ななかった。
その神刀のうちに封じられたのだった。
そこからの獣の記憶はない。
これが愛刀のルーツ。そして、今の私のルーツの一つ。
肉体を失い、神刀の中で長い年月をかけて封じられた神狼は、いまや純全たる“力”としてある。
はっきりとした意識はなく、刀として使い手を選ぶだけであった。
あの日、蔵を探検して吸い込まれるようにこの刀を発掘して手にした私。
刀に呼ばれたのか。お互いに引き合ったのか。
神狼と刀は今や力と記憶のみなっているから、真実はわからない。
ただ一つ言えることは……私とこの刀が、正確に言えばこの刀のうちに封じられた神狼と異常に相性が良かったということだけだ。
記憶を辿っても、この刀を手にした幾人もの剣士の誰も、耳や尻尾が生えた試しはない。
刀が持ち手以外を強く拒絶したこともないし、常に携えていなければならなかったこともない。
そう、私だけだった。
今度こそアンジニティの侵攻を、ワールドスワップを……止める。
使えるものは使う。いつまでも戦えるこの身はある意味で好都合ではある。
阻止が出来るなら私はもう死んでいるのだし、いつでもこの身を投げ捨てよう。
いつか、それが必要になるならば。
ふぅーーーー。
大きく息をついて閉じていた目を開く。
愛刀を鞘に納め、立ち上がる。
休憩は終わり。次は東の方へ行くと聞く。
昇った朝日の中で、仲間の影が白む景色に目を細めた。
――――――先へ進もう。



ENo.24 バケツヘルム卿 とのやりとり

ENo.207 ランノ とのやりとり

ENo.420 リンカ とのやりとり

ENo.431 ミハクサマ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ミハクサマ(431) から 爪 を手渡しされました。
バケツヘルム卿(24) に ItemNo.9 藍鉄鉱 を手渡ししました。
ItemNo.12 謎の焼肉 を食べました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 増幅10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












ミハクサマ(431) から 何か固い物体 を受け取りました。
ミハクサマ(431) から 牙 を受け取りました。
変化LV を 20 DOWN。(LV20⇒0、+20CP、-20FP)
武術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
解析LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
武器LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ItemNo.6 何か固い物体 から射程3の武器『舞刀飛刃』を作製しました!
⇒ 舞刀飛刃/武器:強さ90/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
わこちゃん(1171) の持つ ItemNo.11 平石 から射程1の武器『果物ナイフ』を作製しました!
リンカ(420) の持つ ItemNo.10 牙 から射程3の武器『リンカイザーアームⅣ』を作製しました!
ランノ(207) により ItemNo.13 お魚 から料理『お魚のホイル焼き』をつくってもらいました!
⇒ お魚のホイル焼き/料理:強さ60/[効果1]活力10 [効果2]敏捷10 [効果3]強靭10
ミーニャ(430) により ItemNo.14 お野菜 から料理『大根の煮物』をつくってもらいました!
⇒ 技巧料理![ 1 1 1 = 3 ]大失敗!何だこれは!!!!料理の効果1~3が消失!
⇒ 大根の煮物/料理:強さ55/[効果1]- [効果2]- [効果3]-
リンカ(420) により ItemNo.6 舞刀飛刃 に ItemNo.16 爪 を付加してもらいました!
⇒ 舞刀飛刃/武器:強さ90/[効果1]攻撃10 [効果2]攻撃10 [効果3]-【射程3】
カザミさん(50) とカードを交換しました!
碧の疾風 (スカイディバイド)

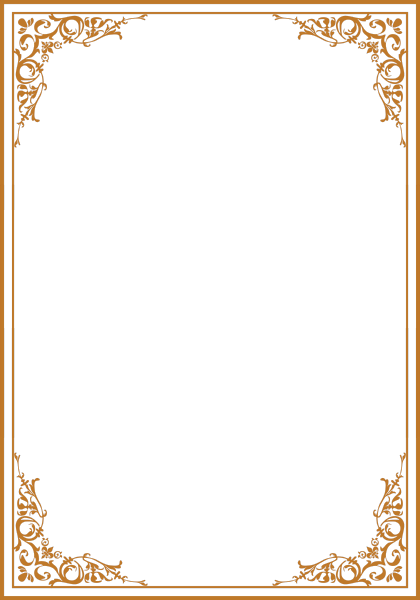
グランドクラッシャー を研究しました!(深度0⇒1)
インフェクシャスキュア を研究しました!(深度0⇒1)
ナース を研究しました!(深度0⇒1)
プリディクション を習得!
フィジカルブースター を習得!
キャプチャートラップ を習得!
ブロック を習得!
スピアトラップ を習得!
フェイタルポイント を習得!
ジャックポット を習得!
リンクブレイク を習得!
阿修羅 を習得!
応酬 を習得!
死線 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



バケツヘルム卿(24) は 山査子 を入手!
リンカ(420) は ラベンダー を入手!
ミハクサマ(431) は ラベンダー を入手!
鈴(1154) は 大蒜 を入手!
ミハクサマ(431) は パンの耳 を入手!
鈴(1154) は 剛毛 を入手!
ミハクサマ(431) は 韮 を入手!
バケツヘルム卿(24) は 韮 を入手!
リンカ(420) は 美味しい草 を入手!



バケツヘルム卿(24) に移動を委ねました。
ヒノデ区 E-11(草原)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 F-11(草原)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 G-11(草原)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 H-11(道路)に移動!(体調18⇒17)
ヒノデ区 I-11(道路)に移動!(体調17⇒16)





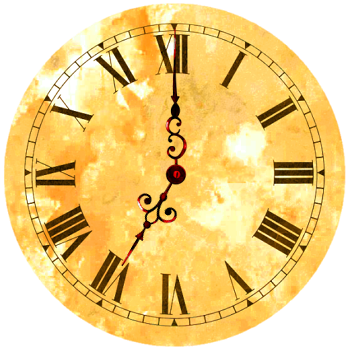
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映し出されるふたり。
チャットから消えるふたり。
チャットが閉じられる――














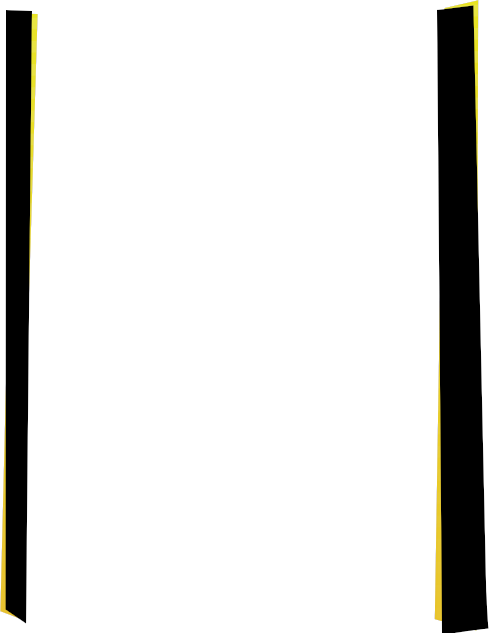
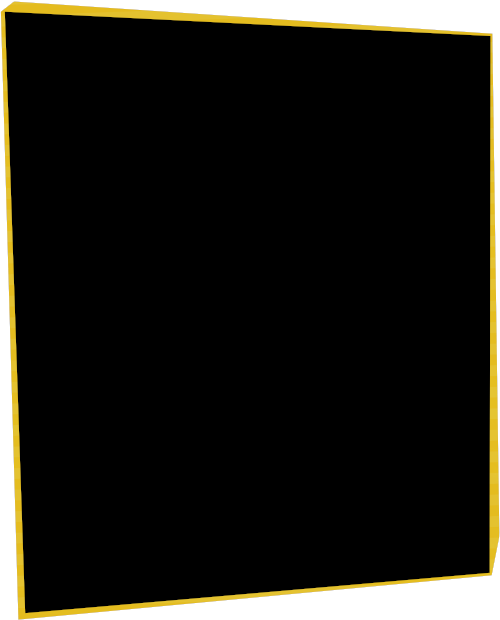





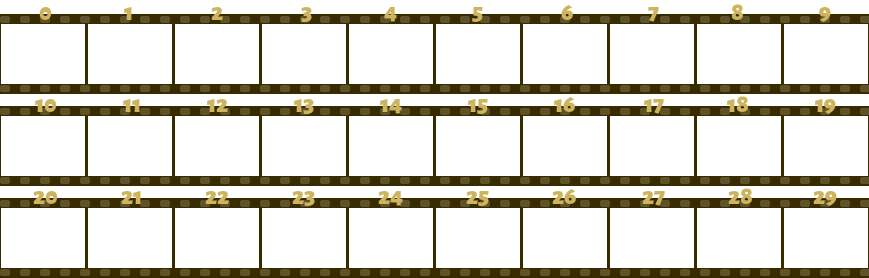





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



―――第3話「耳尻尾のルーツ」
練習試合の戦闘の合間、移動の隙間時間を見繕って鈴は得物の手入れをしていた。
己自身ともいえる大妖刀「大神成」、それと同時に振るう銘の無い他の五刀。
厳密にいえば手入れが必要なのは無銘の五刀。汚れを拭い、打粉で拭い研ぎ、錆止めの油を塗る。
今となっては極稀だが、欠けが大きければ砥石で研磨する。
僅かな鞘走りの差が勝敗を分けることもあるし、代わりの得物が手に入るかもわからない今は長持ちするよう丁寧に扱うべきだ。
しばしの後、5本の手入れを終えて愛刀の手入れに取り掛かる。
手入れといっても多少拭うだけだ。
神刀と化したこの刀は己の本体であり、生半可なことでは傷も入らない。
そう、刀身を拭うこれは、人でいうシャワーを浴びるようなものだ。
なんとなくすっきりした気分になって眼前に刃を立てる。
透き通るような清冽な輝きを宿すその刀身は、朝焼けの光を受けてきらりと瞬いた。
目を閉じ、己のうちに思いを馳せる。
イバラシティに生きる鈴とアンジニティを放浪した鈴、そしてこの神刀とうちに封じられたモノ。
全てが混じったこの身体に私が意識を残しているのは奇跡なのかもしれない。
一度目の異変は、徒党を組んだならず者共を追い払った時だった。
あの時は、まだ私は甘かったし、人を斬ることに慣れていなかった。
全身を打たれ斬られながらも戦い続け、最後に立っていたのは私だけだった。
全身が傷だらけだし、左腕はちぎれかけ。失血して頭が働かなくて、動けなくなったときは「あ、ここで死ぬのか。」そう思った。
よしんば助かったとしてももう戦えないのだろうな。みんな、もう守れなくてごめんね。遠く暗くなっていく視界の中、謝りながらふっつりと意識は途切れた
けれど―――死ななかった。起きた時はもうほとんどの傷が治っていて。
その時はどうして治ってるのかわからなくて、通りすがりの誰かが治してくれたのだろうか、なんてありもしないことを考えていた。
―――それが、私の愛刀「大神成」のおかげだということが分かったのは4度目の異変からしばらく経った後だった。
そう、あれから3度私は死んだ。正しくは、死に掛けて気づけば治っていた。
それもこれもこの刀のおかげで助かっていて、この刀が無ければ私は死んでいたはずだ。
私の扱える力が強くなっている。身体能力も、刀が持っているらしい雷を操る力も、素直に扱える。
刀もいつも以上に手に馴染む。武器の扱いに習熟した達人が到達するような身体と一体となって手の延長となったような感覚。それが以前とは比べ物にならないほど強くなっていた。
それはそうだ。当たり前のこと。私と刀は文字通り混然一体となり始めていたのだから。
夢を見た。
それは獣の夢。
山に住むその獣は、生まれた時から雷を起こす権能を持っていた。
念ずれば身から稲妻が迸り、高らかに遠吠えをすればたちまち空に暗雲が立ち込め雷が降り落ちた。
意のままに降り注ぐ落雷は害獣や侵略者を打ち倒し、畑には豊穣をもたらした。
そんな、獣はいつしか近隣の人里で“神狼”として祀られるようになった。
神狼は供えられた食べ物で腹を満たし、信仰で力を得た。そのお礼に、雷を程よく呼び、害獣や化生の類が現れればそれを退治することに一層励んだ。
それでも、神狼にどうにもできないことはあった。病だ。
周辺の村落で病が流行った。流行りに流行ったその病にかかった人間は、床に臥せってたちまち死んでしまう。
数か月のうちにほとんどの人間が死んでしまった。運良く生き延びた人間はこんな有り様では生活出来ぬとどこか遠くへ行ってしまった。
神狼は置いて行かれた。病が理解できない神狼は捨てられた。と理解した。
それでも、死んだ人間は己を捨てなかった人間である。その程度は理解できた。
撃ち捨てられた人里に転がる己を崇めていた人間だったものを一口食べては順番に埋葬し、いつしかその身には死臭が染みついた。
裏切られたと思った神狼は、恨みを募らせ遠く高らかに吠え上げた。
それは完全に八つ当たりであったが、報復とばかりに付近を通りかかる人間を噛み殺し、人の味を覚えた。
いつしかその山の周辺は魔狼の棲む山として方々に恐れられた。
そして当然、人を喰らう魔物として名の知れた獣は、退治される。
獣を調伏するためだけに打たれた神刀によって斬られたのだ。
ただ、一時は神狼とされた格の高い獣である。斬られるだけでは死ななかった。
その神刀のうちに封じられたのだった。
そこからの獣の記憶はない。
これが愛刀のルーツ。そして、今の私のルーツの一つ。
肉体を失い、神刀の中で長い年月をかけて封じられた神狼は、いまや純全たる“力”としてある。
はっきりとした意識はなく、刀として使い手を選ぶだけであった。
あの日、蔵を探検して吸い込まれるようにこの刀を発掘して手にした私。
刀に呼ばれたのか。お互いに引き合ったのか。
神狼と刀は今や力と記憶のみなっているから、真実はわからない。
ただ一つ言えることは……私とこの刀が、正確に言えばこの刀のうちに封じられた神狼と異常に相性が良かったということだけだ。
記憶を辿っても、この刀を手にした幾人もの剣士の誰も、耳や尻尾が生えた試しはない。
刀が持ち手以外を強く拒絶したこともないし、常に携えていなければならなかったこともない。
そう、私だけだった。
今度こそアンジニティの侵攻を、ワールドスワップを……止める。
使えるものは使う。いつまでも戦えるこの身はある意味で好都合ではある。
阻止が出来るなら私はもう死んでいるのだし、いつでもこの身を投げ捨てよう。
いつか、それが必要になるならば。
ふぅーーーー。
大きく息をついて閉じていた目を開く。
愛刀を鞘に納め、立ち上がる。
休憩は終わり。次は東の方へ行くと聞く。
昇った朝日の中で、仲間の影が白む景色に目を細めた。
――――――先へ進もう。



ENo.24 バケツヘルム卿 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.207 ランノ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.420 リンカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.431 ミハクサマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
バケツヘルム卿 「今回の練習、その、なんだ……女性比率が高くないか?」 |
| リンカ 「ローストビーフっす! ローストビーフっすよ、リンカイザー!!」 |
| リンカイザー 「そうだね、ローストビーフだね。」 |
 |
剣魔 「そろそろ接敵するかもしれないわね。気を引き締めていきましょう。」 |
ミハクサマ(431) から 爪 を手渡しされました。
| ミハクサマ 「…我の爪ではないし?」 |
バケツヘルム卿(24) に ItemNo.9 藍鉄鉱 を手渡ししました。
ItemNo.12 謎の焼肉 を食べました!
 |
剣魔 「ま、悪くはないわね。焼くだけでも腕って出るものなのかしら。」 |
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 増幅10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





TeamNo.223
|
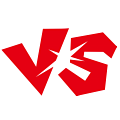 |
ミハクサマ親衛隊
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 6 増加!
影響力が 6 増加!



ミハクサマ(431) から 何か固い物体 を受け取りました。
ミハクサマ(431) から 牙 を受け取りました。
変化LV を 20 DOWN。(LV20⇒0、+20CP、-20FP)
武術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
解析LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
武器LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ItemNo.6 何か固い物体 から射程3の武器『舞刀飛刃』を作製しました!
⇒ 舞刀飛刃/武器:強さ90/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
 |
剣魔 「少し改良を施すわ。」 |
わこちゃん(1171) の持つ ItemNo.11 平石 から射程1の武器『果物ナイフ』を作製しました!
リンカ(420) の持つ ItemNo.10 牙 から射程3の武器『リンカイザーアームⅣ』を作製しました!
ランノ(207) により ItemNo.13 お魚 から料理『お魚のホイル焼き』をつくってもらいました!
⇒ お魚のホイル焼き/料理:強さ60/[効果1]活力10 [効果2]敏捷10 [効果3]強靭10
 |
ランノ 「ふむ。こんな感じか?ちゃんと火は通ってると思うぞ。食材が色々あると付け合わせにも困らないな。冷めないうちに食べるといい」 |
 |
ほかほかと湯気が立ち上る魚のホイル焼きが差し出された。 |
ミーニャ(430) により ItemNo.14 お野菜 から料理『大根の煮物』をつくってもらいました!
⇒ 技巧料理![ 1 1 1 = 3 ]大失敗!何だこれは!!!!料理の効果1~3が消失!
⇒ 大根の煮物/料理:強さ55/[効果1]- [効果2]- [効果3]-
 |
ミーニャ 「時間が経てば立つほど味がしみて美味しくなるよ、でも置きすぎるとダメになっちゃうから注意してね?」 |
リンカ(420) により ItemNo.6 舞刀飛刃 に ItemNo.16 爪 を付加してもらいました!
⇒ 舞刀飛刃/武器:強さ90/[効果1]攻撃10 [効果2]攻撃10 [効果3]-【射程3】
| リンカイザー 「リンカニック・クリエイト……お待たせ。 求める物になっているといいのだけど、どうかな?」 |
カザミさん(50) とカードを交換しました!
碧の疾風 (スカイディバイド)

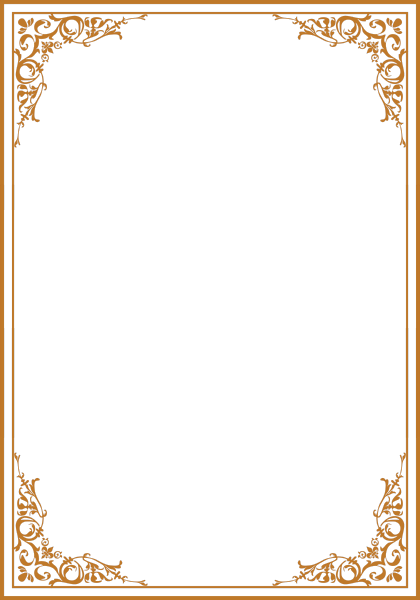
グランドクラッシャー を研究しました!(深度0⇒1)
インフェクシャスキュア を研究しました!(深度0⇒1)
ナース を研究しました!(深度0⇒1)
プリディクション を習得!
フィジカルブースター を習得!
キャプチャートラップ を習得!
ブロック を習得!
スピアトラップ を習得!
フェイタルポイント を習得!
ジャックポット を習得!
リンクブレイク を習得!
阿修羅 を習得!
応酬 を習得!
死線 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



バケツヘルム卿(24) は 山査子 を入手!
リンカ(420) は ラベンダー を入手!
ミハクサマ(431) は ラベンダー を入手!
鈴(1154) は 大蒜 を入手!
ミハクサマ(431) は パンの耳 を入手!
鈴(1154) は 剛毛 を入手!
ミハクサマ(431) は 韮 を入手!
バケツヘルム卿(24) は 韮 を入手!
リンカ(420) は 美味しい草 を入手!



バケツヘルム卿(24) に移動を委ねました。
ヒノデ区 E-11(草原)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 F-11(草原)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 G-11(草原)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 H-11(道路)に移動!(体調18⇒17)
ヒノデ区 I-11(道路)に移動!(体調17⇒16)





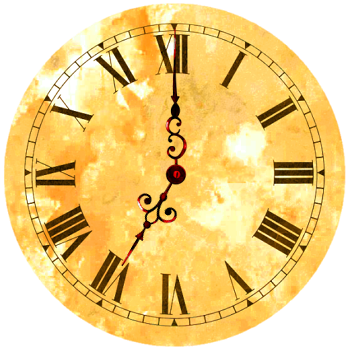
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「うんうん、順調じゃねーっすか。 あとやっぱうるせーのは居ねぇほうが断然いいっすね。」 |
 |
白南海 「いいから早くこれ終わって若に会いたいっすねぇまったく。 もう世界がどうなろうと一緒に歩んでいきやしょうワカァァ――」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カグハ 「・・・わ、変なひとだ。」 |
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
白南海 「――ん、んんッ・・・・・ ・・・なんすか。 お前らは・・・あぁ、梅楽園の団子むすめっこか。」 |
 |
カオリ 「チャットにいたからお邪魔してみようかなって!ごあいさつ!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
 |
白南海 「勝手に人の部屋に入るもんじゃねぇぞ、ガキンチョ。」 |
 |
カオリ 「勝手って、みんなに発信してるじゃんこのチャット。」 |
 |
カグハ 「・・・寂しがりや?」 |
 |
白南海 「・・・そ、操作ミスってたのか。クソ。・・・クソ。」 |
 |
白南海 「そういや、お前らは・・・・・ロストじゃねぇんよなぁ?」 |
 |
カグハ 「違うよー。」 |
 |
カオリ 「私はイバラシティ生まれのイバラシティ育ち!」 |
 |
白南海 「・・・・・は?なんだこっち側かよ。 だったらアンジニティ側に団子渡すなっての。イバラシティがどうなってもいいのか?」 |
 |
カオリ 「あ、・・・・・んー、・・・それがそれが。カグハちゃんは、アンジニティ側なの。」 |
 |
カグハ 「・・・・・」 |
 |
白南海 「なんだそりゃ。ガキのくせに、破滅願望でもあんのか?」 |
 |
カグハ 「・・・・・その・・・」 |
 |
カオリ 「うーあーやめやめ!帰ろうカグハちゃん!!」 |
 |
カオリ 「とにかく私たちは能力を使ってお団子を作ることにしたの! ロストのことは偶然そうなっただけだしっ!!」 |
 |
カグハ 「・・・カオリちゃん、やっぱり私――」 |
 |
カオリ 「そ、それじゃーね!バイビーン!!」 |
チャットから消えるふたり。
 |
白南海 「・・・・・ま、別にいいんすけどね。事情はそれぞれ、あるわな。」 |
 |
白南海 「でも何も、あんな子供を巻き込むことぁねぇだろ。なぁ主催者さんよ・・・」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



ハザマ探索相談所
|
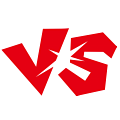 |
ミハクサマ親衛隊
|


ENo.1154
寸原 鈴

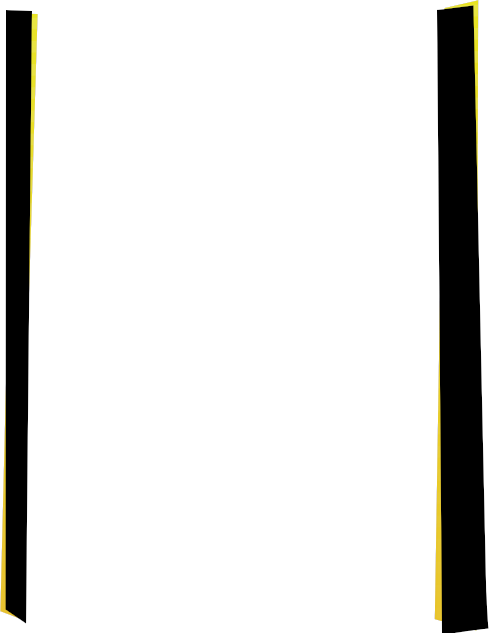
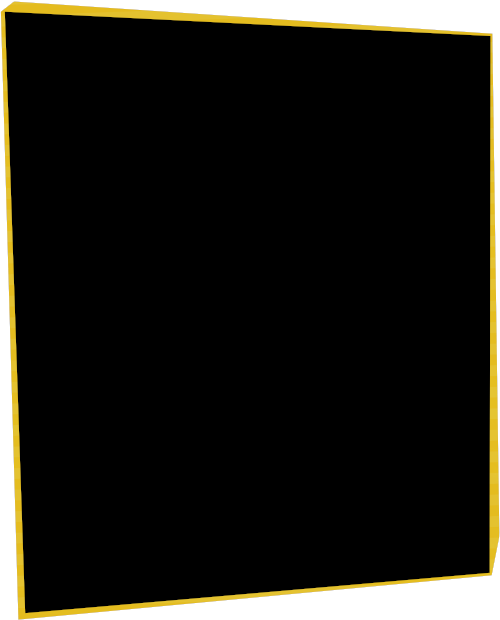
名前:寸原 鈴 (スンバラ リン)
性別:女
年齢:17
種族:人間
所属:イバラシティ
異能:念動力
趣味:刀剣蒐集・鑑賞
愛刀:無銘
部活:イノカク部
「私はれっきとした人間。耳と尻尾は・・・訳があるの。あんまり気にしないでほしいのよね。」
イバラ創藍高校に通う少女。3年生。
イバラシティにある古くから続く剣術道場、詠心一刀流の師範の一人娘。
黒髪黒目、ショートヘアの女子高生。
種族は人間だが、狼様の耳と尻尾が生えている。
何故か首輪をつけている。
性格は真面目でやや堅物。
人の話はきちんと聞こうとするが、本人は無自覚であるが最終的には力で解決しようとするやや脳筋なきらいがある。
幼い頃より鍛錬に明け暮れその才覚を早々に開花させてきた。
鈴の異能はシンプルな念動力。同時に3点まで力を発現させることが出来、その出力は発現する念動力の数だけそれぞれ分散する。
範囲は3m程度。それより外側になると離れる程極端に出力が落ちていく。
最近は、身に着けた詠心一刀流をベースに、念動力を用いた自己流多刀術を編み出すことに研鑽している。
最高で両手の二刀流と宙に浮かせた三刀の合わせて五刀流まで可能。
愛刀はいわゆる妖刀であり名前がなく、使い手を選ぶ。使い手である鈴の許可なくば、触れるとばちりとする。それでも手放そうとしないものには容赦のない出力になるようだ。
使い手を選ぶ代わりに、選ばれた使い手に獣の如き力を与え、その一閃は雷を操ると言われている。
実際雷を操れるかはわからないが、刀身をびりびりばちばちさせることはたまにできた。
妖刀の効力により身体能力が上がった代わりに狼様の耳と尻尾が生えてしまった。
望んで選ばれたわけではないので、選ばれてしまった当初は方々に掛け合ってお祓いや解呪を試したが
この刀の力が強いこと、邪悪なものでないことから効果は無く、現在は諦めている。
首輪は強くなり過ぎた聴覚や嗅覚を常人レベルに落とすための呪具である。
これがないと、数時間で頭痛が起き始め、数日で床に臥せることになる。
当初は腕輪や指輪、ネックレス等の日常で違和感のないアクセサリの形で作られたが
すぐに壊れてしまった、おふざけで付けた首輪が壊れずにすんだためこれをつけている。
――――――――
正体は、いつかの昔ワールドスワップで故郷の世界を奪われた女子高生。スワップの後、生存競争を繰り返した果てに今は意思無き妖刀“大神成”と混じりきった存在。
年齢不詳、種族不明(人と刀と神狼が混じる)
結果、首輪が無くてもケモノの力を制御出来るようになり、加えて刀の持っていた雷を操る力も使えるようになった。
また、長年の放浪の結果、異能で刀を4本操れるようになり、最高で六刀流となる。
刀とケモノの本能のままに刀を振るう危険な人物であったが、元の鈴としての心を取り戻した結果、鈴という少女としての人格が本能を抑えて表層に現れるようになった。普段は鈴として理性の下に行動をするが、ふとした瞬間に本性が現れてしまう。あくまでベースは剣魔なのである。
――あらすじ―――――――――――――――――――――
過去にワールドスワップの被害にあった世界の住人。世界を守ろうと戦ったが奮戦虚しく負けてしまい世界を奪われた。
スワップ先の世界は不毛の地であり、唐突に放り出された元世界の住人達は次第に食うにも困窮し始める。
困窮し始めれば当然他者から奪う者も出始め殺伐とした世界になり始めた。新世界でも力ある者として弱き者を守ろうとする鈴であったが、多勢に無勢、弱者を狙うならず者との戦いに明け暮れ何度も死にかけ、その度に刀が力を分け与え、混ざり合いつつも生き延びるのであった。
斬って斬られて次第に心が磨り減っていく鈴に止めの機会が訪れる。これまで何度も裏切りや騙し討ちはあって慣れ始めていたものの、ずっと守り続けて庇護してきたものに裏切られ差し出されたのだった。
敵、そして今まで守ってきた人。全てを切り伏せた時、既に磨り減っていた心は壊れ、正気を失ってしまう。
それ以来、1人さ迷い近付く者を斬り捨てる1つの獣と化し、剣魔と恐れられるようになったのだった。
刀と混ざり合い、完全に人で無くなった時。今のアンジニティへと流れ付くのであった。
時は流れ、現在のワールドスワップ。
ハザマにて平和なイバラシティの日常の記憶が剣魔の心を刺激する。
思い起こされる大切ないつかの日々。
その時、剣魔は“鈴”としての心を取り戻すのであった。
ーーーこんな無法者達にあの平和な日常を侵させはしない。
今度こそ、守り通す。
ーーーたとえ、私はもうそこに戻れないとしても。
それが、既に終わった“ヒト”の、せめてもの誓い。
―――――――――――――――――――――――――
性別:女
年齢:17
種族:人間
所属:イバラシティ
異能:念動力
趣味:刀剣蒐集・鑑賞
愛刀:無銘
部活:イノカク部
「私はれっきとした人間。耳と尻尾は・・・訳があるの。あんまり気にしないでほしいのよね。」
イバラ創藍高校に通う少女。3年生。
イバラシティにある古くから続く剣術道場、詠心一刀流の師範の一人娘。
黒髪黒目、ショートヘアの女子高生。
種族は人間だが、狼様の耳と尻尾が生えている。
何故か首輪をつけている。
性格は真面目でやや堅物。
人の話はきちんと聞こうとするが、本人は無自覚であるが最終的には力で解決しようとするやや脳筋なきらいがある。
幼い頃より鍛錬に明け暮れその才覚を早々に開花させてきた。
鈴の異能はシンプルな念動力。同時に3点まで力を発現させることが出来、その出力は発現する念動力の数だけそれぞれ分散する。
範囲は3m程度。それより外側になると離れる程極端に出力が落ちていく。
最近は、身に着けた詠心一刀流をベースに、念動力を用いた自己流多刀術を編み出すことに研鑽している。
最高で両手の二刀流と宙に浮かせた三刀の合わせて五刀流まで可能。
愛刀はいわゆる妖刀であり名前がなく、使い手を選ぶ。使い手である鈴の許可なくば、触れるとばちりとする。それでも手放そうとしないものには容赦のない出力になるようだ。
使い手を選ぶ代わりに、選ばれた使い手に獣の如き力を与え、その一閃は雷を操ると言われている。
実際雷を操れるかはわからないが、刀身をびりびりばちばちさせることはたまにできた。
妖刀の効力により身体能力が上がった代わりに狼様の耳と尻尾が生えてしまった。
望んで選ばれたわけではないので、選ばれてしまった当初は方々に掛け合ってお祓いや解呪を試したが
この刀の力が強いこと、邪悪なものでないことから効果は無く、現在は諦めている。
首輪は強くなり過ぎた聴覚や嗅覚を常人レベルに落とすための呪具である。
これがないと、数時間で頭痛が起き始め、数日で床に臥せることになる。
当初は腕輪や指輪、ネックレス等の日常で違和感のないアクセサリの形で作られたが
すぐに壊れてしまった、おふざけで付けた首輪が壊れずにすんだためこれをつけている。
――――――――
正体は、いつかの昔ワールドスワップで故郷の世界を奪われた女子高生。スワップの後、生存競争を繰り返した果てに今は意思無き妖刀“大神成”と混じりきった存在。
年齢不詳、種族不明(人と刀と神狼が混じる)
結果、首輪が無くてもケモノの力を制御出来るようになり、加えて刀の持っていた雷を操る力も使えるようになった。
また、長年の放浪の結果、異能で刀を4本操れるようになり、最高で六刀流となる。
刀とケモノの本能のままに刀を振るう危険な人物であったが、元の鈴としての心を取り戻した結果、鈴という少女としての人格が本能を抑えて表層に現れるようになった。普段は鈴として理性の下に行動をするが、ふとした瞬間に本性が現れてしまう。あくまでベースは剣魔なのである。
――あらすじ―――――――――――――――――――――
過去にワールドスワップの被害にあった世界の住人。世界を守ろうと戦ったが奮戦虚しく負けてしまい世界を奪われた。
スワップ先の世界は不毛の地であり、唐突に放り出された元世界の住人達は次第に食うにも困窮し始める。
困窮し始めれば当然他者から奪う者も出始め殺伐とした世界になり始めた。新世界でも力ある者として弱き者を守ろうとする鈴であったが、多勢に無勢、弱者を狙うならず者との戦いに明け暮れ何度も死にかけ、その度に刀が力を分け与え、混ざり合いつつも生き延びるのであった。
斬って斬られて次第に心が磨り減っていく鈴に止めの機会が訪れる。これまで何度も裏切りや騙し討ちはあって慣れ始めていたものの、ずっと守り続けて庇護してきたものに裏切られ差し出されたのだった。
敵、そして今まで守ってきた人。全てを切り伏せた時、既に磨り減っていた心は壊れ、正気を失ってしまう。
それ以来、1人さ迷い近付く者を斬り捨てる1つの獣と化し、剣魔と恐れられるようになったのだった。
刀と混ざり合い、完全に人で無くなった時。今のアンジニティへと流れ付くのであった。
時は流れ、現在のワールドスワップ。
ハザマにて平和なイバラシティの日常の記憶が剣魔の心を刺激する。
思い起こされる大切ないつかの日々。
その時、剣魔は“鈴”としての心を取り戻すのであった。
ーーーこんな無法者達にあの平和な日常を侵させはしない。
今度こそ、守り通す。
ーーーたとえ、私はもうそこに戻れないとしても。
それが、既に終わった“ヒト”の、せめてもの誓い。
―――――――――――――――――――――――――
16 / 30
484 PS
ヒノデ区
I-11
I-11



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 妖刀「大神成」 | 武器 | 40 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 砥石 | 防具 | 35 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 舞刀飛刃 | 武器 | 90 | 攻撃10 | 攻撃10 | - | 【射程3】 |
| 7 | 血界のミサンガ | 装飾 | 67 | 治癒15 | - | - | |
| 8 | 浮刀飛刃 | 武器 | 40 | 衰弱10 | - | - | 【射程3】 |
| 9 | 何か固い物体 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20) | |||
| 10 | バックレスニット | 防具 | 82 | 奪命10 | 奪命10 | - | |
| 11 | たけのこ | 食材 | 20 | [効果1]貫撃10(LV15)[効果2]器用10(LV25)[効果3]深手20(LV35) | |||
| 12 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
| 13 | お魚のホイル焼き | 料理 | 60 | 活力10 | 敏捷10 | 強靭10 | |
| 14 | 大根の煮物 | 料理 | 55 | - | - | - | |
| 15 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 16 | 大蒜 | 素材 | 20 | [武器]体力15(LV30)[防具]体力15(LV30)[装飾]体力15(LV30) | |||
| 17 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 20 | 拘束/罠/リスク |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 50 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 6 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| 練3 | デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| 練3 | チャージ | 6 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| 練3 | ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| フェイタルポイント | 5 | 0 | 80 | 敵:精確痛撃 | |
| キーンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:DX・貫撃LV増 | |
| ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| 練3 | イレイザー | 8 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| ディクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が低めになる | |
| 練3 | ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| オーバーウェルム | 5 | 0 | 300 | 自:増幅・強靭・強撃LV増 | |
| イクスプロイト | 5 | 0 | 160 | 敵:攻撃&AT奪取&3D6が10以下ならDX奪取 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 血気 | 6 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
| 応酬 | 5 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】対:精確攻撃 | |
| 死線 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃命中率増 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
狙い撃ち (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
渡りの魔力 (クイック) |
0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 練3 |
雄牛 (チャージ) |
0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
|
ヘイルカード (ヘイルカード) |
0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| 練3 |
tea time (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
| 練3 |
アンノウンズフェイク (チャージ) |
0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
|
碧の疾風 (スカイディバイド) |
1 | 150 | 敵貫:風撃&風耐性減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]インフェクシャスキュア | [ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]リザレクション |
| [ 3 ]ヒールハーブ | [ 1 ]グランドクラッシャー | [ 1 ]ダウンフォール |
| [ 3 ]マーチ | [ 3 ]コンテイン | [ 3 ]ケイオティックチェイス |
| [ 1 ]ナース | [ 1 ]アブソーブ |

PL / 結城