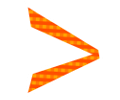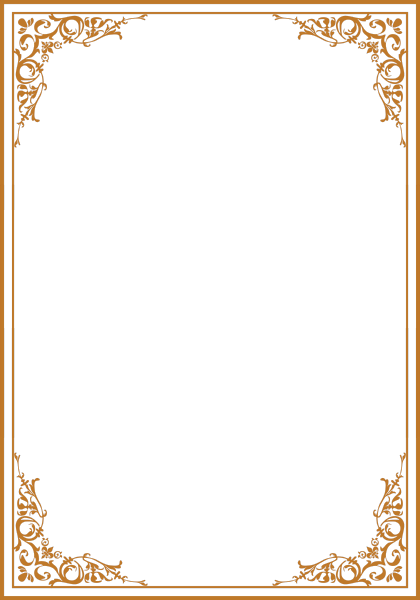<< 5:00~6:00




──目を開く。
息を吸い、そして吐いた。両手を目の高さまで持ち上げ、握り、そして開いてみる。
感じた。握り込まれた指や爪の感触、暖かさ。その圧力。
こつこつと、ブーツのつま先で地面を叩いてみる。
地面の固さを感じた。杖がなくとも、しっかり立てる。
「……っふ。」
息を吐き出すように、笑う。
こちらの自分は、まだ動ける。“あちら”の自分は着実に伽藍に冒されてはいるが、それでも行き着くべきところへ歩み続けている。
あとは、間に合うか否か──。
『葛子さま。』
思考に閉じた身のうちに声が響き、ふと顔を上げる。連れ合いたちはおのおの会話を楽しんでいるようだ。葛子に話しかける者は、今はいない。なれば……。
『さとりか。どうした。』
離れて行動している、あやかしたちからの念話。さとりはこうして、心を通わせる術に長ける。
『また、以前のようなあやかしを見つけました。陣営に関係なく喰らい、その身から陰陽のにおいを漂わせている。おそらくは、保名さまの造り出したものかと。』
その名を聞いて、葛子は僅かに目を伏せる。しかしそれも一瞬のこと。
『あいわかった。合流しよう。』
葛子は連れ合いに休憩を提案し、あれこれと理由をつけてその場を離れた。
△▼
チナミ区、Oー16番地。通称、“梅楽園”。
荒廃した街の景色の中にあって、梅の花が美しく咲く様は優美さよりも前に妖しさを感じさせる。
ぼんやりと明るい並木の道で、ざわざわと風が流れる音がした。
「──こんな時でなければ、見惚れていたのやも知れませんが。」
ぽつり、つぶやくは黒髪の少年。前髪が片目を隠すように長く伸び、男としての身体の性徴を迎える前の顔立ちは、何処となし中性をはらむようである。背丈はあさなと同じ程度。葛子よりも一回り小さい。
装いは黒地の甚平に下駄姿。やんちゃ盛りの年頃に見えるその姿から、発されたのはひどく落ち着いた声。 あやかし、“さとり”。心を読み、心を手繰る。
そう伝えられ、畏れられた旧きモノである。
「“むこう”の梅楽園も佳いものじゃ。いつか、皆で行きたいものじゃな。」
葛子が微笑むと、おろちは鼻を鳴らす。
「此方で言っても詮無きことだろう。どうせ覚えてはおらぬのだから。」
「きっと、このハザマでこのような話をしたことを覚えておらずとも、皆で行こうとなる気がします!」
想像したのか、あさながくすくすと笑いながら言う。ね、と雪女に同意を求めた。
「いや、あーしらはともかくおろちさまは無理っしょ。ヒトのかたちにはなれないんだし?」
苦笑して返す雪女に、おろちはシュルシュルと吐息を漏らした。
「興味はない。留守を預かる。」
「えぇ~。だからあそーいうぼっちムーヴ禁止って言ったじゃん? あーしは花見すんならおろちさまと一緒がいいの~。」
「……あまり葛の君を困らせるな、心遣いは受け取っておくゆえ。」
「雪女様。葛乃葉様を困らせてはいけません。」
「うぇ、やまびこもそっちの味方なの!? もー……まぁいいけど。」
いいけど、と言いつつも不満げな雪女。おろちはそんな彼女をしばらく見、二度目のため息を吐いた。
雪女、と声を掛ける。
「梅の花を一輪、持ち帰れ。その香りだけで充分に愉しめよう。
その時は雪女……共に、酌を交わそうぞ。」
「んっ! マジで? おろちさまのお酒のめんの? やった~いくいく絶対付き合う! 朝まで呑むかんね~!」
はしゃぐ雪女。おろちは呆れたようで、けれど珍しくも小さく笑う。
「……ふふ。だから、覚えてはおらんだろうと言ったろうに。」
「だがまあ、そうだな。彼方でも同じ約束をできたなら、佳い。」
さとりが笑みを浮かべた。「佳いですね。」とやまびこがうなずく。「くずこさまも一緒に行きますからね!」とあさなが稲穂の女にじゃれついた。
葛子が浮かべる笑みは、安らいでいた。
「──うらやましい。」
梅の香に埋めて、か細く呟く声。
男のもの、女のもの、子供のもの。幾重にも幾重にも重なって聞こえてくる。
「囲まれていますね。」
さとりが辺りを見回し、いかがいたしますか、と葛子を仰ぐ。
「……梅に魂を縛り付けられておるか。女子供も容赦なしと。
ヒトはみな、並べてわしに追い縋るための材料に過ぎぬ、か。保名さまの考えそうなことじゃ。」
梅の咲き誇る地面から、どっと土塊(つちくれ)が巻き上がる。沢山の手が、地面の下から突き出していた。
芽吹いた新芽が幹に育つのを早回しで見ているかのように、手は伸び、腕となる。本来は肘があるべき場所にそれは無く、何十、何百という数の白い腕は病んだ植物の蔓のようである。
「うらやましい。あたたかい、わらっている。ああうらやましい。
わたしたちはこんなにもこわくて、いたいというのに。」
声が聞こえる。悲痛と怨みにまみれた、救われない怪異の唸りが。
「……ヒトよ、同情しねーかんな。そうなっちゃったらもう、同情なんて感情はお前らのためになんねーしさ。」
雪女が鉄扇を懐から取り出した。ついた吐息が凍り付き、辺りには霜が降りはじめる。
「くずこ姉ぇ、あーしがやっからね。姉ぇのその力、使う度に姉ぇの身体を喰い散らかしてってる。マジ手出し要らんから。」
朱色の瞳は、深雪の白銀のその色を変え。
葛子は頷く。その前にあさなが陣取った。
「葛子さまの護りはお任せくださいっ!」
「あっはは、とーぜん。んじゃいくかんね。おろち様、さとり、やまびこ。」
パキパキパキ、と全てが凍てついていく音。
おろちは無言で、白着物に薄桃の上着を着た雪女の横に並び立つ。雪女の後ろには、彼女と全く同じ姿形の人物が一人。
「やまびこの“それ”、毎度慣れませんね。心の中まで一切の全てを写しとるのは止めませんか。」
「止めません。」
にべもなく……というより、直前の相手の発言を繰り返すことしかできない相手の返事に、さとりはため息を吐いた。
「そうですか。まあ──」
その背から、背負っていた一丁の長銃を下ろし、クリップから弾薬を装填する。
「いいんですが。」
「あんたの“ソレ”の方がよっぽど慣れないんだけどね……。」
ボルトレバーを難なく閉鎖するさとりが苦笑した。
「じゃ、行くか。くずこ姉ぇのためにさ。」



ENo.223 兎乃 とのやりとり

ENo.492 つづり とのやりとり

ENo.705 けもの とのやりとり

ENo.789 無名 とのやりとり




玉護(276) から 半濁音チャプチェ を手渡しされました。












六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



すごい石材(400 PS)を購入しました。
領域LV を 7 UP!(LV15⇒22、-7CP)
防具LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
料理LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)
兎乃(223) の持つ ItemNo.15 皮 から防具『レザースカート』を作製しました!
へちま(1642) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『白タイツ』を作製しました!
五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度1⇒2)
五月雨 を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



玉護(276) は ぬめぬめ を入手!
えみりん(1239) は 羽 を入手!
玉護(276) は 花びら を入手!
兎乃(223) は 花びら を入手!
狐疑(263) は 毛 を入手!
えみりん(1239) は 毛 を入手!
玉護(276) は 毛 を入手!
玉護(276) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
えみりん(1239) のもとに オオドジョウ が泣きながら近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに ジャンボゼミ が泣きながら近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに ダンデライオン が興味津々な様子で近づいてきます。



兎乃(223) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
玉護(276) をパーティに勧誘しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- 玉護(276) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 を選択!
- 玉護(276) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》





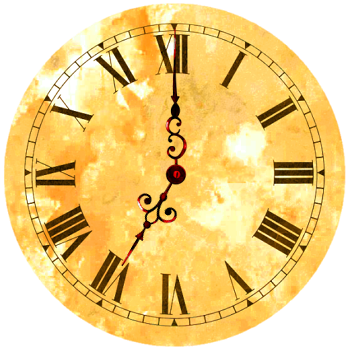
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映し出されるふたり。
チャットから消えるふたり。
チャットが閉じられる――








仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!







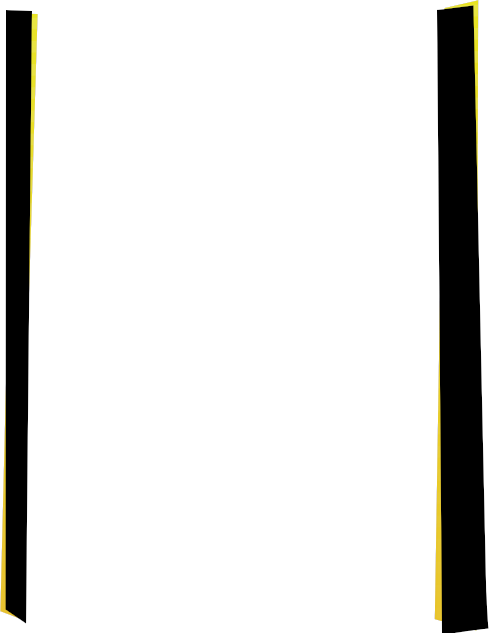
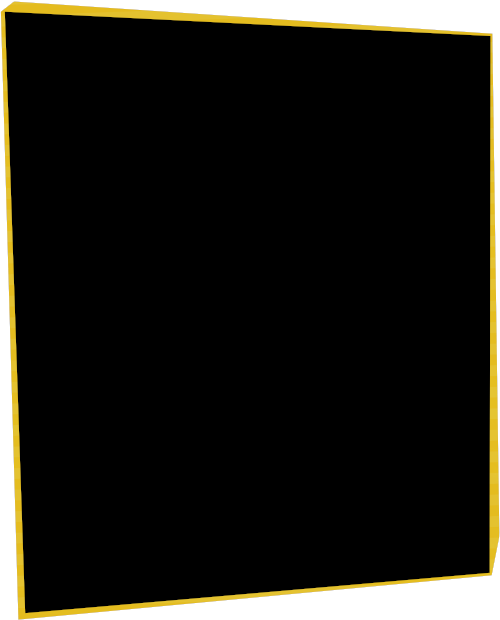





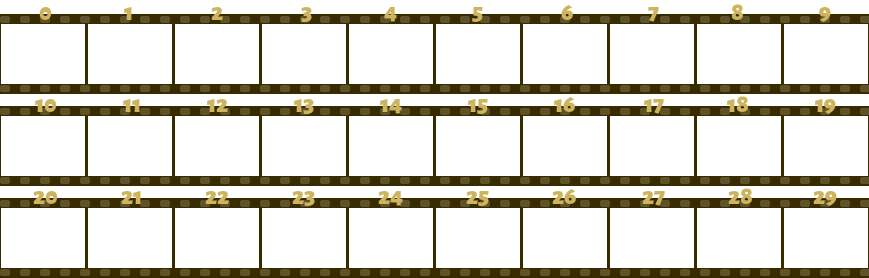





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



──目を開く。
息を吸い、そして吐いた。両手を目の高さまで持ち上げ、握り、そして開いてみる。
感じた。握り込まれた指や爪の感触、暖かさ。その圧力。
こつこつと、ブーツのつま先で地面を叩いてみる。
地面の固さを感じた。杖がなくとも、しっかり立てる。
「……っふ。」
息を吐き出すように、笑う。
こちらの自分は、まだ動ける。“あちら”の自分は着実に伽藍に冒されてはいるが、それでも行き着くべきところへ歩み続けている。
あとは、間に合うか否か──。
『葛子さま。』
思考に閉じた身のうちに声が響き、ふと顔を上げる。連れ合いたちはおのおの会話を楽しんでいるようだ。葛子に話しかける者は、今はいない。なれば……。
『さとりか。どうした。』
離れて行動している、あやかしたちからの念話。さとりはこうして、心を通わせる術に長ける。
『また、以前のようなあやかしを見つけました。陣営に関係なく喰らい、その身から陰陽のにおいを漂わせている。おそらくは、保名さまの造り出したものかと。』
その名を聞いて、葛子は僅かに目を伏せる。しかしそれも一瞬のこと。
『あいわかった。合流しよう。』
葛子は連れ合いに休憩を提案し、あれこれと理由をつけてその場を離れた。
△▼
チナミ区、Oー16番地。通称、“梅楽園”。
荒廃した街の景色の中にあって、梅の花が美しく咲く様は優美さよりも前に妖しさを感じさせる。
ぼんやりと明るい並木の道で、ざわざわと風が流れる音がした。
「──こんな時でなければ、見惚れていたのやも知れませんが。」
ぽつり、つぶやくは黒髪の少年。前髪が片目を隠すように長く伸び、男としての身体の性徴を迎える前の顔立ちは、何処となし中性をはらむようである。背丈はあさなと同じ程度。葛子よりも一回り小さい。
装いは黒地の甚平に下駄姿。やんちゃ盛りの年頃に見えるその姿から、発されたのはひどく落ち着いた声。 あやかし、“さとり”。心を読み、心を手繰る。
そう伝えられ、畏れられた旧きモノである。
「“むこう”の梅楽園も佳いものじゃ。いつか、皆で行きたいものじゃな。」
葛子が微笑むと、おろちは鼻を鳴らす。
「此方で言っても詮無きことだろう。どうせ覚えてはおらぬのだから。」
「きっと、このハザマでこのような話をしたことを覚えておらずとも、皆で行こうとなる気がします!」
想像したのか、あさながくすくすと笑いながら言う。ね、と雪女に同意を求めた。
「いや、あーしらはともかくおろちさまは無理っしょ。ヒトのかたちにはなれないんだし?」
苦笑して返す雪女に、おろちはシュルシュルと吐息を漏らした。
「興味はない。留守を預かる。」
「えぇ~。だからあそーいうぼっちムーヴ禁止って言ったじゃん? あーしは花見すんならおろちさまと一緒がいいの~。」
「……あまり葛の君を困らせるな、心遣いは受け取っておくゆえ。」
「雪女様。葛乃葉様を困らせてはいけません。」
「うぇ、やまびこもそっちの味方なの!? もー……まぁいいけど。」
いいけど、と言いつつも不満げな雪女。おろちはそんな彼女をしばらく見、二度目のため息を吐いた。
雪女、と声を掛ける。
「梅の花を一輪、持ち帰れ。その香りだけで充分に愉しめよう。
その時は雪女……共に、酌を交わそうぞ。」
「んっ! マジで? おろちさまのお酒のめんの? やった~いくいく絶対付き合う! 朝まで呑むかんね~!」
はしゃぐ雪女。おろちは呆れたようで、けれど珍しくも小さく笑う。
「……ふふ。だから、覚えてはおらんだろうと言ったろうに。」
「だがまあ、そうだな。彼方でも同じ約束をできたなら、佳い。」
さとりが笑みを浮かべた。「佳いですね。」とやまびこがうなずく。「くずこさまも一緒に行きますからね!」とあさなが稲穂の女にじゃれついた。
葛子が浮かべる笑みは、安らいでいた。
「──うらやましい。」
梅の香に埋めて、か細く呟く声。
男のもの、女のもの、子供のもの。幾重にも幾重にも重なって聞こえてくる。
「囲まれていますね。」
さとりが辺りを見回し、いかがいたしますか、と葛子を仰ぐ。
「……梅に魂を縛り付けられておるか。女子供も容赦なしと。
ヒトはみな、並べてわしに追い縋るための材料に過ぎぬ、か。保名さまの考えそうなことじゃ。」
梅の咲き誇る地面から、どっと土塊(つちくれ)が巻き上がる。沢山の手が、地面の下から突き出していた。
芽吹いた新芽が幹に育つのを早回しで見ているかのように、手は伸び、腕となる。本来は肘があるべき場所にそれは無く、何十、何百という数の白い腕は病んだ植物の蔓のようである。
「うらやましい。あたたかい、わらっている。ああうらやましい。
わたしたちはこんなにもこわくて、いたいというのに。」
声が聞こえる。悲痛と怨みにまみれた、救われない怪異の唸りが。
「……ヒトよ、同情しねーかんな。そうなっちゃったらもう、同情なんて感情はお前らのためになんねーしさ。」
雪女が鉄扇を懐から取り出した。ついた吐息が凍り付き、辺りには霜が降りはじめる。
「くずこ姉ぇ、あーしがやっからね。姉ぇのその力、使う度に姉ぇの身体を喰い散らかしてってる。マジ手出し要らんから。」
朱色の瞳は、深雪の白銀のその色を変え。
葛子は頷く。その前にあさなが陣取った。
「葛子さまの護りはお任せくださいっ!」
「あっはは、とーぜん。んじゃいくかんね。おろち様、さとり、やまびこ。」
パキパキパキ、と全てが凍てついていく音。
おろちは無言で、白着物に薄桃の上着を着た雪女の横に並び立つ。雪女の後ろには、彼女と全く同じ姿形の人物が一人。
「やまびこの“それ”、毎度慣れませんね。心の中まで一切の全てを写しとるのは止めませんか。」
「止めません。」
にべもなく……というより、直前の相手の発言を繰り返すことしかできない相手の返事に、さとりはため息を吐いた。
「そうですか。まあ──」
その背から、背負っていた一丁の長銃を下ろし、クリップから弾薬を装填する。
「いいんですが。」
「あんたの“ソレ”の方がよっぽど慣れないんだけどね……。」
ボルトレバーを難なく閉鎖するさとりが苦笑した。
「じゃ、行くか。くずこ姉ぇのためにさ。」



ENo.223 兎乃 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.492 つづり とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.705 けもの とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.789 無名 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||



 |
兎乃 「無事にベースキャンプに戻れたし、ここで一旦お別れね。縁があったらまた会いましょ♪」 |
玉護(276) から 半濁音チャプチェ を手渡しされました。
 |
玉護 「…何だろ?これ。 …ボクにもさっぱり、さ。」 |





TeamNo.223
|
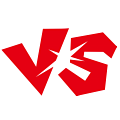 |
ミハクサマ親衛隊
|



チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
TeamNo.223
|
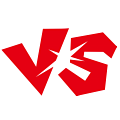 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



すごい石材(400 PS)を購入しました。
領域LV を 7 UP!(LV15⇒22、-7CP)
防具LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
料理LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)
兎乃(223) の持つ ItemNo.15 皮 から防具『レザースカート』を作製しました!
へちま(1642) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『白タイツ』を作製しました!
五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度1⇒2)
五月雨 を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



玉護(276) は ぬめぬめ を入手!
えみりん(1239) は 羽 を入手!
玉護(276) は 花びら を入手!
兎乃(223) は 花びら を入手!
狐疑(263) は 毛 を入手!
えみりん(1239) は 毛 を入手!
玉護(276) は 毛 を入手!
玉護(276) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
えみりん(1239) のもとに オオドジョウ が泣きながら近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに ジャンボゼミ が泣きながら近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに ダンデライオン が興味津々な様子で近づいてきます。



兎乃(223) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
玉護(276) をパーティに勧誘しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- 玉護(276) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 を選択!
- 玉護(276) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》





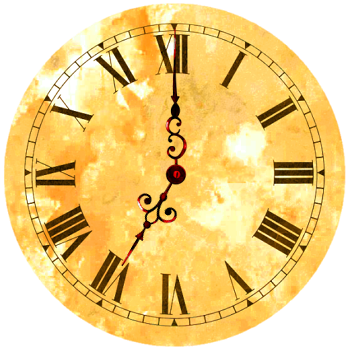
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「うんうん、順調じゃねーっすか。 あとやっぱうるせーのは居ねぇほうが断然いいっすね。」 |
 |
白南海 「いいから早くこれ終わって若に会いたいっすねぇまったく。 もう世界がどうなろうと一緒に歩んでいきやしょうワカァァ――」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カグハ 「・・・わ、変なひとだ。」 |
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
白南海 「――ん、んんッ・・・・・ ・・・なんすか。 お前らは・・・あぁ、梅楽園の団子むすめっこか。」 |
 |
カオリ 「チャットにいたからお邪魔してみようかなって!ごあいさつ!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
 |
白南海 「勝手に人の部屋に入るもんじゃねぇぞ、ガキンチョ。」 |
 |
カオリ 「勝手って、みんなに発信してるじゃんこのチャット。」 |
 |
カグハ 「・・・寂しがりや?」 |
 |
白南海 「・・・そ、操作ミスってたのか。クソ。・・・クソ。」 |
 |
白南海 「そういや、お前らは・・・・・ロストじゃねぇんよなぁ?」 |
 |
カグハ 「違うよー。」 |
 |
カオリ 「私はイバラシティ生まれのイバラシティ育ち!」 |
 |
白南海 「・・・・・は?なんだこっち側かよ。 だったらアンジニティ側に団子渡すなっての。イバラシティがどうなってもいいのか?」 |
 |
カオリ 「あ、・・・・・んー、・・・それがそれが。カグハちゃんは、アンジニティ側なの。」 |
 |
カグハ 「・・・・・」 |
 |
白南海 「なんだそりゃ。ガキのくせに、破滅願望でもあんのか?」 |
 |
カグハ 「・・・・・その・・・」 |
 |
カオリ 「うーあーやめやめ!帰ろうカグハちゃん!!」 |
 |
カオリ 「とにかく私たちは能力を使ってお団子を作ることにしたの! ロストのことは偶然そうなっただけだしっ!!」 |
 |
カグハ 「・・・カオリちゃん、やっぱり私――」 |
 |
カオリ 「そ、それじゃーね!バイビーン!!」 |
チャットから消えるふたり。
 |
白南海 「・・・・・ま、別にいいんすけどね。事情はそれぞれ、あるわな。」 |
 |
白南海 「でも何も、あんな子供を巻き込むことぁねぇだろ。なぁ主催者さんよ・・・」 |
チャットが閉じられる――







カミセイ区 H-4
チェックポイント《森の学舎》
チェックポイント。チェックポイント《森の学舎》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《SNAKE》
黒闇に包まれた巨大なヘビのようなもの。
 |
守護者《SNAKE》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!





ENo.263
犬前葛子

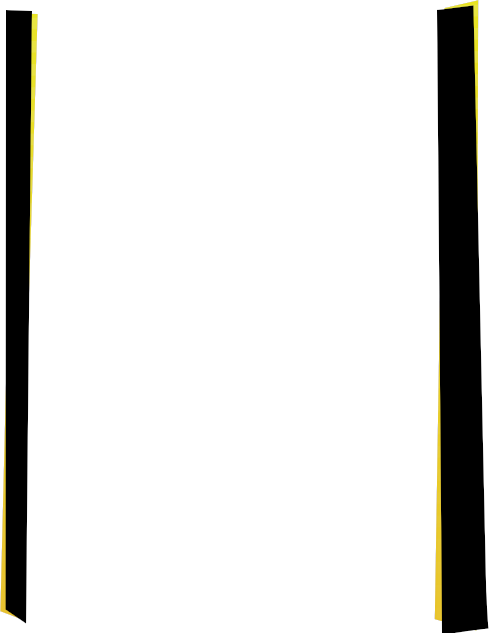
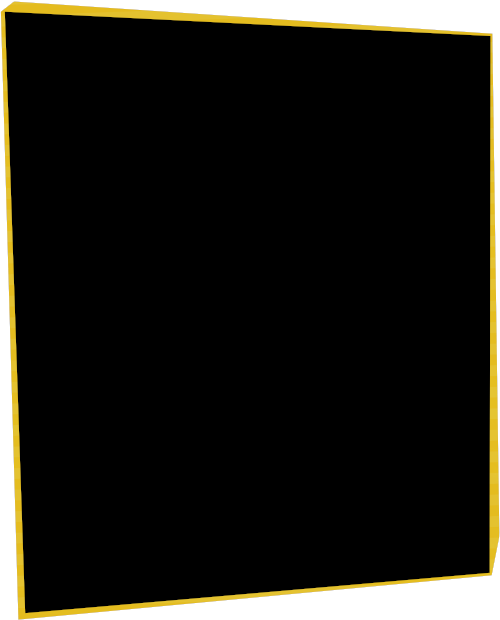
.
手に結ぶ 月に宿れる月影の
在るか亡きかの 世にこそ在りつれ
■犬前葛子
種族 狐疑(前・混成狐神)
年齢 約2200歳
身長 149cm
体重 47kg
異能 伽藍夙(がらんつとめて)
陣営 イバラシティ
記憶の引き継ぎ あり(ハザマでの記憶はハザマ内でのみ取得)
イバライン http://lisge.com/ib/talk.php?p=1765
============================
■
稲穂の色の髪に、同じ色の瞳。
古風な言葉遣いに、教え諭すような言葉。
胸元には首から紐で下げた、小さな白金糸の御守り。
民営ラジオでは人気パーソナリティ、通称“くずこさん”。
どこか浮世離れしつつ、茶目っ気たっぷりな俗っぽさも持ち併せる女性。
果たしてその正体は、ヒトではない。
怪異、あやかし、妖怪、神使。
そう呼ばれるもの達の重鎮──“葛乃葉狐”が他の狐たちの力を受け継ぎ、主神“宇迦之御魂神”の権能すらも取り込んで現代まで在り続けた。そんな、常ならぬ狐の総体、混成狐神。
それが、安倍葛子──平行世界のイバラシティにおける、彼女の本性であった。
■
そして現在、犬前葛子は世界線転移の際に起きた“とある出来事”の影響により、狐としてのすべての権能を失っている。
この世界線において、彼女は“犬前葛子”である。
しかし同時に、前世界線に存在した狐神の成れの果て、ヒトでもなければあやかしでもカミでもないあわいものである。
故、彼女の今の正体は。
誰が呼んだか、己が正体すら失った哀れな狐を“狐疑(こぎ)”と云う。
■異能名【伽藍夙】[がらんつとめて]
種別別称:Ⅳ類特型(類型無し-ユニークスキル)
効果:
対象の異能・超常・異質を鎮静させる。
また、効力の及んだ事象からは存在意義を削り取る。同事象は一定時間発生しづらくなる。
知生体に対して効力が及んだ場合、対象は強い睡魔に襲われる。
能動的に発動し、対象を選択する“匁(もんめ)”
身にまとい、受動的に減衰させる“累(かさね)”
の2種類が存在する。
上記の2種は共に発動後、匁は自立稼働する体高80cmほどの巨大な狐として、累は椿の花が描かれた羽織着物として視認が可能。両者ともに白く半透明なエフェクトであり、物理的な防御力はない。
葛乃葉そのものとは一切関係のない出自の力である。
彼女の元の異能はこの伽藍夙によって消滅寸前まで鎮静させられているため、使用は不可能。
狐疑はこの異能に自らの在り方を再定義されかかっており、それが完遂されると“虚疑”として覚醒を果たす。
別名“星狩りの閨”。
これは、ヒトの夜への怖れそのもの。
怖ろしいものへの、苛烈な害意が形を成したもの。
ヒトの心が神秘を蹂躙する、その体現。
外敵殺し、守護と排斥の極致。
異能名【宇迦信太へぐい】[うかしのだへぐい]
種別別称:異能登録データ無し・違法所持異能
効果:
ꂁ�岔쾕겐삎첑瞁變咔璗碁?徐릓徐折䆁ꢂ?톂횊䆘溑?芃悃宁璃즂떂붂욂皎?䆁熃枃庌첂삎첑䊁붉ꦂ즂�쮈떂쒂ꊂ?꾂얂춂좂궂䆁뚐?붂?슌첂�岔䊁?极變咔璗梁ꢂ?톂极徐折?첂쾌梁ꪂ鶎슂䎃膃宁垃즂璕辐랂?岔춗?ꆕ钐?Ꚃ䆁玍枎랂?놂욂ꪂ슉岔䊁삎玍슉岔좂岔춗춂좈몉첂쪒?䊁?䖁?좂斃貃炃境岔춗?䖁芍碓좂뚌暘䆁뚌炏첂玍枎岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁?曦璕店岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁玕涊?좂庉붖놊슏岔춗?䖁侔꺓춗?䖁쾌첂ꢎ욂䮐?榁沎?檁ꪂ뚐Ꚃ?䖁殚澊䖁꺒澊ꪂ궔䊒랂?䖁ﮌ늒ꪂ쎌䲏궂좂?ꂁ庉붖놊슏岔춗禁侎쾌䆉窗릓榁�꾂슂ꢂ?�?ꒂ잂ꒂ檁突?䲖?徐욂뮂첂徐枎얂ꂂ?쾌?꾓?讎랂?꾖풊悓뎏䆁�붂횊䆘溑?얂ꂂ?徐?첂䆉窗璎悓?麍?뺂䆁變咔璗첂얍?�岔䊁?禁徐榁變咔璗檁즂䚋?ꢁ䚋솂붂튎즂颗皉?붂?랂突욂ꊂꒂ皃趃媃境얂䆁캑�첂玕涊?庉붖?䒍펈䦓즂쾕嶓뎂릂?䊁?ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ?ꂁ熂澂?즂鞉ꊂ쒂䆁캑�첂徃䎃境뮔?庉?䮕皗욂랂?玍꺓즂?鶕좂?뎐?솉Ꚃ?䊁榁ꚁ궔뚐広䎃纃鎃侃춂䎔펈䊁벑澂抂沗첂徃䎃境䖁熂澂뮔?讌쪉?궋Ꞑ랂?첂얂춂ꂂ?�릂?䊁枎炗첂�춂늂趒펈궂뺂뎂ꊂ䊁ꚁ檁?ꂁ极䚋?梁욂ꊂꒂ枃誃䮃宁玍히즂?䆁��뎖?辌즂궔꺓랂?䊁붂뺂떂䆁极䚋?梁玍히튎ꪂ變咔璗첂뎐첑䆁�붂箖�岔즂슂ꊂ쒂力涒얂좂꾂?캂좂?좂ꊂ䊁?箖�岔첂䲗?추춈춂䎃澃覃嚃斃䊃첂蚒첂�䊁
□葛乃葉が自身に祈ることで補正をかけることも可能。ただしこの行為によって彼女の自我と異能は段階的に破壊され、最終的には葛乃葉そのものが消滅する
■Sub:箱守あさな
はこもりあさな。
しのだの杜の管理人。くせのない黒髪をショートボブにそろえ、質素な和装で公園内の掃除などを行っている。
正体は“座敷童子”と呼ばれるあやかし。
本来は穏やかで、頑張り屋な性格。葛子の助けになろうと、普段はしっかり者の仮面を被っている。
所持する異能は【箱守】。
“家”と定めた領域の境界線に障壁を作り、外界から遮断する。障壁の強度は領域の広さに反比例。
また、領域内の対象を自由に選択し、領域外に排出することが可能。
「とまあ、困ったことにはなっておるのじゃが」
「だからと言って、皆の悩みはなくならぬ!」
「さあゆくぞ! 今宵も佳き頃、佳き宵、佳き眠気!」
「おやすみ前のひととき、わしの声にまどろみを
委ねてはいかが? 皆さん一緒に、はいせーのっ」
『Stay tuned for the FOXNET RADIO
coming up next!!』
『【くずこさん、こんばんは!】こんばんは~なのじゃ~!』
■FOXNET RADIO
おきつねっとラジオ。
犬前葛子がメインパーソナリティを務めるラジオ番組。
放送時間は深夜、近頃は昼時に出張放送も行っている。生放送。
彼女が務める民放ラジオ局から電波は発信されており、通常のラジオ機器のほか、携帯端末のアプリからも放送を聴くことができる。
また各地の喫茶店や飲食店と契約し、店内放送としてラジオを配信するサービスも行っている。
(投稿フォーム http://lisge.com/ib/talk.php?p=3234)
■いただきもの
・ICON27
蒼さん(ENo.26)より。
・キャラクターイラスト(コミッション依頼にて)
ねこれーさん(ENo.783)より。
・ICON10~24(コミッション依頼にて)
83さん(@8Tanzanite3)より。
ありがとうなのじゃ!
手に結ぶ 月に宿れる月影の
在るか亡きかの 世にこそ在りつれ
■犬前葛子
種族 狐疑(前・混成狐神)
年齢 約2200歳
身長 149cm
体重 47kg
異能 伽藍夙(がらんつとめて)
陣営 イバラシティ
記憶の引き継ぎ あり(ハザマでの記憶はハザマ内でのみ取得)
イバライン http://lisge.com/ib/talk.php?p=1765
============================
■
稲穂の色の髪に、同じ色の瞳。
古風な言葉遣いに、教え諭すような言葉。
胸元には首から紐で下げた、小さな白金糸の御守り。
民営ラジオでは人気パーソナリティ、通称“くずこさん”。
どこか浮世離れしつつ、茶目っ気たっぷりな俗っぽさも持ち併せる女性。
果たしてその正体は、ヒトではない。
怪異、あやかし、妖怪、神使。
そう呼ばれるもの達の重鎮──“葛乃葉狐”が他の狐たちの力を受け継ぎ、主神“宇迦之御魂神”の権能すらも取り込んで現代まで在り続けた。そんな、常ならぬ狐の総体、混成狐神。
それが、安倍葛子──平行世界のイバラシティにおける、彼女の本性であった。
■
そして現在、犬前葛子は世界線転移の際に起きた“とある出来事”の影響により、狐としてのすべての権能を失っている。
この世界線において、彼女は“犬前葛子”である。
しかし同時に、前世界線に存在した狐神の成れの果て、ヒトでもなければあやかしでもカミでもないあわいものである。
故、彼女の今の正体は。
誰が呼んだか、己が正体すら失った哀れな狐を“狐疑(こぎ)”と云う。
■異能名【伽藍夙】[がらんつとめて]
種別別称:Ⅳ類特型(類型無し-ユニークスキル)
効果:
対象の異能・超常・異質を鎮静させる。
また、効力の及んだ事象からは存在意義を削り取る。同事象は一定時間発生しづらくなる。
知生体に対して効力が及んだ場合、対象は強い睡魔に襲われる。
能動的に発動し、対象を選択する“匁(もんめ)”
身にまとい、受動的に減衰させる“累(かさね)”
の2種類が存在する。
上記の2種は共に発動後、匁は自立稼働する体高80cmほどの巨大な狐として、累は椿の花が描かれた羽織着物として視認が可能。両者ともに白く半透明なエフェクトであり、物理的な防御力はない。
葛乃葉そのものとは一切関係のない出自の力である。
彼女の元の異能はこの伽藍夙によって消滅寸前まで鎮静させられているため、使用は不可能。
狐疑はこの異能に自らの在り方を再定義されかかっており、それが完遂されると“虚疑”として覚醒を果たす。
別名“星狩りの閨”。
これは、ヒトの夜への怖れそのもの。
怖ろしいものへの、苛烈な害意が形を成したもの。
ヒトの心が神秘を蹂躙する、その体現。
外敵殺し、守護と排斥の極致。
異能名【宇迦信太へぐい】[うかしのだへぐい]
種別別称:異能登録データ無し・違法所持異能
効果:
ꂁ�岔쾕겐삎첑瞁變咔璗碁?徐릓徐折䆁ꢂ?톂횊䆘溑?芃悃宁璃즂떂붂욂皎?䆁熃枃庌첂삎첑䊁붉ꦂ즂�쮈떂쒂ꊂ?꾂얂춂좂궂䆁뚐?붂?슌첂�岔䊁?极變咔璗梁ꢂ?톂极徐折?첂쾌梁ꪂ鶎슂䎃膃宁垃즂璕辐랂?岔춗?ꆕ钐?Ꚃ䆁玍枎랂?놂욂ꪂ슉岔䊁삎玍슉岔좂岔춗춂좈몉첂쪒?䊁?䖁?좂斃貃炃境岔춗?䖁芍碓좂뚌暘䆁뚌炏첂玍枎岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁?曦璕店岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁玕涊?좂庉붖놊슏岔춗?䖁侔꺓춗?䖁쾌첂ꢎ욂䮐?榁沎?檁ꪂ뚐Ꚃ?䖁殚澊䖁꺒澊ꪂ궔䊒랂?䖁ﮌ늒ꪂ쎌䲏궂좂?ꂁ庉붖놊슏岔춗禁侎쾌䆉窗릓榁�꾂슂ꢂ?�?ꒂ잂ꒂ檁突?䲖?徐욂뮂첂徐枎얂ꂂ?쾌?꾓?讎랂?꾖풊悓뎏䆁�붂횊䆘溑?얂ꂂ?徐?첂䆉窗璎悓?麍?뺂䆁變咔璗첂얍?�岔䊁?禁徐榁變咔璗檁즂䚋?ꢁ䚋솂붂튎즂颗皉?붂?랂突욂ꊂꒂ皃趃媃境얂䆁캑�첂玕涊?庉붖?䒍펈䦓즂쾕嶓뎂릂?䊁?ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ?ꂁ熂澂?즂鞉ꊂ쒂䆁캑�첂徃䎃境뮔?庉?䮕皗욂랂?玍꺓즂?鶕좂?뎐?솉Ꚃ?䊁榁ꚁ궔뚐広䎃纃鎃侃춂䎔펈䊁벑澂抂沗첂徃䎃境䖁熂澂뮔?讌쪉?궋Ꞑ랂?첂얂춂ꂂ?�릂?䊁枎炗첂�춂늂趒펈궂뺂뎂ꊂ䊁ꚁ檁?ꂁ极䚋?梁욂ꊂꒂ枃誃䮃宁玍히즂?䆁��뎖?辌즂궔꺓랂?䊁붂뺂떂䆁极䚋?梁玍히튎ꪂ變咔璗첂뎐첑䆁�붂箖�岔즂슂ꊂ쒂力涒얂좂꾂?캂좂?좂ꊂ䊁?箖�岔첂䲗?추춈춂䎃澃覃嚃斃䊃첂蚒첂�䊁
□葛乃葉が自身に祈ることで補正をかけることも可能。ただしこの行為によって彼女の自我と異能は段階的に破壊され、最終的には葛乃葉そのものが消滅する
■Sub:箱守あさな
はこもりあさな。
しのだの杜の管理人。くせのない黒髪をショートボブにそろえ、質素な和装で公園内の掃除などを行っている。
正体は“座敷童子”と呼ばれるあやかし。
本来は穏やかで、頑張り屋な性格。葛子の助けになろうと、普段はしっかり者の仮面を被っている。
所持する異能は【箱守】。
“家”と定めた領域の境界線に障壁を作り、外界から遮断する。障壁の強度は領域の広さに反比例。
また、領域内の対象を自由に選択し、領域外に排出することが可能。
「とまあ、困ったことにはなっておるのじゃが」
「だからと言って、皆の悩みはなくならぬ!」
「さあゆくぞ! 今宵も佳き頃、佳き宵、佳き眠気!」
「おやすみ前のひととき、わしの声にまどろみを
委ねてはいかが? 皆さん一緒に、はいせーのっ」
『Stay tuned for the FOXNET RADIO
coming up next!!』
『【くずこさん、こんばんは!】こんばんは~なのじゃ~!』
■FOXNET RADIO
おきつねっとラジオ。
犬前葛子がメインパーソナリティを務めるラジオ番組。
放送時間は深夜、近頃は昼時に出張放送も行っている。生放送。
彼女が務める民放ラジオ局から電波は発信されており、通常のラジオ機器のほか、携帯端末のアプリからも放送を聴くことができる。
また各地の喫茶店や飲食店と契約し、店内放送としてラジオを配信するサービスも行っている。
(投稿フォーム http://lisge.com/ib/talk.php?p=3234)
■いただきもの
・ICON27
蒼さん(ENo.26)より。
・キャラクターイラスト(コミッション依頼にて)
ねこれーさん(ENo.783)より。
・ICON10~24(コミッション依頼にて)
83さん(@8Tanzanite3)より。
ありがとうなのじゃ!
30 / 30
266 PS
チナミ区
D-2
D-2













| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | たけのこ | 食材 | 20 | [効果1]貫撃10(LV15)[効果2]器用10(LV25)[効果3]深手20(LV35) | |||
| 4 | 伽藍ノ胴 | 防具 | 20 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 巫虚鈴 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 7 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 8 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 9 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 10 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 12 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
| 13 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 14 | 雪幻 | 装飾 | 45 | 回復10 | - | - | |
| 15 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 16 | 禁断じゃない果実 | 食材 | 5 | [効果1]攻撃5(LV5)[効果2]防御5(LV5)[効果3]器用5(LV5) | |||
| 17 | 禁断じゃない果実 | 食材 | 5 | [効果1]攻撃5(LV5)[効果2]防御5(LV5)[効果3]器用5(LV5) | |||
| 18 | 半濁音チャプチェ | 料理 | 45 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 19 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||
| 20 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 22 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 防具 | 50 | 防具作製に影響 |
| 料理 | 2 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| 練1 | ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 |
| 練1 | エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| 練1 | リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| コールドウェイブ | 5 | 0 | 80 | 敵4:水撃&凍結+自:炎上 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 練2 | ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| 練1 | デイドリーム | 5 | 0 | 80 | 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 |
| フィックルティンバー | 5 | 0 | 80 | 敵:風痛撃&3D6が11以上なら風痛撃 | |
| アトラクト | 5 | 0 | 50 | 自:HATE・連続増 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| マナポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| 練1 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| 練1 | ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| コールドイミッター | 5 | 0 | 120 | 敵貫:水撃&凍結+自:精確火撃&炎上 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| ディスインフェクト | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+肉体変調を守護化 | |
| リザレクション | 5 | 0 | 150 | 味傷:HP増+瀕死ならHP増 | |
| ワイドアナリシス | 5 | 1 | 100 | 自:朦朧+味全:DX増(3T)&名前に「罠」を含む付加効果のLV減 | |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| ポーションラッシュ | 5 | 0 | 240 | 味傷6:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 対症下薬 | 5 | 3 | 0 | 【HP回復後】対:変調軽減+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 戴天 | 5 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】自:次受ダメ減+瀕死なら守護 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ファイアレイド | [ 3 ]デアデビル | [ 3 ]イレイザー |
| [ 3 ]サモン:ハンター | [ 3 ]ポーションラッシュ | [ 2 ]ファイアダンス |
| [ 3 ]五月雨 |

PL / Alphecca