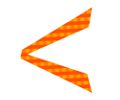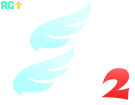<< 4:00~5:00




巨体が崩れ落ちる。
洞窟の天井が落ちてきたと錯覚するほどの音をたてて、最後の関門である巨大な蛇が倒れ落ちた。
異能のある世界では、敵もまた異能を持つ。
無限に再生する巨大な蛇の化物なんてものも、当然のように存在するわけだ。
もっとも、場合によっては、子供二人で化物を細切れにすることだってできる。
異能にはそれぞれリスクや代償というものがあって、失うものが大きいほどその力は大きい傾向がある。
ニレリアの異能は捧げた代償の分だけ威力が増していくものだから、
代償さえ準備することができれば、何だって倒すことができた。
不死鳥の聖杯とは、とても相性がいい。
とはいえ、全員がそれほどの力を持つわけではないようだ。
これだけの力を個人で有することができながら、この国の規模は昔から変わらないのだから。
何百年も昔から、この国はずっと昔のままでいる。
巨大な蛇を倒して、洞窟を踏破した先にあったのは古い神殿だった。
その建物は数階層にもわたる洞窟の奥底とは思えないほど美しく、明らかに人為的な、
それでいて定期的な清掃が行われていることが見て取れた。
その周囲には青白く光る湖が広がっていて、
水辺には同じく青い花が生い茂り空には金色の光が舞っていた。
きらきらと輝く光の粒が、次々に水面に落ちては消えていく。
あれはアマノヒホタルだ。
この国の洞窟に固有の種であり、明け方に飛ぶことから朝を告げる光と言われる。
宙を埋め尽くす光景はまるで星が降るかのようで、日が登る前触れと言われればそう見えなくもない。
それが今しがたニレリアが両手に抱えこんだカエルに丸呑みにされるのを見ながら、
なんだかなとため息をついた。
もう一度辺りを見渡してみる。
綺麗さの代わりに神秘さを感じないのは、ここが神々を祀る古代の神殿や異端の隠れ家などではなく、
元々儀式を行うために造られたもので今も国の手により管理されているからだろうか。
いくつか足跡もあり、既にこの洞窟を踏破したものの存在や、管理する人間の気配がほうぼうに感じられた。
苦労して抜けてきた身としては、少し悲しくなる光景だが、ニレリアの言うようにこれは単なる篩い分け。
そういうものだと気を立て直す。
カエルを抱えたままのニレリアと一緒に神殿に足を踏み入れてみれば、
待っていたのは笑顔で手を差し伸べる現国王とメイド達、資格者を記録する役割を持った偉い神官様、
それに、ニレリアの姉の姿だった。
暇なのだろうか。それともこれも仕事なのだろうか。
娯楽として見に来たとしか思えないその様子に、ため息がまたひどくなった。
二人にとっては血まみれの体とぼろぼろの服で這いずる死にものぐるいの冒険譚も、
大人達にとってみれば子供の成長を見守るためのイベントみたいなものだったというわけだ。
王の資格が欲しくて日々挑んでいると言っていたあたり、本来ここはもっと気軽に挑戦できる場所なのだろう。
もっともニレリアの言うようにやけにレベルが高すぎる気がしないわけではなかったが、
それでも、これはいつも通りの日常の一コマでしかない。
ため息を落とす中、ふと顔をあげるとニレリアの姉がこっちを見ていた。
あまりにも明るくて、ニレリアを数倍濃くしたような、眩しく輝く太陽のような女性だ。
ニレリアの唯一の家族であることもあり小さい頃からよく知っている。
"おはようハイネ君!今日も元気にしてたかな?"
"クッキー焼いたけど食べない?今ならチョコチップもサービスしておくよ"
"えっ、足りない!?……むむむ、しかたない。お姉さんのとっておきをあげよう"
"チョコアイスというものがあってだね、これをクッキーに乗せると絶品なのさ!"
ころころ変わる表情と声が浮かぶ。振り付けまで浮かぶ。
ニレリアのことを心から愛していて、驚くほど甘い。
お祝い事には山のような料理を作るのが習わしだったから、よく分けてもらった。
あまりにも美味しいので、レシピをいくつか教えてもらったほどだ。
なるほど、最近やる気がなくなったようだとは聞いていたが、やる気がないというよりは目が死んでいる。
元々顔立ちが整っていると評判ではあったが、今はまるで人形のようだ。
踏破を祝い、輪になって踊る隣のメイド達や年甲斐もなくはしゃぐ現国王と比べるとあまりにも浮いて見える。
踏破者を置いておいてどんどん盛り上がる現国王に白けたと言うならば理解もできるというものだが。
友達の姉や兄に話しかける時、どう呼んでいいのかわからない時がある。今がそれだ。
だけれど、それでもそれなりに長い付き合いだから、こう話しかけた時に次にどうくるかはよく分かっている。
こういう風に呼ぶと、笑顔で頭に手を載せてくる。
くすくすと笑い、髪の毛をわしゃわしゃとして、
“もー……なぁじゃないよハイネ君。私の名前は―――”
そんな風に笑顔で怒ってくるのだ。
想像しただけで釣られて笑いそうになる。しかし仕方がない。
ニレリアを数倍濃くしたような存在に、釣られないわけがないのだ――
帰ってきたのは、驚くほど平坦な声だった。
たった二言でわかるほど、抑揚が感じられない。
記憶とのあまりの落差に、体調不良を疑ってしまう。
それどころか、別人ではないかと疑いたくなるほどだ。
やる気がないというのも確かにうなずけるのだが、何かそれ以上の原因があるように思えた。
自分勝手な話だが、違和感を感じていた。
少なくとも、ニレリアよりも落ち着いていることなどありえないのだ。例え、大人になって落ち着いたとしても。
そうか、と一呼吸をあける。
いくつかの質問にも反応は同じだった。
あらゆる質問に返事をする。しかしそれ以外のことはしない。
これをやる気がないと解釈すればそうだろう。
だが、明らかに普通ではないように思えた。
駆け寄ってきたニレリアに質問を浴びせる。
何が、という風な反応に、わずかに不安が増した。
ニレリアが首を傾げた。
どうやらおかしいとは思っていなかったようで、何がおかしいのか悩んでいる様子だ。
ニレリアが動きを止めた。
なんだそれが知りたかったのか、と言いたげに笑顔で口を開いた。
何故かその笑顔に、不安が増していく。
いつもは元気をくれるその顔に、何か自分がどこかで道を踏み外したような、そんな不安がついてくる。



ENo.270 レン とのやりとり

ENo.819 十村蘇芳 とのやりとり













オオホタル と別れました。
疾走雑草 をエイドとして招き入れました!
すずめ(586) から 金串 を受け取りました。
響鳴LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ウレイ(419) により ItemNo.7 美味しい果実 から料理『フルーティー春巻き』をつくってもらいました!
⇒ フルーティー春巻き/料理:強さ82/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
ツクモ(106) の持つ ItemNo.4 赤いマフラー に ItemNo.8 古雑誌 を付加しました!
クリス(169) の持つ ItemNo.4 スティックブレイド に ItemNo.10 柳 を付加しました!
ウレイ(419) の持つ ItemNo.12 瘴気を纏ったバール に ItemNo.13 皮 を付加しました!
よなか(268) とカードを交換しました!
鉄の三角定規 (クライオセラピー)

パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
デスペラート を研究しました!(深度0⇒1)
阿修羅 を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
ヴィジランス を習得!
マーチ を習得!
コンテイン を習得!
チャージ を習得!
ユニティ を習得!
ブレイブハート を習得!
カウンター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ツクモ(106) は ラベンダー を入手!
クリス(169) は 木瓜 を入手!
ハイネ(416) は 山査子 を入手!
ウレイ(419) は 山査子 を入手!
ハイネ(416) は ダンボール を入手!
ツクモ(106) は 剛毛 を入手!
クリス(169) は 毛皮 を入手!
ハイネ(416) は ネジ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ハイネ(416) のもとに ダンボールマン が軽快なステップで近づいてきます。
ハイネ(416) のもとに ぞう が恥ずかしそうに近づいてきます。
ハイネ(416) のもとに 化け狐 がスキップしながら近づいてきます。



チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調6⇒5)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調5⇒4)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調4⇒3)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- ツクモ(106) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- クリス(169) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- ハイネ(416) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- ウレイ(419) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――












梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・














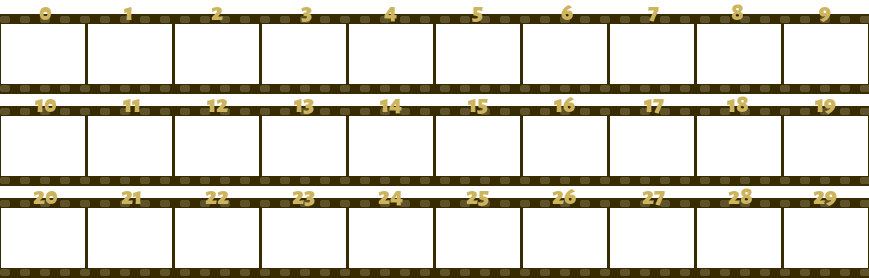


































No.1 疾走雑草 (種族:疾走雑草)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [戦闘:エイド2]OK. [戦闘:エイド3]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



巨体が崩れ落ちる。
洞窟の天井が落ちてきたと錯覚するほどの音をたてて、最後の関門である巨大な蛇が倒れ落ちた。
| ニレリア 「やっぱり単なるふるい落としの試験にあっていいものじゃないよ。明らかにレベル違いってやつだね」 |
異能のある世界では、敵もまた異能を持つ。
無限に再生する巨大な蛇の化物なんてものも、当然のように存在するわけだ。
もっとも、場合によっては、子供二人で化物を細切れにすることだってできる。
異能にはそれぞれリスクや代償というものがあって、失うものが大きいほどその力は大きい傾向がある。
ニレリアの異能は捧げた代償の分だけ威力が増していくものだから、
代償さえ準備することができれば、何だって倒すことができた。
不死鳥の聖杯とは、とても相性がいい。
とはいえ、全員がそれほどの力を持つわけではないようだ。
これだけの力を個人で有することができながら、この国の規模は昔から変わらないのだから。
何百年も昔から、この国はずっと昔のままでいる。
| ニレリア 「流石に来るのが早すぎたかな。今度はもっとレベルを上げてからくることにしよう」 |
| ハイネ 「次があるものなのか」 |
| ニレリア 「また挑む者達に向けたメッセージということでひとつ」 |
巨大な蛇を倒して、洞窟を踏破した先にあったのは古い神殿だった。
その建物は数階層にもわたる洞窟の奥底とは思えないほど美しく、明らかに人為的な、
それでいて定期的な清掃が行われていることが見て取れた。
その周囲には青白く光る湖が広がっていて、
水辺には同じく青い花が生い茂り空には金色の光が舞っていた。
きらきらと輝く光の粒が、次々に水面に落ちては消えていく。
あれはアマノヒホタルだ。
この国の洞窟に固有の種であり、明け方に飛ぶことから朝を告げる光と言われる。
宙を埋め尽くす光景はまるで星が降るかのようで、日が登る前触れと言われればそう見えなくもない。
| ニレリア 「ハイネ、カエル捕まえた!」 |
 |
カエル 「モシャモシャ」 |
| ハイネ 「返してきなさい」 |
それが今しがたニレリアが両手に抱えこんだカエルに丸呑みにされるのを見ながら、
なんだかなとため息をついた。
| ハイネ 「……」 |
もう一度辺りを見渡してみる。
綺麗さの代わりに神秘さを感じないのは、ここが神々を祀る古代の神殿や異端の隠れ家などではなく、
元々儀式を行うために造られたもので今も国の手により管理されているからだろうか。
いくつか足跡もあり、既にこの洞窟を踏破したものの存在や、管理する人間の気配がほうぼうに感じられた。
苦労して抜けてきた身としては、少し悲しくなる光景だが、ニレリアの言うようにこれは単なる篩い分け。
そういうものだと気を立て直す。
| ニレリア 「あれ、どうやらゴールテープを持ってくれている人がいるみたいだよ。いつのまに」 |
カエルを抱えたままのニレリアと一緒に神殿に足を踏み入れてみれば、
待っていたのは笑顔で手を差し伸べる現国王とメイド達、資格者を記録する役割を持った偉い神官様、
それに、ニレリアの姉の姿だった。
暇なのだろうか。それともこれも仕事なのだろうか。
娯楽として見に来たとしか思えないその様子に、ため息がまたひどくなった。
二人にとっては血まみれの体とぼろぼろの服で這いずる死にものぐるいの冒険譚も、
大人達にとってみれば子供の成長を見守るためのイベントみたいなものだったというわけだ。
王の資格が欲しくて日々挑んでいると言っていたあたり、本来ここはもっと気軽に挑戦できる場所なのだろう。
もっともニレリアの言うようにやけにレベルが高すぎる気がしないわけではなかったが、
それでも、これはいつも通りの日常の一コマでしかない。
ため息を落とす中、ふと顔をあげるとニレリアの姉がこっちを見ていた。
あまりにも明るくて、ニレリアを数倍濃くしたような、眩しく輝く太陽のような女性だ。
ニレリアの唯一の家族であることもあり小さい頃からよく知っている。
"おはようハイネ君!今日も元気にしてたかな?"
"クッキー焼いたけど食べない?今ならチョコチップもサービスしておくよ"
"えっ、足りない!?……むむむ、しかたない。お姉さんのとっておきをあげよう"
"チョコアイスというものがあってだね、これをクッキーに乗せると絶品なのさ!"
ころころ変わる表情と声が浮かぶ。振り付けまで浮かぶ。
ニレリアのことを心から愛していて、驚くほど甘い。
お祝い事には山のような料理を作るのが習わしだったから、よく分けてもらった。
あまりにも美味しいので、レシピをいくつか教えてもらったほどだ。
| ハイネ 「……?」 |
なるほど、最近やる気がなくなったようだとは聞いていたが、やる気がないというよりは目が死んでいる。
元々顔立ちが整っていると評判ではあったが、今はまるで人形のようだ。
踏破を祝い、輪になって踊る隣のメイド達や年甲斐もなくはしゃぐ現国王と比べるとあまりにも浮いて見える。
踏破者を置いておいてどんどん盛り上がる現国王に白けたと言うならば理解もできるというものだが。
| ハイネ 「……」 |
| ハイネ 「……なぁ」 |
友達の姉や兄に話しかける時、どう呼んでいいのかわからない時がある。今がそれだ。
だけれど、それでもそれなりに長い付き合いだから、こう話しかけた時に次にどうくるかはよく分かっている。
こういう風に呼ぶと、笑顔で頭に手を載せてくる。
くすくすと笑い、髪の毛をわしゃわしゃとして、
“もー……なぁじゃないよハイネ君。私の名前は―――”
そんな風に笑顔で怒ってくるのだ。
| ハイネ 「ふ……」 |
想像しただけで釣られて笑いそうになる。しかし仕方がない。
ニレリアを数倍濃くしたような存在に、釣られないわけがないのだ――
| 「はい」 |
| ハイネ 「……」 |
帰ってきたのは、驚くほど平坦な声だった。
たった二言でわかるほど、抑揚が感じられない。
| ハイネ 「……もしかして体調が悪いのか。悪いところがあるのなら、何でも治すぞ」 |
記憶とのあまりの落差に、体調不良を疑ってしまう。
それどころか、別人ではないかと疑いたくなるほどだ。
やる気がないというのも確かにうなずけるのだが、何かそれ以上の原因があるように思えた。
| ハイネ 「はい、体調は悪くありません」 |
| ハイネ 「……」 |
自分勝手な話だが、違和感を感じていた。
少なくとも、ニレリアよりも落ち着いていることなどありえないのだ。例え、大人になって落ち着いたとしても。
| ハイネ 「あー……そういうのは似合わないと思うけど」 |
| ハイネ 「えーっと」 |
| ハイネ 「……もしかして、からかっているのか?」 |
| ハイネ 「からかっていません」 |
そうか、と一呼吸をあける。
| ハイネ 「……なぜ喜んでやらない?」 |
| 「私はとても喜んでいます」 |
| ハイネ 「……」 |
| ハイネ 「なぁ、ニレリア」 |
| 「はい、私はニレリアです」 |
| ハイネ 「違う、黙っていてくれ」 |
いくつかの質問にも反応は同じだった。
あらゆる質問に返事をする。しかしそれ以外のことはしない。
これをやる気がないと解釈すればそうだろう。
だが、明らかに普通ではないように思えた。
| ニレリア 「どうしたのハイネ。こっちはだいたい終わったよ。詳しいことはまた後日だってさ」 |
| ハイネ 「あれは、どうしたんだ」 |
| ニレリア 「あれ?あぁ、姉さんのこと」 |
駆け寄ってきたニレリアに質問を浴びせる。
何が、という風な反応に、わずかに不安が増した。
| ニレリア 「言ったじゃないか。やる気がなくなったみたいだって」 |
| ハイネ 「あれはやる気とかそういうものじゃないだろう、もっと何か――」 |
| ニレリア 「そうかな」 |
| ハイネ 「そうだろう」 |
| ニレリア 「……」 |
| ニレリア 「……」 |
ニレリアが首を傾げた。
どうやらおかしいとは思っていなかったようで、何がおかしいのか悩んでいる様子だ。
| ハイネ 「あれは、いつからだ」 |
| ニレリア 「……」 |
ニレリアが動きを止めた。
なんだそれが知りたかったのか、と言いたげに笑顔で口を開いた。
何故かその笑顔に、不安が増していく。
いつもは元気をくれるその顔に、何か自分がどこかで道を踏み外したような、そんな不安がついてくる。
| ニレリア 「あぁ、そういうこと。それはさっき言ったとおりだよ。ハイネ」 |
| ニレリア 「全部ハイネが治してくれたんじゃないか」 |
| ニレリア 「起きてからずっとあんな感じ。助けてもらった、あの日からね」 |



ENo.270 レン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.819 十村蘇芳 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||



 |
クリス 「何かさー。最近動物に嫌われてない……?」 |
| ハイネ 「鹿肉が手に入るかと思ったが、消えてなくなってしまったな」 |
| ハイネ 「自分たちで食べれないまでも、餌になるかと思ったのだが」 |
 |
ウレイ 「えっ……あの鹿の肉を食べる気でいたの??!あれ食べていい鹿なの?」 |
 |
ウレイ 「……ってああ、餌」 |
 |
ウレイ 「餌……?」 |





狐火の徒
|
 |
アライアンス・レイダーズ
|



オオホタル と別れました。
疾走雑草 をエイドとして招き入れました!
すずめ(586) から 金串 を受け取りました。
 |
すずめ 「使えると思います」 |
響鳴LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ウレイ(419) により ItemNo.7 美味しい果実 から料理『フルーティー春巻き』をつくってもらいました!
⇒ フルーティー春巻き/料理:強さ82/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
 |
ウレイ 「餃子の皮みたいなので包んで揚げてみたら、パイみたいなデザートの食感になるんじゃないかなって思うんだけど。どうかな?」 |
ツクモ(106) の持つ ItemNo.4 赤いマフラー に ItemNo.8 古雑誌 を付加しました!
クリス(169) の持つ ItemNo.4 スティックブレイド に ItemNo.10 柳 を付加しました!
ウレイ(419) の持つ ItemNo.12 瘴気を纏ったバール に ItemNo.13 皮 を付加しました!
よなか(268) とカードを交換しました!
鉄の三角定規 (クライオセラピー)

パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
デスペラート を研究しました!(深度0⇒1)
阿修羅 を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
ヴィジランス を習得!
マーチ を習得!
コンテイン を習得!
チャージ を習得!
ユニティ を習得!
ブレイブハート を習得!
カウンター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ツクモ(106) は ラベンダー を入手!
クリス(169) は 木瓜 を入手!
ハイネ(416) は 山査子 を入手!
ウレイ(419) は 山査子 を入手!
ハイネ(416) は ダンボール を入手!
ツクモ(106) は 剛毛 を入手!
クリス(169) は 毛皮 を入手!
ハイネ(416) は ネジ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ハイネ(416) のもとに ダンボールマン が軽快なステップで近づいてきます。
ハイネ(416) のもとに ぞう が恥ずかしそうに近づいてきます。
ハイネ(416) のもとに 化け狐 がスキップしながら近づいてきます。



チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調6⇒5)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調5⇒4)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調4⇒3)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- ツクモ(106) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- クリス(169) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- ハイネ(416) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- ウレイ(419) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――







これだから最近の若者は
|
 |
狐火の徒
|




チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・





ENo.416
薊野 灰音



氏名:薊野 灰音【アザミノ ハイネ】
年齢:20 歳
身長:180 cm
創峰大学の2年生。
1年間別の大学に通っていたが退学し今の大学に入り直した。
必要科目ぎりぎりでやる気がないように見えるが講義態度はいたってまじめ。書かれるノートは参考書よりも参考書らしい。
講義を受けていない時は喫煙所でタバコをふかす日々である。
住み込みバイトで学費を稼いでおり、授業がない日と夜間はカスミ区の喫茶店で珈琲の味を追求し続けている。恐らく、授業よりも本気度が高い。
常に吹かしているタバコは異能のせいか、灰は落ちず匂いもしない。本来は花の香りがするらしい。
------
【異能】
不死鳥の聖灰
灰や燃え痕に必要な元素を加えることで、元の形を作り出すことができる再生の異能。一方で、水の入った紙コップに水は戻らないし、形のないものは元に戻すことはできない。
【ペット】
カエル
よく左肩に乗っている不思議な生き物。虫などを食べない代わりに無機物を丸呑みにして形を真似ることができる。擬態の一種のようであるが、その精度は異常なほど高い。イバラシティの異能の影響を受けた変異種であると考えられている。食べたものを吐き出すこともできるため、バッグの代わりになっている。
年齢:20 歳
身長:180 cm
創峰大学の2年生。
1年間別の大学に通っていたが退学し今の大学に入り直した。
必要科目ぎりぎりでやる気がないように見えるが講義態度はいたってまじめ。書かれるノートは参考書よりも参考書らしい。
講義を受けていない時は喫煙所でタバコをふかす日々である。
住み込みバイトで学費を稼いでおり、授業がない日と夜間はカスミ区の喫茶店で珈琲の味を追求し続けている。恐らく、授業よりも本気度が高い。
常に吹かしているタバコは異能のせいか、灰は落ちず匂いもしない。本来は花の香りがするらしい。
------
【異能】
不死鳥の聖灰
灰や燃え痕に必要な元素を加えることで、元の形を作り出すことができる再生の異能。一方で、水の入った紙コップに水は戻らないし、形のないものは元に戻すことはできない。
【ペット】
カエル
よく左肩に乗っている不思議な生き物。虫などを食べない代わりに無機物を丸呑みにして形を真似ることができる。擬態の一種のようであるが、その精度は異常なほど高い。イバラシティの異能の影響を受けた変異種であると考えられている。食べたものを吐き出すこともできるため、バッグの代わりになっている。
3 / 30
469 PS
チナミ区
O-16
O-16







No.1 疾走雑草 (種族:疾走雑草)
 |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| ブレイブハート | 5 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| エアスラッシュ | 5 | 0 | 110 | 敵:5連風撃 | |
| 神風 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘離脱前】敵傷:風痛撃 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 見切 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率増 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 衝撃波 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】対:精確風撃&連続減 |
最大EP[20]
No.2 こぐま (種族:こぐま)
|
|
|||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| カウンター | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| デスペラート | 5 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 | |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 背水 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど被攻撃ダメージ減 |
最大EP[20]
No.3 大黒猫 (種族:大黒猫) |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| 決3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 巧技 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX・LK増 | |
| 見切 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率増 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 防刃モッズコート | 防具 | 30 | 活力10 | 風柳10 | - | |
| 5 | 銀色のシガーケース | 装飾 | 35 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 杉 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV30)[防具]放盲15(LV25)[装飾]舞盲10(LV20) | |||
| 7 | フルーティー春巻き | 料理 | 82 | 攻撃10 | 防御10 | 強靭15 | |
| 8 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 9 | 金串 | 武器 | 40 | 治癒10 | - | - | 【射程2】 |
| 10 | シガレット「杉」 | 装飾 | 90 | 舞盲10 | - | - | |
| 11 | 金毛弾 | 武器 | 40 | 束縛10 | - | - | 【射程2】 |
| 12 | 山査子 | 素材 | 15 | [武器]防疫15(LV30)[防具]耐疫10(LV20)[装飾]快癒10(LV25) | |||
| 13 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 14 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 使役 | 15 | エイド/援護 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 45 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 6 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 6 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| ヴィジランス | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+次受ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| リライアンス | 5 | 0 | 120 | 自従傷:MHP・DF・HL増 | |
| シュリーク | 5 | 0 | 50 | 敵貫:朦朧+自:混乱 | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| パワーブースター | 5 | 0 | 40 | 自従:AT・DF・DX・AG・HL増(3T) | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 決3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブロック | 6 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ユニティ | 5 | 0 | 120 | 自:応報LV増+自従全:護衛 | |
| ブレイブハート | 5 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カウンター | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| チャームダンス | 5 | 0 | 140 | 敵全:魅了 | |
| マインドリカバー | 6 | 0 | 0 | 自:連続減+SP30%以下ならSP増+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| エレジー | 5 | 0 | 100 | 敵:攻撃&AT・DX減(2T) | |
| ラッシュ | 6 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| モラール | 5 | 0 | 210 | 味全:DX増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 狂歌乱舞 | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:混乱+自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増(2T) |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
降り注ぐてるてる坊主 (クイック) |
0 | 50 | 敵:3連撃 | |
|
カラーカスケード (ショックウェイブ) |
0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
|
インスタント・サーヴァント (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
|
火行式『領火』 (スカイディバイド) |
1 | 150 | 敵貫:風撃&風耐性減 | |
| 決3 |
波打つ秋水 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
|
鉄の三角定規 (クライオセラピー) |
0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]ダウンフォール | [ 1 ]リザレクション |
| [ 1 ]バーニングチューン | [ 1 ]阿修羅 | [ 1 ]チャクラグラント |
| [ 1 ]五月雨 | [ 1 ]ヒートイミッター | [ 1 ]チャージ |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]グランドクラッシャー | [ 1 ]デアデビル |
| [ 1 ]ハードブレイク | [ 1 ]デスペラート | [ 1 ]アリア |
| [ 1 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]イグニス | [ 1 ]パワフルヒール |

PL / 揚げノワール