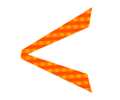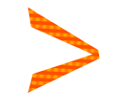<< 1:00~2:00




これは記だ。当然のことながら。
湯沸かし器を新調した。
それも、ただの湯沸かし器ではない。スイッチ一つで勝手にお湯が沸くハイテクノロジーな代物だ。寒い部屋で一人孤独に湯を沸かす自分のことを見かねた上司が提案してくれたもので、確かに冬場は辛いものがあったため、素直に厚意に甘えることにした。話が決まるや否や善は急げとばかりに年末にも向かったエンジョイなんとかというホームセンターに向かうと、大小様々な湯沸かし器を物色し、大きすぎず小さすぎないちょうど良いサイズのものを購入した。押すのがスイッチなのかボタンなのかについては少々論議があったが、普段から円滑なコミュニケーションを心掛けている上司とは円満に解決することが出来た。
年の初めからお金を使うと、その年は散在するという言い伝えもある。しかし、金で生活の質が向上するならばこの手の呪言は甘んじて受け入れるつもりだった──どうせ経費だし。人類の歴史は退化の歴史だ。人は楽をするために科学技術を進歩させ、昨日より明日を楽に生きるために生きてきた。この一杯のカプチーノは歴史の到達点であると同時に、明日にはこの手間すら面倒に感じてしまう退廃の象徴となるだろう。人の欲に限度はないのだから。
スイッチを入れて数分後、ごぼごぼと水の茹る音とともに蒸気が吹き上がる。部屋はまだ寒く、蒸気の量もかなりのものだった。うかつに近づけば一瞬にして眼鏡が曇ってしまう。一瞬とはいえ視界を失うのは極めて危険だが、流石に速度はガスよりも圧倒的に早い。必要なリスクとして受け入れる必要があるだろう。
カプチーノを淹れて飲んだ。クソ寒い中、出社して朝一番に水を汲んでヤカンを火にかけガスで湯を沸かして飲むコーヒーよりもはるかに手がかからない上、魔法瓶に移し替えて冷める心配もない。熱々の熱湯をすする羽目になってまたもや火傷しそうになったのと、その際口元にひげが出来てしまった姿を見て、上司は静かに笑っていた。カプチーノは妙に美味い気がしたが、それは胸の中にしまっておいた。
物事には順序がある。コーヒーを淹れるためにお湯を沸かすように、楽にお湯を沸かすために湯沸かし器を買うように──会話をするためには、何をこなす必要があるのだろうか。長くはない付き合いの関係とはいえ、まさかコミュニケーションの根源について悩まされることになるとは思っていなかった。
「……ここまではわかるかしら。」
「ええと。話は理解しました。概ね……」
「そう、なら、今日の戦闘で必要な物資をキチンと集めること。私からはとりあえず以上よ。何かあるかしら」
まともに報告すら出来ないというのは、最良から最悪まで予想していた状況のひとつではあったが。それでも単に想像でしかなかったことに比べれば、実際にそうなってしまったのとではわけが違った。チャット越しの仮想的なやり取りにはなかった、直接対面して初めて得られた言外の反応は、彼女が貫く言外の拒絶を雄弁に物語っているような気がした。矢継ぎ早にまくし立てられる言葉の数々は、無難な言葉の相槌で勢いが衰えるのを待っているうちに、気づけば会話が打ち切られている。何か意見はと言われても、それは事務的なやりとりであって、本当に意見を求めているわけではないようにすら感じてしまう。
「危機意識については、僕も茅芽さんと共有しているつもりです。こんなところで、死にたくないですし。それに──」
取り付く島もない態度について、当初は不慣れからくるものと思っていた。慣れない環境での苛立たしさ、ストレス、ハザマへの拒否感。そういったものから生じた、いわば八つ当たりのような拒絶だと。事実、イバラシティにおける彼女の印象と比較して、目の前の彼女はあまりにも血色が悪かったため、単なる不健康というよりは精神的なものだろうと予想していた。
しかし、そうではない。そうではなかったのだ。合流すれば何とかなるという過去の甘い幻想は既に朽ち果て、孤独よりもはるかに厄介な問題を抱え込むことになってしまった。有有有利有利有利(アドアドアドバンテージテージ)が、最悪の──これから先が良くなるという前提だが──、あるいは最善の仮説を囁き続ける。彼女の態度が何に根差したものなのか。確かめるには、相応のリスクを支払う覚悟が必要だった。愚かにも、触れずに黙って気づかぬフリをしていたとしても誰も責めないような、絶望的な直感の答え合わせをする覚悟が。
これから口にする言葉は、賭けにもならないと分かりきっていた。全てが終わったゲームにベットするのは愚の骨頂だ。強化された異能が囁き続けている気がした。言葉が多いと言われたのはどこの誰だ。絶対にやめろ。碌なことにならない。
「争事、向吉。誠意に答えよ……”おみくじ”にあった通り、しっかり対応さえすれば、リスクは減りますしね」
抱え込んだ問題は、その複雑さとは裏腹に、皮肉にも明瞭な名前を持つ。
不安、という名を。
戦闘があったのは、渡りに船だったかもしれない。
謎の適性存在ナレハテに続く敵たち、そして話には聞いていたアンジニティ側の人間との決闘。事態への対処という形でやむを得ず行われた二人の初めての共同作業は、二人の間に横たわるであろう暗く深い溝を埋め、つかの間の結束をもたらした。良くも悪くも、悩むことなく頭を空っぽにすることが出来る。
(あまり、深く考えすぎない方が良いのかもしれない)
ワイヤーを振るい、時にワイヤーに使われながら、襲い来る敵を捌いてゆく。無論、笹子さんの存在は常に気にかけながら。ここにいるのは二人だけ。場所が違えばロマンチックなシチュエーションだったかもしれないが、いかんせん場所は違わない。暗く冷たい現実の上で、擦り切れるほどに踵を鳴らし踊り続けている。
心当たりのない問題に悩み続けるよりも、戦っている方が気が紛れる分いくらかマシに思われた。勝つか負けるかは別として、戦いは終わる。一度はまってしまった思考の沼はそう簡単には終わらない。終わりの見えないトンネルを好む人間はいないだろう。
””あの””笹子さんが何を考えているのか、自分が何を考えているのか。もしくは端的に、どうすれば良いのか──分からなくなってきた。つい先刻までの楽観的な、合流すれば笹子さんが何とかしてくれるに違いないという他力本願に逃れられていた頃が既に懐かしい。
直感は囁かない。異能リソースが戦闘に割かれているのだろう。凡人程度の身体能力しか持たない身にありながら、こうも上手く立ち回れているのは異能のおかげだ。危険が迫れば察知して回避する。有効打の通りそうな場所に気づく。断続的に迫る無数の選択肢の中から、直感の赴くままに答えをはじき出し続ける間は、抱えた不安から解放されることが出来る。
答えを待つのが怖かった。彼女の態度の原因が、自分そのものへの拒絶だと判明してしまうのが。
怪談が嫌いなのは嘘だ。不要な恐怖を自ら生んでしまう、己の愚かさが嫌いだった。



ENo.507 マナカ とのやりとり

ENo.831 Dr.笹子 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 不思議な料理……? を食べました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 器用13 敏捷13 耐疫13 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








レイシー(409) に ItemNo.8 吸い殻 を送付しました。
優兎佳(372) から 羽 を受け取りました。
制約LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
合成LV を 10 UP!(LV20⇒30、-10CP)
オニキス(301) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 超絶合成![ 2 5 6 = 13 ]不発!
フタバ(515) により ItemNo.10 ねばねば から射程2の武器『硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ"』を作製してもらいました!
⇒ 硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ"/武器:強さ40/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
Dr.笹子(831) により ItemNo.9 不思議な食材 から料理『不可思議な料理』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 6 1 2 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ 不可思議な料理/料理:強さ30/[効果1]器用13 [効果2]敏捷13 [効果3]耐疫13
士円(1230) とカードを交換しました!
ラーメン (ファーマシー)

クリエイト:グレイル を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
エチュード を習得!
リフレクション を習得!
プリディクション を習得!
マーチ を習得!
コンテイン を習得!
フィジカルブースター を習得!
フィックルティンバー を習得!
カマイタチ を習得!
タッチダウンライズ を習得!
アースタンブア を習得!
ノーマライズ を習得!
プチメテオカード を習得!
ミラー&ミラー を習得!
精神変調耐性 を習得!
瑞星 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 O-6(沼地)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



これは記だ。当然のことながら。
湯沸かし器を新調した。
それも、ただの湯沸かし器ではない。スイッチ一つで勝手にお湯が沸くハイテクノロジーな代物だ。寒い部屋で一人孤独に湯を沸かす自分のことを見かねた上司が提案してくれたもので、確かに冬場は辛いものがあったため、素直に厚意に甘えることにした。話が決まるや否や善は急げとばかりに年末にも向かったエンジョイなんとかというホームセンターに向かうと、大小様々な湯沸かし器を物色し、大きすぎず小さすぎないちょうど良いサイズのものを購入した。押すのがスイッチなのかボタンなのかについては少々論議があったが、普段から円滑なコミュニケーションを心掛けている上司とは円満に解決することが出来た。
年の初めからお金を使うと、その年は散在するという言い伝えもある。しかし、金で生活の質が向上するならばこの手の呪言は甘んじて受け入れるつもりだった──どうせ経費だし。人類の歴史は退化の歴史だ。人は楽をするために科学技術を進歩させ、昨日より明日を楽に生きるために生きてきた。この一杯のカプチーノは歴史の到達点であると同時に、明日にはこの手間すら面倒に感じてしまう退廃の象徴となるだろう。人の欲に限度はないのだから。
スイッチを入れて数分後、ごぼごぼと水の茹る音とともに蒸気が吹き上がる。部屋はまだ寒く、蒸気の量もかなりのものだった。うかつに近づけば一瞬にして眼鏡が曇ってしまう。一瞬とはいえ視界を失うのは極めて危険だが、流石に速度はガスよりも圧倒的に早い。必要なリスクとして受け入れる必要があるだろう。
カプチーノを淹れて飲んだ。クソ寒い中、出社して朝一番に水を汲んでヤカンを火にかけガスで湯を沸かして飲むコーヒーよりもはるかに手がかからない上、魔法瓶に移し替えて冷める心配もない。熱々の熱湯をすする羽目になってまたもや火傷しそうになったのと、その際口元にひげが出来てしまった姿を見て、上司は静かに笑っていた。カプチーノは妙に美味い気がしたが、それは胸の中にしまっておいた。
物事には順序がある。コーヒーを淹れるためにお湯を沸かすように、楽にお湯を沸かすために湯沸かし器を買うように──会話をするためには、何をこなす必要があるのだろうか。長くはない付き合いの関係とはいえ、まさかコミュニケーションの根源について悩まされることになるとは思っていなかった。
「……ここまではわかるかしら。」
「ええと。話は理解しました。概ね……」
「そう、なら、今日の戦闘で必要な物資をキチンと集めること。私からはとりあえず以上よ。何かあるかしら」
まともに報告すら出来ないというのは、最良から最悪まで予想していた状況のひとつではあったが。それでも単に想像でしかなかったことに比べれば、実際にそうなってしまったのとではわけが違った。チャット越しの仮想的なやり取りにはなかった、直接対面して初めて得られた言外の反応は、彼女が貫く言外の拒絶を雄弁に物語っているような気がした。矢継ぎ早にまくし立てられる言葉の数々は、無難な言葉の相槌で勢いが衰えるのを待っているうちに、気づけば会話が打ち切られている。何か意見はと言われても、それは事務的なやりとりであって、本当に意見を求めているわけではないようにすら感じてしまう。
「危機意識については、僕も茅芽さんと共有しているつもりです。こんなところで、死にたくないですし。それに──」
取り付く島もない態度について、当初は不慣れからくるものと思っていた。慣れない環境での苛立たしさ、ストレス、ハザマへの拒否感。そういったものから生じた、いわば八つ当たりのような拒絶だと。事実、イバラシティにおける彼女の印象と比較して、目の前の彼女はあまりにも血色が悪かったため、単なる不健康というよりは精神的なものだろうと予想していた。
しかし、そうではない。そうではなかったのだ。合流すれば何とかなるという過去の甘い幻想は既に朽ち果て、孤独よりもはるかに厄介な問題を抱え込むことになってしまった。有有有利有利有利(アドアドアドバンテージテージ)が、最悪の──これから先が良くなるという前提だが──、あるいは最善の仮説を囁き続ける。彼女の態度が何に根差したものなのか。確かめるには、相応のリスクを支払う覚悟が必要だった。愚かにも、触れずに黙って気づかぬフリをしていたとしても誰も責めないような、絶望的な直感の答え合わせをする覚悟が。
これから口にする言葉は、賭けにもならないと分かりきっていた。全てが終わったゲームにベットするのは愚の骨頂だ。強化された異能が囁き続けている気がした。言葉が多いと言われたのはどこの誰だ。絶対にやめろ。碌なことにならない。
「争事、向吉。誠意に答えよ……”おみくじ”にあった通り、しっかり対応さえすれば、リスクは減りますしね」
抱え込んだ問題は、その複雑さとは裏腹に、皮肉にも明瞭な名前を持つ。
不安、という名を。
戦闘があったのは、渡りに船だったかもしれない。
謎の適性存在ナレハテに続く敵たち、そして話には聞いていたアンジニティ側の人間との決闘。事態への対処という形でやむを得ず行われた二人の初めての共同作業は、二人の間に横たわるであろう暗く深い溝を埋め、つかの間の結束をもたらした。良くも悪くも、悩むことなく頭を空っぽにすることが出来る。
(あまり、深く考えすぎない方が良いのかもしれない)
ワイヤーを振るい、時にワイヤーに使われながら、襲い来る敵を捌いてゆく。無論、笹子さんの存在は常に気にかけながら。ここにいるのは二人だけ。場所が違えばロマンチックなシチュエーションだったかもしれないが、いかんせん場所は違わない。暗く冷たい現実の上で、擦り切れるほどに踵を鳴らし踊り続けている。
心当たりのない問題に悩み続けるよりも、戦っている方が気が紛れる分いくらかマシに思われた。勝つか負けるかは別として、戦いは終わる。一度はまってしまった思考の沼はそう簡単には終わらない。終わりの見えないトンネルを好む人間はいないだろう。
””あの””笹子さんが何を考えているのか、自分が何を考えているのか。もしくは端的に、どうすれば良いのか──分からなくなってきた。つい先刻までの楽観的な、合流すれば笹子さんが何とかしてくれるに違いないという他力本願に逃れられていた頃が既に懐かしい。
直感は囁かない。異能リソースが戦闘に割かれているのだろう。凡人程度の身体能力しか持たない身にありながら、こうも上手く立ち回れているのは異能のおかげだ。危険が迫れば察知して回避する。有効打の通りそうな場所に気づく。断続的に迫る無数の選択肢の中から、直感の赴くままに答えをはじき出し続ける間は、抱えた不安から解放されることが出来る。
答えを待つのが怖かった。彼女の態度の原因が、自分そのものへの拒絶だと判明してしまうのが。
怪談が嫌いなのは嘘だ。不要な恐怖を自ら生んでしまう、己の愚かさが嫌いだった。



ENo.507 マナカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.831 Dr.笹子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
偽黒初 「そろそろ……ちょっと、慣れてきましたね。慣れたくもないですが」 |
ItemNo.7 不思議な料理……? を食べました!
| 偽黒初 「手料理を……食います!」 |
今回の全戦闘において 器用13 敏捷13 耐疫13 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







レイシー(409) に ItemNo.8 吸い殻 を送付しました。
優兎佳(372) から 羽 を受け取りました。
制約LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
合成LV を 10 UP!(LV20⇒30、-10CP)
オニキス(301) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 超絶合成![ 2 5 6 = 13 ]不発!
フタバ(515) により ItemNo.10 ねばねば から射程2の武器『硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ"』を作製してもらいました!
⇒ 硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ"/武器:強さ40/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
 |
忌蛇穴 「細く、しなやかにして、強か。そして、"""硬い"""」 |
Dr.笹子(831) により ItemNo.9 不思議な食材 から料理『不可思議な料理』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 6 1 2 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ 不可思議な料理/料理:強さ30/[効果1]器用13 [効果2]敏捷13 [効果3]耐疫13
士円(1230) とカードを交換しました!
ラーメン (ファーマシー)

クリエイト:グレイル を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
エチュード を習得!
リフレクション を習得!
プリディクション を習得!
マーチ を習得!
コンテイン を習得!
フィジカルブースター を習得!
フィックルティンバー を習得!
カマイタチ を習得!
タッチダウンライズ を習得!
アースタンブア を習得!
ノーマライズ を習得!
プチメテオカード を習得!
ミラー&ミラー を習得!
精神変調耐性 を習得!
瑞星 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 O-6(沼地)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







ENo.77
偽黒初



とある組織の助手。正確な肩書きは部長秘書兼所長代理補佐。
白長須、スーシロナガとも呼ばれることで知られるが、今回は偽黒初を名乗る。支所立ち上げのため、上司と共に栄転してきた。
特技はトランプ手裏剣。武器はワイヤー。ワイヤー使いにしては情に厚く涙もろい一面もある男だったが――?
好き:ハーブティ(ジャスミンとカモミール)
ベリー系のお菓子 女児アニメ 定期ゲー
嫌い:辛いもの 生臭い魚 窓の無い風呂
よくないAI ツイッター
資格:普通免許三十段 ワイヤー使い(乙種) 第一種五行鑑定士
異能:有有有利有利有利(アドアドアドバンテージテージ)
リスクリターンの直感を強化する異能。
??:Unknown.....
──以下サブキャラ──
シズカ・バンクラプト
避田高の体育教師。クズ。
異能:ヨケルギウスの加護
アイコン24
〼子美麗(ますこ・みゅうる)
避田高の全聞部部長。
異能:濃縮還元(プレスリリース)
アイコン25~29
白長須、スーシロナガとも呼ばれることで知られるが、今回は偽黒初を名乗る。支所立ち上げのため、上司と共に栄転してきた。
特技はトランプ手裏剣。武器はワイヤー。ワイヤー使いにしては情に厚く涙もろい一面もある男だったが――?
好き:ハーブティ(ジャスミンとカモミール)
ベリー系のお菓子 女児アニメ 定期ゲー
嫌い:辛いもの 生臭い魚 窓の無い風呂
よくないAI ツイッター
資格:普通免許三十段 ワイヤー使い(乙種) 第一種五行鑑定士
異能:有有有利有利有利(アドアドアドバンテージテージ)
リスクリターンの直感を強化する異能。
??:Unknown.....
──以下サブキャラ──
シズカ・バンクラプト
避田高の体育教師。クズ。
異能:ヨケルギウスの加護
アイコン24
〼子美麗(ますこ・みゅうる)
避田高の全聞部部長。
異能:濃縮還元(プレスリリース)
アイコン25~29
16 / 30
15 PS
チナミ区
P-9
P-9






















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 安物のスマートウォッチ | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 守りの石 | 防具 | 35 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な料理 | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 8 | 黄鉄鉱 | 素材 | 15 | [武器]麻痺10(LV20)[防具]反光10(LV25)[装飾]光纏10(LV20) | |||
| 9 | 不可思議な料理 | 料理 | 30 | 器用13 | 敏捷13 | 耐疫13 | |
| 10 | 硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ" | 武器 | 40 | 衰弱10 | - | - | 【射程2】 |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 合成 | 30 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| エアブレイド | 5 | 0 | 100 | 敵列:風撃 | |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| イーグルタロン (デアデビル) | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| スキューア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:地痛撃&次受ダメ増 | |
| アジャイルフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:AG増 | |
| フィックルティンバー | 5 | 0 | 80 | 敵:風痛撃&3D6が11以上なら風痛撃 | |
| カマイタチ | 5 | 0 | 100 | 敵:風撃+領域値[風]3以上なら、敵全:風撃&領域値[風]減 | |
| タッチダウンライズ | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+HP減+連続増 | |
| フラワリング | 5 | 0 | 50 | 敵列:魅了+領域値[地]3以上なら束縛 | |
| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| プチメテオカード | 5 | 0 | 40 | 敵:粗雑地撃 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| アゲインスト (アゲンスト) | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 幸星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:祝福 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 超絶合成 | 5 | 0 | 0 | 【常時】3D6が16以上なら合成後のアイテムの強さが増加するが、5以下なら減少する。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ヒール (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
ホーリーポーション (ホーリーポーション) |
0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 | |
| 決3 |
ラーメン (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]カームフレア | [ 1 ]アイシング |
| [ 1 ]ヒールハーブ | [ 1 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]チャージ |
| [ 1 ]イレイザー | [ 2 ]ハードブレイク |

PL / sironagasu_koen