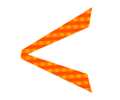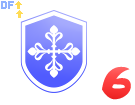<< 1:00~2:00




新しい景色を見るのは、いつだって楽しかった。
知っている言葉だけに落とし込んで伝えるのは、
とてももどかしいような、勿体ないような気持ちになる時もあったけれど。
それでも、たどたどしいそれにも耳を傾けて目を輝かせてくれる。
一緒に見ようと、ふたりの夢が増えていく。その時間が楽しかった。
一度、寝てばかりいる兄に、寝ている間の空の色を全部教えてあげよう、と考えた事があった。
毛布を被って、窓におでこを付けて、じっと息を潜めて、中々移り変わらない夜空を、見つめ続けていた。
結局途中で眠り込んでしまったけれど、はっと目を覚ました時に、私は見た。
ゆっくりと、塗りつぶすのが難しそうな夜色の緞帳を押し上げて行く、淡い炎のように引かれた赤い光を。
夕焼けとはまた違う、夜と朝の、鮮やかに溶け合った境目を。
かぎろい
火光
あの色を、あの瞬間を、私は兄に、何と伝えただろう。
+++++++++++++++++++++++++++++
吸血鬼の王オニキス。
彼は、イバラシティでの『天河ザクロ』を単なる虚像だと言い切った。
イバラシティでの天河ザクロは、確かにイバラシティで生きていた。
今現在だけではなく、過去を持ち、積み重ねてきた知識を、自身の考えを持ち、未来を見つめていた。
それすらも全て生み出されたもので、そんな存在が、他に何人もいるのなら、
この侵略戦争の舞台を作り上げているのなら、
それはとても、途方もない力に思えて。
これまで揺ぎ無くあった事だと信じていたものが欠けて、ぐらつく。
自分の中に、あとどれ程作り上げられた記憶があるのか。
あと何度、この感覚を飲み込まなければならないのか。
それもまた、途方もない事のように思えて、眩暈がした。
オニキスは語る。
アンジニティの世界のこと。
彼らは確固たる個を持つこと。
和解は出来ないこと。
『力』のみが、互いの間で通じる規則だということ。
彼が求めるのは、『力』と『己の定義』。
彼自身の存在によって揺らいだそれを改めて己のものにしろと彼は言う。
実際、それは否定の世界で生きてきた彼らと渡り合うために必要なものなのだと思う。
けれど、ひとつだけ。
「イバラシティで、どれほどの言葉と思い出を重ねてきたとしても……?」
彼らは、揺らがないものなのだろうか。
『オニキス』という現実を目の前にしても、
アンジニティの過酷さを耳にした後でも、口にせずにはいられなくて。
「――束の間の火光(かぎろい)が、己を塗り替えることなど、ない。定義以前の、公理としてだ」
彼の答えは静かで冷たく、はっきりとしたものだった。
分かり切っていた答えに、胸がじくりと痛みながらも、不思議と笑ってしまっていた。
それはきっと、彼の言葉を、そのまま鵜呑みにするつもりがなかったから。
私達を死なせないために、躊躇わずに戦わせるために語った事実なのだとしても、
どうしても自分の目で確かめたかった。
彼にとっては陽炎でも、私にとっての火光は、夜を朝に塗り替えていくものだから。













防具LV を 25 DOWN。(LV25⇒0、+25CP、-25FP)
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 30 UP!(LV0⇒30、-30CP)
オニキス(301) の持つ ItemNo.8 擦り切れた外套 に ItemNo.12 を付加しようとしましたが、付加材料を見失ってしまいました。
オニキス(301) の持つ ItemNo.5 ガーネットリング に ItemNo.10 不思議な石 を付加しました!
イデオローグ(474) の持つ ItemNo.5 黒手袋 に ItemNo.8 美味しくない草 を付加しました!
カードを作成しましたが誰とも交換されず自分のものとなりました!
石に花咲く (ヒールハーブ)


ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度1⇒2)
ストライク を研究しました!(深度2⇒3)
サステイン を習得!
タービュレントブルーム を習得!
スコーピオン を習得!
クレイジーチューン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



オニキス(301) は 藍鉄鉱 を入手!
巳羽(473) は 平石 を入手!
イデオローグ(474) は 平石 を入手!
さき(911) は 藍鉄鉱 を入手!
さき(911) は 剛毛 を入手!
巳羽(473) は 何か固い物体 を入手!
オニキス(301) は 大軽石 を入手!
巳羽(473) は 何か固い物体 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
イデオローグ(474) のもとに ぞう がスキップしながら近づいてきます。
イデオローグ(474) のもとに ハニワ がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
イデオローグ(474) のもとに 歩行小岩 が興味津々な様子で近づいてきます。



イデオローグ(474) に移動を委ねました。
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――



























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



新しい景色を見るのは、いつだって楽しかった。
知っている言葉だけに落とし込んで伝えるのは、
とてももどかしいような、勿体ないような気持ちになる時もあったけれど。
それでも、たどたどしいそれにも耳を傾けて目を輝かせてくれる。
一緒に見ようと、ふたりの夢が増えていく。その時間が楽しかった。
一度、寝てばかりいる兄に、寝ている間の空の色を全部教えてあげよう、と考えた事があった。
毛布を被って、窓におでこを付けて、じっと息を潜めて、中々移り変わらない夜空を、見つめ続けていた。
結局途中で眠り込んでしまったけれど、はっと目を覚ました時に、私は見た。
ゆっくりと、塗りつぶすのが難しそうな夜色の緞帳を押し上げて行く、淡い炎のように引かれた赤い光を。
夕焼けとはまた違う、夜と朝の、鮮やかに溶け合った境目を。
かぎろい
火光
あの色を、あの瞬間を、私は兄に、何と伝えただろう。
+++++++++++++++++++++++++++++
吸血鬼の王オニキス。
彼は、イバラシティでの『天河ザクロ』を単なる虚像だと言い切った。
イバラシティでの天河ザクロは、確かにイバラシティで生きていた。
今現在だけではなく、過去を持ち、積み重ねてきた知識を、自身の考えを持ち、未来を見つめていた。
それすらも全て生み出されたもので、そんな存在が、他に何人もいるのなら、
この侵略戦争の舞台を作り上げているのなら、
それはとても、途方もない力に思えて。
これまで揺ぎ無くあった事だと信じていたものが欠けて、ぐらつく。
自分の中に、あとどれ程作り上げられた記憶があるのか。
あと何度、この感覚を飲み込まなければならないのか。
それもまた、途方もない事のように思えて、眩暈がした。
オニキスは語る。
アンジニティの世界のこと。
彼らは確固たる個を持つこと。
和解は出来ないこと。
『力』のみが、互いの間で通じる規則だということ。
彼が求めるのは、『力』と『己の定義』。
彼自身の存在によって揺らいだそれを改めて己のものにしろと彼は言う。
実際、それは否定の世界で生きてきた彼らと渡り合うために必要なものなのだと思う。
けれど、ひとつだけ。
「イバラシティで、どれほどの言葉と思い出を重ねてきたとしても……?」
彼らは、揺らがないものなのだろうか。
『オニキス』という現実を目の前にしても、
アンジニティの過酷さを耳にした後でも、口にせずにはいられなくて。
「――束の間の火光(かぎろい)が、己を塗り替えることなど、ない。定義以前の、公理としてだ」
彼の答えは静かで冷たく、はっきりとしたものだった。
分かり切っていた答えに、胸がじくりと痛みながらも、不思議と笑ってしまっていた。
それはきっと、彼の言葉を、そのまま鵜呑みにするつもりがなかったから。
私達を死なせないために、躊躇わずに戦わせるために語った事実なのだとしても、
どうしても自分の目で確かめたかった。
彼にとっては陽炎でも、私にとっての火光は、夜を朝に塗り替えていくものだから。







熾す魂火、絶えぬ火光
|
 |
夕礼書店調査隊
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 2 増加!
影響力が 2 増加!



防具LV を 25 DOWN。(LV25⇒0、+25CP、-25FP)
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 30 UP!(LV0⇒30、-30CP)
オニキス(301) の持つ ItemNo.8 擦り切れた外套 に ItemNo.12 を付加しようとしましたが、付加材料を見失ってしまいました。
オニキス(301) の持つ ItemNo.5 ガーネットリング に ItemNo.10 不思議な石 を付加しました!
イデオローグ(474) の持つ ItemNo.5 黒手袋 に ItemNo.8 美味しくない草 を付加しました!
カードを作成しましたが誰とも交換されず自分のものとなりました!
石に花咲く (ヒールハーブ)


ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度1⇒2)
ストライク を研究しました!(深度2⇒3)
サステイン を習得!
タービュレントブルーム を習得!
スコーピオン を習得!
クレイジーチューン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



オニキス(301) は 藍鉄鉱 を入手!
巳羽(473) は 平石 を入手!
イデオローグ(474) は 平石 を入手!
さき(911) は 藍鉄鉱 を入手!
さき(911) は 剛毛 を入手!
巳羽(473) は 何か固い物体 を入手!
オニキス(301) は 大軽石 を入手!
巳羽(473) は 何か固い物体 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
イデオローグ(474) のもとに ぞう がスキップしながら近づいてきます。
イデオローグ(474) のもとに ハニワ がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
イデオローグ(474) のもとに 歩行小岩 が興味津々な様子で近づいてきます。



イデオローグ(474) に移動を委ねました。
チナミ区 N-7(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



狭間シティ防衛線
|
 |
熾す魂火、絶えぬ火光
|


ENo.473
結城 巳羽



結城 巳羽 ゆうきみう
熾盛天晴学園中等部2年5組に在籍。
身長は155cm。普段から気怠げに目を細めている少女。
制服は規定通り。
鞄も髪型も飾り気がないのは、
溺愛してくる両親から買い与えられる
愛らしいお洋服、小物からの反動。
高等部になったら直ぐにバイトを始め、
自分のお金で服を揃えたいと思っている。
みう、という己の名前も気に入ってはおらず、
学園外では名字を名乗ることが多い。
結城伐都との兄妹仲は良好。呼び方はバツ兄(ばつにい)。
趣味は石集め。
++++++++++++++++++++++++++++
巳羽の異能メモ。
【石に花咲く】
豪腕、鋭敏、跳躍などなど。
石に役割を込め身に付ける事で力を発揮する。
思い入れの深さに依存するため
巳羽がピンときた石にしか効力を発揮しない。
一番のお気に入りの石は、
毎日健康の祈りを込めて、兄に持たせている。
++++++++++++++++++++++++++++++
石拾いのキャラクターイラスト、カード絵は、鴉瓜様に描いて頂きました。
素敵なイラストをありがとうございます。
熾盛天晴学園中等部2年5組に在籍。
身長は155cm。普段から気怠げに目を細めている少女。
制服は規定通り。
鞄も髪型も飾り気がないのは、
溺愛してくる両親から買い与えられる
愛らしいお洋服、小物からの反動。
高等部になったら直ぐにバイトを始め、
自分のお金で服を揃えたいと思っている。
みう、という己の名前も気に入ってはおらず、
学園外では名字を名乗ることが多い。
結城伐都との兄妹仲は良好。呼び方はバツ兄(ばつにい)。
趣味は石集め。
++++++++++++++++++++++++++++
巳羽の異能メモ。
【石に花咲く】
豪腕、鋭敏、跳躍などなど。
石に役割を込め身に付ける事で力を発揮する。
思い入れの深さに依存するため
巳羽がピンときた石にしか効力を発揮しない。
一番のお気に入りの石は、
毎日健康の祈りを込めて、兄に持たせている。
++++++++++++++++++++++++++++++
石拾いのキャラクターイラスト、カード絵は、鴉瓜様に描いて頂きました。
素敵なイラストをありがとうございます。
15 / 30
137 PS
チナミ区
P-9
P-9





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 守りの石 | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 最初に拾った石 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | ソーダキャンディ | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | ほしがたちょこ | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 平石 | 素材 | 15 | [武器]器用15(LV25)[防具]防御10(LV10)[装飾]治癒15(LV25) | |||
| 9 | 何か固い物体 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20) | |||
| 10 | 何か固い物体 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 使役 | 5 | エイド/援護 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 30 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| 練2 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| タービュレントブルーム | 5 | 0 | 60 | 敵全:地撃+3D6が15以上ならAT減(2T) | |
| ヒールハーブ | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ビラッディホルン (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 練2 |
クリエイト:フライング亀 (クリエイト:タライ) |
0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 |
|
石に花咲く (ヒールハーブ) |
0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ストライク | [ 3 ]デアデビル | [ 3 ]イレイザー |

PL / なっき