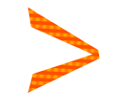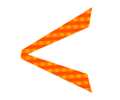<< 1:00~2:00




人であることと神であることの違いを試行によって知らされている。
神として在ったときと環境から異なるとはいえ。
そう、『環境』。それ自体が人と神とは異なるものだ。
人である「曇食日」とは、愚かで哀れだが、並び立つものを得た。
神とは異なる精神性がそれをゆるすのだろう。
神であるわたしはどうか、といえば、曇食日の意識で体感したそれを、自らの思考で「再生」できない不自然さに首を傾げるばかりだ。視界のない生き物に空の色を教えるが如く、実感は経験を楔にしてすらなおこの身に馴染まない。神は人を理解できない。わかっていたこととはいえ、掴めていたものがそうでなくなるのは、なるほど無価値を証明するかのようだと笑みすら浮かぶ。
神の精神性は並ぶものをゆるしはしないし、そもそもそんなものが必要になる環境ではない。
神には、得られるものなどなく、与えるだけ。
いや、与えられすら、しないのだ。
結局のところ、
「わたしにとっては」すべて無価値。
わかっていることだ。はるかな昔から。
歩く、という作業に時間を取られるのはどうにも気にくわないものがある。
そもそも慣れていないことを、戦争の最中にすべきではない。
縁のあるものを呼び、移動する拝殿を設け、同行者を住まわせることにした。
家電製品やらなにやらが紛れ込むのは私の権能というよりは、才能に近い分野の問題であるが、いわゆるセンスの問題は如何ともし難い。この手のことにはリーの方が慣れているとみえ、形をそれらしく整えるのはあちらに任せた。
「は?こんな場所に集合すんの?もっといい感じにならないの。するね。」
……言われてみればそれはそうなのだし、リーが整えた外形は、なるほどたしかに、神と人とが共存するに相応しい姿をしているようだった。かといって同じようにしようとすると、なぜだか知らんが洗濯機とか脱穀機混じりの柱が生えるので、もうたぶんこの手のやつはだめなのだと思う。元々私のいた社が不法投棄業者の蔓延る醜い山と化したのが原因のひとつではあるとおもうが、どうにも、私は神気を操るのに不器用であるようだ、というのが、比較として明らかになった。かなしいになってしまった。
やがて、人と、その他。
私の眷属と……同行者、それから、『曇食日』が己を明け渡したものを呼びつけ、私の拝殿は成った。
正確にいうならば、それは明け渡したものの、本来のすがた、というべきであろうし、私にとっては未だ興味の範囲を脱してはいない対象ではあるが。
だが、それは、主神から捨てられ、新しく捨てられることを厭うようであったし、……ここは、私の拝殿なのだから、
捨てられたものが行き着くのは、当然なのだろう。私とて、そうなのだから。
やがて、ヒトが、神の使いが、どこかへ飛び立つにせよ。
私は何も拒まず、何も捨てない。
去るものを許さず、呪い、恨み尽くす、とはいえ。
信仰を失った神の伸ばす手が届くかどうかも、今となっては知れた話。
そんなものは、届かない。
何にも。どこにも。
『神は何も救わない』。
ヒトはそう口にするのだと、曇食日は知っている。
そうとも、救いなどしない!そのための手段などどこにもありはしない!
こうして、ここに、在るだけだ、それすら証明もできないままに!
だから、ヒトよ、すべてよ、堕ちるがいい。
私のもとへ、堕ちてくるがいい。
触れられるのなら、二度と逃しはしない。
叶いもしない願いを抱いている。
赤い空と赤い土、この場でなら、僅かに、触れられる願いだ。
幾度となくそれをなぞる。私の願いはこんなかたちをしている。
私はこれを再び失うのだろうか。曇食日が得た感覚を失っていくように。
私は私を失うだろうか。
それは神の死と、呼ぶのだろうか。
私の願い。
胎廻洞。
由来は、今の私の権能と同じ。
イバラシティ、で得た虚構の嬰児が現実に楔を下ろした、その信仰。
在るだけの、意味を持たない、叫びのような原始的な祈り。
それを糧にして、醜い社が育っている。
やがて醜い花を咲かせ、根付いたこの地に祝いを与えよう。
虚無に堕ち、私の腕に抱かれて眠れ、私を知らぬヒトよ。
「示せ、娘らよ。ヒトの渇望を。神の恩恵を広める土地を。」
「次なる戦いを始めよう。我が腕に抱かれて眠る子を、その渇望によってえらぶがいい、娘らよ」
拝殿は赤い土地を這い、百足に似た跡を戦場へ遺す。
ごうごうと風が吹くなか、二人の娘が割れ鏡越しの景色を指さした。



ENo.84 アゲハ とのやりとり

ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり

ENo.383 レオン とのやりとり

ENo.927 リズン とのやりとり

以下の相手に送信しました













百薬LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
雷火(200) により ItemNo.8 毛 から装飾『割玻璃』を作製してもらいました!
⇒ 割玻璃/装飾:強さ40/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
リーと従者(206) の持つ ItemNo.9 松 から射程3の武器『祭火の錫杖』を作製しました!
こはる(89) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『いわちヒレ酒』をつくってもらいました!
⇒ いわちヒレ酒/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
ロベリア(1509) とカードを交換しました!
いやほい (ダークネス)


パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
パワフルヒール を研究しました!(深度2⇒3)
ウィンドカッター を習得!
ストーンブラスト を習得!
カース を習得!
エアブレイド を習得!
アイアンナックル を習得!
ブラックバンド を習得!
スキューア を習得!
イービルカード を習得!
フラワーバド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



こはる(89) は 花びら を入手!
雷火(200) は 白石 を入手!
リーと従者(206) は 花びら を入手!
くもくいさま(440) は 白石 を入手!
くもくいさま(440) は ネジ を入手!
くもくいさま(440) は 不思議な雫 を入手!
こはる(89) は ネジ を入手!
くもくいさま(440) は ネジ を入手!



こはる(89) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- こはる(89) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- リーと従者(206) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

Cross+Roseの音量を調整する。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



人であることと神であることの違いを試行によって知らされている。
神として在ったときと環境から異なるとはいえ。
そう、『環境』。それ自体が人と神とは異なるものだ。
人である「曇食日」とは、愚かで哀れだが、並び立つものを得た。
神とは異なる精神性がそれをゆるすのだろう。
神であるわたしはどうか、といえば、曇食日の意識で体感したそれを、自らの思考で「再生」できない不自然さに首を傾げるばかりだ。視界のない生き物に空の色を教えるが如く、実感は経験を楔にしてすらなおこの身に馴染まない。神は人を理解できない。わかっていたこととはいえ、掴めていたものがそうでなくなるのは、なるほど無価値を証明するかのようだと笑みすら浮かぶ。
神の精神性は並ぶものをゆるしはしないし、そもそもそんなものが必要になる環境ではない。
神には、得られるものなどなく、与えるだけ。
いや、与えられすら、しないのだ。
結局のところ、
「わたしにとっては」すべて無価値。
わかっていることだ。はるかな昔から。
歩く、という作業に時間を取られるのはどうにも気にくわないものがある。
そもそも慣れていないことを、戦争の最中にすべきではない。
縁のあるものを呼び、移動する拝殿を設け、同行者を住まわせることにした。
家電製品やらなにやらが紛れ込むのは私の権能というよりは、才能に近い分野の問題であるが、いわゆるセンスの問題は如何ともし難い。この手のことにはリーの方が慣れているとみえ、形をそれらしく整えるのはあちらに任せた。
「は?こんな場所に集合すんの?もっといい感じにならないの。するね。」
……言われてみればそれはそうなのだし、リーが整えた外形は、なるほどたしかに、神と人とが共存するに相応しい姿をしているようだった。かといって同じようにしようとすると、なぜだか知らんが洗濯機とか脱穀機混じりの柱が生えるので、もうたぶんこの手のやつはだめなのだと思う。元々私のいた社が不法投棄業者の蔓延る醜い山と化したのが原因のひとつではあるとおもうが、どうにも、私は神気を操るのに不器用であるようだ、というのが、比較として明らかになった。かなしいになってしまった。
やがて、人と、その他。
私の眷属と……同行者、それから、『曇食日』が己を明け渡したものを呼びつけ、私の拝殿は成った。
正確にいうならば、それは明け渡したものの、本来のすがた、というべきであろうし、私にとっては未だ興味の範囲を脱してはいない対象ではあるが。
だが、それは、主神から捨てられ、新しく捨てられることを厭うようであったし、……ここは、私の拝殿なのだから、
捨てられたものが行き着くのは、当然なのだろう。私とて、そうなのだから。
やがて、ヒトが、神の使いが、どこかへ飛び立つにせよ。
私は何も拒まず、何も捨てない。
去るものを許さず、呪い、恨み尽くす、とはいえ。
信仰を失った神の伸ばす手が届くかどうかも、今となっては知れた話。
そんなものは、届かない。
何にも。どこにも。
『神は何も救わない』。
ヒトはそう口にするのだと、曇食日は知っている。
そうとも、救いなどしない!そのための手段などどこにもありはしない!
こうして、ここに、在るだけだ、それすら証明もできないままに!
だから、ヒトよ、すべてよ、堕ちるがいい。
私のもとへ、堕ちてくるがいい。
触れられるのなら、二度と逃しはしない。
叶いもしない願いを抱いている。
赤い空と赤い土、この場でなら、僅かに、触れられる願いだ。
幾度となくそれをなぞる。私の願いはこんなかたちをしている。
私はこれを再び失うのだろうか。曇食日が得た感覚を失っていくように。
私は私を失うだろうか。
それは神の死と、呼ぶのだろうか。
私の願い。
胎廻洞。
由来は、今の私の権能と同じ。
イバラシティ、で得た虚構の嬰児が現実に楔を下ろした、その信仰。
在るだけの、意味を持たない、叫びのような原始的な祈り。
それを糧にして、醜い社が育っている。
やがて醜い花を咲かせ、根付いたこの地に祝いを与えよう。
虚無に堕ち、私の腕に抱かれて眠れ、私を知らぬヒトよ。
「示せ、娘らよ。ヒトの渇望を。神の恩恵を広める土地を。」
「次なる戦いを始めよう。我が腕に抱かれて眠る子を、その渇望によってえらぶがいい、娘らよ」
拝殿は赤い土地を這い、百足に似た跡を戦場へ遺す。
ごうごうと風が吹くなか、二人の娘が割れ鏡越しの景色を指さした。



ENo.84 アゲハ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.383 レオン とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.927 リズン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
こはる 「……さてと。それじゃ行こうか。『勝利』とやらを得に」 |
 |
がんばろね! ぺんぎんは『むらびと』たちに てをふった。 |
 |
リー 「おまたせ。……ああ進む方向ね。」 |
 |
サク 「……。」 |
 |
サク 「行こうか。」 |
 |
くもくいさま 「拝殿移動で酔ったとして、それは乗り物酔いと呼ぶのだろうか。」 |





天に在るモノ
|
 |
かに玉フィロソフィア
|



百薬LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
雷火(200) により ItemNo.8 毛 から装飾『割玻璃』を作製してもらいました!
⇒ 割玻璃/装飾:強さ40/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
リーと従者(206) の持つ ItemNo.9 松 から射程3の武器『祭火の錫杖』を作製しました!
こはる(89) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『いわちヒレ酒』をつくってもらいました!
⇒ いわちヒレ酒/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
 |
いわちのぱたぱたのところ…… ぱたぱたじゃないところはどこにいってしまったのか…… そんなことを考えながらうつわをもつ……もつ?ぺんだ。わっととと。 |
 |
こはる 「お神酒にしては俗っぽいなあ……いいのかな……」 言いながら、網の上でヒレを焼いている。香ばしい香りがあたりに漂う…… なおこれはいわしではない。 |
ロベリア(1509) とカードを交換しました!
いやほい (ダークネス)


パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
パワフルヒール を研究しました!(深度2⇒3)
ウィンドカッター を習得!
ストーンブラスト を習得!
カース を習得!
エアブレイド を習得!
アイアンナックル を習得!
ブラックバンド を習得!
スキューア を習得!
イービルカード を習得!
フラワーバド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



こはる(89) は 花びら を入手!
雷火(200) は 白石 を入手!
リーと従者(206) は 花びら を入手!
くもくいさま(440) は 白石 を入手!
くもくいさま(440) は ネジ を入手!
くもくいさま(440) は 不思議な雫 を入手!
こはる(89) は ネジ を入手!
くもくいさま(440) は ネジ を入手!



こはる(89) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- こはる(89) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- リーと従者(206) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
エディアン 「わぁこんにちはノウレットさーん! えーと音量音量・・・コンフィグかな?」 |
Cross+Roseの音量を調整する。
 |
エディアン 「よし。・・・・・さて、どうしました?ノウレットちゃん。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたッ!」 |
 |
エディアン 「おや、てっきりあのざっくりした説明だけなのかと。」 |
 |
ノウレット 「お役に立てそうで嬉しいです!!」 |
 |
エディアン 「よろしくお願いしまーす。」 |
 |
ノウレット 「ではでは・・・・・ジャーンッ!こちらがロスト情報ですよー!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
エディアン 「なるほど、いろんなかたがいますねぇ。 彼らの願望を叶えることで影響力を得て、ハザマで強くもなれるんですか。」 |
 |
エディアン 「どこにいるかとか、願望の内容とか、そういうのは分かります?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「むむむ・・・・・頑張って見つけないといけませんねぇ。 こう、ロストには頭にマークが付いてるとか・・・そういうのは?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・システムメッセージなのかなこれ。 ・・・ノウレットちゃんの好きなものは?」 |
 |
ノウレット 「肉ですッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・嫌いなものは?」 |
 |
ノウレット 「白南海さん、です・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・さては何かしましたね、彼。」 |
 |
エディアン 「では、ロスト情報もそこそこ気にしながら進めていきましょう!」 |
 |
ノウレット 「ファイトでーすッ!!」 |
チャットが閉じられる――







天に在るモノ
|
 |
チームオオキタグルメ班(仮)
|


ENo.440
曇食 日



連絡先は[クモリクラウディ連絡先]へ。
*イバラのすがた*
【曇食 日】くもりくらう でい
二十代男性。職業出張ホスト。要は本番可能ということ。
自己を含む全ての価値を認めておらず、さも価値があるように謳う世界の全てを憎み、恨んでいる。彼が世界に復讐するために選んだ手段は、「自分の価値のない血を撒き散らし、世界を価値無きものに確定する」こと。そのため、女性のみならず「ワンチャン異能でなんとかできる」男性も守備範囲である。
「いちばん」同士の相手ができたが、その価値に関してよく理解できていない。
・クモリクラウディの彼女を名乗るのはフリーです
・クモリクラウディの妻を名乗るのもフリーです
・肉体関係を持っている設定もフリーです
・その結果に関してもぜんぜんフリーです
・できれば連絡先に一報ください、たのしいので
【種を播く地を解する力〈タガシラ〉】
それを種と認識すれば、向かう地を。
それを地と認識すれば、芽吹く種を。
理解し、相互の結びつきを強くする。
たったそれだけの異能であるが、応用をすれば「子供が120%できる(双子の可能性も増えるという意味)」「その人間の欲する言葉が理解できる」「割る鶏卵がなんかぜんぶ双子」「野苺がみつけやすい」など利用方法は多岐に渡る。農家になればよかったのに。
*ハザマのすがた*
【くもくいさま】
僻地の寒村、だった土地の、捨て置かれた社の、忘れられた農耕神。
為せることは何もない。
何も無かったので、村は滅び、残った民も孤独に死んだ。
荒れ果てた社は、今や不法投棄の電化製品が転がり落ちる山の中。
蜘蛛の巣だらけのその場所を訪れるものはない。
【堕神祠〈ダカンシ〉】
くもり「まだひみつだよ」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ピンクの男子↓
**
【道枝陽樹】みちえようき
身長192せんち、細身、高校生、男子。
テンションがあんまり高くないが髪の色はテンションが高い。
胡乱な高校(所属なし)に通っており、胡乱な校則はわりと真面目にまもっている。
【鏡面仕上げ】
「僅かなダメージ」をゼロにできる能力。
つまりスマホの画面はつねにつるつるだし、髪の染め変えしても髪が痛まない。紫外線は気にしなくて済むし多少の暑さ寒さや服の染みも無効、その上なんとタンスに小指をぶつけた痛みも完全カバー!
しかしダメージジーンズは直らない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
何度も出てきて恥ずかしくないんですか?の人↓
**
【蜜雨】: イバラのすがた
その日その日を適当に生きている。
no.366と深い友達。
本名は不明だが、ヒモの経験があることはわかっている。
ろくな人間じゃない。
異能はなんか健康になってるやつともっぱらの評判。
【蜜雨】: ハザマのすがた
所属してた世界がなくなった不老不死の男。アムリタ。
no.366がハザマに行ってみるっていうから駄々こねて来た。
根がドクズなのでよその世界がどうなろうと知らんと思っている。
*イバラのすがた*
【曇食 日】くもりくらう でい
二十代男性。職業出張ホスト。要は本番可能ということ。
自己を含む全ての価値を認めておらず、さも価値があるように謳う世界の全てを憎み、恨んでいる。彼が世界に復讐するために選んだ手段は、「自分の価値のない血を撒き散らし、世界を価値無きものに確定する」こと。そのため、女性のみならず「ワンチャン異能でなんとかできる」男性も守備範囲である。
「いちばん」同士の相手ができたが、その価値に関してよく理解できていない。
・クモリクラウディの彼女を名乗るのはフリーです
・クモリクラウディの妻を名乗るのもフリーです
・肉体関係を持っている設定もフリーです
・その結果に関してもぜんぜんフリーです
・できれば連絡先に一報ください、たのしいので
【種を播く地を解する力〈タガシラ〉】
それを種と認識すれば、向かう地を。
それを地と認識すれば、芽吹く種を。
理解し、相互の結びつきを強くする。
たったそれだけの異能であるが、応用をすれば「子供が120%できる(双子の可能性も増えるという意味)」「その人間の欲する言葉が理解できる」「割る鶏卵がなんかぜんぶ双子」「野苺がみつけやすい」など利用方法は多岐に渡る。農家になればよかったのに。
*ハザマのすがた*
【くもくいさま】
僻地の寒村、だった土地の、捨て置かれた社の、忘れられた農耕神。
為せることは何もない。
何も無かったので、村は滅び、残った民も孤独に死んだ。
荒れ果てた社は、今や不法投棄の電化製品が転がり落ちる山の中。
蜘蛛の巣だらけのその場所を訪れるものはない。
【堕神祠〈ダカンシ〉】
くもり「まだひみつだよ」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ピンクの男子↓
**
【道枝陽樹】みちえようき
身長192せんち、細身、高校生、男子。
テンションがあんまり高くないが髪の色はテンションが高い。
胡乱な高校(所属なし)に通っており、胡乱な校則はわりと真面目にまもっている。
【鏡面仕上げ】
「僅かなダメージ」をゼロにできる能力。
つまりスマホの画面はつねにつるつるだし、髪の染め変えしても髪が痛まない。紫外線は気にしなくて済むし多少の暑さ寒さや服の染みも無効、その上なんとタンスに小指をぶつけた痛みも完全カバー!
しかしダメージジーンズは直らない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
何度も出てきて恥ずかしくないんですか?の人↓
**
【蜜雨】: イバラのすがた
その日その日を適当に生きている。
no.366と深い友達。
本名は不明だが、ヒモの経験があることはわかっている。
ろくな人間じゃない。
異能はなんか健康になってるやつともっぱらの評判。
【蜜雨】: ハザマのすがた
所属してた世界がなくなった不老不死の男。アムリタ。
no.366がハザマに行ってみるっていうから駄々こねて来た。
根がドクズなのでよその世界がどうなろうと知らんと思っている。
16 / 30
118 PS
チナミ区
I-14
I-14



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 神髪 | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 綿織捻布 | 法衣 | 17 | 防御10 | - | 幸運5 | |
| 6 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 7 | いわちヒレ酒 | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 割玻璃 | 装飾 | 40 | 回復10 | - | - | |
| 9 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 10 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 12 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 武器 | 30 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| 決1 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| エアブレイド | 5 | 0 | 100 | 敵列:風撃 | |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| スキューア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:地痛撃&次受ダメ増 | |
| イービルカード | 5 | 0 | 50 | 敵:風撃&名前に「纏」を含む付加効果があれば、1つ消滅させて闇撃化(1T) | |
| フラワーバド | 5 | 0 | 70 | 敵3:地撃+自:束縛+3D6が15以上なら地撃LV増 | |
| 決2 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| 決1 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| パワフルポーション | 5 | 0 | 120 | 自:AT・DF増+猛毒・麻痺・衰弱 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ハードブレイク | 6 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ブレス | [ 3 ]パワフルヒール | [ 3 ]イグニス |

PL / もつ