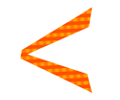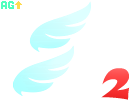<< 0:00~1:00




───昔語り
ある旧家に男児が生まれた。
生まれたばかりの子を掲げる父、母も産婆も、みな諸手を挙げて喜んだ。
──…というのが、一般的であったろう。
ところがその子は家にとっては厄介者で、生まれてすぐ離れの蔵に押し込められたのだ。
理由は簡単、子は父の不貞により産まれたものであるからだった。
もしも子が、その家に唯一の存在であれば、もう少し違ったのかもしれない
けれど正妻には既に何人かの子等が居たので、その子供はただ疎ましい存在でしか無かった。
産んだ女は子を置き幾ばくかの金と共に姿をくらまし、家の者にただ遺恨を残すものとなる。
捨てられなかったのは、父に僅かばかりな情があったからではない、
『外聞をはばかる』
ただそれだけだ。
けれど、ただそれだけ、で子は生きた。
身の回りの世話は家に仕えるものが行った。
学がないというのも恥と捉えたのか、家庭教師をつけられもした。
蔵の中より自由はなかったが、その蔵というのも、手付かずになって放置されていたのだが
曽祖父とやらが何某かを集めては収集していたとする古いもので
骨董やら書物はもちろん、通常の生物とも取れぬ白骨など、傾向が読めないモノで溢れていた。
子に退屈はなかった。
最初は、物を触ったり、動かして遊んだり、文字が読めるようになってからは
蔵書に手を出しては読み耽ける日々
家の者は皆、蔵の物を気味悪がって近づかなかったが
子はそれらに強く関心を寄せたのか進んで手にとっては観察を繰り返した。
そんな子の様子は使用人達にはひどく奇妙に映ったのだろう
気味の悪い子だと口々に囁いては、さらに遠巻きに扱うようになった。
この時点で、子と家の者に、まともな交流は成立していない。
使用人達は指示された事のほかは行わず、子と言葉を交わすこともなく
家族も誰一人とて、蔵に訪れたことすらなかった。
唯一、受け答えが成立していたのは家庭教師との間だけであったが
その家庭教師というのも、子に親切にするのはその父に取り入るためであった。
病弱な可哀想な子、と考えていた家庭教師が、子が家全てから疎まれていることを知ると
手の平を返したように態度を変え、手を上げるようになったものだから
子は息を潜めて不興を買わぬように過ごす事を覚えた。
人というものは勝手だ。
己の為に動くものなのだ。
向けられる親切も、笑顔も、何もかも。
純粋な善意。そんな綺麗なものは、本の中にしか無いのだ。
……
…
そうして幾ばくかの月日が流れた頃、それは起こる。
まず最初に、家庭教師が亡くなった。
自然死ではない、赤に倒れ伏すそれの傍には、刃物を携えた子が佇んでいた。
使用人がそれを見つけ驚き逃げたのを追って初めて子は蔵の外を知った───…
…結果として
その旧家に居た者は蔵子を除き、全てその生を閉じる事となった。
最後に倒れた男が吐いたのは子への侮蔑と拒絶の言葉。
「…ああ。あなたが、僕の父だったのですね」
見下ろす子に、罪悪はなく
そして世界は反転する。

十ほどの子がどうやってこのような惨劇を起こしたのか
後に残された屋敷は離れの蔵の一部を残し全焼、
ただ蔵の書棚にはごっそりと抜け落ちた部分があると推察されるが
その関連は不明と判じられる。
これは拭い去れない昔の記憶。紛れもない己の罪の話。
決して人に知られてはいけないと胸に秘める過去。
"廿里 崇司"は両世界に置いてその全てに"差異がない"。
罪悪は今もない、あれらにかける情けもない。
けれどこんな己でも常識というものを持ち合わせているつもりだ。
だから、知っている。



ENo.73 シェリル とのやりとり

ENo.263 狐疑 とのやりとり

ENo.747 布施 とのやりとり

ENo.758 虫喰い山羊 とのやりとり

ENo.1223 アンジー とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。









解析LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
呪術LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ルリオ(418) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『回遊する飛沫』を作製しました!
肉売り(1484) とカードを交換しました!
従業員調達 (サモン:サーヴァント)

ファイアダンス を研究しました!(深度0⇒1)
ウィンドカッター を研究しました!(深度0⇒1)
レッドショック を研究しました!(深度0⇒1)
闇の祝福 を習得!
ダウンフォール を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





ルリオ(418) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 布施(747) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



───昔語り
ある旧家に男児が生まれた。
生まれたばかりの子を掲げる父、母も産婆も、みな諸手を挙げて喜んだ。
──…というのが、一般的であったろう。
ところがその子は家にとっては厄介者で、生まれてすぐ離れの蔵に押し込められたのだ。
理由は簡単、子は父の不貞により産まれたものであるからだった。
もしも子が、その家に唯一の存在であれば、もう少し違ったのかもしれない
けれど正妻には既に何人かの子等が居たので、その子供はただ疎ましい存在でしか無かった。
産んだ女は子を置き幾ばくかの金と共に姿をくらまし、家の者にただ遺恨を残すものとなる。
捨てられなかったのは、父に僅かばかりな情があったからではない、
『外聞をはばかる』
ただそれだけだ。
けれど、ただそれだけ、で子は生きた。
身の回りの世話は家に仕えるものが行った。
学がないというのも恥と捉えたのか、家庭教師をつけられもした。
蔵の中より自由はなかったが、その蔵というのも、手付かずになって放置されていたのだが
曽祖父とやらが何某かを集めては収集していたとする古いもので
骨董やら書物はもちろん、通常の生物とも取れぬ白骨など、傾向が読めないモノで溢れていた。
子に退屈はなかった。
最初は、物を触ったり、動かして遊んだり、文字が読めるようになってからは
蔵書に手を出しては読み耽ける日々
家の者は皆、蔵の物を気味悪がって近づかなかったが
子はそれらに強く関心を寄せたのか進んで手にとっては観察を繰り返した。
そんな子の様子は使用人達にはひどく奇妙に映ったのだろう
気味の悪い子だと口々に囁いては、さらに遠巻きに扱うようになった。
この時点で、子と家の者に、まともな交流は成立していない。
使用人達は指示された事のほかは行わず、子と言葉を交わすこともなく
家族も誰一人とて、蔵に訪れたことすらなかった。
唯一、受け答えが成立していたのは家庭教師との間だけであったが
その家庭教師というのも、子に親切にするのはその父に取り入るためであった。
病弱な可哀想な子、と考えていた家庭教師が、子が家全てから疎まれていることを知ると
手の平を返したように態度を変え、手を上げるようになったものだから
子は息を潜めて不興を買わぬように過ごす事を覚えた。
人というものは勝手だ。
己の為に動くものなのだ。
向けられる親切も、笑顔も、何もかも。
純粋な善意。そんな綺麗なものは、本の中にしか無いのだ。
……
…
そうして幾ばくかの月日が流れた頃、それは起こる。
まず最初に、家庭教師が亡くなった。
自然死ではない、赤に倒れ伏すそれの傍には、刃物を携えた子が佇んでいた。
使用人がそれを見つけ驚き逃げたのを追って初めて子は蔵の外を知った───…
…結果として
その旧家に居た者は蔵子を除き、全てその生を閉じる事となった。
最後に倒れた男が吐いたのは子への侮蔑と拒絶の言葉。
「…ああ。あなたが、僕の父だったのですね」
見下ろす子に、罪悪はなく
そして世界は反転する。

廿里 崇司
一家惨殺の末アンジニティへ堕ちた人間。
自身を否定した"世界"はとても小さなものだったが同時にそれが彼の全てであった。
齢、十余の頃である。
自身を否定した"世界"はとても小さなものだったが同時にそれが彼の全てであった。
齢、十余の頃である。
十ほどの子がどうやってこのような惨劇を起こしたのか
後に残された屋敷は離れの蔵の一部を残し全焼、
ただ蔵の書棚にはごっそりと抜け落ちた部分があると推察されるが
その関連は不明と判じられる。
これは拭い去れない昔の記憶。紛れもない己の罪の話。
決して人に知られてはいけないと胸に秘める過去。
"廿里 崇司"は両世界に置いてその全てに"差異がない"。
罪悪は今もない、あれらにかける情けもない。
けれどこんな己でも常識というものを持ち合わせているつもりだ。
だから、知っている。
 |
つづり 「───人殺しを受け入れる人なんて、居やしないでしょう」 |



 |
ハザマの地を目的の人物(というと正しくはないが)を探して彷徨う。 記憶を持つというアドバンテージから向かうのは次元タクシー、 もしかして手を上げて呼べば来るかもしれないが、探しているものを 全く探さずに乗り込むには少々気が早い。 …そうしている間に影を泳ぐクジラを見つけた。 |
 |
珍しい!というのは、周囲の異形を見る限り沢山あるものだが。 クジラというのも初めて見たので、一層興味を惹かれたのもある。 全く知らないことばかりで新鮮であるからして、この侵略には感謝しなくては いけないのかもしれないが、それはそれこれはこれ、というやつで。 面倒に巻き込んでくれたことに変わりはない。 |
 |
鳴き声が悲しげであるが、影を泳ぐその姿は気持ちよさそうで 目的ついでに後を追いかける。 そのうちに生物の影もまばらになってきた頃、視界にそれを捉えた。 "会いに行く"といった相手ともう一人、まさか彼も此方側であるとは思わなかったけれども 異なる姿にそうだと思い込むが、きっとこれは間違いではないと予感と共に。 (挨拶、上手くできるといいのだけれど) なんて呑気な事を考えていた。 |
ENo.73 シェリル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.263 狐疑 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.747 布施 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.758 虫喰い山羊 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1223 アンジー とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
つづり 「アンジニティ同士ですし、どうぞよろしくお願いします。 …ところで……」 |
 |
つづり 「皆さんのことなんて呼べばいいんでしょう? 此方での名前わかりませんし… あっ、僕は廿里崇司で大丈夫ですので、お好きにどうぞ」 |
 |
つづり 「一先ずはシュロさんとヤギヒコさん、で 呼ばせていただきますけど、名前があるなら後で教えて下さいね。 ……クジラさんだけ…全くわからないんですけど」 |
 |
つづり 「まぁ、なんとかなりますよね。 とりあえずこれからどこに行きましょうか、…やっぱりクジラさんだったら海、ですかね? ハザマの海は、あまり綺麗ではないですけど……、地形は変わってますが 此処はイバラシティと似た所の様ですしシモヨメ区の辺り目指してみます?」 |
 |
布施 「こんにちわ。はじめまして。これからよろしく頼むよ。…ちゃんとあいさつ出来てる?俺。」 |
ItemNo.7 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。





巻き込まれ型冒険組
|
 |
運動不足ニティ
|



解析LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
呪術LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ルリオ(418) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『回遊する飛沫』を作製しました!
肉売り(1484) とカードを交換しました!
従業員調達 (サモン:サーヴァント)

ファイアダンス を研究しました!(深度0⇒1)
ウィンドカッター を研究しました!(深度0⇒1)
レッドショック を研究しました!(深度0⇒1)
闇の祝福 を習得!
ダウンフォール を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





ルリオ(418) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 布施(747) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――







TeamNo.164
|
 |
運動不足ニティ
|


ENo.492
廿里 崇司



テストより継続キャラです。
前回の記憶を引き継いでいます。
ハザマでの記憶はイバラシティで反映はされていません
(ハザマでは思い出せます)
----------------☆------------------
名前:廿里 崇司(つづり そうし)
年齢:21 性別:男性
身長:168cm 体重:55kg(細身)
一人称:僕 二人称:キミ、あなた、貴方
物静かで読書が趣味な何処にでもいる青年。
ツクナミ区にてシジマ書店を営んでいる、コーヒーが好物。
アンジニティ住民だが、ごくごく平凡な人間である。
特殊な蒐集癖を持ち、とある罪でアンジニティに堕とされた。
彼はイバラ/アンジ両側で外見、性格ともに変化は無く、
その生い立ちすら差異はない。
★異能は『蒐集装幀ビブリオ』
欲しいと思った物を異能書物へ吸収し保管することが出来る。
物理的な物に限らずエネルギー物質ですら収集可能で
奪ったものを使い攻撃を仕掛けるなどの使用もできる。
収めた物を複製する事もできるらしい。
制約として、ビブリオには生きているものは収集できない。
が、何を生きているとするのかは線引きがはっきりしておらず、本人の認識によるところが大きい。
☆ただ欲しいと思うだけで基本的に悪意はない。
【魔術】
異能とは別に、つづりが行使するもの。
蒐集物の中にある魔導書より習得した
これによりつづりは実質、魔術師としての活動が可能だが
普段の生活で使ってはいないようだ。
使える魔術の幅は広いが、使用頻度の高いものは
ゼブルの瞳という魔導の瞳での看破、鑑定、暴露である。
【シジマ書店】
店内には認識錯誤の魔術が施されており
求める本が目に付きやすく、それ以外のものは意識より逸れる効果がある。
また、必要としないものには絶対に見つけられない。という効果も付与される。
また、防護の術も同時展開されているので並の方法では
本が傷つけられるという事はない。
魔術に関する本なども置いてあり、それら全ては複製品。
原本はつづりが異能"ビブリオ"の内部に保管している。
一般書籍は業者を介しての取り寄せである。
(業者は特殊なものであるがその正体はつづり本人は知らない)
店自体が異能に近い何かであるかもしれないがつづりのものではない。
しかし、つづりに縁が紐付けられているものである。
☆------------------------------☆
<Special Thanks>
宮沢さん、鴉瓜さん
※一部イラストはご依頼して作成いただいたものです
素敵なイラストをありがとうございます!
☆------------------------------☆
エンジョイしたい、交流メインプレイです
動ける時間帯は夜が多め、ロールお返事などゆっくりです。
必ずしも友好的なキャラというわけではありません。
☆PL向け情報
[友好/不穏/大人向け etc]
・ロールは基本的に何でもOKです。
此方でキャラに合わせたお返事を返します。
ただ、ロールが得意とは言い切れません!
温かく見守って下さい
・出来るだけ流れは追いたいですがゲーム仕様上難しいです
頑張りますがわからない時は聞きます、よしなに!
それか適当に話を合わせます、此方、ぶっつけ本番ばかり
ですのでなんとでもなりましょう[楽観視]
・所謂、NL(HL),GL,BL等も全く問題ないです。
前回の記憶を引き継いでいます。
ハザマでの記憶はイバラシティで反映はされていません
(ハザマでは思い出せます)
----------------☆------------------
名前:廿里 崇司(つづり そうし)
年齢:21 性別:男性
身長:168cm 体重:55kg(細身)
一人称:僕 二人称:キミ、あなた、貴方
物静かで読書が趣味な何処にでもいる青年。
ツクナミ区にてシジマ書店を営んでいる、コーヒーが好物。
アンジニティ住民だが、ごくごく平凡な人間である。
特殊な蒐集癖を持ち、とある罪でアンジニティに堕とされた。
彼はイバラ/アンジ両側で外見、性格ともに変化は無く、
その生い立ちすら差異はない。
★異能は『蒐集装幀ビブリオ』
欲しいと思った物を異能書物へ吸収し保管することが出来る。
物理的な物に限らずエネルギー物質ですら収集可能で
奪ったものを使い攻撃を仕掛けるなどの使用もできる。
収めた物を複製する事もできるらしい。
制約として、ビブリオには生きているものは収集できない。
が、何を生きているとするのかは線引きがはっきりしておらず、本人の認識によるところが大きい。
☆ただ欲しいと思うだけで基本的に悪意はない。
【魔術】
異能とは別に、つづりが行使するもの。
蒐集物の中にある魔導書より習得した
これによりつづりは実質、魔術師としての活動が可能だが
普段の生活で使ってはいないようだ。
使える魔術の幅は広いが、使用頻度の高いものは
ゼブルの瞳という魔導の瞳での看破、鑑定、暴露である。
【シジマ書店】
店内には認識錯誤の魔術が施されており
求める本が目に付きやすく、それ以外のものは意識より逸れる効果がある。
また、必要としないものには絶対に見つけられない。という効果も付与される。
また、防護の術も同時展開されているので並の方法では
本が傷つけられるという事はない。
魔術に関する本なども置いてあり、それら全ては複製品。
原本はつづりが異能"ビブリオ"の内部に保管している。
一般書籍は業者を介しての取り寄せである。
(業者は特殊なものであるがその正体はつづり本人は知らない)
店自体が異能に近い何かであるかもしれないがつづりのものではない。
しかし、つづりに縁が紐付けられているものである。
☆------------------------------☆
<Special Thanks>
宮沢さん、鴉瓜さん
※一部イラストはご依頼して作成いただいたものです
素敵なイラストをありがとうございます!
☆------------------------------☆
エンジョイしたい、交流メインプレイです
動ける時間帯は夜が多め、ロールお返事などゆっくりです。
必ずしも友好的なキャラというわけではありません。
☆PL向け情報
[友好/不穏/大人向け etc]
・ロールは基本的に何でもOKです。
此方でキャラに合わせたお返事を返します。
ただ、ロールが得意とは言い切れません!
温かく見守って下さい
・出来るだけ流れは追いたいですがゲーム仕様上難しいです
頑張りますがわからない時は聞きます、よしなに!
それか適当に話を合わせます、此方、ぶっつけ本番ばかり
ですのでなんとでもなりましょう[楽観視]
・所謂、NL(HL),GL,BL等も全く問題ないです。
21 / 30
5 PS
チナミ区
I-11
I-11





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 蒐集装幀ビブリオ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 黒いカーディガン | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 20 | 呪詛/邪気/闇 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
| 練3 | ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ウィンドカッター | [ 1 ]レッドショック | [ 1 ]ファイアダンス |
| [ 1 ]アラベスク | [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]パリィ |

PL / iti