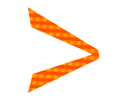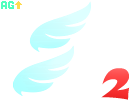<< 0:00~1:00




本を眺める視界の端に、ぶんぶんと手を振る姿が見えた。
蒼い瞳に金色の髪。光に透かせばうっすらと紫色に見えるそれは、
離れたところからでもキラキラと輝いて見えた。
駆け寄ってくるその姿は今もたまに夢に見る。
もう、だいぶ昔のことだと言うのに。
Thistle = Nirelia
ぴょんぴょんと飛び跳ねるあいつは、だいたいいつもこんな感じでやってきた。
山の上、湖の下、森の中に洞窟の奥。目を離すとすぐに居なくなって、気付けばまた帰ってくる。
こっちはだいたいどこかで本を読んでいるというのに。
どちらかと言えば、神出鬼没なのはあっちのほうだと今でも思っている。
どこにでも走っていく彼は、初めのうちはとても異質なものに映った。
どちらかと言えばインドア派の自分には、まるで太陽のように思えたのである。
だからだろうか。
ずれた歯車同士とでも言うべきか。
本来噛み合うとも思えなかった僕ら2人は、何故か意気投合して良く一緒に居た。
数少ない、いや、唯一といっていい友達だ。
少なくとも過去において、彼以上に気が合う相手に出会ったことがない。
イバラシティに引っ越してくる前、もっともっと遠いところで暮らしていた。
こことは違う、でも、不思議な力が認知された国。
その国はもっともっと西の先、それこそ世界の果てなんじゃないかってところにあって、
そんなに大きくはなかったように思う。
雪はあまり降らない暖かな気候で、どちらかと言えば農業に力を入れていた。
今になって思い返してみれば、不思議な力の存在も相まって笑ってしまうほど
ファンタジーな世界だったように思える。
近代化から大きく遅れていたのは、僕らの持つ不思議な力のせいもあったのだろう。
皆がそれぞれ能力に応じた役割を持っていて、その多くが、代々引き継いだ能力に依存していた。
周りにもそういった国々がいくつかあって、いつも面倒ないざこざがあった。
この時代に未だに剣士が居て、弓手が居て、魔女が居て、かと思えば近代の装備に身を包んだ人々も居る。
どちらにせよ、生活の多くを不思議な力に依存した僕たちは、
今更外に出ていく気もなく、外からの変化を受け入れることもなく、
ただただ、不思議な力で隠匿された領地を取り合う争いを続けていた。
時代から取り残された僕らは、遠くない未来に消えてしまう運命だった。
僕らはまだ戦う必要もなくて、こうして屋上でただただ本でも読んでいれば良かったのだけど、
どうにもあいつはそうは思っていないようだった。
そう言って、いつも血まみれの体を見せてくる。
初めは驚いたものだが、今ではすっかり慣れてしまった。
大人になってから大概のことが気にならなくなったのは、絶対あいつのせいだと思っている。
今日は胸元から縦一直線に血の痕がついていたけれど、確かにこれくらいは大したことがない。
前は腕がなかったし、その前は足がなかったし、大穴が空いていたこともある。
思わずため息が漏れた。
手を振りながら走ってくるからだいぶ混乱してしまう。
ニッ、と笑って見せるあいつはいつもどこかしら怪我していたように思えた。
そう言いながら、血に濡れた手や足を元に戻してやるのが、いつもの流れだった。
手を伸ばした。血まみれのニレリアの腕を手に取り、指先で触れる。
指先から炎が燃え移った。
初めは熱いらしい。けれど、すぐに仄かな暖かさしか感じなくなると言っていた。
体を這う炎の波が、埃も、汗も、涙も、古い体のすべてを焼き尽くして即座に再生させる。
完璧な肉体の再構成。本来あるべき正常な姿へと、物質を組み上げ直す。
ぼろぼろに破れた服も、繊維の一本に至るまで再現された。
血まみれの姿なんてどこにもない。目の前にあるのは、昨日見た形と同じだ。
絶対にバレていると思うのだが、バレていないと言うのだからそうなのだろう。
すべてが再構成される力とはいえ、血まみれで街中を走り回った事実は消えないというのに。
あいつはいつも褒めてくれる。
ほとんどが生まれ持った不思議な力によって決まるこの世界で、腕前を褒められるのは悪い気がしない。
ただ逆に、この力を使うのはそんなに好きではなかった。
目の前で笑うあいつは力を使う前後で何も変わっちゃいない。
そのはずなのに、何かが軋み続けて音をたてる。
妙に耳に残るその音が、ずっと自分を呼んでいるような気がしていた。
どうも自分は考えが後ろ向きになりがちだ。
きっとこいつのように、何にでも挑戦していくほうがいいのだろう。
だからではないが、目の前で飛び跳ねる相手がどんなに腹立たしいポーズでねだってこようと、
襟首を掴んで揺さぶってこようと、それに反対する気は少しもなかった。
これは明日まで帰ってこられないな、と目を閉じて観念する。
力を使ってこっちは疲れるが、向こうは元気いっぱいだ。
あいつにしては珍しく、一瞬の間を置いて、大きく息を吸って口にした。
その姿を見ても、ため息しかでてこない自分はやはりどうにも後ろ向きだ。
ずっと何かに依存していて、それ無しでは生きられない。
だけど、だからこそ支えられるものだってある。
いずれはこうして遊べなくなるとわかっていても、その時がくるまではずっとついて行こうと決めた。



ENo.270 レン とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。









使役LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
セラエ(1043) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『銀色のシガーケース』を作製してもらいました!
⇒ 銀色のシガーケース/装飾:強さ35/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ウレイ(419) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『生焼けのホットケーキ』をつくってもらいました!
⇒ 生焼けのホットケーキ/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
唯(369) とカードを交換しました!
栗鼠年 (ヒールポーション)


デアデビル を研究しました!(深度0⇒1)
イグニス を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
ラッシュ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ツクモ(106) は ぬめぬめ を入手!
クリス(169) は 何かの殻 を入手!
ハイネ(416) は ボロ布 を入手!
ウレイ(419) は ぬめぬめ を入手!
ツクモ(106) は 羽 を入手!
クリス(169) は ねばねば を入手!
ツクモ(106) は 甲殻 を入手!
クリス(169) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ハイネ(416) のもとに オオホタル が泣きながら近づいてきます。
ハイネ(416) のもとに 豆ゾンビ がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
ハイネ(416) のもとに ヤンキー が微笑を浮かべて近づいてきます。



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――



























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



本を眺める視界の端に、ぶんぶんと手を振る姿が見えた。
「やーっと見つけた!やっほーハイネ!」 |
蒼い瞳に金色の髪。光に透かせばうっすらと紫色に見えるそれは、
離れたところからでもキラキラと輝いて見えた。
駆け寄ってくるその姿は今もたまに夢に見る。
もう、だいぶ昔のことだと言うのに。
「まさかこんなに手間取るとは思わなかったよ。 君はほんとに神出鬼没というかなんというか」 |
Thistle = Nirelia
ぴょんぴょんと飛び跳ねるあいつは、だいたいいつもこんな感じでやってきた。
山の上、湖の下、森の中に洞窟の奥。目を離すとすぐに居なくなって、気付けばまた帰ってくる。
こっちはだいたいどこかで本を読んでいるというのに。
どちらかと言えば、神出鬼没なのはあっちのほうだと今でも思っている。
| ハイネ 「お前はいつも無意味に明るいな」 |
どこにでも走っていく彼は、初めのうちはとても異質なものに映った。
どちらかと言えばインドア派の自分には、まるで太陽のように思えたのである。
| ニレリア 「いいや違うね。君が暗いんだと思うな」 |
だからだろうか。
ずれた歯車同士とでも言うべきか。
本来噛み合うとも思えなかった僕ら2人は、何故か意気投合して良く一緒に居た。
| ハイネ 「暗いと言われると否定できないから困るな」 |
数少ない、いや、唯一といっていい友達だ。
少なくとも過去において、彼以上に気が合う相手に出会ったことがない。
イバラシティに引っ越してくる前、もっともっと遠いところで暮らしていた。
こことは違う、でも、不思議な力が認知された国。
その国はもっともっと西の先、それこそ世界の果てなんじゃないかってところにあって、
そんなに大きくはなかったように思う。
雪はあまり降らない暖かな気候で、どちらかと言えば農業に力を入れていた。
今になって思い返してみれば、不思議な力の存在も相まって笑ってしまうほど
ファンタジーな世界だったように思える。
近代化から大きく遅れていたのは、僕らの持つ不思議な力のせいもあったのだろう。
皆がそれぞれ能力に応じた役割を持っていて、その多くが、代々引き継いだ能力に依存していた。
周りにもそういった国々がいくつかあって、いつも面倒ないざこざがあった。
この時代に未だに剣士が居て、弓手が居て、魔女が居て、かと思えば近代の装備に身を包んだ人々も居る。
どちらにせよ、生活の多くを不思議な力に依存した僕たちは、
今更外に出ていく気もなく、外からの変化を受け入れることもなく、
ただただ、不思議な力で隠匿された領地を取り合う争いを続けていた。
時代から取り残された僕らは、遠くない未来に消えてしまう運命だった。
| ニレリア 「あぁ、そうそう忘れてた。そんな話をしにきたんじゃないんだよ」 |
僕らはまだ戦う必要もなくて、こうして屋上でただただ本でも読んでいれば良かったのだけど、
どうにもあいつはそうは思っていないようだった。
| ニレリア 「いやほら、また擦りむいちゃってさ。母さん達にバレる前に治したいんだよね」 |
そう言って、いつも血まみれの体を見せてくる。
初めは驚いたものだが、今ではすっかり慣れてしまった。
大人になってから大概のことが気にならなくなったのは、絶対あいつのせいだと思っている。
| ハイネ 「擦りむいた、ね」 |
今日は胸元から縦一直線に血の痕がついていたけれど、確かにこれくらいは大したことがない。
前は腕がなかったし、その前は足がなかったし、大穴が空いていたこともある。
思わずため息が漏れた。
手を振りながら走ってくるからだいぶ混乱してしまう。
ニッ、と笑って見せるあいつはいつもどこかしら怪我していたように思えた。
| ハイネ 「……また洞窟に潜ってたのか?その探究心がどこからくるのか不思議でならないよ」 |
そう言いながら、血に濡れた手や足を元に戻してやるのが、いつもの流れだった。
| ハイネ 「はぁ……」 |
手を伸ばした。血まみれのニレリアの腕を手に取り、指先で触れる。
指先から炎が燃え移った。
| 指先が光に包まれる |
初めは熱いらしい。けれど、すぐに仄かな暖かさしか感じなくなると言っていた。
| 血まみれの体の上を炎の波が伝っていく |
体を這う炎の波が、埃も、汗も、涙も、古い体のすべてを焼き尽くして即座に再生させる。
完璧な肉体の再構成。本来あるべき正常な姿へと、物質を組み上げ直す。
ぼろぼろに破れた服も、繊維の一本に至るまで再現された。
血まみれの姿なんてどこにもない。目の前にあるのは、昨日見た形と同じだ。
| ハイネ 「終わったぞ」 |
| ニレリア 「おぉ、何度見ても不思議だ。これなら母さんにもバレっこない」 |
絶対にバレていると思うのだが、バレていないと言うのだからそうなのだろう。
すべてが再構成される力とはいえ、血まみれで街中を走り回った事実は消えないというのに。
| ニレリア 「ハイネのこれと、コーヒーの味だけは逆立ちしても追いつける気がしないよ」 |
あいつはいつも褒めてくれる。
ほとんどが生まれ持った不思議な力によって決まるこの世界で、腕前を褒められるのは悪い気がしない。
ただ逆に、この力を使うのはそんなに好きではなかった。
| ハイネ 「……」 |
目の前で笑うあいつは力を使う前後で何も変わっちゃいない。
そのはずなのに、何かが軋み続けて音をたてる。
妙に耳に残るその音が、ずっと自分を呼んでいるような気がしていた。
| ニレリア 「力を使ってもらうと、なんだか凄くいい音が聞こえるんだよね。 毎回思うけどなんだろうねこれ」 |
| ニレリア 「なぁ、これハイネの音楽的才能に由来するんじゃないか。 将来は音楽家もいけるかもしれないよ。コーヒーを淹れてギターでも引いてさ、最高じゃん!」 |
| ハイネ 「……はは、音楽家はともかく、コーヒーのほうは考えておくよ」 |
どうも自分は考えが後ろ向きになりがちだ。
きっとこいつのように、何にでも挑戦していくほうがいいのだろう。
| ニレリア 「ところでさ、こうして怪我も治ったわけだよ。ねぇねぇねぇねぇ、遊びに行こ~~~よ~~~!」 |
だからではないが、目の前で飛び跳ねる相手がどんなに腹立たしいポーズでねだってこようと、
襟首を掴んで揺さぶってこようと、それに反対する気は少しもなかった。
| ハイネ 「はぁ……。……しかたない、どこまで行くんだ」 |
これは明日まで帰ってこられないな、と目を閉じて観念する。
力を使ってこっちは疲れるが、向こうは元気いっぱいだ。
| ニレリア 「よし来た!試練の洞窟の5階まで行こう」 |
| ハイネ 「あれはまだ大人が居ないと入っちゃいけないんじゃなかったか、 というか、20歳までに踏破すればいいんだよな」 |
| ニレリア 「20歳なんて待ってられないね!さっきも行ってきたんだから大丈夫さ」 |
| ハイネ 「血まみれで帰ってきたくせに、よくもまぁそんな自信がでるものだ」 |
| ニレリア 「だからハイネのところに来たんだろ。ハイネがいれば道に迷うことはないし、謎解きはすぐにクリアしちゃうし、食べられる植物だってわかるし、調理法もわかるし、怪我したって死なないもんね、それに」 |
あいつにしては珍しく、一瞬の間を置いて、大きく息を吸って口にした。
| ニレリア 「僕は早く王になりたいんだよ!試練なんかで止まってられない!」 |
| ニレリア 「戦いは任せろ、体は任せた! ばーっと駆け抜けて僕を王にしてくれ!この国を再生させるためにさ!」 |
その姿を見ても、ため息しかでてこない自分はやはりどうにも後ろ向きだ。
ずっと何かに依存していて、それ無しでは生きられない。
だけど、だからこそ支えられるものだってある。
いずれはこうして遊べなくなるとわかっていても、その時がくるまではずっとついて行こうと決めた。



ENo.270 レン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| ツクモ 「…行き先、ちゃんと分かってるのかな?」 |
 |
クリス 「いよっし!みんな私についてこい!!」 |
 |
ウレイ 「着いていくのは良いけど行き先はちゃんと確認してよね。 訳解らない土地で迷子なんてオチは勘弁なんだから」 |
ItemNo.7 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。





狐火の徒
|
 |
H&OoH WORLD
|



使役LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
セラエ(1043) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『銀色のシガーケース』を作製してもらいました!
⇒ 銀色のシガーケース/装飾:強さ35/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ウレイ(419) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『生焼けのホットケーキ』をつくってもらいました!
⇒ 生焼けのホットケーキ/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
 |
ウレイ 「あれ、おかしいな…書いてある通りに火加減調整したんだけど」 |
唯(369) とカードを交換しました!
栗鼠年 (ヒールポーション)


デアデビル を研究しました!(深度0⇒1)
イグニス を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
ラッシュ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ツクモ(106) は ぬめぬめ を入手!
クリス(169) は 何かの殻 を入手!
ハイネ(416) は ボロ布 を入手!
ウレイ(419) は ぬめぬめ を入手!
ツクモ(106) は 羽 を入手!
クリス(169) は ねばねば を入手!
ツクモ(106) は 甲殻 を入手!
クリス(169) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ハイネ(416) のもとに オオホタル が泣きながら近づいてきます。
ハイネ(416) のもとに 豆ゾンビ がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
ハイネ(416) のもとに ヤンキー が微笑を浮かべて近づいてきます。



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。





ENo.416
薊野 灰音



氏名:薊野 灰音【アザミノ ハイネ】
年齢:20 歳
身長:180 cm
創峰大学の一年生。
1年間別の大学に通っていたが退学し今の大学に入り直した。
必要科目ぎりぎりでやる気がないように見えるが講義態度はいたってまじめ。書かれるノートは参考書よりも参考書らしい。
講義を受けていない時は喫煙所でタバコをふかす日々である。
住み込みバイトで学費を稼いでおり、授業がない日と夜間はカスミ区の喫茶店で珈琲の味を追求し続けている。恐らく、授業よりも本気度が高い。
常に吹かしているタバコは異能のせいか、灰は落ちず匂いもしない。本来は花の香りがするらしい。
------
【異能】
不死鳥の聖灰
灰や燃え痕に必要な元素を加えることで、元の形を作り出すことができる再生の異能。一方で、水の入った紙コップに水は戻らないし、形のないものは元に戻すことはできない。
【ペット】
カエル
よく左肩に乗っている不思議な生き物。虫などを食べない代わりに無機物を丸呑みにして形を真似ることができる。擬態の一種のようであるが、その精度は異常なほど高い。イバラシティの異能の影響を受けた変異種であると考えられている。食べたものを吐き出すこともできるため、バッグの代わりになっている。
年齢:20 歳
身長:180 cm
創峰大学の一年生。
1年間別の大学に通っていたが退学し今の大学に入り直した。
必要科目ぎりぎりでやる気がないように見えるが講義態度はいたってまじめ。書かれるノートは参考書よりも参考書らしい。
講義を受けていない時は喫煙所でタバコをふかす日々である。
住み込みバイトで学費を稼いでおり、授業がない日と夜間はカスミ区の喫茶店で珈琲の味を追求し続けている。恐らく、授業よりも本気度が高い。
常に吹かしているタバコは異能のせいか、灰は落ちず匂いもしない。本来は花の香りがするらしい。
------
【異能】
不死鳥の聖灰
灰や燃え痕に必要な元素を加えることで、元の形を作り出すことができる再生の異能。一方で、水の入った紙コップに水は戻らないし、形のないものは元に戻すことはできない。
【ペット】
カエル
よく左肩に乗っている不思議な生き物。虫などを食べない代わりに無機物を丸呑みにして形を真似ることができる。擬態の一種のようであるが、その精度は異常なほど高い。イバラシティの異能の影響を受けた変異種であると考えられている。食べたものを吐き出すこともできるため、バッグの代わりになっている。
21 / 30
54 PS
チナミ区
I-11
I-11









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 防刃モッズコート | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 銀色のシガーケース | 装飾 | 35 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 生焼けのホットケーキ | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 使役 | 15 | エイド/援護 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 25 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| パワーブースター | 5 | 0 | 40 | 自従:AT・DF・DX・AG・HL増(3T) | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| マインドリカバー | 5 | 0 | 0 | 自:連続減+SP30%以下ならSP増+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]デアデビル | [ 1 ]アリア | [ 1 ]チャージ |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]ハードブレイク | [ 1 ]イグニス |

PL / 揚げノワール