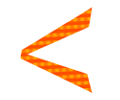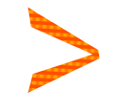<< 0:00~0:00




此処は・・・・?地面、そう。地面が有る。
と言う事はそうか。私は今地に立っているのだな。何とも奇妙な話だ。己が何処に居て、立っているのか座って居るのかさえ判断出来ないとは。
そこでもう一つ気づいた事が有る。眼前が暗い。目を閉じていたようだ。ゆっくりと瞼を開いてみる。
うむ、殺伐とした景色が見える。視力は問題無い様だ。しかし景色に見覚えが有るような気もしたが、やはり無かった。ここは・・・?
目の前には男がいた。こんな近距離に居て気配さえ読み取れないとは。
男はこの場の事、自分が(ドチラ)なのか、等を一方的に話しきると良く分からない生き物を残して行ってしまった。忙しいのだろうか。
私は向って来る生き物を退けながら、男の話から自分の他にも知能を持った生き物がいるのだろうと推察した。そして相対する者が居るという事も。
しかし先ほどの戦闘を経て理解した事が有る。自分が色々な事を忘れていたという事に。
自分の一人称は余で、異形の怪人だという事。そして元は人だったという事。
己がアンジニティの生き物で在りながらイバラで生きイバラとして就いた記憶。
だが何故かアンジニティとして過ごしていた時分の記憶は支離滅裂で、まるで熱に浮かされた夜に見る悪夢の様な異様さがあった。故にこれが果たして本当に己の記憶なのか、今の自分には判別が付かなかった。
「イルハザーク」
これからどうするべきか思案していると、唐突に名を呼ぶ声がした。その音により余は己の名を思い出した。そうだった。これは、イルハザークは、余の名だ。
「何時まで呆けているのだ。今のお前は己で思考する事も可能であろう。返事くらいしろ」
背後の声が呆れた様にため息をつく。
「あぁ・・・」
余は返事のつもりで発声したが、存外それは弱弱しいものとなってしまった。
イバラではなんの支障もなく会話をしていた気がするのだが、今は何故かとても懐かしく感じる。
今の姿といい、色々と勝手が違うのだろう。イレギュラーなこの空間において思考に没頭するのは得策では無い。余はそう結論付け考える事をやめた。
「まるで虫の羽音の様だな・・・情けない」
背後の声は吐き捨てる様にそう呟くと、こちらに近づいて来た。先程まで感じなかった殺気に咄嗟に余も振り返る。しかし目の前には人影は無かった。
「下だ」
己の胸元からする声に視線を下げると、そこには一人の娘が居た。容姿にとても見覚えが有る。何処かで遭った事が有るのだろうか・・・。
「己を見ても分らんか。まあ今のお前は絞りカスの様な物だからな・・・。それに、幾ら元が同じとてお前と同じ姿で居るのも適わん。故に我はこの女の姿で居る事にした。
本来であれば今ここでお前を消し去りたい所だが、生憎我も顕現したばかり。今は見逃してやろう」
娘は良く分からない事をこれまた一方的に告げると、踵を返し去ってしまった。先程の男と言い、今しがたの娘と言い、この地に居る者は一方的な話が好きなのか。
だが無駄な争いを回避出来た様なので、それには内心ホッとした。先の謎の生物と対峙した際余り思う様に動けなかった為だ。この状態のままでよく知らない相手と戦闘になれば
恐らく無傷では居られなかっただろう。あの娘が何者で何が目的なのか全く分らないが、この場に存在し、口ぶりから戦闘を行える様子であった事も含め自分と相対する者、なのだろうか・・・。
「分からぬ事ばかりだな・・・」
思わず口をついて出た言葉に自分で嘲笑してしまう。
己の事も殆ど思い出せない異形の自分がただただイバラ側としてアンジニティと争え・・・か。等と取り留めの無い感情に流されかけていた所でふとある記憶が蘇った。
己が学生としてイバラで過ごしていた時、共に居た学生達。その殆どとは話す事も適わなかったが、ほんの少しだけ会話をした者も居た。余が入学するつもりであった学校の学生もその一人だった。
余の振る舞いに呆れた様子ながらも会話をしてくれていた横顔を思い出したのだ。あの学生は無事だろうか・・・。彼もこの地に居るのだろうか。もし居るのならばイバラなのか。それとも・・・。
己が在籍していたクラスの子供達の顔も思い浮かぶが、同じ様な結果にしかならず、結局は考えるだけ無駄に終わった。
「しかしどうしたものか・・・あの男の口ぶりからすると、これから先も交戦は避けられぬ様だしな・・・下手に動く訳にもいくまい」
十分に動けない現状単独で動くのは危険だが、仲間となりえる存在が居る保証も無い。しかしそれと同時に今の己の様に動くに動けぬ者が居るのかも知れない。
そこまで考え至った所で余は腹を括る事にした。何故今自分がこの姿なのか、そして何故アンジニティで在りながら、イバラシティの側なのか。理解の出来ない事ばかりだが、
何処かで動けぬ者が居るのなら向かうべきだと、ただそう思った。
いざ行かん!と足を踏み出そうとした所で丁度目の前にタクシーが止まった。そう、あのタクシーだ。
先程まで本当に気配も何も無かったのに、タクシーだ。やはりこの場所は色々おかしい。改めてそう思った。
乗るかどうかを問われ凄まじく胡散臭くも感じたが、仮にこの運転手があちら側であればこんな勿体ぶった演出もする必要は無い・・・のか?
と考え至り、余は乗る事にした。全く現実的なタクシーという乗り物に、余という怪人が乗り込む様は奇異でしかない筈なのだが、運転手は慣れた様子で話しかけて来た。
余以外にも乗車した者が居るのだろうか。怪人等。等とこの状況に若干戸惑っているとあっという間に行き先が決まった。本当にこの場に居る者は話が早い。正直余は話半分も頭に入って
いないぞ。
等と不満を覚える事が出来る程には現状に慣れて来た所でタクシーは発射した。流れる景色に目を向けながらこれから先どうなって行くのか。
余の漠然とした心とは裏腹にタクシーは軽快に道を進んで行った。









駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
制約LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
泥蘇光悪渡(150) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『禁賊抜刀』を作製しました!
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『goddamn finger』を作製しました!
⇒ goddamn finger/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
瑠璃(338) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『拾ったフライパン』を作製しようとしましたが、相手から取引生産許可が出ていませんでした。
万智花(1159) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『金の首飾り』を作製してもらいました!
⇒ 金の首飾り/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
リラ(903) とカードを交換しました!
スナイプショット (ピンポイント)

アリア を研究しました!(深度0⇒1)
スコーピオン を研究しました!(深度0⇒1)
ガードフォーム を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
ティンダー を習得!
アサルト を習得!
レッドショック を習得!
デアデビル を習得!
アリア を習得!
チャージ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 C-8(水地)には移動できません。
泥蘇光悪渡(150) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 泥蘇光悪渡(150) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- イルハ(324) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ユイノ(388) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 晴(428) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――


















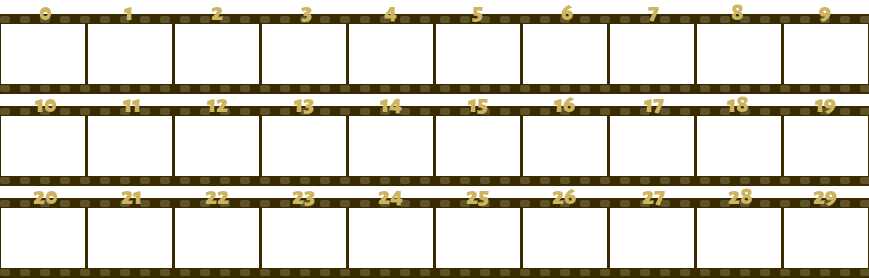





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



此処は・・・・?地面、そう。地面が有る。
と言う事はそうか。私は今地に立っているのだな。何とも奇妙な話だ。己が何処に居て、立っているのか座って居るのかさえ判断出来ないとは。
そこでもう一つ気づいた事が有る。眼前が暗い。目を閉じていたようだ。ゆっくりと瞼を開いてみる。
うむ、殺伐とした景色が見える。視力は問題無い様だ。しかし景色に見覚えが有るような気もしたが、やはり無かった。ここは・・・?
目の前には男がいた。こんな近距離に居て気配さえ読み取れないとは。
男はこの場の事、自分が(ドチラ)なのか、等を一方的に話しきると良く分からない生き物を残して行ってしまった。忙しいのだろうか。
私は向って来る生き物を退けながら、男の話から自分の他にも知能を持った生き物がいるのだろうと推察した。そして相対する者が居るという事も。
しかし先ほどの戦闘を経て理解した事が有る。自分が色々な事を忘れていたという事に。
自分の一人称は余で、異形の怪人だという事。そして元は人だったという事。
己がアンジニティの生き物で在りながらイバラで生きイバラとして就いた記憶。
だが何故かアンジニティとして過ごしていた時分の記憶は支離滅裂で、まるで熱に浮かされた夜に見る悪夢の様な異様さがあった。故にこれが果たして本当に己の記憶なのか、今の自分には判別が付かなかった。
「イルハザーク」
これからどうするべきか思案していると、唐突に名を呼ぶ声がした。その音により余は己の名を思い出した。そうだった。これは、イルハザークは、余の名だ。
「何時まで呆けているのだ。今のお前は己で思考する事も可能であろう。返事くらいしろ」
背後の声が呆れた様にため息をつく。
「あぁ・・・」
余は返事のつもりで発声したが、存外それは弱弱しいものとなってしまった。
イバラではなんの支障もなく会話をしていた気がするのだが、今は何故かとても懐かしく感じる。
今の姿といい、色々と勝手が違うのだろう。イレギュラーなこの空間において思考に没頭するのは得策では無い。余はそう結論付け考える事をやめた。
「まるで虫の羽音の様だな・・・情けない」
背後の声は吐き捨てる様にそう呟くと、こちらに近づいて来た。先程まで感じなかった殺気に咄嗟に余も振り返る。しかし目の前には人影は無かった。
「下だ」
己の胸元からする声に視線を下げると、そこには一人の娘が居た。容姿にとても見覚えが有る。何処かで遭った事が有るのだろうか・・・。
「己を見ても分らんか。まあ今のお前は絞りカスの様な物だからな・・・。それに、幾ら元が同じとてお前と同じ姿で居るのも適わん。故に我はこの女の姿で居る事にした。
本来であれば今ここでお前を消し去りたい所だが、生憎我も顕現したばかり。今は見逃してやろう」
娘は良く分からない事をこれまた一方的に告げると、踵を返し去ってしまった。先程の男と言い、今しがたの娘と言い、この地に居る者は一方的な話が好きなのか。
だが無駄な争いを回避出来た様なので、それには内心ホッとした。先の謎の生物と対峙した際余り思う様に動けなかった為だ。この状態のままでよく知らない相手と戦闘になれば
恐らく無傷では居られなかっただろう。あの娘が何者で何が目的なのか全く分らないが、この場に存在し、口ぶりから戦闘を行える様子であった事も含め自分と相対する者、なのだろうか・・・。
「分からぬ事ばかりだな・・・」
思わず口をついて出た言葉に自分で嘲笑してしまう。
己の事も殆ど思い出せない異形の自分がただただイバラ側としてアンジニティと争え・・・か。等と取り留めの無い感情に流されかけていた所でふとある記憶が蘇った。
己が学生としてイバラで過ごしていた時、共に居た学生達。その殆どとは話す事も適わなかったが、ほんの少しだけ会話をした者も居た。余が入学するつもりであった学校の学生もその一人だった。
余の振る舞いに呆れた様子ながらも会話をしてくれていた横顔を思い出したのだ。あの学生は無事だろうか・・・。彼もこの地に居るのだろうか。もし居るのならばイバラなのか。それとも・・・。
己が在籍していたクラスの子供達の顔も思い浮かぶが、同じ様な結果にしかならず、結局は考えるだけ無駄に終わった。
「しかしどうしたものか・・・あの男の口ぶりからすると、これから先も交戦は避けられぬ様だしな・・・下手に動く訳にもいくまい」
十分に動けない現状単独で動くのは危険だが、仲間となりえる存在が居る保証も無い。しかしそれと同時に今の己の様に動くに動けぬ者が居るのかも知れない。
そこまで考え至った所で余は腹を括る事にした。何故今自分がこの姿なのか、そして何故アンジニティで在りながら、イバラシティの側なのか。理解の出来ない事ばかりだが、
何処かで動けぬ者が居るのなら向かうべきだと、ただそう思った。
いざ行かん!と足を踏み出そうとした所で丁度目の前にタクシーが止まった。そう、あのタクシーだ。
先程まで本当に気配も何も無かったのに、タクシーだ。やはりこの場所は色々おかしい。改めてそう思った。
乗るかどうかを問われ凄まじく胡散臭くも感じたが、仮にこの運転手があちら側であればこんな勿体ぶった演出もする必要は無い・・・のか?
と考え至り、余は乗る事にした。全く現実的なタクシーという乗り物に、余という怪人が乗り込む様は奇異でしかない筈なのだが、運転手は慣れた様子で話しかけて来た。
余以外にも乗車した者が居るのだろうか。怪人等。等とこの状況に若干戸惑っているとあっという間に行き先が決まった。本当にこの場に居る者は話が早い。正直余は話半分も頭に入って
いないぞ。
等と不満を覚える事が出来る程には現状に慣れて来た所でタクシーは発射した。流れる景色に目を向けながらこれから先どうなって行くのか。
余の漠然とした心とは裏腹にタクシーは軽快に道を進んで行った。



 |
イーサン 「余に任せておくが良い。」 |





駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
制約LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
泥蘇光悪渡(150) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『禁賊抜刀』を作製しました!
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『goddamn finger』を作製しました!
⇒ goddamn finger/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
イーサン 「ふふふ!これはどうだ?」 |
瑠璃(338) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『拾ったフライパン』を作製しようとしましたが、相手から取引生産許可が出ていませんでした。
万智花(1159) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『金の首飾り』を作製してもらいました!
⇒ 金の首飾り/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
リラ(903) とカードを交換しました!
スナイプショット (ピンポイント)

アリア を研究しました!(深度0⇒1)
スコーピオン を研究しました!(深度0⇒1)
ガードフォーム を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
ティンダー を習得!
アサルト を習得!
レッドショック を習得!
デアデビル を習得!
アリア を習得!
チャージ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ひと仕事っと。一服してから次行くかねぇ。」 |
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 C-8(水地)には移動できません。
泥蘇光悪渡(150) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 泥蘇光悪渡(150) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- イルハ(324) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ユイノ(388) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 晴(428) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――







外道ヒーロー「泥蘇光悪渡・悪漢」
|
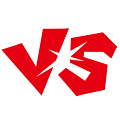 |
アンヂニチィ
|


ENo.324
イーサン/イーちゃん



姫園イーサン
身長177cm(ヒール込み+15cm) 体型:筋肉質
一人称:余 二人称:お前、貴様
好きな物:肉、食べ放題、ジャンクフード、お洒落
嫌いな物:質素な食べ物、地味な物、小賢しい奴
顔だけ見ると美少女。しかし低音イケメンボイスの持ち主。
そして声がめっちゃデカい。
背格好からよく年長者に間違われるが、満更でも無い様子。
自己肯定感ゴリラなナルシスト。
普段は自信満々の振る舞いを見せるが、実の所割とポンコツ。
しかし本人はそれもまた個性なのだと気にしていない。
双子の妹にだけは頭が上がらず、塩対応に凹む様子も見られる。
養父母の元で暮らしており、姫園の性も引き取られてから名乗っている。
仲は良好で、よく家事等を手伝ったりしている。家の中では年相応な素直さを見せたり見せなかったり。
一転妹は絶賛反抗期中で、余り家に帰らない為イーサンがよく探しに出掛けたりもしている。
身長177cm(ヒール込み+15cm) 体型:筋肉質
一人称:余 二人称:お前、貴様
好きな物:肉、食べ放題、ジャンクフード、お洒落
嫌いな物:質素な食べ物、地味な物、小賢しい奴
顔だけ見ると美少女。しかし低音イケメンボイスの持ち主。
そして声がめっちゃデカい。
背格好からよく年長者に間違われるが、満更でも無い様子。
自己肯定感ゴリラなナルシスト。
普段は自信満々の振る舞いを見せるが、実の所割とポンコツ。
しかし本人はそれもまた個性なのだと気にしていない。
双子の妹にだけは頭が上がらず、塩対応に凹む様子も見られる。
養父母の元で暮らしており、姫園の性も引き取られてから名乗っている。
仲は良好で、よく家事等を手伝ったりしている。家の中では年相応な素直さを見せたり見せなかったり。
一転妹は絶賛反抗期中で、余り家に帰らない為イーサンがよく探しに出掛けたりもしている。
26 / 30
5 PS
チナミ区
D-8
D-8




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | goddamn finger | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 金の首飾り | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 武器 | 20 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| 決3 | アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ガードフォーム | [ 1 ]アリア | [ 1 ]スコーピオン |

PL / 大介