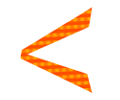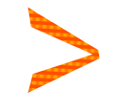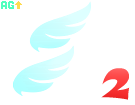<< 0:00~0:00




/00
「この街にとって"守り人"が多すぎるのも都合が悪い」と、いかにも今考えましたと言わんばかりの理由を告げられた双海七夏は、幾つかの反論を思い浮かべながらも飲み込んで、叔父に促されるままに地元を離れ、単身イバラシティへと引っ越す運びとなった。
住む場所が変わること自体は構わない。けれど、電脳通信に最適化されたあの街を出るというのであれば心境も複雑になろうものだ。
電脳化した人間に向けてあらゆる面に配慮された街から一転、あえて非効率な暮らしを送った際の何かしらの変化を観察したい、などと大層な言い訳まで添えられてしまっては、最早辞退する道も残ってはいない。
もっと言えば、学業や守り人としての仕事以外で外出する機会を増やす為に、そういった力技に訴えたのかとすら思えるからなお質が悪い。
律儀に高校受験までさせられた挙げ句、諸々の準備から開放され「さあ文句の一つでもぶつけてやろう」とその気になったのが出発便のフェリーの船上とくれば、当時の自分がいかに滅入っていたかがよくわかる。
せめてもの助け舟と称して電通用通信衛星の一基から回線を幾つか都合したと教えられた時、呆れすら覚えたのは記憶に新しい。
そういった次第で船が着いたのはイバラシティ西部、オオキタ区はオオキタ港。
特筆するほど観光に時間を割けなかったので名物その他については割愛するとして、どうも下船直後から脳に違和感を覚え始めていた。
そこでは船酔いの類いだと判断し、次いで駅から電車に揺られウラド駅へ向かう。
更にバスを利用して隣街ツクナミ区で下車したその時、鈍い頭痛に襲われた。
「う、あ――」
ただの頭痛というよりも寧ろ電脳内の不調に由来するような――ブレインハックにも似た不可解な感覚。
防壁を抜かれた感触も無ければ、電脳使いらしき気配すらもない。
それでも脳内にはうるさいくらいに警報が鳴り響き、赤く染まったウィンドウが異常を知らせる。
電脳に常駐していた緑の相棒の手も借りて、なんとか近くのベンチに腰を下ろすと、七夏は頭を抱える。
「全体的に動作が鈍い……鈍い? 大容量の通信をしているわけでもあるまいに……」
通信の混線や通信妨害などは検出されていないし、そもそもそれらに影響されるほどやわではない。
ましてこんな環境で膨大なデータをダウンロードしているはずもないが――
「……なに、これ」
原因を精査していて、電脳の記憶領域の一角に、あらゆる操作を受け付けない詳細不明のファイルが一つ見つかった。
どうやらデータ容量が少しずつ増えているらしいそれは、今この時も更新され続け肥大化を進めている。
「記憶にない」の一言で片付けるにはあまりに不審で、不思議なファイル。
理解の外側に位置しながら、けれどどこか見覚えのある、得体の知れない"何か"がそこにある。
「ぅぐ――」
一瞬、鋭い痛みに苛まれ、視界が白ける。
耳鳴りめいた雑音を伴って、精神が肉体から引き抜かれるような錯覚に全身が痺れていく。
脱力して地面に座り込んでしまったのだろう、脚に妙な冷たさがあった。
「――は、ぁ……はっ、う――」
痛みも痺れもすぐに引き、両の目にも色が戻る。
荒い呼吸に肩を震わせ、手にべっとりとついた脂汗に視線を落とし、今一度大きく息を吐いた。
いつの間にやら視界の隅で点滅していた電脳通信の呼び出しに応答するだけして、人目も憚らずベンチに体を預ける。
『無事に着いたかい、七夏』
「……無事、といえば確かに無事だろうね」
微かなノイズが混じる、聞き慣れた男の声。
音だけで聞けば爽やかであるのに、どこか底知れなさを感じずにはいられない不気味な声。
事の発端とも言える叔父の呼びかけに僅かながらの安心感を覚えつつ、やや遅れて返事をする。
『七夏、何かあったね?』
「…………」
『何かあったんだろう。隠してどうなるものでもないのだから、言ってごらん』
双海七夏という少女は、昔から叔父相手に頭が上がらない。その最たるものがこの察しの良さだ。
一時期理屈を確かめようとして躍起になったことがあったが、自分のような超能力由来であるのか、或いは叔父と姪という関係性が原因なのか、結局答えが出ないまま終わってしまった。
苦手な人物の一人に嘘をつく元気もなく、七夏はありのままを説明して判断を仰ぐ。
『――なるほどね。今の様子はどうだい?』
「特に何も。相変わらずこちらからのアクションには反応がないし、図体もかなりのものだ」
すっかり痛みは引き、電脳全体の動作は通常通り回復している。
件のファイルも容量は先程より更に跳ね上がったが、今は静かだ。最終更新日時は鋭い頭痛と同時刻とある。
『聞いた限りでは、キミがそこを訪れたことに関係がありそうだな』
「心当たりと言ったら、まあ。ただそうなると一番怪しいのが叔父さんってことになるんじゃあ」
『その街を推薦したのが僕で、電通を寄越したタイミングもぴったりだから、か。残念ながら反証が見つからないな』
「あくまで可能性の一つとしてだけど。言い出すとキリが無さそうだ」
冗談めかして小さく笑ってみせると、ふと脳裏に浮かんだことを尋ねる。
「……叔父さん。わたし、"モンブラン"はどうしたんだっけ」
『モンブラン? 食べ残しかい? 冷蔵庫にはそんなもの入ってなかったような』
「いや、何かみーちゃんに謝らないといけないことが、あった、よう……な――」
声に出すにつれ、次第に思考にもやがかかり始める。
そうだ、自分は確かに"モンブラン"を持ち出して、彼女と――――
――彼女? 久護、未来?
あの子との間に何かあったのか? あの子に何をしたんだ?
なにか、取り返しのつかないような、こと?
……いつ? どこで?
考えが纏まらない。記憶の海は荒波立って邪魔をする。
憶えているはずのこと、自分が体験したはずのことが、何故だかまるで思い出せない。
知っているはずのこと、何度も苦しんだはずのことが、何故だかまるで思い出せない。
確かにそこにあるのに、その記憶はどこか大きくズレている。
確かにあの時見たのに、その記憶はとても大きく違っている。
今の相手と一致しない。今の時間と一致しない。
それはまるで、複数の記憶が混在しているかのような。
「……キベルネテス、キミは……」
名前を呼ぶ。はっきりと声に出して、その名を口にする。
何かしでかしたんじゃないか、と。
それが出来るとしたらお前だけだろう、と。
長い間を共に過ごした相棒の名前を発声しても、当然、答えなど返ってこない。
口が利けないからというだけではない。偏に何も知らないからだ。
「…………」
『――聞こえているのかい、七夏』
「……え、あれ。叔父さん? どうして……」
『どうして、って……さてはかなり疲れているね?
今日は早めに休みなさい。念のため制御ソフトの調子も確認するように』
返答を待たず通信が切れ、ウィンドウが閉じる。
かくして明らかとなった記憶の齟齬が、この上なく不愉快でもどかしい。
そも"モンブラン"とは何のことか、先程の自分の言動にさえ疑問符が浮かぶ。
あの街で他人の記憶に潜った時は、一度たりともこうはならなかったのに。
「……休もう。部屋は手配してあるはず、確か――」
"あなたが意識してたかまでは分かりかねるけれど、このエクレールって皮肉な名前よね"
この街に居るはずのない者の声がする。
幻聴か、幻覚か。どちらにせよ、電脳の不調は早急に対処しなくては。
エクレールツクナミ、702号室。
初めて訪れる気がしないその部屋で、双海七夏は眠りに落ちた。
◆ ◆ ◆
"「どこまでも付き合ってもらうぞ、キベルネテス」"
◆ ◆ ◆
/01
ハザマ。狭間の世界。どちらでもあって、どちらでもない世界。
覚えのある街並み。しかし決定的に異なって見える荒廃した街。
初めて訪れる場所。けれども来たくはなかったと頭が痛む場所。
本来はその程度の認識で済むはずだった光景。
所持品をリストアップし、置かれた状況を確かめて、"ミクスタ"の存在を認めたところで――
ここに来てようやく、記憶領域にあった謎のデータがアクセスを受け付けた。
真っ先に視界に飛び込んできたのは、殆ど同じ場所に立つ自分自身の姿だった。
空を見上げ、古臭い作りのメッセージシステムに繋いでは、どこかへと走っていく自分。
乱れる呼吸、痛む胸や足までも精確に追体験しながら記憶を辿る。
そうして駆け抜けた廃墟のどこか、ぽつんと佇む少女に声をかけ。
こちらに振り向いたその顔を目にした瞬間、記憶への接続が弾かれた。
「……そうか。これはそういう記憶だったんだな」
ようやく合点がいった。
あの街で暮らし始めてから記憶に齟齬が生じた原因。
事あるごとに脳裏にちらつく、やけに鮮明な幻聴の、幻覚の正体。
こ こ
ハザマに来るまで干渉出来ずにいた、最大の理由。
「もう一人の双海七夏、か。
突拍子もない話だけれど、なるほど"わたし"の考えそうなことだ」
それは、或いはありえたかもしれない可能性の一つ。
本来観測されるはずのない、別の時間軸に位置する自分の記憶。
そういった異物が流れ込んで、不明なファイルとして堆積していったのなら。
「あの子に会う必要がある。でも――」
会って、何を話す?
ここでの彼女は味方ではないかもしれない。
話が通じるかも定かでないのに、この身を危険に晒していいのか?
大きく息を吸い、静かに吐き出して、心を決めた。
最後に、首から下げた銀のロケットを摘み、開く。
(ごめんなさい。きっと、無事には帰れません)
中に入っている母の写真を一瞥して、何度目かの謝罪を胸に秘める。
それから蓋の内側に視線を向け、記憶との決定的な違いに歯を軋ませた。
他の誰の写真もそこにはない。
ないことを知っていながら、無意識にそちらを見やった。
何もないはずなのに――その手は震え、指に嵌めたリングとぶつかってかちんと音が鳴る。
「……わたしが信じないで、誰が彼女を信じてやれるんだ」
今更、迷う必要はない。
彼女がハザマに居るのなら、同じように確かめればいい。
もう、後悔したくはないから。
◆ ◆ ◆



ENo.195 天使様 とのやりとり

ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり

ENo.513 十神 とのやりとり

ENo.654 夏鈴 とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。






お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
解析LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
放課後探検部(723) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
アイ(783) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
ねえさん(814) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
三科(286) とカードを交換しました!
ほほえみ (ヒール)


リフレッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
リフレッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
リフレッシュ を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
ブロック を習得!
☆リンクブレイク を習得!
☆ウィークサーチ を習得!
☆技巧料理 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが6増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)
放課後探検部(723) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- アイ(783) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――





















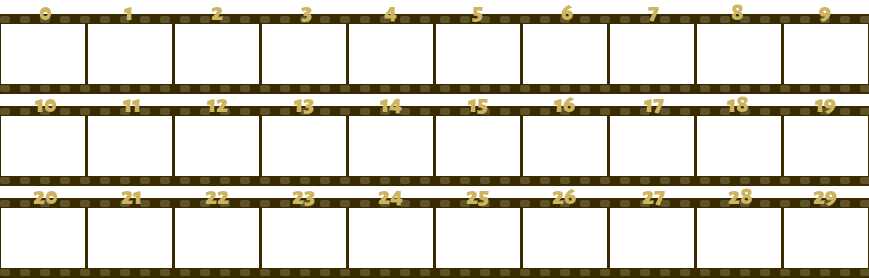





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



/00
「この街にとって"守り人"が多すぎるのも都合が悪い」と、いかにも今考えましたと言わんばかりの理由を告げられた双海七夏は、幾つかの反論を思い浮かべながらも飲み込んで、叔父に促されるままに地元を離れ、単身イバラシティへと引っ越す運びとなった。
住む場所が変わること自体は構わない。けれど、電脳通信に最適化されたあの街を出るというのであれば心境も複雑になろうものだ。
電脳化した人間に向けてあらゆる面に配慮された街から一転、あえて非効率な暮らしを送った際の何かしらの変化を観察したい、などと大層な言い訳まで添えられてしまっては、最早辞退する道も残ってはいない。
もっと言えば、学業や守り人としての仕事以外で外出する機会を増やす為に、そういった力技に訴えたのかとすら思えるからなお質が悪い。
律儀に高校受験までさせられた挙げ句、諸々の準備から開放され「さあ文句の一つでもぶつけてやろう」とその気になったのが出発便のフェリーの船上とくれば、当時の自分がいかに滅入っていたかがよくわかる。
せめてもの助け舟と称して電通用通信衛星の一基から回線を幾つか都合したと教えられた時、呆れすら覚えたのは記憶に新しい。
そういった次第で船が着いたのはイバラシティ西部、オオキタ区はオオキタ港。
特筆するほど観光に時間を割けなかったので名物その他については割愛するとして、どうも下船直後から脳に違和感を覚え始めていた。
そこでは船酔いの類いだと判断し、次いで駅から電車に揺られウラド駅へ向かう。
更にバスを利用して隣街ツクナミ区で下車したその時、鈍い頭痛に襲われた。
「う、あ――」
ただの頭痛というよりも寧ろ電脳内の不調に由来するような――ブレインハックにも似た不可解な感覚。
防壁を抜かれた感触も無ければ、電脳使いらしき気配すらもない。
それでも脳内にはうるさいくらいに警報が鳴り響き、赤く染まったウィンドウが異常を知らせる。
電脳に常駐していた緑の相棒の手も借りて、なんとか近くのベンチに腰を下ろすと、七夏は頭を抱える。
「全体的に動作が鈍い……鈍い? 大容量の通信をしているわけでもあるまいに……」
通信の混線や通信妨害などは検出されていないし、そもそもそれらに影響されるほどやわではない。
ましてこんな環境で膨大なデータをダウンロードしているはずもないが――
「……なに、これ」
原因を精査していて、電脳の記憶領域の一角に、あらゆる操作を受け付けない詳細不明のファイルが一つ見つかった。
どうやらデータ容量が少しずつ増えているらしいそれは、今この時も更新され続け肥大化を進めている。
「記憶にない」の一言で片付けるにはあまりに不審で、不思議なファイル。
理解の外側に位置しながら、けれどどこか見覚えのある、得体の知れない"何か"がそこにある。
「ぅぐ――」
一瞬、鋭い痛みに苛まれ、視界が白ける。
耳鳴りめいた雑音を伴って、精神が肉体から引き抜かれるような錯覚に全身が痺れていく。
脱力して地面に座り込んでしまったのだろう、脚に妙な冷たさがあった。
「――は、ぁ……はっ、う――」
痛みも痺れもすぐに引き、両の目にも色が戻る。
荒い呼吸に肩を震わせ、手にべっとりとついた脂汗に視線を落とし、今一度大きく息を吐いた。
いつの間にやら視界の隅で点滅していた電脳通信の呼び出しに応答するだけして、人目も憚らずベンチに体を預ける。
『無事に着いたかい、七夏』
「……無事、といえば確かに無事だろうね」
微かなノイズが混じる、聞き慣れた男の声。
音だけで聞けば爽やかであるのに、どこか底知れなさを感じずにはいられない不気味な声。
事の発端とも言える叔父の呼びかけに僅かながらの安心感を覚えつつ、やや遅れて返事をする。
『七夏、何かあったね?』
「…………」
『何かあったんだろう。隠してどうなるものでもないのだから、言ってごらん』
双海七夏という少女は、昔から叔父相手に頭が上がらない。その最たるものがこの察しの良さだ。
一時期理屈を確かめようとして躍起になったことがあったが、自分のような超能力由来であるのか、或いは叔父と姪という関係性が原因なのか、結局答えが出ないまま終わってしまった。
苦手な人物の一人に嘘をつく元気もなく、七夏はありのままを説明して判断を仰ぐ。
『――なるほどね。今の様子はどうだい?』
「特に何も。相変わらずこちらからのアクションには反応がないし、図体もかなりのものだ」
すっかり痛みは引き、電脳全体の動作は通常通り回復している。
件のファイルも容量は先程より更に跳ね上がったが、今は静かだ。最終更新日時は鋭い頭痛と同時刻とある。
『聞いた限りでは、キミがそこを訪れたことに関係がありそうだな』
「心当たりと言ったら、まあ。ただそうなると一番怪しいのが叔父さんってことになるんじゃあ」
『その街を推薦したのが僕で、電通を寄越したタイミングもぴったりだから、か。残念ながら反証が見つからないな』
「あくまで可能性の一つとしてだけど。言い出すとキリが無さそうだ」
冗談めかして小さく笑ってみせると、ふと脳裏に浮かんだことを尋ねる。
「……叔父さん。わたし、"モンブラン"はどうしたんだっけ」
『モンブラン? 食べ残しかい? 冷蔵庫にはそんなもの入ってなかったような』
「いや、何かみーちゃんに謝らないといけないことが、あった、よう……な――」
声に出すにつれ、次第に思考にもやがかかり始める。
そうだ、自分は確かに"モンブラン"を持ち出して、彼女と――――
――彼女? 久護、未来?
あの子との間に何かあったのか? あの子に何をしたんだ?
なにか、取り返しのつかないような、こと?
……いつ? どこで?
考えが纏まらない。記憶の海は荒波立って邪魔をする。
憶えているはずのこと、自分が体験したはずのことが、何故だかまるで思い出せない。
知っているはずのこと、何度も苦しんだはずのことが、何故だかまるで思い出せない。
確かにそこにあるのに、その記憶はどこか大きくズレている。
確かにあの時見たのに、その記憶はとても大きく違っている。
今の相手と一致しない。今の時間と一致しない。
それはまるで、複数の記憶が混在しているかのような。
「……キベルネテス、キミは……」
名前を呼ぶ。はっきりと声に出して、その名を口にする。
何かしでかしたんじゃないか、と。
それが出来るとしたらお前だけだろう、と。
長い間を共に過ごした相棒の名前を発声しても、当然、答えなど返ってこない。
口が利けないからというだけではない。偏に何も知らないからだ。
「…………」
『――聞こえているのかい、七夏』
「……え、あれ。叔父さん? どうして……」
『どうして、って……さてはかなり疲れているね?
今日は早めに休みなさい。念のため制御ソフトの調子も確認するように』
返答を待たず通信が切れ、ウィンドウが閉じる。
かくして明らかとなった記憶の齟齬が、この上なく不愉快でもどかしい。
そも"モンブラン"とは何のことか、先程の自分の言動にさえ疑問符が浮かぶ。
あの街で他人の記憶に潜った時は、一度たりともこうはならなかったのに。
「……休もう。部屋は手配してあるはず、確か――」
"あなたが意識してたかまでは分かりかねるけれど、このエクレールって皮肉な名前よね"
この街に居るはずのない者の声がする。
幻聴か、幻覚か。どちらにせよ、電脳の不調は早急に対処しなくては。
エクレールツクナミ、702号室。
初めて訪れる気がしないその部屋で、双海七夏は眠りに落ちた。
◆ ◆ ◆
"「どこまでも付き合ってもらうぞ、キベルネテス」"
◆ ◆ ◆
/01
ハザマ。狭間の世界。どちらでもあって、どちらでもない世界。
覚えのある街並み。しかし決定的に異なって見える荒廃した街。
初めて訪れる場所。けれども来たくはなかったと頭が痛む場所。
本来はその程度の認識で済むはずだった光景。
所持品をリストアップし、置かれた状況を確かめて、"ミクスタ"の存在を認めたところで――
ここに来てようやく、記憶領域にあった謎のデータがアクセスを受け付けた。
真っ先に視界に飛び込んできたのは、殆ど同じ場所に立つ自分自身の姿だった。
空を見上げ、古臭い作りのメッセージシステムに繋いでは、どこかへと走っていく自分。
乱れる呼吸、痛む胸や足までも精確に追体験しながら記憶を辿る。
そうして駆け抜けた廃墟のどこか、ぽつんと佇む少女に声をかけ。
こちらに振り向いたその顔を目にした瞬間、記憶への接続が弾かれた。
「……そうか。これはそういう記憶だったんだな」
ようやく合点がいった。
あの街で暮らし始めてから記憶に齟齬が生じた原因。
事あるごとに脳裏にちらつく、やけに鮮明な幻聴の、幻覚の正体。
こ こ
ハザマに来るまで干渉出来ずにいた、最大の理由。
「もう一人の双海七夏、か。
突拍子もない話だけれど、なるほど"わたし"の考えそうなことだ」
それは、或いはありえたかもしれない可能性の一つ。
本来観測されるはずのない、別の時間軸に位置する自分の記憶。
そういった異物が流れ込んで、不明なファイルとして堆積していったのなら。
「あの子に会う必要がある。でも――」
会って、何を話す?
ここでの彼女は味方ではないかもしれない。
話が通じるかも定かでないのに、この身を危険に晒していいのか?
大きく息を吸い、静かに吐き出して、心を決めた。
最後に、首から下げた銀のロケットを摘み、開く。
(ごめんなさい。きっと、無事には帰れません)
中に入っている母の写真を一瞥して、何度目かの謝罪を胸に秘める。
それから蓋の内側に視線を向け、記憶との決定的な違いに歯を軋ませた。
他の誰の写真もそこにはない。
ないことを知っていながら、無意識にそちらを見やった。
何もないはずなのに――その手は震え、指に嵌めたリングとぶつかってかちんと音が鳴る。
「……わたしが信じないで、誰が彼女を信じてやれるんだ」
今更、迷う必要はない。
彼女がハザマに居るのなら、同じように確かめればいい。
もう、後悔したくはないから。
◆ ◆ ◆



ENo.195 天使様 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.513 十神 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.654 夏鈴 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。





お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
解析LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
放課後探検部(723) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
アイ(783) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
ねえさん(814) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
三科(286) とカードを交換しました!
ほほえみ (ヒール)


リフレッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
リフレッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
リフレッシュ を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
ブロック を習得!
☆リンクブレイク を習得!
☆ウィークサーチ を習得!
☆技巧料理 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが6増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「はいお疲れさん。サービスの飴ちゃん持ってきな。」 |
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)
放課後探検部(723) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- アイ(783) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



異世界モフモフツアーズ
|
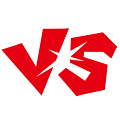 |
TeamNo.723
|


ENo.12
双海七夏



◆キャラクター紹介◆
◆メイン・左側、白髪◆
電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋
双海 七夏
http://lisge.com/ib/prof.php?id=RAkF3WGSIXxdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632
◆サブ・右側、黒髪◆
書架の守り人 - 女学院の健啖家
黒葛 彗華
http://lisge.com/ib/prof.php?id=JBJqMoQQTNCd47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3
◆ロール的連絡先◆
七夏/彗華宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165
◆メイン・左側、白髪◆
電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋
双海 七夏
http://lisge.com/ib/prof.php?id=RAkF3WGSIXxdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632
◆サブ・右側、黒髪◆
書架の守り人 - 女学院の健啖家
黒葛 彗華
http://lisge.com/ib/prof.php?id=JBJqMoQQTNCd47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3
◆ロール的連絡先◆
七夏/彗華宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165
25 / 30
5 PS
チナミ区
D-9
D-9







| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 解析 | 20 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 20 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 技巧料理 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の強さが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1~3がなくなる。 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]リフレッシュ |

PL / かのしき