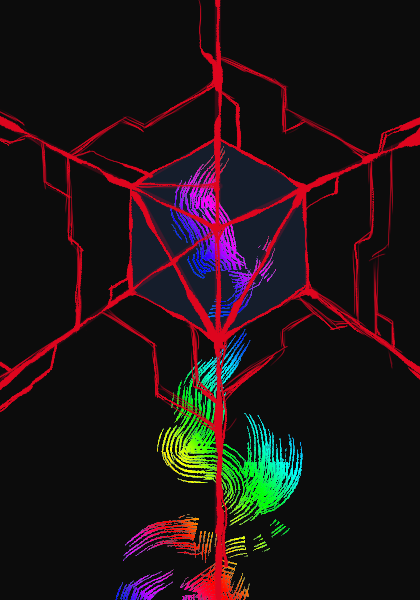<< 5:00




ぜい、ぜい、と。
苦しそうな呼吸を止めてやる方法すら、わたしにはわからなかった。
喉元を温める手でもあれば、私は何か報いてやれたろうに。
老婆が死にゆくのを、私は何をするわけでもなく、ただ見ていた。
最後の一人だった。
集落に残ったたった一人。随分前から足を悪くして、私の社の掃除にも来ることができなくなっていた。
あばら家に置いた木の板に向かって私への詫びを幾度も呟いていた。
寒くなりかけた秋口に、肺を病んで死んだ。
飢えていたので、彼女は暫く腐ることもなく、枯れ木のように布に包まれてそこにあった。
大きく開けた口に蜘蛛の巣が貼った。
やがて冬が訪れ、野犬が彼女を食い尽くした。
骨が残り、雪に潰されたあばら家が彼女の生きていた痕跡を綺麗に覆い、夏が幾つか過ぎた頃には、集落は森に飲み込まれていった。
彼女は親類に見捨てられ、集落に一人残り、近くの集落とも親交を断ち、孤独に死んだ。
彼女は集落に何を見ただろう?
親と見守った夕日だろうか、夫と毟った山菜だろうか、子を負ぶって帰った畦道だろうか。
蛙の鳴き声に眠る月夜か、外れの枯れ木が折れた嵐か、全てを奪った炎の揺らめきか。
私はそのどれも与えてやれなかった。死にゆく夢を謳うことすらしてやれなかった。
私はただ、それを見ていた。
ただ、信仰を受け取り、何をするでもなく、それを見届けた。
彼女と同じように社は朽ちていて、信仰を失った私は野犬にやる肉も持っていなかった。
彼女よりよほど早くに私の社は森の一部と化していて、森を分け入る道は蔦と落枝に塗れ、かつての私を知る者さえ社には辿り着けぬ有様と化していた。
死体にすら劣る神。
それが私だった。
なんて。
無価値な神。
追放を待つまでもなく、私は私に失望した。
『種を蒔く地を解する力』
タガシラ。
土、人の体、心。
それを種と認識すれば、向かう地を。
それを地と認識すれば、芽吹く種を。
理解できる。たったそれだけの力が成せることはとても少ない。
理解とは、それだけだ。理解をしたところで、為すべき腕がなければ、為すべき力がなければ、何をも為すことはできない。
私は私に失望した!
見守り、理解するだけの身の上に!
私は価値がない、あれらの、ヒトの一片にも満たぬ虚無でしかない!
私がヒトであったなら、
私がヒトであったなら、あの老婆を攫っていったろう。
手を取り、どこぞの街の隅で共に生きたろう。
彼女がそれを望まぬのなら、集落に住み続けても構わなかった。
私がヒトであったなら。
『堕神祠』
ダカンシ。
そうして私は肉を持った。
しあわせになりたい、と、ヒトは言う。
だから私は歓喜をもってそれを迎えよう。
価値のない私が、お前たちに寄り添おう。
お前の望みを叶えてやろう。
「お前はがんばってここまで来たのだね」
聞こえているかどうかわからないけれど、少年がそれを望んだので、私は少年に幸福を与えてやることにした。ぜい、ぜい、と苦しげな呼吸にそっと枯れた手を添えて、私は少年に夢を囁いてやることにした。
少年は不幸な生い立ちだった。旧い農村にも見られた、不幸な子供であったのだ。少年を守るべき大人たちに搾取され、抵抗するすべも持たず、与えられるべき糧を心にも体にも与えられず、しかし『なぜ苦しいのか』を教えられることもなく、ただ、苦痛に喘いでいる。かつて、彼らは湖や崖の下へ身を投げていったけれど、それは孤独な道行きであったことだろう。
彼には今、私がいる。
傷つけられた魂は元には戻るまい。
しかし、緩やかに、穏やかに、眠るように痺れさせ、休ませるすべを私は既に手に入れていた。
それは、ことばを放つ口であり、差し伸べることのできる腕であり、寄り添うことのできる命であった。
「お前の憂いを晴らしてやろう。お前の恐れる全てを退けてやろう。こちらへ逃げておいで。私が守ってあげるから。私はお前を害したりしない。お前の嫌がることをしたりはしない。お前を微睡んだままにしてあげる。よく頑張ったね。幸せにおなり。望む夢を見るんだ。お前はそれができるから」
少年は、僅かにもがいている。
意思とは裏腹に、生命がそうさせる。苦しいだろう、と蜘蛛糸を添えた。生にしがみつく手に絹糸のような輝きが幾重にも巻きつけば、少年は安心を求めるようにそれを握りしめた。
ヒトは、もとより無力ではない。
望めばその手で為すべきことができるだろう。
望めば集落を旅立つことも、温かい手を添えてやることも、
己の見たい夢を望んであばら家にとどまることもできるだろう。
私はそれを伝えてやりたいのだ。
お前は無力ではなく、私はそれを見守っている、と、伝えてやりたかったのだ。
そのためにこの身がある。
穢れた身でも、私自身より無価値なものはない。
蜘蛛糸は幾重にも少年の体に巻きついた。
望むようにできる手のひらと、望む場所に行ける、足がある。朽ち果ててすら、お前たちは為せることがある。
ああ、だから、大丈夫、
「安心して逝くといい」
死体になったって、私よりもできることはあるのだから、
見たい夢をのぞむ意思があるのだから、
望みと、その肉があれば、なんだってできるのだから、
安心して死ぬといい、と、少年に伝えるころ、少年の首の拍動は完全に停止した。
雲は晴れただろうか?
泣き喚いた少年は、安らかに眠っている。
目を瞑らせてやり、地面へと寝かせた。かつてはこの程度のこともできなかった。
端で見守っていた、大きな獣が歩み寄る。これは獣というより、妖の類なのか、彼の魂が綻びていたのを嗅ぎつけていたのだろう。
「死体にも為すべきことがあるのだね。いつの時代も、変わらない」
獣がそれを望むのならば、私は邪魔をするべきではない。死体の肉は神よりも価値があるのだから。
肉と骨を失ったころ、少年はどんな夢を見るだろう?
獣が立ち去る姿を眺め、私は彼を迎える支度をすることにした。
価値のない世界へ、ようこそ。
何にも手を伸ばせないけれど、何もお前に手を伸ばしたりはしない。
暫くはここで、ゆっくりと微睡んでいるといい。
大丈夫。
ふたたび肉を得るための穢れ方も教えてあげる。
お前は望みを得たのだから、私よりもよほど上手く夢を見られるだろう。



ENo.173 レオン とのやりとり

ENo.201 ユーリ とのやりとり

ENo.751 ??? とのやりとり

以下の相手に送信しました

















チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



枯れ落ちた八月(122) は 雑木 を入手!
藍浦英里緒(391) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 石英 を入手!
サイトウ(906) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 花びら を入手!
枯れ落ちた八月(122) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は ぬめぬめ を入手!
藍浦英里緒(391) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
藍浦英里緒(391) は 何か柔らかい物体 を入手!



無為 と別れました。
らうらさん(88) とカードを交換しました!
おいしいお水 (ヒールポーション)

イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
イバラ を研究しました!(深度1⇒2)
イバラ を研究しました!(深度2⇒3)



枯れ落ちた八月(122) に移動を委ねました。
特に移動せずその場に留まることにしました。
採集はできませんでした。
- 藍浦英里緒(391) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 藍浦英里緒(391) の選択は ヒノデ区 D-9:落書き広場(ベースキャンプ外のため無効)





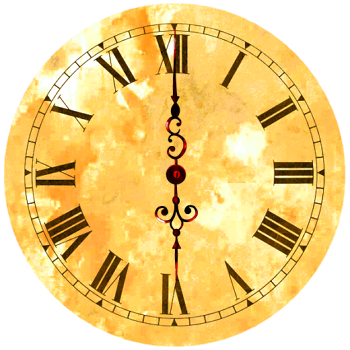
―― ハザマ時間が紡がれる。


ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
声は淡々と、話を続ける。
声はそこで終わる。
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK.



ぜい、ぜい、と。
苦しそうな呼吸を止めてやる方法すら、わたしにはわからなかった。
喉元を温める手でもあれば、私は何か報いてやれたろうに。
老婆が死にゆくのを、私は何をするわけでもなく、ただ見ていた。
最後の一人だった。
集落に残ったたった一人。随分前から足を悪くして、私の社の掃除にも来ることができなくなっていた。
あばら家に置いた木の板に向かって私への詫びを幾度も呟いていた。
寒くなりかけた秋口に、肺を病んで死んだ。
飢えていたので、彼女は暫く腐ることもなく、枯れ木のように布に包まれてそこにあった。
大きく開けた口に蜘蛛の巣が貼った。
やがて冬が訪れ、野犬が彼女を食い尽くした。
骨が残り、雪に潰されたあばら家が彼女の生きていた痕跡を綺麗に覆い、夏が幾つか過ぎた頃には、集落は森に飲み込まれていった。
彼女は親類に見捨てられ、集落に一人残り、近くの集落とも親交を断ち、孤独に死んだ。
彼女は集落に何を見ただろう?
親と見守った夕日だろうか、夫と毟った山菜だろうか、子を負ぶって帰った畦道だろうか。
蛙の鳴き声に眠る月夜か、外れの枯れ木が折れた嵐か、全てを奪った炎の揺らめきか。
私はそのどれも与えてやれなかった。死にゆく夢を謳うことすらしてやれなかった。
私はただ、それを見ていた。
ただ、信仰を受け取り、何をするでもなく、それを見届けた。
彼女と同じように社は朽ちていて、信仰を失った私は野犬にやる肉も持っていなかった。
彼女よりよほど早くに私の社は森の一部と化していて、森を分け入る道は蔦と落枝に塗れ、かつての私を知る者さえ社には辿り着けぬ有様と化していた。
死体にすら劣る神。
それが私だった。
なんて。
無価値な神。
追放を待つまでもなく、私は私に失望した。
『種を蒔く地を解する力』
タガシラ。
土、人の体、心。
それを種と認識すれば、向かう地を。
それを地と認識すれば、芽吹く種を。
理解できる。たったそれだけの力が成せることはとても少ない。
理解とは、それだけだ。理解をしたところで、為すべき腕がなければ、為すべき力がなければ、何をも為すことはできない。
私は私に失望した!
見守り、理解するだけの身の上に!
私は価値がない、あれらの、ヒトの一片にも満たぬ虚無でしかない!
私がヒトであったなら、
私がヒトであったなら、あの老婆を攫っていったろう。
手を取り、どこぞの街の隅で共に生きたろう。
彼女がそれを望まぬのなら、集落に住み続けても構わなかった。
私がヒトであったなら。
『堕神祠』
ダカンシ。
そうして私は肉を持った。
しあわせになりたい、と、ヒトは言う。
だから私は歓喜をもってそれを迎えよう。
価値のない私が、お前たちに寄り添おう。
お前の望みを叶えてやろう。
「お前はがんばってここまで来たのだね」
聞こえているかどうかわからないけれど、少年がそれを望んだので、私は少年に幸福を与えてやることにした。ぜい、ぜい、と苦しげな呼吸にそっと枯れた手を添えて、私は少年に夢を囁いてやることにした。
少年は不幸な生い立ちだった。旧い農村にも見られた、不幸な子供であったのだ。少年を守るべき大人たちに搾取され、抵抗するすべも持たず、与えられるべき糧を心にも体にも与えられず、しかし『なぜ苦しいのか』を教えられることもなく、ただ、苦痛に喘いでいる。かつて、彼らは湖や崖の下へ身を投げていったけれど、それは孤独な道行きであったことだろう。
彼には今、私がいる。
傷つけられた魂は元には戻るまい。
しかし、緩やかに、穏やかに、眠るように痺れさせ、休ませるすべを私は既に手に入れていた。
それは、ことばを放つ口であり、差し伸べることのできる腕であり、寄り添うことのできる命であった。
「お前の憂いを晴らしてやろう。お前の恐れる全てを退けてやろう。こちらへ逃げておいで。私が守ってあげるから。私はお前を害したりしない。お前の嫌がることをしたりはしない。お前を微睡んだままにしてあげる。よく頑張ったね。幸せにおなり。望む夢を見るんだ。お前はそれができるから」
少年は、僅かにもがいている。
意思とは裏腹に、生命がそうさせる。苦しいだろう、と蜘蛛糸を添えた。生にしがみつく手に絹糸のような輝きが幾重にも巻きつけば、少年は安心を求めるようにそれを握りしめた。
ヒトは、もとより無力ではない。
望めばその手で為すべきことができるだろう。
望めば集落を旅立つことも、温かい手を添えてやることも、
己の見たい夢を望んであばら家にとどまることもできるだろう。
私はそれを伝えてやりたいのだ。
お前は無力ではなく、私はそれを見守っている、と、伝えてやりたかったのだ。
そのためにこの身がある。
穢れた身でも、私自身より無価値なものはない。
蜘蛛糸は幾重にも少年の体に巻きついた。
望むようにできる手のひらと、望む場所に行ける、足がある。朽ち果ててすら、お前たちは為せることがある。
ああ、だから、大丈夫、
「安心して逝くといい」
死体になったって、私よりもできることはあるのだから、
見たい夢をのぞむ意思があるのだから、
望みと、その肉があれば、なんだってできるのだから、
安心して死ぬといい、と、少年に伝えるころ、少年の首の拍動は完全に停止した。
雲は晴れただろうか?
泣き喚いた少年は、安らかに眠っている。
目を瞑らせてやり、地面へと寝かせた。かつてはこの程度のこともできなかった。
端で見守っていた、大きな獣が歩み寄る。これは獣というより、妖の類なのか、彼の魂が綻びていたのを嗅ぎつけていたのだろう。
「死体にも為すべきことがあるのだね。いつの時代も、変わらない」
獣がそれを望むのならば、私は邪魔をするべきではない。死体の肉は神よりも価値があるのだから。
肉と骨を失ったころ、少年はどんな夢を見るだろう?
獣が立ち去る姿を眺め、私は彼を迎える支度をすることにした。
価値のない世界へ、ようこそ。
何にも手を伸ばせないけれど、何もお前に手を伸ばしたりはしない。
暫くはここで、ゆっくりと微睡んでいるといい。
大丈夫。
ふたたび肉を得るための穢れ方も教えてあげる。
お前は望みを得たのだから、私よりもよほど上手く夢を見られるだろう。



ENo.173 レオン とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.201 ユーリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.751 ??? とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
なにものかに呼ばれるようにして 漂っていた彼の 歩みが止まる。 |
 |
日向結城 「姉さん?」 |
 |
あなたたちの背後に いつの間にか やせこけた女が立っていた。 |
 |
日向環 「…結城。」 |
 |
そう 枯れ落ちた八月を呼ぶものは、彼によく似た貌をしていた。 |
 |
藍浦英里緒 「……チッ。嗚呼、何だ、此度は時間切れらしい。各自自由にしやがれ。」 |
 |
くもくいさま 「悪くはなかったよ。……去る者はいるのか?そう、私はお前を愛しているよ。」 |



秘密結社『欠けた蜜蝋』
|
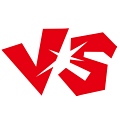 |
ハザマに生きるもの
|



ファッションファッションモンスター
|
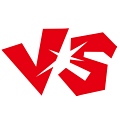 |
秘密結社『欠けた蜜蝋』
|



チナミ区 P-3:瓦礫の山
秘密結社『欠けた蜜蝋』
|
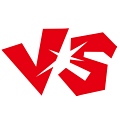 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 P-3:瓦礫の山
 |
マイケル 「な、なんだとー。ぐわー。」 |
チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



枯れ落ちた八月(122) は 雑木 を入手!
藍浦英里緒(391) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 石英 を入手!
サイトウ(906) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 花びら を入手!
枯れ落ちた八月(122) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は ぬめぬめ を入手!
藍浦英里緒(391) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
藍浦英里緒(391) は 何か柔らかい物体 を入手!



無為 と別れました。
らうらさん(88) とカードを交換しました!
おいしいお水 (ヒールポーション)

イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
イバラ を研究しました!(深度1⇒2)
イバラ を研究しました!(深度2⇒3)



枯れ落ちた八月(122) に移動を委ねました。
特に移動せずその場に留まることにしました。
採集はできませんでした。
- 藍浦英里緒(391) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 藍浦英里緒(391) の選択は ヒノデ区 D-9:落書き広場(ベースキャンプ外のため無効)





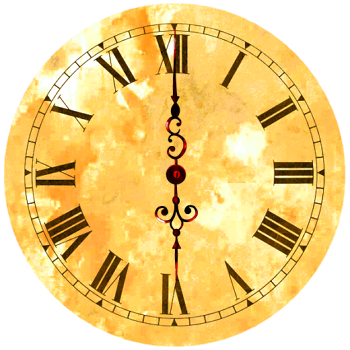
―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「……時計台に呼ばれてしまいましたが、はてさて。」 |
 |
エディアン 「なーんか、嫌な予感がします。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
 |
エディアン 「ほら……ほらぁ……。」 |
 |
榊 「どういうことでしょうねぇ。」 |
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝してます。」 |
 |
エディアン 「……ワールドスワップの能力者さんですよね。 機会を与えてくれて、感謝していますよ?」 |
 |
榊 「お姿は拝めないんですかねぇ。私は興味津々桃色片想いなのですが。」 |
声は淡々と、話を続ける。
 |
声 「どうやらこのワールドスワップ、時計の進みが狂っているようです。 特殊な因子を含めてしまった為と能力が訴えます。その因子が――」 |
 |
声 「――榊さん、貴方のようですね。何か、心当たりは?」 |
 |
榊 「大いにございます!特殊な世界の住人ゆえ、私は今や特異な存在なのでしょう。 妻に『貴方は変人』とよく言われていましたが、そういうことでしたか!納得ですッ」 |
 |
榊 「では、役目を果たすのは難しいということでよろしいですか?」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
榊 「……? ……どうしました?」 |
 |
声 「……仕切り直し、世界線を変更する、と能力が言ってきます。 貴方が案内役にならない世界線。イバラシティも、アンジニティも、新たなものになる……と。」 |
 |
エディアン 「……そ、そんなことまでできてしまう能力? ワールドスワップという名の範疇を超えてません?」 |
 |
榊 「世界線を別のものと交換する……と考えるなら、ギリギリ……ですかね。 というか、スワップから外れた現象は既に起こっていますが。」 |
 |
声 「これは能力ではなく、……呪い。呪いという言葉が合う。 今まで勝手に発動した数度、自分への利はない。制御下にない、把握できない、呪い。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「ハザマへの次の転送時間に、ハザマに転送される代わりに、世界線が変更される。 そして、案内役も、転送対象も、変わる。」 |
 |
声 「変わるものは、多いだろう。しかし変わらぬものも、あるだろう。」 |
 |
エディアン 「別の世界線、ですものね。 ……どうせなら私がアンジニティにいない世界線がいいんですけど。」 |
 |
榊 「……なるほど、奇妙な枝の正体は世界線操作者でしたかッ! 少なくとも私が案内役となれない世界線になるのですね、残念です。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「連絡は終わり。さようなら。」 |
声はそこで終わる。
 |
榊 「さて…… とても短い間ではありましたが、 エディアンさん、皆様、お付き合いありがとうございました!」 |
 |
エディアン 「お別れですか。悪人顔っぽくて敵視しやすい相手だったんですけどねー。」 |
 |
榊 「こんな素敵な笑顔を悪人顔呼ばわりとは、失礼な娘さんです。 なるほどアンジニティにいらっしゃるわけですねぇ。」 |
 |
エディアン 「……うるっさいですね。事情は人それぞれあるんですよ、色々!」 |
 |
榊 「……それでは、」 |
 |
エディアン 「……それでは、」 |
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
 |
榊 「お疲れ様でした。」 |
 |
エディアン 「お疲れ様でしたー!」 |

ENo.780
曇食 日



《曇食 日 (クモリクラウ デイ)》 → 《道枝陽樹》は 下部
己の存在を価値なきモノと苦しんでいたが
価値なきものだけの世界にならば安息が得られると気づき
『平等に価値なき世界をつくるため』
あらゆる女を抱き、無数に子供を作ることを目標としている
メンヘラヤリチン野郎
ハザマの世界では無数の蜘蛛で出来た雲を纏わせている
☆血縁について☆
「クモリクラウディの子供がいる、妊娠中である」というロールは、クモリクラウディ本人及びPLの知らないところで自由に使っていただいて構いません。PC、モブ、イバラのみならずハザマの敵にそういうのがいるとかでも全く構いませんのでご自由に取り扱い下さい。
ただしほかのPCさんへの確定ロールに使うのはだめですからね。メッ。
タ ガ シ ラ
『種を蒔く地を解する力』
土、人の体、心。
それを種と認識すれば、向かう地を。
それを地と認識すれば、芽吹く種を。
理解できる。たったそれだけの力が成せることはとても少ない。
ダカンシ
『堕神祠』
---|||||=|||9|669|||||----
《道枝陽樹(みちえようき)》
高校生。17歳。192cm。
ヨーキ、ヨースケ、あのピンクなどと呼ばれる。
ピンク色に染めた長髪、ひょろ長い体躯。
「僅かなダメージを無にできる」異能、『鏡面仕上げ』を持つ。
胡乱な校則のある胡乱な高校に通うが、詳細不明。なにせ胡乱な高校なので、常人には把握しにくいのである。
己の存在を価値なきモノと苦しんでいたが
価値なきものだけの世界にならば安息が得られると気づき
『平等に価値なき世界をつくるため』
あらゆる女を抱き、無数に子供を作ることを目標としている
メンヘラヤリチン野郎
ハザマの世界では無数の蜘蛛で出来た雲を纏わせている
☆血縁について☆
「クモリクラウディの子供がいる、妊娠中である」というロールは、クモリクラウディ本人及びPLの知らないところで自由に使っていただいて構いません。PC、モブ、イバラのみならずハザマの敵にそういうのがいるとかでも全く構いませんのでご自由に取り扱い下さい。
ただしほかのPCさんへの確定ロールに使うのはだめですからね。メッ。
タ ガ シ ラ
『種を蒔く地を解する力』
土、人の体、心。
それを種と認識すれば、向かう地を。
それを地と認識すれば、芽吹く種を。
理解できる。たったそれだけの力が成せることはとても少ない。
ダカンシ
『堕神祠』
---|||||=|||9|669|||||----
《道枝陽樹(みちえようき)》
高校生。17歳。192cm。
ヨーキ、ヨースケ、あのピンクなどと呼ばれる。
ピンク色に染めた長髪、ひょろ長い体躯。
「僅かなダメージを無にできる」異能、『鏡面仕上げ』を持つ。
胡乱な校則のある胡乱な高校に通うが、詳細不明。なにせ胡乱な高校なので、常人には把握しにくいのである。
9 / 30
482 PS
チナミ区
P-3
P-3




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 祈っているワイシャツ | 防具 | 33 | 防御10 | 体力10 | - | |
| 5 | 合一 | 装飾 | 20 | 幸運10 | 幸運10 | - | |
| 6 | 腐木 | 素材 | 15 | [武器]腐食15(LV25)[防具]反腐15(LV30)[装飾]舞腐15(LV30) | |||
| 7 | 平石 | 素材 | 15 | [武器]攻撃15(LV25)[防具]治癒10(LV10)[装飾]防御15(LV25) | |||
| 8 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) | |||
| 9 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]器用10(LV10)[防具]活力10(LV10)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | 地錆の錫杖 | 武器 | 25 | 攻撃10 | - | - | 【射程4】 |
| 11 | 石英 | 素材 | 15 | [武器]反射10(LV30)[防具]地纏10(LV30)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 12 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]加速10(LV15)[防具]幸運10(LV5)[装飾]水纏15(LV25) | |||
| 13 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 14 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) | |||
| 15 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 16 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 百薬 | 9 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 29 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| ヒールポーション | 6 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| プロテクション | 6 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| ヴァニッシュ | 5 | 0 | 80 | 敵:闇撃&治癒LV減+風撃&復活LV減 | |
| レックレスチャージ | 5 | 0 | 80 | 自:HP減+敵全:風痛撃 | |
| インシジョン | 5 | 0 | 60 | 敵:風痛撃+領域値[風]3以上なら、更に風痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増+護衛 | |
| デスパレイト | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃+自:瀕死なら連続増 | |
| ヴェノム | 5 | 0 | 50 | 敵:猛毒・麻痺・衰弱 | |
| タクシックゾーン | 7 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| ブラックアサルト | 7 | 0 | 90 | 敵:3連鎖闇撃&闇痛撃 | |
| パラライズ | 5 | 0 | 60 | 敵:麻痺 | |
| サンクタム | 5 | 0 | 60 | 味全:守護+祝福状態なら更に守護 | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| キュアディジーズ | 5 | 0 | 70 | 味肉2:HP増&肉体変調減 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 90 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
| コロージョン | 6 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
フェルテウス (ピンポイント) |
0 | 20 | 敵:痛撃 | |
|
死に至る病 (カースバインド) |
0 | 80 | 敵:闇撃&衰弱 | |
|
黒ノ影塊 (エナジードレイン) |
0 | 160 | 敵:闇撃&DF奪取 | |
|
煙幕 (プロテクション) |
0 | 60 | 味傷:守護 | |
|
ゆめまぼろし (ヴァニッシュ) |
0 | 80 | 敵:闇撃&治癒LV減+風撃&復活LV減 | |
|
おいしいお水 (ヒールポーション) |
0 | 60 | 味傷:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]デスパレイト | [ 3 ]タクシックゾーン | [ 1 ]ブラックアサルト |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]ファイアボール | [ 1 ]ストライキング |
| [ 1 ]サモン:ウルフ | [ 3 ]イバラ | [ 1 ]サモン:レッサーデーモン |
| [ 1 ]サモン:ガーゴイル |

PL / もつ