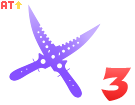<< 5:00




少年は、あてもなくハザマの世界を歩く。傍には少女と大きな猫。
何か言葉を発するのでもなく、静かに脚を動かしている
先程足を踏み入れた街で見たものは。
まるで何かに導かれるように、それを目にすることが運命で決められていたかのように。
イバラシティで語らった少女の変わり果てた姿と、壊れたヘアピンだった。
それだけで察せてしまう──理解してしまった。彼らはもうどこにも居ないのだと
頭痛が酷くなっていく。どうにも、無理に塞ぎ込んだ記憶の蓋が、赤いヘアピンを視認したのと同時に──溢れてくる
これは、そう。 侵略戦争が始まる、たった一日だけ前の話。
ぱちりと目を開くと、室内の明るさが朝を告げている。
今日も目が覚めてしまったなぁ、と日課のように瞬きをして
寝ぼけ眼を擦りながら薄汚れたカーテンを引っ張れば、さんさんと眩しいだけの光が僅かに照らしてくる
朝日に、不快だなぁ、と、呟くこともなく、誰も居ない家という空間をぼんやり見渡す
家と言うには嫌に静かで、でもその静寂が心地良い。良かった、誰も居なくて。
朝は嫌いだ。一日の始まりが、どうしても苦痛だ。
対して楽しい日々なんて、待っていないから
制服姿の、同い年くらいの奴らが視界に入るのが、すごく嫌だ。
どうしてあいつらと俺の間には、こうも差があるんだろう
そんなこと言っていたって、何も変わらないことは嫌なくらい分かっている癖に。
静かな空間に、ひとりぶんだけの生活音が暫く流れ続けて、
床に散らばる制服を踏みつけて、髪もそのままに家を出た。
家に居るのは、嫌いで、嫌いで、大嫌いだ。
人目を避けて、暗い路地裏に向かって、所謂悪い友達っていう奴を増やしていく
友達なんて言ったって、その時だけの方便なので、きっと本当にそう思っている人なんて居ないけれど。
無法地帯みたいになってるとこを歩くのが良い。こんな時間から子供が歩いてても、誰も気にしないような場所。
学校なんて、数えるくらいしか行ってない。やることも、やりたいことも、無いので。
煙草は、ここで教わった。
もしくは、無理にねじ込まれたんだったか、覚えていない
……好きで吸う訳無いじゃん、こんなものをさ。
はじめてそれを口にした時、頭がくらくらして、咳き込んで、ひどい気分だった
路地裏で吐きながら、ふわふわ揺れる煙を見つめたあの時、確かに自分の異能を自覚した。
今となっては見事に依存症。最初は白いパッケージ、それがだんだん物足りなくなって、黄色に手を伸ばした
そこで、誰でも良い。適当に人を捕まえて、とにかく家に帰らなくて済むように
何をされてもいい、どんな事をされてもいい。帰るよりは、酷いことをされないから。
うちは父親がひとり、男手一つで息子を育てる、有名らしい大きな会社の重役とかなんとか。
仕事に真面目で堅実、最近は転勤が多く、イバラシティに戻って来る日は少ない。
温和で優しく、出来た人だと言われているのを聞いたことがある
当の息子の俺と言えば、そんな風に思ったことは一度もなく。
家でのあいつは暴君そのものな訳で、殴る蹴るは日常茶飯事だ
出来る人間って言うのは当然頭も回る。ちょっと服を脱いだって簡単には認識できない場所をよく理解していた
逃げた母に似てるだとか、ただそこに居たからだとか。
理由はいつだってそういったもので、だから、生きてる自分が悪いんだな、と思って。
ひとつだけ褒められた事を覚えている。長い髪は、引っ張りやすくて良いらしい。
頭上に手が伸びれば、それが撫でる行為ではないことだけよく理解していた
──でも、そうだ。その日は確か、思いついたんだ。
ボヤ騒ぎのニュースをたまたま耳にして、嗚呼、帰りたくないなら、帰れなくしたら良いんだなって。
ライターなんて、腐るほど手に入った。燃やす物は、足りなければこの身を焚べれば良い
住み慣れた場所を火の海にするための手段は腐る程あって、それらを実行するのも容易かった。
さあ、早く、この世界から逃げ出そう。
一本の煙草を咥えながら、手始めに父の書斎に火を放った
あの日の本当の記憶を"思い出し"て。
唇は弧を描き、笑う、笑う、──ただ、笑う
その光景に、大事な幼馴染なんて登場しない。する筈もない。
そんな事は、分かっていたじゃないか
記憶改変ってのは、便利だ。
こんなつまらない人間だって、かんたんに笑顔にさせられるんだから
この戦争が始まる前の自分は──あんな笑顔をしたこともない!
笑う。笑う。
紐解いてしまった"記憶"は、まるで水流のようにどんどん流れ込んできて、
それは全ての反逆。 幸福の、幸せへの否定。
どんなに叫んだところで、吐き気のするような現実はなにひとつ変わらなくて、
感情が、思いが、苦しみが、胸の奥から込み上げてくる。
馬鹿みたいじゃないか!
イバラシティであんなにただ笑って、人を信じて、悩んで、庇って。笑って。
そんな無意味なことに全力になって、それが楽しくて!
現実に帰りたくない。戻りたくない!
どうして何もないまま、放っておいてくれなかった!手の届かない幻の幸せなんて与えやがった!
知ってしまった、得てしまった!"幸せ"を!
それに手を伸ばす方法を、知ってしまった!
伸ばしたいと願うことを、希望を抱いてしまった!
叫ぶ。叫ぶ。
その叫びは誰かの耳に届くのだろうか。誰かの心に、届くのだろうか?
どうあっても、きっと、届いて欲しい人の元には伝わらない
そういう巡り合わせなのだろう。望むことは、落胆する事だと、よく知っていたじゃないか
淡く淡く願う事すら意味が無かったから、とっくの昔に辞めたじゃないか!
いつの間にか頬は濡れていて。
それが自分の瞳から流れたことに気が付いたのは、暫くして傍らの少女に拭われてからだった
知らなければ良かった。こんな思いをするなら、幸せなんて知りたくなかった
繋がれた手の暖かさを、頭を撫でられる事の嬉しさを。
思いが通じ合うことの悦びを、愛し愛される幸せを。
故に、望んでしまう。叶わないと知りながら!
幸せになりたい、と、無意識下で小さく小さく呟けば、少女はただ頷いた。
これからどうするつもりなのか、どうしたいのか。まるで全部分かっているみたいに。
微笑んで、答えるのだ。
この少女は、どうして自分の側に居るのだろう。
何故涙を拭ってくれるのだろう、支えてくれるのだろう。
その答えをぼんやり掴みかけて、いや、彼女が言わないのなら、態々聞く必要もないのだろう。
ありがとうと一言だけ伝え、腕を伸ばして大きな猫の喉をひと撫でして、ごろりと鳴らされる声に少しだけ自己満足。
虚ろな目で、それでも確かに奥底には希望が灯っていて。
一歩、また一歩と歩き出して、
誰に言うでもなく、何かに祈る。
幸せは、あそこには存在しないから。違うところへ、行かないといけないから
途端に足元に纏わりつく手首は首へと伸びてきて、ぎゅっと呼吸を妨げた。
声にならない声を吐く。
この手首が何者なのか、どうして今自分の首を締め上げるのか
ちかちかと点滅していく景色を前に、それらは、どうでもよかった。
心の何処かで、理解していたから。
脳への血液を奪っていくそれは想像以上に苦しくて、それでも抵抗する気は起きなくて。
ただ、あの温もりが、正義をうたう笑顔が、暗い路地裏を照らすような光が脳裏に浮かべば、ゆるりと身体が踠いて、
それを思考ごと──何かに絡め取られて。
きっと、本気で抵抗すればこの手は簡単に引き剥がせるのだろうけれど。
逃れてどうする?侵略戦争が終われば、また何もない生活に戻るのだろうか
彼の居ない生活に、戻るのだろうか。
それは、嫌だなぁ、と、逃れるために伸ばしかけた手を、止める。
『 。』
『 、 。』
脳裏に浮かぶ言葉の音、香り。
どう足掻いても、彼と自分の世界は交わらない
それならば。いっそここで、足を止めて、それこそを幸せと形容するのは、どうだろうか。
あの世界で生きるよりは、きっと幸せな筈だ。
呼吸を奪うこの手は、確かに暖かくて。
伝わってくる、優しい思い。
そういえば、誰かが、この侵略戦争をチャンスだと形容していた
──彼の隣で、笑えるかな。
そのまま、すっと暗くなっていく視界と共に、意識は段々と薄れていった。
少女は見届けていた。少年のさいごを。
四肢を黒い蜘蛛糸に絡め取られ、四肢から力が抜けていき、呼吸が止まるまでの間
少しだけ離れた場所から、同じように祈っていた。
彼が幸せになれるように、と
屈んで、地面に落ちた槍を拾い上げる。先程まで少年の所持品だったものだ
悲しい、という気持ちは出てこなかった。
彼は最期、笑顔だった。辛く苦しい世界から逃れられて、良かったなぁと私も仄かに笑う
こういうとき、自分はアンジニティで産まれたんだと実感してしまう。
自身の無力さは痛感しているつもりだ。
付け焼き刃で侵略が叶うものではないと、分かっている
それでも、足を止める理由にはならなかった。
少年に──少年だったものに背を向けて、ハザマを歩く。
大きな猫と少女は道を違えたが、それを気に留める余裕は今の少女には無かった



ENo.45 セン とのやりとり

ENo.114 街喰らい とのやりとり

ENo.780 くもくいさま とのやりとり

ENo.914 例の双子 とのやりとり

ENo.1656 大化け猫 とのやりとり

以下の相手に送信しました




例の双子(914) から 吸い殻 を手渡しされました。
ItemNo.7 わかめおにぎり を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(12⇒13)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!











チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



セン(45) は 雑木 を入手!
ユーリ(201) は 雑木 を入手!
暗黒の鎧(454) は 雑木 を入手!
例の双子(914) は 雑木 を入手!
暗黒の鎧(454) は 羽 を入手!
セン(45) は ボロ布 を入手!
暗黒の鎧(454) は 腐肉 を入手!
暗黒の鎧(454) は 毛 を入手!
セン(45) は 何か柔らかい物体 を入手!
ユーリ(201) は 何か柔らかい物体 を入手!
例の双子(914) は 何か柔らかい物体 を入手!



制約LV を 3 UP!(LV2⇒5、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV32⇒35、-3CP)
魔緒(231) とカードを交換しました!
スキルカード:ヘイスト (ヘイスト)

イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
イバラ を研究しました!(深度1⇒2)
イバラ を研究しました!(深度2⇒3)
リストリクト を習得!
オフェンシブ を習得!
アイシング を習得!
クリエイト:チェーン を習得!
サンクタム を習得!



特に移動せずその場に留まることにしました。





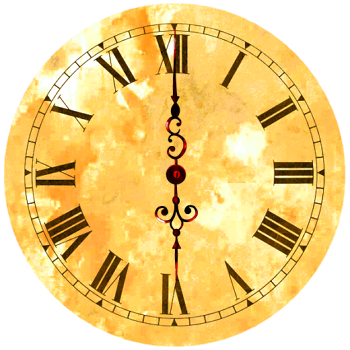
―― ハザマ時間が紡がれる。


ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
声は淡々と、話を続ける。
声はそこで終わる。
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



少年は、あてもなくハザマの世界を歩く。傍には少女と大きな猫。
何か言葉を発するのでもなく、静かに脚を動かしている
先程足を踏み入れた街で見たものは。
まるで何かに導かれるように、それを目にすることが運命で決められていたかのように。
イバラシティで語らった少女の変わり果てた姿と、壊れたヘアピンだった。
それだけで察せてしまう──理解してしまった。彼らはもうどこにも居ないのだと
頭痛が酷くなっていく。どうにも、無理に塞ぎ込んだ記憶の蓋が、赤いヘアピンを視認したのと同時に──溢れてくる
これは、そう。 侵略戦争が始まる、たった一日だけ前の話。
ぱちりと目を開くと、室内の明るさが朝を告げている。
今日も目が覚めてしまったなぁ、と日課のように瞬きをして
寝ぼけ眼を擦りながら薄汚れたカーテンを引っ張れば、さんさんと眩しいだけの光が僅かに照らしてくる
朝日に、不快だなぁ、と、呟くこともなく、誰も居ない家という空間をぼんやり見渡す
家と言うには嫌に静かで、でもその静寂が心地良い。良かった、誰も居なくて。
朝は嫌いだ。一日の始まりが、どうしても苦痛だ。
対して楽しい日々なんて、待っていないから
制服姿の、同い年くらいの奴らが視界に入るのが、すごく嫌だ。
どうしてあいつらと俺の間には、こうも差があるんだろう
そんなこと言っていたって、何も変わらないことは嫌なくらい分かっている癖に。
静かな空間に、ひとりぶんだけの生活音が暫く流れ続けて、
床に散らばる制服を踏みつけて、髪もそのままに家を出た。
家に居るのは、嫌いで、嫌いで、大嫌いだ。
人目を避けて、暗い路地裏に向かって、所謂悪い友達っていう奴を増やしていく
友達なんて言ったって、その時だけの方便なので、きっと本当にそう思っている人なんて居ないけれど。
無法地帯みたいになってるとこを歩くのが良い。こんな時間から子供が歩いてても、誰も気にしないような場所。
学校なんて、数えるくらいしか行ってない。やることも、やりたいことも、無いので。
煙草は、ここで教わった。
もしくは、無理にねじ込まれたんだったか、覚えていない
……好きで吸う訳無いじゃん、こんなものをさ。
はじめてそれを口にした時、頭がくらくらして、咳き込んで、ひどい気分だった
路地裏で吐きながら、ふわふわ揺れる煙を見つめたあの時、確かに自分の異能を自覚した。
今となっては見事に依存症。最初は白いパッケージ、それがだんだん物足りなくなって、黄色に手を伸ばした
そこで、誰でも良い。適当に人を捕まえて、とにかく家に帰らなくて済むように
何をされてもいい、どんな事をされてもいい。帰るよりは、酷いことをされないから。
うちは父親がひとり、男手一つで息子を育てる、有名らしい大きな会社の重役とかなんとか。
仕事に真面目で堅実、最近は転勤が多く、イバラシティに戻って来る日は少ない。
温和で優しく、出来た人だと言われているのを聞いたことがある
当の息子の俺と言えば、そんな風に思ったことは一度もなく。
家でのあいつは暴君そのものな訳で、殴る蹴るは日常茶飯事だ
出来る人間って言うのは当然頭も回る。ちょっと服を脱いだって簡単には認識できない場所をよく理解していた
逃げた母に似てるだとか、ただそこに居たからだとか。
理由はいつだってそういったもので、だから、生きてる自分が悪いんだな、と思って。
ひとつだけ褒められた事を覚えている。長い髪は、引っ張りやすくて良いらしい。
頭上に手が伸びれば、それが撫でる行為ではないことだけよく理解していた
──でも、そうだ。その日は確か、思いついたんだ。
ボヤ騒ぎのニュースをたまたま耳にして、嗚呼、帰りたくないなら、帰れなくしたら良いんだなって。
ライターなんて、腐るほど手に入った。燃やす物は、足りなければこの身を焚べれば良い
住み慣れた場所を火の海にするための手段は腐る程あって、それらを実行するのも容易かった。
さあ、早く、この世界から逃げ出そう。
一本の煙草を咥えながら、手始めに父の書斎に火を放った
 |
智鈎 「………ぁ、」 |
あの日の本当の記憶を"思い出し"て。
唇は弧を描き、笑う、笑う、──ただ、笑う
その光景に、大事な幼馴染なんて登場しない。する筈もない。
そんな事は、分かっていたじゃないか
 |
智鈎 「そりゃ、思い出したくもないわ。こんなの」 |
記憶改変ってのは、便利だ。
こんなつまらない人間だって、かんたんに笑顔にさせられるんだから
この戦争が始まる前の自分は──あんな笑顔をしたこともない!
 |
智鈎 「あー、あー!あーっはっはっは!ははは!はは、」 |
笑う。笑う。
紐解いてしまった"記憶"は、まるで水流のようにどんどん流れ込んできて、
 |
智鈎 「ああ、ああ!はは、はははは!やめてくれよ、やめろよぉ!」 |
それは全ての反逆。 幸福の、幸せへの否定。
どんなに叫んだところで、吐き気のするような現実はなにひとつ変わらなくて、
感情が、思いが、苦しみが、胸の奥から込み上げてくる。
馬鹿みたいじゃないか!
イバラシティであんなにただ笑って、人を信じて、悩んで、庇って。笑って。
そんな無意味なことに全力になって、それが楽しくて!
 |
智鈎 「ああ、あああ!嫌だ!嫌だ嫌だ!戻りたくない!戻りたくない!」 |
現実に帰りたくない。戻りたくない!
どうして何もないまま、放っておいてくれなかった!手の届かない幻の幸せなんて与えやがった!
知ってしまった、得てしまった!"幸せ"を!
それに手を伸ばす方法を、知ってしまった!
伸ばしたいと願うことを、希望を抱いてしまった!
 |
智鈎 「嫌だ!嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ!嫌だ!たすけて、助けてよ!逃してよ!」 |
叫ぶ。叫ぶ。
その叫びは誰かの耳に届くのだろうか。誰かの心に、届くのだろうか?
どうあっても、きっと、届いて欲しい人の元には伝わらない
そういう巡り合わせなのだろう。望むことは、落胆する事だと、よく知っていたじゃないか
淡く淡く願う事すら意味が無かったから、とっくの昔に辞めたじゃないか!
いつの間にか頬は濡れていて。
それが自分の瞳から流れたことに気が付いたのは、暫くして傍らの少女に拭われてからだった
 |
夢璃 「………」 |
知らなければ良かった。こんな思いをするなら、幸せなんて知りたくなかった
繋がれた手の暖かさを、頭を撫でられる事の嬉しさを。
思いが通じ合うことの悦びを、愛し愛される幸せを。
故に、望んでしまう。叶わないと知りながら!
幸せになりたい、と、無意識下で小さく小さく呟けば、少女はただ頷いた。
これからどうするつもりなのか、どうしたいのか。まるで全部分かっているみたいに。
微笑んで、答えるのだ。
 |
夢璃 「なろう。幸せに。」 |
この少女は、どうして自分の側に居るのだろう。
何故涙を拭ってくれるのだろう、支えてくれるのだろう。
その答えをぼんやり掴みかけて、いや、彼女が言わないのなら、態々聞く必要もないのだろう。
ありがとうと一言だけ伝え、腕を伸ばして大きな猫の喉をひと撫でして、ごろりと鳴らされる声に少しだけ自己満足。
虚ろな目で、それでも確かに奥底には希望が灯っていて。
一歩、また一歩と歩き出して、
 |
智鈎 「ね、──── 、 、 。」 |
誰に言うでもなく、何かに祈る。
幸せは、あそこには存在しないから。違うところへ、行かないといけないから
途端に足元に纏わりつく手首は首へと伸びてきて、ぎゅっと呼吸を妨げた。
 |
智鈎 「、 」 |
声にならない声を吐く。
この手首が何者なのか、どうして今自分の首を締め上げるのか
ちかちかと点滅していく景色を前に、それらは、どうでもよかった。
心の何処かで、理解していたから。
脳への血液を奪っていくそれは想像以上に苦しくて、それでも抵抗する気は起きなくて。
ただ、あの温もりが、正義をうたう笑顔が、暗い路地裏を照らすような光が脳裏に浮かべば、ゆるりと身体が踠いて、
それを思考ごと──何かに絡め取られて。
きっと、本気で抵抗すればこの手は簡単に引き剥がせるのだろうけれど。
逃れてどうする?侵略戦争が終われば、また何もない生活に戻るのだろうか
彼の居ない生活に、戻るのだろうか。
それは、嫌だなぁ、と、逃れるために伸ばしかけた手を、止める。
『 。』
『 、 。』
 |
智鈎 「(……セン。)」 |
脳裏に浮かぶ言葉の音、香り。
どう足掻いても、彼と自分の世界は交わらない
それならば。いっそここで、足を止めて、それこそを幸せと形容するのは、どうだろうか。
あの世界で生きるよりは、きっと幸せな筈だ。
 |
智■ 「(もう、疲れた。疲れたよ、 いいだろう?)」 |
呼吸を奪うこの手は、確かに暖かくて。
伝わってくる、優しい思い。
そういえば、誰かが、この侵略戦争をチャンスだと形容していた
 |
■■ 「(ああ、それなら、良いな。 また、)」 |
──彼の隣で、笑えるかな。
そのまま、すっと暗くなっていく視界と共に、意識は段々と薄れていった。
 |
夢璃 「あ、」 |
少女は見届けていた。少年のさいごを。
四肢を黒い蜘蛛糸に絡め取られ、四肢から力が抜けていき、呼吸が止まるまでの間
少しだけ離れた場所から、同じように祈っていた。
彼が幸せになれるように、と
屈んで、地面に落ちた槍を拾い上げる。先程まで少年の所持品だったものだ
悲しい、という気持ちは出てこなかった。
彼は最期、笑顔だった。辛く苦しい世界から逃れられて、良かったなぁと私も仄かに笑う
こういうとき、自分はアンジニティで産まれたんだと実感してしまう。
 |
夢璃 「……私、侵略、出来るかな」 |
自身の無力さは痛感しているつもりだ。
付け焼き刃で侵略が叶うものではないと、分かっている
それでも、足を止める理由にはならなかった。
少年に──少年だったものに背を向けて、ハザマを歩く。
大きな猫と少女は道を違えたが、それを気に留める余裕は今の少女には無かった



ENo.45 セン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.114 街喰らい とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||
ENo.780 くもくいさま とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.914 例の双子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.1656 大化け猫 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
セン 「これでやっと皆と話せるなー。うん。これが本当の自分って感じ。」 |
 |
セン 「今回も皆で頑張ってこーぜ!」 |
 |
リスカード 「え!?静かにされても困るですって!? では愉快になる話をいたしましょう! これは前々回の探索で拾ったアイテム「吸い殻」なんですが」 |
 |
ダートモール 「チカギがポイ捨てしたゴミな」 |
 |
リスカード 「あっオチを言わないでください」 |
例の双子(914) から 吸い殻 を手渡しされました。
 |
リスカード 「あ、そうだ。これを差し上げます。」 |
ItemNo.7 わかめおにぎり を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(12⇒13)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





TeamNo.45
|
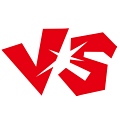 |
姫を守り隊
|





チナミ区 P-3:瓦礫の山
 |
マイケル 「な、なんだとー。ぐわー。」 |
チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



セン(45) は 雑木 を入手!
ユーリ(201) は 雑木 を入手!
暗黒の鎧(454) は 雑木 を入手!
例の双子(914) は 雑木 を入手!
暗黒の鎧(454) は 羽 を入手!
セン(45) は ボロ布 を入手!
暗黒の鎧(454) は 腐肉 を入手!
暗黒の鎧(454) は 毛 を入手!
セン(45) は 何か柔らかい物体 を入手!
ユーリ(201) は 何か柔らかい物体 を入手!
例の双子(914) は 何か柔らかい物体 を入手!



制約LV を 3 UP!(LV2⇒5、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV32⇒35、-3CP)
魔緒(231) とカードを交換しました!
スキルカード:ヘイスト (ヘイスト)

イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
イバラ を研究しました!(深度1⇒2)
イバラ を研究しました!(深度2⇒3)
リストリクト を習得!
オフェンシブ を習得!
アイシング を習得!
クリエイト:チェーン を習得!
サンクタム を習得!



特に移動せずその場に留まることにしました。





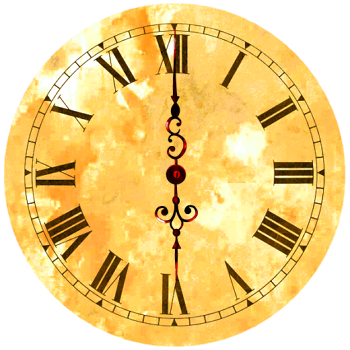
―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「……時計台に呼ばれてしまいましたが、はてさて。」 |
 |
エディアン 「なーんか、嫌な予感がします。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
 |
エディアン 「ほら……ほらぁ……。」 |
 |
榊 「どういうことでしょうねぇ。」 |
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝してます。」 |
 |
エディアン 「……ワールドスワップの能力者さんですよね。 機会を与えてくれて、感謝していますよ?」 |
 |
榊 「お姿は拝めないんですかねぇ。私は興味津々桃色片想いなのですが。」 |
声は淡々と、話を続ける。
 |
声 「どうやらこのワールドスワップ、時計の進みが狂っているようです。 特殊な因子を含めてしまった為と能力が訴えます。その因子が――」 |
 |
声 「――榊さん、貴方のようですね。何か、心当たりは?」 |
 |
榊 「大いにございます!特殊な世界の住人ゆえ、私は今や特異な存在なのでしょう。 妻に『貴方は変人』とよく言われていましたが、そういうことでしたか!納得ですッ」 |
 |
榊 「では、役目を果たすのは難しいということでよろしいですか?」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
榊 「……? ……どうしました?」 |
 |
声 「……仕切り直し、世界線を変更する、と能力が言ってきます。 貴方が案内役にならない世界線。イバラシティも、アンジニティも、新たなものになる……と。」 |
 |
エディアン 「……そ、そんなことまでできてしまう能力? ワールドスワップという名の範疇を超えてません?」 |
 |
榊 「世界線を別のものと交換する……と考えるなら、ギリギリ……ですかね。 というか、スワップから外れた現象は既に起こっていますが。」 |
 |
声 「これは能力ではなく、……呪い。呪いという言葉が合う。 今まで勝手に発動した数度、自分への利はない。制御下にない、把握できない、呪い。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「ハザマへの次の転送時間に、ハザマに転送される代わりに、世界線が変更される。 そして、案内役も、転送対象も、変わる。」 |
 |
声 「変わるものは、多いだろう。しかし変わらぬものも、あるだろう。」 |
 |
エディアン 「別の世界線、ですものね。 ……どうせなら私がアンジニティにいない世界線がいいんですけど。」 |
 |
榊 「……なるほど、奇妙な枝の正体は世界線操作者でしたかッ! 少なくとも私が案内役となれない世界線になるのですね、残念です。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「連絡は終わり。さようなら。」 |
声はそこで終わる。
 |
榊 「さて…… とても短い間ではありましたが、 エディアンさん、皆様、お付き合いありがとうございました!」 |
 |
エディアン 「お別れですか。悪人顔っぽくて敵視しやすい相手だったんですけどねー。」 |
 |
榊 「こんな素敵な笑顔を悪人顔呼ばわりとは、失礼な娘さんです。 なるほどアンジニティにいらっしゃるわけですねぇ。」 |
 |
エディアン 「……うるっさいですね。事情は人それぞれあるんですよ、色々!」 |
 |
榊 「……それでは、」 |
 |
エディアン 「……それでは、」 |
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
 |
榊 「お疲れ様でした。」 |
 |
エディアン 「お疲れ様でしたー!」 |

ENo.201
社 夢璃



▽社 夢璃(ヤシロ ユーリ)。相良伊橋高校1-4
16歳の可愛らしい少女
着痩せするタイプ。最近まで海外で暮らしていたらしい、ちょっぴり頑固でクールな女の子
他者の異能を強化できる異能。振れ幅は不安定なようだ
------------------
・既知設定やらなんでも、楽しい事ならだいたいオッケーです。
・PLが置きレス気味です。そんな日もあります
・構って貰えると喜びます。ロール歓迎
・一部アイコンは【ENo1656:646】様から使用許可を頂きました
@Orgs_u
16歳の可愛らしい少女
着痩せするタイプ。最近まで海外で暮らしていたらしい、ちょっぴり頑固でクールな女の子
他者の異能を強化できる異能。振れ幅は不安定なようだ
------------------
・既知設定やらなんでも、楽しい事ならだいたいオッケーです。
・PLが置きレス気味です。そんな日もあります
・構って貰えると喜びます。ロール歓迎
・一部アイコンは【ENo1656:646】様から使用許可を頂きました
@Orgs_u
13 / 30
414 PS
チナミ区
P-3
P-3





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | どうでもよさげな物体 | 素材 | 10 | [武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2) | |||
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 5 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 6 | 絡みつく手首 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 7 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 8 | スタッブ | 武器 | 42 | 麻痺10 | - | - | 【射程2】 |
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 10 | シュピラーレ | 武器 | 58 | 混乱10 | 束縛10 | - | 【射程2】 |
| 11 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 12 | 何かの骨 | 素材 | 20 | [武器]舞衰10(LV15)[防具]活力15(LV30)[装飾]鎮痛10(LV15) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 35 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 7 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| クリエイト:タライ | 8 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| アイスバインド | 6 | 0 | 80 | 敵:水撃&凍結 | |
| オフェンシブ | 5 | 0 | 80 | 自:AT増+AG減 | |
| クリエイト:ウェポン | 6 | 0 | 60 | 味:追撃LV・次与ダメ増 | |
| スパイン | 6 | 0 | 110 | 自:反撃LV増 | |
| アイシング | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増&強制凍結 | |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 70 | 敵:水撃&連続減 | |
| フリーズ | 6 | 0 | 130 | 敵全:凍結 | |
| クリエイト:チェーン | 5 | 0 | 60 | 敵3:攻撃&束縛+自:AG減(1T) | |
| サンクタム | 5 | 0 | 60 | 味全:守護+祝福状態なら更に守護 | |
| クリエイト:バリケード | 5 | 0 | 40 | 味傷:次受ダメ減+守護 | |
| イレイザー | 6 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
| サモン:ウルフ | 5 | 0 | 300 | 自:ウルフ召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
安寧の一息 (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
吐き戻せ、人生を (ピンポイント) |
0 | 20 | 敵:痛撃 | |
|
桜の下の少年 (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
冥境止水 (テリトリー) |
0 | 160 | 味列:DX増 | |
|
トキワ工房機動兵派遣申請書 (サモン:ゴーレム) |
0 | 400 | 自:ゴーレム召喚 | |
|
スキルカード:ヘイスト (ヘイスト) |
0 | 40 | 自:AG増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]エキサイト | [ 1 ]ストレングス | [ 2 ]ヒールポーション |
| [ 1 ]ライトジャベリン | [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]コロージョン |
| [ 3 ]サモン:ウルフ | [ 3 ]イバラ | [ 1 ]ヒールミスト |

PL / くさったおさとう