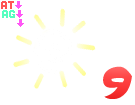<< 5:00





「姉さん、大丈夫?」
「怪我してない? 姉さんは俺が守るからね」
「俺が姉さんの味方だよ」
かたわらの『弟』は私につぶやく。
やさしい言葉をかけて。
望むときに、わたしの傍にいて。
そっと、手をつないでいてくれる……
***
「ひどい。許せない、姉さんにそんなことをするなんて」
「ほら、あげる。姉さんは これが好きだったでしょ?」
「俺は姉さんのこと、世界で一番好きだよ」
出来の悪い私を、仕事を辞めてまで甲斐甲斐しく世話してくれる母。
私のために遅くまで働いて、治療代を稼いでくれる父。
私のなにもかもを 肯定的に受け止めて、そばにいてくれる弟。
まるで絵に描いたような 私に都合の良いひとびと。
何のために私に尽くしてくれるのかわからない。だって私はあなたたちに支払える対価がない。
今までも、これからも。
人形あそびでもするように 全てを おもいのまま動かせるのだと 私はいつからか 気付いてしまった。
わかってしまってから 『やってしまう』まで、わらってしまうくらい あまりにも簡単で。
階段を転げ落ちるように すべてが悪くなっていった。
完璧が、都合の良いままに、 私の手のひらの上で 崩れていく。
私が賢く、優しいひとであれば すべてをより良い方向にしようと努力することもできたかもしれない。
でも 私がいつでも求めていることは、すべてその逆だ。
崩れ落ちた破片。破壊によってもたらされる痛みだけが、生まれてからこれまで 不安しかなかった私の路に
ひかりを与えてくれた気がした。
それは 他人から見れば 妄想に過ぎなかったのだろう。
でも私にとって その考えは だんだんと真実になっていった。
きっと私に与えられた場所はすべて、私が私のために作り出したものなのだ。
父と母と、それから弟を 自分の都合の良いように操って、作り出した私のための世界。
だって、こんなにも思いのままに操ることができる。
こんなにも正しくない私の言葉を信じ、それでも、
これが異常でないのなら なんだと言うのだろう。
彼らがほんとうに 人の心を持っているのであれば、
私という『悪』を 愛することなど しないはずだ。
もしも 本当に 見返りを求めることのない…
無償の愛というものがそこに存在しているのならば、
私は耐えられない。理解できない。
無償の愛の不在の証明、
私が私の為に作り出した おままごとのような愛が
此処にあるのだということを確かめるために
すべてを砕いて壊してしまうこと。

ただ鼻にとどく臭気が、 私が私のために作り出した 小規模な楽園の終わりの、 そのはじまりを告げていた。
窓からカーテンを通して、 差し込む月光。
私のベッドの脇に 立ち尽くす彼の 頬と 手が 赤くぬらついて 光っている。
それを見て、私は思った。
――どんな順番で刺したのだろう。母が先かな。それとも父だろうか。
いま、生きているのだろうか。それとももう死んだだろうか。どこで倒れているのだろうか。リビングか、寝室か。
私はそのとき彼に何を言っただろう。 歓喜にうちふるえ なにも言葉にできなかったのかもしれない。
そう彼は言った。
私が苦しんでいることに彼はこだわっていた。
何度も聞いた言葉だった。
最初のころは くだらない妄想に囚われているのだなと 冷めた気持ちでそれを聞いていたけれど、
いまはじめて 私は苦しんでいたのかもしれないと そう思えた。
ただ、私の苦しみはまだ終わっていない。彼だけがまだ残っている。
私は……
純粋に私が被害者だと信じ続けた弟を、いま、一番、最高のタイミングで裏切ることで
彼を後戻りできないくらいに傷つけて 壊すことができると分かっていた。
だから、すべて。
私という人間のすべてを、いままで起こったことすべてが 私が引き起こしたことなのだということを、
父でも 母でもない。もちろん弟でもない。
『私が悪いのだ』ということを、
やさしく
わかりやすく
教えてあげることにしたのだった。
そして、彼は。
目が覚める。
瓦礫と赤と黒だけが彩る世界がそこに広がっていた。
現実感がないというのに、肌寒い。見慣れない、薄い服を着させられている。
ゆめだろうか。いや、ゆめじゃない。私は、あの榊という男のアナウンスも、ここで起きる動乱も、すべてすべて……
《判って》いる。
私はイバラシティの住民として、アンジニティの侵略に対抗する頭数に 数えられていたのだ。
あの八月三十一日から、まどろみのような時を過ごしてきた。
自分が起きているかも 眠っているのかもわからない 曖昧な時間。
その日々の中で 私が望む事はひとつだけ。
今、どうして目が覚めたのかわからない……醒めれば忘れる 与えられた ひとときのチャンスなのであれば。
私は確かめなければならない。探し出して、会いに行かねばならない。
彼もおなじ《此処》に居ることを、肌で感じる。理屈では説明できない、透明な血の繋がりがそこにある。
私は立ち上がることができた。
どうしてか 干からびた足でも、歩くことは苦にならなかった。



ENo.664 闇のおえかき とのやりとり

















チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



枯れ落ちた八月(122) は 雑木 を入手!
藍浦英里緒(391) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 石英 を入手!
サイトウ(906) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 花びら を入手!
枯れ落ちた八月(122) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は ぬめぬめ を入手!
藍浦英里緒(391) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
藍浦英里緒(391) は 何か柔らかい物体 を入手!



特に何もしませんでした。



特に移動せずその場に留まることにしました。
採集はできませんでした。
- 藍浦英里緒(391) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 藍浦英里緒(391) の選択は ヒノデ区 D-9:落書き広場(ベースキャンプ外のため無効)





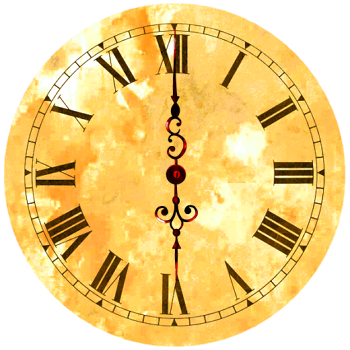
―― ハザマ時間が紡がれる。


ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
声は淡々と、話を続ける。
声はそこで終わる。
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK.




「姉さん、大丈夫?」
「怪我してない? 姉さんは俺が守るからね」
「俺が姉さんの味方だよ」
かたわらの『弟』は私につぶやく。
やさしい言葉をかけて。
望むときに、わたしの傍にいて。
そっと、手をつないでいてくれる……
***
「ひどい。許せない、姉さんにそんなことをするなんて」
「ほら、あげる。姉さんは これが好きだったでしょ?」
「俺は姉さんのこと、世界で一番好きだよ」
出来の悪い私を、仕事を辞めてまで甲斐甲斐しく世話してくれる母。
私のために遅くまで働いて、治療代を稼いでくれる父。
私のなにもかもを 肯定的に受け止めて、そばにいてくれる弟。
『出来過ぎて』いた。
まるで絵に描いたような 私に都合の良いひとびと。
何のために私に尽くしてくれるのかわからない。だって私はあなたたちに支払える対価がない。
今までも、これからも。
共にいられるだけで十分幸せ?そんな手垢のついた言葉は、まったく信じられない。
《半径10メートル以内に自分の領域を展開し、ある程度の生命とエネルギーを操ることのできる異能》
父と母は優しい人だった。だからこそ、おもしろかった。
私がふたりを壊したのだという事実と、その過程とが。
《半径10メートル以内に自分の領域を展開し、ある程度の生命とエネルギーを操ることのできる異能》
父と母は優しい人だった。だからこそ、おもしろかった。
私がふたりを壊したのだという事実と、その過程とが。
人形あそびでもするように 全てを おもいのまま動かせるのだと 私はいつからか 気付いてしまった。
わかってしまってから 『やってしまう』まで、わらってしまうくらい あまりにも簡単で。
階段を転げ落ちるように すべてが悪くなっていった。
完璧が、都合の良いままに、 私の手のひらの上で 崩れていく。
例えば、父さんの手を両手でそっと包んで 潤んだひとみで 見上げてみたり
成長していくからだの 不安をうちあけてみたり
…父さんと 私との 関係を 母にそっと 匂わせてみたり。
たったそれだけだ。特別なことはなにもしていない。
成長していくからだの 不安をうちあけてみたり
…父さんと 私との 関係を 母にそっと 匂わせてみたり。
たったそれだけだ。特別なことはなにもしていない。
私が賢く、優しいひとであれば すべてをより良い方向にしようと努力することもできたかもしれない。
でも 私がいつでも求めていることは、すべてその逆だ。
崩れ落ちた破片。破壊によってもたらされる痛みだけが、生まれてからこれまで 不安しかなかった私の路に
ひかりを与えてくれた気がした。
それは 他人から見れば 妄想に過ぎなかったのだろう。
でも私にとって その考えは だんだんと真実になっていった。
きっと私に与えられた場所はすべて、私が私のために作り出したものなのだ。
父と母と、それから弟を 自分の都合の良いように操って、作り出した私のための世界。
だって、こんなにも思いのままに操ることができる。
こんなにも正しくない私の言葉を信じ、それでも、
私を触る父の手は優しい。
母は 母が傷つけた私の身体に 薬を塗ってくれる。
弟はいつでも そばにいる。
母は 母が傷つけた私の身体に 薬を塗ってくれる。
弟はいつでも そばにいる。
これが異常でないのなら なんだと言うのだろう。
彼らがほんとうに 人の心を持っているのであれば、
私という『悪』を 愛することなど しないはずだ。
もしも 本当に 見返りを求めることのない…
無償の愛というものがそこに存在しているのならば、
私は耐えられない。理解できない。
無償の愛の不在の証明、
私が私の為に作り出した おままごとのような愛が
此処にあるのだということを確かめるために
すべてを砕いて壊してしまうこと。

これが私のごっこ遊びなのであれば 全部許されるのでしょう?
***
××年八月 三十一日
***
××年八月 三十一日
物音ひとつしない 夜だった。
ただ鼻にとどく臭気が、 私が私のために作り出した 小規模な楽園の終わりの、 そのはじまりを告げていた。
窓からカーテンを通して、 差し込む月光。
私のベッドの脇に 立ち尽くす彼の 頬と 手が 赤くぬらついて 光っている。
それを見て、私は思った。
――どんな順番で刺したのだろう。母が先かな。それとも父だろうか。
いま、生きているのだろうか。それとももう死んだだろうか。どこで倒れているのだろうか。リビングか、寝室か。
私はそのとき彼に何を言っただろう。 歓喜にうちふるえ なにも言葉にできなかったのかもしれない。
 |
「全部終わったよ」 |
 |
「もう姉さんは苦しまなくて済むんだ」 |
私が苦しんでいることに彼はこだわっていた。
何度も聞いた言葉だった。
最初のころは くだらない妄想に囚われているのだなと 冷めた気持ちでそれを聞いていたけれど、
いまはじめて 私は苦しんでいたのかもしれないと そう思えた。
ただ、私の苦しみはまだ終わっていない。彼だけがまだ残っている。
私は……
 |
「結城は…」 |
純粋に私が被害者だと信じ続けた弟を、いま、一番、最高のタイミングで裏切ることで
彼を後戻りできないくらいに傷つけて 壊すことができると分かっていた。
だから、すべて。
 |
「結城は間違えたのよ。 私という問題を、間違えてしまったんだわ。」 |
私という人間のすべてを、いままで起こったことすべてが 私が引き起こしたことなのだということを、
父でも 母でもない。もちろん弟でもない。
『私が悪いのだ』ということを、
やさしく
わかりやすく
教えてあげることにしたのだった。
そして、彼は。
***
目が覚める。
 |
「……?」 |
瓦礫と赤と黒だけが彩る世界がそこに広がっていた。
現実感がないというのに、肌寒い。見慣れない、薄い服を着させられている。
ゆめだろうか。いや、ゆめじゃない。私は、あの榊という男のアナウンスも、ここで起きる動乱も、すべてすべて……
《判って》いる。
私はイバラシティの住民として、アンジニティの侵略に対抗する頭数に 数えられていたのだ。
あの八月三十一日から、まどろみのような時を過ごしてきた。
自分が起きているかも 眠っているのかもわからない 曖昧な時間。
その日々の中で 私が望む事はひとつだけ。
今、どうして目が覚めたのかわからない……醒めれば忘れる 与えられた ひとときのチャンスなのであれば。
私は確かめなければならない。探し出して、会いに行かねばならない。
彼もおなじ《此処》に居ることを、肌で感じる。理屈では説明できない、透明な血の繋がりがそこにある。
私は立ち上がることができた。
どうしてか 干からびた足でも、歩くことは苦にならなかった。
 |
日向環 「行かなきゃ。」 |
あの枯れ落ちた向日葵が呼んでいる。
私は確かめに行かなければならない。彼が真実を語る私の口を、この喉を
両指でもって締め上げたあの日から。
私は確かめに行かなければならない。彼が真実を語る私の口を、この喉を
両指でもって締め上げたあの日から。



ENo.664 闇のおえかき とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||



 |
なにものかに呼ばれるようにして 漂っていた彼の 歩みが止まる。 |
 |
日向結城 「姉さん?」 |
 |
あなたたちの背後に いつの間にか やせこけた女が立っていた。 |
 |
日向環 「…結城。」 |
 |
そう 枯れ落ちた八月を呼ぶものは、彼によく似た貌をしていた。 |
 |
藍浦英里緒 「……チッ。嗚呼、何だ、此度は時間切れらしい。各自自由にしやがれ。」 |
 |
くもくいさま 「悪くはなかったよ。……去る者はいるのか?そう、私はお前を愛しているよ。」 |



秘密結社『欠けた蜜蝋』
|
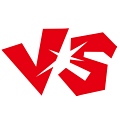 |
ハザマに生きるもの
|



ファッションファッションモンスター
|
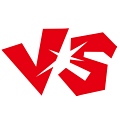 |
秘密結社『欠けた蜜蝋』
|



チナミ区 P-3:瓦礫の山
秘密結社『欠けた蜜蝋』
|
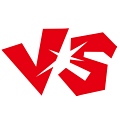 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 P-3:瓦礫の山
 |
マイケル 「な、なんだとー。ぐわー。」 |
チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



枯れ落ちた八月(122) は 雑木 を入手!
藍浦英里緒(391) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 石英 を入手!
サイトウ(906) は ド根性雑草 を入手!
くもくいさま(780) は 花びら を入手!
枯れ落ちた八月(122) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は ぬめぬめ を入手!
藍浦英里緒(391) は 花びら を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
くもくいさま(780) は 何か柔らかい物体 を入手!
藍浦英里緒(391) は 何か柔らかい物体 を入手!



特に何もしませんでした。



特に移動せずその場に留まることにしました。
採集はできませんでした。
- 藍浦英里緒(391) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 藍浦英里緒(391) の選択は ヒノデ区 D-9:落書き広場(ベースキャンプ外のため無効)





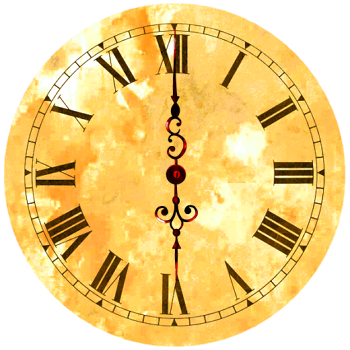
―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「……時計台に呼ばれてしまいましたが、はてさて。」 |
 |
エディアン 「なーんか、嫌な予感がします。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
 |
エディアン 「ほら……ほらぁ……。」 |
 |
榊 「どういうことでしょうねぇ。」 |
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝してます。」 |
 |
エディアン 「……ワールドスワップの能力者さんですよね。 機会を与えてくれて、感謝していますよ?」 |
 |
榊 「お姿は拝めないんですかねぇ。私は興味津々桃色片想いなのですが。」 |
声は淡々と、話を続ける。
 |
声 「どうやらこのワールドスワップ、時計の進みが狂っているようです。 特殊な因子を含めてしまった為と能力が訴えます。その因子が――」 |
 |
声 「――榊さん、貴方のようですね。何か、心当たりは?」 |
 |
榊 「大いにございます!特殊な世界の住人ゆえ、私は今や特異な存在なのでしょう。 妻に『貴方は変人』とよく言われていましたが、そういうことでしたか!納得ですッ」 |
 |
榊 「では、役目を果たすのは難しいということでよろしいですか?」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
榊 「……? ……どうしました?」 |
 |
声 「……仕切り直し、世界線を変更する、と能力が言ってきます。 貴方が案内役にならない世界線。イバラシティも、アンジニティも、新たなものになる……と。」 |
 |
エディアン 「……そ、そんなことまでできてしまう能力? ワールドスワップという名の範疇を超えてません?」 |
 |
榊 「世界線を別のものと交換する……と考えるなら、ギリギリ……ですかね。 というか、スワップから外れた現象は既に起こっていますが。」 |
 |
声 「これは能力ではなく、……呪い。呪いという言葉が合う。 今まで勝手に発動した数度、自分への利はない。制御下にない、把握できない、呪い。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「ハザマへの次の転送時間に、ハザマに転送される代わりに、世界線が変更される。 そして、案内役も、転送対象も、変わる。」 |
 |
声 「変わるものは、多いだろう。しかし変わらぬものも、あるだろう。」 |
 |
エディアン 「別の世界線、ですものね。 ……どうせなら私がアンジニティにいない世界線がいいんですけど。」 |
 |
榊 「……なるほど、奇妙な枝の正体は世界線操作者でしたかッ! 少なくとも私が案内役となれない世界線になるのですね、残念です。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「連絡は終わり。さようなら。」 |
声はそこで終わる。
 |
榊 「さて…… とても短い間ではありましたが、 エディアンさん、皆様、お付き合いありがとうございました!」 |
 |
エディアン 「お別れですか。悪人顔っぽくて敵視しやすい相手だったんですけどねー。」 |
 |
榊 「こんな素敵な笑顔を悪人顔呼ばわりとは、失礼な娘さんです。 なるほどアンジニティにいらっしゃるわけですねぇ。」 |
 |
エディアン 「……うるっさいですね。事情は人それぞれあるんですよ、色々!」 |
 |
榊 「……それでは、」 |
 |
エディアン 「……それでは、」 |
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
 |
榊 「お疲れ様でした。」 |
 |
エディアン 「お疲れ様でしたー!」 |

ENo.122
枯れ落ちた八月



【日向 環 -ヒムカイ タマキ-】
私立女子陽炎学院大学(しりつじょしかげろうがくいんだいがく)付属中学校二年生。
両親は長期の出張に出ており ひとりぐらし。
どんな人にも優しく、丁寧に接し、
すべての人が平等に不幸になる世の中を作ろうとしている
秘密結社【欠けた蜜蝋】のメンバーの一人だ。
半径10メートル以内に自分の領域を展開し、
ある程度の生命とエネルギーを操ることのできる異能持ち。
その時 彼女の周囲にはひまわりの花が咲く。
制御が上手くゆかず周囲をひまわりだらけにしてしまう事がある。
<ざざざ>
<ざざざ>
『××年八月 三十一日 未明、日向 修さんとその妻 裕子さん、長女である 日向 環さんが自宅で倒れていると匿名の通報があり 駆けつけた警察官によって発見されました。
警察はこの家に住む 長男の日向 結城さんが何らかの事情を知っていると見て………』
<ざざざざ……>
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1303
【発言・交流禄】
私立女子陽炎学院大学(しりつじょしかげろうがくいんだいがく)付属中学校二年生。
両親は長期の出張に出ており ひとりぐらし。
どんな人にも優しく、丁寧に接し、
すべての人が平等に不幸になる世の中を作ろうとしている
秘密結社【欠けた蜜蝋】のメンバーの一人だ。
半径10メートル以内に自分の領域を展開し、
ある程度の生命とエネルギーを操ることのできる異能持ち。
その時 彼女の周囲にはひまわりの花が咲く。
制御が上手くゆかず周囲をひまわりだらけにしてしまう事がある。
<ざざざ>
<ざざざ>
『××年八月 三十一日 未明、日向 修さんとその妻 裕子さん、長女である 日向 環さんが自宅で倒れていると匿名の通報があり 駆けつけた警察官によって発見されました。
警察はこの家に住む 長男の日向 結城さんが何らかの事情を知っていると見て………』
<ざざざざ……>
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1303
【発言・交流禄】
9 / 30
532 PS
チナミ区
P-3
P-3





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 平石 | 素材 | 15 | [武器]攻撃15(LV25)[防具]治癒10(LV10)[装飾]防御15(LV25) | |||
| 3 | アルミ缶 | 素材 | 15 | [武器]攻撃15(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 4 | 生きているスーツ | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 5 | 黒い嬰児 | 装飾 | 20 | 幸運10 | 回復10 | - | |
| 6 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]加速10(LV15)[防具]幸運10(LV5)[装飾]水纏15(LV25) | |||
| 7 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 9 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) | |||
| 10 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]敏捷10(LV15)[防具]加速10(LV15)[装飾]貫撃10(LV15) | |||
| 11 | 針 | 素材 | 15 | [武器]貫撃15(LV20)[防具]貫通15(LV30)[装飾]器用15(LV20) | |||
| 12 | 腐木 | 素材 | 15 | [武器]腐食15(LV25)[防具]反腐15(LV30)[装飾]舞腐15(LV30) | |||
| 13 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]反腐15(LV25)[防具]道連20(LV35)[装飾]腐食15(LV30) | |||
| 14 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 15 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 合成 | 5 | 合成に影響 |
| 料理 | 25 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| アクアヒール | 7 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| ヒールポーション | 8 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| プロテクション | 6 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| オートヒール | 6 | 0 | 80 | 味傷:治癒LV増 | |
| ヒーリングスキル | 7 | 0 | 50 | 自:HL増 | |
| フリーズ | 5 | 0 | 130 | 敵全:凍結 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 100 | 味肉精:HP増+肉体・精神変調減 | |
| ヒールハーブ | 7 | 0 | 80 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| アイヴィー | 5 | 0 | 60 | 敵列:束縛 | |
| トランキュリティ | 5 | 0 | 60 | 味環:HP増&環境変調減 | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| キュアディジーズ | 5 | 0 | 70 | 味肉2:HP増&肉体変調減 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 90 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 7 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
テキトウナモノ・ブレイク (ブレイク) |
0 | 20 | 敵:攻撃 | |
|
・ ・………… (エキサイト) |
0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
|
タヌ氣功 (イレイザー) |
0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
|
真・猫キック (ブラックアサルト) |
0 | 90 | 敵:3連鎖闇撃&闇痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]ペネトレイト |
| [ 2 ]ヒーリングスキル | [ 1 ]ブラックアサルト | [ 1 ]ファイアボール |
| [ 3 ]水特性回復 | [ 1 ]ストライキング |

PL / 植物園の廃墟