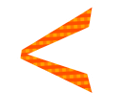<< 4:00>> 6:00




二回目の死は――ただ、虚しかった。
一度目の死は、眠っている間に起こったものだったし、治療のおかげもあり苦しくはなかった。自分の体、自分の死が彼女の役に立ったのだと、そう思うと満ち足りた気持ちですらあった。
心残りもなかった。憧れていた隊長は、いつの間にか共に過ごすべき人を見つけていて、そのことは少しだけ寂しくはあった。だが、そのことはかえって自分を安心させた。隊長はやはり大丈夫なのだ、除隊した後も幸せな生活を続けていくのだという確信が持てた。
そうして雫は、憧れていた隊長と、献身的に治療をしてくれた医師と同じ屋根の下で、深夜にひっそりと死へ誘われたのだった。自分の人生にありがたいと思いながら、この世を去ったのであった。
しかし、二回目の死はどうだろう。ただただ、必要だから殿を務めて、必要だから時間を稼いで、そして結果として死んだ。身体から力が抜ける感覚がして、硬そうな地面が目の前に迫ってきて、遠くで音が響いて、不思議と衝撃は感じなかった。自分が自分から離れて遠くに落ちていく感じがして、ああ、これが死なんだなと冷静に自分自身を見つめている自分がいた。
自分が死んだことには、全く後悔はしていない。自分の死が虚しく、意味がないものだったとしても、それはあの場、あの瞬間においては必要なことだった。
ただ、戦場における死は寂しく、あっけなかった。自分の仲間はたくさん戦場で散っていったが、皆があの思いを経験しているのあろうか。そう考えると、戦場を結局生き延びた自分より、皆は強かったのかもしれない、と思った。
目が覚めたときは野ざらしであった。一番に考えたのは、これじゃ風邪を引くなということだった。傍に落ちていた背嚢から火酒を取り出し、ぐびりと飲み下すと胃の中から温かさが全身に広がっていった。ふぅ、とため息が漏れる。お酒の熱が全身へ回っていく感覚は、何度経験しても心地がよかった。
それにしても、自分は死んだはずだ。再び死へと誘われたはずだ。それなのに、どうしてこの地に立っているのだろうか。ハザマの効果だろうか。この地に引き寄せられたときと同じように。
いや、おそらくは違う。自分の中に何か別なものが入り込んできている。目が覚めてから、そう感じていた。これに似た感覚は前にも感じたことがあった。治療で、生命力を流し込まれたときだ。
首につけたお守りを指でなぞる。思い当たることといえば、これくらいだった。落とさないようにと服の中へ入れこんでいた、このお守りだ。
もしかしたら、このお守りが自分を死から掬い上げたのかもしれない、と思った。確信はないが、何となくそう思った。何といったって、このお守りをくれたのはすごい狐さんなのだ。
もう一口、火酒を飲み下す。栓を締めて、荷物をまとめた。先に撤退した皆のところへ追い付かなければならない。
何気ない顔をして征こう。元より死は覚悟の上で、実際に戦場で死んでみて大きな負担にならないことは分かった。もし、次に死んでみて、蘇生できなければ、残念ではあるがそれまでのことだ。むしろ、それが自然なことだ。
ためらわずに命を投げ出す覚悟でいこう。生きるも死ぬも結果に過ぎない。そして、昔と同じように、戦場でそう振舞うことが、自分が皆のところに行ける道筋だろうだろうから。



ENo.7 ランノ とのやりとり

ENo.87 ゆい とのやりとり

ENo.245 兎乃 とのやりとり

ENo.510 ジャックドゥ とのやりとり

ENo.624 ヒバリ とのやりとり

ENo.777 りりぃ とのやりとり

ENo.791 ミロワール とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 おいものスープ を美味しくいただきました!
体調が 2 回復!(10⇒12)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!











チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



ハティ(741) は 柳 を入手!
れーこ(764) は 杉 を入手!
ソラ(936) は 古雑誌 を入手!
雫(939) は 杉 を入手!
雫(939) は 牙 を入手!
雫(939) は 毛 を入手!
れーこ(764) は 羽 を入手!
ソラ(936) は 剛毛 を入手!
れーこ(764) は 何か柔らかい物体 を入手!
れーこ(764) は 何か柔らかい物体 を入手!
雫(939) は 何か柔らかい物体 を入手!



武術LV を 3 DOWN。(LV15⇒12、+3CP、-3FP)
響鳴LV を 4 DOWN。(LV4⇒0、+4CP、-4FP)
自然LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
れーこ(764) により ItemNo.9 美味しい草 から料理『美味しいサラダ』をつくってもらいました!
⇒ 美味しいサラダ/料理:強さ40/[効果1]体力10 [効果2]防御10 [効果3]治癒10
ランメイ(1289) とカードを交換しました!
エキサイト (エキサイト)

ファイアダンス を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアダンス を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアダンス を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
トランキュリティ を習得!
アドバンテージ を習得!
クラック を習得!
グランドクラッシャー を習得!



ソラ(936) に移動を委ねました。
チナミ区 H-17(森林)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 H-18(森林)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 H-19(森林)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 H-20(沼地)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!
- ハティ(741) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- れーこ(764) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- ソラ(936) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- 雫(939) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 を選択!
- ハティ(741) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山
- れーこ(764) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山
- ソラ(936) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山
- 雫(939) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。












瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。














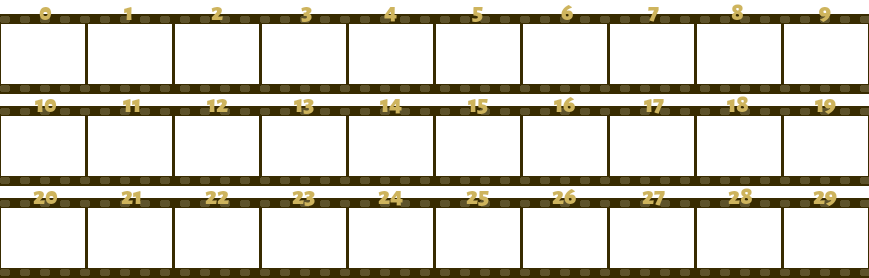





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



二回目の死は――ただ、虚しかった。
一度目の死は、眠っている間に起こったものだったし、治療のおかげもあり苦しくはなかった。自分の体、自分の死が彼女の役に立ったのだと、そう思うと満ち足りた気持ちですらあった。
心残りもなかった。憧れていた隊長は、いつの間にか共に過ごすべき人を見つけていて、そのことは少しだけ寂しくはあった。だが、そのことはかえって自分を安心させた。隊長はやはり大丈夫なのだ、除隊した後も幸せな生活を続けていくのだという確信が持てた。
そうして雫は、憧れていた隊長と、献身的に治療をしてくれた医師と同じ屋根の下で、深夜にひっそりと死へ誘われたのだった。自分の人生にありがたいと思いながら、この世を去ったのであった。
しかし、二回目の死はどうだろう。ただただ、必要だから殿を務めて、必要だから時間を稼いで、そして結果として死んだ。身体から力が抜ける感覚がして、硬そうな地面が目の前に迫ってきて、遠くで音が響いて、不思議と衝撃は感じなかった。自分が自分から離れて遠くに落ちていく感じがして、ああ、これが死なんだなと冷静に自分自身を見つめている自分がいた。
自分が死んだことには、全く後悔はしていない。自分の死が虚しく、意味がないものだったとしても、それはあの場、あの瞬間においては必要なことだった。
ただ、戦場における死は寂しく、あっけなかった。自分の仲間はたくさん戦場で散っていったが、皆があの思いを経験しているのあろうか。そう考えると、戦場を結局生き延びた自分より、皆は強かったのかもしれない、と思った。
目が覚めたときは野ざらしであった。一番に考えたのは、これじゃ風邪を引くなということだった。傍に落ちていた背嚢から火酒を取り出し、ぐびりと飲み下すと胃の中から温かさが全身に広がっていった。ふぅ、とため息が漏れる。お酒の熱が全身へ回っていく感覚は、何度経験しても心地がよかった。
それにしても、自分は死んだはずだ。再び死へと誘われたはずだ。それなのに、どうしてこの地に立っているのだろうか。ハザマの効果だろうか。この地に引き寄せられたときと同じように。
いや、おそらくは違う。自分の中に何か別なものが入り込んできている。目が覚めてから、そう感じていた。これに似た感覚は前にも感じたことがあった。治療で、生命力を流し込まれたときだ。
首につけたお守りを指でなぞる。思い当たることといえば、これくらいだった。落とさないようにと服の中へ入れこんでいた、このお守りだ。
もしかしたら、このお守りが自分を死から掬い上げたのかもしれない、と思った。確信はないが、何となくそう思った。何といったって、このお守りをくれたのはすごい狐さんなのだ。
もう一口、火酒を飲み下す。栓を締めて、荷物をまとめた。先に撤退した皆のところへ追い付かなければならない。
何気ない顔をして征こう。元より死は覚悟の上で、実際に戦場で死んでみて大きな負担にならないことは分かった。もし、次に死んでみて、蘇生できなければ、残念ではあるがそれまでのことだ。むしろ、それが自然なことだ。
ためらわずに命を投げ出す覚悟でいこう。生きるも死ぬも結果に過ぎない。そして、昔と同じように、戦場でそう振舞うことが、自分が皆のところに行ける道筋だろうだろうから。



ENo.7 ランノ とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.87 ゆい とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.245 兎乃 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.510 ジャックドゥ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.624 ヒバリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.777 りりぃ とのやりとり
| ▲ |
| ||||
| |||||||
ENo.791 ミロワール とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



| れーこ 「なんなのあの人達…! みんないる、よね…?」 |
 |
ソラ 「みんな、大丈夫? 安全に休める場所まで、もう少しがんばって。」 |
| 雫 「すみません、お待たせしました。さあ、征きましょう。」 |
ItemNo.6 おいものスープ を美味しくいただきました!
体調が 2 回復!(10⇒12)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





いつか見た景色
|
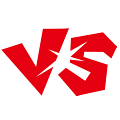 |
行き当たりばったり4人組
|





チナミ区 H-15:釣り堀
 |
マイケル 「上出来ですね。それでは、どうぞどうぞ。」 |
チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



ハティ(741) は 柳 を入手!
れーこ(764) は 杉 を入手!
ソラ(936) は 古雑誌 を入手!
雫(939) は 杉 を入手!
雫(939) は 牙 を入手!
雫(939) は 毛 を入手!
れーこ(764) は 羽 を入手!
ソラ(936) は 剛毛 を入手!
れーこ(764) は 何か柔らかい物体 を入手!
れーこ(764) は 何か柔らかい物体 を入手!
雫(939) は 何か柔らかい物体 を入手!



武術LV を 3 DOWN。(LV15⇒12、+3CP、-3FP)
響鳴LV を 4 DOWN。(LV4⇒0、+4CP、-4FP)
自然LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
れーこ(764) により ItemNo.9 美味しい草 から料理『美味しいサラダ』をつくってもらいました!
⇒ 美味しいサラダ/料理:強さ40/[効果1]体力10 [効果2]防御10 [効果3]治癒10
| れーこ 「…だい、じょうぶ?」 |
ランメイ(1289) とカードを交換しました!
エキサイト (エキサイト)

ファイアダンス を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアダンス を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアダンス を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
トランキュリティ を習得!
アドバンテージ を習得!
クラック を習得!
グランドクラッシャー を習得!



ソラ(936) に移動を委ねました。
チナミ区 H-17(森林)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 H-18(森林)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 H-19(森林)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 H-20(沼地)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!
- ハティ(741) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- れーこ(764) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- ソラ(936) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- 雫(939) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 を選択!
- ハティ(741) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山
- れーこ(764) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山
- ソラ(936) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山
- 雫(939) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |







学生暴動ではありません
|
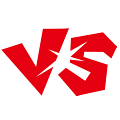 |
行き当たりばったり4人組
|




チナミ区 P-3
瓦礫の山
瓦礫の山
 |
マイケル 「あ、来ましたかー。チェックポイントはこちらですよー。」 |
瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「遠方までご苦労さまです、私はマイケルです。 お疲れでしょう。とりあえずお茶でも。」 |
チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
 |
マイケル 「……少しは休めましたか?」 |
 |
マイケル 「それではさっさとおっ始めましょう。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんからねぇー!!」 |





ENo.939
狭霧雫/兎斬雫



名前:狭霧 雫(さぎり しずく)
年齢:14歳(イバラ創藍高校中等部二年生)
身長:156cm 体重:52kg
好き:お肉、甘いもの、炭酸水、歌うこと、散歩
嫌い:孤独、雪
タニモリ区の北部にある狭霧精肉店の一人娘。
家の手伝いをすることが多いため、帰宅部。
家の近くにあるヤガミ神社をよく訪れている。
異能は人並み外れた怪力と身体能力。
その副作用として犬耳と犬の尻尾が生えている。
不断着は和服かジャージのことが多い。
基本的には穏やかで心優しい性格。
以下の精神的な疾患を抱えている。
・他者を傷つけることに忌避感を抱かない。
・音楽(旋律)を覚えることが極端に苦手。
_____________________
本名:兎斬 雫(うさぎり しずく)
イバラシティの住人でもアンジニティの住人でもない。
アンジニティの住人と同じく、イバラシティでは元の記憶を失っている。
ハザマでは本来の記憶を取り戻す。見た目は変わらない。
半妖と呼ばれる遺伝子変異した人間で、元軍人。
14歳のときに死出の旅路に出たはずであったが、
今回の侵略行動に巻き込まれる形で参戦している。
世界間の抗争には関心を示さず、ただ戦場を駆け抜ける。
_____________________
交流歓迎。置きレス多めかもしれません。
既知設定やロールプレイの相談など、お気軽にどうぞ。
現在、プロフ絵は3種類。
▼ホームスポット▼
[狭霧精肉店]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=332
▼よく行くスポット▼
[ヤガミ神社]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=62
[イバラ創藍高校]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=161
[桜並木のさんぽみち]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=443
▼今までのロールプレイ記録▼
[雫の日記帳]
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1532
_____________________
【サブキャラ】
名前:六徳堂 慈(りっとくどう いつき)
年齢:12歳(イバラ創藍高校初等部六年生)
身長:140cm 体重:35kg
好き:味噌汁
嫌い:悲しいこと
最近イバラシティに引っ越してきた男の子。祖父と一緒に住んでいる。
狸の耳と狸の尻尾が生えている。素直で、頭のねじが緩い。
異能は封印されており、使うことができない。
年齢:14歳(イバラ創藍高校中等部二年生)
身長:156cm 体重:52kg
好き:お肉、甘いもの、炭酸水、歌うこと、散歩
嫌い:孤独、雪
タニモリ区の北部にある狭霧精肉店の一人娘。
家の手伝いをすることが多いため、帰宅部。
家の近くにあるヤガミ神社をよく訪れている。
異能は人並み外れた怪力と身体能力。
その副作用として犬耳と犬の尻尾が生えている。
不断着は和服かジャージのことが多い。
基本的には穏やかで心優しい性格。
以下の精神的な疾患を抱えている。
・他者を傷つけることに忌避感を抱かない。
・音楽(旋律)を覚えることが極端に苦手。
_____________________
本名:兎斬 雫(うさぎり しずく)
イバラシティの住人でもアンジニティの住人でもない。
アンジニティの住人と同じく、イバラシティでは元の記憶を失っている。
ハザマでは本来の記憶を取り戻す。見た目は変わらない。
半妖と呼ばれる遺伝子変異した人間で、元軍人。
14歳のときに死出の旅路に出たはずであったが、
今回の侵略行動に巻き込まれる形で参戦している。
世界間の抗争には関心を示さず、ただ戦場を駆け抜ける。
_____________________
交流歓迎。置きレス多めかもしれません。
既知設定やロールプレイの相談など、お気軽にどうぞ。
現在、プロフ絵は3種類。
▼ホームスポット▼
[狭霧精肉店]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=332
▼よく行くスポット▼
[ヤガミ神社]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=62
[イバラ創藍高校]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=161
[桜並木のさんぽみち]
http://lisge.com/ib/talk.php?s=443
▼今までのロールプレイ記録▼
[雫の日記帳]
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1532
_____________________
【サブキャラ】
名前:六徳堂 慈(りっとくどう いつき)
年齢:12歳(イバラ創藍高校初等部六年生)
身長:140cm 体重:35kg
好き:味噌汁
嫌い:悲しいこと
最近イバラシティに引っ越してきた男の子。祖父と一緒に住んでいる。
狸の耳と狸の尻尾が生えている。素直で、頭のねじが緩い。
異能は封印されており、使うことができない。
30 / 30
332 PS
チナミ区
D-2
D-2






| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 杉 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV30)[防具]舞痺10(LV20)[装飾]加速10(LV10) | |||
| 2 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]器用10(LV15)[装飾]反撃10(LV25) | |||
| 3 | 剣鉈 | 武器 | 39 | 器用10 | - | - | 【射程1】 |
| 4 | コルト・ガバメント | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 真綿のお守り | 装飾 | 36 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | 防弾チョッキ | 防具 | 33 | 鎮痛10 | 治癒10 | - | |
| 9 | 美味しいサラダ | 料理 | 40 | 体力10 | 防御10 | 治癒10 | |
| 10 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 11 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 12 | 身体/武器/物理 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 32 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 月の型・月虹 (ブレイク) | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 雪の型・早雪 (ピンポイント) | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 花の型・早梅 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 雪の型・雪風 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練1 | 雪の型・深雪 (エキサイト) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| 練3 | 月の型・蘿月 (ストーンブラスト) | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 |
| 練1 | 心構・雄風 (ストレングス) | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 |
| 花の型・残英 (ビブラート) | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| 花の型・散花 (クラッシュ) | 5 | 0 | 80 | 敵列:地撃 | |
| 心構・飛雨 (ガードフォーム) | 5 | 0 | 80 | 自:DF増(2T) | |
| 練1 | 隠し・春雷 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 100 | 敵貫:攻撃 |
| 練3 | アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 |
| 花の型・花陰 (ロックスティング) | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃 | |
| 練3 | 心構・澄清 (アニマート) | 5 | 0 | 120 | 味全:AT増(2T) |
| トランキュリティ | 5 | 0 | 60 | 味環:HP増&環境変調減 | |
| アドバンテージ | 5 | 0 | 80 | 敵:攻撃&AT奪取 | |
| 練3 | 月の型・落月 (イレイザー) | 7 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| クラック | 5 | 0 | 160 | 敵全:地撃&次与ダメ減 | |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 200 | 敵:粗雑地撃+回避された場合、敵列:地撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 雪泥鴻爪 (攻撃) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 行雲流水 (器用) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 槿花一朝 (活力) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 海底撈月 (体力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 氷姿雪魄 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
テストカード (クイック) |
0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 練1 |
AT寿司 (ストレングス) |
0 | 100 | 自:AT増 |
|
流速制御・偽 (アクアスピット) |
2 | 200 | 敵貫2:水痛撃 | |
|
ウィスコンシン (ガードフォーム) |
0 | 80 | 自:DF増(2T) | |
| 練1 |
エキサイト (エキサイト) |
0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ファイアダンス | [ 3 ]フレイムブラスター | [ 3 ]レッドインペイル |
| [ 3 ]ブレッシングレイン | [ 3 ]見切り |

PL / そめいろ