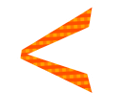<< 4:00>> 6:00




――――。
――――――――。
―――――――――――。
血腥さと、何かが焼ける臭いが立ち込める中、二つの小さな影がその中で揺らめく。
影の正体は、同じくらいの背丈の二人の少女。
少女達は双子の姉妹であった。
姉は所々に大きな傷を負ってはいるものの、まだ健全である事は確かであり、しかし、もう妹の方は全身を朱色に塗し、所々は欠ける様に傷を負い、何よりも穴が開いた胴からは、はたはたと赤い花びらを大量に零していた。
誰もが判るほどの致命傷だ。
そんな中で、短い間に交わされる言葉。
片方は必死に紡ぎ、もう片方は泣きながら留めようとする。
ある言葉を最期に、姉の言葉は届かない儘、妹の意識は底知れない暗がりへと堕ちていく。
もしかすると、随分前から、姉の言葉は妹には届いていなかったのかもしれない。
堕ちてしまえば、きっと二度と這い上がって来れない程に深い穴底。
でも、それは、押し寄せる死の痛みと凍えの中でも、とても心地よく感じられた。
姉を守り、その姉を待つティーナの元へと帰せるのであれば、これ以上にない程に善い終りだと、〝悔いのない死に方〟ができたと、少女は思っていた。
ふ、と。
自分を〝何か〟が繋ぎ止め、掬い上げようとする力を感じられた。
しかし、それと同時に少女の意識はそこで完全に途切れた。
――夢の中での意識が途切れると同時に、現実での意識が浮上する。
重く錆付いた思考を、窓から入る清涼な風が取り払う様に撫でていく。
夢の内容を反芻する様に茫洋とし、そして、それは決して夢では無い。
この現実に続いている事を再認識すれば、身体が震えだした。
最早、何度目か分からない、喪失したものへの自覚。
身体が震え、喉が渇く様に、引き攣る。呼吸の仕方さえ忘れ、無様に噎せこみ喘ぐ。
その様子に気付いたのか、緑色の髪の少女が慌てて駆け寄ってきた。
背中を摩り、喪失感と恐怖で震える手を抑えようと握りながら、穏やかな言葉がかけられる。
その手の温もりと言葉の温かさは、少女が求めていたもので――だけど、違和感も同時に感じられる。
――あぁ。そうだ、これは。これは、あの子と違うものだ。
「ティー、ナ……?」
確かめる様に名前を呼んで、少女へと視線をやる。
その言葉に、ティーナと呼ばれた少女は、恐る恐るといった風に頷いてみせた。
――息苦しさで涙が滲む視界に映ったのは、赤い瞳。
それは、自分が知っていた瞳の色と違う気がして、少女は眼を見開く。
こんな色であっただろうか。
後遺症なのか、思い出そうとしても靄がかかったように、記憶が定かにならない。
自分の大切な記憶だと言う事だけは分かるのに、それなのに、その曖昧さに息が詰まる。
そこから先は、何時も通りの反応だった。
違うとすれば、いつもよりもずっと強い拒絶。
「……っ!い、やっ……!」
ティーナの手を振り払い、部屋から逃げる様に飛びだす。
穏やかで、暖かさに満ちた手ではあったけど、少女は逆に、それがとても怖かった。
ティーナの姿をしているのに、ティーナの顔をしているのに、ティーナの香りがするのに。
それは、自分が知るティーナではない。姿形はティーナであるのに、別の気配を感じる存在。
優しさも、穏やかさも、あの時と変わらないものではあるのに、それが余計に怖くて堪らない。
思うように力の入らない身体に、鞭を打ち、只管に走った。
足が縺れ、何度か転びそうになっても、踏み堪え、息を切らしながら走った。
庭園へと逃げ込む様に夢中で走り、そこで、身体が悲鳴を上げて地面へと倒れこむ。
酸素が不足していた肺に空気を取り込もうと、喘ぐように呼吸を整える。
苦い液体が込み上げてくるのを必死に押さえ込み、身体を起こした。
身体を起こし、上げた視界に蒼い薔薇が咲き誇っているのが眼に入る。
「ここ、は」
三人の思い出の場所だと言う事を思い出し、声が揺れる。
思い出を想起するには、十分過ぎる場所だった。
匂い、色、そこで噛み締めた幸せと、満ち足りた思い出。
だからこそ、わかってしまった。
自分の知っているティーナは、もうこの世界に居ないという事実を。
愛した姉の楔奈も、愛したティーナも、もう、いない。
自分の手を取ってくれた二人は、もう居ないのだ。
その事実に気付いた瞬間、どうしようもなく怖くなる。
まるで、知らない夜の野山に放り出されたような――真夜中の大海に投げ出されたような、そんな恐恐怖心が、少女の心を蝕んでいく。
適当な花壇の器を割り、破片を手に握りしめる。
やり方は知っている。どう突けば、命を手折れるのかは学んでいる。
だが、その破片を喉輪へと突きいれようとも、拒絶する様に手が震え、其れを拒んだ。
内側から込み上げる、強迫観念にも近い、〝生きたい〟という望み。
ああ、そうだ。私は、一杯の物を踏み台にして生かされたんだ。
その分まで〝生きなきゃいけない〟のだ。
空の器に、そんな想いが満ちていく。
『生きなきゃ生きなきゃ生きなきゃ生きて生きて生きて生きて生きたい生きたい生きたい生きたい生きて
――凛音、わたしも、帰りたいよ……』
内側から響き渡る、声。
それが、自分の命を断つ事を許してはくれなかった。
力一杯に握りしめた破片が手に食い込み、赤い雫を滲ませる。
「ううぅ……あああああああぁぁぁぁぁあっ!!!」
絶叫とも言える声を上げて、頭を打ちつける。
内側から響く、自分のものではない、あの場に居た〝誰か〟の想いが、自分が死を望む事を否定する。
お願いだから、止めて。この声とこの想いで、私を満たさないで。
私も、あの二人と一緒に逝かせて――そんな望みが込みあげても。
そんな願いを無視するかのように、自分の中に蠢く数多の渇望が、その欲望を許しはしなかった。
自分を活かす為に、望まず糧となったモノ達が決してそれは許さないと言う様に。
「……解った、解かったから……!もうその声を、止めて……!」
それでも声は止んでくれない声から逃げる様に、頭を抱え、耳を塞ぎ、狂った様に叫び声を上げる。
「ねえさまぁ……、ティーナぁ……、わたしだけ……っ、おいていかないでよぉ……っ」
もう誰も居ない。誰も知らない。帰れる場所も無い、戻れる場所もない。
あの二人は――もう、傍に、居ない。もう、何処にも居ない。
何時も取り囲んで居てくれた温もりがない。風が吹けば、透ける様に自分を薙いでいく。
どうしようも無い程に、凍えてしまうくらい酷く寒かった。
ぼろぼろと、頬から雫が零れ落ちていく。泣けば、泣く程に胸が苦しくて痛い。
嗚咽が止まらず、吐き出せば吐きだす程に、その悲しみは深くなる。
喘ぐように鳴き声をあげ、溺れるように意識を沈ませていく。
治癒は受けても、完全に復調したわけではないその身体は、そんな情動でも今は堪えてしまう。
やがて、少女は意識を途絶えさせた。
――暫くして、温かいものが額に触れて、目が覚める。
不安そうに覗きこむ顔、触れても良かったのだろうかという怖れを交えた、泣きそうになっている〝ティーナ〟の顔。
寂しさなのか、或は、悲しさなのか、何時もなら明るい少女の顔色はそんな色に染まっていた。
(あぁ、そう言えば――)
何故、そんな顔をしているのだろうと思いながらも、この少女も自分と同だと言う事に、少女は気が付く。
誰も居ない、誰も知ることのない、独りになってしまった。
形は違えど、同じ痛みを持っているのだ
もし、この少女が〝ティーナ〟である何かだとしても、それでも、この少女は自分を見つけ出し、助けに来てくれた。
共絶し、それを拒んでも、この少女は手を手繰り寄せようと伸ばし続けてくれた。
「……ごめんね、ティーナ。
――もう、大丈夫。私が、貴女の事を守るから。だから一緒に、生きよう?」
再び、その手を掴む。
あの時みたいに手を引かれ、誘われるままではなく、今度は自分自身が引っ張れるようにと力を込めて。
幸い、その手の差し出し方を、引っぱり方を、少女は教えられている。
――残された想いがあるなら、きっと、また歩き出せるから。
――それは、最初の記憶。
朧気ながらも、誰かの手の温もりで、眠りから揺り起こされた様な、穏やかな目覚めの記憶。
緑色の髪を持つ少女が、細い銀糸の髪の人形の様な少女の手を取りながら、先導するように歩いていた。
手を引かれるがままに、けれど、足取りはしっかりと。
其の少女へとついて行く。
辿りついた場所は、蒼い薔薇が咲き誇る庭園だった。
未だ不完全な心を持つ少女でも、その蒼に彩られた庭園がキレイな物だと言う事は理解ができたのか、ほんのりと表情を緩め、同じ色合いをした瞳を細めた。
『……ふふ、ごめんね。急で驚かせちゃった?』
その様子を見た、緑色の髪をした少女が朗らかに笑む様に表情をつくり、人形の少女の顔を覗き込む。
『……あ。来たんだね、リンネ』
その二人を出迎える様に、
「――?」
『あ、いけない。言い忘れちゃってた。
わたしはね、ティーナ。水原ティーナ。
……あなたが、わたしをまもってくれる、もう一人の〝きし〟の子なんだよね?』
『……あはは、ごめんね。まだ、リンネはよくわかってないし、自分が無いから。
――ほら、リンネも挨拶、しよう?』
『うん、もう一度、君たちの事を教えて?』
「……私。私の、名前は――」
『わたしは白妙楔奈。ティーナを守る、守護騎士の一人。此れからは、どうか末長く――ほら、リンネ?』
「……ぁ。はい。私の、名前は、白妙凛音、です。
あなたを、護る……守護騎士、です。よろしく、お願い……します」
『……うん。できたできた』
『ふふ。
……うん、君たちみたいな子が、わたしを守ってくれるなら、きっと怖くなさそう』
良かった、とにこやかに微笑むティーナに、楔奈も穏やかに笑みを浮かべる。
『さ、行こう、凛音。今日は、一杯つきあって貰うんだから。まずは、わたしとセツナが作った秘密基地に――』
案内した時と同じように手を取り、握り締める。
優しく、離させない様な強さを持ったティーナの手の温もり。
自然と、凛音の表情に〝笑み〟というものが浮かんだ。
自分ではまだ、其れが何を意味するか分からない程に淡い感情のイロ。
それが最初の、少女がヒトとしての灯かりが心に点いた、一番最初の記憶。
―――――――――――。
――――――――。
――――。
『うん、巧く撮れて良かった。
……ふふ、いい顔して笑ってるじゃない。始めての笑顔だね、凛音』
二人のやりとりを眺め、少し離れた場所でその写真を撮っていた楔奈は、嬉しげに笑みを浮かべる。
妹が始めて浮かべた笑顔で、それが、自分の愛する少女が与えたモノだと思えば、誇らしく思えたから。
最愛の二人が手を取り、笑い合う姿は、傷を持つ少女に取って心を奮い立たせるには十分な糧であった。
この写真は将来二人が大人になった時にでも見せて、からかってやろうと――悪戯気で、だけど幸福に満ちた笑顔で、撮れた物を眺め――庭園を走る二人の後を追いかけた。




ENo.505 日明と月夜 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 パン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(11⇒12)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










武術LV を 3 DOWN。(LV15⇒12、+3CP、-3FP)
解析LV を 6 UP!(LV4⇒10、-6CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
ラフィ(132) とカードを交換しました!
鼠と竜のゲーム (ライトジャイアント)


ストライキング を研究しました!(深度0⇒1)
ストライキング を研究しました!(深度1⇒2)
ストライキング を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
エリアグラスプ を習得!
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!
追究 を習得!



ティーナ(709) に移動を委ねました。
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 N-15(草原)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 O-15(草原)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調9⇒8)
採集はできませんでした。
- ティーナ(709) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- スペイド(725) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。


















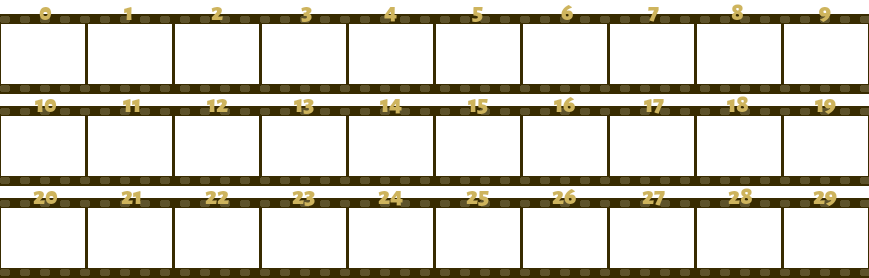





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



――――。
――――――――。
―――――――――――。
血腥さと、何かが焼ける臭いが立ち込める中、二つの小さな影がその中で揺らめく。
影の正体は、同じくらいの背丈の二人の少女。
少女達は双子の姉妹であった。
姉は所々に大きな傷を負ってはいるものの、まだ健全である事は確かであり、しかし、もう妹の方は全身を朱色に塗し、所々は欠ける様に傷を負い、何よりも穴が開いた胴からは、はたはたと赤い花びらを大量に零していた。
誰もが判るほどの致命傷だ。
そんな中で、短い間に交わされる言葉。
片方は必死に紡ぎ、もう片方は泣きながら留めようとする。
ある言葉を最期に、姉の言葉は届かない儘、妹の意識は底知れない暗がりへと堕ちていく。
もしかすると、随分前から、姉の言葉は妹には届いていなかったのかもしれない。
堕ちてしまえば、きっと二度と這い上がって来れない程に深い穴底。
でも、それは、押し寄せる死の痛みと凍えの中でも、とても心地よく感じられた。
姉を守り、その姉を待つティーナの元へと帰せるのであれば、これ以上にない程に善い終りだと、〝悔いのない死に方〟ができたと、少女は思っていた。
ふ、と。
自分を〝何か〟が繋ぎ止め、掬い上げようとする力を感じられた。
しかし、それと同時に少女の意識はそこで完全に途切れた。
――夢の中での意識が途切れると同時に、現実での意識が浮上する。
重く錆付いた思考を、窓から入る清涼な風が取り払う様に撫でていく。
夢の内容を反芻する様に茫洋とし、そして、それは決して夢では無い。
この現実に続いている事を再認識すれば、身体が震えだした。
最早、何度目か分からない、喪失したものへの自覚。
身体が震え、喉が渇く様に、引き攣る。呼吸の仕方さえ忘れ、無様に噎せこみ喘ぐ。
その様子に気付いたのか、緑色の髪の少女が慌てて駆け寄ってきた。
背中を摩り、喪失感と恐怖で震える手を抑えようと握りながら、穏やかな言葉がかけられる。
その手の温もりと言葉の温かさは、少女が求めていたもので――だけど、違和感も同時に感じられる。
――あぁ。そうだ、これは。これは、あの子と違うものだ。
「ティー、ナ……?」
確かめる様に名前を呼んで、少女へと視線をやる。
その言葉に、ティーナと呼ばれた少女は、恐る恐るといった風に頷いてみせた。
――息苦しさで涙が滲む視界に映ったのは、赤い瞳。
それは、自分が知っていた瞳の色と違う気がして、少女は眼を見開く。
こんな色であっただろうか。
後遺症なのか、思い出そうとしても靄がかかったように、記憶が定かにならない。
自分の大切な記憶だと言う事だけは分かるのに、それなのに、その曖昧さに息が詰まる。
そこから先は、何時も通りの反応だった。
違うとすれば、いつもよりもずっと強い拒絶。
「……っ!い、やっ……!」
ティーナの手を振り払い、部屋から逃げる様に飛びだす。
穏やかで、暖かさに満ちた手ではあったけど、少女は逆に、それがとても怖かった。
ティーナの姿をしているのに、ティーナの顔をしているのに、ティーナの香りがするのに。
それは、自分が知るティーナではない。姿形はティーナであるのに、別の気配を感じる存在。
優しさも、穏やかさも、あの時と変わらないものではあるのに、それが余計に怖くて堪らない。
思うように力の入らない身体に、鞭を打ち、只管に走った。
足が縺れ、何度か転びそうになっても、踏み堪え、息を切らしながら走った。
庭園へと逃げ込む様に夢中で走り、そこで、身体が悲鳴を上げて地面へと倒れこむ。
酸素が不足していた肺に空気を取り込もうと、喘ぐように呼吸を整える。
苦い液体が込み上げてくるのを必死に押さえ込み、身体を起こした。
身体を起こし、上げた視界に蒼い薔薇が咲き誇っているのが眼に入る。
「ここ、は」
三人の思い出の場所だと言う事を思い出し、声が揺れる。
思い出を想起するには、十分過ぎる場所だった。
匂い、色、そこで噛み締めた幸せと、満ち足りた思い出。
だからこそ、わかってしまった。
自分の知っているティーナは、もうこの世界に居ないという事実を。
愛した姉の楔奈も、愛したティーナも、もう、いない。
自分の手を取ってくれた二人は、もう居ないのだ。
その事実に気付いた瞬間、どうしようもなく怖くなる。
まるで、知らない夜の野山に放り出されたような――真夜中の大海に投げ出されたような、そんな恐恐怖心が、少女の心を蝕んでいく。
適当な花壇の器を割り、破片を手に握りしめる。
やり方は知っている。どう突けば、命を手折れるのかは学んでいる。
だが、その破片を喉輪へと突きいれようとも、拒絶する様に手が震え、其れを拒んだ。
内側から込み上げる、強迫観念にも近い、〝生きたい〟という望み。
ああ、そうだ。私は、一杯の物を踏み台にして生かされたんだ。
その分まで〝生きなきゃいけない〟のだ。
空の器に、そんな想いが満ちていく。
『生きなきゃ生きなきゃ生きなきゃ生きて生きて生きて生きて生きたい生きたい生きたい生きたい生きて
――凛音、わたしも、帰りたいよ……』
内側から響き渡る、声。
それが、自分の命を断つ事を許してはくれなかった。
力一杯に握りしめた破片が手に食い込み、赤い雫を滲ませる。
「ううぅ……あああああああぁぁぁぁぁあっ!!!」
絶叫とも言える声を上げて、頭を打ちつける。
内側から響く、自分のものではない、あの場に居た〝誰か〟の想いが、自分が死を望む事を否定する。
お願いだから、止めて。この声とこの想いで、私を満たさないで。
私も、あの二人と一緒に逝かせて――そんな望みが込みあげても。
そんな願いを無視するかのように、自分の中に蠢く数多の渇望が、その欲望を許しはしなかった。
自分を活かす為に、望まず糧となったモノ達が決してそれは許さないと言う様に。
「……解った、解かったから……!もうその声を、止めて……!」
それでも声は止んでくれない声から逃げる様に、頭を抱え、耳を塞ぎ、狂った様に叫び声を上げる。
「ねえさまぁ……、ティーナぁ……、わたしだけ……っ、おいていかないでよぉ……っ」
もう誰も居ない。誰も知らない。帰れる場所も無い、戻れる場所もない。
あの二人は――もう、傍に、居ない。もう、何処にも居ない。
何時も取り囲んで居てくれた温もりがない。風が吹けば、透ける様に自分を薙いでいく。
どうしようも無い程に、凍えてしまうくらい酷く寒かった。
ぼろぼろと、頬から雫が零れ落ちていく。泣けば、泣く程に胸が苦しくて痛い。
嗚咽が止まらず、吐き出せば吐きだす程に、その悲しみは深くなる。
喘ぐように鳴き声をあげ、溺れるように意識を沈ませていく。
治癒は受けても、完全に復調したわけではないその身体は、そんな情動でも今は堪えてしまう。
やがて、少女は意識を途絶えさせた。
――暫くして、温かいものが額に触れて、目が覚める。
不安そうに覗きこむ顔、触れても良かったのだろうかという怖れを交えた、泣きそうになっている〝ティーナ〟の顔。
寂しさなのか、或は、悲しさなのか、何時もなら明るい少女の顔色はそんな色に染まっていた。
(あぁ、そう言えば――)
何故、そんな顔をしているのだろうと思いながらも、この少女も自分と同だと言う事に、少女は気が付く。
誰も居ない、誰も知ることのない、独りになってしまった。
形は違えど、同じ痛みを持っているのだ
もし、この少女が〝ティーナ〟である何かだとしても、それでも、この少女は自分を見つけ出し、助けに来てくれた。
共絶し、それを拒んでも、この少女は手を手繰り寄せようと伸ばし続けてくれた。
「……ごめんね、ティーナ。
――もう、大丈夫。私が、貴女の事を守るから。だから一緒に、生きよう?」
再び、その手を掴む。
あの時みたいに手を引かれ、誘われるままではなく、今度は自分自身が引っ張れるようにと力を込めて。
幸い、その手の差し出し方を、引っぱり方を、少女は教えられている。
――残された想いがあるなら、きっと、また歩き出せるから。
――それは、最初の記憶。
朧気ながらも、誰かの手の温もりで、眠りから揺り起こされた様な、穏やかな目覚めの記憶。
緑色の髪を持つ少女が、細い銀糸の髪の人形の様な少女の手を取りながら、先導するように歩いていた。
手を引かれるがままに、けれど、足取りはしっかりと。
其の少女へとついて行く。
辿りついた場所は、蒼い薔薇が咲き誇る庭園だった。
未だ不完全な心を持つ少女でも、その蒼に彩られた庭園がキレイな物だと言う事は理解ができたのか、ほんのりと表情を緩め、同じ色合いをした瞳を細めた。
『……ふふ、ごめんね。急で驚かせちゃった?』
その様子を見た、緑色の髪をした少女が朗らかに笑む様に表情をつくり、人形の少女の顔を覗き込む。
『……あ。来たんだね、リンネ』
その二人を出迎える様に、
「――?」
『あ、いけない。言い忘れちゃってた。
わたしはね、ティーナ。水原ティーナ。
……あなたが、わたしをまもってくれる、もう一人の〝きし〟の子なんだよね?』
『……あはは、ごめんね。まだ、リンネはよくわかってないし、自分が無いから。
――ほら、リンネも挨拶、しよう?』
『うん、もう一度、君たちの事を教えて?』
「……私。私の、名前は――」
『わたしは白妙楔奈。ティーナを守る、守護騎士の一人。此れからは、どうか末長く――ほら、リンネ?』
「……ぁ。はい。私の、名前は、白妙凛音、です。
あなたを、護る……守護騎士、です。よろしく、お願い……します」
『……うん。できたできた』
『ふふ。
……うん、君たちみたいな子が、わたしを守ってくれるなら、きっと怖くなさそう』
良かった、とにこやかに微笑むティーナに、楔奈も穏やかに笑みを浮かべる。
『さ、行こう、凛音。今日は、一杯つきあって貰うんだから。まずは、わたしとセツナが作った秘密基地に――』
案内した時と同じように手を取り、握り締める。
優しく、離させない様な強さを持ったティーナの手の温もり。
自然と、凛音の表情に〝笑み〟というものが浮かんだ。
自分ではまだ、其れが何を意味するか分からない程に淡い感情のイロ。
それが最初の、少女がヒトとしての灯かりが心に点いた、一番最初の記憶。
―――――――――――。
――――――――。
――――。
『うん、巧く撮れて良かった。
……ふふ、いい顔して笑ってるじゃない。始めての笑顔だね、凛音』
二人のやりとりを眺め、少し離れた場所でその写真を撮っていた楔奈は、嬉しげに笑みを浮かべる。
妹が始めて浮かべた笑顔で、それが、自分の愛する少女が与えたモノだと思えば、誇らしく思えたから。
最愛の二人が手を取り、笑い合う姿は、傷を持つ少女に取って心を奮い立たせるには十分な糧であった。
この写真は将来二人が大人になった時にでも見せて、からかってやろうと――悪戯気で、だけど幸福に満ちた笑顔で、撮れた物を眺め――庭園を走る二人の後を追いかけた。




ENo.505 日明と月夜 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
リンネ 「……天使さま。また、はぐれちゃいましたけども……?」 |
 |
天使様 「行きますよ、リンネ!」 |
ItemNo.6 パン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(11⇒12)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









武術LV を 3 DOWN。(LV15⇒12、+3CP、-3FP)
解析LV を 6 UP!(LV4⇒10、-6CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
ラフィ(132) とカードを交換しました!
鼠と竜のゲーム (ライトジャイアント)


ストライキング を研究しました!(深度0⇒1)
ストライキング を研究しました!(深度1⇒2)
ストライキング を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
エリアグラスプ を習得!
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!
追究 を習得!



ティーナ(709) に移動を委ねました。
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 N-15(草原)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 O-15(草原)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調9⇒8)
採集はできませんでした。
- ティーナ(709) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- スペイド(725) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |







星の十字教団
|
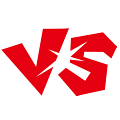 |
石☆油☆王
|


ENo.168
白妙 凛音



【名前】白妙凛音(しろたえ りんね)
【性別】女性
【年齢】17歳
【身長】170cm
【所属】星の十字教団・助祭 相良伊橋高校2年1組
ボランティア部員 兼 異能総合格闘部所属
生徒会役員・保健委員長
仄かに紫色を帯びた銀髪と、左右非対称の色の瞳を持つ、少し風変わりな女子。
世間一般では、星の十字教団の肩書シスター、実質は助祭の。一般では相良伊橋高校生の二年生として通している。
生真面目で、勤勉な性格。物静かというわけではないが、口数は控え目な部類。
幼い時からずっと一緒であり、家族よりも長い時を過ごした幼馴染であり、星の十字教団の教祖である、水原ティーナ(Eno709)には良くも悪くも振りまわされている。
余程じゃない限りは、年上は当然、年下相手にも丁寧な態度と接尾語を付ける。逆を言えば大抵の人に靡かず、平等に接する気質の持ち主。
――実際は、教祖を護衛する立場を持つ〝守護騎士〟。現代的に言えば、SPのような物。
教祖を守る事もさることながら、大聖堂の警護等も含まれており、実質は星の十字団の騎士団長の様なもの。
元々『守護騎士』の役割を受け持つ家柄に産まれた為、物心付く前から、如何なる状況や環境でも、対象を護り通す事が出来る様にと、あらゆる武芸と技術を、仕える物に対する献身の心を教えながら育てられた。
経緯上、武芸十八般を学んではいるが、特に剣術と体術に秀で、異能の使用を基本的には封じるという戦闘スタイルの事もあり、補うものとして魔術を自己習得している。
警戒心の薄く自己犠牲を平然と行う教祖に付いていることで、数々の修羅場と死線を潜り抜けてきているせいもあり、あまり物事に対して動じない胆力を持っているものの、自らにふりかかる危険に対してはやや鈍い傾向にある。
※同学園内部であれば、学生であること。
星の十字教団を内部を知っていたり、事情通であれば、教祖の守護騎士であること 。
上記であれば、認知フリーです。
※ロール上、教祖様(Eno709)の護衛等の為に、危害を加える場合はシスターが飛んできますのでご了承ください。
異能【Magnolia Pride】
盟約を結んだ対象が近くにいる場合、自身のステータスを大きく向上させる異能。
また、対象者へ害意(あらゆる状況を含む)を向けるモノが相対、若しくは、危機的状況における場合、更に著しく能力を上げる。
その対象が負傷などした場合、更に上乗せされる。
複数を対象には出来ず、一度盟約を結めば、切ることは出来ない、生涯一度きりの条件。これは、〝使用者〟の死亡以外では如何なるものでも切ることができない。
一度でも発動すれば、以降は永続的に効果を得る。能力は任意。範囲は大凡、一区画半程度。
また盟約が結ばれている場合、精神作用におけるもの、精神汚染に完全な耐性を付与される。
簡単に言ってしまえば、絆に依る力である。
サブ①
【名前】源 楔奈(みなもと せつな)
【性別】女性
【年齢】外見年齢10~12歳前後(17歳?)
【身長】140cm
【所属】-
白妙凛音の姉。十年程前の事故で死亡しているが、様々な因果が重なり、その場に留まっている。今は白妙姓を捨てて、源クリスと同じ姓を名乗っている。
現在は、最愛の少女であるクリスとのんびりとお屋敷暮しをしている。
※どちらも不穏など巻き込みは歓迎。大抵は食えます。
事前確認してもしないでもお気兼ねなく。
※平日は基本置きレス進行となっています。
【性別】女性
【年齢】17歳
【身長】170cm
【所属】星の十字教団・助祭 相良伊橋高校2年1組
ボランティア部員 兼 異能総合格闘部所属
生徒会役員・保健委員長
仄かに紫色を帯びた銀髪と、左右非対称の色の瞳を持つ、少し風変わりな女子。
世間一般では、星の十字教団の肩書シスター、実質は助祭の。一般では相良伊橋高校生の二年生として通している。
生真面目で、勤勉な性格。物静かというわけではないが、口数は控え目な部類。
幼い時からずっと一緒であり、家族よりも長い時を過ごした幼馴染であり、星の十字教団の教祖である、水原ティーナ(Eno709)には良くも悪くも振りまわされている。
余程じゃない限りは、年上は当然、年下相手にも丁寧な態度と接尾語を付ける。逆を言えば大抵の人に靡かず、平等に接する気質の持ち主。
――実際は、教祖を護衛する立場を持つ〝守護騎士〟。現代的に言えば、SPのような物。
教祖を守る事もさることながら、大聖堂の警護等も含まれており、実質は星の十字団の騎士団長の様なもの。
元々『守護騎士』の役割を受け持つ家柄に産まれた為、物心付く前から、如何なる状況や環境でも、対象を護り通す事が出来る様にと、あらゆる武芸と技術を、仕える物に対する献身の心を教えながら育てられた。
経緯上、武芸十八般を学んではいるが、特に剣術と体術に秀で、異能の使用を基本的には封じるという戦闘スタイルの事もあり、補うものとして魔術を自己習得している。
警戒心の薄く自己犠牲を平然と行う教祖に付いていることで、数々の修羅場と死線を潜り抜けてきているせいもあり、あまり物事に対して動じない胆力を持っているものの、自らにふりかかる危険に対してはやや鈍い傾向にある。
※同学園内部であれば、学生であること。
星の十字教団を内部を知っていたり、事情通であれば、教祖の守護騎士であること 。
上記であれば、認知フリーです。
※ロール上、教祖様(Eno709)の護衛等の為に、危害を加える場合はシスターが飛んできますのでご了承ください。
異能【Magnolia Pride】
盟約を結んだ対象が近くにいる場合、自身のステータスを大きく向上させる異能。
また、対象者へ害意(あらゆる状況を含む)を向けるモノが相対、若しくは、危機的状況における場合、更に著しく能力を上げる。
その対象が負傷などした場合、更に上乗せされる。
複数を対象には出来ず、一度盟約を結めば、切ることは出来ない、生涯一度きりの条件。これは、〝使用者〟の死亡以外では如何なるものでも切ることができない。
一度でも発動すれば、以降は永続的に効果を得る。能力は任意。範囲は大凡、一区画半程度。
また盟約が結ばれている場合、精神作用におけるもの、精神汚染に完全な耐性を付与される。
簡単に言ってしまえば、絆に依る力である。
サブ①
【名前】源 楔奈(みなもと せつな)
【性別】女性
【年齢】外見年齢10~12歳前後(17歳?)
【身長】140cm
【所属】-
白妙凛音の姉。十年程前の事故で死亡しているが、様々な因果が重なり、その場に留まっている。今は白妙姓を捨てて、源クリスと同じ姓を名乗っている。
現在は、最愛の少女であるクリスとのんびりとお屋敷暮しをしている。
※どちらも不穏など巻き込みは歓迎。大抵は食えます。
事前確認してもしないでもお気兼ねなく。
※平日は基本置きレス進行となっています。
8 / 30
239 PS
チナミ区
O-16
O-16





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 修道服 | 防具 | 36 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 木瓜 | 素材 | 15 | [武器]器用10(LV10)[防具]攻撃10(LV10)[装飾]攻撃10(LV10) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | 樹鉄の両手剣 | 武器 | 36 | 体力10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 戦乙女の星十字の首飾り | 装飾 | 54 | 活力10 | - | - | |
| 10 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]敏捷10(LV10)[効果2]復活10(LV10)[効果3]体力15(LV25) | |||
| 11 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 13 | 投擲用ダガー | 武器 | 39 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 14 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]火纏10(LV25)[防具]鎮痛10(LV15)[装飾]復活10(LV15) | |||
| 15 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]敏捷10(LV15)[防具]加速10(LV15)[装飾]貫撃10(LV15) | |||
| 16 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]器用10(LV10)[防具]活力10(LV10)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 12 | 身体/武器/物理 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 32 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 決3 | アルベァフート (エキサイト) | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| クローヌオルト (プロテクション) | 6 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| ツォルンフォート (スパイン) | 6 | 0 | 110 | 自:反撃LV増 | |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 90 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
| 決3 | シャイテルハウ (イレイザー) | 6 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| ホークアイ (テリトリー) | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |
| クイックアナライズ | 5 | 0 | 200 | 敵全:AG減 | |
| ロンゲンオルト (エスコート) | 5 | 0 | 80 | 自:次受ダメ減+味列:護衛 | |
| ウィークポイント | 5 | 0 | 140 | 敵:3連痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| コンセントレーション (器用) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| アクセラレータ (敏捷) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 御使いの加護 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 追究 | 5 | 1 | 0 | 【常時】自身のスキル研究によるスキルの弱化具合が増加 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ますみブロマイド (ブラスト) |
0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| 決3 |
お人形さん、おいで (ファイアボール) |
0 | 180 | 敵全:火撃 |
|
腐食の茨 (コロージョン) |
0 | 70 | 敵貫:腐食 | |
|
鼠と竜のゲーム (ライトジャイアント) |
0 | 200 | 自:AT増(5T)+領域値[光]3以上ならDF増(5T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 2 ]ブラックアサルト | [ 1 ]イレイザー |
| [ 3 ]ストライキング | [ 1 ]ウィークポイント | [ 2 ]シーアーチン |
| [ 2 ]アクアスピット |

PL / 青色