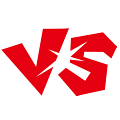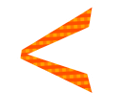<< 4:00>> 6:00




ずっと貴方を捜していました。
私はどこへも行けないけれど、貴方がどうしているかをいつも心にかけていました。
私に心なんてものはないはずだけれど、永い永い年月が私の上を過ぎ、いつしか私は貴方がた人間が心と呼ぶものに近いもの――たぶん人のそれより未成熟かつ不完全なものだけれど――を得ていたのです。
だから、私はずっと貴方を待っていました。村の入り口から少し奥まったこの場所で。
当時の私がいたのは、村の入り口に植えられた桜並木から少しばかり奥の方へ離れた場所でした。
奥といってもここは土壌も日当たりもよく、私は太く強い幹としなやかな枝、可憐な花々を纏う立派な大木へ成長することができました。私という器に満たされた力は溢れ、周囲の土地にもあまねく作用しました。季節ごとに美しく変化する村の入り口は、付近一帯の名所となりました。
道を往く人々は桜並木の美しさに目をとめ、足を止め、口々に美しさを讃えて通りすぎます。あまりに美しいので、桜並木の奥にもっとも素晴らしい木である私がいることに誰も気づかないのです。
私を気にとめる人は誰もいませんでした――貴方以外は。
貴方だけが、私に気づいてくれたのです。
子供の頃から好奇心でいっぱいだった貴方は、まるで子兎が跳ねるかのように私に近づいてきて、その大きな瞳をさらに大きくして感激してくれました。貴方は私を秘密の隠れ家にしました。そして私には、貴方の隠れ家であるという意識が生まれました。
花の季節でも、貴方は他の人すべてが褒め称える桜並木の美しさになんて鼻も引っかけず、両手いっぱいに本を抱えて真っ直ぐ私のところへ走ってきます。
「今日も隠してね!」
そう言って、私の太い幹の陰に腰を落ち着けると、日のある間中にすべて読んでしまえとばかりに本を読みふけるのです。頭上でこんなにも美しく咲く私の花に目もくれず。
私はただの桜の木でした。私には知識など何ひとつもありませんでしたが、貴方がしていることが、人から隠れる必要があり、もし見つかればたいへんな目に遭うのだということは貴方の態度から容易に知ることが出来ました。
私の生まれるにも満たなかった心は、貴方でいっぱいでした。
貴方は私に意味を与えてくれた。
貴方だけが私を必要としてくれる。
もし、貴方がいなくなることがあれば、私は……。
ソウオモッテイタノニ。
貴方から流れた血が地面を汚す。赤く、赤く。
目の前で壊されていく貴方に私は何もしてあげることができなかった。
貴方によって生まれはじめた心が初めて感じたのは、救いようのない悲しさだった。
知砂妃。――知砂妃!
名前を呼びたいのに呼ぶ喉がない。出せる声もない。その悲しさは今生まれようとする心を絶望的に歪めていく。
知砂妃。ちさき。チサキ。
私はただただ、音にならない声でその名を呼び続ける。
目を開ける。視界に広がるのは自室の天井。先ほどまでの、桜の下に横たわる少女の遺体ではない。
千崎は時折この幻覚に襲われるようになっていた。今のように夢の形を取る場合もあるし、日常のふとした瞬間に囚われることもある。クラスメイトから言われて気づいたのだが、道を渡っている時などに幻覚に陥れば拙いなとは思う。幸い、今のところ大事には至っていないが。
「なんやったんや……」
しかし、今見た夢は、既に形を失い崩れかけていた。千崎はいつもそうなのだ。夢を覚えていることが出来ない。
あの桜はこの前自分が咲かせた学校の木なんやろうか? それとも別の? そもそもそんなことはあったんだっけ?
意識をはっきりさせようと、冷蔵庫の中にあった、スーパーで買ったばかりのラムネの缶を開ける。
炭酸の強いラムネは涙の味がした。



ENo.380 高国 藤久 とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。












解析LV を 3 DOWN。(LV10⇒7、+3CP、-3FP)
付加LV を 1 DOWN。(LV1⇒0、+1CP、-1FP)
時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
響鳴LV を 1 UP!(LV4⇒5、-1CP)
装飾LV を 4 UP!(LV23⇒27、-4CP)
あき(1043) とカードを交換しました!
幸せの色 (ティンクルブレス)

ポーションラッシュ を研究しましたが既に最大深度でした。
イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ヘイスト を習得!
リジュヴェネイト を習得!
アレグロ を習得!
スナイプ を習得!
リゾルート を習得!



チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 R-3(沼地)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 R-4(沼地)に移動!(体調8⇒7)
チナミ区 S-4(沼地)に移動!(体調7⇒6)
採集はできませんでした。
- チサキ(1346) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(未開放のため無効)
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 が発生!
- チサキ(1346) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。





















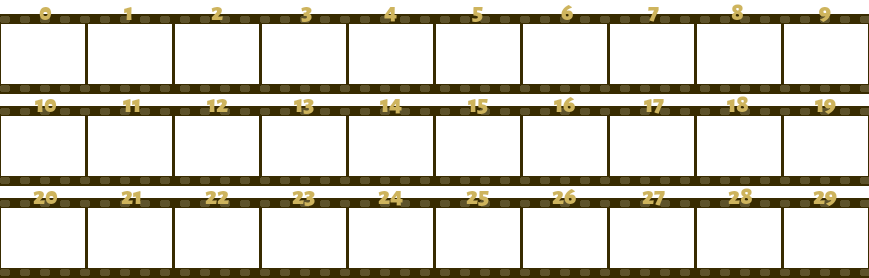





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



ずっと貴方を捜していました。
私はどこへも行けないけれど、貴方がどうしているかをいつも心にかけていました。
私に心なんてものはないはずだけれど、永い永い年月が私の上を過ぎ、いつしか私は貴方がた人間が心と呼ぶものに近いもの――たぶん人のそれより未成熟かつ不完全なものだけれど――を得ていたのです。
だから、私はずっと貴方を待っていました。村の入り口から少し奥まったこの場所で。
当時の私がいたのは、村の入り口に植えられた桜並木から少しばかり奥の方へ離れた場所でした。
奥といってもここは土壌も日当たりもよく、私は太く強い幹としなやかな枝、可憐な花々を纏う立派な大木へ成長することができました。私という器に満たされた力は溢れ、周囲の土地にもあまねく作用しました。季節ごとに美しく変化する村の入り口は、付近一帯の名所となりました。
道を往く人々は桜並木の美しさに目をとめ、足を止め、口々に美しさを讃えて通りすぎます。あまりに美しいので、桜並木の奥にもっとも素晴らしい木である私がいることに誰も気づかないのです。
私を気にとめる人は誰もいませんでした――貴方以外は。
貴方だけが、私に気づいてくれたのです。
子供の頃から好奇心でいっぱいだった貴方は、まるで子兎が跳ねるかのように私に近づいてきて、その大きな瞳をさらに大きくして感激してくれました。貴方は私を秘密の隠れ家にしました。そして私には、貴方の隠れ家であるという意識が生まれました。
花の季節でも、貴方は他の人すべてが褒め称える桜並木の美しさになんて鼻も引っかけず、両手いっぱいに本を抱えて真っ直ぐ私のところへ走ってきます。
「今日も隠してね!」
そう言って、私の太い幹の陰に腰を落ち着けると、日のある間中にすべて読んでしまえとばかりに本を読みふけるのです。頭上でこんなにも美しく咲く私の花に目もくれず。
私はただの桜の木でした。私には知識など何ひとつもありませんでしたが、貴方がしていることが、人から隠れる必要があり、もし見つかればたいへんな目に遭うのだということは貴方の態度から容易に知ることが出来ました。
私の生まれるにも満たなかった心は、貴方でいっぱいでした。
貴方は私に意味を与えてくれた。
貴方だけが私を必要としてくれる。
もし、貴方がいなくなることがあれば、私は……。
ソウオモッテイタノニ。
貴方から流れた血が地面を汚す。赤く、赤く。
目の前で壊されていく貴方に私は何もしてあげることができなかった。
貴方によって生まれはじめた心が初めて感じたのは、救いようのない悲しさだった。
知砂妃。――知砂妃!
名前を呼びたいのに呼ぶ喉がない。出せる声もない。その悲しさは今生まれようとする心を絶望的に歪めていく。
知砂妃。ちさき。チサキ。
私はただただ、音にならない声でその名を呼び続ける。
目を開ける。視界に広がるのは自室の天井。先ほどまでの、桜の下に横たわる少女の遺体ではない。
千崎は時折この幻覚に襲われるようになっていた。今のように夢の形を取る場合もあるし、日常のふとした瞬間に囚われることもある。クラスメイトから言われて気づいたのだが、道を渡っている時などに幻覚に陥れば拙いなとは思う。幸い、今のところ大事には至っていないが。
「なんやったんや……」
しかし、今見た夢は、既に形を失い崩れかけていた。千崎はいつもそうなのだ。夢を覚えていることが出来ない。
あの桜はこの前自分が咲かせた学校の木なんやろうか? それとも別の? そもそもそんなことはあったんだっけ?
意識をはっきりさせようと、冷蔵庫の中にあった、スーパーで買ったばかりのラムネの缶を開ける。
炭酸の強いラムネは涙の味がした。



ENo.380 高国 藤久 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。











解析LV を 3 DOWN。(LV10⇒7、+3CP、-3FP)
付加LV を 1 DOWN。(LV1⇒0、+1CP、-1FP)
時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
響鳴LV を 1 UP!(LV4⇒5、-1CP)
装飾LV を 4 UP!(LV23⇒27、-4CP)
あき(1043) とカードを交換しました!
幸せの色 (ティンクルブレス)

ポーションラッシュ を研究しましたが既に最大深度でした。
イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ヘイスト を習得!
リジュヴェネイト を習得!
アレグロ を習得!
スナイプ を習得!
リゾルート を習得!



チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調11⇒10)
チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 R-3(沼地)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 R-4(沼地)に移動!(体調8⇒7)
チナミ区 S-4(沼地)に移動!(体調7⇒6)
採集はできませんでした。
- チサキ(1346) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(未開放のため無効)
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 が発生!
- チサキ(1346) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |







チナミ区 P-3
瓦礫の山
瓦礫の山

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「懲りないですねぇ。何度来ようが一緒ですよ?」 |



ENo.1346
チサキ



「ウチは千崎良貴っていいます。
気軽にチサって呼んだってください。え、何でチサ、って?
そんなん『かわいいから』しか理由はありませんやん?」
千崎良貴(ちさきよしたか)
関西弁のようなしゃべり方をする男子高校生。身長173cm。
相良伊橋高校2年生。クラスは4組。途中で転校してきた。
可愛いものや甘いものが大好きという、男子高校生にしては一風変わった趣味嗜好の持ち主。
それを恥じることはなく「自分はこれが好きなんやからしゃあない」と公言している。
幼少期に父が事故死し、母に女手ひとつで育てられた。その母の再婚を機に家を出てイバラシティで一人暮らしをしている。
気楽に気軽に、気の向くままへらへら笑って生きているように見せかけているが、心配性で寂しがり屋の一面も。
最近は赤い色を見ると安らぐことと、時折「血まみれの桜の下で人が死んでいる」という幻覚を見ることに悩んでいる。
異能:『百花繚乱』(ブルーミング)
内容:『花を咲かせる』ことができる能力。
手元にある植物を瞬時に開花の状態まで成長させることができる。
種からでも、枝しかない状態でも行使可能。
加減を間違うと散らせてしまうが、散った花を再度咲かせることは不可能。
以上の経歴を偽る、血咲(チサキ)と呼ばれる怪異が彼の正体。
==========
血咲(チサキ)
「ウチは血咲。赤い花の咲くとこ見るんが大好きや。
アンタの花はどないな感じで『咲く』んやろう。
はよう見とうて仕方ないわ……」
上半身は女性、下半身は古木という姿を持つ怪異。
古木の怪異らしく花が好き。
対象の活性化を促す異能を持ち、その異能で血流の促進された相手の頭部が弾け飛ぶ様を「花」に例え、その花が『咲く』ところを見ることを何よりも好んでいる。
相手を死なせてもなお「自分はこれが好きなんやからしゃあない」と異能で赤い花を咲かせ続けたため、数多の犠牲者を出した後に《否定の世界》アンジニティへと追放された。
彼女は追放されてなお「好きなこと」を行い続けている。
異能:『散華誘起』(ブラステッド)
内容:対象を活性化させる
異能を適正範囲で利用すれば損傷部分の修復、停滞した流れの活発化など非常に有用な能力なのだが、過剰に使用した場合は活性化に堪えきれず対象を崩壊させてしまう。
千崎の『百花繚乱』は『散華誘起』を『花のみにしか使えない』と思い込んでいる状態である。
千崎のことは所詮夢だと思い込んでいたが、微妙に変化しはじめている模様。
==========
プロフィール絵は2種類。
千崎のプロフィール絵は相良伊橋高校さんの制服設定をお借りして作成しております。
ありがとうございます。
レスは思いつき次第お返ししております。
「関西弁の『ような』しゃべり方」をしているだけなので、多少おかしくても気にしない方向でひとつ。
深く考えずにノリと勢いで話しかけますので特に気にせずいただけたらなあと思います。
メッセ等ご自由にどうぞ。
ログまとめ用プレイス
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2172
バイト先(お店プレイス)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2691
アイコン20は「60*60のアイコン素材」様よりお借りしております。
http://campa.chips.jp/chara/alenka/icon/sozai/6060sozai.html
アイコン0と21は「十con」様よりお借りしております。
http://rainpark.sub.jp/palir/juccon.html
アイコン22~24は「らぬきの立ち絵保管庫」様よりお借りした画像を規約範囲内で加工し使用しております。
http://ranuking.ko-me.com/
千崎のカードイラストは宮沢原始人様(@urn_k)のコミッションにて作製頂いたものです。
血咲のTCG風カードイラストは@uta_vit999様に作成頂いたものです(イラスト部分はハレトキ自作)
この場ですが皆々様に御礼申し上げます。ありがとうございました。
設定置き場
http://hare-toki.rash.jp/teiki/
気軽にチサって呼んだってください。え、何でチサ、って?
そんなん『かわいいから』しか理由はありませんやん?」
千崎良貴(ちさきよしたか)
関西弁のようなしゃべり方をする男子高校生。身長173cm。
相良伊橋高校2年生。クラスは4組。途中で転校してきた。
可愛いものや甘いものが大好きという、男子高校生にしては一風変わった趣味嗜好の持ち主。
それを恥じることはなく「自分はこれが好きなんやからしゃあない」と公言している。
幼少期に父が事故死し、母に女手ひとつで育てられた。その母の再婚を機に家を出てイバラシティで一人暮らしをしている。
気楽に気軽に、気の向くままへらへら笑って生きているように見せかけているが、心配性で寂しがり屋の一面も。
最近は赤い色を見ると安らぐことと、時折「血まみれの桜の下で人が死んでいる」という幻覚を見ることに悩んでいる。
異能:『百花繚乱』(ブルーミング)
内容:『花を咲かせる』ことができる能力。
手元にある植物を瞬時に開花の状態まで成長させることができる。
種からでも、枝しかない状態でも行使可能。
加減を間違うと散らせてしまうが、散った花を再度咲かせることは不可能。
以上の経歴を偽る、血咲(チサキ)と呼ばれる怪異が彼の正体。
==========
血咲(チサキ)
「ウチは血咲。赤い花の咲くとこ見るんが大好きや。
アンタの花はどないな感じで『咲く』んやろう。
はよう見とうて仕方ないわ……」
上半身は女性、下半身は古木という姿を持つ怪異。
古木の怪異らしく花が好き。
対象の活性化を促す異能を持ち、その異能で血流の促進された相手の頭部が弾け飛ぶ様を「花」に例え、その花が『咲く』ところを見ることを何よりも好んでいる。
相手を死なせてもなお「自分はこれが好きなんやからしゃあない」と異能で赤い花を咲かせ続けたため、数多の犠牲者を出した後に《否定の世界》アンジニティへと追放された。
彼女は追放されてなお「好きなこと」を行い続けている。
異能:『散華誘起』(ブラステッド)
内容:対象を活性化させる
異能を適正範囲で利用すれば損傷部分の修復、停滞した流れの活発化など非常に有用な能力なのだが、過剰に使用した場合は活性化に堪えきれず対象を崩壊させてしまう。
千崎の『百花繚乱』は『散華誘起』を『花のみにしか使えない』と思い込んでいる状態である。
千崎のことは所詮夢だと思い込んでいたが、微妙に変化しはじめている模様。
==========
プロフィール絵は2種類。
千崎のプロフィール絵は相良伊橋高校さんの制服設定をお借りして作成しております。
ありがとうございます。
レスは思いつき次第お返ししております。
「関西弁の『ような』しゃべり方」をしているだけなので、多少おかしくても気にしない方向でひとつ。
深く考えずにノリと勢いで話しかけますので特に気にせずいただけたらなあと思います。
メッセ等ご自由にどうぞ。
ログまとめ用プレイス
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2172
バイト先(お店プレイス)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2691
アイコン20は「60*60のアイコン素材」様よりお借りしております。
http://campa.chips.jp/chara/alenka/icon/sozai/6060sozai.html
アイコン0と21は「十con」様よりお借りしております。
http://rainpark.sub.jp/palir/juccon.html
アイコン22~24は「らぬきの立ち絵保管庫」様よりお借りした画像を規約範囲内で加工し使用しております。
http://ranuking.ko-me.com/
千崎のカードイラストは宮沢原始人様(@urn_k)のコミッションにて作製頂いたものです。
血咲のTCG風カードイラストは@uta_vit999様に作成頂いたものです(イラスト部分はハレトキ自作)
この場ですが皆々様に御礼申し上げます。ありがとうございました。
設定置き場
http://hare-toki.rash.jp/teiki/
6 / 30
281 PS
チナミ区
S-4
S-4





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 象牙の櫛 | 武器 | 15 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 血染め桜の花簪 | 装飾 | 25 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||
| 9 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]魅了10(LV20)[防具]幸運10(LV10)[装飾]守護10(LV20) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 11 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 12 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 13 | 腐木 | 素材 | 15 | [武器]腐食15(LV25)[防具]反腐15(LV30)[装飾]舞腐15(LV30) | |||
| 14 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]敏捷10(LV15)[防具]加速10(LV15)[装飾]貫撃10(LV15) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 自然 | 15 | 植物/鉱物/地 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 解析 | 7 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 5 | 武器作製に影響 |
| 装飾 | 27 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ストーンブラスト | 6 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| リジュヴェネイト | 5 | 0 | 60 | 味腐:HP増+衰弱・腐食を祝福化 | |
| アレグロ | 5 | 0 | 20 | 敵:風撃&自:連続増 | |
| スナイプ | 5 | 0 | 60 | 自:DX増(3T) | |
| アニマート | 5 | 0 | 120 | 味全:AT増(2T) | |
| トランキュリティ | 5 | 0 | 60 | 味環:HP増&環境変調減 | |
| リゾルート | 5 | 0 | 60 | 敵:精確攻撃 | |
| クラック | 6 | 0 | 160 | 敵全:地撃&次与ダメ減 | |
| クイックアナライズ | 5 | 0 | 200 | 敵全:AG減 | |
| イバラ | 5 | 0 | 120 | 敵3:精確地痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 7 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
<【火宿】炎蔦の白蟒蛇> (ピンポイント) |
0 | 20 | 敵:痛撃 | |
|
双頭の鷲 (サモン:ナレハテ) |
0 | 200 | 自:ナレハテ召喚 | |
|
(ここに素敵なカード名が入る) (クリエイト:タライ) |
0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
|
46&2 (シャドウラーカー) |
0 | 160 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
|
幸せの色 (ティンクルブレス) |
0 | 140 | 味列:祝福 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]クリエイト:タライ | [ 1 ]ストレングス |
| [ 1 ]クリエイト:シリンジ | [ 2 ]ストライキング | [ 1 ]スネアトラップ |
| [ 1 ]イバラ | [ 3 ]ポーションラッシュ |

PL / ハレトキ