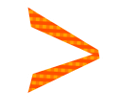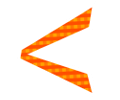<< 3:00>> 5:00




俺の能力――羽柴に"スキンウォーカーと"名付けられた異能は生まれついてのものだった。
それでも、最初は耳とか尻尾が生えてくるとか。その程度の変化で済んでいた。
羽柴によれば、異能が俺の意識とは無関係に発動する条件は《ストレス》だ。
急激なストレスを感じると、程度を問わず自分の意図しない形で能力が発動してしまう。
俺はずっと《激怒する》ことによって発動すると思っていたが、怒りもある種ストレスだ。
それでもいつだって、俺の暴走は《怒り》から引き起こされていた。
「お前は自分が思っている以上に繊細だ。これは短気ってのとは違う」
羽柴は相変わらず、校内でサボる俺を見つけては話をしにきた。
いつしか追い払うのも面倒になるくらい、羽柴と話す時間は長くなっていった。
「他者、特に弱いものへ感情移入しやすい。だから”あの日”も暴走しちまったんだろうな」
俺は小さく唇を噛みしめる。
―――あの日。
俺は怒りによって文字通り、我を忘れてしまった。
そして思い出す、こうなる前のあいつとの思い出を。
◆ ◆ ◆
俺はお世辞にも真面目な生徒とは言えなかった。
授業はサボるし、自他校問わず喧嘩ばかりしていたから教師からは問題児扱いをされていた。
とはいえ俺は売られた喧嘩を買っていただけで、どんな奴でも手を出されない限り自分から殴ったりはしなかった。
どんなに不利でも絶対勝とうとするのは、二度と喧嘩を売られないためだ。
それでも噂は広がるし、俺がそんな事考えて喧嘩してるなんて思ってる奴は誰もいない。
絶えない生傷と、尾ひれが大きくなっていく噂話で、俺は学校からは孤立していた。
そんな俺にも、《鳴海》という名前の、友人と呼べるクラスメイトが一人だけいた。
俺の友人というには見た目も性格も、あまりにも大人しくて、気の小さい奴だった。
つるむようになったきっかけは些細なことだった。
中学三年に上がった頃。
学校に向かう近道に路地裏を歩いていた途中、嗅ぎ慣れた臭いに俺の足が止まった。
(血の、におい)
次いで聞こえくる悲鳴にも似た誰かの謝る声。複数人の怒号。
ここまで揃えばこの先に見える状況は、嫌でもわかる。
「邪魔なんだけど」
見えたのは三人の男――二人は見た目が派手な痩男で、もう一人は明らかに体格もでかい坊主頭――と、地面にうずくまる男だった。
三人組の方は着ている制服から、近所の有名な不良校の高校生だとわかった。
普段はこんな朝からいるような連中ではないのに、ツイてない。
うずくまっている方については、俺と同じ制服を着ているが、知り合いかはわからない。
「ンだよ。今取り込み中だ、あっち行ってな」
喋った瞬間息とともに漂ってくる酒の臭い。今日は月曜。
恐らく日曜から朝まで飲み明かした帰りだと悟る。
「俺だって学校行く途中なんだ、そっちがどけよ」
構わず先を行こうとすると、不良の一人が俺に大股で歩み寄り、壁のように立ち塞がった。
「調子ノってんなよ、ガキ。お前もこうなりたいワケ?」
言うなり足下の男を、道端の小石を蹴るのと同じように足で転がす。
そいつもそいつで本当に石みたいに固くなっていて、微動だにしない。
「おーい、生きてっか」
見下ろしてくる不良の視線に構わず、声を掛ける。
かろうじて持ち上げられた顔は赤と紫のまだら色になっていたが、やはり知らない顔だった。
とはいえこわごわ動かされた口元は、確実に「たすけて」と言っていた。
「ほら行くぞ、立てるか」
不良を肩で押しのけるようにして、ボロボロになったそいつを立たせようと手を伸ばそうとしたところだった。
右肩を強く掴まれ、振り返る。さっき立ちはだかった不良が舌打ちと共に俺を睨んでいた。
「もういいだろ、こんだけボコボコにすりゃあ。離せよ」
「余裕こいてンじゃねえぞ、中坊が。殴られねーと立場がわかんないみたいだな」
「悪ィけど俺、無抵抗の人間殴るような趣味ないから」
「うぜぇな、死んどけよ」
振るわれた拳を露骨に顔面に食らい、文字通り吹っ飛ばされる。
残りの不良二人の歓声と、地面に転がったままの男が小さく声を上げる。
殴ってきた相手はそのままこちらへ向かって来ると、起き上がろうとついた俺の手をゆっくりと踏んできた。
「ははっ、大丈夫かぁ?さっきの威勢の良さはどこいったんだよクソガキ!」
手を踏みつけていた足が今度は腹に向かって振りかぶられ――俺の手がその足蹴を止める。
「わかった」
「はぁ?」
素っ頓狂な声を上げる男を俺は見上げ、相手の足を持ったまま腕を大きく振り上げた。
鈍い音とともに、バランスを崩した男がコンクリートの地面にすっ転ぶ。
静かに息を吐きながら、俺は立ち上がる。倒れたままの不良を、今度は俺が見下ろす。
「……殴ったってことは、殴られてもいいってことだよな」
一歩、俺は不良へ歩み寄る。
「クッソ、テメェふざけたこと…」
「言ったろ。俺は”無抵抗の人間”を殴る趣味はない」
もう一歩。
「だから、アンタは別だ」
「ご、ごめんな…!大丈夫か?血、血が…」
開口一番、そいつは俺に言った。
俺はといえば肩で息をしながら鼻や頭から血を流し、そいつも右目は腫れて唇が切れていた。
怪我の具合で言ったらどっこいなのだが。
「あ?いや、別に。慣れてるし」
「慣れてるって……でも、ありがと。マジで死ぬかと思った…三対一でよく勝てたな…」
「まあ腕っぷし強いのアイツ一人だけだったし。他の二人は騒いでただけで大したことなかったけど」
俺の言葉に苦笑いを浮かべるも、切れた唇が傷んだのかすぐに顔を歪めた。
多分怪我は顔だけじゃないだろう。さっきから立っているのもやっとな状態に見える。
「何したらそこまでボコられんだよ」
「……いや、何も…すれ違う時ちょっとぶつかってきただけで。
ていうかぶつかってきたの向こうなんだけどさ」
酒臭かったし、多分酔いが覚めてなかったんだろう。
そこまで考えて遠くからチャイムの音が響いてきた。
「あっ!遅刻…っ」
音に反応して身を乗り出した男の手を掴んで制す。
「いやいや、無理だって。こんだけやられてりゃ、遅刻の理由には十分だろ」
俺の言葉に少々戸惑った表情を見せるも、納得したのか掴まれていた手を力なく下ろす。
「お前東中だろ?一年?」
「いや、今年で三年。変な時期だけど、転校生で…」
「なんだ、タメじゃん。俺も東中」
「えっ?あ、そうなんだ。体大きいし喧嘩強いから高校生かと思った…」
ようやく安心したのか大きく息を吐くと、小さく笑って俺と目を合わせる。
「俺、鳴海。幸田鳴海…ありがとな、助けてくれて」
「……獅堂、美和」
「美和…あの、早速だけど学校まで一緒に来てもらえると嬉しいんだけど…そもそもここに来たのも迷ってたからでさ…」
「んだそれ…いいけど正門までな」
「えっ、なんで」
「俺と二人で、しかもこんな状態で登校すんの見られたら、あとあと面倒になんだよ。それと俺と会ったこと、誰にも言うなよ」
念を押すように鳴海の眼前に人差し指を向けると、こくこくと小さく頷かれた。
これが、最初。
“あの日”が起きるまでの、最初の話。



ENo.170 雷蔵 とのやりとり

以下の相手に送信しました




カオル(217) から 何かの殻 を手渡しされました。









ミツ(140) は 孔雀石 を入手!
カオル(217) は 孔雀石 を入手!
美和(568) は 孔雀石 を入手!
サナエ(928) は 平石 を入手!
サナエ(928) は ボロ布 を入手!
ミツ(140) は ボロ布 を入手!
カオル(217) は 何か固い物体 を入手!
ミツ(140) は 何か固い物体 を入手!
ミツ(140) は 楔石 を入手!



サナエ(928) に ItemNo.8 ねばねば を送付しました。
サナエ(928) から 甲殻 を受け取りました。
解析LV を 4 UP!(LV5⇒9、-4CP)
付加LV を 4 UP!(LV20⇒24、-4CP)
ItemNo.1 ピアス に ItemNo.3 アルミ缶 を合成実験し、どうでもよさげな物体 に変化することが判明しました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
ItemNo.1 ピアス に ItemNo.10 孔雀石 を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
雷蔵(170) の持つ ItemNo.1 指ぬきグローブ に ItemNo.3 孔雀石 を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
カオル(217) により ItemNo.8 甲殻 から装飾『カーキ色のズボン』を作製してもらいました!
⇒ カーキ色のズボン/装飾:強さ58/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-
サナエ(928) により ItemNo.3 アルミ缶 から射程1の武器『獣爪』を作製してもらいました!
⇒ 獣爪/武器:強さ58/[効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】
アキジ(1129) により ItemNo.2 何かの殻 から防具『赤い毛皮』を作製してもらいました!
⇒ 赤い毛皮/防具:強さ58/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-
雷蔵(170) により ItemNo.2 赤い毛皮 に ItemNo.4 どうでもよさげな物体 を付加してもらいました!
⇒ 赤い毛皮/防具:強さ58/[効果1]幸運10 [効果2]治癒10 [効果3]-
リンカ(855) とカードを交換しました!
ゴキゲンな音楽データ (バトルソング)

スニークアタック を研究しました!(深度0⇒1)
スニークアタック を研究しました!(深度1⇒2)
スニークアタック を研究しました!(深度2⇒3)



ミツ(140) に移動を委ねました。
チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



俺の能力――羽柴に"スキンウォーカーと"名付けられた異能は生まれついてのものだった。
それでも、最初は耳とか尻尾が生えてくるとか。その程度の変化で済んでいた。
羽柴によれば、異能が俺の意識とは無関係に発動する条件は《ストレス》だ。
急激なストレスを感じると、程度を問わず自分の意図しない形で能力が発動してしまう。
俺はずっと《激怒する》ことによって発動すると思っていたが、怒りもある種ストレスだ。
それでもいつだって、俺の暴走は《怒り》から引き起こされていた。
「お前は自分が思っている以上に繊細だ。これは短気ってのとは違う」
羽柴は相変わらず、校内でサボる俺を見つけては話をしにきた。
いつしか追い払うのも面倒になるくらい、羽柴と話す時間は長くなっていった。
「他者、特に弱いものへ感情移入しやすい。だから”あの日”も暴走しちまったんだろうな」
俺は小さく唇を噛みしめる。
―――あの日。
俺は怒りによって文字通り、我を忘れてしまった。
そして思い出す、こうなる前のあいつとの思い出を。
◆ ◆ ◆
俺はお世辞にも真面目な生徒とは言えなかった。
授業はサボるし、自他校問わず喧嘩ばかりしていたから教師からは問題児扱いをされていた。
とはいえ俺は売られた喧嘩を買っていただけで、どんな奴でも手を出されない限り自分から殴ったりはしなかった。
どんなに不利でも絶対勝とうとするのは、二度と喧嘩を売られないためだ。
それでも噂は広がるし、俺がそんな事考えて喧嘩してるなんて思ってる奴は誰もいない。
絶えない生傷と、尾ひれが大きくなっていく噂話で、俺は学校からは孤立していた。
そんな俺にも、《鳴海》という名前の、友人と呼べるクラスメイトが一人だけいた。
俺の友人というには見た目も性格も、あまりにも大人しくて、気の小さい奴だった。
つるむようになったきっかけは些細なことだった。
中学三年に上がった頃。
学校に向かう近道に路地裏を歩いていた途中、嗅ぎ慣れた臭いに俺の足が止まった。
(血の、におい)
次いで聞こえくる悲鳴にも似た誰かの謝る声。複数人の怒号。
ここまで揃えばこの先に見える状況は、嫌でもわかる。
「邪魔なんだけど」
見えたのは三人の男――二人は見た目が派手な痩男で、もう一人は明らかに体格もでかい坊主頭――と、地面にうずくまる男だった。
三人組の方は着ている制服から、近所の有名な不良校の高校生だとわかった。
普段はこんな朝からいるような連中ではないのに、ツイてない。
うずくまっている方については、俺と同じ制服を着ているが、知り合いかはわからない。
「ンだよ。今取り込み中だ、あっち行ってな」
喋った瞬間息とともに漂ってくる酒の臭い。今日は月曜。
恐らく日曜から朝まで飲み明かした帰りだと悟る。
「俺だって学校行く途中なんだ、そっちがどけよ」
構わず先を行こうとすると、不良の一人が俺に大股で歩み寄り、壁のように立ち塞がった。
「調子ノってんなよ、ガキ。お前もこうなりたいワケ?」
言うなり足下の男を、道端の小石を蹴るのと同じように足で転がす。
そいつもそいつで本当に石みたいに固くなっていて、微動だにしない。
「おーい、生きてっか」
見下ろしてくる不良の視線に構わず、声を掛ける。
かろうじて持ち上げられた顔は赤と紫のまだら色になっていたが、やはり知らない顔だった。
とはいえこわごわ動かされた口元は、確実に「たすけて」と言っていた。
「ほら行くぞ、立てるか」
不良を肩で押しのけるようにして、ボロボロになったそいつを立たせようと手を伸ばそうとしたところだった。
右肩を強く掴まれ、振り返る。さっき立ちはだかった不良が舌打ちと共に俺を睨んでいた。
「もういいだろ、こんだけボコボコにすりゃあ。離せよ」
「余裕こいてンじゃねえぞ、中坊が。殴られねーと立場がわかんないみたいだな」
「悪ィけど俺、無抵抗の人間殴るような趣味ないから」
「うぜぇな、死んどけよ」
振るわれた拳を露骨に顔面に食らい、文字通り吹っ飛ばされる。
残りの不良二人の歓声と、地面に転がったままの男が小さく声を上げる。
殴ってきた相手はそのままこちらへ向かって来ると、起き上がろうとついた俺の手をゆっくりと踏んできた。
「ははっ、大丈夫かぁ?さっきの威勢の良さはどこいったんだよクソガキ!」
手を踏みつけていた足が今度は腹に向かって振りかぶられ――俺の手がその足蹴を止める。
「わかった」
「はぁ?」
素っ頓狂な声を上げる男を俺は見上げ、相手の足を持ったまま腕を大きく振り上げた。
鈍い音とともに、バランスを崩した男がコンクリートの地面にすっ転ぶ。
静かに息を吐きながら、俺は立ち上がる。倒れたままの不良を、今度は俺が見下ろす。
「……殴ったってことは、殴られてもいいってことだよな」
一歩、俺は不良へ歩み寄る。
「クッソ、テメェふざけたこと…」
「言ったろ。俺は”無抵抗の人間”を殴る趣味はない」
もう一歩。
「だから、アンタは別だ」
「ご、ごめんな…!大丈夫か?血、血が…」
開口一番、そいつは俺に言った。
俺はといえば肩で息をしながら鼻や頭から血を流し、そいつも右目は腫れて唇が切れていた。
怪我の具合で言ったらどっこいなのだが。
「あ?いや、別に。慣れてるし」
「慣れてるって……でも、ありがと。マジで死ぬかと思った…三対一でよく勝てたな…」
「まあ腕っぷし強いのアイツ一人だけだったし。他の二人は騒いでただけで大したことなかったけど」
俺の言葉に苦笑いを浮かべるも、切れた唇が傷んだのかすぐに顔を歪めた。
多分怪我は顔だけじゃないだろう。さっきから立っているのもやっとな状態に見える。
「何したらそこまでボコられんだよ」
「……いや、何も…すれ違う時ちょっとぶつかってきただけで。
ていうかぶつかってきたの向こうなんだけどさ」
酒臭かったし、多分酔いが覚めてなかったんだろう。
そこまで考えて遠くからチャイムの音が響いてきた。
「あっ!遅刻…っ」
音に反応して身を乗り出した男の手を掴んで制す。
「いやいや、無理だって。こんだけやられてりゃ、遅刻の理由には十分だろ」
俺の言葉に少々戸惑った表情を見せるも、納得したのか掴まれていた手を力なく下ろす。
「お前東中だろ?一年?」
「いや、今年で三年。変な時期だけど、転校生で…」
「なんだ、タメじゃん。俺も東中」
「えっ?あ、そうなんだ。体大きいし喧嘩強いから高校生かと思った…」
ようやく安心したのか大きく息を吐くと、小さく笑って俺と目を合わせる。
「俺、鳴海。幸田鳴海…ありがとな、助けてくれて」
「……獅堂、美和」
「美和…あの、早速だけど学校まで一緒に来てもらえると嬉しいんだけど…そもそもここに来たのも迷ってたからでさ…」
「んだそれ…いいけど正門までな」
「えっ、なんで」
「俺と二人で、しかもこんな状態で登校すんの見られたら、あとあと面倒になんだよ。それと俺と会ったこと、誰にも言うなよ」
念を押すように鳴海の眼前に人差し指を向けると、こくこくと小さく頷かれた。
これが、最初。
“あの日”が起きるまでの、最初の話。



ENo.170 雷蔵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
「ん、」 こてんと首が傾く。“みか”を指差しながら。 「こいつ、さすがにイバラシティではもうちょいちいさいぞ。 こんな無駄にバカでかくなったのはやっぱハザマだからかなー? あ、こいつ、一応こっちの言ってることはわかってるみたいだから大丈夫」 |
 |
「殺し合えって言われても困るけど、侵略行為なのにポイント制も確かに変わった試みだよね。 僕たちが盤上の駒みたいな感じで、あまり気分は良くないなぁ」 |
カオル(217) から 何かの殻 を手渡しされました。
 |
「僕にはなんの殻だか検討つかないなぁ。 あ、食べ物じゃないからね?食べてはいけないよ?」 |





chimeRa
|
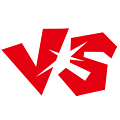 |
星の十字教団
|



ミツ(140) は 孔雀石 を入手!
カオル(217) は 孔雀石 を入手!
美和(568) は 孔雀石 を入手!
サナエ(928) は 平石 を入手!
サナエ(928) は ボロ布 を入手!
ミツ(140) は ボロ布 を入手!
カオル(217) は 何か固い物体 を入手!
ミツ(140) は 何か固い物体 を入手!
ミツ(140) は 楔石 を入手!



サナエ(928) に ItemNo.8 ねばねば を送付しました。
サナエ(928) から 甲殻 を受け取りました。
解析LV を 4 UP!(LV5⇒9、-4CP)
付加LV を 4 UP!(LV20⇒24、-4CP)
ItemNo.1 ピアス に ItemNo.3 アルミ缶 を合成実験し、どうでもよさげな物体 に変化することが判明しました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
ItemNo.1 ピアス に ItemNo.10 孔雀石 を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
雷蔵(170) の持つ ItemNo.1 指ぬきグローブ に ItemNo.3 孔雀石 を合成実験しようとしましたが、LVが足りないようです。
カオル(217) により ItemNo.8 甲殻 から装飾『カーキ色のズボン』を作製してもらいました!
⇒ カーキ色のズボン/装飾:強さ58/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-
 |
「犬は太腿が太いから特注サイズだ!一人で履けなかったらいつでも手伝うよ!」 |
サナエ(928) により ItemNo.3 アルミ缶 から射程1の武器『獣爪』を作製してもらいました!
⇒ 獣爪/武器:強さ58/[効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】
アキジ(1129) により ItemNo.2 何かの殻 から防具『赤い毛皮』を作製してもらいました!
⇒ 赤い毛皮/防具:強さ58/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-
雷蔵(170) により ItemNo.2 赤い毛皮 に ItemNo.4 どうでもよさげな物体 を付加してもらいました!
⇒ 赤い毛皮/防具:強さ58/[効果1]幸運10 [効果2]治癒10 [効果3]-
リンカ(855) とカードを交換しました!
ゴキゲンな音楽データ (バトルソング)

スニークアタック を研究しました!(深度0⇒1)
スニークアタック を研究しました!(深度1⇒2)
スニークアタック を研究しました!(深度2⇒3)



ミツ(140) に移動を委ねました。
チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――







chimeRa
|
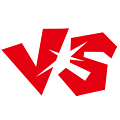 |
石☆油☆王
|


ENo.568
獅童 美和



獅童美和(シドウ ミカズ)
175cm/16歳/男
地方出身のヤンキー。とある事情によりイバラシティへ引っ越してきた。
マガサ区にある轟木工業高校へ進学。父と2人暮らし。
好きなものはメンチカツと豚骨ラーメンと乳酸飲料。軽度の喫煙者。
短気で無愛想だが、気を許した相手にはかまってちゃんになる傾向がある。
近くに住んでいる従姉である沙和子によく世話になっており、バーガーショップで一緒にバイト中。
喧嘩っ早く口が悪いが、仲間思いでやたらつるみたがる。
素直でないとこはあるが、すぐ顔にでたりとわかりやすい。ただ笑うことはない。頭はあまりよくないが、無駄に運動神経がいい脳筋。
すぐ手が出るため、喧嘩も多く生傷が絶えない。
能力については中学生頃に発動。まだ使いこなせていない。
≪スキンウォーカー≫
動物の能力を使用したり、動物に変身する能力。
变化する度合いや能力についてはある程度調節が可能だが、まだ完全にコントロールできていない部分があるため、急激な感情の変化(驚き、激怒など)によっては、無意識に一部が獣化したりすることもある(耳が飛び出したり、牙・爪が生えるなど)
ログまとめ:http://lisge.com/ib/talk.php?dt_s=562&dt_kz=12&dt_st=49
175cm/16歳/男
地方出身のヤンキー。とある事情によりイバラシティへ引っ越してきた。
マガサ区にある轟木工業高校へ進学。父と2人暮らし。
好きなものはメンチカツと豚骨ラーメンと乳酸飲料。軽度の喫煙者。
短気で無愛想だが、気を許した相手にはかまってちゃんになる傾向がある。
近くに住んでいる従姉である沙和子によく世話になっており、バーガーショップで一緒にバイト中。
喧嘩っ早く口が悪いが、仲間思いでやたらつるみたがる。
素直でないとこはあるが、すぐ顔にでたりとわかりやすい。ただ笑うことはない。頭はあまりよくないが、無駄に運動神経がいい脳筋。
すぐ手が出るため、喧嘩も多く生傷が絶えない。
能力については中学生頃に発動。まだ使いこなせていない。
≪スキンウォーカー≫
動物の能力を使用したり、動物に変身する能力。
变化する度合いや能力についてはある程度調節が可能だが、まだ完全にコントロールできていない部分があるため、急激な感情の変化(驚き、激怒など)によっては、無意識に一部が獣化したりすることもある(耳が飛び出したり、牙・爪が生えるなど)
ログまとめ:http://lisge.com/ib/talk.php?dt_s=562&dt_kz=12&dt_st=49
15 / 30
249 PS
チナミ区
K-14
K-14





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | ピアス | 武器 | 33 | 器用10 | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 赤い毛皮 | 防具 | 58 | 幸運10 | 治癒10 | - | |
| 3 | 獣爪 | 武器 | 58 | - | - | - | 【射程1】 |
| 4 | |||||||
| 5 | 怒り爪 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 貝柱だしの海鮮塩ラーメン | 料理 | 33 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | カーキ色のズボン | 装飾 | 58 | 活力10 | - | - | |
| 9 | 犬牙 | 武器 | 36 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 10 | 孔雀石 | 素材 | 20 | [武器]猛毒10(LV15)[防具]反毒10(LV15)[装飾]耐災10(LV15) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 解析 | 9 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 24 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 合成 | 5 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 決3 | エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| クラッシュ | 5 | 0 | 80 | 敵列:地撃 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 80 | 自:DF増(2T) | |
| アキュラシィ | 6 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 | |
| ロックスティング | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃 | |
| トランキュリティ | 5 | 0 | 60 | 味環:HP増&環境変調減 | |
| アドバンテージ | 5 | 0 | 80 | 敵:攻撃&AT奪取 | |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】[スキル使用設定不要]生産行動『効果付加』時、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
狙い撃ち (ピンポイント) |
0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 決3 |
かちわり (イレイザー) |
0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
|
Armed (ストレングス) |
0 | 100 | 自:AT増 | |
|
ゴキゲンな音楽データ (バトルソング) |
0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]ペネトレイト | [ 3 ]ヒールハーブ |
| [ 1 ]パワフルヒール | [ 3 ]チャージ | [ 3 ]スニークアタック |

PL / るか