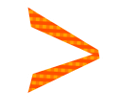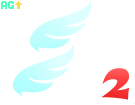<< 3:00>> 5:00




渡辺慧の場合 2/2
「君がそうしたいんならそうすれば? ただ、今一つ分からないんだけど……、君、別にその役割に俺を宛がう必要はないだろ。自分で出来るんだろ、君は。なぁ、……なんで俺を」
余計な文言が混じる。こんなこと言うつもりはなかった。言う必要もなかった。
何かが変わり始めている。厭な予感だ。
「では。『そうしたい』ので、『そうします』ね。……きみは独り立ちができねー性質でしょうから。これはヤエのお節介です。でも、ヤエは『そうしたい』ですので。……では渡辺慧。あーんしてください。ヤエに」
「……わかった、わかったから。俺の負けだよ、勘弁してくれよ。自由でいさせてくれよ、これで勝手に心が離れてくれよ、どんだけ自我が強いんだ、馬鹿かよ。例え俺が『そう』すればって言ったって、『そう』見ない事ぐらい分かってんだろ。何がお節介だよ」
“だって”この女はこうでも言わなければ、こう言ったところで、“本当に”やる。
どうしてそれを知ってしまった。知らないままでよかったのだ。
「嫌だって、ちゃんと言えんじゃねーですか。きみのほうこそどれだけ強情なんですか。……わかってるなら、はじめから。全て『こう』しておけばよかったんですよ。……アドバイスじゃあねーですけども。嫌なことは、嫌だと言わねかったら損しますよ。要らないことに巻き込んで、きみの足を引っ張ることでしょう。それを、『別に構わない』みたいな顔してたら……そのうち、もっと悪いことに足をとられます。きみは、ちっともそれがわかってねんですよ」
「『それ』でいいつもりだよ。それでいいつもり……だったんだけどな。いや、そうだよ。……『それ』が崩れるより、悪い事なんかない。俺が崩れてしまうより、悪い事なんかない。……なんか食うか?」
「コーラおかわりあります? 口の中ベッタベタなんですよね。……正直になった気分はどうです? ヤエは、たいそう気分がいいですけど」
「……厭な問いだな。どう答えたって、最悪だ。厭な奴だ、君はさ。……ちょっと待ってて。お茶位しかないと思うけど」
疲弊から、撫で下がった肩を揺らし、台所へ歩く。お湯はわかしてある。急須だってある。
ないのは、今、これを打破できる言葉だ。一方的に、背中からかけられるこえを、中空に放る術を今や失っている。精一杯の抵抗として、顔を向ける事はしない。
「お茶でもいいですよ。何だってヤエは構いません。そう、最悪ならよかったじゃねーですか。厭な奴だと言われても、ヤエにはきみが必要だったのですから。きみにはヤエは必要ねかったみてーですけどね」
「一方的に話させるだけ話させて、そして、俺もそれでいい。その上でこうするなら……、いや。君は『話せる』のか。……最悪だ。その必要ってのが、誰かの代わりじゃねえ事を祈りでもしてあげるよ。どっちでもいいけどさ。なんでもいいさ。どうでもいい」
「話せますよ。話せたうえで、ヤエはこうしているだけです。だから、渡辺慧が『望むのであれば』、ヤエはなんだって話してあげましょう。……きみのその『どうでもいい』、とっくに意味がないこと、ご存知なんでしょう?」
「るさい。厭な奴のままでいればいい。……なんだって君みたいのが態々此処に来たんだろうな。……ほんと。最悪だ……」
己は、誰の元にも所属しない。社会性のままに、そのまま朽ちるのだとしても、“そうしたい”からそうしている。
他人からどう見られようとも、それだけが自分が出来る、……防衛だったはずだ。
“本当に?”
聞こえた女の声に、脳裏でうるさいとかみ砕いた。
「残念でした。……きみが、最初から素直でしたら。こんな女に目をつけられることも、なかったでしょうにね」
本当に。
この女は……“厭な奴だ。”



ENo.421 根岸 とのやりとり

ENo.492 つづり とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。











料理LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
アイシング を研究しました!(深度1⇒2)



マジメ(711) に移動を委ねました。
チナミ区 O-6(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 P-6(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 Q-6(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 R-6(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 S-6(森林)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



渡辺慧の場合 2/2
「君がそうしたいんならそうすれば? ただ、今一つ分からないんだけど……、君、別にその役割に俺を宛がう必要はないだろ。自分で出来るんだろ、君は。なぁ、……なんで俺を」
余計な文言が混じる。こんなこと言うつもりはなかった。言う必要もなかった。
何かが変わり始めている。厭な予感だ。
「では。『そうしたい』ので、『そうします』ね。……きみは独り立ちができねー性質でしょうから。これはヤエのお節介です。でも、ヤエは『そうしたい』ですので。……では渡辺慧。あーんしてください。ヤエに」
「……わかった、わかったから。俺の負けだよ、勘弁してくれよ。自由でいさせてくれよ、これで勝手に心が離れてくれよ、どんだけ自我が強いんだ、馬鹿かよ。例え俺が『そう』すればって言ったって、『そう』見ない事ぐらい分かってんだろ。何がお節介だよ」
“だって”この女はこうでも言わなければ、こう言ったところで、“本当に”やる。
どうしてそれを知ってしまった。知らないままでよかったのだ。
「嫌だって、ちゃんと言えんじゃねーですか。きみのほうこそどれだけ強情なんですか。……わかってるなら、はじめから。全て『こう』しておけばよかったんですよ。……アドバイスじゃあねーですけども。嫌なことは、嫌だと言わねかったら損しますよ。要らないことに巻き込んで、きみの足を引っ張ることでしょう。それを、『別に構わない』みたいな顔してたら……そのうち、もっと悪いことに足をとられます。きみは、ちっともそれがわかってねんですよ」
「『それ』でいいつもりだよ。それでいいつもり……だったんだけどな。いや、そうだよ。……『それ』が崩れるより、悪い事なんかない。俺が崩れてしまうより、悪い事なんかない。……なんか食うか?」
「コーラおかわりあります? 口の中ベッタベタなんですよね。……正直になった気分はどうです? ヤエは、たいそう気分がいいですけど」
「……厭な問いだな。どう答えたって、最悪だ。厭な奴だ、君はさ。……ちょっと待ってて。お茶位しかないと思うけど」
疲弊から、撫で下がった肩を揺らし、台所へ歩く。お湯はわかしてある。急須だってある。
ないのは、今、これを打破できる言葉だ。一方的に、背中からかけられるこえを、中空に放る術を今や失っている。精一杯の抵抗として、顔を向ける事はしない。
「お茶でもいいですよ。何だってヤエは構いません。そう、最悪ならよかったじゃねーですか。厭な奴だと言われても、ヤエにはきみが必要だったのですから。きみにはヤエは必要ねかったみてーですけどね」
「一方的に話させるだけ話させて、そして、俺もそれでいい。その上でこうするなら……、いや。君は『話せる』のか。……最悪だ。その必要ってのが、誰かの代わりじゃねえ事を祈りでもしてあげるよ。どっちでもいいけどさ。なんでもいいさ。どうでもいい」
「話せますよ。話せたうえで、ヤエはこうしているだけです。だから、渡辺慧が『望むのであれば』、ヤエはなんだって話してあげましょう。……きみのその『どうでもいい』、とっくに意味がないこと、ご存知なんでしょう?」
「るさい。厭な奴のままでいればいい。……なんだって君みたいのが態々此処に来たんだろうな。……ほんと。最悪だ……」
己は、誰の元にも所属しない。社会性のままに、そのまま朽ちるのだとしても、“そうしたい”からそうしている。
他人からどう見られようとも、それだけが自分が出来る、……防衛だったはずだ。
“本当に?”
聞こえた女の声に、脳裏でうるさいとかみ砕いた。
「残念でした。……きみが、最初から素直でしたら。こんな女に目をつけられることも、なかったでしょうにね」
本当に。
この女は……“厭な奴だ。”



ENo.421 根岸 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.492 つづり とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。





DV研究会
|
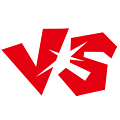 |
TeamNo.244
|





料理LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
アイシング を研究しました!(深度1⇒2)



マジメ(711) に移動を委ねました。
チナミ区 O-6(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 P-6(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 Q-6(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 R-6(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 S-6(森林)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――







DV研究会
|
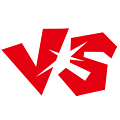 |
夕礼書店調査隊
|


ENo.323
渡辺慧



イバラシティの学生。相良伊橋二年四組。
普段着は白いパーカーを着用していることが多い。
容姿は、少しだけ茶色がかった長すぎない髪。
身長170程度。細身だがある程度引き締まっている。
気分屋。快楽主義というわけでもない。
ころころと様々な場所に顔を出すが特に何をするわけでもない。
正しく在れるのはどちらだったのかという話であり。
どちらを取ったところで大した差がないというのも、事実でもある。
、
I'm slowly.
自身の体感速度がゆっくりになる。だけ。
反射速度とか上がる。後ゆっくり考えられる。
終り。
既知ロール等はやりやすいようにやっていただければ幸いです。
http://lisge.com/ib/talk.php?s=183
現在居住地
ENo.142、鏑木ヤエのPL様よりキャラクターイラスト等頂きました。
普段着は白いパーカーを着用していることが多い。
容姿は、少しだけ茶色がかった長すぎない髪。
身長170程度。細身だがある程度引き締まっている。
気分屋。快楽主義というわけでもない。
ころころと様々な場所に顔を出すが特に何をするわけでもない。
正しく在れるのはどちらだったのかという話であり。
どちらを取ったところで大した差がないというのも、事実でもある。
、
I'm slowly.
自身の体感速度がゆっくりになる。だけ。
反射速度とか上がる。後ゆっくり考えられる。
終り。
既知ロール等はやりやすいようにやっていただければ幸いです。
http://lisge.com/ib/talk.php?s=183
現在居住地
ENo.142、鏑木ヤエのPL様よりキャラクターイラスト等頂きました。
15 / 30
132 PS
チナミ区
S-6
S-6





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | バニークラウン | 防具 | 30 | 敏捷10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | 黄鉄鉱 | 素材 | 15 | [武器]防御10(LV10)[防具]器用10(LV10)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 10 | 空間/時間/風 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 料理 | 29 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 加速 (ヘイスト) | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| 乱雑に蹴る (ウィンドスピア) | 5 | 0 | 100 | 敵貫:風痛撃 | |
| 四回蹴る (エアスラスト) | 5 | 0 | 60 | 敵:4連風撃 | |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 | |
| 意識改革 (アクセルフォーム) | 6 | 0 | 140 | 自:AG・加速LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]アクアヒール | [ 2 ]ヒールポーション | [ 2 ]アイシング |

PL / チズ