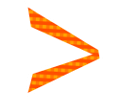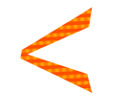<< 1:00>> 3:00




人間、まあ十数年生きてりゃ転機の一つや二つはあるもので。
俺、若宮線引にとってそれは15になる歳の春先に訪れた。
突然黒い車が隣に止まったと思ったらそこから出てきた男二人に拘束された。
その手際の良さたるやまるで布団を畳むような動作と速度で、
とてもじゃないが抵抗とか恐怖とかそんな物すら感じる暇はなかった。
とにかく動くな喋るな騒ぐなという三つのことを耳元で囁かれ、
たどり着いたのは場末の喫茶店だった。
まあ食え、ご馳走してやるから、と強面に言われ、目の前にパフェが置かれる。
言外の圧力ですでに食欲なんかなくなっていた俺はただただパフェを見つけたまま、
膝の上に置いた両こぶしの中にじっとりと汗を掻きながら、はい、はい、と機械的に返答した。
男たちはそんな俺の様子を笑うでも面白がるでもイラつくでもなく淡々と説明を始める。
「我々は『赤笠組』の者だ」
「組の命令でお前に説明に来た」
「お前は赤笠組の現組長である二代目の血を引いている子供の内の一人だ」
「お前は三代目に当たる」
「だがお前は17番目の嫡子だ」
「お前のような子供はバックアップとして何人も存在する」
「それぞれは母親も違う」
「素性も生き方も様々だ」
「血を絶やさぬために多数仕込んだ種の内の一つだ」
「自分の存在を過大に評価をされては困る」
「一方で現在二代目が病に伏している」
「現在も存命である」
「だが病状は軽くない」
「三代目の17番であるお前も周囲が少しやかましくなるだろう」
「指示があるまで何もするな」
「指示があるまで何も考えるな」
「だが知っておけ」
「備えておけ」
「お前の人生は、ここから変わる」
「お前の血の中には赤笠の血が流れている」
「その血からは逃れられない」
「お前の異能のことも知っている」
「俺たちに拘束され使わなかったことは賢明だ」
「少しでも使う素振りを見せれば本当に殺していた」
「俺たちはお前の異能を買っている」
「二代目もお前のことを多少評価していたようだ」
「お前にその気があるのならば『お前の立場が悪くならないよう』取り計らうことも可能だ」
「監視が一人つく」
「その監視を振り切ろうと思うな」
「だがその監視がお前を守ることはない」
「ただお前はその監視下に常にある」
「俺たちの埒外で目立つな」
「お前の親しい者に危害を及ぼしたくなければな」
「ここ数年で決着はつく」
「或いは今まで通りの生活に戻れることもあるだろう」
「それまでの数年は、お前にも付き合ってもらうぞ」
最後に。
「……パフェ、嫌いか?」
嫌いだから食わないわけじゃねえよ。
目の前に座ると食欲がなくなる作用のある二人は言うべきことは伝えたと席を立ち、
口止め料とパフェ代と帰りのタクシー代として何枚かの紙幣を俺の胸ポケットにねじ込み、去っていった。
あとに残されたのはどろっどろにアイスの溶けたパフェと、同じくらい席の背もたれに溶けた俺だった。
誇張なしに言おう。
終わったということを感じていた。
本当に、今この瞬間、自分は死んだと思った。
若宮線引として15年近く生きてきたわけだが、その人生はここで終了を迎えたと思った。
予兆もなく、予感もなく、徐々に降りてくるカーテンすらもなく、
まるでスイッチを落とすように終幕を迎えたと思った。
殺されなかっただけで、命を奪われなかったわけではない。
自分が今まで割と愛着を以って暮らしてきた若宮線引の人生を、続けていく自信がなくなった。
あの二人が言った言葉がどこまで本当かはわからないが、
冗談と笑い飛ばせるものでもないことを肌で感じていた。
自分はヤクザの息子で。
その息子の中でも割と優先順位の低い存在で。
でももう、カタギの暮らしには幸運が重ならないと戻れないらしい。
成程、道理で俺には親がおらず、小さいころから婆ちゃんと二人暮らしだったわけだ。
なんとなく子供のころにおいて親のことを祖母に尋ねたら曖昧な笑顔をした理由がそれか。
そりゃまあ、婆ちゃんも言いづらいわな。
そんなことってあるか?
若宮線引の人生は順調だ。
友達に囲まれ、彼女こそいないものの親しくしてくれる女子はおり、先輩にも後輩にも恵まれた。
今年の受験を終えて、来年は華の高校生だ。
そう思っていた矢先の春。
俺はカタギの人生から一歩だけ足を踏み外した。
もう一回言うが、そんなことってあるかよ。
☆ ★ ☆ ★ ☆
転げ落ちてからは早い。
雪山を転がる雪玉のようなものだ。
夏ごろにはもうその稼業の一部を手伝うようになっていた。
理由の一つは『保身』であり、もう一つは『自分に今まで関わってしまった人間を守るため』だ。
相手に自らの手のひらの中に何もないことを示すには、
相手の手を握るのが一番早いと思った。
まあでも後者の理由はあくまで自分が自分を納得させるために付与した後付けの理由かもしれない。
結局は俺は獅子の身中が一番安全であることを本能的に悟っただけだと思う。
彼らが自分の異能である『境界線使い』を高く評価していたというのは嘘ではないようで、
妙な話だがその線の使い方を考えるのはあちらさんの方が上手だった。
壁越しに爆発物を処理する『線』。
鍵が閉まっている部屋に音もなく侵入する『線』。
異なる場所にいる二つのグループを通信で繋ぐ『線』と。
その異能を使う本人である自分も感心するような利用の仕方を次々と編み出した。
与えられる指示は殆どがそういった補助的な機能で、俺が直接他人を害すことこそないが、
自分がそういった暴力行為の片棒を担いでいるという自覚はあった。
赤笠組という県内では小さな暴力組織が人数構成に比べて破竹の勢いで勢力を拡大していった背景に、
自分が一切存在していなかったとは今でも言えない。
自分の本質が悪であると言われれば首を横に振るが『悪用』が出来、
そして『悪』にも染まりえるということは疑いようもなかった。
ただまああちらもカタギの人間ではないし、都合が全部主体性があるわけもなく、
状況や状態に応じて呼び出される俺の使い方は、『酷使』と言って憚りもないくらい遠慮がなかった。
休日、時には平日まで呼び出されて片棒を担がされるというのは、
少なくとも肉体的にも精神的にもしんどい状態が続いた。
しんどさが翌日まで抜けきらず、なんのためにこれやってるんだろうと思うこともしばしばだった。
俺は荒れた。
中三の夏ごろからだ。自分でもわかりやすいと思う。
学校も前述の理由で途中で抜けたり遅刻していったりと状況も後押ししていたからだとも思う。
その自覚に引きずられてか、肉体の疲労が手伝ってか、
或いは自分が今思い返せばそういう態度を取って他人を遠ざければ、
少しは関わってくる人間を少なくできるとも思ったからだ。
割と俺の人間性が人を寄せる性質があることも、
俺が他人を必要とする程度には寂しがりであることも自覚していたので、
遅まきながら見せた少しの抵抗のようだったものだと思う。
もちろん荒れること自体『目立つな』と俺に告げた赤笠組の意向とは反する。
だから予め組の人間には意図があることも伝えていた。
「明日から荒れます」と。流石にこれは爆笑をもらったが。
まあ、でなければそうやって悪目立ちすること自体が危険因子と判断されるだろうとも思ったからだ。
俺は荒れた。
いやあ、荒れたね。
夜更かしして風呂入らずに寝た翌日の肌くらい荒れた。
分かりやすかったとも思う。
校則を違反すれば悪い奴だというくらい根が真面目で、
何をすれば悪いことかもよく理解できなかった自分は、まともに悪くなるために色んなことを試したし経験した。
煙草、遅刻、無断欠席辺りから始めた記憶がある。
煙草は煙たいのですぐに挫折したが、遅刻と無断欠席に関しては一定以上の効果を上げてくれた。
最初こそ反抗期と笑っていた旧友や教師陣も、最近調子に乗っていると難癖をつけてきた奴らと
真面目に喧嘩をしてからはしっかりと『変わった』という評価を下してくれた。
喧嘩からその悪友たちとつるみ始め、そいつらから悪さとは何かを真剣に学んだ。
目につくもの全てに睨みを利かせ、肩で風を切って歩いていたあの時期は、
俺に話しかけてくるようなやつはいなかったし、そのお陰で自分が裏の稼業に手を染めていた最中も、
大して旧友たちに直接的な被害を与えることはなかった。
親しい人間と呼べる相手や、色々な出会いの機会を失ったことは確かだが、
今更もう終わった若宮線引のカタギとしての人生で交友の手を広げることなど無意味で、
だからまあ少し寂しくはあったが本望でもあった。
去年まで馬鹿な話をしていた友人がよそよそしく視線を合わさないようになったこととか、
割と仲良かった女子がこちらを見るや明らかな恐怖の表情を浮かべてくることなんざ、
そいつらが荒事に巻き込まれるよりはよっぽど良かった。
自分が敷いた導火線の先にある爆発物で、
そいつらが傷つくことを考えたら、よっぽど自分が傷ついた方がマシだ。
まあただ、それを完全に許容できるほどは自分の心をコントロール出来ていたわけでもなく。
荒れたという評価に対して荒れる、というスパイラルによって、俺の心はささくれ立って行った。
当時の俺としてはまあ自然に自分の心が荒れるのは都合が良く、
ただ今に至ってはそのころの口の悪さが言葉の端々にとげとなって残っており、
割と気を許した相手ほど傷つけてしまうという呪いに変わってしまっていることも自覚している。
まあでも。
そんなもん、当時自分が傷つけたものにくらべたら些細なもので。
ただそうやって口が悪くなり、結構きついことも言うようになり、
さらには高宮曰く「怖い先輩」と思われるほどに目つきも悪くなって、
見た目も中身も立派な悪に変わった俺に対して。
ただ。
一人だけ。
たった一人だけ、その俺の努力を。
俺が正当に悪くなり、距離を置き、みんなを守ろうとする強い意志を持ち振る舞うことを。
意に介さないやつがいた。
気にせず踏み込んでくるやつがいた。
……今までと、変わらず接してくるやつがいた。
「センパイ、今日もオールバック似合ってなくてダサいですね」

……こいつである。



ENo.184 黒羽 とのやりとり

ENo.413 伊上 司 とのやりとり




ItemNo.6 ありあわせの料理(激辛) を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








線引(468) は パンの耳 を入手!
マナカ(469) は パンの耳 を入手!
線引(468) は 毛 を入手!
マナカ(469) は ねばねば を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マナカ(469) のもとに 道端ガムマン が微笑を浮かべて近づいてきます。



武術LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
色欲(228) の持つ ItemNo.8 駄石 から防具『鉄納戸色のロングスカート』を作製しました!
強欲(945) により ItemNo.8 駄石 から装飾『シルバーリング』を作製してもらいました!
⇒ シルバーリング/装飾:強さ33/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-
いちこ(1106) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ほくほくコロッケ』をつくってもらいました!
⇒ ほくほくコロッケ/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
みとちゃん(1224) とカードを交換しました!
正義の護り手 (プロテクション)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――
















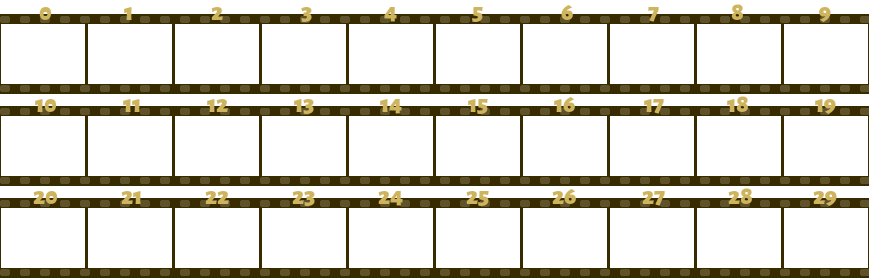





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



人間、まあ十数年生きてりゃ転機の一つや二つはあるもので。
俺、若宮線引にとってそれは15になる歳の春先に訪れた。
突然黒い車が隣に止まったと思ったらそこから出てきた男二人に拘束された。
その手際の良さたるやまるで布団を畳むような動作と速度で、
とてもじゃないが抵抗とか恐怖とかそんな物すら感じる暇はなかった。
とにかく動くな喋るな騒ぐなという三つのことを耳元で囁かれ、
たどり着いたのは場末の喫茶店だった。
まあ食え、ご馳走してやるから、と強面に言われ、目の前にパフェが置かれる。
言外の圧力ですでに食欲なんかなくなっていた俺はただただパフェを見つけたまま、
膝の上に置いた両こぶしの中にじっとりと汗を掻きながら、はい、はい、と機械的に返答した。
男たちはそんな俺の様子を笑うでも面白がるでもイラつくでもなく淡々と説明を始める。
「我々は『赤笠組』の者だ」
「組の命令でお前に説明に来た」
「お前は赤笠組の現組長である二代目の血を引いている子供の内の一人だ」
「お前は三代目に当たる」
「だがお前は17番目の嫡子だ」
「お前のような子供はバックアップとして何人も存在する」
「それぞれは母親も違う」
「素性も生き方も様々だ」
「血を絶やさぬために多数仕込んだ種の内の一つだ」
「自分の存在を過大に評価をされては困る」
「一方で現在二代目が病に伏している」
「現在も存命である」
「だが病状は軽くない」
「三代目の17番であるお前も周囲が少しやかましくなるだろう」
「指示があるまで何もするな」
「指示があるまで何も考えるな」
「だが知っておけ」
「備えておけ」
「お前の人生は、ここから変わる」
「お前の血の中には赤笠の血が流れている」
「その血からは逃れられない」
「お前の異能のことも知っている」
「俺たちに拘束され使わなかったことは賢明だ」
「少しでも使う素振りを見せれば本当に殺していた」
「俺たちはお前の異能を買っている」
「二代目もお前のことを多少評価していたようだ」
「お前にその気があるのならば『お前の立場が悪くならないよう』取り計らうことも可能だ」
「監視が一人つく」
「その監視を振り切ろうと思うな」
「だがその監視がお前を守ることはない」
「ただお前はその監視下に常にある」
「俺たちの埒外で目立つな」
「お前の親しい者に危害を及ぼしたくなければな」
「ここ数年で決着はつく」
「或いは今まで通りの生活に戻れることもあるだろう」
「それまでの数年は、お前にも付き合ってもらうぞ」
最後に。
「……パフェ、嫌いか?」
嫌いだから食わないわけじゃねえよ。
目の前に座ると食欲がなくなる作用のある二人は言うべきことは伝えたと席を立ち、
口止め料とパフェ代と帰りのタクシー代として何枚かの紙幣を俺の胸ポケットにねじ込み、去っていった。
あとに残されたのはどろっどろにアイスの溶けたパフェと、同じくらい席の背もたれに溶けた俺だった。
誇張なしに言おう。
終わったということを感じていた。
本当に、今この瞬間、自分は死んだと思った。
若宮線引として15年近く生きてきたわけだが、その人生はここで終了を迎えたと思った。
予兆もなく、予感もなく、徐々に降りてくるカーテンすらもなく、
まるでスイッチを落とすように終幕を迎えたと思った。
殺されなかっただけで、命を奪われなかったわけではない。
自分が今まで割と愛着を以って暮らしてきた若宮線引の人生を、続けていく自信がなくなった。
あの二人が言った言葉がどこまで本当かはわからないが、
冗談と笑い飛ばせるものでもないことを肌で感じていた。
自分はヤクザの息子で。
その息子の中でも割と優先順位の低い存在で。
でももう、カタギの暮らしには幸運が重ならないと戻れないらしい。
成程、道理で俺には親がおらず、小さいころから婆ちゃんと二人暮らしだったわけだ。
なんとなく子供のころにおいて親のことを祖母に尋ねたら曖昧な笑顔をした理由がそれか。
そりゃまあ、婆ちゃんも言いづらいわな。
そんなことってあるか?
若宮線引の人生は順調だ。
友達に囲まれ、彼女こそいないものの親しくしてくれる女子はおり、先輩にも後輩にも恵まれた。
今年の受験を終えて、来年は華の高校生だ。
そう思っていた矢先の春。
俺はカタギの人生から一歩だけ足を踏み外した。
もう一回言うが、そんなことってあるかよ。
☆ ★ ☆ ★ ☆
転げ落ちてからは早い。
雪山を転がる雪玉のようなものだ。
夏ごろにはもうその稼業の一部を手伝うようになっていた。
理由の一つは『保身』であり、もう一つは『自分に今まで関わってしまった人間を守るため』だ。
相手に自らの手のひらの中に何もないことを示すには、
相手の手を握るのが一番早いと思った。
まあでも後者の理由はあくまで自分が自分を納得させるために付与した後付けの理由かもしれない。
結局は俺は獅子の身中が一番安全であることを本能的に悟っただけだと思う。
彼らが自分の異能である『境界線使い』を高く評価していたというのは嘘ではないようで、
妙な話だがその線の使い方を考えるのはあちらさんの方が上手だった。
壁越しに爆発物を処理する『線』。
鍵が閉まっている部屋に音もなく侵入する『線』。
異なる場所にいる二つのグループを通信で繋ぐ『線』と。
その異能を使う本人である自分も感心するような利用の仕方を次々と編み出した。
与えられる指示は殆どがそういった補助的な機能で、俺が直接他人を害すことこそないが、
自分がそういった暴力行為の片棒を担いでいるという自覚はあった。
赤笠組という県内では小さな暴力組織が人数構成に比べて破竹の勢いで勢力を拡大していった背景に、
自分が一切存在していなかったとは今でも言えない。
自分の本質が悪であると言われれば首を横に振るが『悪用』が出来、
そして『悪』にも染まりえるということは疑いようもなかった。
ただまああちらもカタギの人間ではないし、都合が全部主体性があるわけもなく、
状況や状態に応じて呼び出される俺の使い方は、『酷使』と言って憚りもないくらい遠慮がなかった。
休日、時には平日まで呼び出されて片棒を担がされるというのは、
少なくとも肉体的にも精神的にもしんどい状態が続いた。
しんどさが翌日まで抜けきらず、なんのためにこれやってるんだろうと思うこともしばしばだった。
俺は荒れた。
中三の夏ごろからだ。自分でもわかりやすいと思う。
学校も前述の理由で途中で抜けたり遅刻していったりと状況も後押ししていたからだとも思う。
その自覚に引きずられてか、肉体の疲労が手伝ってか、
或いは自分が今思い返せばそういう態度を取って他人を遠ざければ、
少しは関わってくる人間を少なくできるとも思ったからだ。
割と俺の人間性が人を寄せる性質があることも、
俺が他人を必要とする程度には寂しがりであることも自覚していたので、
遅まきながら見せた少しの抵抗のようだったものだと思う。
もちろん荒れること自体『目立つな』と俺に告げた赤笠組の意向とは反する。
だから予め組の人間には意図があることも伝えていた。
「明日から荒れます」と。流石にこれは爆笑をもらったが。
まあ、でなければそうやって悪目立ちすること自体が危険因子と判断されるだろうとも思ったからだ。
俺は荒れた。
いやあ、荒れたね。
夜更かしして風呂入らずに寝た翌日の肌くらい荒れた。
分かりやすかったとも思う。
校則を違反すれば悪い奴だというくらい根が真面目で、
何をすれば悪いことかもよく理解できなかった自分は、まともに悪くなるために色んなことを試したし経験した。
煙草、遅刻、無断欠席辺りから始めた記憶がある。
煙草は煙たいのですぐに挫折したが、遅刻と無断欠席に関しては一定以上の効果を上げてくれた。
最初こそ反抗期と笑っていた旧友や教師陣も、最近調子に乗っていると難癖をつけてきた奴らと
真面目に喧嘩をしてからはしっかりと『変わった』という評価を下してくれた。
喧嘩からその悪友たちとつるみ始め、そいつらから悪さとは何かを真剣に学んだ。
目につくもの全てに睨みを利かせ、肩で風を切って歩いていたあの時期は、
俺に話しかけてくるようなやつはいなかったし、そのお陰で自分が裏の稼業に手を染めていた最中も、
大して旧友たちに直接的な被害を与えることはなかった。
親しい人間と呼べる相手や、色々な出会いの機会を失ったことは確かだが、
今更もう終わった若宮線引のカタギとしての人生で交友の手を広げることなど無意味で、
だからまあ少し寂しくはあったが本望でもあった。
去年まで馬鹿な話をしていた友人がよそよそしく視線を合わさないようになったこととか、
割と仲良かった女子がこちらを見るや明らかな恐怖の表情を浮かべてくることなんざ、
そいつらが荒事に巻き込まれるよりはよっぽど良かった。
自分が敷いた導火線の先にある爆発物で、
そいつらが傷つくことを考えたら、よっぽど自分が傷ついた方がマシだ。
まあただ、それを完全に許容できるほどは自分の心をコントロール出来ていたわけでもなく。
荒れたという評価に対して荒れる、というスパイラルによって、俺の心はささくれ立って行った。
当時の俺としてはまあ自然に自分の心が荒れるのは都合が良く、
ただ今に至ってはそのころの口の悪さが言葉の端々にとげとなって残っており、
割と気を許した相手ほど傷つけてしまうという呪いに変わってしまっていることも自覚している。
まあでも。
そんなもん、当時自分が傷つけたものにくらべたら些細なもので。
ただそうやって口が悪くなり、結構きついことも言うようになり、
さらには高宮曰く「怖い先輩」と思われるほどに目つきも悪くなって、
見た目も中身も立派な悪に変わった俺に対して。
ただ。
一人だけ。
たった一人だけ、その俺の努力を。
俺が正当に悪くなり、距離を置き、みんなを守ろうとする強い意志を持ち振る舞うことを。
意に介さないやつがいた。
気にせず踏み込んでくるやつがいた。
……今までと、変わらず接してくるやつがいた。
「センパイ、今日もオールバック似合ってなくてダサいですね」

……こいつである。



ENo.184 黒羽 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.413 伊上 司 とのやりとり



| マナカ 「それにしても、ずいぶん気合入ったスーツですね……何用なんですかそれ」 |
ItemNo.6 ありあわせの料理(激辛) を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







線引(468) は パンの耳 を入手!
マナカ(469) は パンの耳 を入手!
線引(468) は 毛 を入手!
マナカ(469) は ねばねば を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マナカ(469) のもとに 道端ガムマン が微笑を浮かべて近づいてきます。



武術LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
色欲(228) の持つ ItemNo.8 駄石 から防具『鉄納戸色のロングスカート』を作製しました!
強欲(945) により ItemNo.8 駄石 から装飾『シルバーリング』を作製してもらいました!
⇒ シルバーリング/装飾:強さ33/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-
 |
強欲 「指輪か。指輪とは、いわば呪いだ。その飾られた指を見て、その装飾の意味を思考せざるを得ない」 |
いちこ(1106) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ほくほくコロッケ』をつくってもらいました!
⇒ ほくほくコロッケ/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
いちこ 「はいおばあちゃん特製食堂コロッケおまちー熱いから気を付けて食べてねえ」 |
みとちゃん(1224) とカードを交換しました!
正義の護り手 (プロテクション)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――







ENo.468
若宮線引



若宮 線引(ワカミヤ センビキ)
相良伊橋高校 2-1 寮暮らし
天才部員 夏生まれ
身長は170後半 やや平均より高め
秘匿しているが両親はカタギではない自由業を営んでいる
その自由業の若い衆からも、クラスの悪友からも「若(わか)」と呼ばれている
好きなものはシンプルな物と理屈が通った物と納得できる物
苦手なものは風凪マナカと嘘泣きと激辛の食べ物、あと機械操作
交友関係は広く浅い。
悪友と呼べる人間は多くとも親友と呼べる人間はいない。
ある一定のラインを引いて交友を遠ざける癖がある。
生家の商売が例の自由業であることが主な原因である。
右目を眼帯で隠しており、周囲には失明していて空洞があるため、
衛生対策でつけていると説明している。真偽は不明。触れると地が出る。
意識した視界の中に"線"を引く異能を持つ
引いた線の種類によって効果はまちまちであり、
その線の種類は即座に使用が可能なものでも20種類を超える。
普段は"線"は生き物のように肌の上を這いまわっており、強く意識すれば制御できるが、
ずっと意識し続けるのは無理なので首筋や袖から時折覗く。
動く刺青のようなもの。
※どんなロールもどんとこいです
※基本、同じクラスだったり既知である必然性があると思った相手は既知としてふるまいます。既知にしたくない場合は知らない感じに返してもらえば一方的に知ってたことにします。
相良伊橋高校 2-1 寮暮らし
天才部員 夏生まれ
身長は170後半 やや平均より高め
秘匿しているが両親はカタギではない自由業を営んでいる
その自由業の若い衆からも、クラスの悪友からも「若(わか)」と呼ばれている
好きなものはシンプルな物と理屈が通った物と納得できる物
苦手なものは風凪マナカと嘘泣きと激辛の食べ物、あと機械操作
交友関係は広く浅い。
悪友と呼べる人間は多くとも親友と呼べる人間はいない。
ある一定のラインを引いて交友を遠ざける癖がある。
生家の商売が例の自由業であることが主な原因である。
右目を眼帯で隠しており、周囲には失明していて空洞があるため、
衛生対策でつけていると説明している。真偽は不明。触れると地が出る。
意識した視界の中に"線"を引く異能を持つ
引いた線の種類によって効果はまちまちであり、
その線の種類は即座に使用が可能なものでも20種類を超える。
普段は"線"は生き物のように肌の上を這いまわっており、強く意識すれば制御できるが、
ずっと意識し続けるのは無理なので首筋や袖から時折覗く。
動く刺青のようなもの。
※どんなロールもどんとこいです
※基本、同じクラスだったり既知である必然性があると思った相手は既知としてふるまいます。既知にしたくない場合は知らない感じに返してもらえば一方的に知ってたことにします。
21 / 30
40 PS
チナミ区
I-11
I-11

























| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 鉄入り靴 | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 5 | 制服 | 防具 | 30 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) |
| 7 | ほくほくコロッケ | 料理 | 33 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 8 | シルバーリング | 装飾 | 33 | [効果1]器用10 [効果2]- [効果3]- |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 3 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 20 | 破壊/詠唱/火 |
| 防具 | 23 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| ファイアボール | 5 | 0 | 180 | 敵全:火撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]イレイザー |

PL / れじ。