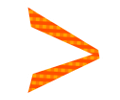<< 2:00>> 4:00




「センパイ、今日は委員会参加されないんですか? 行きましょうよ」

「センパイ、帰りどこか寄って帰りません?」
「センパイ、そんなジェルでガチガチにしてると髪の毛傷んじゃいますよ」

「センパイ、猫いますよ」
「センパイ、寝ぐせ」

「センパイ?」

「いい加減にしろよお前!! どんだけ肝太ぇんだよ!
こんだけ邪険にしてんだからちったぁ離れていけよお前もよぉ!!」
「あ、いつものセンパイだ」
泣きが入った。
俺、若宮線引が風凪マナカに対して完全に根負けしたのが、中三の夏の終わりだ。
期間にして二ヵ月。もう少し持つだろと思うやつもいれば、よくもそれだけ持ったと言うやつもいるだろう。
ともあれ風凪という後輩は俺の変化に対して何のリアクションもしなかった唯一の人間であり、
それはその時俺が叫んだような「肝が太い」とも「図太い」とも違う、何か妙な確信を以って俺との距離を変えなかった。
元々風凪との因縁は、俺が中二時、風凪が中一時に「生活委員会」という
曖昧な定義の委員会での先輩後輩だったことに端を発する。
活動内容はほぼほぼ校内清掃やら下校しない生徒への注意喚起など他愛無いものだったんだが、
そこで初めて俺は「年下」ではなく「後輩」という存在と触れ合い、まあ過剰にそいつらを可愛がった。
風凪はその内の一人であり、委員会活動中に特に自分に懐いて来た後輩だったように、当時は思っていた。
何かわからないことがあれば何でも聞け、という俺の先輩風を受けて順風満帆に帆を張った風凪は、
二ヵ月もしないうちに「センパイ清掃の方法教えてください」を出港し「センパイ彼女いませんよね」にまで到達した。
育て方を間違えたのか。
育ち方が間違っていたのか。
まあでもその時点で風凪の距離の縮め方は俺からしてみても可愛いもので。
変に後輩に噂が立たないかということばかり心配していたように思う。
ただ、その後、例の俺の実家のヤのつく稼業が明らかになり、
出来るだけ今までの交友を遠ざけようと不良に振る舞った俺の努力を、こいつは徹底的に無視をした。
外見を変え、中身を荒らし、今までの交友をリセットするかの如く振る舞った俺の好意を、
本当に徹底的に、徹底的に無視を決め込み、今までと全く変わりなく接してきた唯一の人間がこいつだった。
風凪の周りの友人からしてみてもそれは異質に映っていたようで、
まるであそこの子とはもう付き合うのを辞めなさいという母親のような視線を向けられることもしばしばだった。
それに対して風凪は後から聞くに、
「だって、センパイは、センパイのままだったじゃないですか」
ときた。
本当。
俺はこの女が、何を考えているのか、何が見えているのか。
今を以ってしても分からない。
当時も、今と同じように風凪に関しては頭を抱えていたように思う。
☆ ★ ☆ ★ ☆
頭を抱えていた日々だったせいか、右目の違和感に気づくのは早かった。
ある日、目の奥に鈍痛があることに気づいてはいたが、
単なる寝不足だろうと思いいつものように"指示"をこなしていると、
"線"を引いたその瞬間に右目の奥に激痛が走った。
眼球を裏から小さな手で鷲掴みにされているような感覚を覚え、右目を押さえたままその場に蹲った。
途端、身体を這い回っている"線"が不安定に蠢き出し、身体のありとあらゆる場所を素早く這い回った。
つまりは、異能の制御が出来なくなった。
その日の指示は早々と切り上げ、赤笠組の相談役である異能者の男に話を聞けば、
恐らく自分の異能を制御しているのは身体を這い回る線そのものではなく、『両の目』であるとのことだった。
あくまでそれは仮説として提示された説でしかなかったが、そう考えるといくつか現実と符合することがあった。
一つ、自分の異能は視界の外側に"線"を引くことが出来ないこと。
一つ、自分の異能は視線を逸らすと"線"自体が長時間保てなくなること。
一つ、最近は特に異能を使うたびに目に疲労が残ること。
集中力の問題や、視界の中の方が安定するからという理由で納得していたんだが、
『両目』こそが自分の『空間に線を引く異能』の源泉であるとするのならばそれらに簡単に説明がつく。
つまりは自分は『視界の中の事象に法則を与え』
『その法則を他人と共有するように幻視させる』ことで影響を生じさせる、
『魔眼』のような異能であるとのことだった。
身体の上をわかりやすく這う線が子供のころからあったので、そちらが異質なのだと勝手に思い込んでいた。
この仮説は今日に至っても覆す理由や覆せる別説が湧いても来ずに、恐らくそうなのだろうと思っている。
そしてそれが事実なのだとしたら。
中三の俺は、その生活の中の異能の酷使によって。
――肉体にエラーが起き始めているということだった。
そんな事情を仕事が加味してくれるはずもなく。
俺は相変わらず異能を使って実家の仕事を手伝い続けていた。
秋口に差し掛かるそのころには、自分の中で家業を手伝う理由の一つとして、
なるべく一般の誰かに被害が及ばないよう、なるべく破壊や損傷が最小限で済むよう、
任務の中で危機を管理調整することが俺の目的になっていた。
俺が上手くやれば、俺が上手く立ち回れば、血なまぐささは最小限で済む。
そのころには自分のことや異能、人間性を認めてくれた組の若い衆は面白がって俺のことを『若』と呼んでいたし、
どんな後ろめたい稼業であろうが、仲間意識くらいのもんは多少なりとも芽生える。
だから俺は、そんな人間が他人を傷つけないよう、他人に傷つけられないよう、
自分の異能の使用を抑えることが出来なかった。
右目に眼帯を付け始めたのはそのころだ。
薬局で医療用の眼帯を嵌め、耳に掛けていつも右目を隠していた。
表向きには喧嘩でケガでもしたように思われただろうし、
医療用の白い眼帯について詳しく聞いてくるようなやつはいなかった。
視界を制限することで右目がかなり休まることは事実だったので、常にその医療用の眼帯をつけていたように思う。
ただ医療用の眼帯は耳に掛けているだけのものなので非常に外れやすく、
少しでも派手な動きをすれば横にも下にもズレて、最後の方は面倒になって上から包帯でぐるぐる巻きにしていた。
日に日にケガが増えていっているように見えたのか、その頃「若宮がどこどこの番長を仕留めた」だの、
「本格的に暴走族から勧誘があってその敵対組織にケジメられた」だの噂が立ったが、
誰だよその番長今どき番長いんのかよとか、当時自転車すら乗れなかった俺に何を暴走しろっつーんだと思っていた。
そんな中ただ一人、
「センパイ、ものもらいですか?」
と聞いて来た後輩がいたが、そいつにだけは、
「そうだよ。先日もらってきたので次はお前に回す」
というと、ふふふ、要りません。と返ってきた。
まあそのときは右目の酷使を抑えるなんて選択肢はなかったし、
その酷使を続けていったとき、どんな変化が訪れるのかも、どういうことが起こるのかも、
それほど真剣には考えていなかったと思う。
というよりは、そうでもしないと生きることが許されないという選択の方を常に真剣に考えていたからこそ、
異能の使用も辞めなかったし、眼球は常に圧迫するような痛みに襲われていたし、
変わってしまった自分の人生を乗り越えるために、
本当に必死で、
必死で、
必死で、
今いる鉄火場を乗り越えるために、
痛みも、繋がりも、何もかもを犠牲にして。
新しく敷かれた、鉄と血のレールの上をただひたすらに歩いていくしかなかったのだった。
ただ、その終わりも。
始まりと同じように、本当に唐突に。
あっさりと、訪れたのだった。
☆ ★ ☆ ★ ☆
下校途中、黒塗りの車に押し込められ。
連れてこられたのは喫茶店。
もはや組に対して協力的であるし、俺を車に押し込めた二人も顔見知りなのに、何故と思いつつ、
喫茶店の正面に座った人物を見て、ツッコミをする前に俺は姿勢を正した。
三代目。
そう、口にしていいものか、ずっと迷っていたが。
その目を見た瞬間。
ああ。もはやこの人が赤笠組の三代目なのだと、そう思った。
「……理解が早くて助かる」
俺の視線に何を納得したのか、俺より二つだけ年上なはずの中分けの男は、
静かに咥えていたパフェのスプーンを置いてそう告げてきた。
同じものが運ばれてきて、俺の目の前に置かれる。
俺が、今置かれている状況と与えられる情報から真実をつかみ取ろうとしていると、
思考に重ねるようにして三代目は言葉を俺の頭の上に置く。
「親父が死んだ。
俺が組を継ぐ。
……他の兄弟親族全て、この組から破門をする」
短く。
それは既に決定事項であるように。
有無を言わさぬ力の強さで、押さえつけるように降ってきた言葉だった。
「最も。
……お前にとっては、願ったり叶ったりだろうが」
立ち上がり、頭の上に手を置かれて去って行かれた後も、俺は一切動けずに居た。
連れ立つように俺を拉致した赤笠組の二人も三代目の後を追い、
再びその空間は俺と溶け切ったパフェだけのある空間へと変わる。
俺は。
長く、長く息を吐いた。
右目が、酷く痛み始める。というよりは、気づかないようにしていた右目の痛みを自覚しただけかもしれない。
俺の中で。
再び「終わった」という感覚が蘇っていた。
あの瞬間覚えた、学生・若宮線引のこれまで歩んできた人生と別れを告げたときの感覚。
それと同じように、組員・若宮線引の人生との別れが音もなくそこに置かれていた。
達成感も。
喪失感も。
何もない。
何も、ない。
昔の平穏が取り戻った感覚も。
今までの不穏から手を離した感覚も。
何もない。
ただまた、俺は。
三度目の人生を歩みださないといけないという事実だけが、溶けかけのパフェとともにそこにあった。
それが、中三の卒業前。
相良伊橋高校の入学が決まる、わずか三日前の出来事だった。
……あまりにも。
過酷すぎるだろ。
俺の人生よぉ。



ENo.245 初早森 兎乃 とのやりとり

ENo.1099 メイド とのやりとり

以下の相手に送信しました




マナカ(469) に ItemNo.9 毛 を手渡ししました。
マナカ(469) から ねばねば を手渡しされました。










ハト(1069) から 吸い殻 を受け取りました。
魔術LV を 4 DOWN。(LV20⇒16、+4CP、-4FP)
武術LV を 2 UP!(LV3⇒5、-2CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
マナカ(469) により ItemNo.3 不思議な装飾 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
強欲(945) の持つ ItemNo.9 不思議な石 から防具『砂金避けの外套』を作製しました!
ハト(1069) の持つ ItemNo.10 毛 から防具『ハートポケット』を作製しました!
アユム(1226) の持つ ItemNo.9 毛 から防具『ライダージャケット』を作製しました!
マナカ(469) により ItemNo.4 鉄入り靴 に ItemNo.3 どうでもよさげな物体 を付加してもらいました!
⇒ 鉄入り靴/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]器用10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
アユム(1226) により ItemNo.4 鉄入り靴 に ItemNo.9 ねばねば を付加してもらいました!
⇒ 鉄入り靴/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]攻撃10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ルカド(438) とカードを交換しました!
紅月の六花クッキー (アウトレイジ)

アキュラシィ を研究しました!(深度0⇒1)
アキュラシィ を研究しました!(深度1⇒2)
アキュラシィ を研究しました!(深度2⇒3)
エキサイト を習得!
プリディクション を習得!
ヒートバインド を習得!
アキュラシィ を習得!
フレイムブラスター を習得!



チナミ区 J-11(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――
















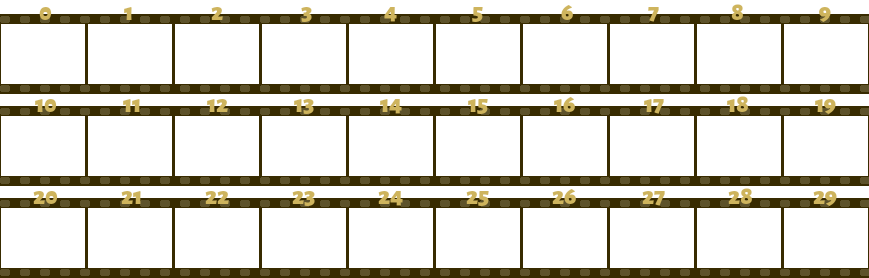





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「センパイ、今日は委員会参加されないんですか? 行きましょうよ」

「センパイ、帰りどこか寄って帰りません?」
「センパイ、そんなジェルでガチガチにしてると髪の毛傷んじゃいますよ」

「センパイ、猫いますよ」
「センパイ、寝ぐせ」

「センパイ?」

「いい加減にしろよお前!! どんだけ肝太ぇんだよ!
こんだけ邪険にしてんだからちったぁ離れていけよお前もよぉ!!」
「あ、いつものセンパイだ」
泣きが入った。
俺、若宮線引が風凪マナカに対して完全に根負けしたのが、中三の夏の終わりだ。
期間にして二ヵ月。もう少し持つだろと思うやつもいれば、よくもそれだけ持ったと言うやつもいるだろう。
ともあれ風凪という後輩は俺の変化に対して何のリアクションもしなかった唯一の人間であり、
それはその時俺が叫んだような「肝が太い」とも「図太い」とも違う、何か妙な確信を以って俺との距離を変えなかった。
元々風凪との因縁は、俺が中二時、風凪が中一時に「生活委員会」という
曖昧な定義の委員会での先輩後輩だったことに端を発する。
活動内容はほぼほぼ校内清掃やら下校しない生徒への注意喚起など他愛無いものだったんだが、
そこで初めて俺は「年下」ではなく「後輩」という存在と触れ合い、まあ過剰にそいつらを可愛がった。
風凪はその内の一人であり、委員会活動中に特に自分に懐いて来た後輩だったように、当時は思っていた。
何かわからないことがあれば何でも聞け、という俺の先輩風を受けて順風満帆に帆を張った風凪は、
二ヵ月もしないうちに「センパイ清掃の方法教えてください」を出港し「センパイ彼女いませんよね」にまで到達した。
育て方を間違えたのか。
育ち方が間違っていたのか。
まあでもその時点で風凪の距離の縮め方は俺からしてみても可愛いもので。
変に後輩に噂が立たないかということばかり心配していたように思う。
ただ、その後、例の俺の実家のヤのつく稼業が明らかになり、
出来るだけ今までの交友を遠ざけようと不良に振る舞った俺の努力を、こいつは徹底的に無視をした。
外見を変え、中身を荒らし、今までの交友をリセットするかの如く振る舞った俺の好意を、
本当に徹底的に、徹底的に無視を決め込み、今までと全く変わりなく接してきた唯一の人間がこいつだった。
風凪の周りの友人からしてみてもそれは異質に映っていたようで、
まるであそこの子とはもう付き合うのを辞めなさいという母親のような視線を向けられることもしばしばだった。
それに対して風凪は後から聞くに、
「だって、センパイは、センパイのままだったじゃないですか」
ときた。
本当。
俺はこの女が、何を考えているのか、何が見えているのか。
今を以ってしても分からない。
当時も、今と同じように風凪に関しては頭を抱えていたように思う。
☆ ★ ☆ ★ ☆
頭を抱えていた日々だったせいか、右目の違和感に気づくのは早かった。
ある日、目の奥に鈍痛があることに気づいてはいたが、
単なる寝不足だろうと思いいつものように"指示"をこなしていると、
"線"を引いたその瞬間に右目の奥に激痛が走った。
眼球を裏から小さな手で鷲掴みにされているような感覚を覚え、右目を押さえたままその場に蹲った。
途端、身体を這い回っている"線"が不安定に蠢き出し、身体のありとあらゆる場所を素早く這い回った。
つまりは、異能の制御が出来なくなった。
その日の指示は早々と切り上げ、赤笠組の相談役である異能者の男に話を聞けば、
恐らく自分の異能を制御しているのは身体を這い回る線そのものではなく、『両の目』であるとのことだった。
あくまでそれは仮説として提示された説でしかなかったが、そう考えるといくつか現実と符合することがあった。
一つ、自分の異能は視界の外側に"線"を引くことが出来ないこと。
一つ、自分の異能は視線を逸らすと"線"自体が長時間保てなくなること。
一つ、最近は特に異能を使うたびに目に疲労が残ること。
集中力の問題や、視界の中の方が安定するからという理由で納得していたんだが、
『両目』こそが自分の『空間に線を引く異能』の源泉であるとするのならばそれらに簡単に説明がつく。
つまりは自分は『視界の中の事象に法則を与え』
『その法則を他人と共有するように幻視させる』ことで影響を生じさせる、
『魔眼』のような異能であるとのことだった。
身体の上をわかりやすく這う線が子供のころからあったので、そちらが異質なのだと勝手に思い込んでいた。
この仮説は今日に至っても覆す理由や覆せる別説が湧いても来ずに、恐らくそうなのだろうと思っている。
そしてそれが事実なのだとしたら。
中三の俺は、その生活の中の異能の酷使によって。
――肉体にエラーが起き始めているということだった。
そんな事情を仕事が加味してくれるはずもなく。
俺は相変わらず異能を使って実家の仕事を手伝い続けていた。
秋口に差し掛かるそのころには、自分の中で家業を手伝う理由の一つとして、
なるべく一般の誰かに被害が及ばないよう、なるべく破壊や損傷が最小限で済むよう、
任務の中で危機を管理調整することが俺の目的になっていた。
俺が上手くやれば、俺が上手く立ち回れば、血なまぐささは最小限で済む。
そのころには自分のことや異能、人間性を認めてくれた組の若い衆は面白がって俺のことを『若』と呼んでいたし、
どんな後ろめたい稼業であろうが、仲間意識くらいのもんは多少なりとも芽生える。
だから俺は、そんな人間が他人を傷つけないよう、他人に傷つけられないよう、
自分の異能の使用を抑えることが出来なかった。
右目に眼帯を付け始めたのはそのころだ。
薬局で医療用の眼帯を嵌め、耳に掛けていつも右目を隠していた。
表向きには喧嘩でケガでもしたように思われただろうし、
医療用の白い眼帯について詳しく聞いてくるようなやつはいなかった。
視界を制限することで右目がかなり休まることは事実だったので、常にその医療用の眼帯をつけていたように思う。
ただ医療用の眼帯は耳に掛けているだけのものなので非常に外れやすく、
少しでも派手な動きをすれば横にも下にもズレて、最後の方は面倒になって上から包帯でぐるぐる巻きにしていた。
日に日にケガが増えていっているように見えたのか、その頃「若宮がどこどこの番長を仕留めた」だの、
「本格的に暴走族から勧誘があってその敵対組織にケジメられた」だの噂が立ったが、
誰だよその番長今どき番長いんのかよとか、当時自転車すら乗れなかった俺に何を暴走しろっつーんだと思っていた。
そんな中ただ一人、
「センパイ、ものもらいですか?」
と聞いて来た後輩がいたが、そいつにだけは、
「そうだよ。先日もらってきたので次はお前に回す」
というと、ふふふ、要りません。と返ってきた。
まあそのときは右目の酷使を抑えるなんて選択肢はなかったし、
その酷使を続けていったとき、どんな変化が訪れるのかも、どういうことが起こるのかも、
それほど真剣には考えていなかったと思う。
というよりは、そうでもしないと生きることが許されないという選択の方を常に真剣に考えていたからこそ、
異能の使用も辞めなかったし、眼球は常に圧迫するような痛みに襲われていたし、
変わってしまった自分の人生を乗り越えるために、
本当に必死で、
必死で、
必死で、
今いる鉄火場を乗り越えるために、
痛みも、繋がりも、何もかもを犠牲にして。
新しく敷かれた、鉄と血のレールの上をただひたすらに歩いていくしかなかったのだった。
ただ、その終わりも。
始まりと同じように、本当に唐突に。
あっさりと、訪れたのだった。
☆ ★ ☆ ★ ☆
下校途中、黒塗りの車に押し込められ。
連れてこられたのは喫茶店。
もはや組に対して協力的であるし、俺を車に押し込めた二人も顔見知りなのに、何故と思いつつ、
喫茶店の正面に座った人物を見て、ツッコミをする前に俺は姿勢を正した。
三代目。
そう、口にしていいものか、ずっと迷っていたが。
その目を見た瞬間。
ああ。もはやこの人が赤笠組の三代目なのだと、そう思った。
「……理解が早くて助かる」
俺の視線に何を納得したのか、俺より二つだけ年上なはずの中分けの男は、
静かに咥えていたパフェのスプーンを置いてそう告げてきた。
同じものが運ばれてきて、俺の目の前に置かれる。
俺が、今置かれている状況と与えられる情報から真実をつかみ取ろうとしていると、
思考に重ねるようにして三代目は言葉を俺の頭の上に置く。
「親父が死んだ。
俺が組を継ぐ。
……他の兄弟親族全て、この組から破門をする」
短く。
それは既に決定事項であるように。
有無を言わさぬ力の強さで、押さえつけるように降ってきた言葉だった。
「最も。
……お前にとっては、願ったり叶ったりだろうが」
立ち上がり、頭の上に手を置かれて去って行かれた後も、俺は一切動けずに居た。
連れ立つように俺を拉致した赤笠組の二人も三代目の後を追い、
再びその空間は俺と溶け切ったパフェだけのある空間へと変わる。
俺は。
長く、長く息を吐いた。
右目が、酷く痛み始める。というよりは、気づかないようにしていた右目の痛みを自覚しただけかもしれない。
俺の中で。
再び「終わった」という感覚が蘇っていた。
あの瞬間覚えた、学生・若宮線引のこれまで歩んできた人生と別れを告げたときの感覚。
それと同じように、組員・若宮線引の人生との別れが音もなくそこに置かれていた。
達成感も。
喪失感も。
何もない。
何も、ない。
昔の平穏が取り戻った感覚も。
今までの不穏から手を離した感覚も。
何もない。
ただまた、俺は。
三度目の人生を歩みださないといけないという事実だけが、溶けかけのパフェとともにそこにあった。
それが、中三の卒業前。
相良伊橋高校の入学が決まる、わずか三日前の出来事だった。
……あまりにも。
過酷すぎるだろ。
俺の人生よぉ。



ENo.245 初早森 兎乃 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1099 メイド とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| マナカ 「迷子にならないよう、手でも繋いであげてた方が良かったですかぁ?」 |
マナカ(469) に ItemNo.9 毛 を手渡ししました。
マナカ(469) から ねばねば を手渡しされました。
| マナカ 「センパイ、靴にガムくっついてますよ」 |









ハト(1069) から 吸い殻 を受け取りました。
| ハト 「今の私はどこからどう見ても 『初対面の人に突然タバコの吸い殻を押し付けにきた変な人』だと思うのですが 違うんです、これは取引の一環であり貴方のお連れ様との契約の執行であり 何卒通報は!通報はお許しください!呼ばないで警察!」 |
魔術LV を 4 DOWN。(LV20⇒16、+4CP、-4FP)
武術LV を 2 UP!(LV3⇒5、-2CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
マナカ(469) により ItemNo.3 不思議な装飾 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
| マナカ 「ちょっとお借りしますねー」 |
強欲(945) の持つ ItemNo.9 不思議な石 から防具『砂金避けの外套』を作製しました!
ハト(1069) の持つ ItemNo.10 毛 から防具『ハートポケット』を作製しました!
アユム(1226) の持つ ItemNo.9 毛 から防具『ライダージャケット』を作製しました!
マナカ(469) により ItemNo.4 鉄入り靴 に ItemNo.3 どうでもよさげな物体 を付加してもらいました!
⇒ 鉄入り靴/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]器用10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
| マナカ 「……あれ? なくなっちゃいましたー」 |
アユム(1226) により ItemNo.4 鉄入り靴 に ItemNo.9 ねばねば を付加してもらいました!
⇒ 鉄入り靴/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]攻撃10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ルカド(438) とカードを交換しました!
紅月の六花クッキー (アウトレイジ)

アキュラシィ を研究しました!(深度0⇒1)
アキュラシィ を研究しました!(深度1⇒2)
アキュラシィ を研究しました!(深度2⇒3)
エキサイト を習得!
プリディクション を習得!
ヒートバインド を習得!
アキュラシィ を習得!
フレイムブラスター を習得!



チナミ区 J-11(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――







ENo.468
若宮線引



若宮 線引(ワカミヤ センビキ)
相良伊橋高校 2-1 寮暮らし
天才部員 夏生まれ
身長は170後半 やや平均より高め
秘匿しているが両親はカタギではない自由業を営んでいる
その自由業の若い衆からも、クラスの悪友からも「若(わか)」と呼ばれている
好きなものはシンプルな物と理屈が通った物と納得できる物
苦手なものは風凪マナカと嘘泣きと激辛の食べ物、あと機械操作
交友関係は広く浅い。
悪友と呼べる人間は多くとも親友と呼べる人間はいない。
ある一定のラインを引いて交友を遠ざける癖がある。
生家の商売が例の自由業であることが主な原因である。
右目を眼帯で隠しており、周囲には失明していて空洞があるため、
衛生対策でつけていると説明している。真偽は不明。触れると地が出る。
意識した視界の中に"線"を引く異能を持つ
引いた線の種類によって効果はまちまちであり、
その線の種類は即座に使用が可能なものでも20種類を超える。
普段は"線"は生き物のように肌の上を這いまわっており、強く意識すれば制御できるが、
ずっと意識し続けるのは無理なので首筋や袖から時折覗く。
動く刺青のようなもの。
※どんなロールもどんとこいです
※基本、同じクラスだったり既知である必然性があると思った相手は既知としてふるまいます。既知にしたくない場合は知らない感じに返してもらえば一方的に知ってたことにします。
相良伊橋高校 2-1 寮暮らし
天才部員 夏生まれ
身長は170後半 やや平均より高め
秘匿しているが両親はカタギではない自由業を営んでいる
その自由業の若い衆からも、クラスの悪友からも「若(わか)」と呼ばれている
好きなものはシンプルな物と理屈が通った物と納得できる物
苦手なものは風凪マナカと嘘泣きと激辛の食べ物、あと機械操作
交友関係は広く浅い。
悪友と呼べる人間は多くとも親友と呼べる人間はいない。
ある一定のラインを引いて交友を遠ざける癖がある。
生家の商売が例の自由業であることが主な原因である。
右目を眼帯で隠しており、周囲には失明していて空洞があるため、
衛生対策でつけていると説明している。真偽は不明。触れると地が出る。
意識した視界の中に"線"を引く異能を持つ
引いた線の種類によって効果はまちまちであり、
その線の種類は即座に使用が可能なものでも20種類を超える。
普段は"線"は生き物のように肌の上を這いまわっており、強く意識すれば制御できるが、
ずっと意識し続けるのは無理なので首筋や袖から時折覗く。
動く刺青のようなもの。
※どんなロールもどんとこいです
※基本、同じクラスだったり既知である必然性があると思った相手は既知としてふるまいます。既知にしたくない場合は知らない感じに返してもらえば一方的に知ってたことにします。
16 / 30
73 PS
チナミ区
K-14
K-14
























| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 鉄入り靴 | 武器 | 30 | 攻撃10 | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 5 | 制服 | 防具 | 30 | 敏捷10 | - | - | |
| 6 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||
| 7 | ほくほくコロッケ | 料理 | 33 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 8 | シルバーリング | 装飾 | 33 | 器用10 | - | - | |
| 9 | |||||||
| 10 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]魅了10(LV20)[防具]幸運10(LV10)[装飾]守護10(LV20) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 13 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 16 | 破壊/詠唱/火 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 防具 | 26 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| ヒートバインド | 5 | 0 | 80 | 敵:火撃&麻痺 | |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 | |
| フレイムブラスター | 5 | 0 | 100 | 自:連続減+敵列:火撃&炎上 | |
| ファイアボール | 6 | 0 | 180 | 敵全:火撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]アキュラシィ | [ 3 ]イレイザー |

PL / れじ。